| 前頁 | 目次 | 次頁 |
|
「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針」について 昭和52年6月14日
原子力委員会
当委員会は、昭和52年5月25日付けをもって原子炉安全技術専門部会から、「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針」について、報告を受けた。 当委員会は、同報告書の内容を検討のうえ、次のとおり「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針」を定める。 なお、昭和40年11月11日、当委員会が定めた「原子炉安全解析のための気象手引について」はこれを廃止する。 発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針
Ⅰ 目的 この指針は、発電用原子炉施設の平常運転時及び想定事故(重大事故及び仮想事故)時における被曝線量評価に際し、大気中における放射性物質の拡散状態を推定するために必要な気象観測方法、観測値の統計処理方法及び大気拡散の解析方法を定めたものである。 本指針は、現在における知識と経験を基礎に実際的な利用を考慮して定めたものであり、今後の経験と新しい知見により有益な情報が得られた場合には、見直される性格のものである。 また、本指針で定めた事項以外の方法を用いる場合があっても、十分な根拠があればその使用は認められるものである。 Ⅱ 気象観測方法 1 気象観測の目的及び区分
気象観測は、大気中における放射性物質の拡散状態を推定するために必要な気象資料を得ることを目的とし、通常観測と特別観測に区分して行う。 通常観測は、原子炉施設設置前及び運転開始後において、被曝線量評価に直接関連する気象資料を得るため、原子炉施設の設置前から原子炉施設の廃止までの間継続して実施する。 特別観測は、原子炉施設設置前の安全解析に際し、敷地及びその周辺の気象特性に関する気象資料を得るため、特定の期間実施する。 2 観測項目
通常観測の観測項目は、風向、風速、日射量、放射収支量及び気温差とする。 特別観測の観測項目は、風向、風速、上層風及び気温差とする。 3 観測方法
気象測器は、原子炉施設の敷地内の適切な場所に設けられた露場又は敷地若しくはその周辺の適切な場所に設けられた観測塔、観測柱等に設置する。 気象測器の種類、測定単位、測定値の最小位数及び気象測器を設置する高さは、第1表及び第2表に掲げるところによる。 気象庁検定の対象となっている気象測器は、検定に合格したものを使用する。 測定値(大気安定度を含む)の欠測率は、連続した12か月において、原則として10%以下とする。 4 観測期間
通常観測は、原子炉施設の設置許可申請前の少なくとも1年前から開始し、原子炉施設が廃止されるまで連続して行う。 特別観測の風向及び風速は、原子炉施設の設置許可申請前において、少なくとも1年間連続して観測し、上層風及び気温差は、この期間の適切な時期に観測する。 第1表 通常観測 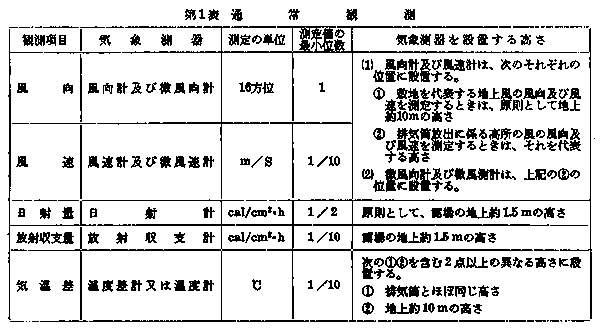 第2表 特別観測 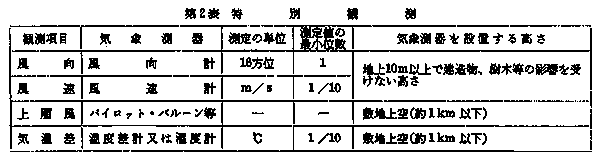 Ⅲ 観測値の統計処理方法 1 毎時の気象資料
以下に定める毎時の気象資料を統計の基礎として使用する。 (1)風向、風速、日射量、放射収支量及び気温差
風向、風速、日射量、放射収支量及び気温差は、それぞれの観測値の正時前10分間の平均値をもって当該時刻の値とする。 (2)大気安定度
大気安定度は、「敷地を代表する地上風」の当該時刻の風速並びに日射量及び放射収支量をもとに第3表によって分類し、これを当該時刻の大気安定度とする。 第3表 大気安定度分類表 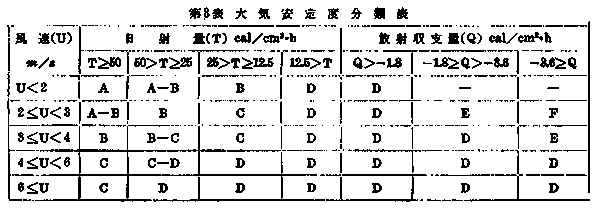 (3)風向、風速及び大気安定度のいずれかの気象要素が欠測の場合には、当該時刻の気象資料は欠測扱いとする。 欠測を除いた観測資料から得られた統計扱、1年間を代表するものとする。 2 気象資料の統計整理
(1)平常運転時の場合
毎時の気象資料は、次の項目について統計整理する。 ① 風向別大気安定度別風速逆数の総和
② 風向別大気安定度別風速逆数の平均
③ 風向別風速逆数の平均
④ 風向出現頻度
⑤ 風速0.5~2.0m/sの風向出現頻度
上記の①②及び③の統計整理に当っては、有風時(風速0.5m/s以上)の観測資料はそのまま使用するが、静穏時(風速0.5m/s未満)の場合には、風速は0.5m/s、風向は風速0.5~2.0m/sの風向出現頻度に応じて比較配分することとする。 (i)風向別大気安定度別風速逆数の総和(Sd,s)は次のように計算する。 有風時における風向別大気安定度別風速逆数の総和(wSd,s)は、(Ⅲ-1)式により計算する。 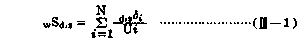 N:実観測回数
Ui:時刻iにおける風速(m/s)
d,sδi:時刻iにおいて風向d、大気安定度sの
場合 d,sδi=1
その他の場合 d,sδi=0
静穏時における風向別大気安定度別風速逆数の総和(cSd,s)は、(Ⅲ-2)式により計算する。 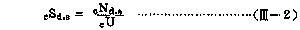 cNd,s:風向dに配分された静穏時大気安定度
sの出現回数
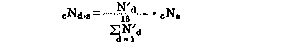 N′d:風速0.5~2.0m/sの風向dの出現回数
cNs:静穏時大気安定度sの出現回数
cU:静穏時の風速(0.5m/s)
Sd,s=wSd,s+sSd,s……(Ⅲ-3)
(ii)風向別大気安定度別風速逆数の平均(Sd,s)は、(Ⅲ-4)式により計算する。 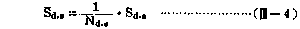 Nd,s:風向d、大気安定度sの総出現回数
Nd,s=wNd,s+cNd,s
wNd,s:有風時の風向d、大気安定度sの出現回数
(iii)風向別風速逆数の平均(Sd)は、(Ⅲ-5)式により計算する。 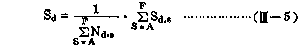 (2)想定事故時の場合
毎時の気象資料は、風向、風速及び大気安定度について毎時刻ごとに整理する。 Ⅳ 基本拡散式 平常運転時及び想定事故時における放射性物質の空気中濃度は、風向、風速、その他の気象条件が全て一様に定常であって、放射性物質が放出源から定常的に放出され、かつ、地形が平坦であるとした場合に、放射性物質の空間濃度分布が水平方向、鉛直方向ともに正規分布になると仮定された次の拡散式を基礎として計算する。 この場合、拡散式の座標は、放出源直下の地表を原点に、風下方向をx軸、その直角方向をy軸、鉛直方向をz軸とする直角座標である。 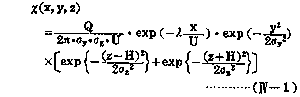 X(x,y,z):点(x,y,z)における放射性物質の濃度(Ci/m3)
Q:放出率(Ci/s)
U:放出源高さを代表する風速(m/s)
λ:放射性物質の物理的崩壊定数(1/s)
H:放出源の高さ(m)
σy:濃度分布のy方向の拡がりのパラメータ(m)
σz:濃度分布のz方向の拡がりのパラメータ(m)
濃度分布の拡がりのパラメータσzは、風下距離と大気安定度の関数として示されるが、この関数関係を第1図及び第2図に示す。 Ⅴ 平常運転時の大気拡散の解析方法 1 被曝線量計算に用いる地表空気中濃度
平常運転時の被曝線量計算に用いる地表空気中濃度は、(Ⅳ-1)式から導かれる(Ⅴ-1)式を用いて計算する。 建屋等の影響により(Ⅴ-1)式が用いられない場合は、(Ⅴ-2)式により計算する。 ただし、風洞実験の結果等により地喪空気中濃度の補正が必要なときは、適切な補正を行う。 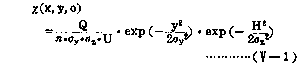 X(x,y,o):点(x,y,o)における放射性物質の濃度(Ci/m3)
Q:放出率(Ci/s)
U:風速(m/s)
σy:濃度分布のy方向の拡がりのパラメータ(m)
σz:濃度分布のz方向の拡がりのパラメータ(m)
H:放出源の有効高さ(m)
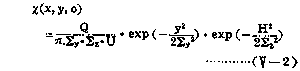 Σy:(σy2+cA/π)1/2
Σz:(σz2+cA/π)1/2
A:建屋等の風向方向の投影面積(㎡)
c:形状係数
2 年間平均濃度の計算
(1)放射性物質の年間平均濃度の計算に当たっては、風が放出点からみて着目地点を含む方位(着目方位)に向かう場合及びその隣接方位に向かう場合の寄与を合算する。 (2)着目方位の年間平均濃度の計算は、連続放出の場合には、風向別大気安定度別風速逆数の総和を用いる。 間欠放出の場合には、着目方位及びその隣接方位に対する風向出現頻度(3方位の出現頻度の合計)と年間放出回数をもとに、その3方位に向かう合計回数を二項確分布の信頼度を67%として求め、これを3方位の風向出現頻度で比例配分する。また、風速については、風向別大気安定度別風速逆数の平均を用いる。 ただし、放出回数が多く、放出時間が長い場合には、各方位への放出回は風向出現頻度に比例するものとする。 (3)着目方位の年間平均濃度の計算に当たっては、風向が1方位内で一様に変動するとして濃度の平均化を行う。 Ⅵ 想定事故時の大気拡散の解析方法 想定事故時の被曝線量計算に用いる放射性物質の地表空気中濃度は、単位放出率当たりの風下濃度(相対濃度と定義する)に事故期間中の放射性物質の放出率を乗じて算出する。 1 被曝線量計算に用いる相対濃度
(1)相対濃度は、毎時刻の気象資料と実効的な放出継続時間(放射性物質の放出率の時間的変化を考慮して定めるもので、以下実効放出継続時間という)をもとに方位別の着目地点について求める。 (2)着目地点の相対濃度は、毎時刻の相対濃度を年間について小さい方から累積した場合、その累積出現頻度が97%に当たる相対濃度とする。 (3)被曝線量計算に用いる相対濃度は、上記(2)で求めた相対濃度のうち最大の値を使用する。 2 相対濃度の計算
相対濃度(X/Q)は、(Ⅵ-1)式により計算する。 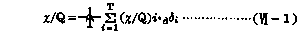 (X/Q):実効放出継続時間中の相対濃度(s/m3)
T:実効放出継続時間(h)
(X/Q)i:時刻iにおける相対濃度(s/m3)
dδi:時刻iにおいて風向が当該方位dにあるとき dδi=1
時刻iにおいて風向が他の方位にあるとき dδi=0
この場合、(X/Q)iは、実効放出継続時間の長短、建屋等の影響の有無に応じて、次により計算する。 ただし、風洞実験の結果等により(X/Q)iの補正が必要なときは、適切な補正を行う。 (1)短時間放出の場合
短時間放出の場合における(X/Q)iの計算に当たっては、風向が一定と仮定して(Ⅵ-2)式より計算する。 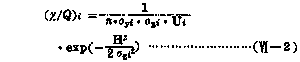 σyi:時刻iにおける濃度分布のy方向の拡がりのパラメータ(m)
σzi:時刻iにおける濃度分布のz方向の拡がりのパラメータ(m)
Ui:時刻iにおける風速(m)
H:放出源の有効高さ(m)
(2)長時間放出の場合
<> 長時間放出の場合における(X/Q)iの計算に当たっては、放出放射性物質の全量が一方位内のみに一様分布とすると仮定して(Ⅵ-3)式により計算する。
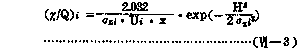 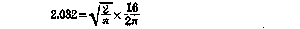 x:放出点から着目地点までの距離(m)
(3)建屋等の影響による補正
建屋等の影響により前述の式が用いられない場合は、(X/Q)iは、次式により計算する。 ① 短時間放出の場合
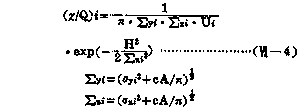 A:建屋等の風向方向の投影面積(㎡)
c:形状係数
② 長時間放出の場合
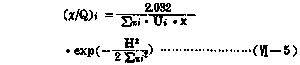 Ⅶ 放出源の有効高さ 放出源の有効高さは、排気筒の地上高さ、排気筒の吹上げ高さ、建屋及び地形による影響等を総合的に検討して定める。 この場合、排気筒の吹上げ高さについては、(Ⅶ-1)式により求める。 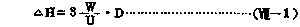 ΔH:吹上げ高さ(m)
W:吹出し速度(m/s)
D:排気筒出口直径(m)
U:風速(m/s)
Ⅷ 風洞実験 敷地の地形が複雑な場合又は放出源に対する建屋等の影響が著しいと予想される場合には、放出源の有効高さ等の妥当性を検討するため、それぞれの幾何学的条件を取り入れた模型を用いて風洞実験を実施する。 第1図 y方向の拡がりのパラメータ(σy) 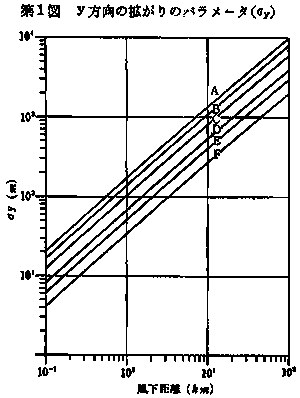 第2図 z方向の拡がりのパラメータ(σz) 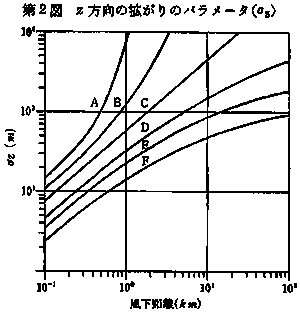 付 記
指針は気体状の放射性物質が放出源から数㎞に拡散される場合の地表空気中濃度の算出を中心に記述したものである。指針に明記していない事項については、指針の趣旨を踏まえ、当面欠のように取り扱うこととする。 1 放射性雲からのγ線量は、地表空気中濃度を用いずに、放射性物質の空間濃度分布を算出し、これをγ線量計算モデルに適用して求める。 想定事故時のy線量については、相対濃度(X/Q)の代りに、空間濃度分布とγ線量計算モデルを組み合わせたD/Q(相対線量と定義する)を使用して指針と同様な考え方により求める。 2 放射性物質が高温高圧の冷却材とともに外気中に放出されるような想定事故時には、蒸気雲の形成、上昇、移動、拡散等を考慮して適切な方法により地表空気中濃度を求める。 3 国民遺伝線量の計算のように放射性物質の拡散が広域にわたるような場合には、適切な風速、拡散幅、大気安定度等を仮定して地表空気中濃度を求める。 解 説
Ⅰ 指針作成の考え方 発電用原子炉施設の安全評価に使用する気象解析法は、昭和40年11月11日、原子力委員会が決定した「原子炉安全解析のための気象手引」(以下「気象手引」という)により運用されてきたが、その後、気象解析に関する調査研究の進展と原子炉施設の建設、運転の経験が蓄積されてきたことにかんがみ、この際、気象手引を見直すとともに新しい観点に立って指針を定めたものである。 原子炉施設の安全解析においては、原子炉施設から放出される放射性物質による原子炉施設周辺の被曝線量がその対象となるので、原子炉施設周辺の放射性物質の大気中における拡散状態を推定することが重要である。 原子炉施設周辺における大気拡散状態を把握するには、関連する要因が多く、また、その対象とする範囲も広いので、理論的かつ十分な精度をもった解析方法を確立することは困難である。従って、指針を作成するに当たっては、既存の知識と経験に照らし、実際的な利用を意図してとりまとめを行った。 原子炉の安全解析は、一般に平常運転時と想定事故時について行われるが、それに使用する気象条件は、それらの現象の特性を考慮して定めることとした。 平常運転時における安全解析は、通常、原子炉施設周辺における1年間等の長期間の被曝線量を評価するものであるから、この場合には、年間の気象データをもとに建屋及び地形等が拡散に及ぼす影響、放出モード等を考慮して現実的な解析を行うこととした。 想定事故時における安全解析は、想定事故期間中の被曝線量を評価するものであるので、この場合には、想定事故が任意の時刻に起こること及び実効的な放出継続時間が短いことを考慮して、平均的な気象条件よりもむしろ出現頻度からみてめったに遭遇しないと思われる厳しい気象条件を用いる必要がある。このため、指針では、気象観測資料をもとに出現確率的観点から想定事故期間中の相対濃度を解析し、放射性物質の濃度が厳しい気象条件に相当するものとなるように考慮することとした。 Ⅱ 気象観測方法 1 観測項目
(1)通常観測
大気拡散式の使用に当たっては、風向、風速及び大気安定度(地表付近の風速、日射量湯び放射収支量)の観測値が必要となるため、これら各要素の観測を行うこととした。 また、気温差は、主として拡散パラメータ推定の参考として観測するものである。 なお、風車型風向風速計を使用する場合には、弱風時において必ずしも正確な値を示さないから、これを補うため、微風向、微風速の測れる測器も使用することとした。 通常観測は、原子炉施設設置前の評価はもちろん、運転開始後の周辺環境における被曝線量の把握のためにも必要であるので、原子炉施設の設置前から施設の廃止までの期間連続して実施することとした。 (2)特別観測
敷地及びその周辺の地域的気象特性を把握するため、通常観測の実施地点以外の地点で必要に応じて地上風を観測し、また、排気筒上空の気象状態の把握のために、適切な時期に上層風及び気温差を観測することとした。 なお、上記の観測以外に、「原子炉の設置、運転等に関する規則」で定められる降雨量、大気温度の観測を行うほか、相対湿度、積雪量、海面水温等の観測を行うことが望ましい。 2 観測方法
気象観測方法については、指針Ⅱ.3に示されているが、それに関連して留意すべき点を次にあげる。 (1)気象観測施設は、気象業務法による観測施設の届出を行うこと。 (2)観測の実施に当たっては、気象庁刊行「地上気象観測法」を参考にすること。 (3)気象庁検定の対象となっていない気象測器は、定期的に較正を行い、その精度が観測目的に必要な範囲内にあることを確認すること。 (4)露場は、原子炉施設敷地内で近くに建造物、樹木等のない平坦な場所にできるだけ広く芝草等を植え、その内に設置すること。 (5)観測塔及び観測柱の設置に当たっては、敷地を代表する地上風、排気筒放出に係る高所の風、その他の参考とする風を観測するのに適切な位置を必要数選定すること。この場合、排気筒の位置、建造物、地形、周辺の集落等を考慮すること。 (6)通常観測では、露場、沸測塔、観測柱等の設置位置は、運転開始後に原則として移転しなくてもよいように選定すること。移転を必要とする場合には、記録の連続性が保たれるような措置をとること。 (7)通常観測における気温差の測定は、指針に示された二つの高さのほか30~50m間隔で行うことが望ましい。 気象観測の測定値は、アナログ方式により記録紙に連続記録するほか、通常観測の測定値は、記録の確実性をますとともに計算機処理が行えるように磁気テープ等に記録し、また、原子炉施設の運転開始後には、中央制御室等、測定値が常時監視できる場所で記録を行うことが望ましい。 これらの観測値は、欠測をも補うよう統計処理されるので、欠測率をできるだけ低くするため、連続した12か月における欠測率は、原則として10%以下とすることとした。なお、欠測が一時期に集中することは好ましくないので、連続した30日間においては、この欠測率が30%以下になるように努めなければならない。このためには、気象測器の点検、保守の方法を確立し、これを定期的に行うとともに必要な測器については、予備測器の整備を行うことが望ましい。 なお、参考のため第1表に気象測器の例を示す。 第1表 気象測器例 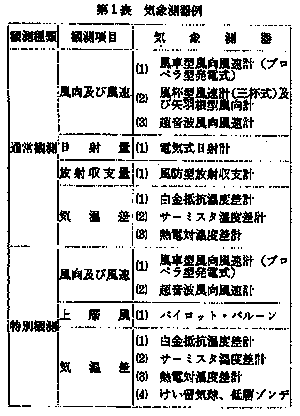 Ⅲ 観測値の統計処理方法 1 通常観測の場合
(1)毎時の気象資料
① 風向、風速、日射量、放射収支量及び気温差指針において、正時前10分間の平均値をもって当該時刻の観測値としたのは、風向及び風速については、気象庁刊行「地上気象観測法」に従ったものであり、その他の観測値については、これに準じたものである。 ② 大気安定度
指針第3表は、Pasquill-Meadeの分類表1)を測器を用いて客観的に適用できるようにわが国で区分値を定めたものである2)。 拡散計算に際して、この表の中間安定度A-B、B-C及びC-Dについては、A-BはBに、B-CはCに、C-DはDに、また、夜間の2m/s未満の欄の「-」はFと見なして処理する。 (2)気象資料の統計整理
毎時の気象資料は、第2表の整理項目に従って整理する。 年間統計を必要とするものについては、利用の便を考慮し、すべての欠測を後述のように処理し、期間1か年に換算した後作表する。 (3)風向別大気安定度別風速逆数の総和及び平均
年間平均濃度の計算に使用される風向別大気安定度別風速逆数の総和(Sd,s)及び平均(Sd,s)は、日射量、夜間放射収支量及び風速(原則として高さ約10m)から決定される大気安定度並びに放出高を代表する高さで観測される風向及び風速を用いて次の手順により求める。 ① 大気安定度、風向及び風速のいずれか一つでも欠測があれば、当該時刻は、欠測扱いとする。 ② 風向別大気安定度別風速逆数の総和Sd,sは、観測資料に欠測がある場合はNt/Nを乗じて1年間の値に換算する。 Nt:1年間の総観測回数(8,760)
N:1年間の欠測を除いた実観測回数
2 特別観測の場合
特別観測の観測値は、次の事項が明らかとなるように統計処理を行う。 (1)敷地内付近の地上及び上空の風の状態
(2)敷地上空の気温の鉛直分布
第2表 統計整理項目 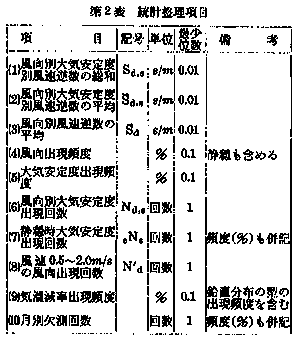 Ⅳ 基本拡散式 指針における大気拡散式は、本来放射性物質が放出源から定常的に放出され、かつ、地形が平坦な場合に使用されるものである。従って、地形が複雑な場合や放出源に対する建屋等の影響が著しいと予想される場合については、この式をそのまま適用するだけでは必ずしも十分とは言いがたい。 このような場合に、風洞実験等によって上記の拡散式による値を補正し、評価する必要がある。 1 基本拡散式
大気中に放出された気体状あるいは微粒子状物質は、風とともに移動すると考えられる。大気は、一般に乱流状態にあるので、放出された物質は、移動しながら比較的速く拡散され希釈される。地表の影響のない一様な大気中の一点から上記物質が連続的に放出される場合、風下の濃度は次の式で計算する。 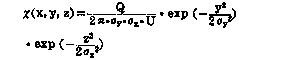 x:点(x,y,z)における濃度(Ci/m3)
Q:放出率(Ci/s)
U:風速(m/s)
σy:y方向の濃度分布の拡がりのパラメータ(m)
σz:z方向の濃度分布の拡がりのパラメータ(m)
ここで座標軸は、放出源を原点に風下方向をx軸とする直角座標である。 次に、地上高Hから連続的に放出される場合を考える。平坦な地面上にx,y軸をとり、z軸は上方に、x軸を風下方向に、原点は放出点直下にとる。いま、地表面で放出物が完全に「反射する」と仮定すると、一定(x,y,z)における濃度は次式であらわされる。 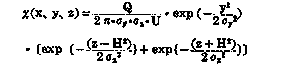 ここでは、風速Uは一定、σy及びσzは風下距離xと大気安定度だけの関数として扱っている。現実には、このような前提の保証はなく、また、前述の平坦な地面や放出物質の完全な反射ということもいつも満たされているとはいえないが、地表面における濃度については、計算値と実験値との一致がはかられるよう式中のσy及びσzが与えられているので、この方法による結果は妥当なものであり、このモデルが広く使用されているのはこのような理由によるものと思われる。σy及びσzの値としては、主に米国で行われた野外実験の資料をもとにして、英国気象局の研究者たち3)の決めた値が一般に用いられている。 なお、その他いくつかの拡散式4)が提案されているが、実際的な適用を考えてここでは採用しなかった。 2 濃度分布の拡がりのパラメータσy及びσz
指針(Ⅳ-1)式に示される拡散式の濃度分布の拡がりのパラメータσy及びσzは、地面の存在を無視して鉛直方向も無限空間とみなし得る場合には、それぞれ水平方向及び鉛直方向に対する濃度分布の標準偏差である。 指針第1図及び第2図は、Pasquill-Meadeの、いわゆる鉛直1/10濃度幅hの図及び水平1/10濃度幅を見込む角θの記述にほぼ忠実に従って作成されたものである。これらの間には、定義により次の関係がある。 h=2.15σz
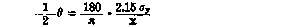 ここで、h、σz、σy及び風下距離xの単位はm、また、θの単位はdegである。 θは、原論文では、θ(0.1㎞)/θ(100㎞)=2とし、風下距離を対数にとった片対数方眼紙上で直線内挿として取扱われている。 σy=0.67775θ0+1・(5-logx)・x (xの単位は㎞)
ここで、θ0+1(deg)は、0.1㎞におけるθの値で次表で与えられる。 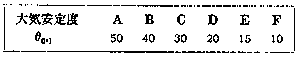 hは、両対数方眼紙上でたとえば2次式又は3次式で近似することができる。 σz=σ1xa1+a2logx+a3(logx)2 (xの単位は㎞)
ここで、σ1、a1、a2及びa3は定数で第3表及び第4表で与えられる。 なお、実用上、上の式で1,000mをこえるσzについては、1,000mとして扱うこととした。 第3表 σ1、a1、a2及びa3(風下距離が0.2㎞以遠) 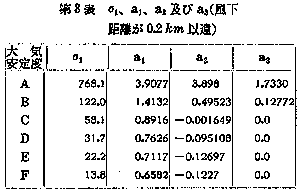 第4表 σ1及びa1(風下距離が0.2㎞未満) 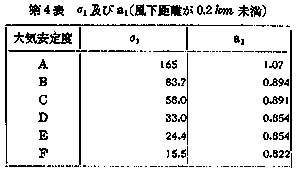 ただし、a2及びa3は0とする。 Ⅴ 平常運転時の大気拡散の解析方法 1 空間濃度分布の計算
排気筒から放出されるプルームは、一般には高所放出とみなして指針(Ⅳ-1)式を用い空間濃度分布の計算を行うことができる。 これに対し、吹上げ高さを考慮した放出源の高さと建屋等の高さとの差が小さい場合、プルームが建屋等の風下方向に巻き込まれる現象はよく知られている。指針では、このような場合(Ⅴ-2)式によって空間濃度分布を計算することとした。この式では、放出源が拡がりをもっているものと仮定されている。すなわち、プルームは、通常の大気拡散によって拡がる前に巻込み現象による拡散が行われたと考える。この拡散パラメータは、建屋等の投影面積の関数であり、かつ、その中での濃度分布は正規分布であると仮定している。いま、巻込み現象による初期拡散のパラメータをσy0、σz0とし、また、風下方向での通常の大気拡散による拡がりのパラメータをσy、σzとすると、総合的な拡散パラメータは、
Σy2=σy20+σy2
Σy2=σz20+σz2
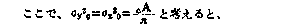 A:建屋等の風向方向の投影面積(㎡)
c:形状係数
指針(Ⅴ-2)式が与えられる。 本式中の形状係数c及び放出源の有効高さHについては、特に根拠が示されるもののほかは原則としてそれぞれ1/2及び0を用いるものとする。なお、Giffordは1/2<c<2としている10)。 2 年間平均濃度の計算
(1)年間平均濃度算出の基本計算
放射性物質が定常的に放射され、かつ、地形が平坦であると仮定した場合の地表面上の濃度分布は、放射性物質の着目地点に向かう間の減衰の効果を無視すると次式で表わされる。 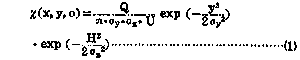 ハχ(x,y,o):点(x,y,o)における放射性物質の濃度(Ci/m3)
Q:放出率(Ci/s)
U:風速(m/s)
H:放出源の有効高さ(m)
σy:濃度分布のy方向の拡がりのパラメータ(m)
σz:濃度分布のx方向の拡がりのパラメータ(m)
年間平均濃度を実際に計算するに当たっては、着目方位及びその隣接方位の寄与を考慮しなければならない。具体的な計算は、原則として、より実際に即している下記①の方法により行う。なお、風向及び風速の出現頻度特性等から下記②の方法によってもよい場合もある。 ①の方法
この方法は、着目方位及びその隣接方位の寄与をそれぞれの方位の気象データを用い、それぞれの寄与について着目方位内での平均化を行うものである。 この方法によって、年間平均濃度を計算するためには、電子計算機を用いて計算を行うことになるが、その計算の基本は次のように示される。 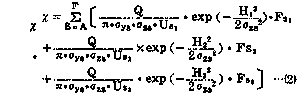 σys,σzs:大気安定度sの時のσy、σz(m)
Us1:大気安定度sの時の着目方位の風速(m/s)
Us2,Us3:大気安定度Sの時の隣接方位の風速(m/s)
H1:着目方位に対する放出源の有効高さ(m)
H2,H3:隣接方位に対する放出源の有効高さ(m)
Fs1:大気安定度sの時の着目方位の濃度の平均化の係数
Fs2,Fs3:大気安定度sの時の隣接方位の濃度の平均化の係数
ただし、平均化の係数、Fs1、Fs2、及びFs3は、次式で示される。 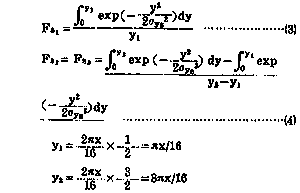 x:放出点から着目地点までの距離(m)
②の方法
この方法は、ある風向の時の放出放射性物質の全量がその方位内に一様分布すると仮定して濃度の平均化を行うものである(これは、着目方位からはずれた部分を着目方位にたたみこんだ方法であるものといえる)。この場合、着目地点の年間平均濃度は、次式で表わされる。 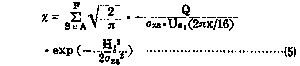 (2)間欠放出について
放出回数がきわめて少なく(年間約20回以下)、その放出量が年間の全放出量にくらべて有意な場合には、その放出形態を間欠放出と定義し、連続放出とは区別して扱うものとした。 間欠放出の場合においても隣接方位の寄与を考慮することとしたので、指針においては、3方位の風向出現頻度に対して二項確率分布を適用した。着目方位と隣接方位への放出回数の配分については、それぞれの風向頻度で比例配分することとした。 なお、二項確率の信頼度の設定に当たっては、ここでは、多少ひかえめな値として2/3(0.67)を採用した。 従って、年間の間欠放出回数をny回とした時、着目方位に対する影響回数がm回である確率は、次式の二項確率の計算から求められる。 F(m)=nyCm・Pm・(1-P)ny-m………………(6)
F(m):着目方位に対する影響回数がm回である確率
nyCm:ny回からm回をとる組合せ
P:着目方位に対する風向出現頻度
間欠放出時の風向が着目方位と一致する期待値を求め、この値をその方位に対する影響回数とすると、次式を満足するrがその方位に対する影響回数となる。 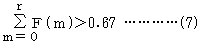 なお、風向頻度と放出回数を与えた場合の影響回数を第5表に示した。 (3)連続放出及び間欠放出の際の年間平均濃度
単位放出率(1Ci/s)、単位風速(1m/s)の時の地表空気中濃度の1方位内平均値をxsとすれば、連続放出及び間欠放出の際の大気安定度sの時の年間平均濃度は、それぞれ次式で表わされる。 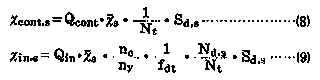 xcont,s,xin,s:それぞれ大気安定度sの時の連続及び間欠の年間平均濃度(Ci/m3)
Qcont,Qin:それぞれ連続及び間欠放出の総量が1年間一様に連続して放出されるとした時の放出率(Ci/s)
Nt:総観測回数(8,760)
Nd,s:方位d、大気安定度sの出現回数
ny,nc:それぞれ間欠放出の回数及びその影響回数(3方位に対する回数)
fdt:着目方位とその隣接方位に対する風向出現頻度の和
なお、指針Ⅲ・2で示したSd,s,Sd,sの算出過程より、
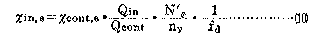 N′e:着目方位又は隣接方位のいずれか1方位に対する影響回数
fd:N′eの影響回数を示す風向の出現頻度
という関係式が得られるので、間欠放出の隣の地表空気中濃度は(10)式をもとに計算すると簡便である。 Ⅵ 想定事故時の大気拡散の解析方法 1 相対濃度
想定事故時における放射性物質の放出量及び放出条件(放出継続時間、放出源の有効高さ等)が定められると、風下の着目地点における放射性物質の濃度は、放出時の気象条件によって定まる。 しかし、想定事故が発生した時に遭遇する気象条件は、あらかじめ知ることができないので、この場合の気象条件は、確率的な手法で解析しなければならない。このため指針では基本拡散式から導かれるx/Qをもとに解析することとした。 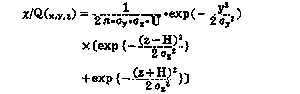 x/Q(x,y,z):点(x,y,z)における相対濃度(s/m3)
σy:濃度分布のy方向の拡がりのパラメータ(m)
σz:濃度分布のz方向の拡がりのパラメータ(m)
U:風速(m/s)
H:放出源の有効高さ(m)
x/Qは、毎時の風向、風速及び大気安定度を用いて計算した単位放出率当たりの当該時刻における風下濃度であり、いわば、大気中における拡散希釈の程度を表わすものである。 指針では、想定事故時においてめったに遭遇しない気象条件下の濃度を導くため、相対濃度の出現確率は過去の経験に照らして97%を採用して解析することとした。 想定事故時の被曝線量計算に用いる濃度は、地表空気中の相対濃度に事故期間中の放射性物質の放出率を乗じて求めることができる。 2 相対濃度の計算
(1)放出源の有効高さ及び大気安定度の種類によって着目地点以遠にx/Qの最大値があらわれることがあるので、適切な距離ごとにx/Qを計算し、年間累積出現頻度が97%に相当するx/Qを距離ごとに求め、そのなかの最大値を当該方位のx/Q値とする。 ただし、着目地点以遠における毎時のx/Qの最大値を着目地点の当該時刻のx/Qとして、それらの年間累積出現頻度が97%に相当するx/Qをその方位のx/Q値としてもよい。 (2)x/Qの具体的な計算は、着目地点にx/Qの最大値があらわれる場合には、実効放出継続時間に応じて次の手順によって行う。 〔例1〕実効放出継続時間が1時間の場合
実効放出継続時間が1時間の場合のx/Qは各方位ごとに計算する。 気象データは、風向、風速及び大気安定度の気象要素が1時間の単位で得られるので、欠測がない場合には1年間の気象データの数は8,760個である。ある方位の1時間のx/Qは、指針(Ⅵ-1)及び(Ⅵ-2)式に1年間の毎時刻の気象データを代入するとえられるが、このなかには、風向が他の方位にあってx/Qが0となる個数も含まれている。 これらのx/Qを小さい値から並べて整理し、その累積出現頻度が97%に相当するx/Qを求め、それを当該方位のx/Q値とする。欠測がある場合は、総観測時間から欠測時間を差し引いた時間数を全数とし、その97%に相当するx/Qを抽出する。同様の手順を各方位について行い方位ごとのx/Q値を抽出し、各方位において抽出されたx/Q値(8方位を対象とする場合は抽出された数は8個である)から最大値を選び、これを被曝線量計算に用いるx/Q値とする。 〔例2〕実効放出継続時間が1時間を超える場合
実効放出継続時間が1時間を超える場合のx/Qは、その時間内におけるx/Qの平均値を求めるものであるので、その求め方は〔例1〕と若干異なる。 例えば、実効放出継続時間が8時間の場合には、次のようになる。 ある方位の8時間のx/Qは、最初に任意の時刻をとり、その時刻から8時間の毎時刻の気象データを指針(Ⅵ-1)及び(Ⅵ-2)式に代入して、当該8時間のx/Qを計算し、次に1時間繰り下げた時刻から8時間の毎時刻の気象データを同じ式に代入して、当該8時間のx/Qを計算する。 同様の手順を1年間について繰り返す。こうして求められたx/Qのなかには当該8時間にわたり風向が全て他方位にあってx/Qが0となるものも含まれている。これらのx/Qを小さい方から並べて整理し、累積出現頻度が97%に当たるx/Qを求め、それを当該方位のx/Q値とする。 同様の手順を各方位について行い、方位ごとのx/Q値を抽出し、それらのうちから最大値を選んで被曝線量計算に用いるx/Q値とする。 当該8時間に欠測時間が含まれる場合のx/Qはその欠測の分布状況を考慮して適切に処理しなければならない。 (3)実効放出継続時間(T)は、想定事故の種類によって放出率に変化があるので、放出モードを考慮して適切に定めなければならないが、事故期間中の放射性物質の全放出量を1時間当たりの最大放出量で除した値を用いることもひとつの方法である。 実効放出継続時間が8時間を超える場合は、長時間放出とみなして計算する。 Ⅶ 静穏時の取扱い 静穏時における拡散は、有風時と同様に取り扱うべきではないが、現在適切な実用拡散式がないため、次の理由から便宜上風速を0.5m/sとして有風時の拡散式に適用することとした。 感度のよい微風向・微風速計では静穏時でも0.5m/s以上の風速を示していることが多く、また、静穏時における放射性雲からのガンマ線被曝も極端に高い実測値がえられていないことから12)、静穏時においても大気による拡散希釈は行われているものと考えられる。 指針では、このような事実を考慮して、静穏時の風速は0.5m/sとして有風時の拡散式を適用することとした。静穏時の風向については、平常運転時の場合には、静穏時の微風向・微風速計による風向分布が0.5~2.0m/sの風向分布にほぼ一致することから0.5~2.0m/sの風向出現頻度に比例配分することとした。また、想定事故時の場合には、風向の持続性等を考慮して静穏時の風向は、静穏出現前の風向とすることとした。 Ⅷ 放出源の有効高さ (1)風下方位の地表空気中濃度は、風速、大気安定度等の気象条件と放射性物質の放出源の有効高さ等の放出条件によって定まる。放出源の有効高さは、通常、排気筒の地上高さに吹上げ高さを加えた高さが用いられるが、原子炉施設周辺の地形が複雑な場合及び建屋等の影響を受ける場合には、拡散に及ぼす影響を考慮して調整した“みかけの放出源高さ”を解析に用いることがある。 このように放出源の有効高さは、吹上け高さや建屋、地形の影響等を考慮して、“みかけの放出源高さ”が使用されるので、指針では、“みかけの放出源高さ”を放出源の有効高さとした。 (2)放出源の有効高さを算出する際に用いる排気筒の吹上げ高さΔHは、排気の力学的及び熱的効果によって生ずる放出高の増加であって、このΔHの算定には、種々の算定式5)6)7)が提案されている。発電用原子炉施設の場合は、排気と周囲の空気との温度差が小さいので、プルームの吹上げはほとんど力学的効果によるものと考えられる。 従来、わが国における吹上げ高さの評価においては、Hollandの式が5)参考にされている例が多い。しかし、Briggs9)は、その後の多くの実験データを検討して、いくつかの気象条件に対応した吹上げ高さの算定式を提案している。年間の被曝線量評価においては、排気筒高さについても平均的な値を使用することが適切である。そこで、指針では、中立状態に対して適用される指針(Ⅶ-1)式によって吹上げ高さを算定することとした。この式中の風速Uは、式中に逆数の形で入っているので、計算のときは、風向別風速平均Sdを用いるのが適当と考えられる。 なお、想定事故時に、吹上げ高さを考慮する場合には適切な方法を用いる必要がある。 Ⅸ 風洞実験 大気拡散の解析に用いられる風洞実験の目的は、排気筒からのプルームの主軸が建屋及び地形等によってどのような影響を受けるか、水平及び鉛直の拡散が特異性をもつかどうか、排気筒の有効高さがどのように変化するかなどを明らかにすることであり、その方法としては、排気筒付近の建屋及び地形の影響等を調査するための小区域模型による実験や敷地境界付近及びそれ以遠の影響を調査するための大区域模型による実験がある4)11)。 ここでは、敷地の地形が複雑な場合又は放出源に対する建屋等の影響が著しいと予想される場合における地表空気中濃度を推定するための風洞実験について以下に述べる。 実験に使用する模型に組み込まれる要素としては、建屋、排気筒、敷地及びその周辺の地形等がある。 具体的な実験に当たっては、地形模型によって着目方位における地表空気中濃度分布を測定するとともに、平坦地形模型を使って、数種の放出高について地表空気中濃度分布を測定し、両者を比較する。 この結果をもとに、例えば、平坦な地形に排気筒が存在しているとした場合の放出源高さを求め、拡散式中でこの放出源高さを使用すれば、地形等の影響を受けた濃度を算定することができる。 Ⅹ その他の気象条件の取扱い 大気中における物質の濃度分布は、多くの実験を基礎に確立された拡散式によって推定されるが、この拡散式のパラメータとなる気象要素は、風向、風速及び大気安定度である。 指針では、これらの気象要素を現地において少なくとも1年間観測して得られた気象資料を拡散式に用いて、放射性物質の地上空気中濃度を解析することとしたが、このほかの気象条件については次のように取り扱うこととした。 1 気象現象の年変動
気象現象は、ほぼ1年周期でくり返されているが、年による変動も存在する。 このため、想定事故時の被曝線量計算に用いる相対濃度についてその年変動を比較的長期にわたって調査してみると、相対濃度の平均値に対する各年の相対濃度の偏差の比は、30%以内であった。 このことから、1年間の気象資料にもとづく解析結果は、気象現象の年変動に伴って変動するものの、その程度はさほど大きくないので、まず、1年間の気象資料を用いて解析することとした。 その場合には、その年がとくに異常な年であるか否かを最寄の気象官署の気象資料を用いて調査することが望ましい。 また、2年以上の気象資料が存在する場合には、これを有効に利用することが望ましい。 2 上層逆転層
排気筒の上方に安定な気層があり、その下層が不安定の状態のとき、ここでは上層逆転層があるという。この場合には上方への拡散が妨げられて、地上付近の濃度が増すことがある。 指針は、地表空気中濃度を拡散式にもとづいて計算することとしているが、この拡散条件に対して特殊な気象状態である上層逆転層についてはその扱いを検討する必要がある。 上層逆転層の発生は、垂直方向の気温を観測して判断されるので、気温差の高度別出現頻度、気温逆転の高度別出現頻度、気温逆転の継続時間等を調査した結果、排気筒真上で放出物質が閉じ込れられるような上層逆転層の発生は比較的少ない現象であると推定された。 一方、上層逆転層発生時の地表空気中濃度を非常に厳しい前提(排気筒のすぐ上にふたがあるように考える)を用いて得た計算値は、指針の拡散式によって得た値と比較して極端に大きくはなかった。 このようなことから、上述のような上層逆転層の発生は、比較的少ない現象であること、たとえ発生してもそれ程大きな濃度を示さないと考えられることから、上層逆転層については、とくに計算に入れないこととした。 しかし、上層逆転層の出現が少ないことをみるため、特定の期間、気温差を観測し、気温逆転の高度別出現頻度、気温差の高度別出現頻度、気温逆転の継続時間等を把握することが望ましい。 第5表 間欠放出時における着目方位に向う回数(67%信頼度) 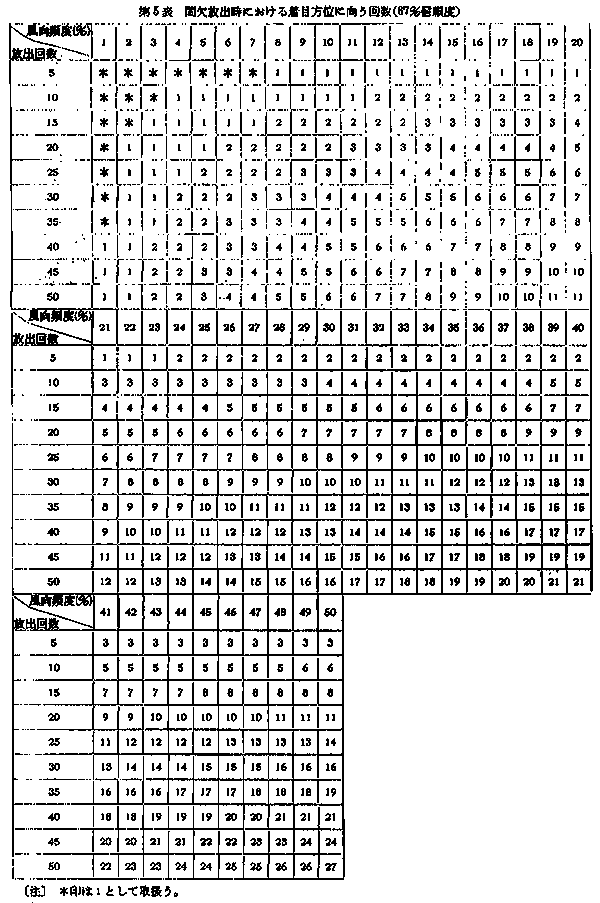 引用文献
1)Meade,P.J;The Effects of Meteorological Factors on the Dispersion of Airborne Material,Rassegns Internasionale Elettronica e Nucleare 6 Rassegna Rome 1959,Vol 11,pp107~130(1959)
2)原子力安全研究協会、夜間雲量雲形の目視観測の代りに放射収支計を用いる方法の確立、原安協報告40(1973)
3)Pasquill,F;The Estimation of the Dispersion of Windborne Material,Meteorol.Mag.90,pp33~49(1961)
4)大気汚染研究全国協議会第三小委員会編:大気汚染気象ハンドブック(第3章大気拡散) コロナ社(1965)
5)U.S.Weather Bureau;A meteorological Survey of the Oak Ridge area;Final Report Covering the Period 1948-1952,USAEC Report ORO-99,pp554-559(1953)
6)Davidson W.F;The Disperison and Spreading of Gases and Dusts from Chimneys,in Trans Conf.Ind.Wastes,14 th Annual Meeting,Industrial Hygiene Foundation of America pp.38-55(1954)
7)Bosanquet C.H;The Rise of a Hot Waste Gas Plume,J.Inst.Fuel 30(197);pp 322-328(1957)
8)Moss II.and Carson,J.E:,Stack Design Parameter Influencing Plume Rise J.Air Poll Control Assoc.,18.pp 456-458(1968)
9)Briggs,G.A;Plume Rise,TID-25075(1969)
10)Slade,D.H(ed);Meteorology and Atomic Energy 1968 TID-24190(1968)
11)横山長之、北林興二、足立芳寛;環境アセスメント手法入門
(第5章 環境濃度シュミレーションの手法)オーム社(1975)
12)伊藤直次;静穏時における41Ar雲からの被曝について
JAERI 5014(1965)、pp 138-140
|
| 前頁 | 目次 | 次頁 |