| 前頁 | 目次 | 次頁 |
|
放射性廃棄物(RI関係)実態調査結果(概要) 昭和51年4月科学技術庁原子力安全局
近年、放射性同位元素の利用の拡大に伴い、非密封の放射性同位元素使用事業所から発生する放射性廃棄物の量が増加し、この処理処分が重要な問題となってきている。これらの放射性廃棄物は、現在、法令に基づき、発生事業所において保管し、又は(社)日本アイソトープ協会が集めて日本原子力研究所において処理したうえ、同所に保管されているが、最近の諸情勢に対処して、放射性同位元素使用事業所における放射性廃棄物の発生保管処理処分の現状及び将来の発生予想量等を把握し、今後の対策の検討に資するため、今般実態調査を行った。 1 調査の概要
(1) 対象事業所
放射線障害防止法に基づく許可、届出事業所のうち、非密封の放射性同位元素(放射性医薬品を含み、核燃料物質及び核原料物質を除く。)を使用している事業所(996)を対象とした。 (2) 調査の時期及び方法
イ 昭和50年10月~11月に実施した。 ロ 各対象事業所に所定の調査票を送付し記入の上返送を求めるという通信自計式調査によった。 (3) 主な調査項目
イ 昭和49年(度)中の放射性同位元素の消費量
ロ 昭和49年(度)中の放射性廃棄物の発生量
昭和50年10月1日現在の同保管量
昭和55年(度)の同発生予想量
ハ 放射性廃棄物の前処理、引渡し先等
(4) 集計事業所 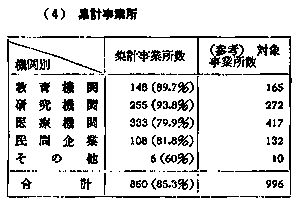 2 調査結果の概要
(1) 昭和49年(度)中に消費(注)した核種及び量(非密封RI(放射性医薬品を含む。)) 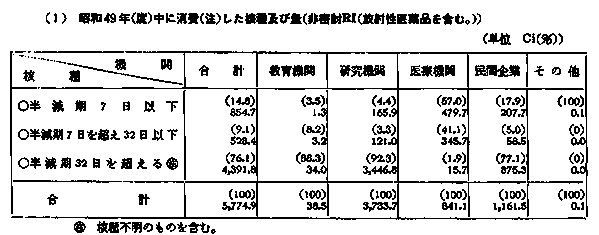 ○ 同上(日本原子力研究所分を除いたもの) 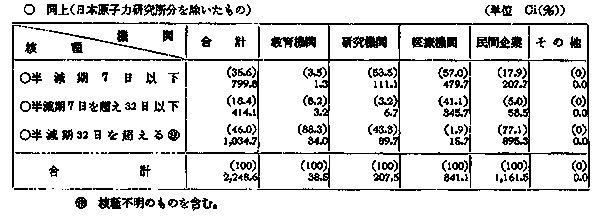 イ 非密封の放射性同位元素の使用の許可を受けている全国の850事業所において、昭和49年(度)の1年間に消費(注)した非密封の放射性同位元素(放射性医薬品を含む。)の量は、合計5,775キュリー(日本原子力研究所分を除くと2,249キュリー)であり、核種別には、半減期32日を超えるもの76.1%、同7日以下のもの14.8%等となっている。 ロ これを、日本原子力研究所分を除いて機関別にみると、消費量は、民間企業が最も多く、1,162キュリー、次いで医療機関841キュリー、研究機関208キュリー等となっており、教育機関及び民間企業では、半減期32日を超えるものが多く、それぞれ1年間の消費量の88.3%、77.1%を占めているのに対し、医療機関、研究機関では、半減期7日以下のものが多く、それぞれ57.0%、53.5%を占めている。 (注) 「消費した核種及び量」は、事業所内において消費したもののみで、加工等により製品化し、販売したものは含まない。 (2) 昭和49年(度)中に発生した放射性廃棄物の種類及び量(放射性医薬品によるものを含む。)
① 汚染核種別 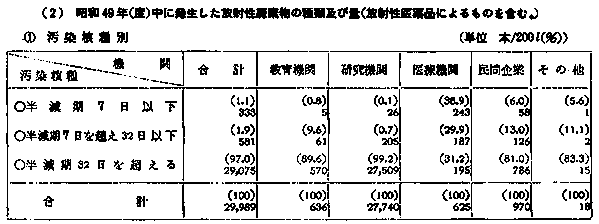 ○ 同上(日本原子力研究所分を除いたもの) 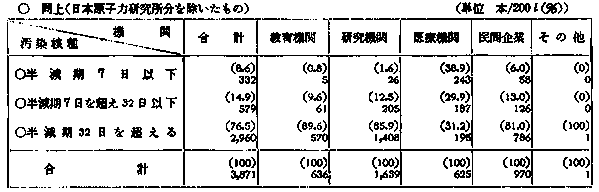 イ 全国の850使用事業所において、昭和49年(度)中に発生した放射性廃棄物の量は、200l換算で合計29,989本(日本原子力研究所分を除くと3,871本)であり、核種別には、半減期32日を超える核種により汚染されたものが圧倒的に多く、97.0%(日本原子力研究所分を除くと76.5%)を占めている。 ロ これを日本原子力研究所分を除いて機関別にみると、発生量は、研究機関が最も多く、1,639本次いで民間企業970本、教育機関636本、医療機関625本となっており、核種別には教育機関、研究機関及び民間企業においては、半減期32日を超える核種により汚染されたものが多く(それぞれ89.6%、85.9%、81.0%)医療機関においては、半減期の短い核種により汚染されたものが多い。 ハ なお、この放射性廃棄物の発生量を機関別に上記(1)の放射性同位元素の消費量と対比してみると、使用核種、使用形態等の相違を反映して、機関別、核種別に両者の数量の関係には、かなりの相違が認められる。 ② 廃棄物の種類別 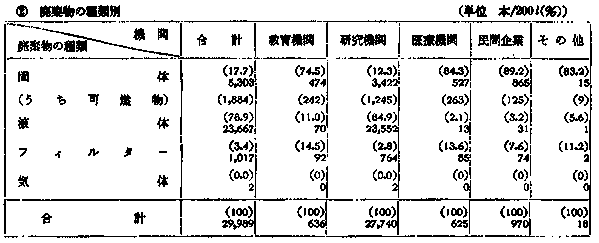 ○ 同上(日本原子力研究所分を除いたもの) 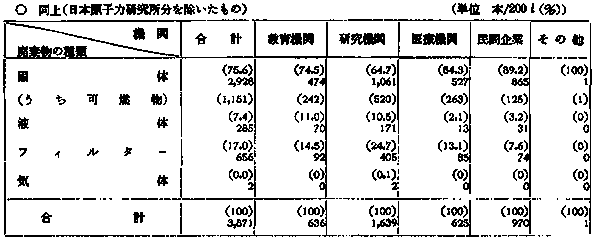 イ 全国の850使用事業所において昭和49年(度)中に発生した放射性廃棄物を種類別にみると、200l換算で、全体では液体廃棄物が23,667本(78.9%)で最も多く、次いで固体廃棄物5,303本(17.7%)フィルター1,017本(3.4%)等であるが、日本原子力研究所分を除くと、固体廃棄物2,928本(75.6%)が最も多く、次いで、フィルターが656本(17.0%)液体廃棄物が285本(7.4%)等である。 ロ 日本原子力研究所分を除いて機関別にみると、いずれの機関も固体廃棄物が大半を占め、民間企業で89.2%医療機関で84.3%教育機関で74.5%等となっている。 (3) 昭和50年10月1日現在の放射性廃棄物保管量
(放射性医薬品によるものを含む) 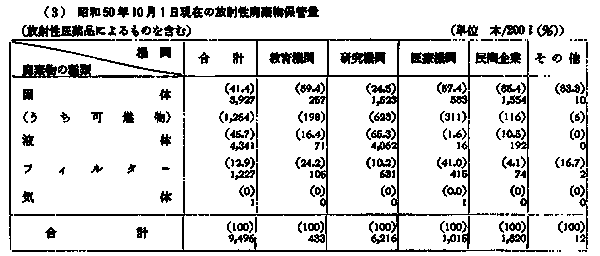 ○ 同上(日本原子力研究所分を除いたもの) 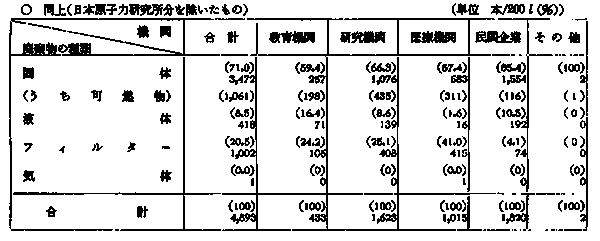 イ 全国の850使用事業所における昭和50年10月1日現在の放射性廃棄物の保管量は、200l換算で合計9,496本(日本原子力研究所分を除くと4,893本)であり、全体としては、液体廃棄物(45.7%)、固体廃棄物(41.4%)が多いが、日本原子力研究所分を除くと、固体廃棄物が大部分で71.0%を占め、次いでフィルターが20.5%となっている。 ロ 日本原子力研究所分を除いて、機関別にみると、総量としては民間企業(1,820本)研究機関(1,623本)が多く、種類別には、民間企業では、固体廃棄物の割合が多く(85.4%)教育機関、研究機関では、固体廃棄物(60%前後)とフィルター(25%前後)の割合が大きく、医療機関ではフィルターの割合が比較的大きい(41%)という特徴がみられる。 (4) 昭和55年(度)の放射性廃棄物発生予想量
① 汚染核種別 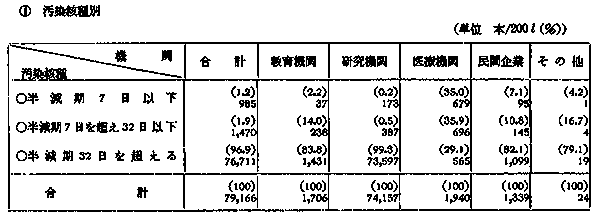 ○ 同上(日本原子力研究所分を除いたもの) 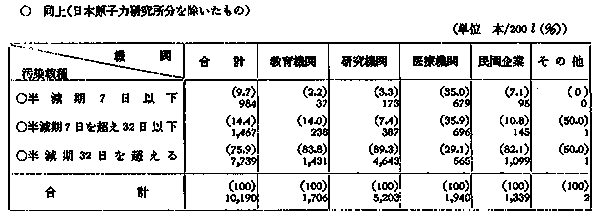 (参考)昭和49年(度)発生量に対する昭和55年(度)発生予想量の比率 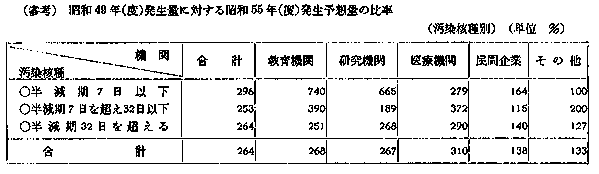 ○ 同上(日本原子力研究所分を除いたもの) 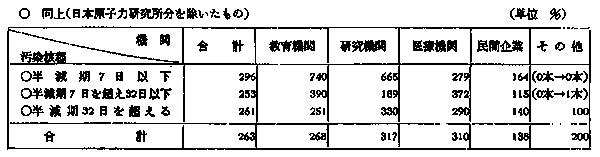 イ 全国の850事業所において、それぞれの事業所が予想している昭和55年(度)1年間の放射性廃棄物発生予想量は、200l換算で合計79,166本(日本原子力研究所分を除くと10,190本)であり、これは昭和49年(度)1年間の発生量の2.64倍(日本原子力研究所分を除くと2.63倍)に相当する。 ロ これを核種別にみると、全体としては、半減期32日を超える核種により汚染された物が圧倒的に多く、96.9%(日本原子力研究所分を除いたものでは75.9%)を占め、これは、上記(2)の昭和49年(度)発生のものと同様となるが、日本原子力研究所分を除いてみると、半減期の短い核種により汚染された廃棄物の割合が大きくなる。 ハ 日本原子力研究所分を除いて、機関別にみると、発生量は、研究機関が最も多く5,203本、次いで医療機関1,940本、教育機関1,706本、民間企業1,339本等であり、昭和49年(度)発生量と比べると、研究機関3.17倍、医療機関3.10倍で増加の予想が大きい。 ニ また、日本原子力研究所分を除いて核種別にみると、教育機関及び研究機関では、半減期7日以下の核種により汚染された物の増加の予想が特に大きく(7倍前後)、医療機関では、半減期7日を超え32日以下の核種により汚染された物の増加の予想が比較的大きい。 ② 廃棄物の種類別 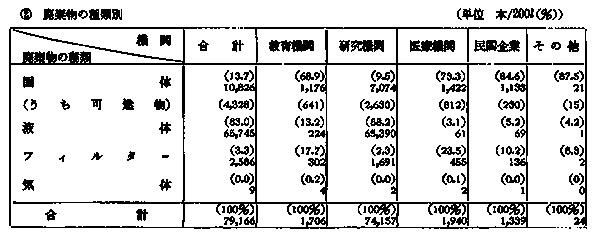 ○ 同上(日本原子力研究所分を除いたもの) 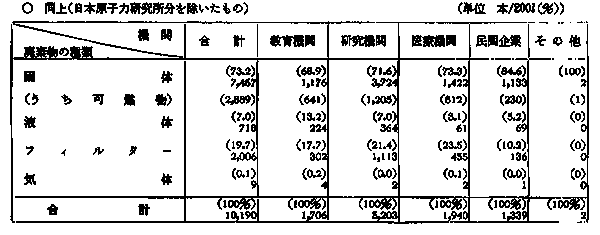 (参考) 昭和49年(度)発生量に対する昭和55年(度)発生予想量の比率 (廃棄物の種類別) 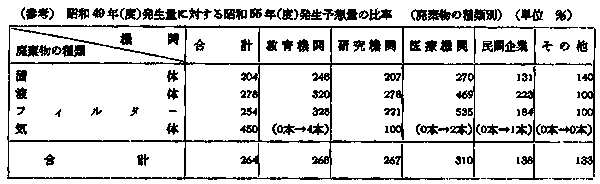 ○ 同上(日本原子力研究所分を除いたもの) 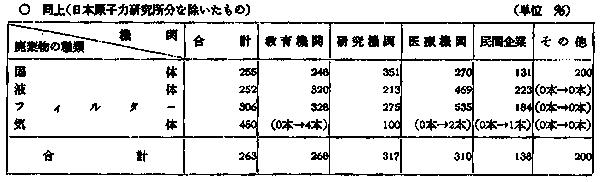 イ 全国の850使用事業における昭和55年(度)1年間の放射性廃棄物発生予想量を種類別にみると、200l換算で、全体では、液体廃棄物が65,745本(83%)で多いが、日本原子力研究所分を除くと、固体廃棄物が7,457本(73.2%)で多い。 ロ 日本原子力研究所分を除いて、昭和49年(度)発生量と比較すると、フィルターは、3.1倍、固体廃棄物は、2.6倍、液体廃棄物は、2.5倍の増加が予想されている。 ハ なお、日本原子力研究所分を除いて機関別にみると、研究機関では、固体廃棄物の増加(3.5倍)医療機関、教育機関では、フィルターの増加(それぞれ5.4倍、3.3倍)の予想が比較的大きい。 (5) 放射性廃棄物の引渡し先 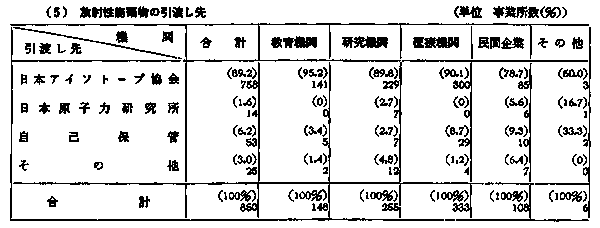 使用事業所の約90%に当たる758事業所が、発生した放射性廃棄物を放射線障害防止法により廃棄業の許可を受けている日本アイソトープ協会に引き渡しており、同じく廃棄業の許可を受けている日本原子力研究所に直接引き渡している事業所は14(1.6%)のみである。また、発生量が少い等により、他に引き渡すことなく使用事業所の保管廃棄設備において、自己保管している事業所が53(6.2%)である。 なお、「その他」とは、日本アイソトープ協会及び日本原子力研究所の双方に引き渡している事業所、廃棄物の発生のない事業所等である。 (6) 事業所における前処理
各使用事業所において、放射性廃棄物を廃棄業者に引き渡す前に何らかの処理をするいわゆる前処理については、この前処理を実施している使用事業所は、123(14.5%)あり、特に研究機関では、前処理を実施している事業所の割合が大きく、研究機関全体の27.1%の事業所で実施している。 前処理の主な内容は、蒸発濃縮、凝集沈殿、固化圧縮等である。 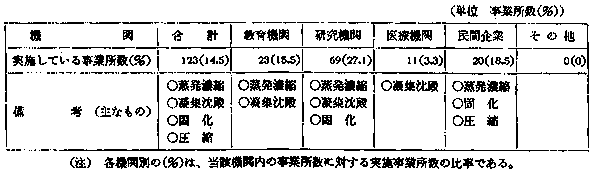 |
| 前頁 | 目次 | 次頁 |