| 前頁 | 目次 | 次頁 |
|
温排水問題に関する中間報告 昭和50年1月
中央公害対策審議会水質部会
特殊問題専門委員会温排水分科会
まえがき
自然環境における熱汚染はエネルギー使用の増大に伴って、大規模、かつ、複雑化しており、国際的にも大きな環境問題となっている。 温排水は、熱汚染の一つであり、その放熱量の増大に伴って、環境汚染として大きくクローズアップされてきた。 環境庁は、中央公害対策審議会水質部会に付託し、温排水問題の考え方、温排水拡散の予測、熱以外の要因も含めた温排水の水生生物、その他環境に与える影響、規制の考え方等について検討を重ねてきた。温排水分科会における検討結果を要約すれば、
「現在までのところ、温排水の排水実態、温排水の拡散の予測、温排水の排出に伴う地先水域の生物相の変化等について、ある程度の知見が得られているものの、温排水の規制基準を最終的に設定するためには、更に必要な調査研究を続けなければならない。」
ということである。 しかし、原子力発電所の建設推進等、温排水として放出される熱量は、今後著しく増大することが予想されるため、これを現状のまま放置することは好ましいことでなく、これらについて適切な措置をとることが緊要であると考えられる。 従って、温排水分科会としては、当面大量の温排水が排出されるような場合に、その排出が地先水域の環境あるいは漁業等が重大な影響を与えることのないよう暫定的な指針を示すとともに、更に引き続き調査研究を行うべき事項等、今後進めるべき方向を明らかにするため本中間報告を取りまとめた。 1 温排水問題の背景
我が国のエネルギー使用量は戦後の重化学工業化を中心とする経済の高度成長の基盤として、昭和35年頃より急激に増加した。このエネルギー需要の増大に伴って、一次エネルギー及び二次エネルギーの供給は急速に拡大し、発電における原子力の利用も本格化した。昭和45年には、敦賀(日本原子力発電株式会社)及び美浜(関西電力株式会社)の両原子力発電所が営業運転を開始するとともに、大型発電所の建設計画があいついで立案されるに至った。 こうした大型発電所の建設により、地先水域に放出される冷却水(いわゆる温排水)の自然環境に与える影響が問題とされるようになった。 このような状況の下に、昭和45年頃より国会等において温排水規制の必要性が論議されるようになった。すなわち、昭和45年12月に改正された公害対策基本法及び新たに制定された水質汚濁防止法において、熱についても水質汚濁の範ちゅうに含めることとする旨が規定され、温排水もこれらの法体系における規制の対象とされ得ることとなった。また、衆議院商工委員会における水質汚濁防止法案の審議において、「熱による排出水の汚染に関する排水基準を速やかに定めるよう努めること。」という附帯決議がなされており、温排水に対して適切な措置を講ずることが要請されている。 近年、発電所等の建設計画は大規模化するとともに、集中立地する傾向にあり、かつ、既存の工業地帯から離れて臨海総合工業地帯として新たに立地する場合が多くなっている。 このような動きを反映して、電源開発調整審議会における発電所建設計画に関する審議〔第58回(47年2月)頃より〕においても、温排水の漁業に対する影響が問題とされるケースが多く見られるようになった。 当時、温排水が水生生物や自然環境に与える影響については、温排水の排出実態すら十分に把握されていない状況であり、不明確な点が多かった。 このため環境庁が中心となって、温排水に関する調査研究を実施するとともに、昭和47年7月に中央公害対策審議会水質部会の下部組織として、特殊問題専門委員会温排水分科会が設置された。 当分科会は温排水の規制に関する基本方針の策定のために必要な調査研究の計画立案及び調査結果に関し審議を行うとともに、これらをもとに温排水の規制について検討を重ねてきた。 2 温排水分科会における審議経過
温排水分科会は、昭和47年7月26日に第1回の審議を行って以来現在までに8回(シミュレーション小委員会による審議を別途に3回実施)にわたり審議を重ねてきた。 審議の経過及び主たる審議事項は以下のとおりである。 温排水分科会審議経過 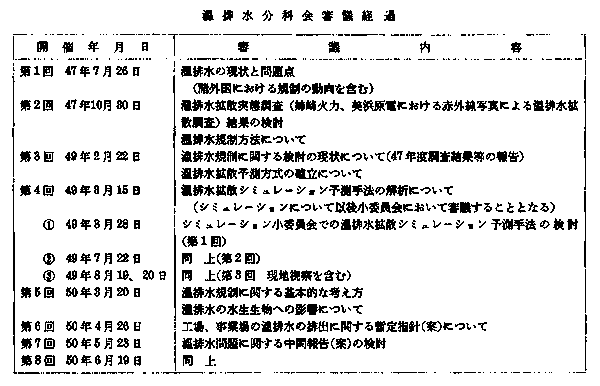 3 温排水の排出実態について
温排水を排出する工場・事業場を対象に昭和48年1月時点において、環境庁が都道府県に依頼して調査した結果は第1表に示すとおりである。 また、温排水を排出する工場・事業場のうち排水量の多い、発電、鉄鋼、石油精製、石油化学等の業種について、代表的な工場・事業場79ケ所を指定し、昭和48年1月から3月にかけて都道府県に委託して実施した実態調査の結果は第2表に示すとおりである。 これによれば、取排水の温度差(いわゆるΔT)は発電では、おおむね5~11℃、鉄鋼5~16℃、石油精製4~11℃、石油化学7~25℃と業種間及び規模等によりかなりの差がみられる。 鉄鋼、石油化学等の業種においてはΔTの値がかなり高いが、排水量は比較的少なく、平均的に見ると温排水として排出される放熱量は発電に比べて少ない。 4 温排水が水生生物に与える影響
魚類その他の水生生物は種類によって冷水を好むものと温水を好むものとがある。また、その生存し得る温度範囲の広いものと狭いものとがある。更に、馴致温度によっても、その範囲が変化することが知られている。多くの水生生物について適温域の上限、下限が知られているが、実際、水域に温排水が排出された場合、その影響の程度は遊泳力を有するものと、底生性や付着性の生物のように移動することが出来ないものとでは異なる。前者は、適温域外の温度に遭遇すれば、近隣の適温水域に移動することが出来るが、後者は移動出来ないため、温度の変化による影響を受けることがあり得る。 プランクトンは、一般に取水口から冷却水に取りこまれて熱交換器を通過する場合にその活性(例えば、クロロフィル-aの濃度の比較)は影響を受けるが、放出後周辺の水塊と混合してのち、水域全体としての活性は回復するものの、その速度は種によってかなり差がある。卵、稚仔、胞子等は熱交換器を通過する場合に機械的にも損傷を受け、死亡率が高いことが知られている。 一般に温度の上昇は生物の生長を促進するが、反面、そのため寿命の短縮や、性的成熟の阻害、孵化率の低下、奇形発生率の増大等が知られている。 実際に大量の温排水が恒常的に放出されている水域における変化を見ると、欧米等の寒冷地区では魚類をはじめとして生物相が温暖地区のそれに近く変化することが知られており、温排水の排出が施設の検査等のために停止すると、これらの生物が急激に寒冷に見舞われて死亡したりする現象が見られることもある。熱帯では、自然環境水温が既に生物の耐えられる上限に近い水温となっている場合もあるので、温排水の排出により生物相に変化をきたし、その種類数が減少することがある。 また、大量の温排水の排出は、温度だけの問題でなく、その水域に水流を生じさせることにより魚類の回遊に変化を与えたり、卵、稚仔、胞子等の分布や底質を変化させ藻場に影響を与えたりするおそれがある。 更に、遊離塩素の使用による生物への影響や富栄養化水域への影響等、二次的な影響も考えられる。 現在までの知見によれば、温排水の排出されている排水路並びにその排出に伴い常時2~3℃以上昇温している水域の範囲で生物相が変化したり、その種類数が減少したりする現象が見られることもあるものの、この水域を外れると生物相の顕著な変化は知られていない。ただ、のり等については、1℃の昇温により影響が見られることもある。 5 温排水の拡散予測
温排水の排出による地先水域の水温上昇範囲を定量的に予測する方法としては、①簡単な物理的モデルによる予測法、②淡水拡散等の調査資料に基づく経験式を利用した予測法、③数理モデルによるシミュレーション解析手法による予測法等がある。これらの予測方式は、いずれも表層放流を前提とし、それぞれ特長を有しており、その適用に当たっては、温排水の放流方式、放流量、放流地先水域の海洋条件、要求される精度等を考慮して選択する必要がある。例えば、①及び②は、半無限海域における温排水の拡散に対する目安を得るための簡便な手法を考えるべきものといえよう。 一方、数理モデルによるシミュレーション解析手法は、対象水域の地形、流れの特性及び気象条件等、温排水の拡散に関する要因をかなり数多く盛り込んで計算できることから、拡散現象を把握するのに有効な手法とされている。 発電所等の新増設に伴う大量の温排水の排出による温度上昇範囲をより精度よく推定する手法の開発が望まれていることから、当分科会では発電所の温排水についてシミュレーション解析手法による温排水拡散範囲の予測を行い、実測値との比較検討を重ねてきた。その結果、発電所のような大量の温排水の拡散予測の手法として、現時点では数理モデルによるシミュレーション解析手法が有効であると考えられるので、これを更に発展させていくことが適当と思われる。 6 温排水の規制に対する考え方
(1) 温排水が自然環境に与える影響としては、①排出地先水域の温度上昇により水生生物が受ける影響②熱交換器においてプランクトン、卵、稚仔等が受ける影響③温排水の流れによる地形、魚類の回遊、底生生物及び漁業の操業に対する影響④大量の放熱が局地的気象に与える影響⑤排出地先水域の水温上昇による水質の二次的変化等の懸念が指摘されている。 温排水の規制を考える場合、単に排出水の温度を規制するだけでは十分でなく、これらの影響を総合的に判断して実施しなければならないが、現時点では温排水の規制基準を最終的に設定するために必要な知見は必ずしも十分でない。 (2) 一般的には、現在までの調査、研究によると、排出温度が高く、放熱量が多い場合には、温排水の排出に伴い排水口に近い水域において、既存の生物相が変化することもあることが認められている。 また、米国等では排出地先水域の選択等が適切でなかった場合に生態系が著しい変化を受けた事例が起きている。 (3) 我が国では、現在までのところ温排水による特に重大な被害を伴う問題を生じていないが、温排水として排出される放熱量は、今後発電所等の規模拡大及び集中化に伴い、著しく増加することが予想される。 このため大量の温排水をこのまま放置すれば、排出地先水域の生物相の変化する範囲が広がり、周辺水域の生態系に変化を与え、海中公園等の保存及び漁業等に悪影響を及ぼすことが懸念されるため、これらについては、適切な対策がなされるべきである。 (4) 温排水の規制方法として、これまで考えられてきたものには、①排出される最高温度を定める方法②取排水の温度差、ΔTの最高値を定める方法③温排水の排出量とΔTとを乗じた総放熱量による規制方法等がある。これらの方法は、いずれも欠陥のあることが指摘されており、より有効な方法の検討が要請されている。 その一つとして、最近では立地しようとする水域の海洋学的な特性による環境容量を考慮して、温排水として排出し得る熱量を定める方式が諸外国において検討されている。この方式は、温排水の放熱量が地先水域の自然環境の許容する枠の中に納まるように定めようとするもので、温排水の規制方法として有効と思われるので、我が国においても早急に検討する必要がある。 7 当面の対策
(1) 現在までに得られた知見によれば、温排水の排出により、自然環境水温(温排水の排出地先水域のなかで、当該温排水の影響を受ける水域以外の水域における表面水温をいう。)が一定温度以上(例えば、2~3℃以上)上昇する水域の範囲に、重要な藻場、魚礁、産卵場、稚仔の生育場、海中公園地区、天然記念物生息水域等が含まれる場合には水産資源の保護、文化財等の保存に悪影響が及ぶことが予想される。また、温排水の排出先が海峡、湾口、河口及び河川の場合には、こられの水域を通過又は溯上、降河する魚類の遊泳が温排水により阻害されることがある。 従って、今後新たに大量の熱量を温排水として排出する場合には、温排水の拡散水域の予測及び水生生物の分布調査等を実施し、拡散水域の範囲と水生生物の分布等を明らかにし、水産資源の保護、文化財等の保存に重大な影響が及ばないことを、あらかじめ検討するとともに、排出後も引き続き恒常的に調査を実施し、長期にわたってそれらの変化の有無を追跡する必要がある。 また、温排水として放出される熱量を少なくする方法としては、今のところ実用的な対応策がないので、温排水の排出地先水域の熱希釈能力等を考慮して、影響域が過大になることのないように立地場所を選定する等、適切な対策がとられるように配慮する必要があろう。 (2) 温排水が自然環境に与える影響の中で流れ、熱交換器等により、プランクトン、卵、稚仔等が受ける影響は施設の構造及び設置場所等により左右されるところが大きいと思われるので、大量の温排水を今後新たに排出する場合には、特にこの点に配慮すべきである。従って、これらについては更に所要の調査、研究を重ねることも必要であると考える。 (3) 現時点において、十分知見の得られていない事項について引き続き所要の調査研究を行い、特に以下の問題について、速やかに結論を得ることに努めるとともに、その成果をまって温排水規制の本基準を作成することが適当であると考える。 今後必要な調査、検討事項等
1 温排水の温度及び流れによる生物相の変化
2 温排水の漁業及び漁業資源に与える影響
3 海域における熱の環境容量の算定方式
4 温排水の拡散過程のメカニズム並びに深層放流の場合の温排水拡散範囲の予測手法
(水理模型あるいはシミュレーション手法による)
5 冷却水の取水に伴う取水域の影響範囲の予測手法
6 熱交換器等冷却系施設でのプランクトン、卵、稚仔等の破壊、損耗、活性低下等に関する研究
7 取排水口の位置、構造等及び熱交換器等冷却系施設の設計基準の検討
8 温排水の海洋気象に与える影響
9 温排水の排出が水質に与える影響
10 温排水の養魚等への有効利用に関する研究
11 1~10をふまえた温排水の環境影響予測手法の確立
12 温排水に関する調査研究を実施する研究機関の充実
〈第1表〉温排水排出事業場数(排水量規模別、温度区分別) 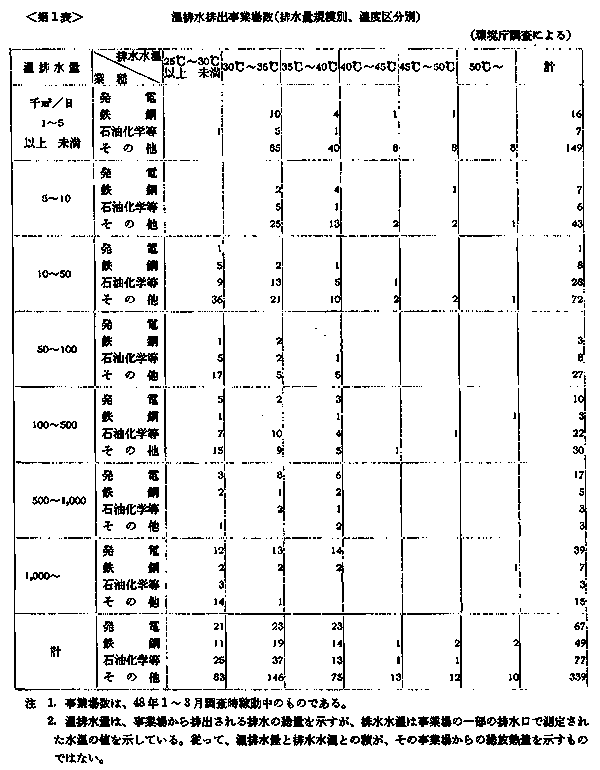 〈第2表〉その1- 発電所排出温排水実態調査 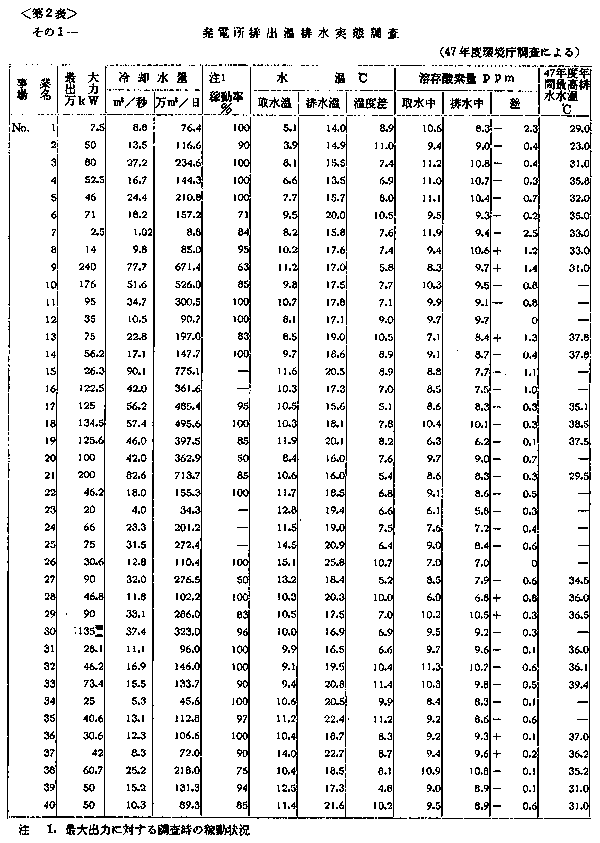 その2- 鉄鋼所排出温排水実態調査 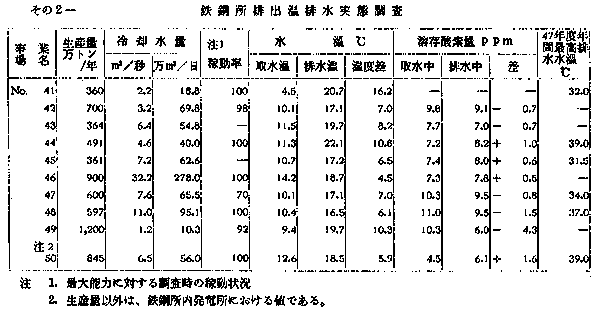 その3- 石油精製工場排出温排水実態調査 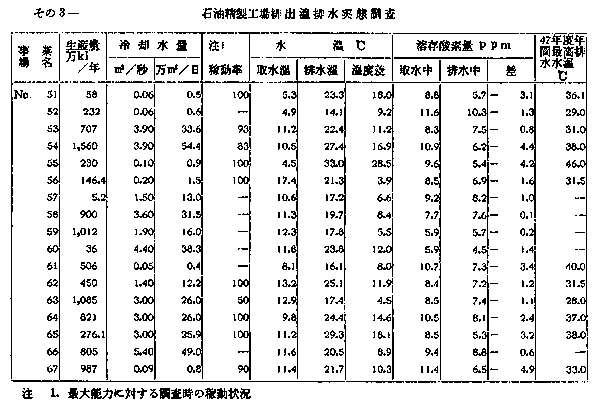 その4- 石油化学工場排出温排水実態調査 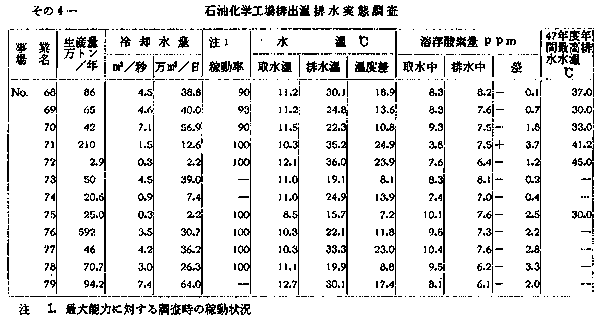 (参考)温排水排出工場実態調査に基づく業種別放熱量 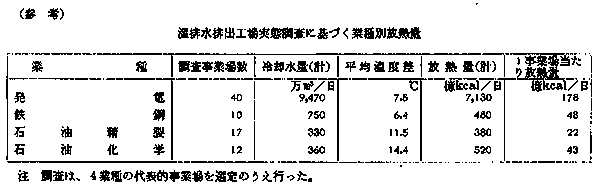 最近建設が計画されている発電所の温排水排出予定量 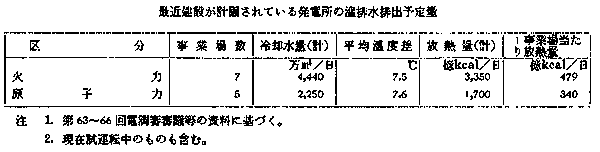
|
| 前頁 | 目次 | 次頁 |