昭和47年7月19日
原子炉安全専門審査会 |
| 原子力委員会 |
| 委員長 中曾根康弘 殿 |
原子炉安全専門審査会 |
| 会長 内 田 秀 雄 |
中部電力株式会社浜岡発電所の原子炉の設置変更(活性炭式希ガスホールドアップ装置の設置)に係る安全性について
当審査会は、昭和47年7月13日付け47原委第269号をもって審査の結果を求められた標記の件について結論を得たので報告します。 |
Ⅰ 審 査 結 果 |
中部電力株式会社浜岡発電所の原子炉の設置変更に関し同社が提出した「浜岡原子力発電所原子炉設置変更許可申請書(原子炉施設の変更)」(昭和47年3月31日付け、原発第32号をもって申請)に基づいて審査した結果、本原子炉の設置変更に係る安全性は十分確保し得るものと認める。 |
Ⅱ 変 更 事 項 |
1.気体廃棄物処理系の排ガス圧縮機および排ガス減衰タンクを廃止し、新たに減衰管および活性炭式希ガスホールドアップ装置を設置する。
2.上記(1)の変更に伴い、安全保護回路補助保護機能中、排ガス減衰タンク後の「排ガスの放射能高」信号で作動する排ガス出口弁の閉鎖機構を取り除く。 |
Ⅲ 審 査 内 容 |
1 変更事項について |
本変更は、気体廃棄物中のタービン復水器空気抽出器系排ガスの放射能を減衰タンクを用いて減衰させる方式をやめ、減衰管を通過させたのち活性炭式希ガスホールドアップ装置で希ガスをホールドアップさせ減衰させる方式に変更するものである。
この空気抽出器系排ガスに加え、タービン衛帯蒸気復水器排ガスおよび復水器真空ポンプからの排ガスについて、放出管理方法を検討しつつ、平常時被ばく評価を行なった。
その結果は、法令に規定する許容被ばく線量を大幅に下回っており、敷地周辺の公衆に対する放射線障害の防止上支障ないものと認める。
なお、放出管理方法、被ばく評価上の仮定および計算結果の概要は、次のとおりである。 |
(1)放出管理方法 |
気体廃棄物の放出にあたっては、将来の増設を考慮しても周辺監視区域外における年間被ばく線量が法令に定める値を下回るのみならず、放出管理を十分に行なってできるだけ被ばく線量を少なくするようにしている。
放出率は年間平均で0.8mCiMeV/secを管理目標とし炉内燃料破損状態が悪い場合にも空気抽出器系排ガスは減衰管にて30分減衰したのち活性炭式希ガスホールドアップ装置を通しXeを約30日、Krを約40時間活性炭にホールドアップさせ放射能を十分減衰させ上記の管理目標を満足するようにしている。
なお、敷地内外に設置する放射線監視設備により周辺への放射性気体廃棄物の放散を監視することになっている。 |
(2)被ばく評価にあたっての仮定 |
(2)-1通常出力運転時 |
① 破損燃料を考慮して希ガスの発生率を30分間減衰換算値で650mCi/sec
とする。
② 空気抽出器系排ガスは約30分間減衰したのちXeを約30日間、Krを約40時間ホールド アップする。
③ タービン衛帯蒸気復水器排ガスは約2分間減衰させる。
④ 排ガスの実効エネルギーは次表のとおりとする。
|
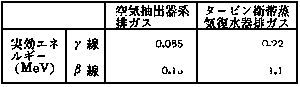 |
⑤ 排ガスは実効高さ100mの高さから放出される。
⑥ 気象条件は敷地における1年間の気象観測で得た実測値を用いる。
⑦ 静穏時の年間線量に対する寄与は、静穏の出現頻度が少ない等を考慮して無視し有風時の値を用いる。
⑧ 原子炉の年間稼働率は80%とする。
⑨ 周辺の被ばく線量の評価は各方位について行なう。
|
(2)-2 真空ポンプ運転時 |
① 真空ポンプにより真空度をあげるため1回当り800CiMeVの放出があるとする。
② プラント停止後短時間のうちに真空ポンプを運転する頻度は年間5回とする。
③ 気象条件は敷地における1年間の気象観測で得た実測値を用いる。
④ 着目方位(東)への影響回数は5回のうち3回とする。
⑤ 着日方位(東)への逆数平均風速は8m/secとする。
|
(3)計 算 結 果 |
上記(2)の仮定を用いて計算した結果、敷地外で年間の被ばく線量が最大になる地点は排気筒から東方850mでその年間被ばく線量は、γ線約1.9ミリレム、β線約1.0ミリレムである。
これは、周辺監視区域外の許容被ばく線量(500ミリレム/年)を十分下まわっている。 |
2 変更事項について |
本変更は、変更事項1にともない、不要となったガス減衰タンク加圧開始のためのインターロックを取りはずすものであり、原子炉の安全上支障のないものと認める。
|
Ⅳ 審 査 経 過 |
当審査会は昭和47年7月19日に開かれた第103回審査会において審査の結果本報告書を決定した。 |