2.1 日本における建物に震害を受けた度数の分布(資料1−1−1)
大日本地震史料、震災予防調査会報告、地震研究所彙報、気象要覧、建築雑誌等から本邦における破壊的地震による地域的被害分布を調査したものである。調査方法はまず日本地図の中に緯度、経度とも10′間隔の線を引き、一つの地震で、網目の区域に1箇所でも震害を受けた記録があれば、その網目に1点を与える。
この作業を年代別に4期に区分して行った。その間の地震回数を列記すれば、第1期599〜1191年(地震回数29回)、第2期1192〜1687年(地震回数51回)、第3期1688〜1871年(地震回数51回)、第4期1872〜1948年(地震回数35回)である。
第1期(599〜1191年)は史料が不十分であり、京都を中心とする近畿地方が特にたびたび被害を受け、第2期は鎌倉付近の被害が増している。これは政治文化の中心に古記録が偏在する結果である。そこで特に史料不備な第1期を除き第2期(1192年)以降第4期の終り(1948年)に至る間の137回の地震についてその被害を調べた。ただし第4期については被害1%以上のものをとった。その結果、被害の生ずるところはいわゆる軟弱地盤地域が著しく、特に東海道筋から近畿地方に及ぶ地帯に被害を受けた度数が多い。これに反し、茨城県および福島県の東部には被害を受けたことがない。すなわち、東海村はこの無被害地域中にあり、過去の地震回数統計からは安全地域内にある。
2.2 日本における大地震の震動記録(資料1-1-2)
日本における強震の器械観測は明治の中ごろから行われてきたが、強震計として性能の不備のため完全な記録はとれていない。
大正12年関東大地震の記録もその例であるが、従来強震計として低倍率(5倍程度)ではや回し(open-time scale)の器械で変位を記録した地震記象には工学上参考になるものもある。
関東大地震の主要動の初めは今村博士によれば全振幅約9cm、周期1.3secであり、これを simple hermonic motion と仮定すれば震度は約0.1gとなる。N.S.-component の描針が記録紙から脱出したのみならず、E.W.-component は地動があまり大きすぎたので振子は振幅制限装置に衝突して実際の地動が記録されなかった。しかしこの記録は貴重なものであるが、工学上要求する地動の性質を十分示していると思われない。
他の長周期地震計も完全な記録を与えていないが、注目すべき点は地震の最初から17cmの変位を示していることである。これは大地震の際土地の傾斜運動も考えられるから、この影響をある程度受けたかも知れないが、短周期の地動を記録するにはさしつかえない。この震動の加速度は周期を4.9sec とすればわずかに15gal(約0.015g)である。
この震動に続くものもかなり大きな振幅を有していたことは他の記録を見てもわかる。すなわち、円板上に書かれた旧式の記録(倍率1倍)では振幅40cmにも及ぶ波動が記録されている。これは地震動により地震計の振子が自己振動をやり、次第に振幅を増大したためであり、相当大きな振幅の地動が繰り返されたことは確かである。
また昭和5年11月の北伊豆地震の際、東京において15cmの全振幅を記録したことなどから、大地震の際は相当大きな変位があることは否定できない。
上記旧式の円板記録上(関東大地震)の波動中にはその振動加速度が120gal(≒0.12g)程度に達しているものと認められ、また権威ある工学者は体験からこの程度以上の震動があったことを記述している。
Open−time scale の強震計記象は大正13年1月15日の関東大地震の余震(震央は丹沢山付近)のときにも本郷で取られている。
この記録上で短周期の0.3〜0.4secの波動には計算によりその加速度が100galを越すものもある。なお茨城県下に起った強震の open−time scale の記録を集めて見ると、大正10年(1921年)12月8日の竜ヶ崎付近の地震および大正12年1月14日の関宿付近の地震のものがある。これらの記象上でも短周期の地動加速度は変位の大きい比較的長期の波動よりも大きいことが明らかである。
地震動の最大加速度およびその周期を与える波動は変位の主要部ではなく、比較的長周期でかつ大振幅の地動に superpose している secondary の波動である。通常の変位地震計の記象から特に近地地震の場合 simple hermonic の仮定に従って加速度を求めることは、不可能とまではいかないがすこぶる困難である。大振動の場合、短周期のsecondary wave は大振幅のためにかくれてしまう。それゆえ、強震の加速度を求めるには最近考案されたSMACの強震計等の独特な地震計が有効である。
2.3 強震の記象(資料1−1−3)
地震学および建築学方面からの所望に答え、科学技術庁資源局の保全防災部会は、関東大震災(1923年)以降日本およびその周辺に起った強震の記録を集録した。
(1)この記録は日本の震度階のIV(strong)以上の強さを有する地震を気象庁管下の各測候所で記録したものを集めている。
(2)1923〜1955年の期間において45回の地震の表および震源地が示されている。
(3)各地震について震度がIV以上であった地名および震度と最大加速度の関係を表にしてある。
(4)各地震ごとに各地の地震記象の簡単な記述、震度分布図を示してある。
(5)地震記象は全部で584であるが、そのうち469枚がmicro−film にとられ、それを複製して気象庁、資源局、その他関係方面においてある。micro−film のindex もその本の巻末にのせてある。
これらの地震記象のうち、東海村の地動を知るに参考となるものは、1933年福島県沖の地震の水戸における観測である。
2.4 東海村の地震特性(資料1−2−1)
東海村における日本原子力研究所の北部地域の地震時における震動性状の調査を行った。
調査地域の地下構造の概略を述べれば
砂層 (地表から深さ7.0mまで)
粘土まじり砂れき層(7.0m〜16.5m)
上部砂れき層
粘土まじり砂れき層 (16.5m〜21.3m)
下部砂れき層
砂質泥岩 (21.3mより深いところ)
地震計はボーリング孔へつり降し、自動的に水平が調整されるものを用い、地表と深さ7.0mおよび21.3mのところに設置し、地震のとき記録紙が同時にstartする仕掛けになっている。
地下における地震動振幅の減少率を求めてみると、深さ7.0mにおいては地表振幅の平均0.65倍、21.3mにおいては平均0.51倍である。また特に短周期の地動の振幅は地下では著しく小さい。振幅減少率は他動周期により異なる。
地表においては砂層の震動が顕著であって(この振動周期は0.2sec前後)地下7mにおけるこの周期の振幅は地表0.5〜0.33倍、また21.3mの深さでは0.17〜0.10倍である。
周期0.4sec程度の震動になると減少率はやや緩和され、7.0mの深さではこの周期の振動振幅は0.5〜1.0倍、21.3mでは0.2〜0.5倍になる。
この事実は従来行われた地下地震動の研究結果と同様の結論に達したが、地下層に構築物の基礎をおくときは土質力学的な安定性とあいまって地震の影響を少なくする効果のあることは疑いない。
地表面の地震動は表面層たる砂層の振動に著しく支配され、また本質的な地動が modify されているので、地震動そのものについて論ずる場合はむしろ地下21.3mの岩盤層における観測結果を用いる方がよい。
地動に関する特性としては、地震動加速度と地動周期との問題をとりあげるべきである。従来加速度の最大値を与える波動は短周期のものと考えられているが、その周期の確実な値については判然としていなかった。また、周期が延びるに従って加速度がどのように変化するかに関しても不明な点があった。これらの問題を解決する一案としては次のような方法を講じた。
東海村の基盤上で観測された地震動の加速度と周期との関係を示す曲線は4本しか得られなかったが、これらをもとにして地震動の spectrum を作ることにした。地盤の振動が一種の構築物の振動と同様に、あるresonance の型をとることはすでに知られているところである。アメリカでいう earthquake spectrum は、地震動加速度に応じた構築物の動き方を論ずるものであるが、ここでいう spectrum は地震動のため、その土地がどういう風に動くかという意味を持つもので、この点はアメリカの Spectrum とはちがっている。そこで“地盤の Spectrum”という名称で区別することにする。
構築物を対象とした spectrum に準じ、横軸に地動周期、縦軸に加速度値をとる。このようにして前述の4とおりの Spectra ができた。
四つの地盤 spectra の縦軸の絶対値は地震により異なることは当然であるが、これらの加速度 spectra の形について述べれば、それぞれの curve の縦軸値の最大は周期0.2〜0.3secの地動に対して起っている。
いま、各地震についてその縦軸値の最大値を non−dimensional に1.0とし、Spectra の曲線を common qualitative scale で表わしてみる。(第1図および第2図参照)
第1図中の spectra は0.2〜0.3secにmax. value
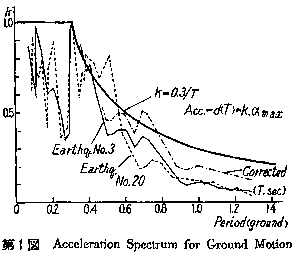
第1図 Acceleration Spectrum
for Ground Motion
|
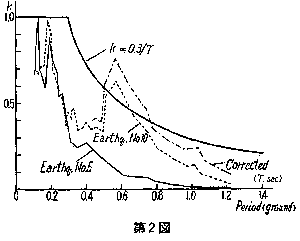
第2図
|
を有する形の曲線であり、第2図中には0.2sec付近に最大値のあるものを示している。これらの曲線は地震によりそれぞれ異なる型を呈する。すなわち、地震の震源位置、起る深さ、その他の条件によってかかる差異を生ずるものと思われるが、Spectrum の形がどの地震のときも一定であるとは考えられない。しかしこの形をいちいち論ずるよりも、地震工学方面においてはすべての地震に対して適用されるような地盤特性を論ずる方がよい。しかもその適用には安全性があるようにすべきである。そこでこれらの curves の envelopeを求め、この envelope の示す値が、各周期の最大加速度を与えるようにすることが必要である。
建物に対する spectrum と同様、この地盤の Spectrumも0〜0.3secまでは最大値を有し、0.3sec以上の長い周期の地動の加速度は、周期Tに逆比例して減少すると仮定する。すなわち図中の太線の双曲線に沿って加速度が周期とともに変化する。たとえば0.6secの地動の場合は最大加速度値の1/2の値を有し、地動の周期1.2secならば1/4の値を有する。
なお、ここに付記することは、これらの spectra が作られた元の地震記象は地震計振子の周期1.0secでほぼcritical damping をもった器械により観測されたのであるから、実際の地動は1.0sec付近では記録されているものの約2倍である。(地震計の感度はcritical damping のとき、振子の自己周期に等しい地動に対してはほぼ1/2である。)このcorrection を施し、鎖線で示したような加速度であるとすれば、実測曲線の0.5sec以上の周期に対するspectra はもっと太線に近くなる。
以上のごとく、東海村における(あるいは一般に?)地震動は周期0.3sec付近に最大加速度値があり、1.0sec以上の波動に対しては最大値の0.3倍以下の加速度値をもつといってよい。
次に太線の示すものは安全性を見て作られたものであって、おそらく大地震のときもたいした差はないと思われる。最大加速度の絶対値はそれぞれの地震により異なることはもちろんであり、また設計のため、これをいかように仮定するも自由である。
いまかりに最大加速度値を 0.2g≒200galとして0.3sec周期の波動の片振幅 A を求めると
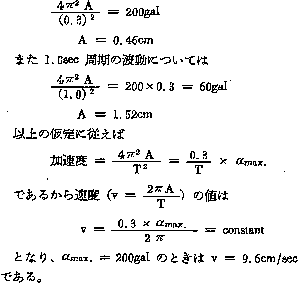
2.5 東海村における常時微動の測定(資料1−2−2)
常時微動は人為的震動源に起因することが多いが、その震動性状は各場所の地盤特有のものとなって現われ、自然地震のときにもその性状が認められるようである。
東海村の日本原子力研究所の北部地域内で、70の地点において常時微動を測定した。微動の記録から通常のごとく各地点における地動周期に対する波数を示す頻度曲線を作り、これらの曲線の形により地盤の振動性状(あるいは地盤の良否)を判定した。上述の70の測定点は多く砂層上にあるから求めた震動性状は砂層に大いに支配されている。測定結果を要約すれば、砂層の表面がまだ固まっていないところでは、頻度曲線は比較的平らとなり、固有周期がはっきりしないが、やや固まったところでは曲線は周期0.1〜0.3secに対して一つの山が生じ、さらに完全に締まって固くなっている砂層では一般の堆積地層のように曲線の山はいっそう明瞭となり、固有周期は明らかに認められる。
東海村のVan de Graaf 設置位置から北および東方に約 300m 程度の地域はこの固く締まった砂層の例であり、固有周期は0.20sec付近である。
常時微動の測定はさらに21.3m の深さの孔内においても実施された。孔底の地層は砂質泥岩であるが自然の岩盤に近い性質を有し、従来この種の岩盤において研究されたような振動性質を示している。すなわち、固有振動周期は明瞭でなく、頻度曲線は平らである。常時微動の性状からも地下21.3m の地層は岩石地盤に相当するものと判定してよい。
2.6 東海村における地震探鉱調査結果(資料1−3−1)
東海村の日本原子力研究所敷地内の北東部で、ほぼ500m×500mの地域において地震探鉱法による地下構造調査を行った。
使用計器、爆薬量その他計測に関する事項の詳細は省略する。
測線上10mごとに振動計用 pick−upを設置し、爆破孔は100〜110mごとにし、測線の長さはそれぞれ420mで、これを4本設けた。
各測線において、地下に速度の異なる地層が5層あることが認められた。すなわち、各層の速度を示せば次のとおりである。
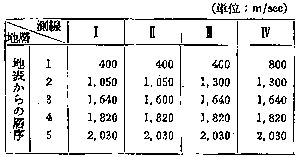
爆破によるP波動(初動)の走時およびこの表の速度から各地層の厚さを計算により求め、地下層の形状を判定した。この形状判定には数種の形状を想定し、それにもとづく走時の計算値と実測値との差が2×10−3sec以下になるような地下状態をもって最も確かなものとした。
各測定線において、第5層目の速度2,030m/secのものはボーリングにより検出されている砂質泥岩層であり、この地層の深さ(20m程度)および形状が原子炉基礎構築上最も注目すべきである。次に、第4層の速度1,820m/sec(深さ10mから20m程度)のものは下部砂れき層であり、前記の砂質泥岩層のすぐ上に存在するものである。また第3層目はさらにこの上の上部砂れき層である。以上の三つの地層は第I〜IVの各測線の地下に存在することが確認された。
第2および第1の地層は測線によって異なり、第Iの測線においては地表を湿った砂がおおい、その下にローム層がところどころに存在し、第II測線は表面砂層下にこのローム層が測線の全長にわたって存在するものと判定される。第III測線においてもこれと同様である。第IV測線においてはローム層は存在しないようである。すなわち地表の砂層はやや水分に富み、さらにその下の第2層においては砂層が水で飽和の状態にある。その下は第3層の上部砂れき層、以下下部砂れき層、砂質泥岩の順序である。
全般的に地下構造を述べれば、調査地域の表面には10m内外の砂層があり、南部丘陵地ではその下にローム層が浅くおおっているが、北方に行くに従いこのローム層は消失する。この下に相当厚い砂れき層があり、さらにその下には砂質泥岩がある。
なお第IV測線上基盤が落ち込んでいるかあるいは削り取られているように思われる地点がある。基盤の欠除範囲は半径12〜15m程度でこれを地形学的に考えれば、旧久慈川の河床の浸蝕がこの地点にまで及び、地下泥岩層がちょうど湾の形に削り取られたためと思われる。いずれにせよ、この付近に重量構造物を建設する際は地下構造を精細に調査することが必要である。また、一般の傾向として各地層の地表からの深さは北に行くほど深くなっている傾向が見られる。
2.7 東海村における地耐力、地盤係数について
(資料1−3−2,1−3−2’,1−3−3)
東海村の地盤構造の概略を述べれば、場所によってかなりの差異はあるがだいたいにおいて厚さ6〜10mの砂層およびローム層あるいはこの両層からなる表土層があり、その下に厚さ13〜20mの砂れき層、さらにその下部に砂質泥岩層が存在する。ただしこの砂れき層は、上部では砂分が多くて粘土を含む場合もあり、下部はれき分が多い傾向がある。
最上部の表土層は重量構造物の支持地盤としては不適当であるが、砂れき層は標準貫入試験結果、地耐力試験結果等を参照すれば、その上部で長期許容地耐力が20t/m2 程度を有し、下部のれき質部分では確実に40t/m2 以上の長期許容地耐力を有するものと考えられる。しかし地層の性質および動力炉の基礎盤は大きさが大きくかつかなりの根入れ深さがある点を考慮すればさらに大きい許容地耐力を見込むことができる。なお最下部の泥岩層では長期許容地耐力は100t/m2以上と推定されるが、これらの値はさらに現地地盤について検討されなければならない。
そこで動力炉が設置される場合、その基礎設置案としては次の二つが考えられる。
(1)下部砂れき層に直接ベタ基礎をおく。
(2)最下部の凝灰質砂岩までピアをおろす。
次に基盤は(1)の工法をとるとして最終沈下量を推定したが、参考資料としては東海村日本原子力研究所建設敷地地耐力試験(鹿島建設技術研究所実施)および東海村日本原子力研究所CP−5型原子炉建屋地耐力試験(清水建設研究部実施)の結果を用いた。これら地耐力試験では、45×45cm2の載荷盤を使用し、砂れき層の地盤係数k45はそれぞれ
k45=120〜300t/m2/cm
なる値がえられている。載荷盤の大きさを 50×50m2(原子炉の基礎盤の大きさ)と仮定し、補正を行ってk5,000を求めれば
k5,000=40〜100t/m2/cm
となる。
一方英国型動力炉の基礎荷重は30t/m2程度と推定されるから沈下量Δは
Δ=30/40 および 30/100=0.75および0.30cm
であり、最終沈下量はこの程度のオーダーになることが予想せられる。
なお上記砂れき層は透水性が比較的大きいから、この沈下は動力炉の建設中あるいはその直後に終ってしまい、その後長期にわたる漸進的沈下現象は見られないであろう。
現在工事進行中のCP−5の基礎の沈下量を測定し、その結果から沈下に関する資料をうることはきわめて効果的であるから、この際沈下測定を実施することを切望する。
2.8 東海村におけるボーリング調査(資料1−3−4,1−3−4’)
東海村の日本原子力研究所の北部地域で、延長550mのほぼ東西に走る直線上の6ヵ所のボーリングが実施された(昭和32年3月)。また地震探鉱法の爆破孔および地震計孔のためのボーリングが同年8月に実施され、地下の地層分布状態がかなりはっきりしてきた。
最初に述べた6ヵ所のボーリングは、西から東へNo.6,5,4,3,1,2の番号がつけられている。(第3図参照)
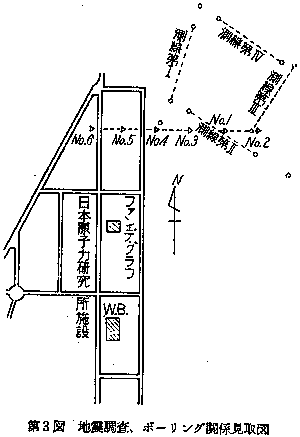
第3図 地震調査、ボーリング関係見取図
|
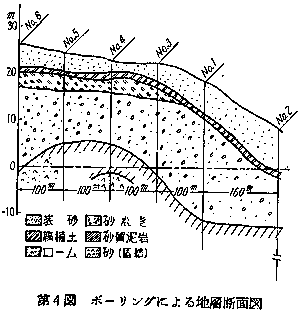
第4図 ボーリングによる地層断面図
|
各ボーリング地点の標高は25.80mから8.070mの間にありNo.3から東部は急に地表面が低くなる。
地層の最上部は砂層で、最東端のNo.2の孔では9mの厚さを有し最も厚い。この下には1m以下の厚さの腐植土層がある。さらにこの下には厚さ2m内外のローム層があるが、No.6〜No.3 間の約300mの区間にのみ存在し、No.3以東では急に消失し、No.1およびNo.2の地点では認められない。この下にある層は砂れき層であって、No.6付近では厚さ約20m、No.5で約12m、No.4で13mであって最も薄く、No.3およびNo.1ではほぼ18mの厚さで等しい。No.2ではやや薄くなり、約13mの厚さを有する。この下にある層は砂質泥岩であり、全般の形状はドーム状あるいは背斜軸類似の形状をなしている。そしてドーム状の頂点はNo.5とNo.4の中央点付近で岩盤面が地表に最も近くなっている。No.3以東この岩盤面は急に下降しNo.1およびNo.2の間はほぼ水平になっている。No.1付近はあるいは過去の海岸線あるいは河川の岸であったかも知れない。泥岩層の中から固結した砂が見いだされたこともある(No.4)。各ボーリングは最下層の泥岩層中に少なくも5m程度は入っているが、さらに異質の層が泥岩層の下にあることを認めていないので、この泥岩層も相当厚いと思われる。(第4図参照)
地震探鉱法の爆破孔は砂層をつらぬきローム層に達する深度まで掘られたものが多いが、地震観測のために掘られた孔は25mに達するものが2本ある。これら2本の試錐によって明らかにされた層序および層の厚さは前述の東西に配列せる6本のボーリング結果から妥当と考えられる。
なお、原子力研究所敷地の南部においては、土地選定直後実施された2本のボーリングがある。すなわちボーリングB−1はもと原子力研究所建設本部のあったところで、阿漕浦のすぐ東にある地点(標高20.5m)で、ここでは地表から深さ1.65mまで砂、その下4.95mまでローム層、深さ12.30mまで砂れき層、以下均質密実な砂質泥岩(第3紀層の多賀層群に属するもの)がある。
ボーリングB−2はB−1の東北東約850mの地点で、標高約8m、地表から深さ5.1mまで細砂、以下9.2mまで砂れきをまじえ、深さ10.75mから粒径の大なるれき層となり、13.8mから14.8mまでれきまじり粘土砂層となるが、ボーリングはこの深さまでであるから、これより下の状態は不明である。粘土砂層は上部のれき層に比し地耐力は相当劣るようである。
2.9 地盤の振動性能について(資料1−4−1)
日本における地震被害の統計的研究によれば、被害度は地盤の性質によることが知られている。そして木造家屋の被害は軟弱地盤において著しいが、木造以外のものの被害状況はまたちがっている。1923年関東大地震による被害調査の結果、各種構造物の破壊状況がよくわかったことと地盤の振動性能の研究が盛んになってきたので、震害といわゆるlocal geology の関係が明瞭にされつつある。
地盤振動の性質をつかむことは、耐震構造の設計、計画等をやる上に重要なことであるので、理論的あるいは観測をもとにした実験的な方法また被害統計から地盤の振動性能の研究が行われた。
地盤振動の理論的研究は地震波の伝播に関する方面からなされ、特に地層が1層あるいは多層からなる場合に波動の多重反射(multiple reflection)について研究された。また地動の地表および地中における比較観測が行われ、常時微動による地盤性状の判定等も各種の地盤で行われた。
理論的に四つの場合について研究された結果は次のとおりである。
(1)下の地層との境目に node(振動の節)を持つような波が(下から垂直に真上に)伝播する場合は、地表面の振幅は最大となる。3層ある場合、1,2および2,3の境界面にそれぞれ node があるときは特に大きくなる。
(2)各地層の境界面では波動の反射によりたがいに波の干渉が起るので、地表面での振幅のspectral response は複雑であるが、非常に特殊な場合を除きrespons の peak 値は1層の場合のように大きくはならない。
(3)入射する波動の period が大きくて表面層の中では node ができないくらいな場合、二つくらいの finite train の波が伝ってきても、その波の地表における振幅はほぼinfinite train の波の場合と同じである。
(4)波動の周期が短くて表面層中で nodes ができるような場合、波動が続いてたくさんこないと、地表の amplitude はある asymptotic value に接近しない。node は第1の境界面と最下層の境界面にあることはまれであるから、振幅が大きくなることもまれである。
なお、波の連続が長くなるにつれで振幅が増大することは常に事実とはいえない。また地表のamplitudeが最初の半波(half wave)で最大になる場合がある。これは、各境界面で反射した波の干渉による結果である。
地盤のSpectral response に関する実験公式においては、地盤の卓越周期(T0)と入射波の周期(T)とをもって振幅値(D)を表わすようになっている。
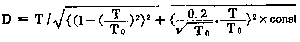
これらの理論的な研究結果から、地盤の振動性能に関するもっともらしい地球物理学上の説明ができる。
(1)震源のまわりの地震波に関しては energy のequipartition が認められる。
(2)周期が短ければ短いほど energy の消失が大きい。
(3)以上の二つのことから、地表層の底部境界面にきている波の横幅は周期に比例している。(ただし極端に短周期の波は除いて考える。)
(4)地表面で観測された spectral response の現われるのは入射波が表面層内で多重反射をやる結果である。
(5)Response の公式では、地盤振動を振子の振動になぞらえてある。常数は、地球物理学的な考察から割り出されたものである。すなわち、振子の強制振動の場合の考え方で、しかも振子の周期がdisplacement に比例して大きくなる場合である。
また、振子のdampingには 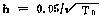 の値を与え、下層へのwave energyのdissipation、地層の viscosity による減衰等の結果を一応考慮に入れてある。 の値を与え、下層へのwave energyのdissipation、地層の viscosity による減衰等の結果を一応考慮に入れてある。
(6)極端に厚い軟弱地層は多くの層の集まりと考えるべきである。
以上概略述べたような研究の結論として次のことがいえる。
1.地震特性は地盤の性質によって異なる。
2.表面層のある地盤ではresonance curve type のspectral response を持っている。数によって卓越している周期はまた振幅において卓越している周期でもある。それゆえ建物の周期がその地盤の周期に近いときはつごうが悪いような地震力が作用する。
3.一つ以上の層から表面層が成り立っている場合にはいわゆる resonance phenomenon はめったに起らない。そして卓越振幅もきまって出てこない。しかしかかる地盤の多くは軟弱地盤であるら、地動の振幅は周期のかなり広い範囲にわたって大きい。それゆえ建物の周期のいかんにかかわらずそのような土地は地震に対して建物は不向である。
|