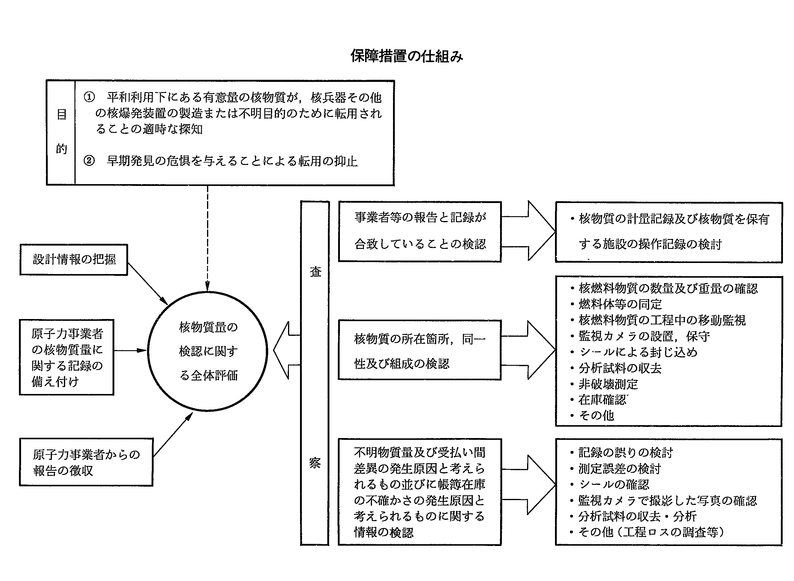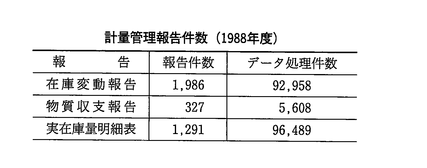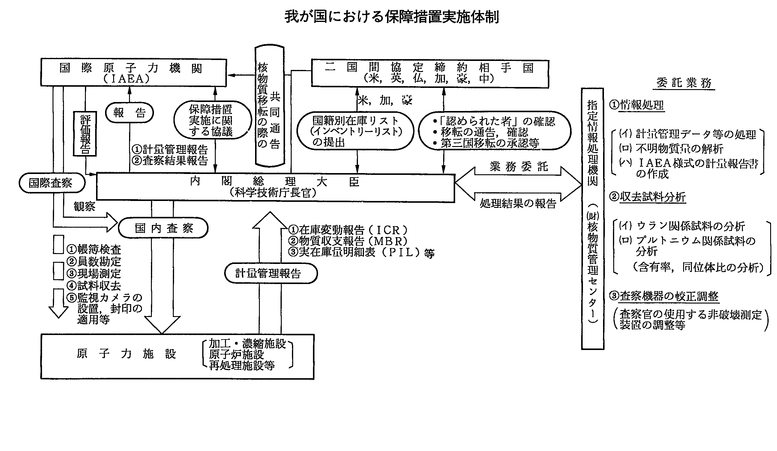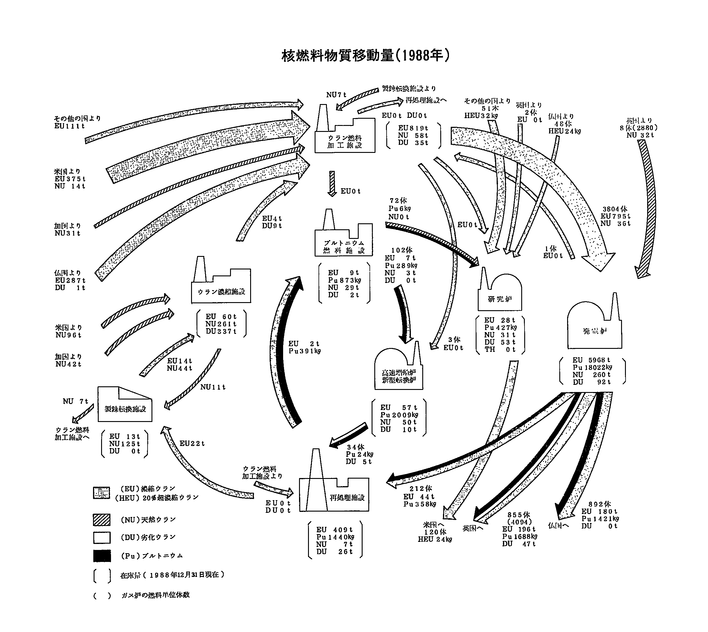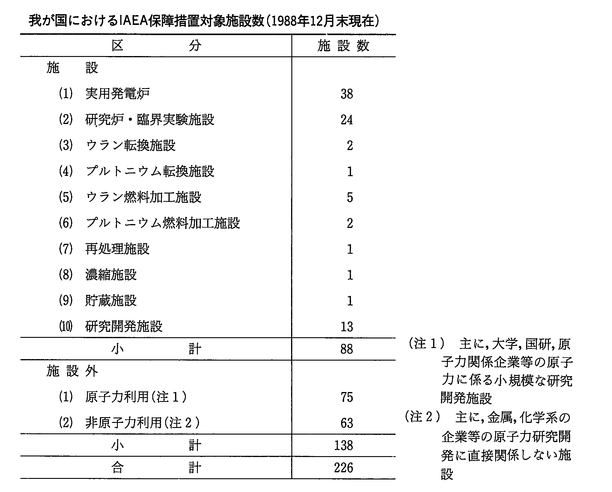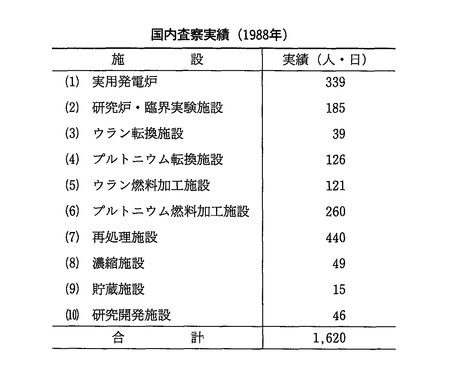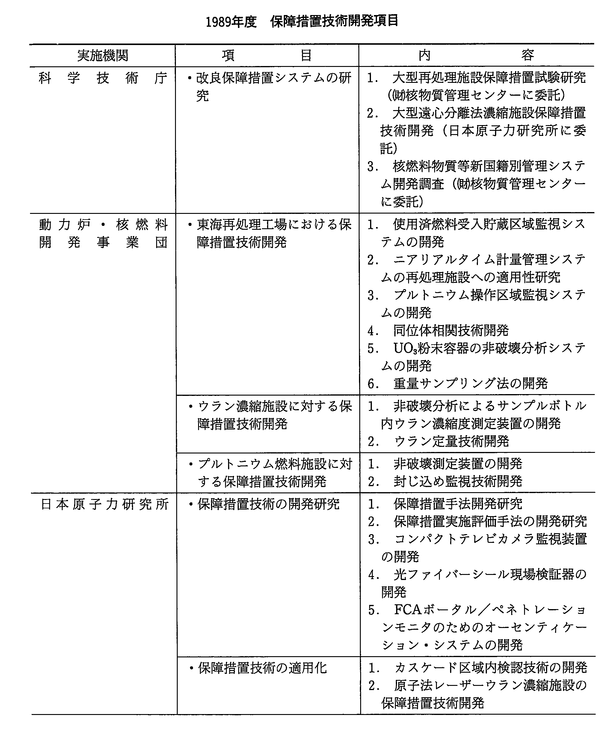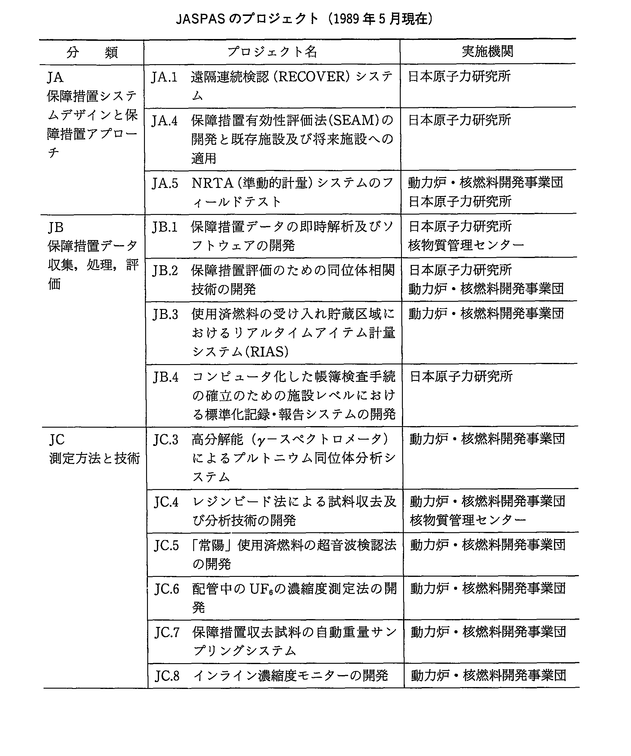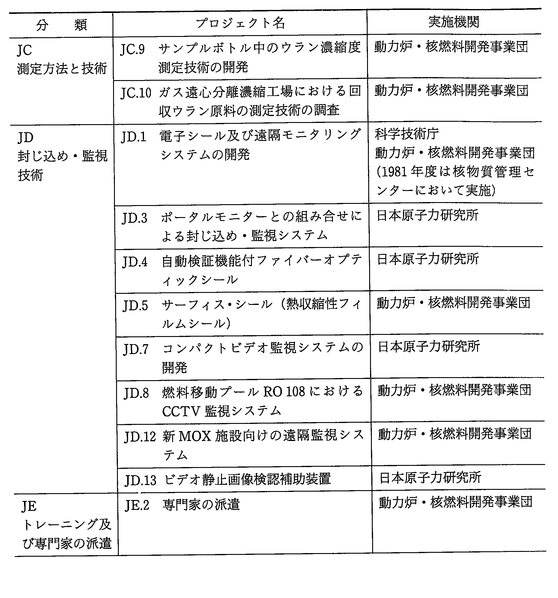3.保障措置
(1)我が国における保障措置体制
我が国は従来より原子力基本法の下に原子力開発利用を平和目的に限って推進するとともに,1976年NPTを批准し,これに基づき1977年3月にIAEAとの間に保障措置協定を締結し,国内の保障措置制度を前提とした国内全ての原子力施設に対するIAEAの保障措置を受け入れている。以上のような我が国における保障措置実施体制を図示する。
(図:我が国における保障措置実施体制)近年,プルトニウム取扱い量の増加等に伴い査察量が増大しているため,保障措置の目標達成と施設の円滑な運転とを両立させるべく保障措置の効果的・効率的適用を図ることが,1987年6月に改定された原子力開発利用長期計画でも求められている。
このためには,商業用再処理施設等今後建設が予定されている大型化・自動化された核燃料サイクル施設について,施設の設計段階から保障措置の適用性について考慮することが必要であり,事業者の協力を得つつ,効果的・効率的な国内保障措置システムの早期確立を図るとともに,それがより一層国際的に信頼性あるものとして受け入れられるようIAEA等の場を通じて働きかけていくことが要請されている。
また,我が国が締結している二国間原子力協力協定上の義務を履行するため,供給当事国別の核物質等の管理を実施してきているが,特に,1988年7月に発効した新日米原子力協定下では,従来にも増して厳格かつ詳細な核物質等の計量管理を行うことが必要となった。このような二国間協定上の義務履行を,より円滑に実施する観点から,1988年10月に国際規制物資の使用に関する規則を改正し,供給当事国ごとの計量管理,記録,報告等について必要な規定の整備を行った。
(2)保障措置の実施状況保障措置は主に核物質の計量・管理,封じ込め・監視及び査察から成り立っている。その仕組みを図(保障措置の仕組み)に示す。
これに基づき1988年度に実施された保障措置活動は下記のとおりである。
①計量管理報告及び情報処理
原子力事業者は,原子炉等規制法に基づき,国に在庫変動報告,物質収支報告及び実在庫量明細表等を提出することが義務づけられている。1988年度の報告件数及びそれらに含まれるデータの処理件数は,表のとおりである。
また,我が国における1988年の核物質の流れは図(核燃料物質移動量)のとおりである。
一方,指定情報処理機関である(財)核物質管理センターの情報処理システムに対し,情報量の増加等に対処するため,データベース管理システムの整備・充実を図っている。
②査察
我が国の原子力施設に対しては,政府による国内査察を基本とし,さらにIAEAによる国際査察が実施されている。1988年12月末現在における保障措置対象施設数及び1988年における国内査察実績は表のとおりである。なお,1988年に我が国及びIAEAが我が国の原子力施設に対して実施した保障措置の結果,核物質の平和目的以外への転用を示す異常な事実は皆無であったとの結論が得られている。
③保障措置分析
1988年度においては,(財)核物質管理センター保障措置分析所においてウラン関係試料114個,プルトニウム関係試料69個の分析を行った。
また,査察時にも非破壊測定を行った。これに加えて,合理化のため,プルトニウムの自動分析装置を用いた測定手法の検討を行った。
(3)保障措置技術に関する研究開発と国際協力日本原子力研究所,動力炉・核燃料開発事業団,(財)核物質管理センター等において,保障措置の適用をより効果的・効率的なものとするための研究開発を進めている。
1989年度の我が国における保障措置技術開発項目は,表のとおりであり,今後の大型原子力施設に対する保障措置適用のための研究開発,再処理施設等のプルトニウム取扱施設及びウラン濃縮施設に対する保障措置適用のための研究開発等に重点を置いている。
国際的には,IAEAの保障措置技術開発を我が国として支援するため,「対IAEA保障措置支援計画(JASPAS)」を,米国,英国,西独,オーストラリア,カナダに次ぎ,1981年11月に発足させた。
また,1986年度より我が国がIAEAに対して特別拠出金を拠出し,商業用大型再処理施設に対する保障措置に関する検討を行うLASCAR(大型再処理施設保障措置)プロジェクトが,米国,英国,仏国,西独,日本及びユーラトムの参加の下に実施されている。1988年10月には我が国で第1回全体会合が開催され,実質的な検討が開始された。
目次へ 第9章 第4節へ