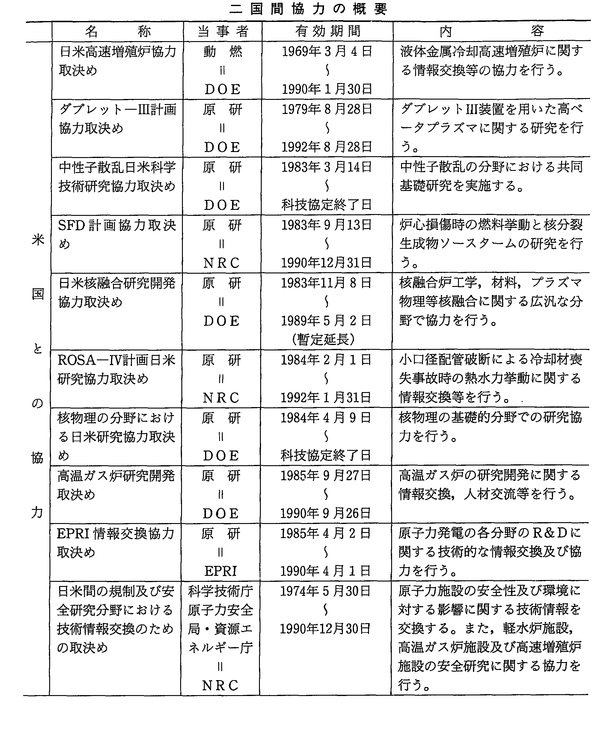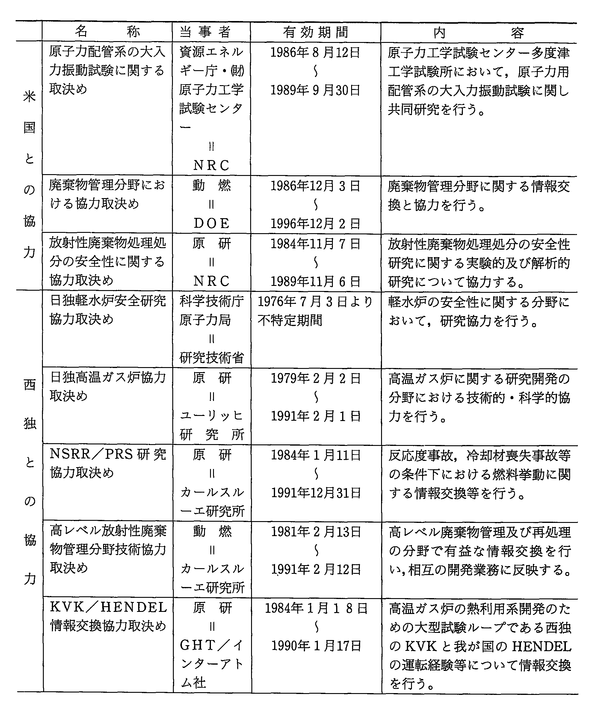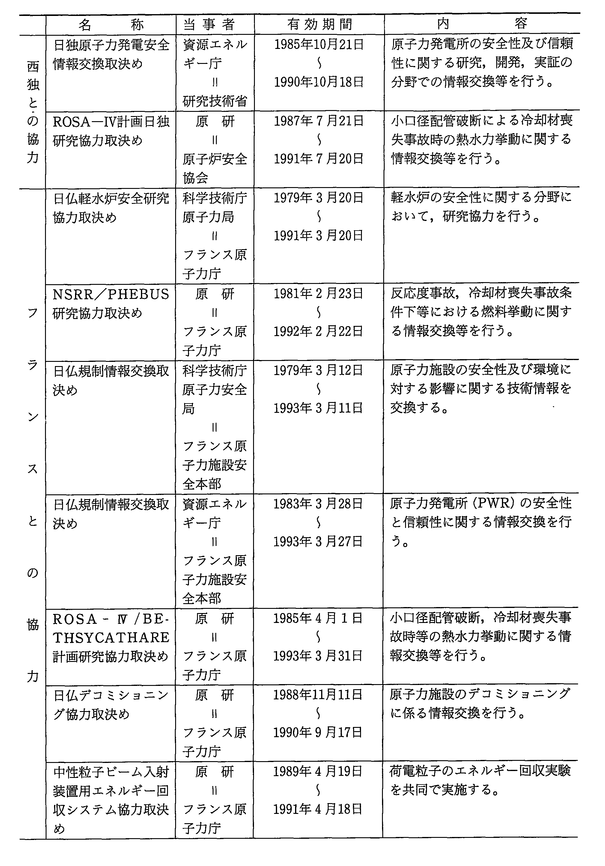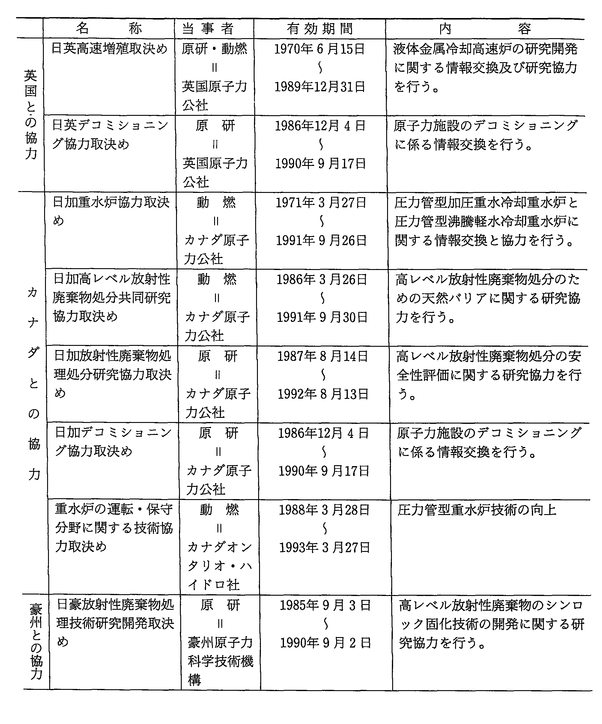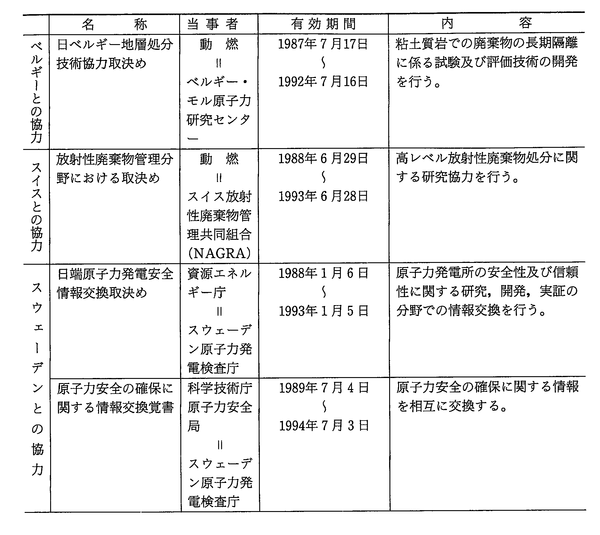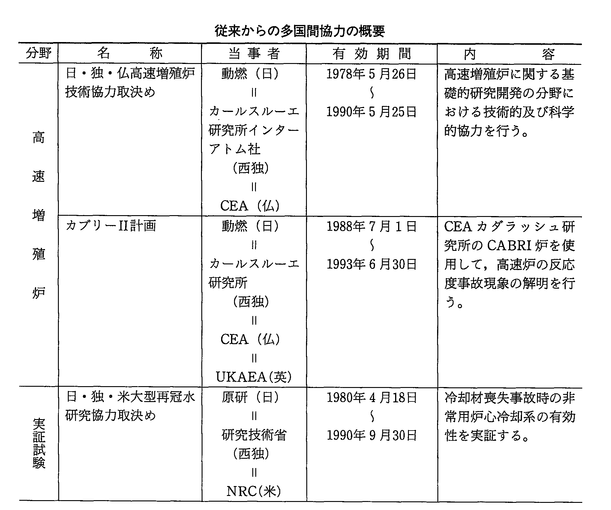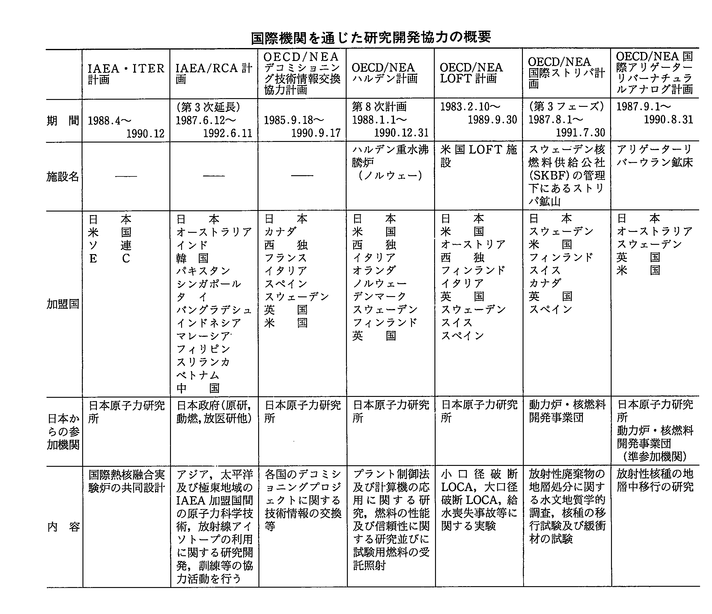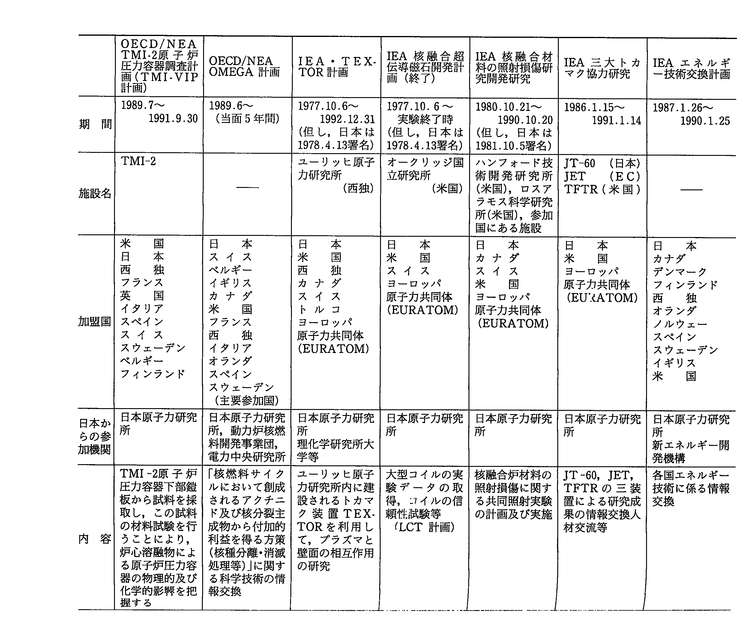1.先進国との国際協力
(1)二国間協力
①米国との協力
米国との間には,「日米間の規制及び安全研究分野における技術情報交換のための取決め」,「SFD計画協力取決め」,「ROSA-IV計画日米研究協力取決め」,「高温ガス炉研究開発取決め」,「日米高速増殖炉協力取決め」,「日米核融合研究開発協力取決め」,「ダブレットIII計画協力取決め」「核物理の分野における日米研究取決め」,「中性子散乱日米科学技術研究協力取決め」「廃棄物管理分野における協力取決め」等が締結され,研究者の相互派遣,情報交換,専門家会合の開催,共同研究等による協力が活発に行われている。
②西独との協力
西独との間には,「日独軽水炉安全研究協力取決め」,「NSRR/PRS研究協力取決め」,「ROSA-IV計画日独研究協力取決め」,「日独高温ガス炉協力取決め」,「高レベル放射性廃棄物管理分野技術協力取決め」,「KVK/HENDEL情報交換協力取決め」,「日独原子力発電安全情報交換取決め」が締結され,研究者の相互派遣,情報交換,専門家会合開催等による協力が行われている。
また,日独科学技術協力協定に基づく日独科学技術合同委員会の下で,保障措置,核燃料サイクルの安全性,重イオンビームによる高密度原子核物質の研究についても協力が行われている。
③フランスとの協力
フランスとの間には,「日仏規制情報交換取決め」,印仏軽水炉安全研究協力取決め」,「NSRR/PHEBUS研究協力取決め」,「ROSA-IV/BETHSY-CATHARE計画研究協力取決め」等が締結されている。
④その他の国との協力
英国との間には「日英高速増殖炉取決め」及び印英デコミショニング協力取決め」が,カナダとの間には「日加重水炉協力取決め」,「日加高レベル放射性廃棄物処分共同研究取決め」,「日加放射性廃棄物処理処分研究協力取決め」,「日加デコミショニング協力取決め」等が,豪州との間には,「日豪放射性廃棄物処理技術研究開発取決め」が,ベルギーとの間には「日ベルギー地層処分技術協力取決め」,スイスとの間には「放射性廃棄物管理分野における取決め」が,スウェーデンとの間には「日端原子力発電安全情報交換取決め」等が,締結されている。また,ECのユーラトム(ヨーロッパ原子力共同体)との間で政府間レベルで核融合協力協定が1989年2月に締結された。
(2)多国間協力
① 従来からの多国間協力
動力炉・核燃料開発事業団は,西独カールスルーエ研究所及びインターアトム社,フランス原子力庁との間で,高速増殖炉開発に関する協力を行っている。また,同事業団は西独カールスルーエ研究所,フランス原子力庁,英国原子力公社との間でフランス原子力庁カダラッシュ研究所のCABRI炉を使用して行われている「日独仏英共同カブリII計画」に参加し,各種の情報交換,専門家会合等を行っている。
また,大型再冠水効果実証試験の一環として,日本原子力研究所は,西独研究技術省及び米国原子力規制委員会(NRC)との間で,「大型再冠水研究協力取決め」を締結しており,冷却材喪失事故(LOCA)時の非常用炉心冷却系の有効性を実証するための研究協力を行っている。
② サミット協力プロジェクト
(i)制御熱核融合専門家会合の開催等により,個々のプロジェクトを調整し,共同計画を推進してきたところ,1987年10月の会合により,しばらく中断することとした。
(ii)高速増殖炉専門家会合の開催等により,安全設計基準,コストダウン,プラント経験等の分野での協力について検討が行われている。
③ 国際熱核融合実験炉(ITER)
1985年11月の米ソ首脳会議(ジュネーブ)における核融合研究開発推進に関する共同声明を契機として,IAEAの下で,日米,EC,ソ連の4極による国際熱核融合実験炉(ITER)の共同概念設計及び支援研究開発を1988年4月から1990年12月までの予定で実施している。
(3)国際機関との協力
① 国際原子力機関(IAEA)
我が国は,保障措置,放射性物質輸送基準,原子力安全,原子力情報システム,廃棄物管理,核融合等IAEAの主催する原子力に関する各種シンポジウム,専門家会合等に多数の専門家を派遣し,また,我が国でこれら会合を開催し,情報の収集と交換を行っている。また,RCA計画等を通して開発途上国援助に関する協力やIAEAが行う保障措置の改善を支援することを目的とした対IAEA保障措置支援計画(JASPAS)や大型再処理施設保障措置に関する検討(LASCAR)計画による協力を行っている。
② 経済協力開発機構原子力機関(OECD/NEA)
OECD/NEAにおいては,原子力施設の安全性,放射性廃棄物管理,原子力の開発と核燃料サイクルの経済的,技術的検討,並びに放射線防護及び公共保健の四分野を中心として技術的側面を主体に,これに政策的側面を併せた活動が行われている。また,1983年から1987年までその活動を一層活性化し,政策指向を目指した活動(「拡大計画」)が,加盟各国の特別拠出により実施された。
我が国は「ハルデン計画(プラント制御法及び計算機の応用に関する研究並びに燃料の性能及び信頼性に関する研究)」,「国際ストリパ計画(放射性廃棄物の地層処分に関する試験研究)」,「NEAデータバンク活動」,「LOFT計画」,「デコミショニング技術情報交換協力計画」等のプロジェクト等に参加し,共同実験,情報交換,専門家の派遣等を行っているほか, NEAの主催する各種委員会,シンポジウム,専門家会合等に多数の専門家を派遣し,意見交換,情報収集等を行っている。また,新しく「TMI-2原子炉圧力容器調査計画」に参加するとともに,我が国から提案した「核種分離・消滅処理等に関する情報交換の国際協力計画」(通称:オメガ計画)が1989年6月発足した。なお,植松邦彦博士(前動力炉・燃料開発事業団理事)が,1988年10月,事務局長に就任した。
③ 経済協力開発機構国際エネルギー機関(OECD/IEA)
我が国は,OECD/IEAの場を通じて,核融合研究に関し,「TEXTOR計画(プラズマと壁面の相互作用の研究)」,「核融合材料照射損傷計画」,「三大トカマク協力計画」また,「エネルギー技術交換計画」等に参加し,専門家派遣,各種の情報交換等を行っている。
目次へ 第8章 第2節へ