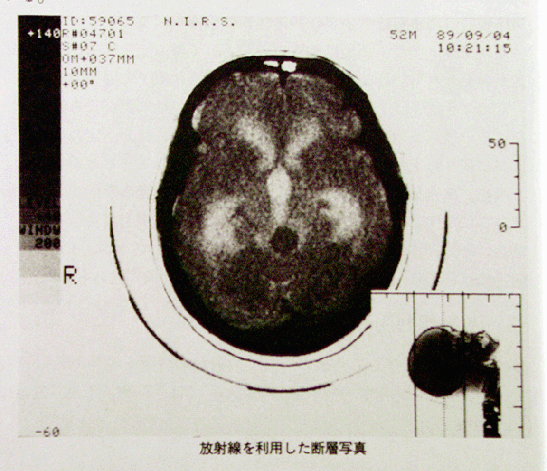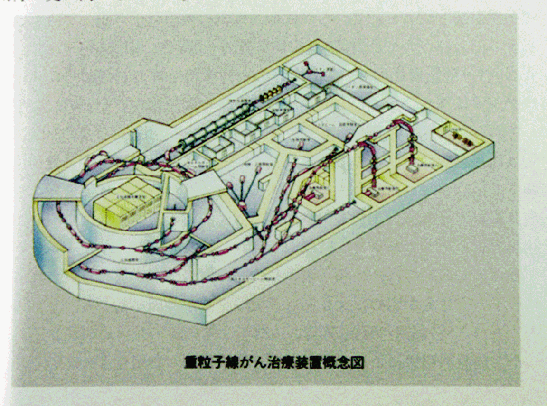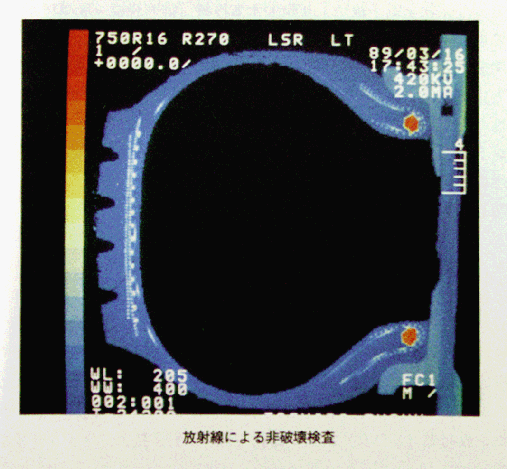2.放射線利用の推進
放射線が物質に与える効果の応用や放射線の性質を利用した計測技術・分析技術への応用等の放射線利用については,医療,工業,農業などの諸分野において活用されている。このような放射線利用は,人々の健康や日常生活に密接に関係して,国民の福祉や生活に大きく役立ち,原子力平和利用において重要な役割を担っている。
(1)医療分野への利用医療分野においては,放射線は診断・治療の手段として既に不可欠のものとして,我々の健康維持に重要な役割を果たしている。
放射線による診断では,最も広く普及している胸・胃等のエックス線撮影を始めとして,エックス線コンピュータ断層撮影(X線CT)による診断等が実用化している。また,特定の部位に選択的に集まる放射性医薬品(放射性同位元素)を体内投与し,脳の機能等を調べるポジトロンCT法による診断も開発されており,他の臓器への適用も研究されている。
このような放射線や放射性物質の利用による診断を多角的に用いることによって疾患を多面的に調べられるようになってきている。例えば脳の疾患の場合,X線CTにより組織の形状変化を診断し,ポジトロンCTにより神経伝達物質の存在や動きを捕らえて脳の機能を診断することが可能である。現在,これらの診断法を使い分け,その結果を総合的に解析・評価することにより,脳卒中,脳腫瘍などの疾患についての正確な診断が下せるようになりつつある。
一方,放射線治療は,臓器や体の機能をあまり損なわないように治療を行うことが可能であるため,その重要性は高まってきている。特に,がんの治療については,外科治療や化学療法とともに,エックス線,ガンマ線等の放射線による治療が広く普及している。放射線治療は,早期がんに対しては,外科療法と同等な治癒効果があることが実証されており,また,最近では,高齢化社会に備えて,放射線治療の効果に対する期待が更に高まっている。
さらに,放射線医学総合研究所においては,がん細胞に対する治療効果が高い重粒子線によるがん治療の早期実現を目指した調査研究も実施されており,重粒子線がん治療装置の製作が進められている。重粒子線によるがん治療は,患部のがん細胞部分を集中的に照射することが可能であるため,正常組織の障害を少なくすることができ,がん治療の切り札としての期待が高い。
(2)農林水産業分野への利用農林水産業分野においては,農作物の品種改良,害虫防除等に放射線が利用されている。特に害虫防除については,鹿児島県奄美群島,沖縄県久米島,宮古群島等において放射線照射により不妊化した虫を放飼すること(不妊虫放飼法)によってウリミバエの根絶に成功している。これによって,キュウリ,スイカ,パパイヤ等55種以上の農作物への被害が防止されるとともに,ウリミバエの本土への侵入を防ぐため,作物の移動が規制されていたこれらの作物の本土への出荷が可能となった。
食品照射については,国連食糧農業機関(FAO),国際原子力機関(IAEA),世界保健機関(WHO)の合同専門委員会が1980年に「10キログレイ以下の線量での照射食品の健全性に問題はない」との結論を出しており,諸外国でその実用化が進められている。さらに,1988年12月,90カ国16機関の専門家の参加により「照射食品の受容,管理,貿易等に関する国際会議」が開催され,各国において,消費者の理解の増進等に取り組むとともに,諸制度の整備等,食品照射の適切な利用についての検討を行うべきであるとの結論が出されている。
我が国においては,1955年頃より食品照射の研究が進められ,1967年に原子力委員会が定めた食品照射研究開発基本計画に基づき,ジャガイモ,玉ねぎ等7品目の研究開発が1988年3月に終了し,この間に,1972年から放射線照射によるジャガイモの発芽抑制が実用化されている。
また,イネ,オオムギ等の耐倒伏性,病虫害抵抗性等改良や,放射性同位元素をトレーサとした海洋中の栄養塩類の生態系内での分布と移動の解明等にも放射線が利用されており,国立試験研究機関を中心に研究が進められている。
(3)工業分野への利用工業分野においては,水分,密度,厚み等の測定に中性子,ガンマ線等の放射線が利用されている。放射線による計測は,非接触測定が可能(厚さ計),壁を通しての測定が可能(レベル計・密度計)であることをはじめ,測定精度が良いため,製品製作の各種工程管理を始め,品質管理等に多く利用されている。
すなわち,鉄鋼,機械,造船業,航空製造業等では放射線源の利用による非破壊検査,電子線照射による高分子材料の改良の他,医療器具の滅菌,電線被覆材の改良,テフロンの分解等にも放射線が広く利用されている。最近は,製紙工場における紙の乾燥工程での水分の自動制御等にも放射線が利用されており,工業分野において放射線は必須のものとなっている。
(4)資源・環境保全への利用放射線は,資源・環境保全にも広く利用されつつあり,下水汚泥の処理,排煙・排水の処理等に利用されている。
日本原子力研究所では,石炭燃焼排ガスの有害成分である二酸化硫黄と窒素酸化物を電子線により除去する技術(排煙脱硫・脱硝技術),下水処理で発生する余剰汚泥の放射線処理による殺菌と速成堆肥化技術等の開発が進められている。特に,排煙脱硫・脱硝技術については,従来の方式に比べ,システムのコンパクト化による配置スペースの低減,経済性の向上等のメリットがあり,米国,西独においても,パイロットプラントが建設され,良好な稼働実績を挙げている。このため,化石燃料の燃焼に対する公害防止技術として,特に開発途上国を中心として各国の関心を集めている。
(5)研究利用放射線利用の一層の高度化を目指した新たな展開を図るための研究が国立試験研究機関を中心に進められている。日本原子力研究所は,現在,多目的イオン照射施設を建設しており,核融合炉用材料,半導体素子の宇宙放射線による劣化の研究,バイオ技術の開発研究等を行うこととしている。また,日本原子力研究所及び理化学研究所は,高輝度シンクロトロン放射光(SOR)による物質・材料系科学技術,ライフサイエンス,情報・電子系科学技術等,広範な分野の研究を行うことを目的として,兵庫県播磨科学都市において1995年の完成を目指し大型放射光施設の建設を計画している。
理化学研究所は,線形加速器及びリングサイクロトロンを用いて,物理,化学,生物学及びその学際領域にわたる重イオン科学の研究を進めている。さらに,1989年3月に,前段加速器であるAVFサイクロトロンが完成し,同年7月には世界最高の加速性能を達成し,内外の注目を集めている。
目次へ 第3章 第3節へ