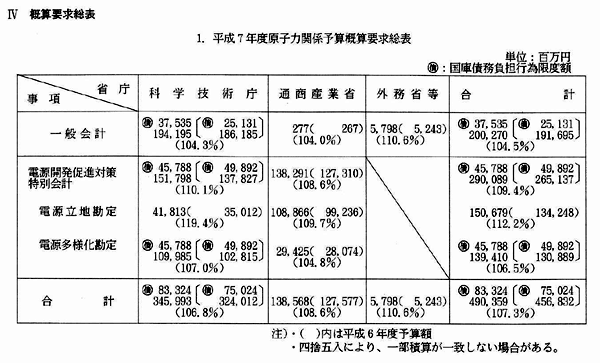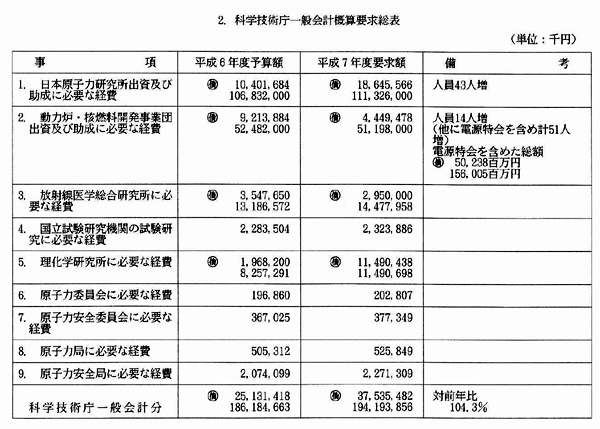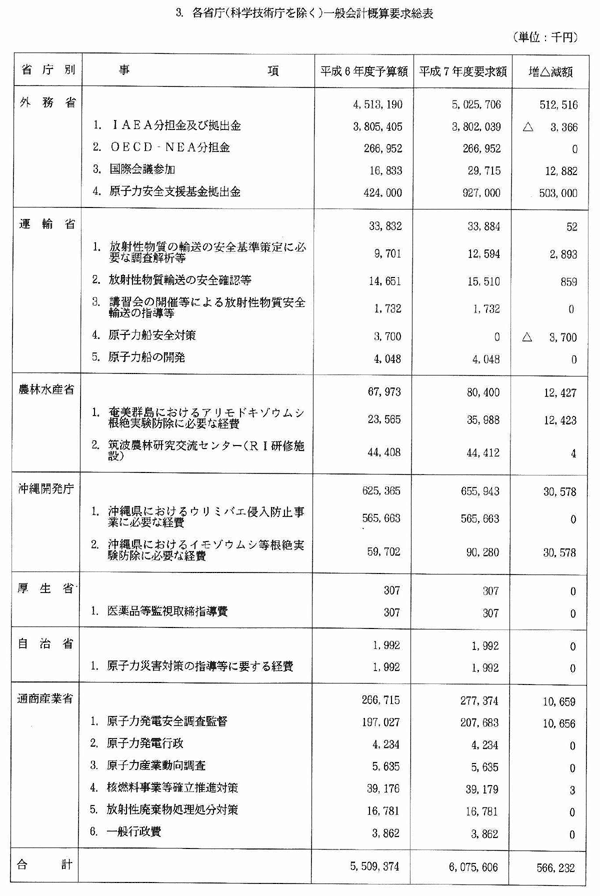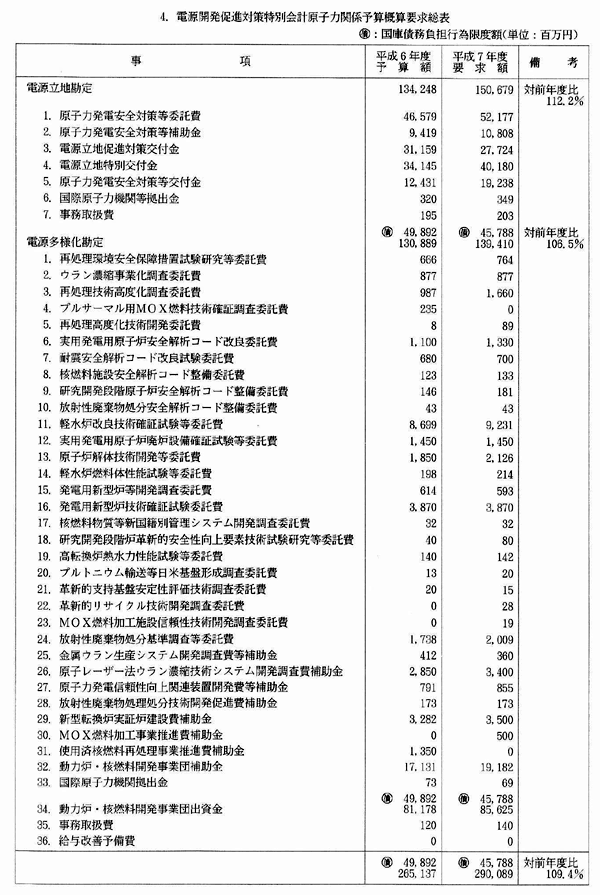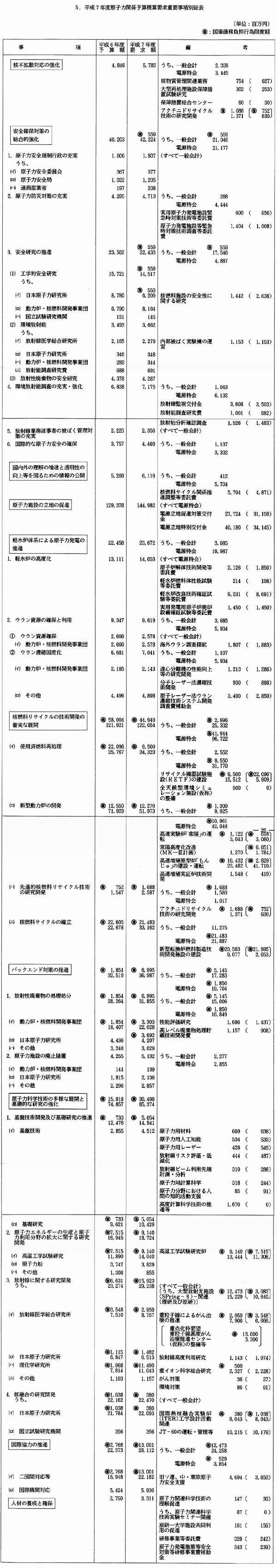| 前頁 | 目次 | 次頁 |
|
委員会の決定等 6原委第99号
平成6年9月9日
内閣総理大臣殿
原子力委員会委員長
平成7年度原子力関係経費の見積りについて 原子力委員会は、原子力委員会及び原子力安全委員会設置法第2条第3号に基づき、平成7年度原子力関係経費の見積りについて別添の通り決定したので報告する。 平成7年度原子力関係経費の見積りについて 平成6年9月9日
原子力委員会
I.基本的な考え方 我が国の原子力開発利用は、平和利用の堅持と安全の確保を大前提に、着実に進展している。現在、原子力発電は、我が国の総発電電力量の約3割を賄うに至っており、今や原子力はエネルギーの安定確保と国民生活の質の向上に必要不可欠なものとなっている。我が国のエネルギー需要は、今後相当程度の省エネルギーに努めることを前提とした試算によっても、2010年には、1991年度の約1.2倍に増加する見通しである。これに対し、我が国のエネルギー供給構造は極めて脆弱であり、我が国としては、引き続きエネルギー需要の増大を抑制するとともに、資源制約や後述する環境制約を考慮すれば、非化石エネルギーに今後大きな役割を持たせていくことが必要である。非化石エネルギーの中でも特に原子力は、優れた供給安定性、経済性を有するため、我が国のエネルギー供給構造の脆弱性の克服に貢献する基軸エネルギーとして位置づけ、その開発利用を着実に推進していくことが必要である。 さらに、原子力はエネルギー供給の観点のみならず、放射線利用についても、医療、農業、工業、生命科学、基礎研究、環境保全など広範な分野に普及しており、今後、放射線を利用した環境条件の向上や重粒子線による治療技術の研究開発にみられるような質の高い健康維持など、身の回りの生活を豊かなものとする上で一層その役割が大きくなると考えられる。 また、我が国が原子力開発利用を推進していくに当たっては、人類社会への貢献という視点を持ちつつ、これに取り組むことが必要である、近年、地球環境問題が内外の大きな関心を呼んでいるが、とりわけ地球温暖化問題はその主要原因物質となる二酸化炭素が人類の活動から不可避的に発生し、人類の生存基盤に深刻な影響を与えかねないため、その解決は人類共通の重要な課題となっている。他の発電方式に比べて圧倒的に二酸化炭素、窒素酸化物等の排出が少ないという長所のある原子力の導入は、地球温暖化や酸性雨の防止などに有効である。さらに原子力開発利用の推進に当たっては、人類にとってのエネルギー供給の多様化を図るという姿勢が重要であり、我が国は科学技術の先進国として核燃料リサイクルを推進するとともに、核融合などの研究開発を推進し、多様なエネルギーが互いに補完しながら使われていく人類社会の実現を目指すことが重要である。 ところで、第二次世界大戦後の国際秩序を規定していた東西の冷戦構造が崩壊し、政治、経済、社会など様々な分野で新たな動きが起こっているが、これは原子力の分野にも及んでいる。 例えば、核兵器の大幅な削減が現実味を帯びるなどの状況が生まれつつある一方、これに伴い生じるプルトニウム等の核物質の取り扱いが重要な課題になってきている。また、北朝鮮、イラクの核兵器開発疑惑を背景に、国際的な核兵器の拡散に対する懸念は一層高まりつつある状況となっている。加えて旧ソ連・ロシアによる放射性廃棄物の日本海等への海洋投棄が国民の不安を招いている。また、旧ソ連、中・東欧の原子力発電所の実態が一層明らかになり、その安全性に対する懸念が以前にも増して高まっており、本年のナポリサミットでも国際的な支援の必要性が取り上げられたところである。これらの状況の中でも、特に平和利用のプルトニウムも含め、プルトニウムの存在やその取扱いが、核兵器の拡散につながるとの懸念から国際的に大きな反響を呼ぶようになってきている。その中で我が国は比較的着実に核燃料リサイクル政策を展開してきており、このようなことを背景として、核兵器の拡散に対する懸念、プルトニウムの安全性への不安、プルトニウム利用の経済性への疑問から、先の仏国からのプルトニウム輸送を契機として、我が国のプルトニウム利用に対して内外から強い関心が寄せられている。 以上のような認識に立ちつつ、原子力委員会は本年6月に、我が国の原子力開発利用に関する基本政策を定める1987年に策定された「原子力開発利用長期計画」を改定し、「原子力の研究、開発及び利用に関する長期計画」(以下「新長期計画」という)を策定したところである。 新長期計画では、おおむね2030年までの原子力開発利用の展開を念頭に置きつつ、2010年頃までの具体的計画を示したが、「原子力の研究、開発及び利用は、平和の目的に限り、安全確保を旨とする」との原子力基本法の定めに則り、我が国は原子力開発利用については、国民や国際社会の理解の下に厳に平和利用に限り、安全の確保を大前提にこれを進めるとし、原子力開発利用の基本方針として、4つの点を掲げた。 第1は、「原子力平和利用国家としての原子力政策の展開」である。 これは、我が国は原子力開発利用を平和目的に徹して推進してきた結果、今日の成果を享受するに至ったが、今後とも、この姿勢を堅持するとともに、平和利用に徹してきた国にふさわしい原子力政策を展開していくことが重要であり、このため、核不拡散についての国際的信頼の確保、平和利用を指向した技術開発、平和利用先進国にふさわしい国際対応、情報の公開・提供に取り組んでいくというものである。 第2は、「整合性ある軽水炉原子力発電体系の確立と更なる信頼性・安全性の向上」である。 これは、まず、今後とも相当長期にわたり、軽水炉が原子力発電の主流を担うこととなると予想されることから、それを睨んで、その安全性、信頼性を確保しつつ、経済性の一層の向上に向けて努力していく必要があるとともに、ウラン資源の確保、ウラン濃縮などを適切かつ合理的な形で進めていくことが重要であり、また、原子力施設の立地の円滑化に向けて立地地域と原子力施設が共生できるよう積極的に取り組むことが必要であるということである。 さらに、整合性ある原子力発電体系という観点から残された最も重要な課題はバックエンド対策(放射性廃棄物の処理処分と原子力施設の廃止措置)を適切に実施するための方策を確立することであり、特に高レベル放射性廃棄物の処分は重要な課題である。 第3は、「将来を展望した核燃料リサイクルの着実な展開」である。 これは、化石エネルギー資源と同様に、ウラン資源も有限であり、軽水炉利用を中心としてこのまま推移すれば、21世紀半ば頃にもウラン需給が逼迫することも否定できないことから、核燃料リサイクルの実用化を目指して着実に研究開発を進めることによって、将来のエネルギーセキュリティの確保に備えるということであるが、核燃料リサイクルは資源や環境を大切にし、また放射性廃棄物の処理処分を適切なものにするという観点からも有意義なものである。 より具体的には、高速増殖炉は原型炉から実証炉へと研究開発の段階を歩みながら2030年までには実用化が可能になるよう、高速増殖炉による核燃料リサイクルの技術体系の確立に向けて官民協力して継続的に着実に研究開発を進め、また将来の高速増殖炉時代に必要な広範な技術体系の確立等の観点から一定規模の核燃料リサイクルを実現することが重要であり、商業規模の再処理工場の建設・運転経験を蓄積するとともに、既存の軽水炉と新型転換炉による核燃料リサイクルの実現を図っていくというものである。 また、核燃料リサイクルを進めるに当たっては、核不拡散に係る国際的な懸念を生じさせないよう保障措置等核物質管理に厳重を期すことはもとより、我が国において計画遂行に必要な量以上のプルトニウム、すなわち余剰のプルトニウムを持たないとの原則を堅持しつつ、合理的かっ整合性のある計画でその透明性の確保に努めていくこととしている。 第4は、「原子力科学技術の多様な展開と基礎的な研究の強化」である。 これは、原子力技術は、核融合エネルギー、高温ガス炉による熱供給、舶用動力、放射線利用など応用範囲は極めて広いものであり、今後とも多様な展開を図るということである。 核融合は、人類の恒久的なエネルギー源の一つになることが期待されており、我が国は自らの研究ポテンシャルを有効に活用し、主体的な国際協力の推進を図りつつ積極的にその研究開発を進める。 放射線利用は、医療、環境保全など生活者を重視した利用技術の普及促進を図るとともに、近年性能の向上が著しい加速器、研究用原子炉、大型放射光施設、レーザー装置等から発生する新しいビームを活用した先端的研究開発を推進していく。 また、既存の原子力技術の高度化のみならず、新しい原子力技術の創出が必要であり、原理、現象に立ち返った基礎研究を積極的に進めるとともにブレークスルーを引き起こす可能性のあるフロンティア領域や将来の新たな技術開発の進展を生み出す基盤を形成する可能性のある技術領域についての研究を重点的に進め、幅広い技術基盤の強化を図る。 平成7年度はこの新長期計画に沿った政策展開の初年度として、以下に示す各分野の具体的施策を講じ、原子力開発利用の総合的かつ計画的な推進を図るものとする。 II.具体的な施策 1.核不拡散対応の強化 原子力の平和利用を確保し、核不拡散対応への取り組みを強化するため、種々の施策を積極的に進める。特に、核兵器の不拡散に関する条約(NPT)に基づく国際的責務を誠実に履行するとともに、これに加えて我が国としての自発的努力を払っていく。 (1)NPTに基づくIAEA保障措置等国際約束の厳格な履行 NPTを厳格に履行するため、我が国は、日・国際原子力機関(IAEA)保障措置協定を締結し、国内保障措置体制を整備することにより、国及びIAEAによる厳格な保障措置を実施している。さらに、保障措置の有効な適用を目的として、保障措置技術分野におけるIAEA等との国際協力を行っている。 最近の国際動向を踏まえ、国内保障措置体制の維持・強化を図るため、新たな計量管理手法の導入に向けた情報処理システムの整備、保障措置の実施に必要な資料分析の効率化及び設計情報管理システムの開発を行うとともに、査察の効果的・効率的実施を目的とした技術開発、機器整備等を進める。 また、青森県六ケ所村において建設中の再処理施設に対する保障措置の実施に必要な体制を整備するため、査察官の増員を図り、該当施設に適用する保障措置の有効性を向上させるための研究開発及び保障措置の実施の中核となる保障措置総合センターのうち保障措置分析所の詳細設計を行う。 また、六ケ所再処理施設に対する核物質防護システムの開発及び動力炉・核燃料開発事業団において核物質防護に関する技術開発等関連調査研究等を行う。 (2)我が国の自発的な核不拡散努力 最近の国際動向を踏まえ、核不拡散に係わる先端的な技術等に関する調査検討、プルトニウム利用に関する透明性を高めるための国際的枠組みの検討への積極的参加、核物質等の新たな国籍別管理の効率化システムの開発等を行う。 このほか、核不拡散の観点から、旧ソ連の核兵器の解体に伴い発生する核物質の貯蔵・管理、平和利用等に関する検討・協力を行い、核物質の発生国が行う非核化のための活動を支援する。動力炉・核燃料開発事業団においては、核不拡散に係わる先端的な技術や透明性向上等に関する調査研究を行う。 さらに、核不拡散に配慮したアクチニドリサイクル技術の研究開発を行う。 2.安全確保対策の総合的強化 原子力の研究開発利用を進めるに当たっては、これまでも厳重な規制と管理を実施し、安全の確保に万全を期してきたところであるが、原子力発電所の高経年化が進みつつあること等を踏まえ、総合的な予防保全対策を強化するなど原子力の安全確保対策を充実し、安全性の一層の向上を図る。さらに、原子力発電の推進、高速増殖原型炉の運転、新型転換炉実証炉の建設計画、再処理工場等核燃料サイクル施設の建設・運転、放射性廃棄物処理処分対策の推進、放射性物質の輸送の増大及び多様化等今後の原子力研究開発利用の進展に対応し、万全の安全確保対策を講じていく必要がある。(1)原子力安全規制行政の充実 原子力の安全確保のための規制については、行政庁において法令に基づき、従来から厳正な安全規制を行っているが、今後とも、安全審査、運転管理・監督体制等のより一層の充実・強化等により安全確保を図る。 原子力安全委員会においては、行政庁の行った設置許可等に係る安全審査についてダブルチェックを行うほか、設置許可等の後の各段階においても必要に応じ調査・審議等を行い、それぞれの行政庁の行う安全規制の統一的評価を行い、原子力の安全確保に万全を期する。 原子力安全委員会の調査・審議に当たっては、原子炉安全専門審査会及び核燃料安全専門審査会の調査・審議等において、独自の安全解析を行うなど審査機能等の充実・強化を図り、客観性・合理性の確保に努める。また、行政庁の行った原子力発電所等主要原子力施設の設置許可等に係る審査についてダブルチェックを行う際には、当該施設の安全性に関し、公開ヒアリング等を実施する。 また、安全規制に必要な各種安全審査指針・基準等の整備を行う。さらに、今後、運転開始後運転年数が長期に及ぶ原子力発電所の増加が見込まれること、また、現在の安全確保の実績に安住することなくより一層の安全性向上に努めることが重要であること等を踏まえ、定期安全レビュー等の高経年化対策及びシビアアクシデント対策等の総合的な予防保全対策等を推進する。 また、条約案が採択された、民生用原子力発電所についての国際的な安全確保を目的とした「原子力安全条約」については、これに対応した所要の措置を講ずる。 放射性物質の輸送の増大・多様化に対処し、輸送の安全確保を図るため、放射性物質の輸送の安全評価等のための調査検討を進める。また、高レベル放射性廃棄物の輸送について安全確保対策の充実を図る。 さらに、IAEAにおける原子炉の安全基準改訂に関する検討、放射性廃棄物安全基準策定に関する検討、放射線防護の諸指針作成に関する検討及び放射性物質の安全輸送に関する検討並びに経済協力開発機構/原子力機関(OECD/NEA)における原子力施設安全規制国際協力事業への参加並びに米国、フランス、旧ソ連、中国等との間での安全規制の情報交換の一層の充実に努め、原子力安全に関する国際協力を一層推進し、我が国の安全審査指針・基準等の整備等安全規制の充実に資するとともに、諸外国からの専門家の招へい、IAEAにおける原子力安全に関する国際条約策定の検討への参加等世界の原子力安全確保の向上に貢献するよう努める。 また、放射性同位元素等の利用の拡大に対処して、より一層の安全確保に努める。 国際放射線防護委員会(ICRP)の1990年勧告については、放射線審議会で調査審議等を行う。 (2)原子力防災対策の充実・強化 原子力施設の万一の緊急時における防災対策を推進するため、緊急時連絡網、緊急時医療体制、防災活動資機材の整備、原子力防災に関する知識の普及等の充実を図る。また、原子力防災支援機能を強化する観点から、緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム及び緊急技術助言組織による助言の迅速・的確化等のためのシステムの整備・高度化を行うとともに、航空機による緊急時モニタリングシステム等の整備、防災支援機能の高度化及び防災業務関係者の資質の向上を図るための防災研修の充実等に努める。 (3)安全研究の推進 安全規制の裏付けとなる科学技術的知見を蓄積し、各種安全審査指針・基準等の整備・充実及び原子力施設等の安全性の向上を図るため、原子力安全委員会の定める年次計画に従い、軽水炉、新型転換炉、高速増殖炉、再処理施設等に関する原子力施設等安全研究、環境中における放射能の挙動及びその影響等に関する環境放射能安全研究及び放射性廃棄物安全研究を推進する。 ①原子力施設等安全研究 軽水炉に関する工学的安全研究については、日本原子力研究所を中心に、国立試験研究機関の協力の下に、総合的かつ計画的に実施する。特に、日本原子力研究所においては、大型非定常ループ(LSTF)等による軽水炉のシビアアクシデントの拡大防止に関する実験(ROSA-V計画)、原子炉安全性研究炉(NSRR)による反応度事故に関する試験研究、材料試験炉(JMTR)及び実用燃料試験施設(大型ホットラボ)による燃料の安全研究、事故時格納容器挙動試験等のシビアアクシデント時の安全研究等を実施する。さらに、圧力容器寿命に与える加圧熱衝撃(PTS)の影響評価研究を実施する。 また、新型転換炉については、動力炉・核燃料開発事業団において、ウラン・プルトニウム混合酸化物燃料(MOX燃料)の健全性評価に関する研究、シビアアクシデントに関する研究等を行う。 高速増殖炉については、動力炉・核燃料開発事業団等において安全設計及び評価方針の策定に関する研究、事故防止及び緩和に関する研究、シビアアクシデントに関する研究等を行う。 核燃料施設に関する工学的安全研究については、日本原子力研究所、動力炉・核燃料開発事業団等において、核燃料施設に共通な分野として臨界安全性に関する研究、遮へい安全性に関する研究、事故評価手法に関する研究、放射線管理技術の研究等を、再処理施設の安全研究では耐食安全性に関する研究、再処理プロセスの安全性に関する研究等を実施する。特に、日本原子力研究所においては、各種安全解析コードの開発等を行うとともに、燃料サイクル安全工学研究施設(NUCEF)を活用し、臨界安全性、TRU核種を含む放射性廃棄物に関する安全研究等を行う。また、動力炉・核燃料開発事業団においては、未臨界度確保に関する安全研究等を進める。 このほか、放射性物質輸送の安全性に関する研究、原子力施設の耐震安全性に関する研究等を船舶技術研究所、建築研究所等の国立試験研究機関等において実施する。 また、確率論的安全評価に関する研究については、日本原子力研究所及び動力炉・核燃料開発事業団を中心として引き続き進める。 さらに、国際協力による安全研究としては、軽水炉に関して日本原子力研究所が、燃料の性能、信頼性等に関する研究を行うハルデン計画、炉心損傷事故時の燃料挙動等に関する研究を行うCSARP計画等に引き続き参加するほか、日本原子力研究所のNSRR、軽水炉のシビアアクシデントの拡大防止に関する実験(ROSA―V計画)等に関し、米国、ドイツ、フランス等との間で研究協力を行う。また、高速増殖炉について、反応度投入事故時の燃料挙動の試験等に関し、動力炉・核燃料開発事業団が引き続き国際協力による研究に参加する。 ②環境放射能安全研究 環境放射能安全研究については、低レベル放射線の人体に及ぼす身体的・遺伝的影響の機構の解明及びそのリスクの評価に関する研究、環境における放射能挙動等に関する研究等を実施する。 低レベル放射線の人体に及ぼす影響については、放射線医学総合研究所において、低線量域における線量効果関係の実証等、人体に対する放射線リスクの評価に係る研究を推進するとともに、プルトニウム等の内部被ばくに関する研究を行う。さらに、その他の国立試験研究機関において、居住環境における放射線レベルの制御に関する研究等を実施する。 環境放射能の挙動等に関する研究については、放射線医学総合研究所その他国立試験研究機関、日本原子力研究所、動力炉・核燃料開発事業団等において、環境放射線モニタリング及び公衆の被ばく線量評価に関する調査研究、一般環境及び人体内の放射能の挙動と水準並びに食品中の放射能水準の調査を引き続き行う。また、日本原子力研究所においては、緊急時においてより広範な放射能影響を予測するためのシステムの高度化を進める。 ③放射性廃棄物安全研究 低レベル放射性廃棄物処分に関する安全研究については、日本原子力研究所等において、各原子力施設等から発生する放射性廃棄物の処分方策に係る安全確保の考え方の確立等に資するための研究等を実施する。 高レベル放射性廃棄物の地層処分に関する安全研究については、日本原子力研究所、動力炉・核燃料開発事業団、地質調査所等において、安全に関する基本的考え方と安全評価の考え方に関する研究、地層処分システムの長期安定性に関する研究等を進めるほか、多重バリアシステムに係る試験研究として、人工バリア要素の安全評価に関する研究、人工バリアシステムにおける放射性核種の移行に関する研究、地下水の水理・地質学的特性に関する研究、天然バリアにおける放射性核種の移行に関する研究、天然バリアの性能を評価するための類似の自然現象(ナチュラルアナログ)に関する調査研究等を実施する。特に、天然バリアに係る試験については、カナダ等との二国間協力及び国際機関との情報交換、人的交流等により積極的に推進する。さらに、地層処分システムの総合安全評価手法に関する研究等を進める。 なお、超ウラン(TRU)核種を含む放射性廃棄物の処分に関する安全研究については、日本原子力研究所、動力炉・核燃料開発事業団等において、TRU核種を含む放射性廃棄物の安全性評価手法に関する研究等を実施する。 (4)環境放射能調査の充実・強化 原子力発電施設等の周辺における環境放射能の的確な監視体制の整備・充実を図るとともに、周辺海域における海洋環境放射能総合評価調査、海洋モニタリングシステムの整備等を引き続き実施する。また、極東海域において旧ソ連・ロシアが放射性廃棄物を多年にわたり投棄してきた問題については、放射能による国民の健康への影響を監視する観点から、日本周辺海域の放射能監視体制の充実を図る。さらに、放射性降下物等の影響を調査するため、環境放射能水準調査等の充実を図るとともに、データの信頼性を向上させるため環境放射能分析技術の研修を充実し、また、環境放射線のデータ等を迅速に収集するためのシステムの整備を進める。 (5)放射線業務従事者の被ばく管理対策の充実 放射線業務従事者の被ばく管理については、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律、労働安全衛生法等に基づき、今後ともその徹底を図る。さらに、定期検査等における従事者の被ばくの低減化対策の充実を図る。 (6)核燃料リサイクル体系の確立、新型炉の開発等に当たっての安全確保 使用済燃料の再処理等核燃料サイクルの確立、原子炉の廃止措置に関する技術開発の推進、高速増殖炉、新型転換炉及び高温工学試験研究炉の開発、核融合の研究開発等の進展に即応して、必要な安全審査指針・基準等の検討及び安全性に関する研究開発を進める。 (7)国際的な原子力安全の確保 国際的な原子力安全の確保に関しては、各国との協議の場を通じて、それぞれの国における原子力施設の故障やトラブル等の情報収集を図るとともに、諸外国の実施する支援と整合性を図りつつ、二国間や多国間の協力の枠組みを通じた協力を実施していく。 具体的には、旧ソ連、中・東欧諸国の原子力安全の支援に関しては、マイクロフォンによる運転中異常検知システムの実証試験等の事故防止等のための短期的な技術改善、廃炉に向けた安全性調査、原子力発電所等の運転員、技術者等の資質向上を図るための研修の実施、専門家の派遣、我が国の支援した運転訓練シミュレータによるトレーニングの実施等を通じて、これらの諸国の原子力の安全性向上に資する。また、IAEAやOECD/NEAを通じた、旧ソ連・中・東欧諸国の原子力安全性調査及び評価、原子力安全解析調査の実施に積極的に参加していく。近隣アジア地域や開発途上国との協力に当たっても、これらの諸国における安全規制の体制整備、規制関係情報の交換等を通じて、これらの諸国における原子力安全確保に重点を置いた協力を行うとともに、欧州復興開発銀行に設けられた原子力安全支援基金を通じた協力を行う。さらに、本年6月に採択された原子力安全条約について所要の措置を講ずる。 3.国内外の理解の増進と透明性の向上等を図るための情報の公開 原子力の研究開発利用を円滑に進めていくためには、原子力施設立地地域の住民を始めとする国民全般の原子力に関する理解と協力を得ることが極めて重要である。このため、原子力施設の安全運転の実績を積み重ね、国民の信頼感を得るとともに、原子力の安全性、必要性等について、正確な知識及び情報を国民に伝えるための施策を関係機関との密接な連携の下に推進していく必要がある。また、情報公開については、核物質防護、核不拡散、財産権の保護に関する情報など支障を及ぼすおそれのあるものを除き、公開を原則として対応していく必要がある。特に、我が国のプルトニウム利用計画の透明性の向上を図っていくことが重要である。具体的には、原子力の研究開発利用に関する国民の正しい認識を深め、原子力発電及び核燃料サイクルを始めとする原子力の研究開発利用を一層円滑に推進するため、一般国民各層を対象とした適時的確で懇切丁寧な広報活動を展開する。 そのため、個別地点対策として、原子力発電所、核燃料サイクル施設等の立地地域等を対象とした広報素材の作成、テレビ等のマスメディアを活用した広報活動等の実施、原子力講座・フォーラム及び講習会の開催等の原子力施設の立地についての地元住民の理解と協力を得るための施策を進め、地方自治体の行う広報対策等への助成を行う。また、地方支分部局等の機能的な活動により、原子力発電所の立地に係る地元調整を推進するとともに、原子力発電の立地地域及び核燃料サイクル施設の立地地域については、原子力連絡調整官等による地元と国との密接な連絡調整を進める。 さらに、全国を対象として、新聞、テレビ、ラジオ等マスメディアを活用した広報事業、映画・ビデオ等各種広報素材の作成・提供のほか、講習会の開催等「草の根」的な広報や体験型の広報を行う。また、情報公開資料室の整備等原子力開発利用に関する情報を積極的に公開するための施策を推進する。 一方、国民の理解と協力を得るための施策の推進に当たっては、国際的な連携を強化することが必要であることから、海外における原子力施設等の安全性等に関する調査、諸外国との密接な情報交換等を行うとともに、IAEA及びOECD/NEAと協力しつつ、パブリック・アクセプタンス(国民的合意形成)に関する事業の推進を図る。 さらに、我が国の原子力開発利用計画に対する関心が国際的に高まっていることを受け、特に我が国の核燃料リサイクルへの取り組みに対する透明性の向上を図り、国内外の理解を得るため、積極的な広報活動を行う。具体的には、二国間・多国間協議の場の活用、情報システムの整備等を通じ、我が国の核燃料リサイクルへの取り組み、プルトニウム利用計画、核不拡散努力等について、幅広く国内外に情報を提供し理解の促進を図る。 4.原子力施設の立地の促進 発電用施設周辺地域整備法等の電源三法制度を活用し、原子力発電施設等の周辺住民の福祉の向上等に必要な公共用施設の整備を引き続き推進するとともに、住民、企業等に対する給付金の交付の実施、地域と発電所との共生の推進、企業立地促進策の拡充、原子力関係者の研修の実施を図ることにより、既設地域を含めた立地地域の自立的・長期的な振興施策を充実・強化し、立地の一層の推進を図る。また、環境放射能の的確な監視体制を整備するとともに、従事者等の追跡健康調査、運転管理方策調査、温排水の影響調査、再処理施設放射能影響調査、防災対策、原子力発電施設等の安全性・信頼性実証試験等を推進するほか、国民生活に密接に関連する分野における放射線の利用や立地地域における原子力基盤技術開発の推進等を通じ、原子力に対する理解の増進を図るための施策を展開し、原子力発電施設等の立地の円滑化を図る。さらに、マスメディアを通じた積極的な広報を進めるほか、中長期的な観点からの新立地方式の研究、立地技術の高度化を図る。5.軽水炉体系による原子力発電の推進 (1)軽水炉の高度化軽水炉については、信頼性及び稼働率の向上、作業員の被ばく低減化等の観点から、自主技術を基本として技術の高度化を図り、我が国に適合した軽水炉を確立するための調査を行うとともに、原子力発電検査技術の開発を行い、また、民間における原子力発電支援システムの開発の助成を行う。 また、軽水炉の安全性・信頼性を実証するため、大型再冠水効果実証試験、配管信頼性実証試験、耐震信頼性実証試験、原子力発電施設安全性実証解析等を実施する。さらに、作業員の被ばく低減化のための技術開発を実施するとともに、高機能炉心に関する技術調査、高燃焼度等燃料確証試験をその実用化のため引き続き実施し、また、安全性、経済性等の側面から、受動的安全性の概念等を取り入れた将来型軽水炉や中小型炉についての調査・設計研究や次世代の軽水炉に適用し得る高度設計システムの開発を進める。また、軽水炉の長寿命化及び稼働率向上のための技術開発、原子力発電所内における使用済燃料貯蔵対策の調査等を実施し、その実用化の促進を図るとともに、実用原子力発電所のヒューマンファクター関連技術開発、確率論的安全評価手法の改良・整備を実施する。さらに、エネルギーを取り出しながら核分裂性プルトニウムの減少を最小限に抑制し、実質的なプルトニウムの炉内貯蔵を目指す軽水炉の研究開発を実施する。 (2)ウラン資源の確保と利用 ①ウラン資源確保策の推進 動力炉・核燃料開発事業団によるオーストラリア、カナダ等における単独又は諸外国の機関と共同で行う海外ウラン調査探鉱活動を実施する。また、金属鉱業事業団の出融資制度等により、民間企業による海外ウラン探鉱開発活動を助成する。 ②ウラン濃縮国産化対策の推進 遠心分離法によるウラン濃縮の国産化を図るため、動力炉・核燃料開発事業団においてウラン濃縮原型プラントの運転試験を継続するとともに、新素材高性能遠心分離機の実用規模カスケード試験装置による試験を進める。さらに、引き続き高度化遠心機の開発を実施するとともに、遠心分離機に係る先導的な研究開発を行う。また、運転を終了した遠心機の解体、処理技術開発を進める。 また、民間によるウラン濃縮商業プラントの円滑な操業を推進するほか、ウラン濃縮の事業化に関する調査、テールウランの再転換貯蔵システム技術の確立等を行うとともに、民間によるウラン濃縮遠心分離機開発を効率的に行うための試験装置の開発に対して助成を行う。 レーザー法ウラン濃縮に関しては、原子レーザー法について日本原子力研究所において基礎的な研究を行うとともに、レーザー濃縮技術研究組合が実施するシステムの最適化を目指した要素技術等の開発に対する助成を行う。また、金属鉱業事業団において、原子レーザー法ウラン濃縮用の金属ウラン生産システムの調査・開発を行う。分子レーザー法については、理化学研究所において従来までの成果を踏まえ、レーザー及び反応に関するブレークスルー研究を行う。動力炉・核燃料開発事業団においても、理化学研究所の協力を得つつ、工学実証試験を実施する。 このほか、引き続きウラン濃縮施設及び新燃料輸送容器に関する安全性実証試験を行う。 ③回収ウランの利用 再処理により回収されたウランの利用方策について検討するとともに、技術の確立を図るため、動力炉・核燃料開発事業団においてMOX燃料の母材としての利用、UF6転換及び再濃縮に関する研究開発を進める。 6.核燃料リサイクルの技術開発の着実な展開 エネルギー資源に恵まれない我が国が、将来にわたりその経済活動を維持・発展させて行くためには、将来を展望しながらエネルギーセキュリティの確保を図っていくことが不可欠である。このため、以下の諸施策により核燃料リサイクル計画の具体化、将来の核燃料リサイクル体系の確立に向けた技術開発等を行う。(1)核燃料リサイクル計画の具体化 ①MOX燃料利用 軽水炉におけるMOX燃料利用については、MOX燃料の健全性等に関する試験を実施する。 また、新型転換炉原型炉「ふげん」については、連続運転を実施して、実証炉設計等へ反映するための運転経験及びデータの蓄積と評価を進める他、プラント運転技術等の開発を進める。同実証戸については、電源開発(株)において、2000年代初頭の運転開始を目標に建設計画を進める。また、同実証戸の安全解析コードの整備を進めるとともに、建設及び運転に必要な技術開発、試験等を行う。 ②使用済燃料再処理 再処理技術の実証と確立を図るため、動力炉・核燃料開発事業団の東海再処理施設及びプルトニウム転換施設の操業を行うとともに、所要の施設整備を行う。また、同事業団等において再処理技術の高度化等の研究開発を進める。 一方、民間による再処理工場の建設を推進することとし、動力炉・核燃料開発事業団の東海再処理施設の建設及び運転によって得られた技術等を活用し、所要の協力を行う。また、大型再処理施設の環境安全の確保、保障措置の適用のための技術開発等を行う。 また、再処理施設の安全解析コードの整備、再処理施設の安全性実証試験等を引き続き実施するとともに、NUCEF等を活用した再処理技術の高度化に関する技術開発等を行う。 さらに、大型再処理施設から放出される放射性物質が環境に与える影響等を調査するため、様々な気象条件を模擬できる「全天候型環境シミュレーション施設(仮称)」等研究施設の整備を進める。 また、高燃焼度使用済燃料輸送容器の安全性実証試験を行う。 ③使用済燃料の貯蔵・管理 使用済燃料管理に関する技術開発、原子力発電所内における貯蔵技術の確証等を行うとともに、将来的な貯蔵方法に関する調査を行う。 ④MOX燃料加工 軽水炉用MOX燃料の加工について、国内事業化を促進するため、PWR、BWR共用化技術等の実証試験に助成を行う。また、動力炉・核燃料開発事業団において、新型転換炉「ふげん」等に使用するMOX燃料の開発のため、引き続きMOX燃料製造施設の操業等を行うとともに、新型転換炉燃料製造技術開発施設の燃料製造設備等の整備を進める。さらに、グローブボックス内の残留MOX粉末の低減化対策等の技術の開発を行う。 ⑤MOX燃料等の返還輸送 海外再処理委託により回収されたプルトニウムを用いたMOX燃料等の返還輸送については、国際的な理解と協力を得ていく必要があり、輸送の安全性、必要性等に係る情報提供や広報活動を適切に実施していく。 (2)将来の核燃料リサイクル体系の確立に向けた技術開発 ①高速増殖炉技術の開発 高速増殖炉の開発については、動力炉・核燃料開発事業団の実験炉「常陽」において熱出力10万kWの照射用炉心での定格運転を行い、燃料、材料の照射試験等を実施するとともに、高燃焼度燃料等の開発に向け照射炉心の高性能化を図るため、「常陽」の高度化改造を進める。 また、同原型炉「もんじゅ」については、核加熱試験・出力試験等を経て、本格的な運転を行い、高速増殖炉によるプルトニウム利用の技術体系を原型炉段階で確認していくとともに運転実績を積み重ねていくこととする。さらに「もんじゅ」の運転開始に伴い、高速増殖炉もんじゅ技術開発センター(仮称)として体制を整備し、大洗工学センターと連携しつつ、高速増殖炉研究開発の中核的役割を果たしていくこととする。また、機器システム、燃料、材料、安全性等の研究開発を進める。 同実証炉の開発については、電気事業者、動力炉・核燃料開発事業団等が相互に連絡・調整をとりながらメーカーの協力を得て進めるが、動力炉・核燃料開発事業団では、原子炉上部からの冷却材流出入方式の特性等を明らかにするため、原子炉冷却系総合試験やプラント機器構造信頼性試験の準備を進める。また、大型構造設計に関する技術確証試験を行う。 ②再処理技術及び燃料加工技術の開発 高速増殖炉の使用済燃料を再処理する技術を確立するため、動力炉、核燃料開発事業団において実際の炉で照射した燃料を用いた工学規模の試験を行うためのリサイクル機器試験施設(RETF)の建設を進めるとともに、所要の研究開発を進める。 また、動力炉・核燃料開発事業団において、高速増殖炉「常陽」、「もんじゅ」等に使用するMOX燃料の開発のため、引き続きMOX燃料製造施設の操業等を行う。 ③先進的核燃料リサイクル技術の研究開発 高レベル放射性廃棄物の処分に当たっての環境負荷の低減、核不拡散性の向上等が期待されるアクチニドリサイクル等の先進的なリサイクル技術の研究開発については、動力炉・核燃料開発事業団において、アクチニドを含む燃料の設計及び炉心設計等の燃焼技術、使用済燃料中のアクチニドの溶媒抽出法による分離回収等の再処理技術、遠隔操作等によるアクチニドを含む燃料の加工技術等の各種研究開発を進める。 また、金属燃料リサイクルシステムの研究開発、窒化物燃料に関する研究開発等を進める。 7.バックエンド対策の推進 原子力発電の進展、核燃料サイクルの事業化等を背景に、放射性廃棄物の処理処分対策とそれらの施設の廃止等に伴う原子力施設の廃止措置対策は、ますますその重要性を増している。これらは、バックエンド対策と総称されるが、これを適切に実施するための方策を確立することは、整合性のある原子力発電体系という観点から残された最も重要な課題である。(1)放射性廃棄物の処理処分対策 放射性廃棄物対策の基本方針としては、多種多様な放射性廃棄物の特性を踏まえて合理的に実施し、安全確保を大前提に、国民の理解と協力の下、関係各機関の責任関係を明確化して計画的に推進していくこととしており、具体的には以下のような施策を推進する。 ①発電所廃棄物の処理処分 原子力発電所等において発生する低レベル放射性廃棄物(発電所廃棄物)については、原子力発電規模の拡大に伴い、今後とも発生量の増加が予想されているところであり、その適正な処理処分のための技術開発を推進するとともに、発生から処理処分に至る効率的な全体システムの確立に資する研究開発や調査等を進める。 発電所廃棄物の陸地処分については、引き続き日本原子力研究所において、計算機によって放射性物質の環境中での移動等を調べる環境シミュレーション試験等の安全評価に関する試験研究等を推進する。また、青森県六ケ所村における民間による発電所廃棄物の埋設計画を推進するとともに、安全性実証試験を継続する。さらに、放射性廃棄物処分に関する安全解析コードの整備、埋設処分を行うことが具体化している放射能濃度の上限値を上回る発電所廃棄物の処分技術の開発等を推進する。 ②サイクル廃棄物の処理処分 再処理施設や燃料加工施設等の核燃料サイクル関連施設から発生する放射性廃棄物(サイクル廃棄物)は、再処理施設において使用済燃料から分離される高レベル放射性廃棄物、再処理施設やMOX燃料加工施設から発生する超ウラン(TRU)核種を含む放射性廃棄物、ウラン燃料加工施設やウラン濃縮施設から発生するウラン廃棄物に大別される。 高レベル放射性廃棄物の処理処分の研究開発については、動力炉・核燃料開発事業団を中心に進める。動力炉・核燃料開発事業団においては、ガラス固化処理の関連技術開発を進めるとともに、ガラス固化技術開発施設において放射性物質を用いた試験運転を実施する。また、地層処分に関しては、地層処分技術の確立を目指した研究開発を国の重要プロジェクトとして引き続き推進し、深部地質環境条件に関する調査研究、地層処分システム、地質環境調査技術等に関する研究開発、全国的な地質環境調査等を行う。さらに、動力炉・核燃料開発事業団が北海道幌延町で計画している地層処分技術を確立するための深地層試験等の研究開発と高レベル放射性廃棄物等の貯蔵を行う貯蔵工学センターについては、深地層試験場、ガラス固化体貯蔵プラント等の概念設計等を進めるほか、地元の理解を深めるための広報活動を行う。 日本原子力研究所においては、高レベル放射性廃棄物の処理処分に関する安全性評価試験等を引き続き実施するとともに、高レベル放射性廃棄物の放射線源としての利用に係る技術開発を行う。また、国立試験研究機関等においても、処理処分に関する基礎的調査研究を実施する。さらに、国際協力の分野においては、日豪協力による高レベル放射性廃棄物の新たな処理法であるシンロック固化処理の研究、日加協力による地層処分の研究等を進めるほか、OECD/NEAにおける豪州のウラン鉱床を用いた天然バリアの隔離機能等の評価研究に引き続き参加していく。 また、動力炉・核燃料開発事業団及び日本原子力研究所において、高レベル放射性廃棄物の処分の効率化及び有用核種の資源化の観点から高レベル放射性廃液の核種分離、長寿命核種の消滅処理等の研究開発等を長期的な課題として積極的に推進するとともに、OECD/NEAにおける核種分離・消滅処理技術の情報交換会議に積極的に参加する。 一方、TRU核種を含む廃棄物やウラン廃棄物などアルファ核種を含む廃棄物の処理処分については、動力炉・核燃料開発事業団や日本原子力研究所等において、研究開発等を引き続き行う。特にTRU核種を含む放射性廃棄物の処理処分については、動力炉・核燃料開発事業団のプルトニウム廃棄物処理開発施設を用いた研究開発を進めるとともに、動力炉・核燃料開発事業団、日本原子力研究所等において発生量の低減化、減容、固化技術等の処理技術及び天然バリア中における核種移行に関する研究、合理的な処分概念の検討等の処分技術の開発を行う。さらに、TRU核種を含む放射性廃棄物の固化等の処理についての安全性実証試験を行う。 また、使用済燃料の海外への再処理委託に伴い発生する廃棄物の返還輸送を円滑に行うため所要の調整等を行う。 ③RI廃棄物及び研究所等廃棄物の処理処分 放射性同位元素等の使用施設等から発生する放射性廃棄物(RI廃棄物)及び研究所等廃棄物については、廃棄物量等の実態調査を行い、それらの処理処分を行うための技術的要件の検討及び安全な処理処分方策の確立に資する検討を行うとともに、濃度が低く不均質に存在する放射性核種の非破壊測定技術の開発等を行う。 (2)原子力施設の廃止措置 実用発電用原子炉の廃止の時期に備えて、日本原子力研究所の動力試験炉(JPDR)をモデルとして解体実地試験を行うなど原子炉の解体の技術開発を推進するとともに、原子炉解体技術の高度化を進める。また、実用発電用原子炉の廃止措置に使用される設備について確証試験を行うとともに、原子炉施設の耐用年数に関する調査研究を行う。さらに、核燃料施設等の解体技術に係る調査や日本原子力研究所の再処理試験施設を対象とした再処理施設の解体に必要な技術開発を行うとともに、動力炉・核燃料開発事業団において核燃料施設の解体のための要素技術開発等を行う。 原子力施設の解体等から発生する放射能濃度の極めて低い廃棄物について、合理的処分に係る安全性実証試験、再利用技術開発等を進める。また、解体炉内構造物等の処理処分技術の開発、原子炉施設の安全貯蔵に係る安全性実証試験等を進める。さらに、核燃料施設等の解体に伴って生じる放射性廃棄物の処理処分方策に係る調査を進める。 8.原子力科学技術の多様な展開と基礎的な研究の強化 (1)基盤技術開発及び基礎研究21世紀の原子力技術体系を構築することを目的として、我が国独自の原子力技術の高度化・多様化に対応することを可能にし、現在の原子力技術体系に大きなインパクトを与え得る革新技術の創出が期待できる基盤技術開発を、日本原子力研究所、動力炉・核燃料開発事業団、理化学研究所及び国立試験研究機関を中心に推進する。 新たに改定された「新長期計画」に基づき、放射線生物影響分野、ビーム利用分野、原子力用材料技術分野、ソフト系科学技術分野及び計算科学技術分野の5技術分野の研究課題を推進する。これらの基盤技術の推進に当たり、特に各機関が研究ポテンシャルを結集して行うべき技術開発課題を原子力基盤技術総合的研究(原子力基盤クロスオーバー研究)として設定し、国際交流を含む産・学・官の連携の下に研究を進める。 計算科学技術の推進に向けては、日本原子力研究所において計算科学技術推進センター(仮称)として体制を整備し、並列処理技術等を、また、動力炉・核燃料開発事業団においては、バーチャルリアリティ等の研究開発を進める。 また、日本原子力研究所においては、先端基礎研究センターを中核として長期的視点に立った創造的、先端的基礎研究を一層効果的に推進するとともに、研究用原子炉(JRR―3、JMTR等)による各種の研究、燃料・材料の照射試験等を引き続き実施する。さらに、タンデム型重イオン加速器の一層の性能向上を図るとともに、核物理、放射線損傷、原子・分子物理の研究等を行う。さらに、大型放射光施設(SPring―8)の直線加速器部分の完成・試験開始を契機として、放射光、レーザー等の光量子に関する研究を総合的に推進するため、関西研究所(仮称)として体制を整備し、関連研究の展開を図る。 新超電導技術に関しては、日本原子力研究所において、耐放射線性の解析のための試験、中性子散乱による構造解析等を行うとともに、動力炉・核燃料開発事業団において、原子力分野における超電導技術の利用に関する調査を進める。 このほか、国立試験研究機関においても、核融合、安全研究、放射線利用等の分野で基礎研究を実施する。 (2)原子力エネルギーの生産と原子力利用分野の拡大に関する研究開発 ①新しい概念の原子力に関する研究開発 日本原子力研究所において、事故時の冷却機能と炉停止機能について受動的安全性を高めた原子炉の研究開発、プルトニウムをほぼ完全に燃焼させて使用済燃料を直接安定な廃棄物として処分することをめざす燃料の研究開発等軽水炉の高度化を図る研究開発を進める。 ②新しい概念の核燃料サイクルシステムに関する研究 日本原子力研究所においては、再処理技術について、新しい抽出剤の開発など、湿式法の高度化に関する研究、高温化学法など乾式法に関する研究等を進める。また、高レベル放射性廃棄物の資源化と処分の効率化を図ることを目指して、群分離・消滅処理技術の研究を進め、原子炉又は大強度陽子加速器の利用による長寿命核種の短寿命化・非放射化に関する研究を推進する。さらに、我が国のエネルギー需給を、資源問題、地球環境問題、経済性等の面から総合的に検討・評価する技術の研究開発を進める。 ③高温工学試験研究 日本原子力研究所において、高温熱供給、高熱効率、高い固有の安全性等優れた特性を有する高温ガス炉技術の基盤の確立・高度化及び高温工学に関する先端的基礎研究を行うための中核的な研究施設である高温工学試験研究炉(HTTR)の建設を平成10年度の臨界達成を目指して進める。平成7年度においては、燃料取り扱い及び貯蔵設備、計測制御設備、プラント補助設備等の製作に着手する。また、HTTRにおいて将来実施する高温工学に関する先端的基礎研究の予備試験を進めるとともに、水素エネルギー製造をはじめとする核熱エネルギーの利用システムの検討を行う。 さらにIAEAの協力研究計画「HTTR熱利用システムの設計及び評価」等に参加し国際協力を積極的に展開していく。 ④原子力船の研究開発 原子力船「むつ」の解役については、原子炉室切断工事、原子炉保管建屋建設工事等所要の措置を講じる。また、原子力船「むつ」の実験航海によって得られた種々の知見、実験データ等をデータベースとして整備するとともに、これをシミュレーション試験等に活用し、引き続き将来の舶用炉開発のための研究を進める。 なお、むつ地点において、海洋関連研究(舶用炉研究及び海洋環境研究)を総合的に推進する。 (3)放射線に関する研究開発 放射線利用については、医療分野における各種疾病の診断、重粒子線等によるがん治療等に関する研究、工業分野における放射線化学等の研究開発、農林水産分野における放射線育種等の研究開発等を推進する。このため、放射線医学総合研究所において、サイクロトロンを用いて速中性子線及び陽子線によるがん治療研究を引き続き進める。さらに、がん細胞の殺傷力が大きく、かつ正常組織の損傷が少ないことから、従来の放射線に比べがん治療成績の著しい向上が期待される重粒子線によるがん治療法に関する臨床試行並びに治療計画法の研究及び診断法の研究等を円滑に実施するため、重粒子プロジェクト研究を推進する。また、臨床試行対象患者の増大に対応するため重粒子線がん治療施設を整備する。さらに、重粒子線がん治療の情報化と高度化のための重粒子線高度がん治療推進センター(仮称)の建設等を進める。また、放射線の影響に関連するヒトゲノム領域の解析・遺伝情報解析研究、宇宙放射線の生物影響に関する研究等、放射線医学分野に新たなる展開をもたらす先導的研究に取り組むグループ研究を開始する。このほか、ポジトロン核種による診断に関する研究開発等、短寿命放射性同位元素による画像診断技術の開発を推進する。 日本原子力研究所においては、放射線化学関係の研究並びに放射性同位元素の生産及び利用を推進するとともに、種々の粒子線の多重照射等により、耐放射線性極限環境材料、機能材料の研究開発やライフサイエンス等の分野において画期的な新材料の開発、新技術の創出に寄与できる研究として産・学・官の研究者から強い要望が寄せられている放射線高度利用研究を行うため、イオン照射研究施設の整備及び所要の研究開発等を推進する。さらに、環境保全のための放射線利用を進めるため、電子線を用いた技術開発を継続的に行う。 理化学研究所においては、AVF型入射器及び線型加速器を前段加速器として、リングサイクロトロンを主加速器とした重イオン科学用加速器を用いて、原子核・原子・素粒子物理等の広い分野にわたった重イオン科学総合研究を推進する。また、重イオン科学総合研究の一環として、ミュオンに関する研究を英国ラザフォード研究所との共同により、また、スピン偏極重イオンに関する研究を米国ブルックヘブン国立研究所との共同により、それぞれ行う。さらに、重イオン科学総合研究の将来の高度化を目指し、大強度RIビーム発生に関する調査研究を行う。 また、日本原子力研究所と理化学研究所においては、関係する研究者の協力の下、原子力分野の研究の基盤を形成すると期待されるSPring-8については、平成6年6月に整備及び利用の円滑化のための法律が公布されたが、引き続き加速器機器の製作及び建屋の建設を進める。さらに、利用者の技術支援、情報支援等放射光利用環境の整備を図ることが必要である。また、国内外の研究者が当該施設を広く利用するための共同利用ビームラインの整備を進めるとともに、平成9年度一部供用開始を目指して線形加速器の試験に着手する。 国立試験研究機関においても、電子技術総合研究所において放射線標準に関する研究、国立病院等において放射性同位元素を用いた疾病の診断及び治療に関する研究、農林水産省各試験場において放射線による品種改良、トレーサー利用による生理生態研究、国立衛生試験所等において食品照射に関する研究を行うほか、国立環境研究所等において放射性同位元素を用いた環境影響の機構解明及び対策手法に関する研究等を実施する。 (4)核融合研究開発 核融合については、大学における各種研究の進展を考慮し、国際協力の推進にも留意しつつ、日本原子力研究所におけるトカマク方式による大規模な研究開発、国立試験研究機関による基礎的研究等を計画的に推進する。 日本、米国、EU及びロシアの4極間の国際協力により進められている国際熱核融合実験炉(ITER)計画については、工学設計活動に関する協定に基づき、日本原子力研究所を中心としてこれに参加し、日本、米国及びEUに設置された共同中央チーム等において設計作業を積極的に実施する。特に、我が国に設置された真空容器外機器の設計を担当する共同中央チームについては、必要な施設等の整備を行う。また、主体的な貢献を果たすべく工学設計活動に必要な工学及び物理研究開発を着実に進める。さらに、ITERの立地環境評価のための予備的な調査を行う。 また、日本原子力研究所においては、臨界プラズマ試験装置(JT―60)において、プラズマ及び中心イオン温度の世界記録を更新しており、今後さらにプラズマ性能等の高度化を図るための実験を行う。 さらに、高性能トカマク開発試験装置(JFT―2M)を用いて非円形断面トーラスプラズマの研究を一層推進するとともに、プラズマ加熱、超電導磁石技術等の炉工学技術及びトリチウム取扱い技術を始めとする核融合炉の安全性に関する研究開発を進める。 電子技術総合研究所においては、高べータ・プラズマの研究のため逆磁場ピンチ型核融合装置による実験等を進めて、プラズマの高性能化等を図る。また、金属材料技術研究所及び名古屋工業技術研究所においては、核融合炉に関連する材料等の基礎的研究を行う。 さらに、米国のダブレット―皿を使った共同実験、核融合材料の共同照射研究、トリチウムの取扱い技術に関する安全性研究、新しいプラズマ加熱方法に関する研究等の日米間の共同研究及び日─EC核融合協力協定に基づくプラズマ対向材料機器に関する共同研究等の二国間協力を推進する。さらに、経済協力開発機構/国際エネルギー機関(OECD/IEA)の下で、米国のTFTR、ECのJET及び我が国のJT―60との間における大型トカマク装置の多国間研究協力等を推進する。 9.国際協力の推進 原子力分野における我が国の国際貢献への要請に応えるべく、原子力開発利用について核不拡散との両立を図るとともに、安全確保の重要性を認識しつつ、積極的な国際貢献を果たしていくこととする。(1)二国間・多国間協力 先進国との協力については、原子炉の安全研究、新型動力炉、高温ガス炉、核融合、放射性廃棄物処理処分、廃炉等の研究開発等の各分野に関し、米国、ドイツ、フランス、イギリス、オーストラリア、カナダ等との二国間協力及び多国間協力を進める。また、我が国原子力施設の規制の充実に資するため、米国、フランス、ドイツ、旧ソ連、中国等との規制情報交換を進める。動力炉・核燃料開発事業団では、高速炉リサイクル国際特別研究員制度を拡充し、高速炉リサイクル研究に関する国際交流の推進を図る。 開発途上国との協力については、原子力関係要人及び専門家の我が国への招へい、原子力技術アドバイザーの開発途上国への派遣、原子力関係管理者研修、原子力専門家の登録・派遣あっせん事業、開発途上国関連情報の収集・提供並びに我が国の研究者の開発途上国への派遣を引き続き行う。さらに、開発途上国の原子力研究者の我が国研究機関への招へいを充実・強化する。 また、チェルノブイル原子力発電所周辺地域の放射線影響等の調査を行う。 さらに、IAEAの「原子力科学技術に関する研究、開発及び訓練のための地域協力協定」(RCA)に基づくRI・放射線利用分野等の協力を引き続き進めていく。 さらに、近隣諸国及び旧ソ連、中・東欧諸国の原子力関係者に対する原子力安全確保についての研修等を拡充するとともに、旧ソ連、中・東欧諸国の原子力発電所の運転員、技術者等の資質向上等運転上の安全対策、運転中異常検知システムの適用等による安全性向上のための短期的な技術改善、運転訓練シミュレータによる原子力発電所の運転員のトレーニング、廃炉へ向けた安全性調査等を通じて、当該諸国の原子力の安全性向上に資する。また、欧州復興開発銀行に設けられた原子力安全支援基金を通じた協力を行う。さらに、核兵器関連技術の流出防止等のために設立された国際科学技術センターに対して協力を行う。 (2)近隣アジア地域との協力 近隣アジア地域との原子力分野における放射線利用、研究炉利用、安全確保対策、放射性廃棄物の処理処分等の共通課題の解決に当たっては、本地域の限られた研究開発資源を効果的・効率的に活用するとの観点から、地域として一体の協力を進めるとともに、個別の要請にもきめ細かく対応していく。このため、引き続き近隣アジア諸国の政策立案者と政策対話を行うとともに安全確保、核不拡散等に関する検討を行う。 (3)国際機関への貢献 IAEAの保障措置業務の改善に協力していくとともに、IAEAを中心として行われている原子力国際協力の枠組みについての国際的検討の場に積極的に参加する。 また、IAEAでの原子炉の安全基準改定事業、放射性廃棄物安全基準制定事業、海洋環境放射能調査事業、OECD/NEAにおける核種分離、消滅処理技術の情報交換会議等に参加するなど、IAEA、OECD/NEA等の国際機関の活動に積極的に貢献するとともに,我が国の原子力活動に対する国際社会の理解の増進を図る。 (4)国内環境の整備 我が国の国際対応を円滑に進めていくため、適切な国内環境の整備を進めていくこととし、増大する外国人研究者の受入れに対処するための宿舎の整備、外国人研究者の受入れ制度(リサーチフェロー制度等)による受入れ、国際人材養成研修等を行う。 10.人材の養成と確保 原子力開発利用の安全確保の一層の充実や関連する先端的技術開発の着実な推進を図るためには、その担い手となる優秀な人材の養成と確保に努力することが不可欠であり、原子力関係研究者、技術者等については、大学等を人材養成の中核機関として、原子力発電所等の技術者、技能者については、民間が所要の措置を講じることにより、その養成と確保を計画的に推進することが望まれる。このため、これらの活動の支援に努めるとともに、政府関係研究開発機関における人材の養成と確保に加え、多様な研修活動を推進していくこととする。 (1)青少年の原子力に関する学習機会の確保等 原子力関連科学技術の理解の促進に資する原子力関連展示物の整備、全国に設置する原子力情報提供窓口等を通じた情報の提供、知識の普及等を行うほか、地域の科学館の指導員を対象とした研修等を実施する。また、原子力関連科学技術に関する実験を含んだセミナー等を開催する。 (2)研究開発機関間の連携の確保 大学等の研究者や学生が政府関係研究開発機関の研究設備・機器等を利用する機会の増大・強化を図るなど人材養成面における関係機関の連携の推進を図る。 (3)原子力関連研究者・技術者等への研修の実施 原子力発電施設、大型再処理施設等の安全の確保のために行われる業務等に従事する者等への都道府県等が行う研修事業等に対して補助を行う。また、地方公共団体の職員等に対し、防災対策の充実強化、環境放射能分析に関する技術的能力の維持向上、大型再処理施設等の安全対策に関する能力向上、保障措置等の平和利用の担保を図るための研修を実施する。また、日本原子力研究所の原子力総合研修センター及び放射線医学総合研究所における養成訓練を引き続き実施する。さらに、原子力発電所等の運転員の長期養成計画、資格制度等の運用により運転員の資質向上を図る。 また、原子力研究開発の国際化に鑑み、原子力平和利用先進国として、諸外国の研究者、技術者等の受け入れを行うほか、国際的な人材の養成に努める。 III.見積りの概要 平成7年度において、以上の施策を進めるために必要な原子力関係経費は、総額約4,904億円(一般会計約2,003億円、電源開発促進対策特別会計約2,901億円)、国庫債務負担行為限度額約833億円(一般会計約375億円、電源開発促進対策特別会計約458億円)と見積られる。原子力関係機関別見積りについては、「IV.概算要求総表」に示すとおりであるが、主要な原子力研究開発機関別の見積りの概要を示せば以下の通りである。 1.日本原子力研究所 日本原子力研究所の総事業費は、約1,269億円であり、これに必要な政府支出金は、約1,113億円(国庫債務負担行為限度額約186億円)である。また、必要な人員増は総計43名である。このうち、原子力施設の工学的安全性研究及び環境安全性研究に必要な経費は約71億円(国庫債務負担行為限度額約5.6億円)であり、増員は7名、核融合の研究開発に必要な経費は約221億円(国庫債務負担行為限度額約3.8億円)であり、増員は10名、高温工学試験研究に必要な経費は約140億円(国庫債務負担行為限度額約91億円)であり、増員は1名、放射線高度利用研究を始めとする一般研究等に必要な経費は約301億円(国庫債務負担行為限度額約86億円)であり、増員は25名である。原子力船の研究開発に必要な経費は約38億円である。 2.動力炉・核燃料開発事業団 動力炉・核燃料開発事業団の総事業費は、約2,209億円であり、これに必要な政府出資金は、約1,560億円(一般会計約512億円、電源開発促進対策特別会計約1,048億円)、国庫債務負担行為限度額約502億円(一般会計約44億円、電源開発促進対策特別会計約458億円)である。また、必要な人員増は総計51名(一般会計約14名、電源開発促進対策特別会計37名)である。このうち、高速増殖炉及び新型転換炉の開発に必要な経費は総額約1,265億円であり、これに必要な政府出資金は、約1,095億円(国庫債務負担行為限度額約471億円)であり、増員は25名、ウラン濃縮技術開発、探鉱開発等核燃料開発に必要な経費は総額約219億円であり、これに必要な政府支出金は約166億円(政府保証借入金約6億円、国庫債務負担行為限度額約15億円)であり、増員は3名、再処理施設の運転等に必要な経費は総額約725億円であり、これに必要な政府支出金は、約299億円(政府保証借入金約149億円、国庫債務負担行為限度額約17億円)であり、増員は23名である。 3.放射線医学総合研究所 重粒子線等の医学利用、放射線被曝のデトリメントに関する生物学的調査及び遺伝情報解析研究、宇宙環境生物医学等をプロジェクト的に行うグループ研究等の放射線医学重点研究の強化推進並びに重粒子線がん治療装置等に必要な経費は約145億円(国庫債務負担行為限度額約30億円)であり、増員は3名である。4.国立試験研究機関 先端的基盤研究、総合的研究、核融合、安全研究、食品照射、環境対策、がん対策等原子力研究に必要な経費は約23億円である。5.理化学研究所 ミュオンに関する研究等の重イオン科学総合研究、原子力用短波長レーザーの開発研究及び自律型プラントのための分散協調知能化システムの開発等の基盤技術開発、大型放射光施設(SPring―8)の建設並びに分子レーザー法によるウラン同位体分離濃縮等の原子力研究に必要な経費は約115億円(国庫債務負担行為限度額約115億円)である。IV 概算要求総表 1.平成7年度原子力関係予算概算要求総表 2.科学技術庁一般会計概算要求総表 3.各省庁(科学技術庁を除く)一般会計概算要求総表 4.電源開発促進対策特別会計原子力関係予算概算要求総表 5.平成7年度原子力関係予算概算要求重要事項別総表 |
| 前頁 | 目次 | 次頁 |