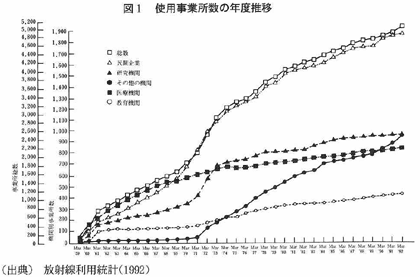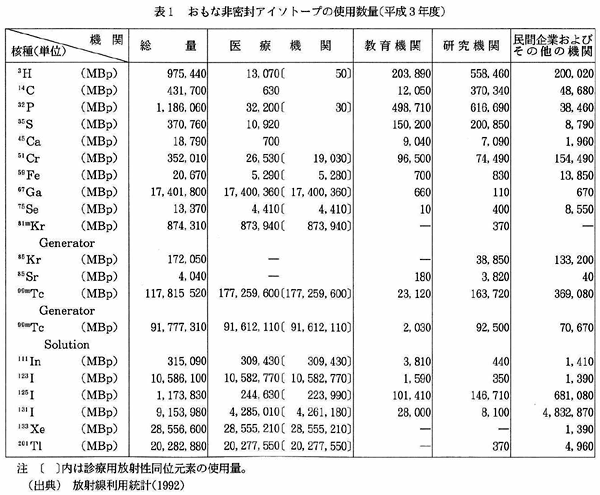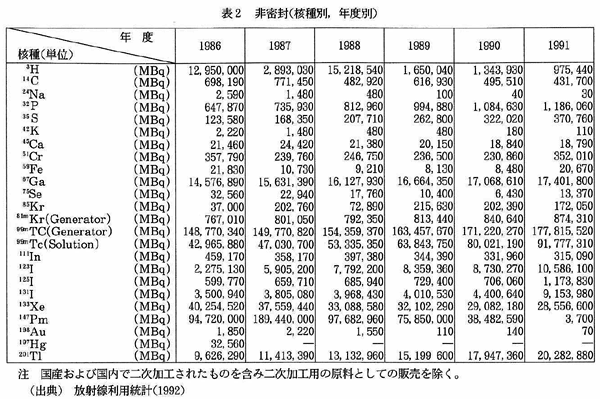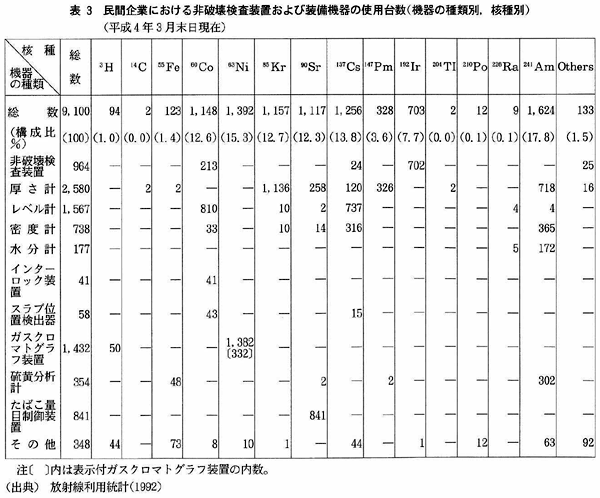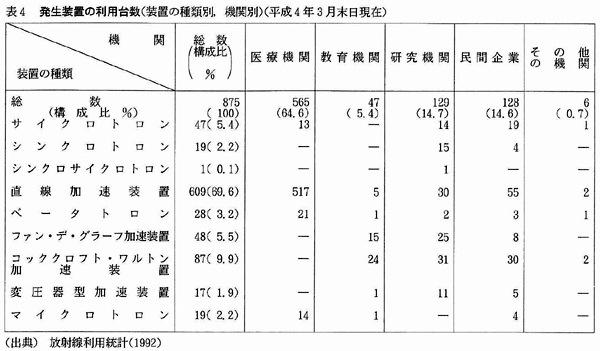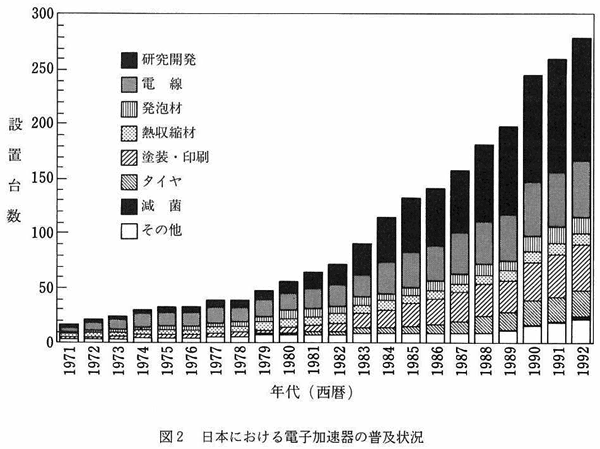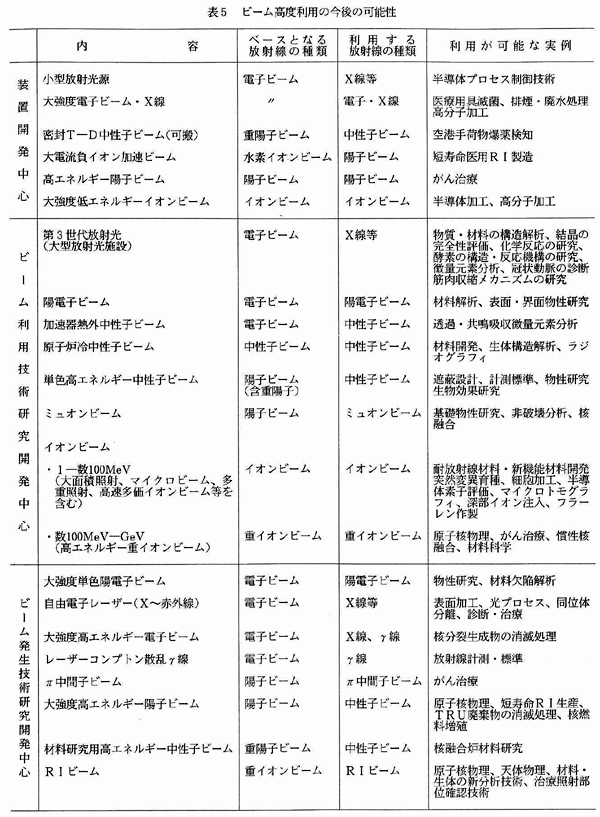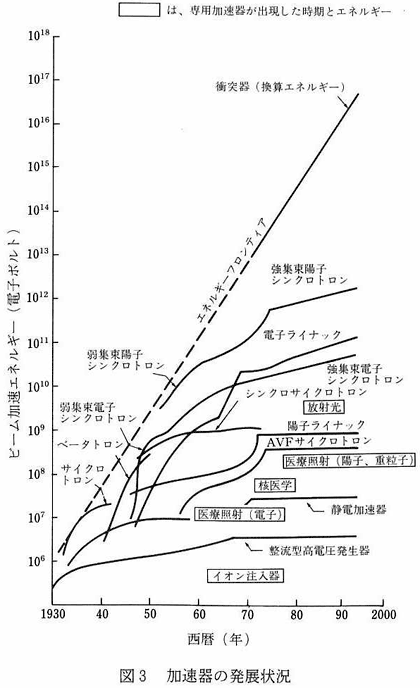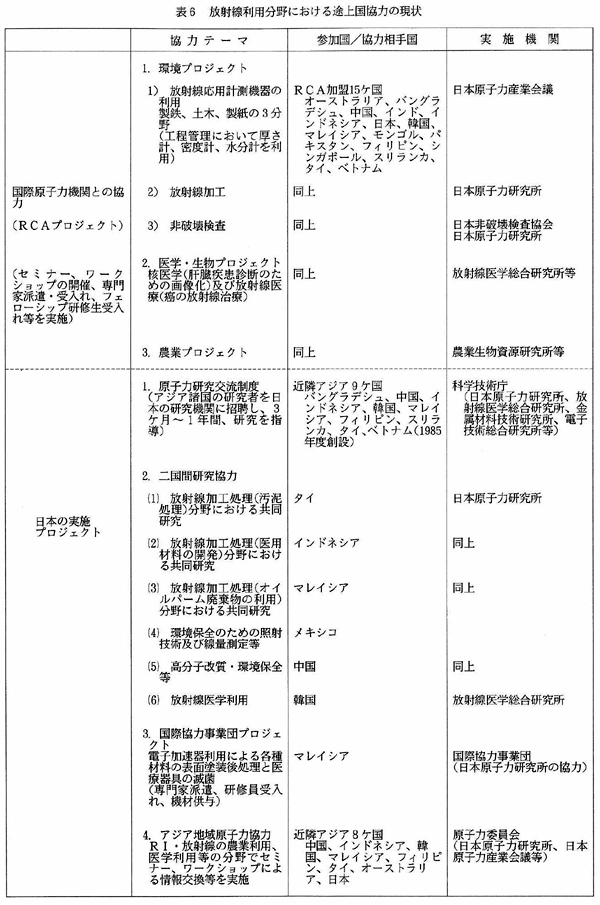| 前頁 | 目次 | 次頁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
資料 放射線利用の新たな展開について 平成5年6月
原子力委員会
放射線利用専門部会
はじめに 放射線利用は、原子力発電と並ぶ原子力開発利用の重要な柱として位置づけられており、今日まで実用化及びそのための研究開発が進められてきた。放射線利用には、大別して、物質の挙動を追跡する放射性同位元素(RI)によるトレーサー利用と放射線の物理的、化学的又は生物学的作用を利用する線源利用の2種類があり、その利用は医療、農林水産業、工業等の幅広い分野にわたっている。
これらの放射線利用は他の技術には見られない特徴を活かして大きな役割を果たしつつあるが、今後は、医療、環境保全といった生活者の立場を重視した利用技術を一層普及していくことが重要である。これらの放射線利用の普及促進がひいては、放射線に対する国民の正しい理解を増進することにも役立つものと期待されている。
一方、近年整備が進められている加速器は、大型化、性能の向上等が著しく、その利用の幅も広がってきており、放射線利用分野での大きな飛躍をもたらすものと期待されている。このため、これらの施設を活用した先端的な研究開発を推進するための研究開発体制の整備が重要である。
また、開発途上国への技術移転等による国際貢献の観点から、放射線利用に係る途上国協力を一層推進することが求められているほか、基礎研究分野での国際貢献の観点からは、積極的に先進国協力にも取り組むことが必要である。
このようなことから本報告では、放射線利用の現状を把握した上で、近年の社会環境等の変化も踏まえながら、今後の放射線利用の推進方策等について取りまとめた。本報告を踏まえ、今後、放射線利用がさらに積極的に展開されることを期待するものである。
第1章 放射性同位元素及び放射線発生装置の利用状況 放射線は、医療、農林水産業、工業等の分野で幅広く利用され、国民生活の向上等に貢献している。図1に示すように、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下「放射線障害防止法」という。)に基づく放射性同位元素(以下「RI」という。)又は放射線発生装置の使用事業所は着実に増加しており、1992年3月末現在、総数で5,006事業所に達している。これを機関別に見ると、民間企業1,875、研究機関948、医療機関820、教育機関416、その他の機関947である。
図1 使用事業所数の年度推移 第1節 RIの利用状況 主な非密封RIの機関別使用数量は表1に示すとおりであり、医療機関における99mTcが大部分が占めている。また、これらの使用量の年度推移は表2に示すとおりで、体内診断用(インビボ)放射性医薬品における67Ga、99mTc、123I、131I、201TIは増加傾向にある。特に、99mTc、123I及び201TIは使用量が急増している。体外診断用(インビトロ)放射性医薬品については、利用核種の大部分は125Iであり、使用量は近年横ばいの傾向にある。一方、教育・研究機関でそのほとんどが使用されている32P、35Sの使用量は着実に伸びている。
また、密封RIの使用事業所数は4,424であり、このうち、民間企業における非破壊検査装置及び装備機器の使用状況を表3に示す。60Coはレベル計に、63Niはガスクロマトグラフ装置に、85Krは厚さ計に、90Srはたばこ量目制御装置に、137Csはレベル計、密度計に、192Irは非破壊検査装置に、241Amは厚さ計、密度計等に主に使用されており、これらの核種を装備した機器の使用台数は漸増傾向にある。医療機関においては、60Co、226Ra等が密封小線源として利用されているほか、60Co及び137Csが遠隔照射治療装置として、また、60Co等が放射線滅菌用の大線源として利用されている。
第2節 放射線発生装置の利用状況 放射線障害防止法に定める放射線発生装置は、1992年3月末現在、875台に達している。放射線発生装置の利用状況は表4に示すとおりであり、その65%は医療機関に設置され、がん治療等に利用されている。また、20%が大学、研究機関等に設置され、さまざまな研究開発に利用されている。
なお、放射線障害防止法の規制対象とはならない低エネルギー電子加速器、イオン注入装置等も民間企業等に多数設置され、幅広く利用されている。
表1 おもな非密封アイソトープの使用数量(平成3年度) 表2 非密封(核種別,年度別) 表3 民間企業における非破壊検査装置および装備機器の使用台数(機器の種類別,核種別) 表4 発生装置の利用台数(装置の種類別,機関別)(平成4年3月末日現在) 第2章 放射線利用技術の実用化及び普及促進方策 放射線利用は、国民生活の向上に多大な貢献を果たしてきたが、されにその裾野を広げるためには、医療、農林水産業、工業等の分野において応用目的を明確にした研究開発を推進するとともに、その普及促進に取り組む必要がある。特に、近年、生活者の立場を重視した科学技術の活用が求められており、医療や環境保全といった領域において重点的に研究開発に取り組むことが望ましい。さらには、国の研究機関や大学で開発された技術については、民間や地方への積極的な技術移転等による普及促進に努める必要がある。
第1節 実用化の現状及び展望 我が国においては、医療、農林水産業、工業等の分野においてRI及び放射線発生装置が利用されており、今後もこれらの分野において実用化に向けた研究開発が進められることが望まれる。
1.医療分野
医療分野において、放射線は診断と治療の両面で利用されている。
診断においては、放射線が生体を透過する性質が利用され、最も広く普及している胸・胃・骨等のX線撮影を始めとして、X線コンピュータ断層撮影(以下「X線CT」という。)等に利用されている。
また、核医学検査には、被検者の体内に放射性医薬品を投与し診断を行うインビボ検査及び被検者から採取した試料に放射性医薬品を加え診断するインビトロ検査がある。
このうちインビボ検査は、脳、心臓、肺、骨等の特定の臓器に集まった放射性医薬品からの放射線をシンチレーションカメラ等で測定し、臓器・組織への分布、蓄積・排泄の早さ等を画像化するものであり、これにより、臓器・組織の機能の亢進・低下、病巣の形態等に関する診断が行われている。最近では、モノクローナル抗体等による免疫学的手法を用いた特異性の高い標識核種医薬品により、悪性腫瘍の診断精度は極めて向上している。また、エミッション・コンピューテッド・トモグラフィは、放射線の測定結果をコンピュータにより画像処理するインビボ検査法の一種であり、使用されるRIの種類により、シングル・フォトン・エミッション・コンピューテッド・トモグラフィ(以下「SPECT」という。)とポジトロン・エミッション・コンピューテッド・トモグラフィ(以下「PET」という。)の二種類に分けられる。SPECT装置は、国内のほとんどの核医学施設に普及し、全国で約700台が利用されている。PETは、患者に投与した短寿命陽電子放出核種からの放射線を検出することにより人体内部の断層像を得るものであり、従来のX線CTが臓器等の形態を撮影するのに対し、脳、心臓等における代謝及び機能の画像診断を可能とするものである。現在、放射線医学総合研究所等における研究開発の結果、PETも実用段階に達した。
一方、インビトロ検査は、採取した血液、尿等の試料と放射性医薬品とを反応させ、反応後の試料からの放射線を測定することにより、ホルモン等の微量な成分を定量する手法であり、糖尿病、がん等の診断が行われている。インビトロ検査の方法としては、ラジオイムノアッセイ(放射免疫測定法)が主として用いられているが、次第にRIを用いないエンザイムイムノアッセイ(酵素免疫測定法)に置き換えられる傾向が見られる。
このような放射線発生装置及びRIの利用により、診断技術は今後一層向上することが期待される。
治療については、放射線によるがん治療が実用化されている。γ線、X線等を体外から照射する方法はがん治療全般に、体内に密封小線源を挿入し、γ線を照射する方法は、舌がん、子宮がん等の治療に、また、放射線医薬品を投与し、病巣に集中的に分布したRIからのβ線又はγ線を照射する方法は、甲状腺がん等の治療にそれぞれ用いられている。我が国において放射線治療を受けたがん患者数は年間約9万人と見込まれ、これは全がん患者数の約3割に相当する。現在、遠隔照射治療装置としては、γ線遠隔照射治療装置が約360台、X線を発生させる直線加速器(電子ライナック)が約520台利用されている。また、遠隔操作式密封小線源治療装置が約170台、近年急速に普及してきた脳定位放射線照射装置が全国で8台整備されている。
2.農林水産分野
農林水産分野では、品種改良、害虫防除、食品照射等に放射線が利用されている。
植物の品種改良については、60Co線源等によるγ線照射を利用して農業生物資源研究所放射線育種場等で進められている。例えば、耐倒伏性の強いイネ、低アレルゲン等の特性を持つイネ、早熟多収性の大豆、黒斑病に強いナシ(ゴールド二十世紀)、常緑性のコウライシバ等が育成され、また、組織培養との併用により花色変化を起こしたキク等が育成されるなど、我が国ではすでに100種に及ぶ新品種が生まれている。このような放射線育種については、世界的にも新たな取組が期待されていることから、有用遺伝子の獲得効率の向上を目的として、放射線照射と細胞培養等のバイオテクノロジー手法を組合わせた品種改良の進展が期待されている。また、イオンビームを利用した突然変異の誘発とその応用も今後の品種改良に大きな寄与をもたらすものと考えられる。
害虫防除については、ウリミバエの蛹にγ線を照射して成虫の不妊化を施し、環境中に放飼する不妊虫放飼法による根絶防除を、沖縄県では1974年から、鹿児島県奄美諸島では1981年から実施している。その結果、奄美諸島では、1989年10月に全域での根絶が達成され、沖縄県では久米島、宮古列島等に続き、1990年10月沖縄本島及び周辺諸島において根絶が達成された。この結果、スイカ、メロン、マンゴー等の果実類の移動規制が解除され、本土への出荷が自由となった。残る八重山列島においても、1993年には、ウリミバエが根絶されるものと見込まれている。また、小笠原諸島においても、不妊虫放飼法により1985年2月に柑橘類の害虫であるミカンコミバエの根滅に成功している。今後は、南西諸島のアリモドキゾウムシ、イモゾウムシ等の根絶が期待されているとともに、諸外国においても各種根絶計画が立案・実施されつつあり、我が国の支援が求められているところである。
食品への放射線照射は、発芽防止、熟度遅延、殺菌、殺虫等により、食品の保存期間を延長するなどの目的で行われる。我が国では、1967年に原子力委員会が定めた「食品照射研究開発基本計画」に基づき、馬鈴薯、玉ねぎ、米、小麦、ウィンナーソーセージ、水産ねり製品、みかんの7品目の安全性、照射効果等の研究開発を日本原子力研究所、国立試験研究機関等が分担して実施し、研究成果が取りまとめられている。我が国で実用化されているのは馬鈴薯であり、1974年から北海道士幌町で発芽防止のため年間1万〜1万5千トンの照射が行われている。また、世界では1991年10月現在、38カ国で合計約60品目について食品照射が法的に許可されている。このような動向を踏まえ、国際原子力機関(IAEA)/国連食糧農業機関(FAO)により照射食品の検知技術に関する研究プロジェクトが1989年からの5年計画で進められており、我が国も本プロジェクトに積極的に協力しているところである。さらに、1980年から開始された国際原子力機関(IAEA)のアジア太平洋地域での食品照射協力プロジェクトにも、我が国は積極的に協力している。今後とも、検知法等の研究を推進するとともに、国民の理解の増進に努めるほか、開発途上国への技術協力を進めていくことが肝要である。
3.工業分野
工業分野での放射線利用は、放射線が物質を透過する性質を利用した計測・検査及び放射線と物質との相互作用による品質の改良に大別される。
放射線の透過性の計測利用については、例えば製鉄所において、高温状態にある鉄板の厚さを測定し一定に保つことに役立つとともに、セロハン、アルミホイル、ラッピングフィルム、ゴム、紙等の製造の工程管理にも利用されている。このようなγ線、β線又は中性子線による厚さ、レベル、密度又は水分の精密な測定等各種の工程管理については、1992年3月末現在、厚さ計が409事業所で2,580台、レベル計が204事業所で1,567台保有されているなど広く普及している。また、鉄鋼、航空機部材等の構造材料のひび割れ等を外部から調べる非破壊検査も広く普及しており、非破壊検査装置は170事業所で964台保有されている。
このような計測・分析利用では、携帯型非破壊検査装置(薄物・細管用)に必要な低エネルギーγ線ラジオグラフィの線源として169Ybの開発が進められている。また、中性子利用では、中性子ラジオグラフィによるエンジン内燃料輸送状態の観察等の非破壊検査が行われるとともに、炭素、窒素、酸素等の軽元素分析による爆発物、麻薬等の検知のための研究開発が進められており、実用化が期待されている。このような中性子ラジオグラフィ技術を、簡便かつ汎用性の高い非破壊検査法として実用化させるためには、可搬性に富んだ小型加速器等の開発が望まれるとともに、周辺技術として高感度の中性子検出器の開発も重要である。
一方、放射線と物質との相互作用の利用については、材料に放射線を照射することにより、耐熱性、強度、耐摩耗性等が向上する場合があり、材料の品質改良に役立てられている。例えば、電線の被覆材に放射線を照射すると耐熱性を向上させることができ、これらの電線はテレビ、ラジオ、自動車等に使用されている。自動車のタイヤの製造中にも放射線が利用されており、成型時の型くずれ防止に役立っている。風呂マット、自動車の内装材料、断熱防水材、スリッパ等に断熱性及びクッション性に優れる発泡ポリオレフィンが使用されるが、その製造工程において発泡の制御を容易にするため放射線が照射されている。また、鋼板、フロッピーディスク等の表面塗装材の硬化にも、硬化までの時間が短いこと、加熱の必要がないこと、溶剤を使用しないこと、塗膜性能が良いこと等の利点を活かして、放射線が利用されている。電線被覆材の架橋等の各種高分子材料の改良等に利用される電子加速器の普及状況は図2に示すとおり近年急速に進んでおり、1992年末現在、全国で約280台稼働している。また、各種静電加速器、サイクロトロン等で発生させたイオンビームは、元素分析、半導体へのイオン注入等に用いられ、これらに利用されている装置は全国で数百台あり世界的にも最先端の状況にある。このほか、研究炉から発生する中性子が半導体製造におけるシリコンドーピングに利用されている。
図2 日本における電子加速器の普及状況 現在、放射線架橋による天然ゴムラテックスヘの加硫技術及びハイドロゲルの製造技術の開発並びに放射線グラフト重合による浸透気化膜、重金属捕集材、有害気体吸着材等の高分離機能材料の開発が進行中であるが、放射線法はプロセスの高度化及び省エネルギー化の要求に対応するのみならず、汚染物質の捕集材、易分解性材料の製造等、今後も有機高分子材料の開発に期待される技術である。また、超耐熱性セラミック繊維の製造、ポリ四フッ化エチレン等の耐放射線性の向上等、電子線架橋による耐放射線性・絶縁性・耐熱性を有する新素材製造技術の研究開発の進展が期待される。
医療用具の滅菌においては、包装してから滅菌が可能であること、化学殺菌のような残留有害物がないこと等から、透過力の大きいγ線により、メス、縫合糸等100種類以上の医療用具の滅菌が全国8カ所で行われている。このうち、人工透析器については、血液中の老廃物をろ過するため細い管状の血流経路を形成しているが、これを化学薬品により滅菌すれば化学薬品が血流経路に残る恐れがあることから、放射線による滅菌が行われている。医療用具の滅菌処理法として、近年、電子線照射も行われ始め、全国3カ所において手術用ガウン等の不織布、プラスチック製縫合糸、採血針等が滅菌されている。
このほか、実験動物用飼料の放射線滅菌が年間200〜400トン行われている。
4.研究分野
ライフサイエンス分野では、DNA塩基配列、特定遺伝子の染色体上の位置等を決定するため、3H、32P等が用いられているほか、核酸、蛋白質、糖及び脂質の構造解明・合成並びに生体膜、膜輸送、細胞周期、物質代謝、免疫応答、造血機能等の研究がオートラジオグラフィ、ラジオイムノアッセイ等により行われており、これには3H、14C、32P、35S、125I等が用いられている。新薬の開発に関しても、薬物の吸収、分布及び代謝を調べるためにRIトレーサーが用いられている。
また、植物に対する施肥効果及び農薬の薬理機構の解明、家畜の代謝・繁殖・泌乳機構の判定による生産性向上及び疾病の診断等のための研究にも3H、32P等が用いられている。今後は33Pを利用した土壌中の蓄積リンの動態解明、マルチトレーサーを用いた多数の金属イオンの植物体内移行・分布の同時測定等の応用が期待できる。
原子炉から発生する中性子については、各種試料の放射化分析、中性子散乱による結晶・生体物質の構造解析等に利用されているほか、近年、冷中性子による即発γ線分析等が注目されつつある。この即発γ線分析により、従来、放射化分析の対象にはなりにくかったH、N、P、S等の分析が可能となる。また、アクチバブルトレーサーとしてのEuは、サケの回遊、農作物の害虫の天敵研究等に用いられており、今後は樹体内で移動性の高いトレーサーを用いた同法による果樹の根活力検診法等の研究が期待される。さらに先述した中性子ラジオグラフィにより、土壌中の植物根の生育状態の把握等が可能となる。
一方、試料に含まれる14Cの崩壊状況を測定することにより、その年代を知ることができるので、放射線は考古学の分野にも利用されている。また、岩石等に微量に含まれているUが自発核分裂した分裂片の痕跡を計測することにより、岩石の年代を推定することが可能となっている。
このほか、放射線発生装置を用いたビーム利用技術は、原子核物理の研究、物質の構造解析、質量分析、材料開発等に用いられている。
第2節 放射線利用の普及促進のための方策 放射線利用の普及促進のためには、放射線の持つ特徴を踏まえ、他の方法では実施が困難若しくは実施できても経済的に見合わない分野又は多少コストはかかっても社会の理解が得られ易い分野を重点領域として研究開発に取り組むべきである。特に近年、生活者の立場を重視しながら、健康の維持・増進、生活環境の向上等に向けて科学技術を活用していくことが求められており、医療や環境保全といった分野において重点的に研究開発に取組むことが望ましい。さらには、国の研究機関や大学で開発された技術については、民間及び地方への積極的な技術移転等による普及促進に努める必要がある。
1.生活者を重視した社会構築に貢献する研究開発の推進
近年、国民の意識は、潤い、快適さといった豊かさを求めるものに変質してきている。このようなことから、快適で充実した生活を送るため、健康の維持・増進、生活環境の維持・向上等に向けた科学技術の必要性が高まっており、放射線利用に係る研究開発においても、医療、環境保全といった分野において重点的に研究開発を進めることが適当である。
(1)医療分野
放射線治療は機能温存に優れた治療法であり、米国では放射線治療の寄与率が約55%と我が国の約2倍に達している。今後、我が国においても豊かな生活の希求及び高齢化の進行の度合が高まるにつれ、質が高く侵襲の少ない治療が求められることになり、放射線治療はこれらの要求に沿うものとして需要が高まることが見込まれる。これに応ずる放射線治療の将来は今後の粒子線治療の進展に大きく依存しており、速中性子線、陽子線、重粒子線等の治療研究が進められているところである。
1992年3月現在我が国では、生物効果が高く放射線抵抗性がんに有効と考えられる速中性子線による耳下腺がん、肉腫等の治療症例数が2,492件に達しており、適応症例の治療法は放射線医学総合研究所で確立しているとともに、海外では専用器の普及も進んでいる。また、京都大学、日本原子力研究所等の研究炉で発生する熱中性子を脳腫瘍等に照射して行う中性子捕捉療法による治療症例数は100例を越す実績をもっている。
一方、陽子線治療は、患部に線量を集中照射することが可能な治療法であり、筑波大学等における治療症例数は352件に達している。近年、眼の悪性腫瘍及び前立腺がんのみならず、他の深部臓器がんに対しても優れた治療効果が得られることが明らかになってきており、核物理研究用のシンクロトロンのビームを一部利用して進められてきた研究的な治療の時代から、本格的な医療専用装置の時代へと移行すべき時期にあると言える。
重粒子線治療については、放射線医学総合研究所において「対がん10ケ年総合戦略」の一環として、重粒子線がん治療装置の建設が進められており、平成5年度から臨床試行が開始される予定である。重粒子線は正常組織への影響を最小限に抑え、患部に集中照射することが可能なことに加え、放射線感受性の低い悪性腫瘍に対しても治療効果が高いなどの優れた特徴を持つものである。今後、肺がん、肝がん、すい臓がん等の難治がんの増加が著しいと予測されており、これらの臓器の早期がんには重粒子線が有用な手段として期待されている。
以上の粒子線治療については、地方自治体等においても関心が高いことから、放射線医学総合研究所等における研究効果を踏まえて装置の小型化等を図ることにより、放射線治療の裾野を広げていく努力が必要である。
治療用小線源としては、Ra針に替わってヘアピン、シングルピン、シード、シンワイヤ等多種類の形状の192Ir線源及び198Auグレインが多く使用されるようになった。一方、術者に被曝がない遠隔操作式密封小線源治療装置については60Co線源に替わって、がん治療に線質面で優れている192Ir線源の開発が進められており、また、デュアルホトン方式による骨粗しょう症診断用として153Gd線源製造法が開発されている。また、正常組織の損傷を最小にし、腫瘍への効果を最大にするため、治療用線源による組織吸収線量の高精度計測技術及びその標準設定の研究を進める必要がある。
また、放射線利用が実用化している医用材料の滅菌技術の分野では、近年、輸血後移植片対宿主病(GVH病)等の予防を目的とした血液製剤等への応用が進みつつあり、薬剤の放射線滅菌に関する研究も開始されている。また、3次元X線CT画像を構成する技術は、がんの早期発見のために大きなニーズがある。このようなことから、この方面の研究開発も積極的に進めることが重要である。
(2)環境保全分野
従来から工業プロセス等に応用されてきた電子線照射による処理技術については、近年の地球環境問題への関心の高まりを受け、排煙、廃水、汚泥等の環境対策技術として注目を集めつつあり、その実用化が望まれている。日本原子力研究所等では、燃焼排ガス中の硫黄酸化物及び窒素酸化物を電子線照射により除去する脱硫・脱硝技術の実用化を目指し、技術的確立を図るため、石炭火力発電所、都市ごみ焼却施設や都市高速道路内トンネルからの排ガスを電子線処理するパイロット試験を実施しているほか、下水処理等から発生する汚泥の放射線処理による殺菌、速成堆肥化等に関する技術開発が進められている。また、東京都アイソトープ総合研究所では、γ線又は電子線による下水の再利用を目指した脱色・殺菌等の研究が行われている。
このような放射線処理法は微量汚染物質の分解に大きな効果を有する方法であり、その特徴を活かして今後、地下水汚染等の原因となっている有機塩素系化合物等の除去技術への利用研究を進める必要がある。また、廃資源・未利用資源の有効利用は、資源のリサイクルだけではなく、環境保全の面からも重要であり、放射線処理による生物資源の有効利用の進展も期待される。
このほか、国立環境研究所等において、RIを利用して、汚染物質の環境影響の解明、環境汚染物質を分解する微生物の開発等が進められている。
今後とも、環境を守るための放射線の利用範囲の拡大が望まれ、これらの技術は地方自治体等において、大いに広がっていく可能性がある。
2.普及促進のための方策
放射線利用に係る研究開発を進めるに当たっては、ニーズを調査して時代の流れに即した新しい応用分野を発掘することが必要であるとともに、既に実用化された技術についてもこのような新しい分野への応用及び技術の高度化に取り組むことが重要である。また、国の研究機関や大学で開発された技術については、民間及び地方への積極的な技術移転等による普及促進に努める必要がある。
(1)放射線利用の普及促進のための機関の整備・拡充
電子線等の利用については、今後ともより幅広い分野への普及・拡大が見込まれる中で、民間企業又は地方機関独自では放射線技術の導入が困難な場合も多いのが現状である。したがって、民間、地方等のニーズに応じて、国の研究機関に蓄積された放射線化学、照射技術等に関する知識・経験を移転するとともに、ここに設置されている施設・装置の有効利用による協力を強化していくことが期待されている。一方、これまでこのような支援を行ってきた電子技術総合研究所、放射線医学総合研究所、日本原子力研究所等の国の研究機関では、放射線の先端的研究に次第に移行しつつあり、既に実用化されている電子線等の利用技術に関する民間等への支援業務に、必ずしも十分に対応できない状況にある。
このような状況を踏まえ、放射線利用の普及促進を行うためには、国の研究機関と民間企業等との仲介機能を果たす機関の整備・拡充が有効であり、このような機関の担うべき役割としては次のようなものが考えられる。
なお、国の研究機関で開発された技術を実用化するには、民間への技術移転が必要である。このような場合、民間企業が負う可能性のある実用化に伴うリスクを軽減するため、新技術事業団が研究開発に係る費用を委託開発制度により支出するなど、企業化を促進してきており、今後とも大いに本制度の活用が図られるべきである。
(2)加速器等の小型化・専用化
放射線利用の裾野を広げるためには、特殊目的に合致した性能を有する、使いやすくて低価格の加速器の開発が必要である。中小型の加速器については、既に短寿命RI製造用サイクロトロン、小型放射光装置、イオン注入装置、低エネルギー電子加速器等で専用化の実例がある。今後こうした専用化のための研究開発が必要であり、これによって先端的利用技術の普及促進がより効果的に可能となると考えられる。
また、近年、RI線源による照射に代わり電子線による医療用具、食品包装材等の滅菌がますます普及する傾向にある。厚物の被照射物への対応等利用の範囲を拡大するには、5〜10MeV領域の電子加速器の高出力化及びX線発生装置の高効率化・安定化が望まれる。また、これらの装置の小型化を進め、用途の拡大を図る必要がある。これらの技術開発が進展すれば、各種の殺菌、環境保全等への応用範囲の広がりをもつ可能性が大きい。
(3)国民の理解の増進
今後、放射線利用の実用化の推進を図っていくためには、放射線の利用に当たっての安全管理に万全を期すことはもちろんのこと、放射線に対する国民の理解を深め、普及・啓発を行うことが必要である。先述した普及促進のための機関をも活用して、地方自治体の協力を得つつ、身近な放射線利用に関する啓発を目的とするセミナー、講習会等を全国各地で行うほど、地域と密着した広報活動を積極的に進める必要がある。
特に、放射線利用は医療分野等においてますます身近なものとなりつつあるとともに、環境保全への貢献も期待されることから、これらの貢献を積極的にアピールすることは、放射線に対する国民の理解の増進に役立つものと期待できる。平成5年度より、電源開発促進対策特別会計において放射線利用試験研究推進交付金が計上されたことから、これを活用して原子力発電施設等の立地自治体において医療分野、環境保全分野等の放射線利用研究が積極的に行われることも、放射線に対する国民の理解の増進に資するものと考えられる。
また、放射線利用に対する正しい知識を青少年に広く普及させるためには、各種メディアを通じた啓発活動とともに、中学・高校教員を対象としたセミナーの開催が有効であると考えられる。これらの取組の推進がひいては放射線利用分野での人材確保にも貢献するものと期待される。
第3章先端的な研究開発の推進及び体制整備 放射線利用に係る研究開発については、原子力委員会が1987年6月に決定した原子力開発利用長期計画で、「今後、原子力利用に新しい途を拓き、幅広い科学技術分野での貢献が期待される新しいビーム発生・利用技術、トレーサー技術等、より高度な技術を生み出すことを目指した研究開発に重点を置いて推進する。」とされている。このような加速器等を用いた新たな放射線利用は、物質・材料系科学技術、ライフサイエンス等の広範な分野での進展が期待され、今後とも積極的に研究開発を実施することが重要である。また、近年、我が国においては大型放射光施設等の先端的な加速器が整備されつつあり、一部では研究が開始されているが、基礎研究の強化及びこの分野での国際貢献の観点から、これらの加速器等を中核とした研究開発体制の整備に努める必要がある。また、研究人材の育成・確保のためには、放射線利用分野の研究開発を先端的で魅力あるものにするとともに、産学官の交流を一層活発化する必要がある。
第1節 先端的な研究開発の現状及び今後の進め方 放射線利用に係る先端的な研究開発については、PETの高度化、RI標識モノクローナル抗体を用いたがんの診断・治療等の新しいRI利用技術及び放射光、RIビーム、陽電子ビーム等新しいビーム発生・利用技術に関する研究開発を一層推進していく必要がある。
1.RIの利用に関する研究開発
医療分野において、RIを用いた診断・治療として現在注目されているものには、陽電子放出核種を利用するインビボ検査(脳、心、肺等の機能的診断)及び免疫核医学的手法を用いたがんの診断・治療があり、ともに研究が進められている。
前者は、病院内に設置された小型サイクロトロンによって製造される11C,13N,15O,18F等の陽電子放出核種を用いたPET装置により診断する手法で、国内18の施設で使用され実用段階に達している。この手法の高度化のため、放射線医学総合研究所等において高解像力・高感度のPETの開発、3次元陽電子イメージングの性能向上に関する研究等が進められているところである。その結果、酸素代謝、血液・血流分布、脳ブドウ糖代謝等、診断の基礎となる生理的データが定量的画像情報として描出されてきており、例えば、脳神経相互間の情報伝達を担っている極微量物質の働きに関する研究により、ドーパミン系ニューロン及びベンゾジアゼン系ニューロンの受容体の映像化に成功している。診断に用いる短寿命RIについては、放射線医学総合研究所を始め、東北大学においても医用サイクロトロンによる短寿命核種の生産、短寿命RI標識化合物の製造技術等に関する研究開発が進められるとともに、国立療養所中野病院、京都大学、群馬大学、九州大学、秋田県立脳血管研究センター等においても、小型サイクロトロンを用いて同様の研究が進められている。
さらに、これらの技術は診断のみならず、薬物の動態、作用機序の解明、動植物における物質代謝の解析等、広く医学・ライフサイエンスの新しい分野への応用が期待されている。特に、生物をまるごと生きたままの状態で観察できることから、インビボの生化学という新しい領域が開拓されようとしている。また、短寿命RIは超高比放射能での標識合成が可能なことから、従来の方法では不可能であった極低濃度領域の生命現象の解明にも期待されている。
このようなPET装置の普及には短寿命RIの安定供給が不可欠であるため、関連する薬剤の自動合成等のバックアップ体制の整備が重要な課題となっている。さらに、PETに用いられる短寿命RIのジェネレーターシステム(62Zn―62Cu等)を利用した放射性薬剤を開発することがこの診断法の普及には有効である。なお、PETで得られた成果をより広く日常診断に普及させる方策としては、PET製剤の利用核種に代替可能な核種である123Iを中心としたSPECT用放射性薬剤の研究開発を推進することが適切であると考えられる。
後者は、がん関連抗原を認識する抗体(モノクローナル抗体)をRIで標識し患者に投与することにより、各部位の病理組織の特異性に従って原発巣及び転移巣の存在を診断することができ、また、適切な核種を選択してさらに大量に投与すれば治療効果も期待できるものである。我が国でも1990年12月に人体投与の際の安全指針が作成・公表されたため、腫瘍組織に対する選択性の向上等今後の技術的ブレークスルーが期待されているところである。このような基礎的な研究成果を踏まえ人体への適用可能性を見据えつつ、免疫核医学を中心とした悪性腫瘍の診断・治療技術の確立のための中核的な研究施設について検討を進めることが望まれる。
また今後、放射性医薬品の診断・治療効果を高めるためには、ドラッグデリバリーシステムの研究を行う必要がある。
農林水産分野においても、サイクロトロン製造による13Nの利用が確立されれば、土壌中の脱窒過程解明等に関する研究が飛躍的に進展することが期待されるとともに、家畜衛生分野におけるPETの利用も期待される。
2.放射線ビーム発生・利用技術に関する研究開発
放射線ビーム発生装置の利用に係る先端的な研究開発課題は表5に示すとおり広範にわたるが、これらの各種ビームの発生・利用技術を一層発展させることが重要である。
表5 ビーム高度利用の今後の可能性 (1)放射光の発生・利用技術
高輝度・短波長のシンクロトロン放射光は、物質・材料系科学技術、ライフサイエンス、情報・電子系科学技術等の広範な基礎研究分野のための有力な研究手段であるとともに、原子力分野におけるこれまでの技術蓄積を活用し得る分野であり、いくつかの機関で放射光の発生・利用のための研究が行われている。このような研究の更なる発展を目指し、日本原子力研究所及び理化学研究所のポテンシャルを結集して、大型放射光施設(SPring―8)の建設・整備が進められている。これを利用して分子レベルの時間的に変化する現象の動的解析(生体内での酵素反応中の構造解析等、動的な蛋白質機能の研究等)、極限環境下(超高圧、超強磁場下等)での物質の構造及び物性の解明、X線ホログラフィによる原子・分子の立体配列の直接観察等が進められることになる。このような利用の更なる高度化(位置分解能の向上等)に向けた放射光のマイクロビーム化が求められており、そのための耐熱性に優れた光学素子、分光器等の開発が必要であるほか、高速イメージング機器等の研究開発も重要である。
また、産業界への波及効果を考えると、挿入光源(ウィグラー、偏光可変アンジュレーター等)を含む大型放射光施設以外の中小型放射光装置の開発も重要である。さらに、リソグラフィ用の小型放射光装置の開発、生物試料を対象としたX線顕微鏡の開発等も期待されている。このほか、医用専用の小型放射光装置整備への要求も高まりつつある。
(2)イオンビームの発生・利用技術
材料開発等のための放射線利用技術高度化の一環として、日本原子力研究所において、エネルギー領域の異なる4台のイオン加速器を有するイオン照射施設の建設・整備が進められており、イオンビームを用いた耐放射線性極限材料、新機能材料の研究等の放射線高度利用研究が開始された。また、バイオ技術の研究として、イオンビーム照射を利用した突然変異育種技術の開発及び局部照射による細胞加工技術の開発も期待される。
基礎物理研究の分野では、理化学研究所において世界最高レベルの重イオン科学用加速器を用いて原子核物理等の研究が行われており、原子番号110番以上の超重元素の発見等が期待されているところである。また、大阪大学においても同様の軽重イオン加速器が稼働を開始した。
このようなイオンビームの更なる高度化のためには、エネルギー幅の小さい超高単色性ビームの発生・利用技術に関する研究開発が必要である。そのほか、イオンビームの高品質化として、エネルギー範囲の拡大、イオン種の拡大、イオン電流範囲の拡大、イオンビームの選択化(励起イオンビーム生成、中性ビーム、負イオンビーム、極短パルスビーム、マイクロイオンビーム)が求められている。また、新しいイオンビーム誘起効果の探索、選択的状態を有するイオンビームによる新分析技術、照射対象分野の拡大等、イオンビーム利用の開拓が期待されている。
(3)RIビームの発生・利用技術
近年、高エネルギー重イオンビームによる入射核破砕反応で生成する高速不安定核ビームを用いた研究の気運が高まってきており、加速粒子が安定核に限られていたこれまでの研究と比べると、研究の範囲が核物理のみならず天体核物理にまで広がっている。わが国では理化学研究所を中心として世界最先端の研究が進められており、例えば、宇宙における元素生成メカニズムや中性子ハロー、中性子スキンの存在がRIビームを利用した研究により発見された。RIビームの利用により、加速粒子の種類が飛躍的に拡大し、これまでになかった核反応や新核種及び新元素の合成が可能になるため、今後、世界の原子核研究において大きな流れのひとつとなることが見込まれるとともに、物質・材料研究、生物研究、基礎医学の研究等の幅広い研究分野への利用が期待される。このような幅広い研究分野への利用及び利用の高度化に当たっては、低エネルギーから高エネルギーまでの広いエネルギー範囲と更に高強化・高品質のRIビームが必要となる。このため、大強度の高エネルギー重イオン連続ビームが得られる超電導リングサイクロトロンの技術開発及びRIビーム発生・利用研究施設の整備が望まれる。
このような基礎研究分野ばかりではなく、重イオンビームで二次的に発生した陽電子放出核ビームを用いて、比較的小さながん標的を照射位置を確認しつつ照射・照合する技術の開発も期待されている。
(4)陽電子ビームの発生・利用技術
陽電子の利用は、RIから得られる白色陽電子の物質中での消滅を扱っていた時代から、エネルギー可変単色ビームが利用できる時代に入り、ますます高密度化する半導体素子でこれまで問題とならなかったような微小・微量の欠陥の評価等に不可欠な分析手段として利用される段階に至っている。
また、単色ビームの利用により、高温超電導機構の解明に必要な電子構造解析を始めとして、放射光等他の手法と相補的な、あるいは他の手法では困難なキャラクタリゼーションが行える手法としての道が拓け、先端材料開発の分野で有望視されている。さらに、陽電子が消滅等の特異な反応のチャンネルを持った基本的な素粒子であり、かつ、消滅γ線等によって与えられる情報量も豊富であることから、原子・分子物理学等の基礎理論の新展開、宇宙進化の研究、DNA損傷による突然変異機構の解明等、材料開発以外の分野でも、その利用が期待されている。
このような広範な応用のためにはRIから得られるよりも大強度の陽電子ビームが必要である。電子技術総合研究所では、世界に先駆けて電子ライナックを用いて大強度陽電子線の発生、直流化、極短パルス化等の研究を進めて、材料分析等の研究に利用している。しかしながら、このような現有施設で発生が可能な単色陽電子ビーム強度は最高108個/秒程度であり、上述の分野での実用化には至っていない。そのため、実用化に必要な2桁以上強力なビームの発生が可能な大強度単色陽電子ビーム発生・利用研究施設を関係研究機関の協力の下に整備することが望まれる。
(5)自由電子レーザーの発振・利用技術
次世代のレーザーとして期待されている自由電子レーザーは、波長可変性、高出力、高効率等の優れた特徴を持っているため、原子力を始めエレクトロニクス、医療、化学工業、医薬品工業等の幅広い分野への応用が期待されている。したがって、今後レーザー発振技術として、高輝度加速器、アンジュレーター、反射率の高い光共振器ミラー等の開発を行うとともに、同位体分離、表面加工、医学利用等の分野における実用化に向けた研究を着実に進める必要がある。また、自由電子レーザーをさらに電子ビームと正面衝突させて発生させる高エネルギー・エネルギー可変のγ線は将来性が期待されている。
(6)陽子ビーム、中性子ビーム等の発生・利用技術
現化学研究所が英国ラザフォードアップルトン研究所の大強度陽子加速器に付帯してミュオンビーム発生施設を建設しており、ミュオンによる物性解析等の基礎研究の進展が期待されている。一方、陽子加速器を利用したパイ中間子によるがん治療については、治療に必要とされる大強度のパイ中間子を発生・制御する技術を確立する必要があり、諸外国の動向を踏まえつつ基礎的な研究を進めることが望ましい。
核融合材料研究のための大強度重陽子加速器によるエネルギー選択型中性子発生技術、長寿命放射性核種の消滅処理のための核破砕反応中性子の工学利用を目的とした大強度陽子加速器技術等の研究開発が行われており、適用プロジェクトの計画の進展状況を勘案しつつ、着実に進めていくことが適当である。
また、研究炉からの中性子ビームの利用については、これまで京都大学研究炉及び日本原子力研究所JRR―2が中核的な役割を果たしてきた。最近改造されたJRR―3が新たに冷中性子源を備え、高性能の冷中性子ビームの供給を可能としたことにより、研究分野が飛躍的に拡大され、高分子化学、生命科学、材料科学、量子力学等、一層広範な研究開発が期待される。
第2節 研究開発体制の整備 第1節に述べた新しいRI利用及びビーム利用に関する先端的な研究開発については、広範な分野の高度な技術の結集が必要であり、中心的な機関を明確にして、各々の分野で十分な研究開発ポテンシャルを有する産業界、大学及び国の研究機関の人材等を結集してこれに当たることが重要である。
特に、我が国においては、現在、大型放射光施設等いくつかの先端的な加速器が整備されつつあるが、その建設・利用に多額の経費及び多くの研究者・技術者を要する先端的な加速器施設を活用し、先端的な研究成果をあげていくためには、このような加速器施設に内外の優れた研究者を結集し、独創的な研究開発を推進することが重要である。このため、このような施設を有する研究機関にあっては、今後、開放性、流動性及び国際性を向上させ、国内外の大学、研究機関等との交流を活発化するなど、研究開発体制を整備する必要がある。このような取組を通じて、先端的な加速器を有する研究機関が優れた中核的研究拠点(センター・オブ・エクセレンス)となることが期待される。
1.加速器の発展動向
加速器はもともと原子核研究用として発明され、原子核・素粒子の研究の発展とともに、進歩してきた。特に、物質の究極の構造を究めるために不可欠な実験装置として図3に示すように大型化、高性能化し、そのエネルギー、ビーム強度及びビーム性能のフロンティアを拡大してきた。すなわち、エネルギーフロンティアの拡大は、単一加速器から複合加速器、さらには衝突器へ並びに大型化及び超電導利用へ移行することにより、強度フロンティアの拡大は、電子銃・イオン源及び蓄積・冷却リングの開発により、また、ビーム性能フロンティアの拡大は、短パルス化、マイクロビーム化及び均一化により達成されてきた。また、加速粒子フロンティアの拡大もイオン源の開発、二次粒子の利用及び不安定核粒子の蓄積・加速・冷却により実現してきている。
一方、加速器は種々の放射線を人工的に創り出し、また物質にイオン種又は高密度のエネルギーを制御性よく注入できる優れた装置である。そのため、加速器を原子核研究以外の研究に利用する試みが、その発明の初期から進められてきた。これは加速器が他の研究装置に比べて極めて先端的な巨大実験装置であり、その建設には多くの技術開発及び多額の経費を要してきたことも一因として考えられる。このような付随的利用から、例えば放射光、イオンビーム等に関する新しい研究分野が生み出されてきている。諸外国では、原子核・素粒子研究の分野で役目の終わった加速器が、それまでは付随的であった利用研究の専用加速器として用いられ、優れた成果をあげる例が多く、これらの成果をもとにして、新しく生み出された研究分野に専用の加速器が開発されている。
図3 加速器の発展状況 2.加速器を中核とした研究開発体制の整備の基本的考え方
(1)先端的な研究施設の整備
加速器研究施設において最先端の研究が行われるためには、当該加速器がエネルギー、強度、性能又は利用できる粒子に関して最先端の性能を持つ必要がある。
ビーム発生装置については、広いビームエネルギー・強度範囲とともに、ビームの強度均一性、集束性等の空間的制御機能、パルス等の時間分解機能、複合・極限条件下でのビーム利用機能、二次ビーム生成機能等の高度なビーム発生・制御機能を有することが重要である。また、利用できる粒子、二次ビーム等のビーム種についても多様性が必要であり、必要に応じ、複数の異なるビームの利用を可能とすることも望まれる。
(2)優れた研究資源の結集
加速器を利用して創造的な研究活動を推進するためには、優秀な研究者を結集し、最先端の研究活動を維持して、内外の優れた研究者を惹き付けることが必要である。そのためには、まず優れた研究者がリーダーシップをとって独創的な研究を遂行する施設固有の研究グループの結成が必要である。
また、研究機関の活性を維持するとともに、加速器を利用した研究に新しい発想を持ち込むためには、若手研究者の積極的な受入れを促進することが重要である。
さらに、得られた研究成果及び技術ノウハウをデータベースとして整備し、積極的に知的資産の蓄積に努めるとともに、国際シンポジウムの開催等により、これらの情報を世界に向けて発信することも重要である。
(3)国内外に開かれた運営体制の整備
研究拠点施設が効率的に運用されるためには、柔軟で流動性が高く、かつ、国内外を問わず開放的な研究運営が必要である。このためには、研究者交流及び研究協力のための制度の充実並びにその積極的活用を進めるとともに、外来研究者のための宿泊施設の整備、旅費の支援等を行うことが重要である。
外部機関の研究グループとの研究協力を一層進めるためには、例えば、外部機関へのサテライト研究グループの設置、高度情報ネットワークによる日常的な研究協力等を推進することも肝要である。
また、加速器等の施設の管理、外来研究者のための利用支援、得られた研究情報の国内外への発信等を効果的・効率的に行えるよう、専門的な知見を有する外部機関の活用の検討も含め、所要の体制整備を図ることが重要である。
このほか、責任ある課題採択制度及び厳しい研究評価制度を確立することも重要である。
3.加速器施設の特徴に応じた研究開発体制の整備
加速器施設の研究開発体制の整備は、1.で述べたような加速器の特徴を踏まえて行う必要がある。
すなわち、大型放射光施設、重粒子線がん治療装置、イオン照射研究施設等のように加速器利用研究の裾野を広げる役割を持つ加速器を整備する研究機関においては、科学技術の広い分野で最先端の基礎的・応用的研究を行うほか、幅広いユーザーの受入れ及び研究支援を進めることが必要である。そのため、特に、民間企業、大学、国公立研究機関、医学分野にあっては医療機関等のユーザーとの連携・交流が大きな課題となる。この場合、課題採択に当たっては、所内外の学識経験者によるユーザーの特徴にも配慮した公正な審査が必要である。また、ユーザーが必ずしも先端的加速器の利用に熟練していない場合も多くなると見込まれることから、研究面・技術面における支援体制の充実が重要である。加速器を利用した研究に不可欠な計測器を実験毎に準備することは、今後、加速器のユーザーを広げるに当たり障壁となる可能性があり、これらの高度測定機器の賃貸制度等周辺環境を整備しておくことが望ましい。さらに、このような加速器施設の場合には、比較的短期間の施設利用が多くなると見込まれるので、高度情報処理システムの整備によるデータ収集・解析の効率化によるユーザー支援も肝要である。
一方、リングサイクロトロンのように、エネルギー、性能又は粒子の観点から世界的なフロンティア加速器を有する研究機関にあっては、まず、加速器の性能、周辺測定機器等を世界のトップレベルに維持・発展させることにより、常に最先端の研究を実施できる状態を保つことが必要である。そのためには、高度技術者の育成・確保、施設に密着した問題提起型の研究者と装置開発担当者との間での積極的協力関係の確立、国内外の先端加速器所有機関との交流強化等を図ることが肝要である。また、国内外の優れた研究者が集まる魅力的な研究機関にするためには、優れた研究拠点にするための明確で具体的な目標をたて、それを達成するための強いリーダーシップが必要である。特に、長期的研究計画の策定、研究グループの結成・評価・解散等に当たって当該研究機関のリーダーの権限及び責任を明確にする必要がある。また、課題採択においても課題採択審査委員会の公正な判断以外にリーダーによる採択枠を設けるなど、リーダーシップの下での柔軟な運営を行うことにより、常に最先端かつ魅力的な研究を推進して行くことが重要である。
第4章 放射利用分野における国際貢献 近年、近隣アジア諸国等においては、生活向上に直接役立つ放射線利用に強い関心を有しており、技術的基盤の充実、人材の養成等を目的とした我が国の協力が強く望まれている。また、先端的な研究分野においては、先進国との研究協力が進められており、基礎研究分野における国際貢献の観点から積極的に進めることが望ましい。
第1節 国際協力の現状 放射線利用の分野における主な国際協力の現状は表6に示すとおりであり、原子力分野の国際協力の大きな柱として積極的に進められている。
表6 放射線利用分野における途上国協力の現状 1.途上国協力
(1)アジア地域原子力協力国際会議の下の協力
我が国の原子力委員会は、近隣アジア諸国における地域協力の具体化に向けて意見交換・情報交換を行い、地域協力テーマに関する関係各国のコンセンサスを得ることを目的に、1990年から近隣アジアの原子力関係者が一堂に会する「アジア地域原子力協力国際会議」を開催している。同会議の下で、放射線の農業利用、医学利用を含む4つの協力テーマについて協力活動が開始されている。
(2)IAEA/RCA
「原子力科学技術に関する研究、開発及び訓練のための地域協力協定」(RCA)は、アジア・太平洋地域の国際原子力機関(IAEA)加盟国間において放射線利用を中心とする原子力科学技術の研究開発及び教育訓練を推進することを目的とするものであり、現在15カ国が参加している。RCA計画では、国連開発計画(UNDP)との環境プロジェクト等、現在12のプロジェクトが進められているが、我が国は、環境、医学・生物及び農業の3分野に対して積極的な協力を行っている。
(3)二国間協力
日本原子力研究所が中心となり、インドネシア原子力庁との間で医用材料の開発に関する研究、タイ原子力庁との間で放射線による汚泥処理に関する研究、マレイシア原子力庁との間でオイルパーム廃棄物の放射線処理に関する研究及びメキシコとの間で環境保全・線量測定に関する研究がそれぞれ行われている。
(4)原子力研究交流制度に基づく協力等
科学技術庁では、1985年より日本の研究機関と開発途上国の研究機関の間で研究者交流を行う原子力研究交流制度を実施している。本制度により、放射線の医学利用、高分子材料の放射線加工、排煙・廃水・汚泥の放射線処理、計測器の校正技術等の分野で、研究者の受入れ、派遣等の研究協力が行われている。そのほか、1989年から、国際協力事業団により、マレイシアにおいて電子加速器の建設を含む電子線による医療器具の滅菌等の放射線利用研究プロジェクトが実施されている。
2.先進国協力
先進国との協力では、米国、英国、ドイツ、フランス等との間で、重イオン科学、イオンビーム利用、中性子利用、排煙の放射線処理等に関する共同研究が進められている。
また、経済協力開発機構国際エネルギー機関(OECD―IEA)及び米国との核融合炉材料の中性子照射に関する研究のほか、国際原子力機関(IAEA)の研究協力計画の中で粒子線加工処理に関する線量測定、伝染病用診断試薬の開発等に関する協力に参加している。
第2節 国際貢献に向けた協力のあり方 放射線利用分野の国際協力の今後の取組としては、途上国協力、先進国協力とも、協力対象国及び協力内容の拡充、受入れ及び派遣体制の整備・強化等を積極的に進める必要がある。国内の関係諸国機関においては、従来の取組を一層推進することに加え、新たな国際協力にも積極的・計画的に取り組んでいくことが望まれる。
特に、開発途上国への放射線利用に関する技術協力は、我が国の原子力分野での国際貢献の大きな柱であり、日本原子力研究所等が専門家の派遣、研修員の受入れ等により協力を行っているが、今後、アジア地域原子力協力等既存の枠組の活用を図るとともに、供与技術を定着させる協力等、途上国のニーズに応じたきめ細かい協力体制の整備について検討する必要がある。
1.途上国協力
放射線利用は、途上国の経済・社会の発展に大きく貢献するのみならず、当該国の科学技術の振興にも寄与することから、多国間協力、二国間協力ともに積極的に推進し、相手国のニーズ及び実情を踏まえ、開発段階に応じたきめ細かい協力を推進していく必要がある。
それにはまず、援助を受ける国が本格的に取り組む姿勢を固めているかどうかが重要であり、協力において肝要な点は、供与された技術が途上国でどのように役立つかを見極めることである。通常、IAEA/RCA計画、二国間協力等においては、当該国との協議の上で技術供与が行われているが、供与された技術が当該国の国情に合致しないケース、あるいは、周辺技術の不足ゆえにその技術が活かされないといったケース等が見受けられる。したがって、技術の供与に当たっては、当該技術だけではなく、その周辺技術も含めて受入れる素地があるかどうかを事前に調査することが望ましい。その上で、放射線利用技術の定着の観点から、例えば電子加速器の運転・維持等の周辺技術も含めた技術協力のあり方について検討しておく必要がある。また、安全規制体系の整備、事業所内での利用体制の確立、放射線取扱技術者の養成等の利用周辺環境の整備、これらに関する日本の現状紹介等も重要である。
さらに、供与された技術を定着させるためのきめ細かな協力については、供与の時点からタイムスケジュールの中に入れておく必要がある。途上国においては、研究指導者の長期派遣の希望が多いため、定年後の研究者の派遣、現役研究者の短期シャトル派遣等の方策も進めていくことが肝要である。
一方、供与された技術を使いこなせる人材の養成を行うことにより、このような協力が一層効果的なものとなるので、人材交流を積極的に進めることについても検討していく必要がある。昨今、我が国の公的な研究機関だけでは、増大する放射線利用分野の技術協力業務への対応に限界が生じており、第2章に述べた普及促進のための機関を活用し、研修生の受入れ、専門家の派遣等を推進することが望まれる。また、一方的な協力関係のみならず、開発途上国の研究者同士の交流の場の設定及びそこへの我が国の参画も効果的であると考えられる。
2.先進国協力
放射線利用分野においては、加速器を中心に研究設備が大型化・複雑化し、多方面の高度な知見が不可欠であるとともに、優れた人材等の確保が重要な要素となってきている。その結果、本分野の研究開発を進めるについては、先進国間の国際的な協力の必要性が高まりつつある。
このような先進国協力において、我が国の研究機関が基礎研究分野での国際貢献を果たすべく、放射線利用分野において積極的にリーダーシップをとって行くためには、まず、我が国の研究機関が世界に先駆けて先端的な研究に着手し、実績を挙げておくことが重要である。
また、このような先進国協力を一層拡大して行くためには、人材及び情報の積極的な交流を進める必要があり、国際的なヒューマンネットワークを作っていくことや先端的な加速器を所有する国内外の研究機関間の情報交換活動を促進することが望まれる。
<参考資料>
1.放射線利用専門部会
(1)開催経過
第4回 平成4年10月6日
第5回 平成4年12月4日
第6回 平成5年3月12日
第7回 平成5年5月28日
(2)構成委員
2.放射線利用推進分科会
(1)開催経過
第9回 平成4年10月28日
第10回 平成4年11月17日
第11回 平成5年1月14日
第12回 平成5年2月12日
第13回 平成5年3月24日
(2)構成委員(平成5年3月末現在)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前頁 | 目次 | 次頁 |