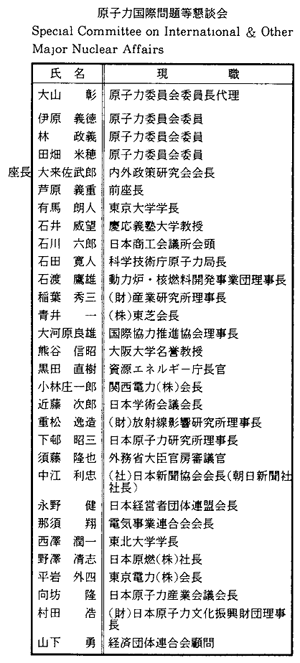| 前頁 | 目次 | 次頁 | |
|
委員会の動き 定例及び臨時会議 第48回(定例) 〔日時〕 1992年12月1日(火) 10:30〜
〔議題〕
(1) 日本原燃(株)六ケ所再処理・廃棄物事業所における再処理の事業の指定について
(2) その他
〔審議事項〕
(1) 議事録の確認
事務局作成の資料「第47回原子力委員会臨時会議議事録」が了承された。
(2) 日本原燃(株)六ケ所再処理・廃棄物事業所における再処理の事業の指定について
平成3年8月22日付け3安(核規)第574号をもって内閣総理大臣から諮問を受けた標記の件について、科学技術庁から同再処理施設の指定に係る原子炉等規制法上の体系について説明がなされ、審議を行った。
第49回(臨時) 〔日時〕 1992年12月4日(金) 10:30〜
〔議題〕
(1) 日本原子力研究所原子力第1船原子炉の設置変更(放射性廃棄物の廃棄施設等の変更)について(答申)
(2) 動力炉・核燃料開発事業団大洗工学センターの原子炉の設置変更(重水臨界実験装置及び高速実験炉原子炉施設の変更)について
(3) 高レベル放射性廃棄物対策推進協議会の動向について
(4) 高レベル放射性廃棄物地層処分研究開発の技術報告書について
(5) その他
〔審議事項〕
(1) 議事録の確認
事務局作成の資料「第48回原子力委員会定例会議議事録」が了承された。
(2) 日本原子力研究所原子力第1船原子炉の設置変更(放射性廃棄物の廃棄施設等の変更)について(答申)
平成4年10月15日付け4安(原規)第305号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認め、内閣総理大臣あて答申することとした。(資料1)
注) 本件は、原子力船「むつ」の解役に伴う解体物の保管に使用するため、「むつ」の附帯陸上施設敷地内に保管建屋を建設するとともに燃料・廃棄物取扱棟の一部変更し、また附帯陸上施設のうち大湊附帯陸上施設を設置許可から削除を行うものである。
(3) 動力炉・核燃料開発事業団大洗工学センターの原子炉の設置変更(重水臨界実験装置及び高速実験炉原子炉施設の変更)について
平成4年10月12日付け4安(原規)第221号をもって、内閣総理大臣から諮問を受けた標記の件について、科学技術庁から資料に基づき、設置変更の目的等について説明がなされ、引き続き審議することとした。
注) 本件は、重水臨界実験装置及び高速実験炉原子炉施設に係わるものである。重水臨界実験装置については未臨界度測定実験の機能を追加するため、炉心の改造及び燃料体の追加等を行うものである。また、高速実験炉原子炉施設については燃料要素の寿命限界把握のため、プルトニウム・ウラン混合炭化物燃料及びプルトニウム・ウラン混合窒化物燃料を燃料材として用いた炭化物及び窒化物試験用要素の追加等を行うものである。
(4) 高レベル放射性廃棄物対策推進協議会の動向について
標記の件について、事務局から資料「高レベル放射性廃棄物処分事業に関する準備のための組織について」に基づき、高レベル放射性廃棄物処分事業に関する準備のための組織について、設立の目的、業務内容等に関して説明がなされ、了承された。(資料2)
(5) 高レベル放射性廃棄物地層処分研究開発の技術開発の技術報告書について
標記の件について、動力炉・核燃料開発事業団から資料に基づき、報告がなされた。また、本報告書については、今後、放射性廃棄物対策専門部会において評価、検討していくこととなった。(資料3)
第50回(定例) 〔日時〕 1992年12月8日(火) 10:30〜
〔議題〕
(1)日本ニユクリア・フユエル(株)における核燃料物質の加工の事業の許可について(諮問)
(2) その他
〔審議事項〕
(1) 議事録の確認
事務局作成の資料「第49回原子力委員会臨時会議議事録」が了承された。
(2) 日本ニユクリア・フユエル(株)における核燃料物質の加工の事業の許可について(諮問)
平成4年12月1日付け4安(核規)第436号をもって内閣総理大臣から諮問を受けた標記の件について、科学技術庁から資料に基づき説明がなされ、引き続き審議することとした。
注) 本件は、作業性向上のため、第1加工棟で取り扱うウランのうち、一部の最高濃縮度を4.0%から5.0%に変更し、燃料集合体の組立作業の改善を行い、組立施設の最大処理能力を640トンU/年から750トンU/年に変更、及び液体廃棄物処理工程の合理化に伴い、受入槽、遠心分離機及び凝集沈澱槽等の設備の変更等を行うものである。
第51回(定例) 〔日時〕 1992年12月15日(火) 11:00〜
〔議題〕
(1) 委員長代理の指名について
(2) 日本原燃(株)六ケ所再処理・廃棄物事業所における再処理の事業の指定について(答申)
(3) その他
〔審議事項〕
(1) 委員長代理の指名について
中島委員長から原子力委員会委員長就任の挨拶があり、原子力委員会及び原子力安全委員会設置法第4条第3項の規定に基づき、原子力委員会委員長代理に大山委員を指名し、さらに大山委員長代理の海外出張等による不在の際の委員長代理には、伊原委員を指名した。
(2) 日本原燃(株)六ケ所再処理・廃棄物事業所における再処理の事業の指定について(答申)
平成3年8月22日付け3安(核規)第574号(平成4年7月16日付け4安(核規)第451号及び平成4年11月18日付け4安(核規)第780号をもって一部補正及び一部修正)をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第44条の2第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認め、内閣総理大臣あて答申することとした。(資料4)
また、本件答申に伴い、本日付けで原子力委員会委員長談話「日本原燃(株)六ケ所再処理・廃棄物事業所における再処理事業の指定に係る答申に当たって」を発表することとした。
注) 本件は、原子力発電所からの使用済ウラン燃料の再処理を行うため、青森県六ケ所村に再処理施設を設置し、再処理事業を行うものである。
第52回(臨時) 〔日時〕 1992年12月18日(金) 10:30〜
〔議題〕
(1) 北海道電力(株)泊発電所の原子炉の設置変更(1号及び2号原子炉施設の変更)について(諮問)
(2) 日本原燃(株)六ケ所濃縮・埋設事業所における核燃料物質の加工の事業の変更の許可について(諮問)
(3) その他
〔審議事項〕
(1) 議事録の確認
事務局作成の資料「第50回原子力委員会定例会議議事録」及び資料「第51回原子力委員会定例会議議事録」が了承された。
(2) 北海道電力(株)泊発電所の原子炉の設置変更(1号及び2号原子炉施設の変更)について(諮問)
平成4年12月9日付け4資庁第8956号をもって通商産業大臣から諮問を受けた標記の件について、通商産業省から資料に基づき説明がなされ、引き続き審議することとした。
注) 本件は、燃料の効率的な使用等を図るため、燃料集合体最高燃焼度及び取替燃料の濃縮度を上昇させ、取替燃料の一部にガドリニア入り燃料を使用し、取替燃料として従来の燃料(A型)のほかに、設計の一部異なる燃料(B型)の採用、従来のバーナブルポイズン(A型)のほかに、設計の一部異なるバーナブルポイズン(B型)の採用等を行うものである。
(3) 日本原燃(株)六ケ所濃縮・埋設事業所における核燃料物質の加工の事業の変更の許可について(諮問)
平成4年12月4日付け4安(核規)第812号をもって内閣総理大臣から諮問を受けた標記の件について、科学技術庁から資料に基づき説明がなされ、引き続き審議することとした。
注) 本件は、核燃料物質の最大処理能力の増加等のため、2号カスケード棟及び2号発回均質棟の増設、保管区域の最大貯蔵能力の変更、核燃料物質の貯蔵施設の貯蔵能力を増強させるため、Bウラン貯蔵庫及びCウラン貯蔵庫の増設等を行うものである。
第53回(定例) 〔日時〕 1992年12月22日(火) 10:30〜
〔議題〕
(1) 原子力国際問題等懇談会構成員の変更について
(2) その他
〔審議事項〕
(1) 議事録の確認
事務局作成の資料「第52回原子力委員会臨時会議議事録」が了承された。
(2) 原子力国際問題等懇談会構成員の変更について
標記の件について、事務局から資料に基づき説明がなされ、了承された。(資料5)
資料1
日本原子力研究所原子力第1船原子炉の設置変更
(放射性廃棄物の廃棄施設等の変更)について(答申) 4原委第116号
平成4年12月4日
内閣総理大臣 殿
原子力委員会委員長
平成4年10月15日付け4安(原規)第305号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る)に規定する基準の適用については妥当なものと認める。
資料2
高レベル放射性廃棄物処分事業に関する
準備のための組織について 平成4年12月2日
高レベル放射性廃棄物
対策推進協議会
1. 名称 高レベル放射性廃棄物処分事業推進準備会(仮称)
2. 目的 我が国の原子力開発の進展を図るために、高レベル放射性廃棄物に関する調査・研究及びその成果の普及・活用等を通じて、国民の理解と協力を得つつ、高レベル放射性廃棄物処分事業の準備の円滑な推進を図ることを目的とする。
3. 業務内容 本準備会は、上述の目的を達成するために次の業務を行う。
(1) 高レベル放射性廃棄物処分の事業化計画に関する事項
(2) 高レベル放射性廃棄物処分の実施主体の形態、業務等に関する事項
(3) 高レベル放射性廃棄物処分の事業資金に関する事項
(4) 高レベル放射性廃棄物処分に係る立地に伴う地域振興等に関する事項
(5) 高レベル放射性廃棄物処分に係る広報に関する調査・研究及び広報活動に関する事項
(6) 高レベル放射性廃棄物処分に係る法制に関する事項
(7) その他、本準備会の目的を達成するために必要な事項
4. 形態及び位置づけ (1) 任意団体とする。
(2) 本準備会は、高レベル放射性廃棄物対策推進協議会の下に設置し、その成果等は必要に応じ推進協議会へ報告、あるいは推進協議会の了解を得るものとする。
(3) 本準備会は、そのまま実施主体に移行するものではない。
5. 運営体制 (1) 会長:未定
(2) 事務局要員:10名程度とし、必要に応じて拡充する。
6. 設立時期 平成5年4月頃を目途に設置する。
資料3
高レベル放射性廃棄物地層処分研究開発の技術報告書
―平成3年度―
平成4年9月
動力炉・核燃料開発事業団
報告書の要約 高レベル放射性廃棄物とは、日本の場合、原子力発電所の使用済燃料を再処理し、ウラン及びプルトニウムを回収したあとに残る廃棄物である。原子力発電は、火力発電に比べて廃棄物の発生量が少なく、この高レベル放射性廃棄物についてもその発生量は限られているが、放射能が高くかつ長く継続することから、その対策にあたっては、長期にわたる安全確保に特に留意する必要がある。
高レベル放射性廃棄物対策に関する日本の基本方針は、これを安定な形態に固化し、30〜50年間程度冷却のため貯蔵したあと、長期的な安全確保を一層確実にする観点から地下数100mより深い地層中に処分(これを地層処分という)することとされている。
地下深部の地層は、地表付近に比べて地質学的に安定であり、廃棄物を長期間にわたって安全に保持することができると考えられる。また、高レベル放射性廃棄物中の放射性物質が地下水中に混入するようなことが仮にあったとしても、地層中の鉱物の吸着作用などによって環境安全が保たれる可能性が高い。これらのことから、国際的には、1950年代に地層処分という概念がすでに考え出され、現在高レベル放射性廃棄物の処分を検討している国々では例外なくこの地層処分を最も合理的かつ実現性の高い処分方法と考え、その研究開発を行っている。
諸外国においては、日本の先んじて研究開発に取り組んでいるところもあり、この地層処分概念の有効性に関する技術的見通しをすでに得つつある国もある。日本においても、これらの諸外国の研究開発成果を参考にしつつ、その見通しをできる限り明らかにする段階にきており、原子力委員会は1989年12月及び1992年8月の放射性廃棄物対策専門部会の報告書の中で、現在までの成果をもとに第1次とりまとめを行う時期にきていると指摘している。本本告書は、この原子力委員会の方針に従い、動力炉・核燃料開発事業団(以下、動燃事業団という)が研究開発の中核推進機関としてこれまで行ってきた研究開発の成果をとりまとめたものである。
地層処分の安全性で最も重視すべき点は、放射性物質が地下水を介して人間とその生活圏に影響を及ぼす可能性に関する安全確保とその安全評価であることが、日本及び諸外国におけるこれまでの研究開発によって明らかになってきている。これは、予めそのようなことが起こらないような措置をできるだけ講じておくとともに、さらに環境への影響をもたらすような事態が仮に生じたとしても、それが有意な影響にならないことを評価し確認しておくべきであるという考え方であり、原子力安全の多重防護の考え方に準拠している。この多重防護の思想に最も合致する安全確保のしくみとして、地層処分においては多重バリアシステムが検討されてきている。多重バリアシステムは、人工的に設けられる多層の安全防護系(人工バリアとよばれる)と、種々の安全防護機能を本来的にそなえている地層(天然バリアとよばれる)との多重の組み合わせによって構成されている。
高レベル放射性廃棄物は、ガラス質に溶融され金属容器に封入されて固化された状態(ガラス固化体とよばれる)で貯蔵される。処分にあたっては、このガラス固化体をさらにオーバーパックとよばれる容器に封入して埋設し、まわりの地層との空間にはたとえば粘土質の充填物(緩衝材とよばれる)をつめておくことが、現在のところ最も有効と考えられている埋設方法である。
この場合、人工バリアはガラス固化体、オーバーパック及び緩衝材という3つの層によって構成され、それらの物理的及び化学的特性により、埋設されたガラス固化体に地下水が接触することを防ぎ、さらに地下水がカラス固化体に接触したとしても、その中の放射性物質が溶出し移動することを抑制するものとして位置づけられている。また、天然バリアは、溶出した放射性物質を鉱物の吸着作用などによって地層中に長期間にわたって保持するとともに、地下水中の放射性物質を分散させ希釈させる効果があるものとして位置づけられている。
この多重バリアシステムの有効性に関しても、諸外国においていろいろな形で研究がなされてきており、その中には日本が参加した国際的協同作業として行われたものもある。動燃事業団は、これらの国際的成果を活用しつつ、多重バリアシステムの日本における有効性について、できるだけ包括的な検討を加えてきたところである。なぜならば、現在日本の地層処分に関する研究開発は、地質環境条件を特定することなく進める段階であり、多重
バリアシステムの有効性の研究についても対象とする地質環境条件をできるだけ広く考えて包括的な検討を行うことが求められているからである。したがって、多重バリアシステムの中でも、まず研究対象をより明確に規定し得る人工バリアに重点を置いて検討を行った。将来、地質環境条件を特定し得る段階に至った場合には、その場所の地質環境条件に最も適した多重バリアシステムを設計して行くことが重要であると考えられる。
地震作であり火山も多い日本においては、そのような特徴も念頭に置きつつ、地層処分に適切な地質環境条件に関し慎重に検討を加えて行くことが必要であるが、その具体的かつ定量的な検討は、基本的には立地選定に際して行われるものと考えられる。現段階では、その際の基礎資料と検討方法を整備する観点から、日本全国を広くとらえ地層処分に関わる地質や地質構造についての基本的知見をできるだけ体系的に整理することが求められている。
原子力委員会放射性廃棄物対策専門部会は、1989年12月の報告書の中で、地層処分の研究開発計画は、地質環境条件の調査研究、処分技術の研究開発及び性能評価研究という3つの領域に分けて行うこととしており、本報告書もそれらの3つの領域から構成されている。
地質環境条件の調査研究は、地層処分の前提となる日本の地質環境とその長期的な安定性についての知見を全国的な視野で捉えて整理し、処分技術の研究開発及び性能評価研究に資することを目的としている。その調査研究にあたっては、対象となる地域や岩石の種類を特定することなく広く捉える観点から、これまでに学術分野において蓄積されてきている情報やデータを中心に整理し体系化を図るとともに、動燃事業団が、既存坑道等において地層科学研究の一環として行っている研究の成果も活用した。
処分技術の研究開発は、人工バリアと処分施設に必要な技術を評価し、工学的な観点から地層処分概念の有効性を確かめることを目的としている。このために、まず人工バリアの設計、製作及び施工に必要な要素技術、次に処分施設の設計、建設、操業及び閉鎖に必要な要素技術に関する検討を行った。
性能評価研究については、地層処分の安全性に関わる性能評価の中でも、特に多重バリアシステムの有効性に関する評価が重要であることから、それを中心に検討を行った。多重バリアシステムの性能評価研究は、適切な地質環境条件の下に構築された多重バリアシステムが、所期の性能を長期にわたり維持し得るかどうかを科学的に確かめることを目的としている。評価研究に際しては、ガラス固化体から溶出した放射性物質が地下水を介して人間の生活圏に至るという仮説的な想定の下に、まずこれに関与する種々の現象を抽出し、それらを解析するモデル体系を構築した。次いでそのモデル体系を用い、地質環境条件の調査研究や処分技術の研究開発の成果を活用しつつ解析を行い、多重バリアシステムの性能を例示的に評価した。
1. 地質環境条件の調査研究 地層処分の観点から地質環境の構成要素の特性及び地質環境の安定性に関する調査を行い、処分技術の研究開発及び性能評価研究に資するために、まず、日本の地質と地質構造に関する知見を整理し、日本列島を構成する要素として岩石、地下水及び変質作用による生成物を挙げ、それらの産状及びに鉱物学的、地球化学的及び水理学的特徴を整理した。また、処分場の立地条件を考えるうえで留意する必要があると考えられる地下資源の存在についてもそのとらえ方を整理した。さらに、地層処分の観点から必要とされる深地層の地質環境データを、できるだけ精確に把握するための調査技術や計測技術に関する開発の状況について調査した。地質環境の長期的な安定性に関連する主要な自然現象として、地震活動、断層活動、隆起・侵食、火成活動、気候変動及び海面変化を取り上げ、それらの過去及び現在における発生や地質環境への影響の程度に関する調査研究を行った。
(1) 日本の地質環境
日本列島の地質を、古生代〜古第三起の地層群とその広域変成岩、カコウ岩類と流紋岩類、新第三起の地層群、第四紀の堆積層及び第四紀の火山岩類という5つの地質単元に分類し、各単元ごとに地質学上の知見を整理した。
日本列島を構成する主な岩石を、火成岩、堆積岩、変成岩、火山砕屑物及び火砕岩に区分して、それらの鉱物学的及び化学的特徴並びに分布と産状を整理した。さらに、処分技術の研究開発や多重バリアシステムの性能評価研究に必要な岩盤物性を文献調査などによりとりまとめた。
日本の地下水については、水理・水文学的及び地球化学的な観点から基礎的な特徴を整理した。文献調査により得られた透水係数の測定データからは、第四紀堆積層を除く固結した岩石に関する限り、地表から数100m以深にかけて透水係数が徐々に低下する傾向が見られた。また、地下水水質の測定データからは、隆水起源と考えられる地下水の全体的傾向として、数100m以深において溶存成分濃度が増し、Na+‐HCO3-型の水質となること、温泉等を除いた地下水では、pHがほぼ5〜10の範囲にあることなどが示された。さらに、事例的な調査からは、深度165mの新第三紀堆積岩とその下位のカコウ岩との境界付近から得られた地下水の酸化還元電位が−300mVであるという結果を得た。
日本における風化作用、続成作用及び熱水変質作用による生成物(鉱物)については、地下水水質の変化や吸着の研究に必要な鉱物学的及び化学的特徴並びに分布と産状を整理した。
地質環境の諸特性を高い精度で把握するためには、既存の調査技術を充分に活用することに加えて、新たな調査技術及び計測技術が必要である。特に、従来の地下の調査技術と比べより低透水性の領域における水理特性や、地下深部において充分な還元状態にある地下水の水質を、より精密に測定するためには新たな技術が必要である。
地層科学研究の一環として、ボーリング孔を利用して地下水流路となるような地質構造などを把握するための物理探査技術、低圧注入微流量測定が可能な水理試験装置、及び原位置地下水の不活性被圧状態での採取が可能な地下水サンプラーを開発し、また、多区間での水理計測と地下水採取ができるシステム、並びに原位置でのpH、酸化還元電位、間隙水圧及び透水係数の測定や採水が可能なシステムについて、諸外国で実用化されている装置の日本の地質環境に対する適用性を検討した。これらの成果は今後の調査に活用することが可能である。
(2) 地質環境の安定性に関連する主な自然現象の特徴
地震活動は地下空洞などに影響を与える可能性が考えられるが、地下百数10m以深での地震観測の結果などをみると、地震動が地質環境に及ぼす影響は地表よりも小さいことが確認されている。
断層活動は、岩盤の変位や破砕などにより周辺の地質環境に影響を与える可能性がある。第四紀に活動したと考えられる断層(活断層)について活動状況を整理した結果、日本の活断層の平均変位速度はほぼ0.01〜10m/1,000年の範囲にあり、大規模な変位の断層は複数回の活動により生じたもので、1回の活動による変位量は数10cm〜数m程度であるといえる。新たな断層の発生の可能性については、規模の大きい活断層を対象に地質構造、応力状態や周辺の既存の断層の形態及び分布を詳細に調査することによって検討することができると考えられる。
隆起・侵食は長期的には地質環境の安定性に影響を与える可能性がある。第四紀における隆起量は地形学的、地質学的手法により推定されており、それによれば、日本においては多くの地域で0.5〜1mm/年であり、山地部で1mm/年以上の地域がある一方、平野部、盆地及び丘陵部では0.5mm/年以下である。また、主要な臨海平野は沈降地域となっている。最近の水準測量による日本の上下変動量もほぼ−10〜+5mm/年の範囲にある。現在の平均的な侵食速度は、山地部において0.1〜1mm/年程度と推定されており、平野部においてはそれ以下と推定されている。長期間を考慮した場合の隆起・侵食の大きさは多くの地域でせいぜい1m/1,000年である。
火山の噴火、マグマの貫入、熱水作用などの火成活動に関しては、たとえば日本列島における火山活動の場は、大局的にみて過去1,200万年間大きく変化していない。また、個々の火山もほぼ同じ場所で繰り返し活動しているものが多い。
気候変動と海面変化は、主として地下水流動系を変化させる可能性のある現象と考えることができる。海面変化は地球全体にわたる現象であり、過去の70万年間において10万年ほどの周期で海進と海退が繰り返されてきた。長期的には、約10万年後に想定される最寒冷期に向かって、気候は寒冷化し海面は低下していくものと予測されている。
地質環境条件の調査研究を今後ともさらに推進していくためには、各分野における最新の知見を収集し、それを地層処分の観点から解析していくとともに、深層ボーリング及び深地層の研究施設での試験研究によって、地表から地下深部までの地質環境の諸特性や諸現象を的確に把握することができるデータを取得することが重要である。また、地質環境の安定性に関する調査研究については、事例研究を通して、自然現象の発生の規則性及び地域性並びにその影響の程度や範囲を明らかにしていくことが重要である。
2. 処分技術の研究開発 人工バリアに要求される性能と処分施設に期待される機能を確保し得る技術的方法を明らかにするために、人工バリアの設計、製作及び施工、並びに処分施設の設計、建設、操業及び閉鎖の要素技術に関する工学的検討を行った。
前提条件としては、日本における地層処分の基本的な考え方にもとづき、ガラス固化体を30〜50年間程度冷却のために貯蔵した後、地下数100m以深の地層中に処分するものとした。処分施設の検討においては、工学的な観点から地層を大きく結晶質岩系岩盤と堆積岩系岩盤に分けて研究を進めた。
人工バリアについては、地下水の接触を抑制し地下水による放射性物質の移行を妨げるという観点から要求される性能を念頭に置き、候補材料の基本特性、構造強度並びに現状技術を適用した製作及び施工法の検討を行った。処分施設については、施設の構成、地下空洞の安定性、放射性廃棄物の発熱による人工バリアや周辺岩盤の温度分布、並びに処分施設の建設、操業及び閉鎖技術とこれらの施工手順について検討し、現状技術の適用性の評価と研究開発課題の抽出を行った。
なお、現段階においては、地層処分の安全性に関する技術的検討を加えることに主眼を置き処分技術の検討を行った。人工バリア及び処分施設の工学システムとしての最適化に関する詳細な検討は今後の課題である。
(1) 人工バリアに関わる検討
人工バリアの構成要素のうち、特にオーバーパック及び緩衝材についての検討を行った。
オーバーパックについては諸外国の例も参考にして、ガラス固化体中の放射性物質が充分減衰するまでの約1,000年の期間、健全性を維持することを前提とし、候補となる材料について耐食性、機械的強度、製作加工性等の比較検討を行った。その結果、オーバーパックの材料としては、炭素鋼、チタン、銅等が有望であるが、腐食挙動の評価が比較的容易であり、機械的強度及び製作加工性の要件も満足しやすく、また周囲の化学的雰囲気を還元性とする効果も期待できることから、第一に研究すべき材料として炭素鋼をとりあげた。
炭素鋼オーバーパックの腐食に関しては、地下深部における地質環境条件を考慮して腐食量を評価した。また、外圧に対する強度を確保するのに必要な厚さについて深部地下1,000mの岩盤応力を保守的に設定し、これを評価した。その結果に基づいて、一つの例として肉厚30cm(うち腐食代5cm)の実寸大炭素鋼オーバーパックの試作を行い、製作技術の予備的検討を行った。その結果、基本的には現状技術とその延長線上の技術で充分対応可能であるという見通しが得られた。なお、肉厚30cmの炭素鋼オーバーパックについてしゃへい計算を行った結果、充分な自己しゃへい性を有することが示された。
緩衝材については、長期に及ぶ地下水の透水抑制機能、放射性物質の移行遅延機能、化学的緩衝性、熱伝導性、オーバーパックの支持耐力、応力緩衝性等が要求されることから、低透水性、高膨潤性、高吸着性等の性質をもつベントナイトを有力な材料として検討を行った。ベントナイトについて物理的及び化学的特性を評価した結果、適切な密度に圧縮したベントナイトは、上記の緩衝材に要求される性能を確保し得ること、また、約100℃以下では熱変質も無視でき、長期の安定性を期待し得る見通しが得られた。
これらの結果をもとに、廃棄体(オーバーパックに封入されたガラス固化体)の設置方式として代表的な坑道横置方式と処分孔堅置方式について、建設及び操業の作業性を考慮して緩衝材の厚さなどを検討した。
今後は、個々の要素技術の信頼性の向上を図るとともに、仕様の合理化や高度化を行い、さらに地圧や地震などに対する挙動の検討を行っていく必要がある。
(2) 処分施設に関わる検討
処分施設については、ガラス固化体の発熱による人工バリア材料への熱的影響の観点からの解析を行い、廃棄体の埋設密度の検討を行った。その結果、ガラス固化体の発熱による人工バリア及び周辺岩盤の温度上昇については、廃棄体の埋設密度を調整することにより制御でき、緩衝材の熱変質に対する許容温度を諸外国の例も参考にして約100℃とした場合、廃棄体の埋設を約80〜100m2に1本とすればよいことが明らかになった。また、地下深部での空洞安定解析を行い、結晶質岩系岩盤及び堆積岩系岩盤それぞれについて坑道支保の程度を評価するとともに、建設及び操業の作業性を考慮して坑道断面や処分区画について検討を行った。
今後は、より信頼性の高い設計手法の確立や経済性を含めた処分施設の詳細な検討が必要である。
3. 多重バリアシステムの性能評価研究 多重バリアシステムの性能を評価するためには、地下水の存在を前提とし、ガラス固化体から溶出した放射性物質が地下水を介して人間の生活圏へ至るという過程(一種の想定であり、地下水シナリオとよぶ)について解析することが重要である。そこで、地下水シナリオに関連する種々の現象についてモデルを作成し、多重バリアシステムの性能の解析を行うことができるようにした。次いで、この解析モデルを用いて、地質環境に関する広域の地下水流動及び地下水の地球化学的性質、人工バリアを含む人工バリア近傍の領域(ニアフィールドと呼ばれる)における熱、応力、水理及び地下水の地球化学的性質、オーバーパックの腐食挙動とガラス固化体からの放射性物質の溶解速度及び溶解度、人工バリア中の移行並びに天然バリア中の移行について解析を実施し、人工バリア及び天然バリアの性能評価を例示的に行った。
(1) 地質環境条件の解析
処分場近傍の水理学的条件は、広域地下水流動解析を行うことによって導いた。すなわち、まず、日本の地形データにもとづき、標高、斜面の勾配、平野の規模などをパラメータとした仮想的な2次元断面地形を考え、水理学的境界条件や断層等の存在による動水勾配への影響について解析を行った。さらに、地層科学研究の一環として行われた実在する地域を対象とする3次元の地下水流動解析例も参考にして、それらの結果からニアフィールドの水理条件及び天然バリア中の放射性物質の移行を解析するうえで必要な動水勾配の条件を充分な安全裕度を見込んで導いた。
地球化学的条件については、深部地下水に関する分析例が限られていることや幅広い日本の地質環境を考慮した解析を行う必要があることから、地下水の水質形成に関与する地球化学プロセスについてモデル化を行い、性能評価上重要な深部地下水の化学的性状に関しその基本的性質を把握するというアプローチをとった。すなわち、地球化学コードを用いた平衡論にもとづく解析によって、pH、酸化還元電位、イオン濃度などを計算し、深部地下水を降水系高pH型、降水系低pH型、海水系高pH型及び海水系低pH型の4種類の還元性地下水モデルに分類したうえ、それらの4種類のモデル地下水を、ニアフィールドにおける地下水の地球化学的特性及び天然バリア中の核種挙動を解析するうえでの基本的条件として用いた。
(2) 人工バリア内の物理的・化学的条件の解析
ニアフィルードの水理解析を行った結果、緩衝材が
極めて低透水性であるため、緩衝材中の物質移動メカニズムは、拡散によって支配されることが明らかとなった。
深部地下水の化学的性質が、人工バリア材料と反応することによって変化するプロセスに関して解析を行い、オーバーパックの腐食並びに放射性物質のガラス固化体からの溶出や緩衝材中での吸着の条件となる地下水組成を導出した。人工バリアに侵入した地下水は緩衝材であるベントナイトと反応する。このとき、ベントナイトの空隙中に取り込まれている酸素や二酸化炭素が地下水中に溶解するが、それらはベントナイト中の鉱物により比較的短い期間で消費されることが解析によって示された。その後、地下水はベントナイト中の鉱物と反応した後にオーバーパックの主要な腐食生成物と平衡に達することを想定し、ガラス固化体の表面に最終的に到達する地下水の化学特性を地球化学コードを用いて解析した。この結果、地下水の化学的特性は、人工バリア材との反応前に比べ高pH及び低酸化還元電位側に変化することが示された。
(3) オーバーパックの腐食挙動に関する解析
ベントナイト中に取り込まれた酸素はベントナイトに含まれる鉱物により比較的早期に消費されることが想定されるため、本来炭素鋼オーバーパックの腐食は進行しにくいものと考えられるが、性能評価上はこの酸素がすべて腐食に寄与するものと仮定して浸食深さを評価した。また、酸素が消費された後の還元性環境下での腐食速度を、地下水の化学的条件を考慮した腐食試験結果をもとに評価した。酸素以外の腐食性物質としてバクテリアによる硫黄化合物の還元物質の影響も考慮し、これらの腐食形態のすべてが働いて腐食が進行するものと仮定して炭素鋼オーバーパックの腐食速度を算出すると、32mm/1,000年の値が得られた。
(4) ガラス固化体からの溶出に関する解析
オーバーパックの健全性が喪失した後、人工バリア材との化学反応を経た地下水がガラス固化体と接触すると仮定し、ガラス固化体の長期的溶解速度及び性能評価上重要な元素の溶解度を評価した。地下水に難溶性の物質の溶解度は、ガラス固化体表面の変質層によって支配されるものと考えられ、地球化学コードを用いて算出した。その結果、人工バリア材との化学反応を経た4種類のモデル地下水に対して、ほとんどの重要元素の溶解度は一様に低く抑えられることが示された。一方、可溶性元素に関しては、実験室研究とモデル解析をもとに評価したガラス固化体の長期的溶解速度にもとづいて、その溶解速度を求めた。これらの溶解度や溶解速度を人工バリア中の移行解析に用いた。
(5) 人工バリア中の移行解析
以上の解析結果をもとに、人工バリア中の放射性物質の移行解析を行った。移行モデルにおいて考慮したプロセスは、拡散による緩衝材中の物質移動、放射性物質の緩衝材への吸脱着、溶解・沈殿反応、及び放射性崩壊である。これにより人工バリアから天然バリアへの移行率を算出した。この移行率に影響を及ぼすと考えられる環境側の最も重要な因子は地下水の化学的性質である。4種類のモデル地下水に対して移行率を評価したところ、ほとんどの元素に対し地下水の化学的性質によってその結果に著しい違いは生じないことから、人工バリアの性能は、地下水の地球化学的条件がある程度変わっても大きく変化することなく保たれる可能性があることが明らかになった。
(6) 天然バリア中の移行解析
天然バリアにおける地下水の移行経路の微視的な特徴に着目して、地質媒体を亀裂性媒体と多孔質媒体とに大別した。このうち、亀裂性媒体については、放射性物質は周囲の鉱物に吸着されながら卓越した亀裂中の地下水の流れによる移流及び分散によって移動すると同時に、その周囲のより微細な岩体母相中
の空隙へ拡散していくものとしてモデル化を行った。一方、多孔質媒体においては、比較的均質な空隙分布を持つ連続体であることから、均質媒体中の移流、分散及び吸着によって放射性物質の挙動をモデル化した。
解析においては、各モデルの入力パラメータ値の取り得る範囲を水理条件の解析結果や現状の調査データー等にもとづきできるだけ広く設定して、それぞれの地質媒体での放射性物質の移行遅延効果についての感度解析を行った。このような解析によって、動水勾配、透水係数、空隙特性等の各媒体特性、放射性物質の吸着特性に対する天然バリアでの移行遅延効果の感度、並びにそれらの効果が有効に作用する範囲や条件を明らかにした。その結果、天然バリアとして充分な性能を有する場合には、人工バリア近傍の地層の保持能力によって地下水の環境安全性を確保できる可能性があり、この点から、ニアフィールドの地質環境条件をできるだけ精確に把握していくことの重要性が示唆された。
性能評価研究における今後の課題は、各解析モデルの検証と信頼性の高いデータの整備である。そのためには、深地層の環境を模擬し、かつ制御できるモデル装置を用いた室内試験や深地層の研究施設での試験研究が重要である。
原子力委員会の方針に従い、動燃事業団が進めている高レベル放射性廃棄物の地層処分に関する研究開発について平成3年度まで成果をとりまとめた。その際、地層処分の安全性にとって最も重要な地下水シナリオを中心課題とし、多重バリアシステムを基本とした地層処分概念の現段階における技術的有効性に関する総合的な検討を行った。
検討にあたっては、地質環境条件の調査研究、処分技術の研究開発及び性能評価研究という3つの研究領域を設定し、各領域における研究開発の成果から地層処分の技術的有効性に関する総合的評価を試みるという体系的アプローチをとった。
その結果、今後のさらなる研究開発と調査によって、地質環境条件をより精緻に把握するとともに技術の高度化や解析の詳細化などを図り、より信頼性の高い評価を行っていく必要があるものの、人工バリアと処分施設の設計や施工等に必要な技術については、基本的に現状技術が適用できること、多重バリアシステムの性能については、人工バリアの性能を評価するための解析手法を中心に包括的に整備できたこと、また、変動幅を考慮しつつモデルとして想定した地質環境条件の下に例示的に解析したところ、人工バリア及び処分施設を地質環境条件に対応して適切に設計し施工すれば、その安全確保のための性能を長期的に保持し得ることが明らかになった。
今後とも、各分野の専門家の指導及び各界の理解と協力を得ながら、計画的に研究開発を進めていく予定である。
資料4
日本原燃(株)六ケ所再処理・廃棄物事業所における
再処理の事業の指定について(答申) 3原委第63号
平成4年12月15日
内閣総理大臣殿
原子力委員会委員長
平成3年8月22日付け3安(核規)第574号(平成4年7月16日付け4安(核規)第451号及び平成4年11月18日付け4案(核規)第780号をもって一部補正及び一部修正)をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第44条の2第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認める。
資料5
原子力国際問題等懇談会構成員の変更について(案)
1992年12月22日(火)
原子力委員会
1. 原子力国際問題等懇談会の構成員を別紙のとおりに改める。 2. 上記に伴い、所要の手続きを取ることとする。 以上
原子力国際問題等懇談会 | |
| 前頁 | 目次 | 次頁 |