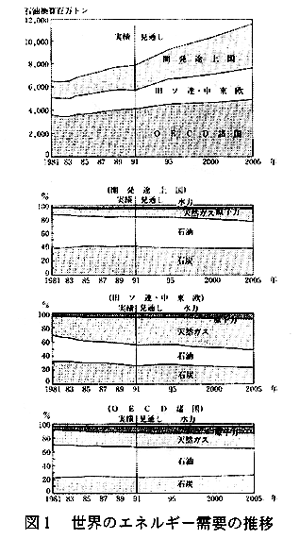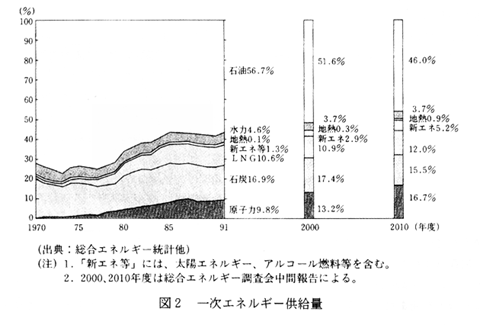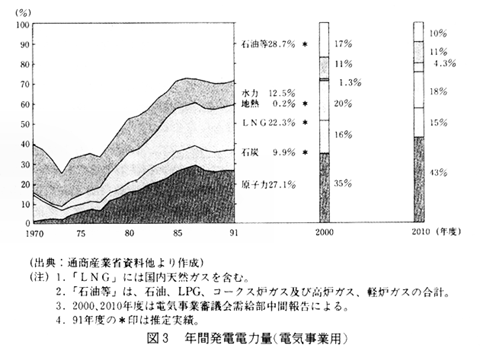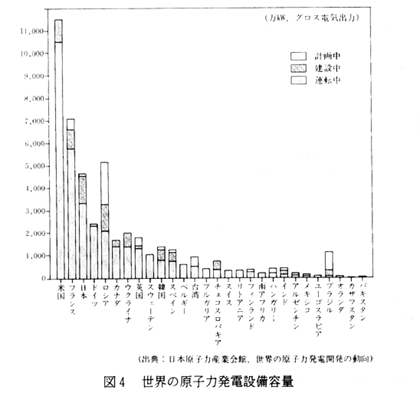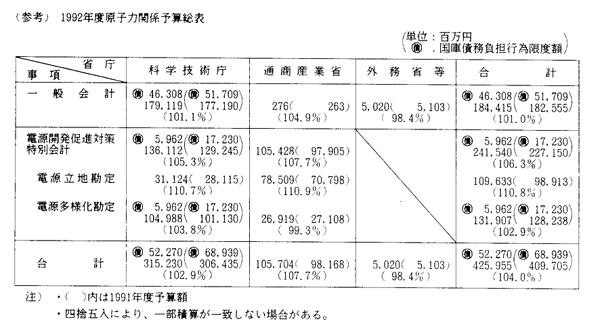| 前頁 | 目次 | 次頁 |
|
委員会の決定等 平成4年原子力白書 平成4年10月
原子力委員会
はじめに 1. 1991年12月のソ連の崩壊により、40年以上にわたり国際情勢の基調をなしてきた東西対立は名実ともに終結し、それに伴い、原子力をめぐる状況も大きく変化している。このような中、1991年より、米国とロシア等の間で、核兵器の大幅な削減合意がなされてきているが、旧ソ連において、核兵器の解体によるプルトニウム・高濃縮ウランなどの核物質の拡散や核兵器関連技術・人材の流出が懸念されている。また、ソ連の崩壊等は旧ソ連・中東欧地域の原子炉に関する情報量を多くし、西側諸国はその安全性に関する懸念を強めることとなった。さらに、イラク、北朝鮮をめぐる動向等は国際原子力機関(IAEA)の保障措置の整備・強化の重要性を認識させた。 2. 一方、世界のエネルギー需要は増加の一途をたどってきており、中長期的には、石油等について供給制約が考えられている。また、先の湾岸危機は、大きな経済的混乱を招くことはなかったものの、我が国のエネルギー供給構造の脆弱性を再認識させた。さらに、地球環境問題への対応の観点からも、供給安定性、経済性、環境影響面で優れた原子力の開発利用の推進の必要性が認識されている。 3. 我が国においては、原子力発電を中心とする原子力開発利用は、着実に進展しており、1991年度において、総発電電力量(電気事業用)の27.1%を原子力による発電によって賄っている。また、我が国が長期にわたって原子力発電を推進し、エネルギー供給の安定化を図る上で極めて重要な自主的な核燃料サイクルについても、青森県六ヶ所村において、その計画が着実に進展している。さらに、原子力の発電以外の用途においても、放射線利用の分野において、医療、農業、工業等国民生活に定着してきており、このように、原子力開発利用は、我が国の経済発展、国民生活の向上に大きく寄与している。 4. また、核兵器の拡散や旧ソ連・中東欧地域の原子炉の安全性などに対する懸念が高まる中、原子力の開発利用を厳に平和利用に限り、国際的にも保障措置に積極的に貢献し、原子力発電所の運転管理等で優れた実績を有する我が国は、信頼性のある核不拡散体制の維持・強化に向けた一層の貢献と旧ソ連・中東欧地域を含めた原子力発電の安全性向上に向けた重要な役割を果たすことが求められている。 5. このような状況の下、原子力委員会は、本書において、国際的な原子力をめぐる状況を概観し、我が国における原子力平和利用のこれまでの経験を踏まえた考え方を述べるとともに、世界のエネルギー需給の状況、原子力の安全確保、各種研究開発など原子力開発利用をめぐる現状を整理し、今後の課題についても記述した。 第1章 変貌する国際情勢と我が国の立場 1. 核兵器の不拡散等をめぐる国際情勢と原子力 (1) 旧ソ連をめぐる動向
① 冷戦の終了と核軍縮の進展
米ソ両大国間の冷戦が終了し、新たな世界平和の秩序が模索されている。ソ連に関しては、アルマ・アタにおいて、グルジア共和国を除くソ連の11共和国が「独立国家共同体(CIS)」の創設に合意し、関連の文書に調印した。さらに、12月25日にはソ連大統領が辞任し、ソ連は崩壊した。その後、戦略核兵器の存在するベラルーシ、カザフスタン、ロシア、ウクライナの各国と米国の間で、1992年5月23日にSTARTの批准に向けた議定書が調印され、旧ソ連の核兵器の不拡散に関する条約(NPT)上の核兵器国としての地位は、ロシアが継続したと考えられる。START調印により、START発効後7年間で戦略核弾頭数が大幅に削減されることとなった。また、1992年2月1日、6月17日に、米露両大統領が会談し、今後2003年(早ければ2000年)までに双方の戦略核弾頭数を約3分の1に削減すること等が合意された。
② ソ連の崩壊と核拡散問題
旧ソ連においては、核軍縮に伴う核兵器関連の開発停止に加え、市場経済への移行に伴い、物価の上昇等経済的、社会的な混乱が見られる。このような状況の下、これまで厳格に管理されてきた核物質、核兵器関連技術・人材の流出による核拡散が懸念されている。
1992年7月7日に発表されたミュンヘン・サミット政治宣言においても、核兵器の廃棄の結果生じる核物質の平和利用を確保するためのロシアの努力を支援することが確認されている。また、1992年8月、米国は、核兵器の廃棄の結果生じる高濃縮ウランの民生用原子炉燃料への転換等に関するロシアとの協定に署名したなどの大統領声明を発表した。
また、核兵器関連人材の流出については、優秀な科学者・技術者が核兵器開発の疑念のある国等へ転出する可能性も懸念されることから、その流出防止が必要である。このため、日本、米国、EC、ロシアにより、旧ソ連の大量破壊兵器関連の科学者・技術者等の能力を平和的活動に向ける機会を提供することを目的とした「国際科学技術センター」を設立する協定の作成交渉が行われている。
(2) 強化される核不拡散体制
① 核不拡散をめぐる最近の動向
(イラクをめぐる動向)
イラクは、NPTに基づき国際原子力機関(IAEA)との間で保障措置協定を締結しているが、秘密裏に電磁法によるウラン濃縮及びプルトニウムの分離に関する研究を行っていたことが判明した。国連及びIAEAは、これらの核物質を押収するとともに、関連施設の破壊、無力化を行った。
(北朝鮮をめぐる動向)
北朝鮮は、核兵器開発につながる活動を行っているという疑惑が世界的に持たれていたが、1992年1月IAEAとの間で保障措置協定を締結、同年4月9日批准した。その後、1992年5月からIAEAの査察が行われている。また、世界的に注目されていた寧辺の放射化学実験施設については、完成すれば再処理プラントとみなすことができるとのIAEAの見方もあり、平和利用の観点だけからは説明できないことに加え、韓国との間で再処理施設を保有しない旨を表明した「朝鮮半島の非核化に関する共同宣言」にも違反するものとして国際的な懸念が持たれている。
(NPT締結国等をめぐる最近の動向)
1991年7月から現在までに南アフリカ共和国、リトアニア、ラトビア、エストニア、中国、スロベニア、フランスがNPTを締結し、すべての核兵器国がNPT締結国となるとともにNPT締結国は150か国となった。
また、1991年12月にはブラジル・アルゼンチン・IAEA共同保障措置協定が署名され、ブラジル、アルゼンチンにおけるすべての原子力活動に係る核物質を対象として、IAEA及び核物質計量管理機関が共同で保障措置を適用することになる見込みである。
② 核不拡散体制の維持・強化の動向
(保障措置の信頼性に対する懸念)
NPTにおいては、非核兵器国はIAEAとの間に保障措置協定を締結してIAEAによる保障措置を受け入れること等が規定されている。保障措置は核不拡散を確保する上での重要な担保手段であるが、イラクの動向等を背景に核不拡散体制の強化が図られることになった。
(保障措置の強化に係る動向)
現在、IAEAにおいて保障措置の整備・強化に関する検討が行われている。1992年2月に開かれたIAEA理事会においては、IAEAが未申告施設に対しても査察(特別査察)を実施できることが改めて確認されたほか、核施設の設計情報の提出段階を早めること、核物質と原子力資機材の輸出入に関する情報のIAEAへの提供を各国が自発的に行うことが合意されている。
加えて、ミュンヘン・サミット政治宣言においても、今後の原子力協力に当たっては、NPT又はこれと同等の既存の国際約束への加入を条件とするとともに、1992年4月に原子力供給国グループにより合意されたとおり、原子力専用品の供給に当たってはIAEAのフルスコープ保障措置(すべての平和的原子力活動に係るすべての核物質に適用される保障措置)の採用を条件とすることになろうとの記述があり、核不
拡散の手段として保障措置の重要性が指摘されている。
なお、保障措置の整備・強化の実施に際しては、保障措置そのものの合理化も不可欠であることから、IAEA理事会において技術的側面から保障措置の合理化に関する検討を行うこと等が確認された。
(原子力供給国会議の動向)
さらに、原子力資機材・技術の拡散防止に向けて、原子力供給国会議(現在27か国が参加)が開催されている。
1992年3月の第2回の会議においては、①従来のロンドンガイドラインに加え、原子力・非原子力両分野に用途を有する関連品目を対象とする新たな規制制度を発足させ、核不拡散を一層強化すること、②全参加国が原子力専用品の輸出に際して受領国に対し原則としてフルスコープ保障措置の受け入れを条件とすること及び今後原子力資機材の供給能力を有する国に対して同条件の採用を働きかけること、③ロンドンガイドライン上ロシアを除くすべてのCIS諸国を非核兵器国とみなすことが合意された。
これらの合意事項の内、新たな原子力関連品目輸出規制制度の発足については、我が国が本制度の事務局機能を引き受けることが決定された。
(NPTの再検討に係る動向)
また、NPTについては、1995年に、条約が無期限に効力を有するか追加の一定期間延長されるかを決定することになっている。NPTは、核拡散防止のための世界で最も重要な体制であることから、ミュンヘン・サミット政治宣言においても「1995年の再検討会議におけるNPTの無期限延長はこの過程(核兵器等の拡散の抑制)における重要な一歩となるものであり、かつ、核兵器の軍備管理及び削減の過程は継続されなければならない」と述べられ、その継続が強く望まれている。
2. 強まる各国間の相互関係 (1) 旧ソ連・中東欧地域等に対する原子力安全に関する協力
(ソ連型原子炉の安全性に関する協力)
IAEAが発表した安全評価結果は、ソ連型加圧水型炉(VVER-440/230)の格納容器の欠如、緊急炉心冷却系が不十分である等の問題点を指摘している。また、ドイツは、旧東ドイツのノルト原子力発電所(VVER-440/230及びVVER-440/213)等の閉鎖を決定した。さらに、1992年4月には、IAEAはソ連型の黒鉛減速軽水冷却沸騰水型炉(RBMK)の安全性に関する意見交換、今後の協力プロジェクトの検討を行う技術委員会を開催した。
ミュンヘン・サミット経済宣言においても、ソ連型の原子力発電所の安全性は重大な懸念材料であり、運転上の安全性改善、安全性評価に基づく短期の技術的改善、規制制度の強化を含む多国間の行動計画の枠組みの中で旧ソ連・中東欧諸国に対する支援を行うことに加え、原子力安全条約の早期締結の必要性が述べられている。
また、1992年7月に開催された西側先進諸国24か国で構成されるG・24原子力安全ワーキンググループ(現G24原子力安全支援調整国際会議)において、ミュンヘン・サミットの経済宣言を受けて既存のG24調整対象国を旧ソ連諸国まで拡大し、より一層効率的にする新しい枠組みを作成することが決定された。
経済協力開発機構原子力機関(OECD/NEA)でも、中東欧地域の原子炉の安全性向上に関する協力についての検討が行われている。
この他、民間による国際協力として、世界原子力発電事業者協会(WANO)が、原子力発電所の交換訪問等の活動を行っている。
(原子力安全条約の検討)
また、1991年9月、IAEA主催の原子力安全国際会議において、原子力安全条約の作成について検討することが了承され、現在、IAEAの条約草案を策定するためのワーキンググループにおいて検討を行っている。
(欧州エネルギー憲章の採択)
また、旧ソ連・中東欧諸国のエネルギー部門を全世界的なエネルギー市場に統合し、エネルギー分野における民間部門の貿易及び投資を促進するための枠組みを創設することを目的として1991年12月、欧州エネルギー憲章が採択され、基本協定及び原子力等の分野の個別議定書の検討が1991年より行われている。
(2) 国際協力による研究開発の推進
1988年4月よりIAEAの支援の下で、日本、米国、EC、ソ連(ソ連崩壊後はロシア)の4極共同による国際熱核融合実験炉(ITER)に関する協力が行われており、工学設計活動に関する協定が1992年7月に署名された。工学設計活動は、1992年から約6年間の予定で研究開発等が実施され、我が国にも設計のための共同中央チームのサイトの一つが設置されることになっている。
また、高レベル放射性廃棄物に含まれる核種をその半減期、利用目的等に応じて分離し、有用核種の利用を図るとともに、長寿命核種の短寿命核種又は非放射性核種への変換を行う技術(核種分離・消滅処理技術)に関しては、情報交換を行う国際協力計画(通称オメガ計画)が我が国の提案によりOECD/NEAにおいて実施されており、現在、システムスタディの実施について検討を進めている。
(3) 開発途上国との協力
原子力委員会の主催で第3回アジア地域原子力協力国際会議が1991年に引き続き1992年3月に東京で開催され、近隣アジア諸国における地域協力の今後の具体的な協力テーマ及び協力計画についての意見交換が行われた。また、我が国は、IAEAの支援の下、「1987年の原子力科学技術に関する研究、開発及び訓練のための地域協力協定(RCA)」の締結により積極的に広くアジア・太平洋地域諸国との協力を行っている。
3. 原子力の平和利用と我が国の立場と役割 (1) 核不拡散体制をめぐる動きに対する我が国の立場と役割
① 核拡散に対する懸念と我が国の立場
核軍縮については、我が国としても、今後とも着実に進展することを歓迎する立場にある。
一方、その結果生ずるプルトニウム等の核物質は、核兵器保有国の責任において厳重に管理し、再び軍事利用されることのないように処置されることが基本であるが、旧ソ連において発生する核物質について、管理や平和利用等の面で国際協力の方策を協議し整えることは重要な国際的課題であり、我が国としても積極的に貢献していく立場にある。平和利用を進める上での不拡散努力を核軍縮から発生する核物質の不拡散努力へ広げることにより、原子力の平和利用の可能性を確実なものとする理解を求めていくべきである。
また、旧ソ連の核兵器関連人材等の流出防止のための「国際科学技術センター」については研究プロジェクトを提供するとともに、2,000万ドルの支援を行い、事務局への人材の派遣を行うことにより、ソ連の崩壊に伴う核拡散問題の解決へ向けた貢献を行っていくことが重要である。
NPTについては、歴史的に重要な1995年の同条約延長会議を迎えるに当たり、この条約の意義と原子力平和利用の重要性を世界が冷静に評価し、核不拡散努力によって核物質の軍事利用の懸念を払拭することにより、プルトニウム利用を含む原子力平和利用に対する国際的なコンセンサスが形成されるよう努力することが必要である。我が国としては、NPTのできる限り長期間の延長が円滑に行われるよう努力していくこととしており、核兵器国による核軍縮が一層進展することを期待している。また、イラクに対しては、核兵器開発の全容を明らかにすることと、核兵器開発能力を完全に放棄することを要請していくこととしており、北朝鮮に対しては、核兵器開発に関する疑念を払拭するよう求めていくこととしている。
②核不拡散体制の強化に対する我が国の役割
我が国はNPTを締結し、IAEAとの保障措置協定に基づき、国内のすべての原子力施設にIAEAの保障措置を受け入れており、非核兵器国の中で原子力施設が多いことから、IAEA査察業務の実に約25%が我が国に集中している。また、我が国は、1981年から「対IAEA保障措置技術開発支援計画(JASPAS)」を行うとともに、1986年度からはIAEAに我が国から特別拠出を行い、大型再処理施設に対する保障措置適用に関する検討を行うLASCAR(大型再処理施設保障措置)プロジェクトに積極的に参加するなど、IAEA保障措置の維持・強化にも積極的に貢献している。
さらに、IAEAにおける保障措置の整備・強化のための検討に当たっては我が国は積極的に貢献してきており、原子力供給国会議では、新たな原子力関連輸出規制制度の発足について、我が国が事務局機能を引き受けることを提案し、全会一致で決定された。
また、核兵器国の平和利用施設への保障措置の適用拡大については、非核兵器国との平等性を高める上で重要であり、IAEAの人的、財政的資源の許す範囲で徐々に実施に移していくことが実際的かつ肝要である。
保障措置の合理化に関しては、保障措置受入れ国の原子力活動の透明性、国内保障措置制度の実効性、機器の積極的な開発及び利用等を考慮して合理化を図るべきとの提案を我が国は行っており、今後も技術的な検討等に積極的に参画することとしている。
なお、我が国は、1988年11月に核物質の防護に関する条約に加入し、適切な核物質防護を行うこととなっているほか、米国等との間に2国間の原子力に関する協力協定を締結し、当該国から供給された核物質については、その防護を誠実に履行することを約束している。中でも、核物質の輸送に係る詳細な情報については、欧米諸国で極めて慎重に取り扱われており、国際的にも核不拡散の重要性が強く認識され、各国が万全の核物質防護を採るべきことに国際的な関心が高まっているという最近の情勢を背景に、政府は1992年4月に核物質の輸送に係る詳細な情報の取扱いは慎重を期すべきとの考え方の周知徹底を図った。
(2) 世界的な原子力の安全性向上に対する我が国の役割
原子力開発利用については、我が国は、これまで30年以上にもわたる研究開発、運転管理の実績を有している。また、原子力の開発利用は、安全の確保に万全を期すことを大前提として進められているところであり、これまで環境に影響を及ぼす事故を起こしたことはなく、9年間にわたり70%以上の高い設備利用率で運転し、安全確保実績を有している。
我が国はこのような実績に基づき世界の原子力発電の安全性向上に対しても積極的に貢献していく必要がある。我が国が旧ソ連・中東欧地域の原子力安全に対して貢献していく際には、当該地域の国々の原子力の安全確保のための自助努力を支援するとの基本的立場に立ち、長期的な観点からも資金や資材・技術を提供する等、我が国の原子力の安全確保のための努力が直接・間接に役立つ方法をその国々と二国間協力により見いだすとともに、他の西側諸国とも協調して、協力を実施していくことが重要である。
我が国としては、これまでIAEAにおけるソ連型原子炉の安全評価プログラムに対して特別拠出を行うとともに、旧ソ連・中東欧諸国の技術者・運転員の資質向上のための研修等を実施することとしているが、さらに、ミュンヘン・サミットで支持された「運転上の安全性改善」、「安全性評価に基づく短期の技術的改善」、「規制制度の強化」等の措置を含む行動計画の考え方に従って、効果的な協力策を展開していく予定であり、今後とも旧ソ連・中東欧諸国の原子力安全に関する協力について引き続き最大限の努力を払っていくこととしている。また、これらの協力を進めていく際、G24原子力安全支援調整国際会議(旧G24原子力安全ワーキンググループ)が調整を行うこととなっているが、このような調整メカニズムに対しても積極的に貢献していくことが望まれる。
IAEAに対しては、今後の具体的な安全対策を実施していく上での前提となる安全評価活動を円滑に展開していくことが期待されることから、我が国からも専門家の派遣を積極的に行うこと等によりこの活動を支援することが重要である。
(3) 原子力の平和利用の実施と牽引力
原子力は、少量の資源から技術によって大量のエネルギーを生み出すという他のエネルギーにない特長を有しており、その供給安定性と経済性が資源などの外的要因ではなく、主に技術の成熟度によって決定されることに大きな特長がある。よって、天然のエネルギー資源に乏しく、また、高度な技術力を有する我が国としては、増大するエネルギー需要という状況下で確固としたエネルギー供給基盤を築くためには、原子力開発利用の推進が極めて重要である。
このような準国産エネルギーとも位置付けることのできる原子力の特長を活かすためには、使用済み燃料を再処理して、回収されたプルトニウム及びウランをリサイクルし、核燃料として再利用する核燃料のリサイクルが不可欠である。
さらに、原子力は、環境面においても、地球温暖化の原因となる二酸化炭素等を発電の過程で排出しないという優れた特長を有している。
我が国においては、以上のような観点から、原子力を基軸エネルギーとして位置付け、核燃料リサイクル政策等に基づく原子力開発利用を積極的に推進している。この際、1991年8月には、必要な量以上のプルトニウムを保持しないようにすること等のプルトニウム利用に係る我が国の基本的政策を示すなど、我が国の原子力開発利用政策を内外に明らかにしてきている。なお、1992年秋頃のフランスからのプルトニウム輸送に当たっては、種々の核物質防護措置及び安全対策を講じ、本輸送が確実に実施されるように万全を期すこととしている。今後とも、我が国としては、核不拡散問題について国際的に疑念を招かないよう透明性に配慮するとともに、原子力平和利用を進める我が国の国際的責務として、前述したようにIAEA保障措置の健全な発展と世界の核不拡散体制の維持・強化に貢献していくことが重要である。
次に、原子力の利用に伴い発生する放射性廃棄物の処理処分対策の確立は、原子力によるメリットを享受している我々の責務である。放射性廃棄物の処理処分対策については、原子力利用を進めている我が国を含め世界各国の課題として積極的に取組がなされている。我が国においては、低レベル放射性廃棄物の陸地処分に関しては埋設施設が青森県六ヶ所村に建設中であり、適切な処理処分対策が円滑に進められている。また、高レベル放射性廃棄物の処理処分に関しては、研究開発について動力炉・核燃料開発事業団が中核推進機関となって実施中であり、一方、2000年を目安に設立される実施主体がこれらの成果等を踏まえ計画的に処分対策を実施していくこととしている。
また、我が国は、日本原子力研究所、動力炉・核燃料開発事業団等が中心となって、米国、ドイツ、フランス、英国などの原子力開発利用先進諸国と核融合、軽水炉、高速増殖炉、再処理、高レベル放射性廃棄物の地層処分、高温ガス炉等の多岐にわたる分野において研究協力、情報交換、人材交流等の二国間協力を行ってきている他、インドネシア、マレイシア、タイ、韓国、中国等と研究炉利用、放射線利用、安全研究、廃棄物処理処分、ウラン鉱資源調査等の分野で協力を行っている。今後もますます効率的な研究開発のため、国際協力を積極的に進めることが重要である。また、近隣諸国で原子力発電計画が検討されていることから安全性分野での協力も今後重要となってくるものと考えられる。
以上のような点をかんがみれば、原子力開発利用の実績を有し、科学技術立国を目指す我が国においては、我が国さらには世界のエネルギー需要の増大に対応して、安定的なエネルギー供給の確保等を目指して、今後とも原子力開発利用を積極的に推進し、欧米等の先進諸国とも協力しつつ、原子力平和利用の世界的な牽引国としての役割を果たしていくとともに、我が国の原子力開発利用政策に対する内外の理解を得ていくことが重要である。
第2章 内外のエネルギー情勢等と我が国の原子力発電、核燃料サイクル等の開発利用の状況 1. 原子力の社会的役割の増大 (1) 内外のエネルギー・電力の情勢と原子力
① 世界のエネルギー・電力の情勢と原子力
(エネルギー情勢)
世界の一次エネルギー需要は、1991年には経済が減速局面にあるため前年に比べ約1%と低い伸び率になっているものの、1983年以降エネルギー需要は増加の一途をたどってきている。国際エネルギー機関(IEA)によると、この傾向は将来にわたっても継続し、エネルギー需要は、1989年から平均年率2.4%で増加し、2005年には、89年に比べ約46%の増加が見込まれている。
地域別には、開発途上国のエネルギー需要増大が顕著であり、1989年から平均年率4.2%で増加し、2005年には、89年に比べ約93%もの増加が見込まれており、世界のエネルギー需要の3分の1を占めるまでになると見通されている。また、開発途上国における化石燃料への依存は変わらず、全世界における化石燃料需要の2005年までの増加分のうち、5割強は開発途上国によるものと見通されている。
一方、先進国におけるエネルギー需要は、経済成長の鈍化、省エネルギー対策の推進等により、1991年には1.4%の伸びにとどまっている。将来の見通しとしては、1989年から平均年率1.3%で増加し、2005年には、89年に比べ約23%の増加が見込まれている。今後、地球環境問題に対応するためにも、非化石エネルギー依存度をさらに向上させることが重要と考えられる。
また、旧ソ連・中東欧諸国のエネルギー需要は、1989、90、91年とマイナスの伸びであったが、IEAによると、市場経済への移行が迅速かつ混乱なく行われると仮定した上で、1989年から平均年率2.3%で増加し、2005年には、89年に比べ約44%の増加が見込まれている。
このように世界のエネルギー需要の伸びが見込まれる中で、供給には制約が考えられる。例えば、石油については北海、北米、旧ソ連等で供給能力の減少が見込まれ、中東産油国への依存度が高まると予想される。また、旧ソ連における政情不安や湾岸危機のような地域紛争に見られるような不確定要因による影響も世界的に懸念されている。
このような状況の下、エネルギー資源の地域分布状況に目を向けると、ウランはアフリカ地域に約33%、北米地域に約27%、オーストラリアに約23%と、政治的・経済的に安定した地域に比較的分散して産出している。
1991年6月に開催されたIEA閣僚理事会のコミュニケにおいても、原子力がエネルギー供給への貢献を認識するとともに、温室効果ガス排出の安定化にも貢献できることに注目し、さらに、原子力は一次エネルギー供給の多様化に必須の要素として、特に、原子力施設の安全運転、放射性廃棄物の処理処分及び新型炉の開発において持続的かつ強化された国際協力を奨励している。
また、1992年7月に開催されたミュンヘン・サミットにおいても、世界のエネルギー供給において、原子力発電が果たす重要な役割を認識するとの記述が経済宣言に盛り込まれている。
(電力需給状況)
世界の電力消費量の増加しており、特に、アジア地域の開発途上国における伸びが著しい。世界の発電電力量は、近年年率約4%という高い伸びで増加している。一方、電源構成の内訳を見ると、先進国においては原子力発電が着実に増加しており、旧ソ連・中東欧諸国においては依然として火力発電が大半の割合を占めている。開発途上国は比較的水力発電の割合が大きいが、火力発電が増大している。
② 我が国のエネルギー・電力の情勢と原子力
(エネルギー情勢)
1991年度の我が国のエネルギー需要(最終エネルギー消費)は、調整過程に入った景気を背景に伸びが鈍化し、原油換算で3.58億キロリットル、対前年度比2.7%の伸び率となった。これに対し、1991年度の一次エネルギー供給は、原油在庫の大幅な変動等により、原油換算5.31億キロリットルとなり、前年度比1.0%の低い伸びにとどまったが、石油の割合は、56.7%となり、依然として石油依存度は高く推移している。
一方、我が国は一次エネルギー総供給の8割以上を海外に依存しており、ほぼ全量を輸入に依存している石油に6割近くを依存している。さらに、輸入原油の約7割を中東地域に依存しており、エネルギーの安定供給確保を図ることが重要である。政府は、エネルギーの安定供給確保に加え地球環境問題に関して、エネルギー政策においても最大限の対応が必要であるという考え方に基づき、1990年10月「石油代替エネルギーの供給目標」を決定した。
(電力需給状況)
1991年度の総需要電力量は7,894億キロワット時、伸び率3.1%となった。部門別には、民生用需要は5.1%の堅調な伸びとなったが、産業用需要は、景気の減速感が広まり、1.7%と低い伸びとなった。また、最大電力の伸び率は2.9%の伸びとなっている。
今後の電力需要については、1992年度電力施設計画によると、総需要電力量は1990年度から平均年率2.4%で増加し、2001年度には9,886億キロワット時に達すると見通されている。
一方、発電電力量(電気事業用)の実績は、1991年度には7,831億キロワット時、伸び率3.4%となった。この中で、原子力発電は着実に増加しており、総発電電力量に占める割合は27.1%と7年間連続で25%以上を占めた。
(2) 地球環境問題と原子力
(地球環境問題)
近年、地球温暖化、酸性雨等の地球環境問題が大きくクローズアップされている。特に、地球温暖化については、国際的協調の下に取り組む重要課題として本格的な議論が行われている。
このような中で、原子力はエネルギー収支が高く、二酸化炭素、窒素酸化物等の温室効果ガスや硫黄酸化物、窒素酸化物を発電の過程において排出せず、地球環境問題を始めとする地球環境問題の解決に当たって重要な役割を果たすことが期待されている。
(国際的な取組)
このように地球環境問題の解決にも資する原子力の重要性が国際的にも認識されつつあり、近年のサミットにおいては「原子力発電は、エネルギー源の多様化及び温室効果ガスの排出削減に貢献する経済的なエネルギー源」として位置付けている。
(我が国の取組)
地球温暖化問題の解決に当たっては、省エネルギー、原子力を始めとした非化石エネルギーへの依存度向上等エネルギー政策の面からの積極的対応が不可欠である。我が国としては、二酸化炭素排出量を2000年以降概ね1990年レベルで安定化させることを目標とする地球温暖化防止行動計画を1990年10月に策定し、原子力等の導入等を推進することとしている。また、1991年7月に改訂されたエネルギー研究開発基本計画においても、原子力は中核的な石油代替エネルギーであり、地球環境問題への対応のためにも重要な役割を果たすものとして、その開発利用の重要性が強調されている。
さらに、技術開発の一環として、電子線を用いて硫黄酸化物や窒素酸化物等を除去する技術の開発が行われている。
2. 世界の原子力発電等の開発利用の状況 (1) 概況
世界における原子力発電所は、今回(1991年7月から1992年6月末まで)フランス1基、日本1基、合計2基が新たに運転に入った。原子力発電国は、ソ連の崩壊による各共和国の独立に伴い、28か国(地域)となった。1992年6月末現在で、418基が運転中で、原子力発電設備容量は3億4,155万キロワットになり、前回(1991年6月末)に比べ、186万キロワットの減少になっている。総発電電力量については、1991年実績では2兆91億キロワット時に達し世界の総発電電力量の約17%を占めた。これは約4億9,000万トンの石油に相当し、中東諸国全体の年間石油生産量(1990年実績約8億4,300万トン)の半分以上に相当する。
1991年は、米国のアルゴンヌ国立研究所(アイダホ)において、高速増殖炉EBR-Ⅰにより世界で初めて原子炉による発電が行われてから40年になる。また1992年は、米国で初めて原子炉による核連鎖反応が起こってから50年になる。以来、原子力発電は順調に増え続けてきたが、チェルノブイル原子力発電所事故後、一部の国では原子力政策の見直しが行われる等、原子力開発は停滞傾向が続いていた。しかし、原子力発電の役割及び必要性が再認識され、一部の国・地域では、原子力発電所プロジェクトが再開される等の動きが出てきている。
一方で、旧ソ連・中東欧諸国の原子力発電所の安全性への懸念が高まり、IAEAを中心に、ソ連型加圧水型炉(VVER-440/230)及び黒鉛減速軽水冷却沸騰水型炉(RBMK)の安全評価、安全性改善に関するプロジェクトが進められつつある。ミュンヘン・サミットでも、旧ソ連・中東欧諸国の原子力発電所に対する安全性向上のための支援を多国間の行動計画の枠組みの中で提供することを決定した。また、原子力安全条約の早期締結を目指すこととしている。次回の東京サミットにおいて、この行動計画の進捗状況が審査される予定である。
(2) 各国の状況
米国は、世界第1位の原子力発電設備容量を有し、1992年6月末現在、110基、1億501万キロワットの原子力発電所を運転している。1991年には、約6,126億キロワット時を原子力発電により発電し、総発電電力量の約22%を供給している。また、1991年の年間設備利用率の平均も過去最高の70.2%であった。
1991年2月、ブッシュ大統領は「国家エネルギー戦略」を発表した。同戦略においては、原子力発電について今後も積極的な活用を期待している。議会においては、同戦略とほぼ同趣旨の国家エネルギー安全保障法案が上院に、包括的エネルギー法案が下院に提出されており、これらの法案はそれぞれ、1992年2月上院本会議で、同年5月下院本会議にて、可決された。両法案の内容には若干の差異があるため、両院による統一法案作成に向けて調整が行われている。原子力規制委員会(NRC)は、1991年11月、原子力発電所の運転延長許可に係る最終規則を承認し、これにより現行40年の運転認可期間が20年を越えない範囲で延長可能となった。しかし、運転期限延長を求める申請の第1号として期待されていたヤンキーロー発電所は、経済的要因等により、1992年2月、閉鎖が決定した。
フランスは、1992年6月末現在、54基、5,760万キロワットの原子力発電所を運転中である。1991年には約3,149億キロワット時を原子力発電により発電し、総発電電力量の約73%を供給している。現在、6基の原子力発電所が建設中であり、そのうちパンリー2号機は1992年中に運転開始が予定されている。
政府は、1991年、エネルギー計画「エネルギー見通し2010年」を発表し、省エネルギー、原子力開発、エネルギー供給源の多様化という従来のエネルギー政策を再確認した。このような積極的な電源開発を基にフランスは、総発電電力量の約12%に当たる534億キロワット時をスイス、イタリア、英国、ドイツ等の国々へ送電している。
フランスは、高速増殖炉実証炉スーパーフェニックスを運転開始しているが、トラブルにより運転停止状態にあり、運転再開の準備が進められてきた。1992年7月、政府は、運転再開のためには安全性確保の実施と、安全性についての公聴会の開催等が必要として、運転再開の延期の決定を行った。
なお、ヨーロッパにおける高速増殖炉の開発については、欧州統合高速炉(EFR)計画が進められている。
ドイツは、1990年10月、東ドイツが西ドイツに統合され、新たにドイツ連邦共和国がスタートした。1992年6月末現在、21基、2,363万キロワットの原子力発電所が運転中であるが、そのすべてが旧西ドイツ分である。1991年には約1,400億キロワット時を原子力発電により発電し、総発電電力量の約28%を供給している。旧東ドイツのノルト原子力発電所1~4号機(VVER-440/230)は1990年に閉鎖が決定されていたが、5号機(VVER-440/213)も、1991年9月、安全性調査結果を受け閉鎖が決定された。また、6、7及び8号機も建設工事を進めないこととなった。
1991年12月、連邦経済省の「統一ドイツのエネルギー政策」が閣議決定され、原子力について、安定的な代替エネルギー源がない限り、引き続き電力生産における重要な役割を果たすことを指摘している。
カナダは、従来から自国の豊富なウラン資源と自主技術によるカナダ型重水炉(CANDU炉)を柱とした独自の原子力政策を一貫して採っている。1992年6月末現在、19基、1,390万キロワットのCANDU炉が運転中である。1991年には約801億キロワット時を原子力発電により発電し、総発電電力量の約16%を供給している。
オンタリオ州議会は1990年11月、新規電源の環境評価の終了まで、原子力の開発を一時停止を決定したが、建設中のダーリントン発電所は1992年から1993年にかけて1、3及び4号機が運転開始する予定である。
英国では、1992年6月末現在、ガス冷却炉(GCR)及び改良型ガス冷却炉(AGR)を中心に、37基、約1,316万キロワットの原子力発電所が運転中である。1991年には約620億キロワット時を原子力発電により発電し、総発電電力量の約21%を供給している。
現在、建設中・計画中の原子力発電所は、すべて加圧水型軽水炉(PWR)であり、その初号機サイズウェルBは順調に工事が進められている。サイズウェルBに続く、ヒンクレーポイントCについては建設計画が承認されたが、建設資金の承認については、1994年に予定される、新規原子力発電所計画の再検討作業が実施されるまで留保されている。
旧ソ連では、1992年6月末現在、48基、3,699万キロワットの原子力発電所が運転中で、1991年には約2,121億キロワット時を原子力発電所により発電し、総発電電力量の約13%を供給している。各共和国で運転中の原子力発電所は、主としてソ連型加圧水型炉(VVER)、黒鉛減速軽水冷却沸騰水型炉(RBMK等)である。各国の内訳は、ロシア31基、ウクライナ14基、リトアニア2基、カザフスタン1基である。
旧ソ連では、チェルノブイル原子力発電所事故後においても原子力発電を同国の重要なエネルギー源と位置付け、原子力開発を着実に進めていく方針は変わっていない。しかし開発は停滞ぎみであり、原子力開発の将来は不透明となっている。その一方、電力不足、環境問題等を背景に、ロシア、カザフスタン等の一部の地域の人民議会において、新規原子力発電所建設賛成の決議がなされるといった動きもある。
アジアにおいては、韓国では、1992年6月末現在、9基、762万キロワットの原子力発電所が運転中であり、1991年には約535億キロワット時を発電し、同国の総発電電力量の約48%を供給している。韓国動力資源部と韓国電力公社は、1991年10月に、長期電源開発計画を取りまとめた。同計画は、建設中・発注済みの5基を含めて18基を2006年までに開発し、2006年の原子力発電規模を現在の約3倍の2,320万キロワットとすることとしている。また、韓国原子力委員会は、1992年6月、「原子力研究開発中・長期計画(1992年~2001年)」を発表した。
台湾は、原子力発電所6基、514万キロワットの設備容量を有し、総発電電力量の約38%を賄っている。凍結されていた7、8号機目に当たる第4原子力発電所の建設計画は、1992年2月に建設再開を承認され、立法院も現在凍結中の準備予算への支出を承認した。7号機は2000年、8号機は2001年の運転開始が予定されている。
中国は、現在、3基の原子力発電所を建設しており、このうち同国で最初の原子力発電所秦山1号機については、1991年12月に初送電に成功した。1992年末に100%出力運転に到達する予定である。現在、建設中の3基に続き、今世紀中に更に5基の建設が計画されている。
インドネシアは、2015年までに700万キロワットの原子力発電所の建設を計画しており、1991年からはジャワ島中部で立地調査が開始された。
3. 我が国の原子力発電、核燃料サイクル、プルトニウム利用等の開発利用の状況 (1) 原子力発電
① 原子力発電の現状
我が国の原子力発電は、1992年9月末現在、運転中の商業用発電炉は41基、設備容量は3,323万9千キロワット、新型転換炉原型炉「ふげん」を含めると、42基、3,340万4千キロワットとなっている。これに建設中及び建設準備中のものを含めた合計は、商業用発電炉で53基、4,590万8千キロワット、研究開発段階発電炉を含めると、55基、4,635万3千キロワットである。
原子力発電は、1991年度末現在、総発電設備容量(電気事業用)の18.5%、1991年度実績で、総発電電力量(電気事業用)の27.1%を占め、主力電源として着実に定着してきている。また、1991年度の設備利用率は、73.8%で、1983年度実績で70%を超えて以来、9年間続いて70%台の高い水準で推移してきている。
② 原子力発電の経済性
平成元年度の通商産業省の試算結果では、発電原価は原子力発電が9円/キロワット時程度、石炭火力及びLNG火力発電が10円/キロワット時程度、石油火力発電が11円/キロワット時程度となっている。
③ 軽水炉技術の研究開発
我が国では、軽水炉の改良標準化計画を第1次から第3次まで実施してきた。これらの成果は、現在運転中又は建設中の在来型軽水炉の一層の改良に反映されるとともに、特に、第3次計画においては改良型軽水炉(ALWR)の開発が進められた。
また、1991年6月に総合エネルギー調査会原子力部会軽水炉技術高度化小委員会が取りまとめた報告書によると、今後の軽水炉技術の開発に当たっては、経験の蓄積を積極的に活用し、安全性の原則を再認識し、新しい知見・技術を取り入れていくことが重要とし、安全性確保の更なる取組として、故障・トラブル対策の高度化、ヒューマンファクターに係る対策の高度化、安全設計の高度化、静的安全性の可能性の追求及び廃炉対応の高度化を挙げている。
④ 原子炉の廃止措置
原子炉の廃止措置に関する技術開発については、1990年代後半に向けて技術の向上を図ることとしており、日本原子力研究所が動力試験炉(JPDR)をモデルとしてその研究開発に取り組んでいる。
また、1988年度に(財)原子力施設デコミッショニング研究協会が設立され、研究開発用施設の廃止措置に関する研究成果の蓄積・普及等を行っている。
(財)原子力発電技術機構においては、廃止措置技術のうち、炉内構造物切断技術、解体廃棄物処理技術等について確証試験を進めている。
電気事業者においては、原子炉の廃止措置費用について、発電を行っている時点で、引当金を積み立てる方式によって料金原価に算入することとし、1989年3月期決算から原子炉廃止措置費用引当金の計上を開始した。
(2) 核燃料サイクル
① 核燃料サイクルの事業化の推進
我が国の核燃料サイクルの研究開発については、動力炉・核燃料開発事業団及び日本原子力研究所を中心として進められてきたが、このうち、核燃料の再転換・成型加工については、既に民間における事業化が進んでおり、多くの実績を積み重ねている。
また、ウラン濃縮、軽水炉使用済燃料再処理、低レベル放射性廃棄物埋設等については、1992年7月に日本原燃産業(株)及び日本原燃サービス(株)の合併により設立された日本原燃(株)により事業化の進展が図られている。
ウラン濃縮施設については、1992年3月に一部の操業が開始された。低レベル放射性廃棄物埋設施設については、1992年12月の操業開始に向けて、現在建設が進められている。使用済燃料の再処理施設については、原子力委員会及び原子力安全委員会による審査中である。また、海外から返還される高レベル放射性廃棄物貯蔵施設については、1992年5月に着工した。操業開始は、1995年2月の予定である。
② ウラン濃縮
我が国におけるウラン濃縮の国産化については、動力炉・核燃料開発事業団が中心となってその研究開発を進めてきた。同事業団は200トンSWU(分離作業単位)/年の能力を有する原型プラントを運転中である。日本原燃(株)は、この成果に基づき、1992年3月に濃縮能力150トンSWU/年の規模で操業を開始した。今後、逐次増設し、最終的には濃縮能力1,500トンSWU/年の規模とする計画となっている。
動力炉・核燃料開発事業団は新素材高性能遠心機に関して、民間との協力により実用規模カスケード試験装置を1992年に建設し、1993年から運転を開始することとしている。
一方、ウラン濃縮に関する新技術としては、レーザー法及び化学法の研究開発が進められてきた。このうち、レーザー法については、日本原子力研究所及びレーザー濃縮技術研究組合が原子レーザー法について各種の試験を行っている。また、動力炉・核燃料開発事業団及び理化学研究所は、分子レーザー法の研究開発を進めている。なお、化学法については、旭化成工業(株)が研究開発を進めてきたが、現在研究開発活動を休止しており、今後の国内需給動向を踏まえて、将来の活動を検討するとしている。
このような新技術の研究開発の進展を踏まえ、ウラン濃縮懇談会は、1992年8月に(ア)遠心法については、六ヶ所濃縮工場の安定操業と経済性の向上を図る必要がある、(イ)原子レーザー法については、研究開発を継続し、平成10年頃に実証段階に進むべきか否かの評価検討を実施することが適当である。(ウ)分子レーザー法については、工学試験を継続し、原子レーザー法に係る評価検討の時期にそれまでの成果を評価検討することが適当である。化学法の開発は、十分な成果が得られたが、実証プラント建設については需給動向等を総合的に踏まえ、判断されるべきである。(エ)六ヶ所濃縮工場以降の国内濃縮事業規模の拡大等については、今後の検討を進めていくことが必要であるといった報告書を取りまとめた。
③ 軽水炉使用済燃料再処理
軽水炉使用済燃料の再処理技術の開発は、これまで動力炉・核燃料開発事業団を中心として行われてきた。同事業団の東海再処理工場は、順調に操業を行い、1991年度末までの累積再処理量は約609トンUに達している。
我が国で発生する使用済燃料の再処理については、同工場のほか、英国及びフランスに委託しており、1991年度末までには、軽水炉使用済燃料約4,200トンUが両国に運ばれている。
将来的には、国内の再処理需要については、東海再処理工場と、日本原燃(株)が計画中の青森県六ヶ所村の再処理工場により対応することとしている。また、国内の再処理能力を上回る使用済燃料は、再処理するまでの間適切に貯蔵・管理することとしている。
六ヶ所村の再処理工場については、1999年頃の操業開始を目指して建設する計画であり、現在、原子力委員会及び原子力安全委員会において審査中である。
④ 低レベル放射性廃棄物の処理処分
原子力発電所等において発生する低レベル放射性廃棄物の累積量は、1992年3月末現在、200リットルドラム缶に換算して約48万本分となっている。
低レベル放射性廃棄物の最終的な処分については、陸地処分及び海洋処分を基本的な方針としている。
このうち、陸地処分については、日本原燃が、1992年12月の操業開始を目指して、青森県六ヶ所村に低レベル放射性廃棄物を比較的浅い地中に処分する低レベル放射性廃棄物埋設施設を建設している。全国の原子力発電所から六ヶ所村の施設までの海上輸送については、原燃輸送(株)所有の「青栄丸」により実輸送に向けて準備が行われている。
また、海洋処分については、関係国の懸念を無視して行わないとの考えの下、慎重に対処することとしている。
使用済燃料の再処理、ウラン・プルトニウム混合酸化物(MOX)燃料の加工の過程で発生する、超ウラン(TRU)核種を含む放射性廃棄物については、原子力委員会放射性廃棄物専門部会は、1991年7月、「TRU核種を含む放射性廃棄物の処理処分に関する報告書」を取りまとめ、同報告書においては、TRU核種を含む放射性廃棄物の区分の考え方等、今後の処理処分の推進のための具体的在り方を示している。
(3) プルトニウム利用
我が国においては、ウラン資源の有効利用を図り、エネルギーの安定供給を確保するなどのため、使用済燃料の再処理により得られるプルトニウムの利用体系の確立が重要である。
原子力委員会核燃料リサイクル専門部会は、1991年8月に、「我が国における核燃料リサイクルについて」を取りまとめた。
この報告書においては、まず、プルトニウムの利用面について、ウラン資源の利用効率が高いなどの特長を有する高速炉(FBR)を、我が国のプルトニウム利用の基本と位置付けており、今後とも、その実用化を目指すとしている。また、我が国の原子力発電計画において、当面主流である軽水炉においてプルトニウム利用を進めることとし、それによって、エネルギー供給面で一定の役割を果たすとともに、併せて、FBRの実用化に向けて、実用規模の核燃料リサイクルに必要な技術、体制等を整備していくことが必要であるとしている。さらに、リサイクル体系の柔軟性を高める観点から、核燃料利用の面で融通性に富む新型転換炉(ATR)において、その特長を活かしつつ、プルトニウムの利用を進めることが適当であるとしている。
① 軽水炉におけるプルトニウム利用及び新型転換炉
我が国における軽水炉によるプルトニウム利用(プルサーマル)は、電気事業者を中心に進められており、既に、少数体規模実証計画が実施されているほか、段階的かつ実用路への導入を図る計画を進めていくこととしている。
新型転換炉については、動力炉・核燃料開発事業団により原型炉「ふげん」が順調に運転されている。
また、これに続く実証炉については、電源開発が2001年3月の運転開始を目指して、青森県大間町において、建設準備を進めている。
② 高速増殖炉
高速増殖炉(FBR)は、発電しながら消費した以上の核燃料を生成する画期的な原子炉であり、将来の原子力発電の主流にすべきものとして開発が進められている。動力炉・核燃料開発事業団では民間の協力を得て、福井県敦賀市に原型炉「もんじゅ」の建設を進めており、1992年度臨界を目途に総合機能試験を行っている。
実証炉については、1990年代後半に着工することを目標に、日本原子力発電を中心に、実証炉関係の研究開発、基本仕様の選定、トップエントリー方式ループ型炉を含めたプラント全般の概念設計等を行うこととしている。なお、動力炉・核燃料開発事業団と日本原子力発電の間で、1989年3月、「高速増殖実証炉の研究開発に関する技術協力基本協定」が締結され、具体的協力が進められている。
③ 高速増殖炉使用済燃料の再処理
高速増殖炉使用済燃料の再処理技術については、動力炉・核燃料開発事業団において、実規模モックアップ試験、高レベル放射性物質研究施設における基礎的データの蓄積等が図られている。今後、工学規模のホット試験施設の建設、プロセス・エンジニアリングの確立を図り、パイロットプラントの建設計画の具体化を図ることとしている。
④ MOX燃料加工
プルトニウム利用体系を確立するためには、多量のプルトニウムの安全な取扱技術を含めて所要の研究開発を進め、MOX燃料加工の実用化を図る必要がある。
MOX燃料加工については、従来から動力炉・核燃料開発事業団が行ってきており、1992年3月末現在、「ふげん」、「常陽」、「もんじゅ」用燃料の累積製造実績は113トンMOXを達成している。さらに現在、新型転換炉実証炉用燃料製造施設の建設計画が予定されている。
また、MOX燃料加工の国内事業化のためには、動力炉・核燃料開発事業団の有する加工技術を民間事業者へ円滑に移転する必要がある。このため同事業団の施設活用等を早急に検討する必要がある。
なお、海外再処理により回収されるプルトニウムについては、一定期間、適切な量について、海外でMOX燃料加工を行うことが適当であり、そのための検討を進めることが必要である。
⑤ プルトニウムの輸送
海外再処理によって回収したプルトニウムの国際輸送については、関係機関の緊密な連携の下に輸送体制の整備を図ることとしている。1988年7月に発効した新日米原子力協定では、一定のガイドラインに従う航空輸送に対し、包括同意が得られ、同年10月には、一定のガイドラインに従う海上輸送についても包括同意の対象となることとなった。
その後、1989年12月の原子力委員会核燃料リサイクル専門部会で、当面の国際輸送は海上輸送で行うこと、1992年秋頃までには輸送を実施すること等を内容とした報告書を取りまとめた。
1992年秋頃には、高速増殖原型炉「もんじゅ」の燃料製造に必要なプルトニウムのフランスからの海上輸送が予定されており、動力炉・核燃料開発事業団を中心に鋭意準備を進めるとともに、海上保安庁においても護衛のための巡視船を1992年4月に完成させるなど、関係機関が協力して準備を行っている。
(4) 高レベル放射性廃棄物処理処分
① 処理処分の基本的進め方
再処理施設において使用済燃料から分離される高レベル放射性廃棄物は、動力炉・核燃料開発事業団の東海再処理工場で発生したものが、1992年3月末現在溶液の状態で、471立方メートルとなっている。
また、電気事業者の使用済燃料の海外再処理に伴い発生する高レベル放射性廃棄物(ガラス固化体)が返還されることになっている。
これらの高レベル放射性廃棄物については、ステンレス製の容器に安定な状態にガラス固化し、30~50年間程度冷却のための貯蔵を行った後、地下数百メートルより深い地層中に処分することを基本的な方針としている。
原子力委員会放射性廃棄物対策専門部会が1992年8月に取りまとめた報告書「高レベル放射性廃棄物対策について」では、高レベル放射性廃棄物の処分と研究開発等の進め方を併行したものとして整理するとともに、高レベル放射性廃棄物対策の進め方に関する具体的なビジョン等が明確に示されている。
今後は、報告書に示された計画に従い、着実にその対策を実施していくこととしている。
② 研究開発の状況
ガラス固化技術については、フランス、英国等において実用規模のプラントが稼動しており、我が国においても、動力炉・核燃料開発事業団を中心に研究開発が進められてきている。同事業団は、この成果を踏まえたガラス固化プラントを1992年4月に完成させ、同年5月から模擬廃液を使った試験を進めており、実廃液を使った試験は1994年以降に開始する予定である。
高レベル放射性廃棄物の地層処分については、動力炉・核燃料開発事業団が中核推進機関となり研究開発を実施してきている。
同事業団の北海道幌延町における貯蔵工学センター計画は、高レベル放射性廃棄物等の貯蔵と併せて、地層処分のための研究開発等を行う総合研究センターを目指したものであり、本計画は処分場の計画と明確に区別したものであるとの認識の下、その着実な推進を図っていくこととしている。
さらに、原子力委員会放射性廃棄物対策専門部会は、高レベル放射性廃棄物の処理処分の効率化、含まれる有用元素の資源化という新たな可能性を目指して、1988年10月「群分離・消滅処理技術研究開発長期計画」を取りまとめた。これらの研究開発については、長期的視野に立って、官民の力を結集して計画的かつ効率的に推進することとしている。また、1989年6月から、核種分離・消滅処理技術に関する情報交換の国際協力計画(通称:オメガ計画)が我が国の提案により経済協力開発機構原子力機関(OECD/NEA)において開始され、現在、同計画の1998年までの期間延長が検討されている。
(5) 放射線利用
(医療分野での利用)
医療分野においては、診断、治療、医用材料や医用デバイスの加工製造及び医療器具等の滅菌に放射線が利用されている。
診断の面では、胸部、胃、骨等のX線撮影や、X線断層撮影等が一般的に普及・利用されている。また、放射性医薬品の体内投与(トレーサー利用)とコンピュータトモグラフィを利用した臓器等の機能の画像化による診断も行われており、ポジトロンCT装置は実用化段階に達している。
治療の面では、X線、γ線、電子線の照射によるがん治療が実用化されているほか、放射線医学総合研究所、日本原子力研究所等において中性子線、陽子線、重粒子線を利用した治療法の研究も行われている。
医療器具の滅菌については、主として、透過力の大きいγ線による滅菌が行われてきたが、最近、高エネルギー電子線による滅菌も行われるようになった。
(農業分野での利用)
農業分野においては、品種改良、害虫防除、食品照射といった分野において放射線が利用されている。
品種改良については、コバルト60を利用し、風害に強い稲、病気に強い梨等、100種に及ぶ成果を挙げている。
害虫防除については、1972年よりウリミバエの不妊虫放飼法による根絶防除を沖縄、鹿児島両県で実施しており、根絶達成地域では果実類の移動規制が解除され、本土市場への出荷が自由となった。八重山群島地域においても1993年には根絶の達成が見込まれている。
食品照射は、食品の保存期間延長等のため、発芽防止、熟度遅延、殺菌、殺虫等を行うものである。1991年10月現在、世界の37か国で合計約60品目について食品照射が法的に許可されている。我が国では馬鈴薯等の発芽防止のための照射が実用化されている。
(工業分野での利用)
工業分野においては、工程管理、品質管理のための精密計測・検査及び材料の改質といった分野で放射線が利用されている。
計測・検査については、透過力の大きいγ線、中性子線等を用いた厚さ、密度、水分含有量等の計測や放射線を用いた亀裂等の非破壊検査が行われている。
材料の改質については、放射線の照射により、電線被覆材、自動車用タイヤ等の耐熱性、耐摩耗性を向上させること等が行われている。
また、マイクロエレクトロニクス、精密加工等にも利用されている。
(その他の分野での利用)
その他、考古学分野における年代測定など学術研究等の分野でも放射線利用の実施例は多く、また、新たな放射線利用技術開発を目指し、日本原子力研究所におけるイオン照射研究施設建設、日本原子力研究所と理化学研究所の協力の下に実施されている大型放射光施設の建設など、イオンビーム、放射光等の放射線利用高度化研究開発が進んでいる。
さらに、放射線利用は環境保全の面でも注目されており、日本原子力研究所ではゴミ焼却場の排煙及び石炭燃焼時の排ガス中の有害成分(硫黄酸化物、窒素酸化物、塩化水素)を電子線により除去する技術や、汚泥の放射線処理による殺菌及び速成堆肥化技術の開発を進めている。
第3章 我が国の先導的プロジェクト等の開発利用の状況と今後の原子力開発利用の進展に向けて 1. 先導的プロジェクト等の推進 (1) 核融合研究開発
核融合については、人類の恒久的なエネルギー源となり得る、地球温暖化や酸性雨の原因となる物質を排出しないなど種々の期待が寄せられており、我が国では、第二段階核融合研究開発基本計画の下で積極的に研究開発が行われてきた。
日本原子力研究所では、トカマク型臨界プラズマ試験装置(JT-60)によりプラズマ性能の向上を目指した高性能化研究が進められており、1992年8月にはイオン温度4.4億度、核融合積50.7億度・秒・兆個/立方センチメートルというプラズマ性能が達成されている。
また、超電導コイル、加熱・電流駆動装置等の炉工学技術の研究開発が行われるとともに、次期大型装置の設計検討も進められている。
大学共同利用機関である核融合科学研究所では大型ヘリカル装置の建設を推進しており、大学等においては、逆磁場ピンチ型等の各種磁場閉じ込め方式や慣性閉じ込め方式による先駆的・基礎的研究が進められている。
このような研究開発の結果、我が国は第二段階核融合研究開発基本計画の目標を大略達成したと判断されるに至ったことから、1992年6月9日、原子力委員会は、自己点火条件の達成及び長時間燃焼の実現並びに原型炉の開発に必要な炉工学技術の基礎の形成を主目標とする第三段階核融合研究開発基本計画を決定した。現在、これに基づいて研究開発が推進されている。
また、日本、米国、EC、ロシアの4極の国際協力による国際熱核融合実験炉(ITER)の工学設計活動に関する協定等が、1992年7月、正式に署名された。ITERの工学設計活動においては、共同中央チームのサイトが、我が国茨城県那珂町(日本原子力研究所那珂研究所)等の3か所に設置され、それぞれにおいて真空容器外側の機器の設計、真空容器内側の機器の設計、設計統合が実施される。人事面ではITER理事会の共同議長、共同中央チームの首席副所長等が我が国から選出された。
一方、常温で核融合の現象が起こっている可能性があると報告されているいわゆる低温核融合については、核融合反応であるか否か確認されていないが、解明、実証のための追試験が引き続き行われている。
(2) 高温工学試験研究
高温工学試験研究については、高温熱供給、高い固有安全性、燃料の高燃焼度等優れた特性を有する高温ガス炉の研究開発を推進しており、高温ガス炉技術の基盤の確立と高度化を図るための研究及び高温工学に関する各種先端的基礎研究のための中核となる研究施設として、高温工学試験研究炉(HTTR)の建設が日本原子力研究所において進められている。HTTRは、現在、建設が進められており、これと並行して大型構造機器実証試験ループ(HENDEL)、高温ガス炉臨界実験装置(VHTRC)等を用いてHTTRに組み込まれる主要機器・部品の機能及び健全性の実証等の各種研究開発を行っている。一方、HTTRから取り出される熱を利用した水素製造の基礎的研究等を行っている。また、研究の効果的促進のために、ドイツ、米国、中国等との国際研究協力を行っている。
(3) 加速器技術等
日本原子力研究所では、エネルギー領域の異なる4台のイオン加速器を有するイオン照射研究施設(TIARA)のうち、1991年10月までに2台の加速器が完成し、イオンビームを用いた耐放射線性材料、バイオ技術、新機能材料等に関する研究など放射線高度利用研究を推進している。また、残る2台については1993年度の完成を予定している。
放射線医学総合研究所では、治療効果が高く、かつ正常組織の損傷が少ないなど、優れた性質を持つ重粒子線を用いたがん治療の研究を行っており、1993年度の臨床試行開始を目指し装置建設を進めている。
理化学研究所では、1989年に世界最高の加速性能を達成したリングサイクロトロンによる原子核物理等の基礎研究が行われている。
動力炉・核燃料開発事業団は、長寿命放射性核種を短寿命化又は安定な核種に核変換する技術(消滅処理技術)の開発を目的として、大出力電子線形加速器の開発を行っている。日本原子力研究所においても、同様の目的で大出力陽子加速器の研究を行っている。
さらに日本原子力研究所と理化学研究所は、兵庫県播磨科学公園都市において、1998年の供用開始を目指し、物質・材料系科学技術、情報・電子系科学技術、ライフサイエンス等の広範な分野の研究を行う世界最大級の大型放射光施設(SPring-8)の建設を推進している。
また、日本原子力研究所では、排煙処理等の環境保全への放射線利用、汚泥の堆肥化等の資源有効利用に関する研究開発を行っている。
(4) 原子力船
原子力船については、日本原子力研究所において原子力船「むつ」による研究開発を実施してきた。「むつ」は、1991年2月より実験航海を実施し、海洋環境下における振動・動揺・負荷変動等が原子炉に与える影響等に関する貴重なデータ、経験的を獲得し、1992年2月14日をもってすべての実験を終了した。
「むつ」は洋上試験・実験航海を通じて、約4.2キログラムのウラン235を燃焼し、原子動力で地球2周強に相当する約82,000キロメートルを航行した。これは重油に換算すると約5,000トンに相当し、1グラムのウラン235で1トン強の重油を節約したことになる。
また、「むつ」の解役については、約1年間使用済燃料を冷却した後、使用済燃料、中性子源、原子炉等を「むつ」より撤去することとしている。
舶用炉の改良研究については、舶用炉の経済性、信頼性等の向上を目指し研究を実施している。なお、1992年6月、科学技術庁原子力局において今後の舶用炉研究開発について報告書が取りまとめられた。
(5) 新しい型の原子炉の研究
受動的安全性を具備した中小型炉、モジュール型液体金属炉、高転換軽水炉等の新しい型の原子炉については、日本原子力研究所等において、幅広く基礎的・基盤的研究を推進し、将来の原子炉技術のブレークスルーの可能性の検討を行っている。
2. 基礎研究・基盤技術開発 我が国の原子力開発利用の基本目標は、①原子力の基軸エネルギーとしての確立、②原子力分野における創造的科学技術の育成、③国際社会への貢献であり、このような基本目標に向けて着実な原子力開発利用の進展を期すためには、国内に確固たる技術的基盤を構築していくことが肝要である。このため、基礎研究・基盤技術開発について、原子力開発利用の基盤を形成する技術及び革新的なブレークスルーをもたらす先導的な研究開発を産学官の密接な連携・協力の下に推進している。
原子力基礎研究については、研究者の自由な発想を重視し、今後ともより一層の充実を図っていくこととしている。
現在、原子力関連の研究開発等を行う国公立機関(特殊法人を含む)は36機関、大学等の研究所は58機関、その他公益法人等は約80機関に上る。また、我が国は、日本原子力研究所、大学等を中心に12基の研究・教育用の原子炉を有し、昨年概ね一年間に国内の学会誌等に掲載された原子力関連論文数は2,700件余に達している。
原子力基盤技術に関しては、現在、日本原子力研究所、動力炉・核燃料開発事業団、理化学研究所及び国立試験研究機関を中心に、原子力用材料技術、原子力用人工知能技術、原子力用レーザー技術、放射線のリスク評価・低減化技術の4領域の技術開発が行われている。
また、これら基盤技術開発のうち、多岐にわたる技術要素から構成され、複数の研究機関のポテンシャルが必要な研究については、「原子力基盤技術総合的研究」(原子力基盤クロスオーバー研究)というシステムにより、関係研究機関の連携・協力による効率的・効果的な研究開発が行われている。
3. 推進基盤の強化 我が国の原子力開発利用の一層の進展のためには、研究開発資金・人材の確保、研究開発体制の整備等の研究開発推進基盤の強化が重要である。
1992年度の政府の原子力関係予算は、科学技術庁分が前年度比約102.9%の約3,152億円、通商産業省分が前年度比約107.7%の約1,057億円、その他が前年度比約98.4%の約50億円であり、一方、産業界における原子力関係支出高(1990年度実績)は、電気事業で約1兆7,355億円(うち研究開発費は約470億円)、鉱工業で約1兆8,540億円(うち研究開発費は約960億円)などとなっている。
人材の確保に関しては、今後の原子力開発利用の拡大に伴い充実を図るとともに、研究開発の国際化に対応するため、各種国際協力への我が国関係者の積極的な参加等を行っている。また、政府関係研究開発機関においては、民間及び大学との積極的な人材交流を行っている。現在、原子力産業における技術系従業員数は約3万3,000人、政府関係研究開発機関における研究者、技術者の数は約5,400人となっている。
しかし、我が国の労働力人口については、近年の出生率の低下を背景に、生産年齢人口(15~64歳の人口)は1995年から減少すると予想されており、さらに、労働時間の短縮も手伝って、労働力市場全般において深刻な人材不足が懸念されている。このような労働力供給構造の中で、着実に拡大する原子力開発利用に対応し得る人材を確保することは極めて重要な課題となりつつある。
今後、原子力開発の一層の進展に資する人材の量的あるいは質的確保に当たっては、教育現場へのアプローチ、原子力に対する不信感の払拭、魅力ある研究分野としての地位の確立などが望まれており、このため、原子力関連研究開発機関と大学等の教育機関との連携の強化、国民の理解の一層の増進などについて検討されることが望まれている。
研究開発体制については、現在、主な原子力関連研究開発機関として、日本原子力研究所、動力炉・核燃料開発事業団、理化学研究所の3つの特殊法人、放射線医学総合研究所、金属材料技術研究所等の国立試験研究機関、関係公益法人があり、これらを始めとした研究開発機関がそれぞれの特長を活かし、効率的な官民協調体制を形成している。また、日本原子力研究所、動力炉・核燃料開発事業団、国立試験研究機関及び大学が人的交流、共同研究の実施等による有機的連携を図り、研究開発推進基盤を強化している。
一方、「研究開発投資の拡充」等の内容を盛り込んだ科学技術政策大綱が閣議決定されるなど、科学技術に対する社会的期待はますます大きくなってきている。人類が今世紀に生んだ科学技術であり、広範な科学技術の水準向上の牽引力たる原子力分野においても、今後とも一層の基盤強化が期待されている。
4. 立地の促進等 我が国の総合エネルギー政策の指針である「長期エネルギー需給見通し」の中で、原子力発電は2000年度に5,050万キロワットの設備容量とすることが目標とされているが、現状の原子力発電設備容量は、1992年9月現在、着工準備中のものも含めて4,635万3千キロワットであり、目標の達成にはさらに約400万キロワットが必要とされている。
また、1986年に発生したチェルノブイル原子力発電所事故以降、国民全体に、原子力の安全性、放射能汚染等に対する不安、懸念が広がったこともあり、各種メディア、原子力モニター制度、説明会、パンフレットの配布等を活用して原子力の安全性、必要性等について地元住民を始めとする国民の理解と協力を得るための努力を重ねている。
さらに、立地地域の振興対策の拡充を図るため、電源三法(発電用施設周辺地域整備法、電源開発促進税法及び電源開発促進対策特別会計法)の活用等が逐次図られており、1992年度には、新たに、原子力発電所新設予定地点における立地の円滑化を図るための電源立地地域温排水等補助金の新設、特別電源地域の科学技術振興事業に対する補助金の追加等の措置が講じられた。
立地の促進策については、関係審議会においても検討がなされており、1992年6月、電気事業審議会需給部会電力基本問題検討小委員会は報告書を取りまとめ、地域と発電所が共生する「地域共生型発電所」という新しいコンセプトを打ち出している。また、1992年7月には、電源開発調整審議会電源立地対策検討委員会が中間取りまとめを発表し、電源立地を「国をあげて支援すべきプロジェクト(ナショナルプロジェクト)」と位置付けるとともに、電源開発調整審議会に上程される前の段階(初期段階)における取組についての方針が示された。
また、最近の動向として、青森県東通村に建設が計画されている東通原子力発電所について、1992年8月、地元漁業共同組合と事業者が漁業補償協定を締結した。これにより建設計画が大きく前進していくものと考えられる。
5. 国民の理解の増進と協力の促進 (最近の世論の状況)
1990年の総理府の世論調査によると、原子力発電の必要性について、「必要である」64.5%、「必要でない」20.7%となっている。また、今後10年間の主力エネルギーとして「原子力」と回答した人は、約50%と最も多くなっている。さらに、今後の原子力発電の増減については、「慎重に増やす」が約44%と最も多く、「現状維持」が約30%となっている。一方、原子力発電を「安全ではない」と考える人(47%)が「安全である」と考える人(44%)よりも若干多い。また、原子力に対する不安については、不安に思うほとんどの項目において、前回調査に比べ増加している。さらに、原子力発電について信用できる説明主体として、「テレビ・ラジオなどの報道」、「学者・専門家」、「新聞・雑誌などの報道」を挙げた人がそれぞれ3~4割と多く、「国・地方自治体」と回答した人は約12%であった。
(原子力に対する国民の理解と協力の増進のための活動の現状)
上記調査結果を踏まえ、国や事業者は、安全確保の実績を積み重ね、情報の迅速・正確な提供、安全管理体制の全体構造、当該事故の状況・影響度・対策等について分かりやすい説明に引き続き努力し、原子力に対する正確な理解を求めるとともに、日頃からの誠実な対応により、信頼感の醸成を図っていくことが求められている。
このような活動を行うに当たっては、国民にとって、原子力の安全性や放射線の性質等が実感できないことも原子力に対する理解と協力の増進を図る上での障害となっており、今後は、国民に原子力施設を実際に見てもらう機会を更に一層増やしていくことが重要である。
他方、未来を担う青少年に対し、科学教育及びエネルギー教育等の場において正確な知識の普及を行うことや、社会人に対してもエネルギーや原子力に対する学習の機会を広く提供することが、原子力を含めエネルギー全般について国民一人一人に考えてもらうためにも必要である。
このような認識の下、現在、国、地方自治体、事業者等によって、原子力に対する国民の理解と協力の増進のための講師派遣、実験セミナー等の活動が行われている。
さらに、立地地域においても、国の担当官や専門家が、各地で説明会・座談会を実施するなど、地域の事情に応じた、懇切丁寧な広報を心掛けている。
(安全確保の実績の積み重ね)
1990年2月に発生した関西電力美浜発電所2号炉の蒸気発生器伝熱管破損事故は、我が国で初めて非常用炉心冷却装置が実作動したことから、国民の原子力発電に対する不安感を抱かせる結果となった。本事故に関しては、振止め金具の挿入不完全に起因して蒸気発生器伝熱管の破断に至ったものであるが、安全審査において評価されたところの安全設計の機能が大筋において適切に働いた結果、安全は基本的に確保されたとする原子力安全委員会の調査審議結果が1992年3月に取りまとめられている。
しかし、安全性の有無に関係なく、事故・故障・トラブルは、それ自体が国民の不安をを抱かせる原因となっていることから、安全確保対策の実施状況や事故・トラブルの環境への影響度などについて、理解を深めてもらうとともに、安全性の一層の向上を図り、安全確保の実績を積み重ねることにより、国民の理解と協力を得るよう努力することが重要である。
(国際評価尺度の導入について)
我が国では、1989年以来、原子力施設における事故・故障等について、その影響の度合いを分かりやすく示すための尺度を導入して、一般国民の的確な理解の促進に資してきたところであるが、1992年8月以降、国際原子力機関(IAEA)と経済協力開発機構原子力機関(OECD/NEA)が協力し、我が国及びフランスの事故・故障等評価尺度の経験を活かして作成した国際原子力事象評価尺度(INES:International Nuclear Event Scale)を導入することとした。
6.原子力開発利用長期計画改定に向けた取組 原子力委員会は、原子力開発利用を国民の理解と協力の下に計画的かつ総合的に遂行していくため、原子力開発利用に関する指針の大綱と基本的な施策の推進方策を記した原子力開発利用長期計画(以下「長期計画」という)をほぼ5年ごとに数次にわたり策定してきている。
現行の長期計画は、1987年6月に改定されたものであるが、原子力委員会において、核不拡散をめぐる状況の変化など内外の情勢が大きく変化していることにかんがみ、1992年7月28日、長期計画の見直しを行うことを決定し、原子力委員会の下に長期計画専門部会を設置した。
同専門部会の下には、基本分科会、第1分科会(軽水炉利用)、第2分科会(核燃料リサイクル)、第3分科会(核不拡散と国際貢献)、第4分科会(技術開発)の5つの分科会を設置することが決められ、現在、これらの分科会等において検討を行っているところである。主要検討事項は、
・21世紀を展望した長期的かつ整合性ある原子力開発利用体系の構築
・東西冷戦後の新たな世界秩序における核不拡散と原子力平和利用との両立
・原子力の技術先進国の一員としての国際貢献、科学技術立国にふさわしい先導的プロジェクト、基礎研究・基盤技術開発の推進
・エネルギー問題、地球環境問題等の世界的課題に取り組む上での原子力の必要性等に対する国民の理解の増進
等である。
激動する国際情勢の中、このような課題を検討・解決し、原子力開発利用を推進し、我が国さらには世界のエネルギー安定供給の確保等を図るとともに、平和利用の世界的な牽引国として国際的に積極的な貢献を行うためにも、今回の長期計画の見直しは極めて重要なものと考えており、原子力委員会としては、長期計画策定に向けて最大限の努力を傾注していく所存である。
(参考) 1992年度原子力関係予算総表 |
| 前頁 | 目次 | 次頁 |