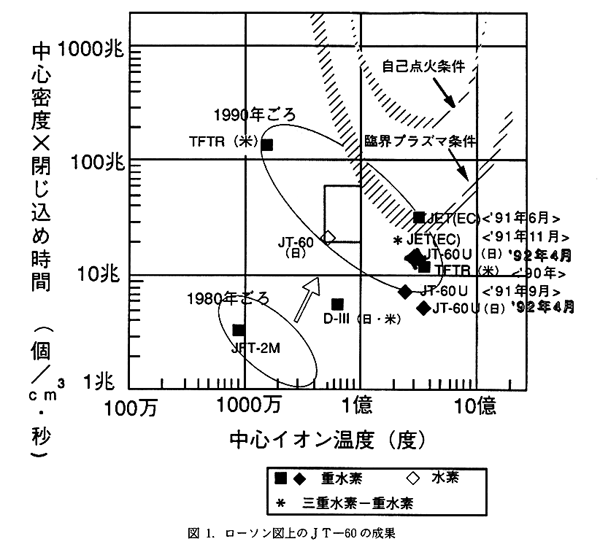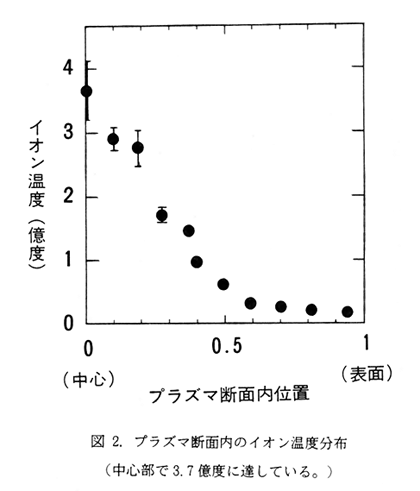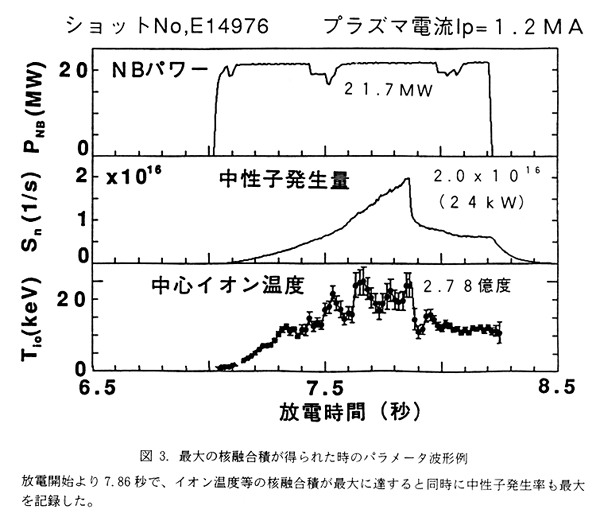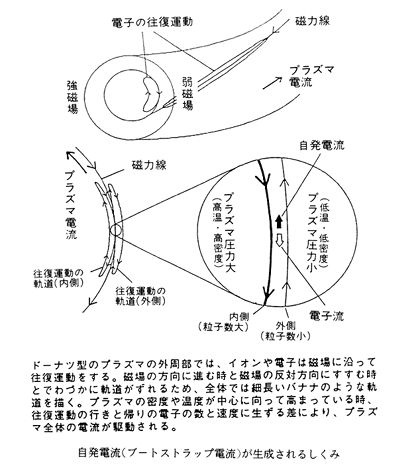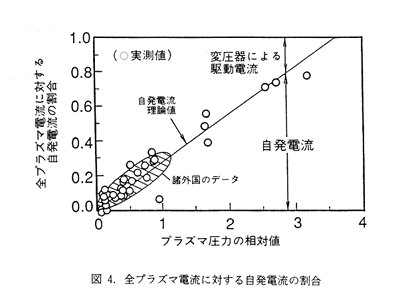| 前頁 | 目次 | 次頁 |
|
資料 JT−60重水素実験の最近の成果 平成4年6月5日
日本原子力研究所
1. JT−60の状況 臨界プラズマ試験装置のJT−60については、大電流化改造が行われた後、昨年3月より高性能化実験(2)が開始された。また、同年7月半ばより重水素を用いたプラズマ実験が開始された。その結果、本年4月迄に以下の成果が得られた。
2. 成果の概要 (1) 高イオン温度モードによる3.7億度の達成
比較的密度の小さいプラズマを高パワーで加熱することにより、低いプラズマ電流においても、プラズマ中のイオン温度を高められる放電状態(高イオン温度モード)が得られる。このモードではプラズマを効率良く加熱できることから、良好な閉じ込め性能が得られる。
大電流化改造後のJT−60の重水素実験において、この放電モードにより以下のような成果が得られた。
・プラズマのイオン温度は最大で3.7億度に達した。これはJET(3.5億度)を上回り、TFTRの4億度に匹敵する記録である。(図.1)、(図.2)
・プラズマの閉じ込め性能の指標である核融合積において、今までの自己の記録を1.6倍上回る、38.3[兆個・cm-3・秒・億度]を得た。これは、核融合積において、TFTRとならび、JETに次ぐ記録である。(図.1)、(図.3)
・このモードでの重水素核融合反応により、中性子発生量は、一秒間あたり最大2.0×1016個(24kW出力相当)に達した。(図.3)
これらは、特に不純物の低減に努めながら、プラズマの加熱効果が高まるよう最適化を図った結果得られた一連の成果である。
(2) 長パルス化研究の成果
・プラズマを高パワーで加熱することにより、プラズマ圧力勾配を大きくして、全プラズマ電流の80%程度の高い比率を占める自発電流が生成された。この検証により、トカマク型装置の高効率長時間運転につながる有効なデータベースが得られた。(図.4)(*)
・ITER等核融合装置の開発において、長時間運転時に、最も苛酷な熱負荷を受けるダイバータ板からの円滑な熱除去を行うことが重要であるが、これまでの予測による熱流束量を低減できることを示唆する、新しいダイバータ熱流束の比例則が得られた。
(3) その他の成果
・高効率閉じ込めモード(Hモード)の実現
プラズマの高効率閉じ込めモード(Hモード)が、高い再現性をもって確認された。特に従来のHモードが、低めのトロイダル磁場(2−3テスラ)のみで得られていたのに対し、JT−60では4テスラと高めのトロイダル磁場までその実現可能な範囲を広げた。これは、高めのトロイダル磁場(4.85テスラ)が想定されているITERのためのデータベースに貢献する成果である。
・リップル損失研究
磁場のトロイダル方向の非均一性によって生ずるプラズマ中の高速イオンのエネルギー損失について、理論予測と実験結果が一致することが世界に先駆けて示され、実験炉以降の設計に対する明確な指針が得られた。
3. 今後の計画 JT−60による今後の高性能化実験の計画については、今までの成果をベースに、ITERの工学設計活動(EDA)に貢献するため、ITER物理R&Dの一環として“閉じ込め改善”と“長パルス化研究”を中心に推進する。
閉じ込め改善の研究においては、高効率閉じ込めモード(Hモード)の最適化等ITERの物理データベースの構築に努める。長パルス化研究においては、ITERのプラズマ加熱と長時間運転に重要となる、負イオン源中性粒子入射装置を用いた高密度プラズマ電流駆動の実験を進める予定である。
* トカマク型装置では、トランスの原理で流す間欠的なプラズマ電流により生ずる磁場を、プラズマ自身の閉じ込めに用いているため、パルス運転が不可欠とされていた。これに対しJT−60では、電磁波による電流駆動など長パルス化研究が意欲的に進められ、高周波により200万アンペアのプラズマ電流を駆動するなど、この分野で先進的成果が得られてきた。
また、プラズマの圧力勾配に比例して、プラズマ中に自発的に電流が流れることが理論的に予測されていたが、近年の大型トカマク型装置(TFTR・JET・JT−60)の高パワー加熱実験によりその現象が相次いで検証された。 なお、今回のJT−60の自発電流に関する実験結果は、高イオン温度モードによる閉じ込めの改善の成果と合わせ、高効率定常トカマク型炉の開発の実現の可能性を示唆している。
|
| 前頁 | 目次 | 次頁 |