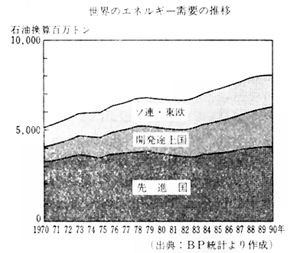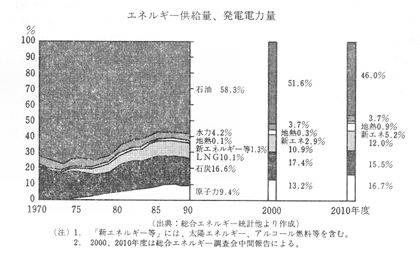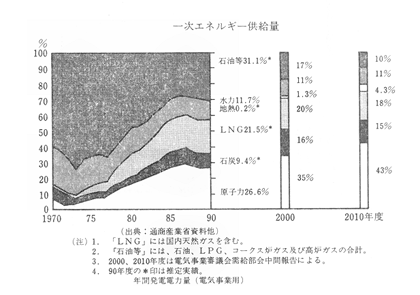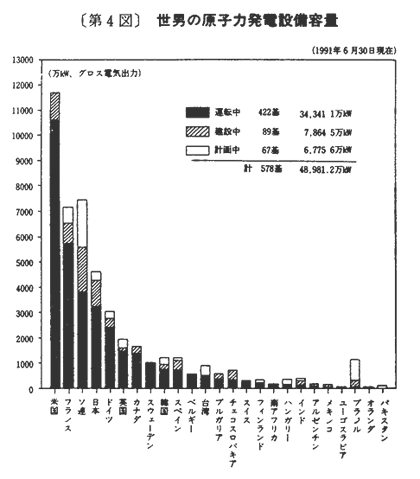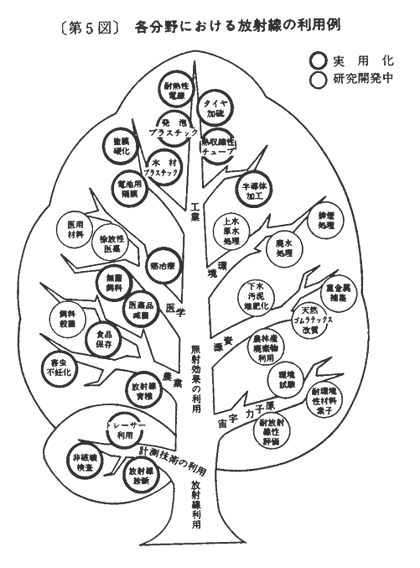| 前頁 | 目次 | 次頁 |
|
委員会の決定等 平成3年原子力年報(要約) 平成3年10月
原子力委員会
はじめに 1. 原子力は、我が国の総発電電力量の約26.6%(1990年実績)を賄うなど、主要なエネルギー源の一つとしての役割を果たしているとともに、放射線についても、重粒子線がん治療装置や大型放射光装置の建設など、医療、農業、工業等の分野でその利用が着実に進展しており、原子力開発利用は我が国の国民生活の向上、経済の発展に大きく寄与している。 2. 一方、湾岸危機においては、大きな経済的混乱はなかったものの、脆弱なエネルギー供給構造を有する我が国にとって、エネルギー安定供給の確保が重要な課題であることが再認識された。湾岸危機はまた、核兵器の拡散の懸念について世界の世論を喚起し、核不拡散体制のより一層の強化の重要性を認識させた。さらに、地球環境保全の観点からも、原子力を始めとする非化石エネルギーへの依存度の向上が重要になっている。 3. 他方、本年2月の美浜発電所2号炉蒸気発生器伝熱管損傷は、国民の原子力発電に対する不安感を増幅させる結果となった。しかし、増大するエネルギー需要に応え、安定供給を図って行くためには、原子力は今後益々重要性を増していくものと見られ、原子力に対する国民の理解と協力の増進を図ることは緊急の課題となっている。このため、事故等が起きないように万全の対策を行い、安全確保の実績を着実に積み重ねていくとともに、情報の正確かつ的確な提供等による理解を深めていくことがより重要となっている。 4. 本年の夏は比較的涼しく電力需給は平穏に推移したが、我が国のエネルギー供給構造の脆弱性や、電力需給の逼迫化など、我が国のエネルギー情勢に鑑みれば、今や、消費者一人一人にエネルギーについて考えてもらうべき時代にきていると考えられる。 5. 以上のような状況を踏まえて、原子力委員会は、本年報において、内外のエネルギー、原子力をめぐる情勢変化を概観した上で、原子力開発利用の状況を整理した。特に、国民の理解と協力について、現状を把握し、今後の課題について述べるとともに、着実に進展している放射線利用についても詳述した。 第1章 原子力に期待される役割と国民の理解と協力の増進 1. 原子力をめぐる内外の情勢変化 (1) 最近の原子力を取り巻く世界の情勢
(エネルギー情勢)
過去20年間の世界のエネルギー需要の推移を振り返ると、1970年から73年にかけて、高い率で増加していたが、第1次及び第2次石油危機直後にはそれぞれ横ばい及び減少に転じ、1983年以降再び増加となり、1986年の石油価格暴落を契機に急増した。このように、全体として1983年以降エネルギー需要は増加の一途をたどってきており、国際エネルギー機関(IEA)によると、2005年のエネルギー需要は、現在の約1.5倍と見通されている。
地域別には、開発途上国のエネルギー需要増大が顕著である。開発途上国におけるエネルギー需要は、今後の人口増、経済発展を考慮すると、2005年には平均して現在の1.9倍となると見通されている。また、開発途上国においては、石油需要も量的には増加するものの、石油依存度は相対的に低下すると見通されている。一方、先進国におけるエネルギー需要は近年高い伸びで増加していたが、1990年には1%程度の低い伸びにとどまった。また、石油依存度は着実に低下し、特に、原子力は全エネルギー需要の約1割を占めるまでに至っている。2005年の先進国におけるエネルギー需要は現在の1.3倍になり、原子力発電も着実に増加する等さらに脱石油化が促進されると見通されている。
また、ソ連及び東欧におけるエネルギー需要は、1989、90年にはマイナスの伸びであったが、IEAによると、市場経済への移行が迅速かつ混乱なく行われると仮定した上で、2005年には、現在の約1.5倍に増加すると見込まれている。エネルギー供給については、原子力発電も2.1倍と大幅に増加すると見込まれている。
世界のエネルギー需要の推移 湾岸危機のエネルギー面における影響は、侵攻直後の心理的要因による原油価格急騰はあったものの、過去2回の石油危機に比べると総じて小さかったといえる。これは、特に先進国において石油代替エネルギーの開発・導入が進んでいたこと、先進国の石油備蓄が確保されていたこと、産油国が増産を行い石油安定供給への努力をしたこと等が主な要因と考えられる。しかし、IEAの見通しによると、2005年には中東産油国への依存度が第1次及び第2次の石油危機の時と同程度にまで達すると予想されており、再び、石油需給が不安定化すると懸念されている。
1991年6月に開催されたIEA閣僚理事会コミュニケにおいても、湾岸危機時に緊急時対応メカニズムの価値が証明されたことを確認し、90年代のエネルギー安全保障には供給の多様化が必要と強調している。中でも、原子力がエネルギー供給に相当貢献することを認識するとともに、温室効果ガス排出の安定化にも貢献できることに注目し、さらに、原子力は一次エネルギー供給の多様化に必須の要素として、特に、安全運転、放射性廃棄物の処理処分及び新型炉の開発において持続的かつ強化された国際協力を奨励している。
また、1991年7月に開催されたロンドン・サミットの経済宣言においても、今回の湾岸危機は世界経済を攪乱するものではなかったとした上で、エネルギーの世界的な安定供給を確保し、環境上及び安全上の高度の基準を奨励するとともに、これらの分野での国際協力を推進するよう努めることを声明している。この関連で、原子力発電はエネルギー源の多様化及び温室効果ガスの排出削減に貢献するものとされている。一方、最高の安全基準を達成し維持することが不可欠であるとした上で、中・東欧及びソ連における安全性の状況への対応策調整のための有効な手段を策定するよう国際社会に要請している。
ここで、エネルギー資源の地域分布状況を比較すると、原油は極端に中東地域に偏在している。天然ガスも同様に一部の地域に偏在している。石炭は偏在が比較的小さい。一方、ウランは政治的・経済的に安定した地域に比較的分散して産出する。
(電力需給状況)
世界の電力消費量は、世界全体としては増加してきている。中でも、開発途上国、特に、アジア地域においては生活水準の向上等により伸びが著しい。世界の発電電力量は、一次エネルギー供給の増加率を上回っている。一方、電源構成の内訳を見ると、先進国においては原子力発電が顕著に増加しており、火力発電の割合が激減している。ソ連・東欧においては、依然として火力発電が大半の割合を占めている。開発途上国は火力発電が増大している。
(地球環境とエネルギー)
近年、地球温暖化、酸性雨等の地球環境問題が大きくクローズアップされている。これらの問題の解決が国際的にも強く望まれており、積極的な取組がなされつつある。特に、地球温暖化については、その影響の大きさ等に鑑み、国際的な協調の下に取り組む最重要課題として様々な国際会議の場において本格的な議論が行われている。
1990年8月に気候変動に関する政府間パネル(IPCC)がまとめた第1次評価報告書によると、エネルギー利用形態が現状のままで増大し続ければ、来世紀末までに平均気温が約3℃、海面が約65cm上昇すると予想され、「本格的な対策が講じられない限り重大かつ潜在的には破壊的ともいえる変化が生じるだろう」とされている。
地球温暖化への寄与はエネルギー起源のものが最も大きく、本問題の解決に当たっては、エネルギー政策の面からの積極的対応が不可欠である。1991年6月のIEA閣僚理事会コミュニケにおいても、再生可能エネルギー、原子力発電システム、革新的な省エネルギー技術等の分野における新たに大幅な進展が必要であることが合意されている。
また、国連の統計を用いたエネルギー起源の世界での二酸化炭素年間排出量は、1988年現在、約59億トン(炭素換算)であり、その半分以上が米国、ソ連、中国の上位3カ国によって占められている。我が国の排出量は世界第4位で、一人当たりの排出量も世界平均の約2倍となっている。なお、主要先進国の中ではフランスの排出量が少
ないことが注目される。
我が国としては、自国のエネルギー起源の二酸化炭素排出量をできる限り抑制することはもとより、世界的な排出量抑制に率先して貢献していく必要があると考えられる。このため、我が国政府は、地球温暖化防止行動計画を1990年10月に策定し、この中で、エネルギー政策においては、世界各国が協調して省エネルギーの推進、クリーンエネルギーの導入、次世代エネルギー技術の開発等に取り組む総合的かつ長期的ビジョン(地球再生計画)作りの具体化の促進の必要があるとされている。
また、1991年7月31日改定されたエネルギー研究開発基本計画の中においても、地球環境問題への対応のためにも重要な役割を果たすものとして、原子力の開発利用の重要性が強調されている。
エネルギー供給量、発電電力量 一次エネルギー供給量 (2) 我が国の原子力発電をめぐる状況
(エネルギー情勢)
我が国のエネルギー需要(最終エネルギー消費)は、第2次石油危機以降数年間は、穏やかな伸びで増加したが、1987年度以降、年率5%前後の伸びで推移し、1990年度は3.8%の伸びで増加した。このような中で発生した湾岸危機において、我が国は、イラクからの原油の全面禁輸等を行ったが、石油備蓄量が十分であったこと、石油依存度が低下していたこと、サウジアラビア等の産油国の増産などを背景に、大きた経済的混乱を起こすものではなかった。しかし、今回の湾岸危機は、我が国のエネルギー供給構造の脆弱性を再認識させる結果となった。
(電力需給状況)
1990年度の総需要電力量の伸び率は7・2%と、4年連続で年率5%以上の高い伸び率となった。部門別の需要電力量を見ると、産業用需要は6.2%の伸びで、民生用需要は8.6%の高い伸びでそれぞれ増加した。また、最大電力の伸び率は、冷房機器の普及拡大による夏季需要の伸び等により需要電力量の伸びを上回っている。
一方、発電電力量(電気事業用)は、1990年度には7,576億キロワット時、伸び率7.7%となった。この中で、原子力発電は着実に増加し、1990年度末には、商業用発電設備容量が3,148万9千キロワット、発電電力量が2,014億キロワット時に達し、原子力発電の総発電電力量に占める割合は26.6%と6年間連続で25%以上を占めた。
1990年夏季には、異例の猛暑による冷房需要の増大等が要因となり、最大電力が大幅に増加したため、供給予備率が3%以下にまで低下する電力会社も出るなど、電力需給は逼迫した。
1991年夏季には、8月が猛暑とならず、7月24日に最大電力需要が記録されたが、電力需給状況は、昨年のような需給調整契約の発動もなく、安定供給が確保された。
(石油代替エネルギーの供給目標)
通商産業省は、1990年6月の総合エネルギー調査会の我が国のエネルギー需給の長期見通しに更に検討を加え、「石油代替エネルギーの供給目標」について、1990年10月30日の閣議決定を経て改定を行った。これらによると、エネルギー需要の増大を最大限抑制し、石油依存度の低減及び新エネルギーの導入を最大限図る等の政策を推進した上で、2010年度のエネルギー需要は6.57億キロリットルと見通し、2010年度における原子力の供給目標値は、出力7,250万キロワット、年間発電電力量4・740億キロワット時となっている。
〔第4図〕 世界の原子力発電設備容量 (3) 原子力発電の各国(地域)の状況
① 概況
世界における原子力発電所は、1991年6月末現在、25カ国(地域)で422基が運転中で、設備容量は約3億4,300万キロワットにのぼり、前年(1990年6月末)に比べ、566万キロワットの増加になっている。総発電電力量は、1990年実績で1兆9,012億キロワット時に達し、世界の総発電電力量の約16%を占めるに至っている。世界の原子力発電規模は、チェルノブイル事故当時と比べ現在までに約6,600万キロワット以上の増加をしている。
近年の世界的なエネルギー需要の増加傾向、湾岸危機の発生、さらに、地球規模の環境問題を踏まえ、一部の国では、エネルギー政策の見直しを行うとともに、原子力発電が再認識される動きも出てきている。
また、国際原子力機関(IAEA)によるチェルノブイル事故影響調査が行われたほか、経済協力開発機構/原子力機関(OECD/NEA)による東欧との原子力セミナーの開催等が行われた。
② 各国(地域)の動向
米国は、世界第1位の原子力発電設備を有し、1991年6月末現在、112基、1億610万キロワットの原子力発電所を運転している。発電電力量についてみると1990年には、約9%増の5,770億キロワット時を原子力により発電し、総発電電力量に占める原子力発電の割合は、過去最高の20.6%になるとともに、稼動率も過去最高の66%を記録した。
米国では、エネルギー需要が増大し、電力需要も好調な推移を続けているのに対し、新規電源開発の立ち後れや電力供給体系の不備から、夏季や冬季の電力需要のピーク時には電力需給の逼迫が深刻化し、電力供給体制の信頼性確保に懸念が生じている。
このような米国内におけるエネルギー問題の抜本的な解決を図るため、1991年2月、ブッシュ大統領は、2010年を目標年度にエネルギーの自立達成に向けて、「国家エネルギー戦略」を公表した。この中で、原子力発電については、国産エネルギー資源であり、化石燃料の使用抑制や地球環境問題へ貢献できることなどから、今後も積極的な活用を期待し、このため、①原子力発電に係わる許認可手続きの簡素化、②高レベル放射性廃棄物処分場の立地、許認可の推進、③新型軽水炉の標準化設計の推進等を挙げている。
原子力規制委員会(NRC)は、商業用原子力発電設備の運転期間を延長する運転許可の更新を行える規則の制定について検討中である。
原子力発電所の建設については、1990年中に3基が運開し、現在、9基が建設中である。
カナダは、従来から自国の豊富なウラン資源と自主技術によるカナダ型重水炉(CANDU炉)を柱とした独自の原子力政策を一貫して採っている。1991年6月末現在、19基、1,385万キロワットのCANDU炉が運転中で、この1年間で約740億キロワット時を発電している。1990年には、ダーリントン1号及び2号が運開し、さらに、1991年から1992年にかけてダーリントン3号及び4号が運開する予定である。
一方、カナダ原子力公社(AECL)は、1990年12月、韓国の月城原子力発電所2号機を受注している。また、モジュラー型のCANDU-3型炉の開発にも力を入れている。
フランスは、エネルギー資源に乏しく、エネルギー自給率を改善するため原子力発電を積極的に導入し、1991年6月末現在、55基、5,698万キロワットの発電設備を有し、総発電電力量の約75%を原子力発電により賄っている。このような積極的な電源開発を基にフランスは、総発電電力量の約11%にあたる457億キロワット時をスイス、イタリア、英国等の国々へ送電している。
また、フランスは、高速増殖炉の原型炉フェニックス、実証炉スーパーフェニックスを運開しているが、両炉とも、1990年からトラブル等のため運転停止状態にあり、現在、運転再開に向けて準備が進められている。さらに、1990年8月、ラ・アーグ再処理工場のUP-3プラントが全面操業し、海外からの委託再処理能力の増強を図っている。
高レベル放射性廃棄物の処分については、1991年6月、議会に、深地層構造の研究等の,3つの方向の研究の同時実施、深地層研究のための地下研究所の設立等を内容とする法律案が提出され下院を通過した。
英国は、1990年4月、電力事業の民営化が実施され、英国中央電力庁(CEGB)は、原子力部門を除き民営化され、新たに国営原子力発電会社(ニュークリア・エレクトリック社)が同時に設立された。また、サイズウェルBに続く、ヒンクレーポイントCについて、1990年9月、政府は、建設計画を承認したが、建設資金の承認については、サイズウェルBの完成後の1994年に予定される新規原子力発電所計画に関する再検討作業が実施されるまで留保することとした。
ドイツは、1990年10月、旧東西両ドイツが統合され、新たにドイツ連邦共和国がスタートした。1990年の原子力による発電実績は、旧西独側が前年とほぼ同規模の1,472億キロワット時を発電し、同地域の総発電電力量の約38%を占めたのに対し、旧東独側では、55億キロワット時を発電し、同地域の総発電電力量の約5%と前年の約半分にとどまった。旧東独の試運転中及び建設中の原子炉については、旧西独側の安全基準にのっとった見直しが要求されている。
1991年1月、連立政権を構成するキリスト教民主・社会同盟と自由民主党の間でまとめられたエネルギー供給構想において、原子力発電は、「電力供給の実質的な部分を占める必要性があり、旧東独地域の原子力発電所が経済上及び安全上の観点から運転を継続することができない場合、旧西独の技術の利用を考慮する」ことが合意された。
一方、建設中の高速増殖炉SNR-300については、1991年3月、連邦政府はそのプロジェクトの継続を断念したが、連邦政府は高速増殖炉開発からの撤退するものではない旨声明を発表している。現在、ドイツ、イギリス、フランスの研究開発を統合した欧州統合高速炉(EFR)計画が進められており、高速増殖炉の実用化に向けての努力が引き続き行われている。
スウェーデンは、2010年までの原子力発電所全廃を決議し、また、その第一歩として1995年から1996年にかけて2基を廃止するという決議をしていた。しかし、1990年4月、首相、エネルギー相等からなる検討委員会は、今後のエネルギー政策を検討し、1995年ないし1996年からの原子力発電の漸次廃止等を同時に達成させながら国内産業の競争力を維持すること等は極めて難しいことを明らかにしたため、社会民主党等の主要3党間において、1995年から1996年にかけて2基を廃止するというスケジュールを先送りすることが1991年1月に合意された。この3党合意をもとに、新たなエネルギー政策が議会に提出され、1991年6月、議会で正式に承認された。
さらに、1990年11月の世論調査によると、2010年までの原子力発電廃止に対する反対が1989年に比べ11%増の64%に達している。
スイスは、1990年9月、原子力発電の存廃をめぐる国民投票を実施し、その結果、「原子力発電所の新規建設禁止、運転中の原子力発電所の早期停止」との案は支持されず、「今後10年間に原子力発電所の建設許可を発給しない」との案が支持された。
ソ連は、チェルノブイル事故後においても、原子力開発を着実に進めていく方針は変わっていないが、チェルノブイル事故を契機に原子力発電所の建設計画は大幅に遅れ、第12次原子力発電開発5カ年計画の1990年目標の約55%(3,836万キロワット)しか達成できなかった。原子力開発計画の大幅な遅れの理由として、チェルノブイル事故に加え、国民の間に原子力に対する不安と政府に対する不信とが重畳しながら原子力反対運動がにわかに高まってきたことが挙げられる。
1990年2月に開始されたチェルノブイル事故における被災住民を対象としたIAEAの放射線影響調査は、「ソ連がこれまで展開してきた構想やこれら地域で住民の健康を維持するために採られてきた各種措置の有効性」について、ソ連政府が、IAEAに対して国際的プロジェクトとしてアセスメントを要請したものである。
この調査においては、放射線影響、医学等に関して、我が国を始めとする世界各国の第一線級の専門家が参加し、ソ連側の調査手法、データ等の評価、検証が行われたほか、住民の健康状態や汚染状況等に関し、IAEA独自の調査も行われた。1991年5月、調査の成果として報告書が取りまとめられ、環境影響、住民の放射線被ばく、健康影響、防護手段について、結論をまとめ、勧告を行っている。
事故管理及び復旧作業のための緊急要員等の職業上被ばくした人々の健康影響等については、ソ連全土の医療センターで監視していると報告されており、また、世界保健機構(WHO)においても調査等が実施されることとなっている。
このほか、ソ連は、現在、チェルノブイル事故に関し、放射線医学、除染技術等種々の研究を国際共同で行うチェルノブイル国際研究センター計画への各国の参加をIAEAを通して呼びかけている。
また、チェコスロバキア、ハンガリー、ブルガリア等の東欧諸国共通の問題として、酸性雨を始め大気汚染等の環境問題の深刻化等が挙げられ、これらの問題を解決するエネルギー源の一つとして原子力発電への期待も大きい。しかし、原子力発電を既に導入している多くの国々では、ソ連型PWR特有の安全性の問題や原子力反対運動の広がり、資金難等の経済的問題も顕在化してきている。
また、IAEAは、東欧及びソ連にあるソ連型PWR(VVER-440/230)の安全性評価に関するプロジェクトを実施しており、1991年6月、ブルガリア政府に対し、ゴズロドイ原子力発電所の安全性を改善する措置を至急採るよう要請した。1991年7月に開催されたロンドン・サミットにおいても、東欧の原子力発電所施設の安全性向上に対する国際的な対応策の必要性を強調している。
この他、1990年12月には、OECD/NEA主催による東欧との原子力開発に関するセミナーが開催された。
韓国は、1991年6月末現在、原子力発電所9基、762万キロワットの設備を有し、1990年実績で総発電電力量の約49%を賄っている。1989年4月に韓国政府が決定した長期電源開発計画によると、1989年から2001年に原子力発電所5基の新設を計画しており、このうち2基は、既に着工している。また、原子力総合計画の樹立と原子力を含む科学技術全体に対する国民の理解を増進するため、「科学技術国民理解協議会」(仮称)の設立を計画している。
台湾は、原子力発電所6基、514万キロワットの設備容量を有し、総発電電力量の約35%を占めている。同国では、1991年から開始される国家建設6カ年計画に第4原子力発電所の建設を組み込み、今世紀中の運転開始を目指している。
インド、パキスタンでも既に原子力発電を導入している。特に、インドにおいては、7基の原子力発電所が運転中で、11基について建設及び準備が行われている。
中国は、原子力発電に積極的に取り組んでいる。現在、3基の原子力発電所を建設しており、このうち秦山1号機については、同国で最初の原子力発電所として慎重に建設を進めている。現在建設中の3基に続き、今世紀中にさらに5基の建設が計画されている。
インドネシアは、2015年までに合計700万キロワットの原子力発電所の建設を計画している。
(4) 核兵器の不拡散をめぐる最近の動向
東西冷戦が実質的に終了し、世界的な緊張緩和、民主化の強まり等の流れの中で新たな国際秩序が模索されている一方、地域紛争の顕在化の可能性や核兵器等の拡散等による危険性が指摘されている。湾岸危機は、世界の人々に核兵器の拡散に対する懸念を現実的なものとして強く印象づけ、核軍縮や核管理の重要性を再認識させた。
このような状況の中、「核兵器の不拡散に関する条約」(NPT)の重要性が再認識されている。1991年になり、南アフリカ等がNPTを締結し、フランスがNPTの締結を原則的に決定したほか、中国も締結の原則決定を表明するなど、前向きな動きがある。1991年7月のロンドン・サミットにおいても、NPTの重要性を再確認し、全ての非署名国に対し署名すること等を要請するとともに、NPT体制の維持強化、IAEA保障措置制度の強化・改善等に努力することも表明している。
また、1991年7月、モスクワにおける米ソ首脳会談において、START(戦略兵器削減条約)合意文書が、調印された。
さらに、より踏み込んだ核兵器の削減について、ブッシュ米国大統領、ゴルバチョフソ連大統領から提案されるなど核軍縮に向けた動きが進んでいる。
我が国においては、核不拡散と原子力平和利用を大前是に原子力開発利用を推進しており、原子力開発利用を平和目的に限ることを原子力基本法において定めるとともに、NPT及び核物質防護条約に加盟し、これらの国際条約上の義務を誠実に履行している。
また、我が国は、今後、我が国政府開発援助の実施に当たっては、被援助国における核兵器の開発等の動向等に十分注意を払いつつ、総合的に判断することを明らかにしている。
(北朝鮮のIAEA保障措置協定締結問題)
1991年6月のIAEA理事会において、NPTに加盟している北朝鮮は、同条約で義務付けられている保障措置協定締結に向けて手続きを進める旨を表明し、同年7月にIAEAとの間で協定案に合意した。本協定案は、同年9月のIAEA理事会において承認されたが、北朝鮮は、署名及び批准に当たっては、韓国に配備された米国の核の脅威の問題の解決が必要との主張をしている。
なお、従来より我が国は、北朝鮮に対し、同国がNPT上の義務として負っているIAEA保障措置協定の締結を無条件かつ早急に行い、同協定を履行するよう強く求めている。
(イラク問題)
1991年4月の湾岸危機の正式停戦条件を定める決議(国連安全保障理事会決議687号)に基づき、イラクの原子力開発状況について、1991年5月以降現在(9月末)まで6次にわたり、国連及びIAEAの合同査察チームが現地調査を実施した。なお、イラクは、7月、電磁法等の方法により少量ながら濃縮ウランを秘密裡に製造したことを認めた。IAEAは、7月、特別理事会を開き、査察結果等に基づきイラクがIAEAとの保障措置協定に違反していた旨認定するとともに、イラクを非難する決議を採択した。また、その後、少量のプルトニウムの分離も行われたことが判明した。その後8月、国連安全保障理事会でイラクが停戦決議に基づく責任を果たしていないことを非難すること等を内容とする決議が採択された。また、9月のIAEA総会において、イラクの保障措置協定違反を非難するとともに、国連安全保障決議の遵守を強く求めること等を内容とする決議が採択された。
保障措置協定は、核不拡散体制を担保するための重要な国際取極であり、イラクが同協定遵守のための是正措置を速やかに採ることが望まれている。
(原子力資材供給国会合)
核物質等の非核兵器国への輸出に際して適用されるガイドライン(ロンドン・ガイドライン)について、原子力資材供給国は、1991年3月、同ガイドライン成立後初めて、約13年ぶりに参加26カ国の代表が出席し、原子力資材供給国会合を開催した。
本会合においては、核不拡散目的の輸出規制の一層の強化の必要性が確認されるとともに、核兵器開発関連の原子力汎用品に関する輸出規制枠組みに関する検討を開始すること等について合意された。
今後、核不拡散上の輸出規制制度の強化・改善のため、我が国も関係機関と協調を図りつつ、積極的に努力することが必要となっている。
(IAEA保障措置の整備・強化)
IAEA保障措置の有効性の一層強化、信頼性の維持の観点から、現在、IAEAにおいて、特別査察の適用等についての検討が進められている。特に、IAEAに対する報告義務を怠っている国に対し、IAEAが当該国にある未申告施設等の核物質に対して、特別査察の適用を検討することは極めて重要であると考えられる。このため、我が国は、本年6月のIAEA理事会において、その重要性を強調し、特別査察の適用に当たっての具体的な手続きの明確化の必要性を主張した。
また、IAEAの限られた人的、財政的資源を効率的に活用するため、より効果的、効率的な保障措置を実施することが望まれる。また、非破壊装置による分析技術等保障措置分野の技術開発に積極的に取り組むとともに、開発された技術が広く加盟国の保障措置に適用されるよう、その実用化を促進していくことなどが必要である。
(核管理の適正化)
今後は更に、核管理の適正化、核軍縮が世界的に強く望まれており、我が国としても、積極的に対応していくことが重要となってきている。
2. 原子力開発利用の位置付けと国民の理解と協力 (1) 我が国における原子力開発利用の位置付け
世界のエネルギー需要は、開発途上国を中心に今後とも着実に増加していくものと見込まれている。これに対して、現在のエネルギーの中心である石油は、供給の不安定化による需給の逼迫化が懸念されている。また、限られた貴重な資源である石油は、開発途上国に、さらには後世代に残していくため、エネルギー源としての利用を抑制することが重要となっている。さらに、地球温暖化等の地球環境問題に対しても、エネルギー政策の面からの積極的対応が不可欠である。
一方、我が国は、これまでの石油代替エネルギーの開発・導入等の努力をしてきたが、主要先進国と比較すると、我が国のエネルギー供給構造の脆弱性が際だっている。また、エネルギー需要が近年高い伸びを示しており、今後とも大幅な増大が見込まれている。
このため、今後のエネルギー政策においては、エネルギーの安定供給、地球環境保全と経済の安定的発展との両立を目指して、①省エネルギーの推進、②石油依存度の引き続きの低減、③石油代替エネルギーの中でも非化石エネルギー(原子力、新エネルギー等)依存度の向上を柱とし、供給安定性、経済性、環境影響を総合的に勘案し、各エネルギー源の特長を最大限に活かした最適な組み合わせ(ベストミックス)を図ることが必要である。
この中で、まず、省エネルギーについては、さらに努力を継続していく必要があるが、相当の省エネルギーを見込んでも、今後の我が国エネルギー需要は増大していくものと予想されているのが現状である。
次に、太陽光、風力などの新エネルギーについては、賦存量が莫大であるとともに環境影響の面で有利であり、最大限の導入を図るべきエネルギー源として従来から積極的な研究開発が行われているが、量的確保、安定供給、経済性の面での課題も多い。新エネルギーは、急速かつ大幅な導入には制約があるのが現状であり、近い将来においては、補完的な役割を果たしていくものと考えられる。
原子力については、燃料であるウランが比較的世界に広く分布している等燃料の供給安定性が高いこと、また、国内における核燃料サイクルの確立により準国産エネルギーとも位置付けることが可能であることなど供給安定性の面で優れ、さらに、他の発電方式と比べて経済的に同等以上であるばかりか、長期的に見て価格の安定性が高いことなど、経済性の面で優れている。さらに、原子力発電はエネルギー収支が高く、二酸化炭素、窒素酸化物等を発電の過程において排出せず、また、燃料生産過程等を含めても、原子力の二酸化炭素排出量は他の発電方式と比較して非常に少なく、地球温暖化を始めとする地球環境問題の解決に当たって重要な役割を果たすものと考えられる。国際的にも、1991年7月のロンドン・サミット経済宣言、1991年3月のベルギー・フランス・ドイツ・英国の4カ国による原子力共同宣言において、この旨確認されている。国内的にも、地球温暖化防止行動計画(1990年10月策定)において、二酸化炭素を排出しないエネルギーとして、安全性の確保を前提に原子力の開発利用を推進すると位置付けられている。
従って、我が国においてベストミックスを図る上で、また、世界的にエネルギーの安全保障を図り、地球環境問題の解決に貢献するなど国際的な責務を果たす上で、供給安定性、経済性、環境影響の面で優れる原子力を今後とも我が国の主要なエネルギー源の一つと位置付け、安全の確保に万全を期しつつ、その開発利用を進めていくことが必要である。
また、原子力は、核燃料リサイクルの実現によって、その供給安定性をさらに高め、準国産エネルギーとも位置付けることが可能であり、資源の節約と再利用というリサイクル社会の形成に貢献し得る。
さらに、原子力は、技術によってエネルギーを生み出すことから、その供給安定性、経済性が外的要因ではなく主に技術によって決定されることに特徴があり、技術によりエネルギー源としての基盤を一層強固なものにできる。従って、科学技術立国を目指す我が国としては、この観点からも原子力開発利用を進める意義は大きい。
一方、原子力の開発利用は、安全の確保に万全を期すことを基本として進められている。また、高レベル放射性廃棄物の処理処分についても、着実に技術開発が進められ、実用化の技術的目途は得られつつあり、しかも、量的には非常に少ないことから、最適な処理処分技術の確立により管理は十分可能と考えられる。
このように、原子力は我が国において必要不可欠なエネルギー源であるが、最近の原子力発電所等の立地は長期化の傾向があり、今後の原子力開発利用の着実な推進のためには、安全のより一層の向上を図り、安全の確保に今後とも万全を期すとともに、国民の理解と協力を得つつ立地の円滑化を図っていくことが重要な課題である。
さらに、我が国としては、原子力開発利用は平和目的に限ることを国是として進めており、今後とも、核不拡散問題について国際的に懸念を招かないよう透明性に配慮するとともに、原子力平和利用を進める我が国の国際的責務として、IAEA保障措置の健全な発展と世界の核不拡散体制の強化に貢献していくことが重要である。
(2) 安全の確保と国民の理解と協力の増進
① 原子力に対する国民の理解と協力の現状と課題
(原子力反対運動の動向)
1986年のチェルノブィル原子力発電所事故は、事故自体が環境に影響を与える大きなものであったこと、食品が放射能に汚染されたことから、これまで原子力に無関心であった都市部の主婦・若年層を始め国民の一般層が、原子力発電に対する「疑念・不安」を感じるようになった。原子力に対する反対運動も、個別地点におけるものから、都市部を始めとする全国的な運動も多く見られるようになった。
1990年4月27日に、全ての原子力施設の廃止などを内容とする脱原発法制定請願が国会に提出されたが、審議未了で廃案となった。
また、青森県において、1991年前半に行われた国政選挙及び地方選挙においては、青森県で進められている核燃料サイクル施設計画が主要な争点の一つとされた。
本年2月9日、関西電力(株)美浜発電所2号炉の蒸気発生器伝熱管が破損し、日本で初めて非常用炉心冷却装置(ECCS)が実作動したことから、各地で原子力発電所の即時停止・点検等を掲げた反対運動が行われるとともに、市民集会が開かれた。
1991年4月26日には、脱原発法制定の第二次請願が計330万人の署名を集め、国会に提出されたが、審議未了で廃案となった。
(最近の世論の状況)
1990年に行われた総理府の世論調査によると、原子力発電の必要性については、「必要である」が64.5%、「必要でない」が20.7%となっている。また、今後の原子力発電の増減については、「慎重に増やす」が約44%、「現状維持」が約30%となっている。一方、原子力発電の安全性については、「安全ではない」と考える人(47%)が「安全である」と考える人(44%)よりも若干多い。また、放射線の人体への影響等の原子力に対して不安に思うほとんどの項目において、前回調査に比べ増加している。
(原子力に対する国民の理解と協力の増進のための活動の現状)
現在、国、地方自治体、事業者等によって、全国各地で開催される勉強会への講師の派遣、電話により質問に答えるテレフォン質問箱、パソコン通信相談室等の対話型の活動、施設見学会や自然放射線を実際に測定する実験セミナーの開催や簡易型放射線測定器の貸出等の体験型の活動を実施している。また、公開資料室等を通じて原子炉の設置許可申請書の閲覧等の情報の公開も実施されている。
さらに、これら全国的広報に加え、立地地域においても、国の担当官や専門家が、各地で説明会・座談会を実施するなど、地域の事情に応じた、懇切丁寧な広報を心がけている。
(美浜発電所2号炉蒸気発生器伝熱管損傷を踏まえた原子力に対する国民の理解と協力に向けた今後の方向)
本年2月に発生した関西電力(株)美浜発電所2号炉の蒸気発生器伝熱管損傷は、日本で初めて非常用炉心冷却装置(ECCS)が実作動したこと等から、国民に原子力発電に対する不安を抱かせる結果となった。通商産業省資源エネルギー庁が、1991年6月に発表した報告書によると、本損傷の原因は、振れ止め金具が設計通りの範囲まで入っていないこと等から、疲労破断したものと推察されている。本損傷は、安全運転実績の積み重ねの重要性を再認識させ、事業者、国等において、万全な安全の確保等に向けた努力が強化されつつある。
原子力発電所は、その運転により発生し蓄積される放射性物質が異常に漏洩した場合には周辺公衆に影響を及ぼしかねないという潜在的危険性を有している。この潜在的な危険性を現実のものとさせないように、平常運転時には放射性物質の放出を合理的に達成できる限り低くするよう管理し、万一の事故に際しては、放射性物質を閉じ込めることによって多量に放出されるのを防止するよう所要の対策を実施することが、安全確保の基本的な考え方である。
このため、原子力施設においては、①異常状態の発生を未然に防止する、②仮に異常状態が発生しても、それが拡大しないよう措置を講ずる、③万一事故状態になったとしても、放射性物質が周辺環境へ異常に放出されるのを防止するという多重防護の考え方に立って、安全の確保が図られている。さらに、④保安規定等に基づき厳格な安全管理や教育訓練を義務づける、⑤行政庁による一次審査や検査に加えて、原子力安全委員会によるダブルチェックを行う等厳格なチェック・監督体制を採るなどの対策を実施している。
このように、原子力施設においては、設計、施工から運転に至るまで、システム・体制全体として、安全を確保することとしている。この結果、我が国ではこれまで周辺公衆に影響を及ぼすような放射性物質の放出を伴う事故はないこと等から、我が国の原子力の安全性確保の水準は高いと考えられる。
本損傷においても、異常状態の進展を防ぎ放射性物質の外部への放出を抑え、環境に影響を与えるような事態の発生はなかった。これは、工学的安全性が保たれたことを意味しており、日本原子力研究所における試験装置での再現実験の結果においても、この旨確認されている。
しかし、事故・故障・トラブルは、それ自体が国民の不安を抱かせる原因となっていることから、安全確保対策の実施状況等について、理解を深めてもらうとともに、安全確保の実績を積み重ねること等により、国民の理解と協力を得るよう努力することが重要である。
② 国民の理解と協力の増進に当たっての重要課題
原子力に対する国民の理解と協力の増進に当たっては、以下の点に重点をおいた方策を進めることが重要となっている。
(イ) 安全確保の実績の積み重ね
国民の理解と協力を得るためには、まずは安全確保の実績を着実に積み重ねることが必要である。このため、今後とも厳重な安全規制と万全な運転・管理の実施、安全研究の充実・強化に積極的に取り組み、国民の信頼感を得られる管理体制の強化を図ることが重要である。また、近時、ヒューマンファクタ面での故障・トラブルが発生していることに鑑み、この面での安全性向上を図るととが重要である。こうした努力により、安全確保の実績を着実に積み重ね、国民の安心と信頼を確立していくことがまず何よりも重要である。
(ロ) 国民の信頼感の醸成
また、国民の理解と協力を得るためには、国、事業者に対する国民の信頼感を増していく努力が必要である。原子力の場合、相当詳細な情報が公開されているが、どのような情報も送り手と受け手の間に相互の信頼関係がなければ、正しく伝達されることはない。
このため、国、事業者は、引き続き、その時点で分かり得る情報を迅速、正確に提供することはもちろん、原子力の持つ潜在的危険性とそれを踏まえた安全管理体制、事故の状況等について、正確な理解を求めるとともに、日頃からの誠実な対応による信頼感の醸成が求められている。
(ハ) エネルギー需給状況に対する正確な理解の促進
本年当初の湾岸危機、我が国の電力需要の急激な増加、地球環境間題の顕在化等の状況の中、我が国においては、今や、国民一人一人がエネルギー問題や省エネルギーも含めた具体的かつ効果的な対応の在り方等について考えるべき時代に来ていると考えられる。
このため、エネルギーを取りまく問題について、広く国民に知らせ、国民一人一人にエネルギーの貴重さ、省エネルギーの必要性、エネルギー安定供給確保や地球環境問題解決の重要性等について考えるための情報提供が重要であり、一人一人がこの問題を総合的に考えていくための基盤作りが極めて重要となってきている。
③ 国民の理解と協力の増進のための活動の今後の方向
これまでの原子力に対する国民の理解と協力の増進のための活動を見ると、分かり易さについて不満足な面があったことは否定できない。このため、最近では、講師派遣等により対話を重視した広報活動など、より分かり易い形での情報提供を進めているところであるが、さらに、受け手の立場に立って、分かりやすい説明を心がけていくことが必要である。
また、国民にとって、放射線の性質等が実感できないことも理解と協力の増進を図る上での障害となっていると言える。このため、今後は、国民に原子力施設を実際に見てもらう機会をさらに一層増やしていくことが重要である。また、直接見ることのできない内部構造等については、模型やビデオ等を活用することなどが必要である。
原子力に対する不安の主要要因となっている放射線については、自然放射線の形で身近に存在していること、放射線が様々な分野で広く利用されて国民生活の向上に貢献していることなど、放射線に関する正確な理解を求めていくことが重要である。
また、原子力に対する国民の理解の上で、報道機関が果たす役割は非常に大きい。このため、報道関係者に対する原子力に関する正確な情報の提供にも特に留意していくことが重要である。
さらに、原子力施設の立地が地域社会の発展に寄与するとともに、地元住民の生活と共存共栄している例は多く、こうした実例についても理解を深めてもらうことが重要と考えられる。
他方、未来を担う青少年に対して科学教育等の場において正確な知識の普及を行うことを始め、社会人等に対してもエネルギーや原子力に対する学習の機会を広く提供することなどにより、エネルギー全般について、国民一人一人に考えてもらうための基盤作りに向けた息の長い努力が必要である。
第2章 我が国における原子力開発利用の現状 1. 我が国における原子力発電の現状 (1) 軽水炉等による原子力発電の動向
① 原子力発電の現状
我が国の原子力発電は、1991年5月末現在、新型転換炉原型炉を含めると、41基、3,222万4千キロワットとなっている。これに建設中及び建設準備中のものを含めた合計は、研究開発段階発電炉を含めると、55基、4,635万3千キロワットである。
原子力発電は、1990年度末現在、総発電設備容量(電気事業用)の18.0%、1990年度実績で、総発電電力量(電気事業用)の26.6%を占め、主力電源として着実に定着してきている。また、1990年度の設備利用率は、72.7%で、8年間続いて70%台の高い水準で推移してきている。
② 原子力発電の経済性
通商産業省の試算結果では、原子力発電が9円/キロワット時程度、石炭火力及びLNG火力発電が10円/キロワット時程度、石油火力発電が11円/キロワット時程度となっており、原子力発電は他の電源と同等以上の経済性を有する電源となっている。
③ 立地の促進等
政府及び事業者は、原子力施設の立地を促進するため、各種メディア、原子力モニター制度等を活用して、地元住民を始めとする国民の理解と協力を得るための努力を重ねている。
また、立地地域の振興対策の拡充を図るため、電源三法の活用等が逐次図られている。
④ 軽水炉技術の研究開発
我が国では、自主技術による軽水炉の信頼性等を目指し、軽水炉の改良標準化計画を第1次から第3次まで実施してきた。第3次計画においては改良型軽水炉(AJWR)の開発が進められ、東京電力(株)柏崎刈羽原子力発電所6、7号炉は、このALWRの初号炉である。
また、1991年6月、総合エネルギー調査会原子力部会軽水炉技術高度化小委員会は、報告書をとりまとめ、今後の軽水炉技術の開発に当たっては、安全性確保の更なる取組として、故障・トラブル対策の高度化等を挙げている。
⑤ 原子炉の廃止措置
原子炉の廃止措置に関する技術開発については、1990年代後半に向けて技術の向上を図ることとしており、日本原子力研究所が1986年度から動力試験炉(JPDR)の解体実地試験を行っており、1991年2月から放射線遮蔽体の解体作業に着手している。また、(財)原子力工学試験センターは、安全性、信頼性の観点から特に重要な技術について確証試験を進めている。さらに、(財)原子力施設デコミッショニング協会は、研究開発用の原子力施設の廃止措置に関する研究成果の蓄積・普及等を行っている。
(2) 核燃料サイクルの確立
① 核燃料サイクル事業化の進展
我が国の核燃料サイクルの研究開発については、動力炉・核燃料開発事業団及び日本原子力研究所を中心として進められてきたが、核燃料の再転換・成型加工については、既に民間において多くの実績を積み重ねている。また、ウラン濃縮、軽水炉使用済燃料再処理、低レベル放射性廃棄物埋設等についても事業化の段階を迎えている。
ウラン濃縮施設については、日本原燃産業(株)が、1991年度の操業開始に向けて建設を進めている。低レベル放射性廃棄物埋設施設については、日本原燃産業(株)が、1990年11月に許可を受けて建設に着手した。軽水炉使用済燃料の再処理施設、海外から返還される高レベル放射性廃棄物の貯蔵施設については、科学技術庁における安全審査が終了し、現在、原子力委員会及び原子力安全委員会によるダブルチェック中である。
② ウラン濃縮
我が国におけるウラン濃縮の国産化については、動力炉・核燃料開発事業団が中心となってその研究開発を進めてきた。同事業団は、200トンSWU/年の原型プラントの操業している。日本原燃産業(株)は、この成果に基づき、1988年10月、青森県六ケ所村に商業プラントの建設を開始し、1991年度に操業開始を予定している。
動力炉・核燃料開発事業団は、新素材高性能遠心機の研究開発に関して、民間との協力により実用規模カスケード試験装置を建設・運転することとしている。
一方、ウラン濃縮に関する新技術としては、日本原子力研究所及びレーザー濃縮技術研究組合において原子レーザー法の研究開発が、また、動力炉・核燃料開発事業団及び理化学研究所において分子レーザー法の研究開発が進められている。その他、化学法についても、開発が進められてきた。
このような新技術の研究開発の進展を踏まえ、1991年7月に原子力委員会はウラン濃縮懇談会において、新技術に係る評価検討等に関する調査審議を行い、ウラン濃縮の長期的進め方等について総合的な調査審議を行うことを決定した。
③ 軽水炉使用済燃料再処理
これまで動力炉・核燃料開発事業団の東海再処理工場は、1977年9月にホット試験を開始し、順調に操業を継続しており、1990年度末までの累積再処理量は約527トンUに達している。
我が国で発生する使用済燃料の再処理については、このほか、英国及びフランスにも委託しており、1990年度末までには、軽水炉使用済燃料約3,900トンUが両国に、ガス炉使用済燃料約1,100トンUが英国に運ばれている。
日本原燃サービス(株)の再処理工場(処理能力は年間800トンU)については、1990年頃の操業開始を目指して、建設する計画である。再処理事業の指定については、科学技術庁における安全審査が終了し、現在、原子力委員会及び原子力安全委員会によるダブルチェック中である。
④ 放射性廃棄物処理処分
〔低レベル放射性廃棄物〕
原子力発電所等において発生する低レベル放射性廃棄物のうち、気体及び一部の液体廃棄物については、所定の濃度以下であることを確認し、大気中または海水中に放出している。その他の液体及び固体廃棄物については、発生量を極力低減した後、焼却等により適切な処理を行って、各発電所等の敷地内に安全な状態で貯蔵されている。1991年3月末現在、その累積量は、200リットルドラム缶に換算して約78万本分となっている。
低レベル放射性廃棄物の陸地処分については、日本原燃産業(株)が1992年の操業開始を目指して、青森県六ケ所村に低レベル放射性廃棄物埋設施設を建設している。
〔高レベル放射性廃棄物〕
高レベル放射性廃棄物については、これまでの動力炉・核燃料開発事業団の東海再処理工場で発生したものが、厳重な管理の下に同工場のタンク内に貯蔵され、1991年3月末現在、その累積量は溶液の状態で、428m2となっている。
これらの高レベル放射性廃棄物については、ステンレス製の容器に安定な状態にガラス固化し、30~50年間程度冷却のための貯蔵を行った後、地下数百メートルより深い地層中に処分することを基本的な方針としている。
ガラス固化技術については、動力炉・核燃料開発事業団が中心となって研究開発を行い、ガラス固化プラントの建設を進めている。
地層処分については、動力炉・核燃料開発事業団を中核推進機関として研究開発・調査を行い、その後、処分事業の実施主体が選定する処分予定地における処分技術の実証を経て、処分場の建設・操業等へと進んで行く計画である。動力炉・核燃料開発事業団の北海道幌延町における貯蔵工学センター計画は、地層処分のための研究開発等を行う総合研究センターを目指したものであり、円滑な実施に配慮しつつ、その着実な推進を図っていくこととしている。
また、1989年6月から、核種分離・消滅処理技術の情報交換計画(通称:オメガ計画)が経済協力開発機構/原子力機関(OECD/NEA)において開始され、1990年11月には、第1回情報交換会議が我が国において開催された。
原子力委員会は、1991年6月、今後の高レベル放射性廃棄物対策の進め方全般について検討を行うこと等を目指し、放射性廃棄物対策専門部会において調査審議を開始することを決定した。これを受け、同専門部会が調査審議を進めている。
〔その他〕
使用済燃料の再処理、ウラン・プルトニウム混合酸化物(MOX)燃料の加工の過程で発生するTRU核種を含む放射性廃棄物については、適切な区分と、その区分に応じた合理的な処分方策を確立することとしている。これを受け原子力委員会放射性廃棄物対策専門部会は、1991年7月、TRU核種を含む放射性廃棄物の区分の考え方、処分方策の具体化の手順等を示した報告書を取りまとめた。
(3) プルトニウム利用への展開
我が国においては、ウラン資源の有効利用、エネルギーの安定供給の確保等のため、使用済燃料の再処理により得られるプルトニウムの利用体系の確立が重要である。
原子力委員会核燃料リサイクル専門部会は、1989年12月に「プルトニウム返還輸送の当面の進め方について」を取りまとめ、1991年8月には、2010年頃までを見通した長期的視野から核燃料リサイクルの具体的方策を提示した「我が国における核燃料リサイクルについて」を取りまとめた。「我が国における核燃料リサイクルについて」においては、今後とも、ウランの利用効率が高い高速炉(FBR)の実用化を目指すこととし、当面主流である軽水炉におけるプルトニウム利用、実用規模の核燃料リサイクルに必要な技術、体制等の整備が必要であり、さらに、核燃料利用の面で融通性に富む新型転換炉(ATR)におけるプルトニウム利用を進めることが適当であるとしている。
① 軽水炉におけるプルトニウム利用及び新型転換炉
我が国における軽水炉によるプルトニウム利用(プルサーマル)は、電気事業者を中心に進められており、現在、MOX燃料少数体規模実証計画が進められている。
新型転換炉(ATR)の開発は、動力炉・核燃料開発事業団の原型炉「ふげん」が順調に運転されているとともに、電源開発(株)が2000年の運転開始を目指して、青森県大間町において、ATR建設のための準備を進めている。
② 高速増殖炉
高速増殖炉(FBR)の開発は、動力炉・核燃料開発事業団が、実験炉「常陽」の運転により蓄積してきた運転経験等を踏まえ、福井県敦賀市に原型炉「もんじゅ」の建設を進めており、1992年の臨界を目途に総合機能試験を行っている。
実証炉については、1990年6月、電気事業者は、当面トップエントリー方式ループ型炉の技術的成立性の確認を主たる目的とした実証炉の予備的概念設計研究を進めていくことを決定し、現在、日本原子力発電(株)において、1992年3月の完了を目指して進められている。なお、動力炉・核燃料開発事業団と日本原子力発電(株)の間で、1989年3月、「高速増殖実証炉の研究開発に関する技術協力基本協定」が締結され、具体的協力を進めている。
③ 高速増殖炉使用済燃料の再処理
高速増殖炉に不可欠な再処理技術については、動力炉・核燃料開発事業団において、基礎的データの蓄積等が図られている。今後の研究開発については、高速増殖炉の開発と整合性を図りつつ、ホット工学試験施設における試験を経て、2000年過ぎの運転開始を目途にパイロットプラントを建設することとしている。
④ MOX燃料加工
MOX燃料加工については、原子燃料公社(現動力炉・核燃料開発事業団)が1966年にMOX燃料製造の技術開発に着手して以来、動力炉・核燃料開発事業団が行ってきている。1991年3月末現在、累積製造実績は107トンMOXを達成している。現在、新型転換炉実証炉用燃料製造施設(40トンMOX/年)の建設計画が進められている。
また、軽水炉用MOX燃料加工の国内事業化の推進のためには、動力炉・核燃料開発事業団の有する技術の民間事業者への円滑な移転等を行う必要があるため、動力炉・核燃料開発事業団の施設活用等について、早急に検討を進める必要がある。なお、海外再処理により回収されるプルトニウムについては、一定期間の間、適切な量について、海外でMOX燃料加工を行うことが適当であり、そのための検討を進めることが必要である。
⑤ プルトニウムの輸送
1989年12月の原子力委員会核燃料リサイクル専門部会で、当面の国際輸送は海上輸送で行うこと、1992年秋頃までには輸送を実施すること等を内容とした報告書を取りまとめた。
現在、海上輸送の円滑な実施に向け、実施主体である動力炉・核燃料開発事業団が中心となって具体的な輸送計画の作成を進めるとともに、護衛のための巡視船の建造を海上保安庁において進めるなど、関係機関が協力して準備を行っている。
2. 放射線利用の現状と今後の展望 (1) 私たちを取り巻く放射線
① 放射線の種類と性質
放射線には、さまざまな種類がある。放射線は、それが人工的に作られたものか天然に存在するものかによらず、種類とエネルギーが同じであれば、本質的に同一のものである。
放射線と物質の相互作用を利用して、材料改質等に役立てられている。一方、放射線が物質を透過する性質を利用して、非破壊検査等に広く用いられている。その他、放射線が散乱される性質を利用して、物質の結晶構造などの決定にも利用されている。
② 身の回りの放射線
自然界には、炭素14、カリウム40、ウラン238、ラドン222、ラジウム226等多数の放射性同位元素が存在している。さらに、太陽等を起源として宇宙線が飛来している。
自然放射線を受ける量は、1988年、国連科学委員会報告によれば、空気中のラドン等による被ばくを考慮すると、一般人の世界平均で一年間に2.4ミリシーベルト(mSv)であり、医療放射線量等を合計すると、約2.8~3.4ミリシーベルトと試算されている。なお、自然放射線を受ける量は地域によって異なっており、日本国内では、花崗岩地帯の多い関西地方が高く、関東地方は低いという傾向がある。
X線は、医療分野でレントゲン検査等の診断で広く用いられ、γ線、電子線等の放射線は工業分野等の多彩な分野で有効に利用されている。
このように、私たちは自然の放射線に囲まれて生活しており、また、放射線を積極的に利用することは、国民生活の向上、経済の発展に役立てられている。
(2) 放射線利用の現状
① 医療分野における利用
医療分野において、放射線は診断と治療の両面で利用されていることに加え、医療用具の滅菌に役立っている。
診断においては、最も広く普及している胸・胃・骨等のX線撮影を始めとして、X線コンピュータ断層撮影(X線CT)などが利用されている。また、核医学検査には、被検者の体内に放射性医薬品を投与し、体外から計測を行うインビボ検査と、被検者から採取した血液、尿などの試料に放射性医薬品を加え、ホルモン等の微量な成分を、定量するインビトロ検査がある。インビボ検査のうち、測定結果をコンピュータにより画像処理するECT(エミッション・コンピューテッド・トモグラフィ)は、放射性同位元素の種類により、SPECT(シングル・フォトン・エミッション・コンピューテッド・トモグラフィ)とポジトロンCTの二種類がある。インビトロ検査の方法としては、ラジオイムノアッセイ(放射免疫測定法)が主として用いられている。
治療については、放射線によるがん治療が実用化されている。γ線、X線等を体外から照射する方法はがん治療全般に、体内にγ線源を入れ、γ線を照射する方法は、舌がん、子宮がんたどの治療に、また、放射性医薬品を投与し、放射性同位元素からのβ線、γ線を照射する方法は、甲状腺がん等の治療にそれぞれ用いられている。さらに、現在、中性子線、陽子線を利用した治療に関する研究も行われており、放射線医学総合研究所においては、重粒子線を用いたがん治療法の研究開発及び重粒子線がん治療装置の建設が進められている。この他、京都大学、日本原子力研究所等の研究炉を用いて、脳腫瘍等に中性子線を照射する医療照射による治療が行われた実績がある。
医療用具の滅菌においては、包装してから滅菌が可能であること、化学殺菌のような残留有害物がないことなどから、透過力の大きいγ線により、メス、縫合糸、人工透析器等の医療器具の滅菌が行われている。
② 農業分野における利用
農業の分野では、品種改良、害虫防除、食品照射等に放射線が利用されている。
植物の品種改良については、密封のコバルト60線源によるγ線照射で、すでに100種に及ぶ品種が改良され、風害に強いイネ、生育の早い大豆等の新種が生まれている。
害虫防除については、1972年から不妊虫放飼法によるウリミバエの根絶防除を鹿児島、沖縄両県で実施しており、鹿児島県の奄美群島全域と沖縄県の久米島、宮古群島等で根絶に成功している。
食品への放射線照射は、我が国では、馬鈴薯等の7品目の安全性、照射効果等の研究成果がとりまとめられ、公表されている。現在、我が国で実用化されているのは馬鈴薯であり、1974年から、北海道士幌町で発芽防止のための照射が行われている。
③ 工業分野における利用
工業の分野では、γ線、中性子線等を用いて厚さ、密度、水分含有量の精密な測定を行うことにより、各種工程管理に広く利用され、また、鉄鋼、航空機製造等では、非破壊検査に放射線が用いられている。さらに、電線被覆材の改良等、各種高分子材料の改質に電子線やγ線が利用されている。
放射線の透過の性質の利用については、製鉄所における厚さ測定やセロハン、アルミホイル、ラッピングフィルム、ゴム、紙等の製造の工程管理に利用されている。この他、構造材料のひび割れ等を調べる非破壊検査が挙げられる。
放射線と物質との相互作用の利用については、材料に放射線を照射することにより、耐熱性、強度、耐摩耗性等が向上するので、材料の品質改良に役立てられている。例えば、電線の被覆材の耐熱性向上や自動車タイヤの成型時の型くずれ防止等、発泡ポリオレフィンの発泡の容易化、瓦等の表面塗装材の硬化にも、放射線が利用されている。
④ 研究、調査等における利用
放射線は、遺伝子等の染色体上の位置の決定、植物に対する施肥の研究に役立てられている。中性子と核反応して放射線を放出するユーロピウムは、サケの回遊等の調査に用いられる。
考古学の分野における炭素14の崩壊状況の測定による年代の推定や、さらに、岩石の年代推定などに、放射線は利用されている。
また、地下水中のラドン濃度と地震との関連が研究されているほか、宇宙線の量を計測することにより、遠隔地の積雪量を自動計測することに用いられる。
〔第5図〕 各分野における放射線の利用例 (3) 放射線利用の安全確保
放射線の取扱いに当たっては安全の確保に十分な注意が必要である。
国際放射線防護委員会(ICRP)では放射線防護の観点から放射線の利用において守るべき3項目(①正当化、②最適化、③線量当量限度)を勧告している。
我が国においては、放射線防護基準策定の際にはICRPの勧告を尊重して、放射線審議会での検討を踏まえた法令が施行されている。
放射性同位元素等の取扱いに伴う安全性の確保については、「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」等に基づき許認可等の厳正な審査、立入検査、監督指導等所要の規制が行われている。
(4) 放射線利用分野における国際協力
放射線利用の分野における主な国際協力として以下のものがある。
① IAEA/RCA
アジア、太平洋地域の国際原子力機関(IAEA)加盟国間の原子力科学技術の研究開発等の推進・協力を目的とする「原子力科学技術に関する研究、開発及び訓練のための地域協力協定」(RCA)の計画の下、現在、我が国は、放射線工業利用等の3分野に対して積極的な協力を行っている。
② 二国間協力
日本原子力研究所が中心となり、インドネシア原子力庁、タイ原子力庁、マレーシア原子力庁との間で放射線利用等に関する研究がそれぞれ行われている。
③ 原子力研究交流制度に基づく協力等
日本の研究所と開発途上国の研究所間で研究者の交流を行う研究交流制度により、放射線の医学利用等の分野で、研究者の受け入れ、派遣等の研究協力が行われている。
この他、1989年から、国際協力事業団により、マレーシアにおいて医療器具の滅菌等の放射線利用研究プロジェクトが実施されている。
(5) これからの放射線利用
① 放射線利用関係の研究開発の動向
イオンビームは、半導体を始めとして金属表層の改質等の材料科学等の研究分野で注目されており、日本原子力研究所では、核融合炉材料等の耐環境性極限材料等の研究開発へのイオンビーム利用を積極的に進めるため、1987年から6年計画で、同研究所の高崎研究所においてイオン照射研究施設を建設している。
放射線医学総合研究所では、重粒子線による効果的ながん治療に関する研究開発、重粒子線がん治療装置の建設が進められている。
理化学研究所では、重イオン科学研究を進めるため、リングサイクロトロンを建設・運転しており、1989年7月には世界最高の加速性能を達成している。
一方、放射光は、物質の構造解析の飛躍的発展等の様々な分野での利用に期待が寄せられているため、日本原子力研究所及び理化学研究所が共同し、兵庫県播磨科学公園都市に1998年の供用開始を目指して、大型放射光施設(SPring-8)の建設を推進している。
この他、日本原子力研究所では、電子線を利用した脱硫・脱硝技術の実用化を目指し、石炭火力発電所においてパイロット試験を実施しているほか、下水処理で発生する汚泥の放射線処理による殺菌技術等の開発が進められている。また、東京都立アイソトープ総合研究所では、γ線等による下水汚泥の脱水効率向上の研究が行われている。
② 放射線利用の今後の方向と課題
医療・農業・工業分野において放射線利用が着実に拡大されることが望まれる。また、新たな放射線利用の分野は、今後とも積極的に研究開発を実施することが重要である。さらに、環境保全を目的とした放射線利用についての研究開発を積極的に進めることも重要である。
一方、今後の拡充に対応して、放射線防護の観点から、十分な安全管理施設、専門的知見を有する人材の確保、管理体制の充実、放射性廃棄物の処理処分対策等の基盤整備が重要である。
なお、放射線の利用を進めるに際しては、国民の理解と協力が重要であり、引き続き放射線利用に関する正しい知識の提供が必要である。
3. 原子力研究開発の推進 (1) 核融合研究開発の推進
日本原子力研究所は、トカマク型臨界プラズマ試験装置(JT-60)において、プラズマ閉じ込め性能の一層の向上性を目指し、1989年11月から大電流化及び重水素使用のための装置の改造、施設整備を進め、1991年3月、高性能化実験(Ⅱ)を開始した。また、炉工学技術の開発研究を行うとともに、次期大型装置の設計検討を進めている。
核融合科学研究所では、大型ヘリカル装置の製作を推進しており、大学等においても、各種閉じ込め方式による先駆的・基礎的研究を行っている。
また、日本原子力研究所は、日本、米国、EC、ソ連の4極による国際熱核融合実験炉(ITER)の設計活動等の核融合の国際協力に積極的に参加している。
一方、低温核融合研究が発表されてから世界各地でその現象の再現が試みられてきたが、その現象は再現性に欠け、また、散発的であるため、核融合反応かどうか確認されていないが、低温核融合現象の解明、実証の追試験が引き続き行われている。
(2) 高温工学試験研究
日本原子力研究所において、高温工学試験研究炉の建設が1991年3月から進められている。また、高温ガス炉技術に関する各種の研究開発が行われ、高温工学試験研究炉から取り出される高温ガスの利用として、水素製造の研究開発が行われている。
(3) 原子力船
日本原子力研究所の原子力船「むつ」は、1990年からの4次にわたる航海により、同年12月に出力上昇試験及び海上試運転をすべて終了し、本年2月、関係法令に基づく証書の交付を受け、日本初の原子力船として完成した。現在、実験航海を実施しており、出力上昇試験から第3次実験航海までの原子動力航行距離は約64,000Kmとなっている。実験航海終了後「むつ」は関根浜定係港において解役する予定である。
また、「むつ」により得られる実験データ等の成果を活用しつつ、船舶炉の改良研究を実施している。
(4) 基礎研究及び基盤技術開発
基礎研究については、日本原子力研究所、大学国立試験研究機関等が、炉物理・核物理に関する研究、放射線に関する生理学研究、燃料・材料の照射試験、放射性物質の環境中及び生態系中の移動に関する研究等を幅広く行っている。
21世紀に必要とされる原子力技術体系の構築を目指す基盤技術開発が、日本原子力研究所、動力炉・核燃料開発事業団、理化学研究所及び国立試験研究機関において、現在、原子力用材料技術、原子力用人工知能技術、原子力用レーザー技術、放射線リスク評価・低減化技術の4領域について1988年度から進められている。このうち、複数の研究機関のポテンシャルを結集すれば効率的・効果的に進めることが可能な課題について、各研究機関の連携の下に「原子力基盤技術総合的研究」を1989年度から実施している。また、原子力用材料開発に関する共有データベースの構築等多機関間の交流による研究開発が積極的に進められている。
また、基礎研究、人材育成に関し、日本学術会議の原子力工学研究連絡委員会は、1991年6月「原子力工学教育に対する社会的要請と今後の研究課題」と題する報告書を取りまとめ、今後の教育研究体制について、①重点化研究の推進、②学外の原子力施設の活用等国内外における教育研究協力体制の整備を提言している。
(5) 新しい型の原子炉の研究
高転換軽水炉、中小型安全炉、モジュール型液体金属炉等の新しい型の原子炉については、将来の原子炉技術のブレークスルーの可能性を検討するため、基礎的・基盤的研究が幅広くかつ段階的に進められている。
4. 国際社会への主体的貢献 (1) 国際協力の推進
① 先進国との協力
先進国との協力については、日本原子力研究所、動力炉・核燃料開発事業団等が中心となり、米国、ドイツ、フランス、イギリス等の原子力開発利用先進諸国と軽水炉、高速増殖炉、再処理等の多岐の分野で情報交換、人材交流、研究協力等の二国間協力を積極的に行ってきている。また、1991年4月には、日ソ原子力協力協定、チェルノブイル原子力発電所事故に係る協力に関する覚書を締結した。
また、二国間協力以外に、協定等に基づく政府レベルの多国間協力や国際機関を通じた協力については、原子力発電所の安全面の協力、高速増殖炉開発に関する協力等に加え、原子力分野の最先端技術研究開発の協力にも取り組んでいる。
国際機関を通じた協力として、国際原子力機関(IAEA)の支援の下で1988年4月より開始した日本、米国、EC、ソ連の4極共同による国際熱核融合実験炉(ITER)の概念設計が1990年12月に終了した。次の段階である工学設計活動については、1991年2月より4極協議を進めてきた結果、7月の第3回会合において、共同設計サイトを、日本国茨城県那珂町(日本原子力研究所那珂研究所)、米国カリフォルニア州サンディエゴ、ECドイツ・ガルヒンクの3カ所に設置すること等が実質的に合意された。
この他、旧型のソ連製加圧水型軽水炉の安全性評価に関するIAEAの特別プロジェクトに、我が国では、日本人専門家の派遣等を通じた協力を実施している。
また、高レベル放射性廃棄物の核種分離・消滅処理技術に関して、我が国は、情報交換による国際協力計画を、経済協力開発機構/原子力機関(OECD/NEA)において、オメガ計画として発足させた。1990年11月には、第1回情報交換会議が我が国で開催された。
民間における国際協力においては、電気事業者間の情報交換を行う世界原子力発電事業者協会(WANO)が設立され、1989年4月より東京にアジア地域のセンター(東京センター)が発足し、現在、各地域センター間で原子力発電所の交換訪問が行われている。
また、我が国は現在、IAEA、OECD/NEAに、事務局職員を派遣し機関の運営や政策の決定に貢献するとともに、WANOにおいても、総裁に選出されるなど人的貢献を着実に進めてきており、今後とも、より一層の人的貢献が期待される。
② 開発途上国等との協力
現在、我が国は、インドネシア、マレイシア、タイ、韓国、中国等と研究利用、放射線利用、安全研究、廃棄物処理処分、ウラン鉱資源調査等の分野で協力を行っている。
また、国際原子力機関(IAEA)の支援の下で実施されている「原子力科学技術に関する研究開発及び訓練のための地域協力協定(RCA)」を1978年に締結し、積極的に広くアジア・太平洋地域との協力を行っている。
近隣アジア諸国における地域協力については、原子力委員会の主催で、昨年に引き続き1991年3月に第2回アジア地域原子力協力国際会議が東京で開催された。
また、韓国との間では、1990年5月、原子力発電所の安全性、放射線防護、放射線の利用等の分野における情報交換、専門家交流、共同研究等を内容とする日韓原子力協力取極が締結され発効した。
(2) 核兵器の不拡散の強化と我が国の役割
① 核不拡散体制の強化
フランスとの間で1972年に締結された日仏原子力協力協定については、平和的非爆発目的使用の明記等を盛り込んだ改正議定書が1990年7月に発効した。
一方、多国間では、1970年に発効した「核兵器の不拡散に関する条約」(NPT)があり、1991年7月に開催されたロンドン・サミットにおいても、その重要性を再確認するとともに、全ての非署名国に対し、同条約に署名するよう要請している。また、第4回の再検討会議が1990年8~9月にジュネーブで開催され、最終文書の採択に至らなかったものの、核兵器の不拡散及び原子力の平和利用に関しては、実り多い議論がなされ、実質的な各国の合意が得られた。
② 保障措置
近年、原子力開発利用の進展によるプルトニウム取り扱い量の増大に伴い、保障措置の効果的かつより一層の効率的適用を図ることが重要となってきていることから、我が国は1981年度より「対IAEA保障措置支援計画(JASPAS)」を行っており、また、1986年度からは、IAEAに対し特別拠出金を拠出し、商業用大型再処理施設に対する保障措置適用に関する検討を行うLASCAR(大型再処理施設保障措置)プロジェクトを進めるなど、IAEA保障措置体制の維持強化に積極的に貢献している。
③ 核物質防護
我が国においては、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」の一部改正を行い、国内体制を整備した上、1988年10月に核物質の防護に関する条約に加入書を寄託し、同条約は同年11月に我が国について効力を生じた。
さらに、同条約は、責任を有する自国の中央当局及び連絡上の当局を明らかにすることを義務づけており、我が国は、1991年1月、科学技術庁を中央当局、外務省を連絡上の当局として、IAEAに登録した。
|
| 前頁 | 目次 | 次頁 |