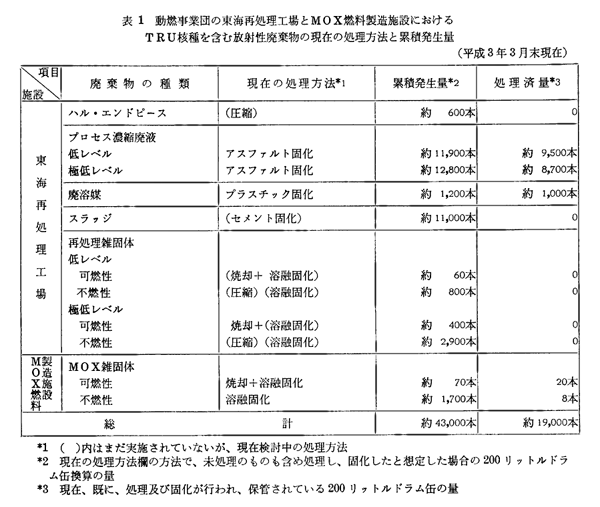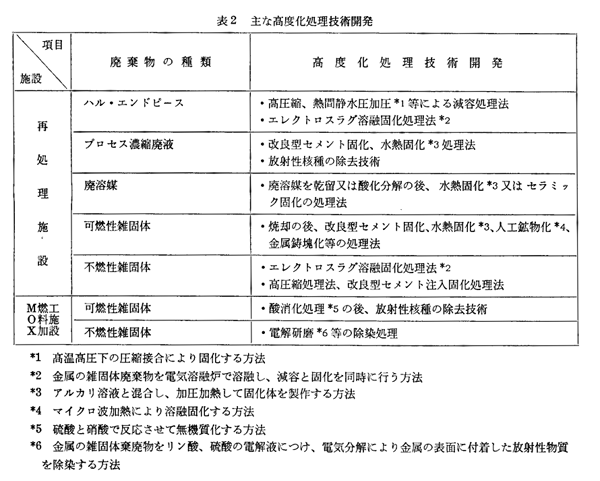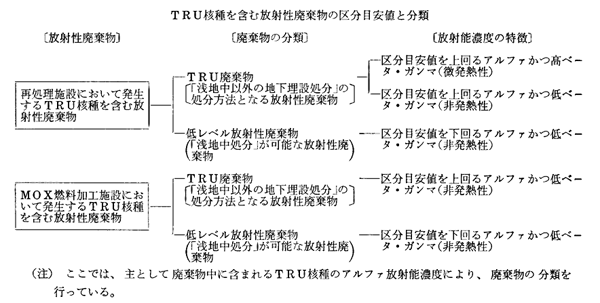| 目次 | 次頁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
委員会の動き 定例及び臨時会議 第27回(臨時) 〔日時〕1991年7月5日(金)10:00~
〔議題〕
(1) 原子力委員会専門委員の変更について
(2) その他
〔審議事項〕
(1) 議事録の確認
事務局作成の資料「第26回原子力委員会臨時会議議事録」が了承された。
(2) 原子力委員会専門委員の変更について
標記の件について、事務局から資料に基づき説明がなされ、了承された。(資料1)
第28回(臨時) 〔日時〕1991年7月12日(金)10:30~
〔議題〕
(1) 中国電力株式会社島根原子力発電所の原子炉の設置変更(1号及び2号原子炉施設の変更)について(諮問)
(2) 日本原子力研究所大洗研究所における廃棄物管理の事業の許可について(一部補正)
(3) その他
〔審議事項〕
(1) 議事録の確認
事務局作成の資料「第27回原子力委員会臨時会議議事録」が了承された。
(2) 中国電力株式会社島根原子力発電所の原子炉の設置変更(1号及び2号原子炉施設の変更)について(諮問)
平成3年6月24日付け2資庁第14470号をもって通商産業大臣から諮問を受けた標記の件について、通商産業省から資料に基づき説明がなされ、引き続き審議することとした。
(解説) 本件は、燃料の効率的な使用等を図るため、高燃焼度8×8燃料を使用すること等を行うものである。
(3) 日本原子力研究所大洗研究所における廃棄物管理の事業の許可について(一部補正)
平成3年7月9日付け3安第252号をもって内閣総理大臣から通知を受けた標記の件について、科学技術庁から資料に基づき説明がなされ、引き続き審議することとした。
(解説) 本件は、平成3年3月6日付け2安第206号をもって諮問のあった標記申請について、添付書類の記述の適正化を図るため一部補正をするものである。
第29回(臨時) 〔日時〕1991年7月19日(金)10:30~
〔議題〕
(1) 動力炉・核燃料開発事業団大洗工学センターの原子炉の設置変更(高速実験炉原子炉施設の変更)について(一部補正)
(2)その他
〔審議事項〕
(1) 議事録の確認
事務局作成の資料「第28回原子力委員会臨時会議議事録」が了承された。
(2) 動力炉・核燃料開発事業団大洗工学センターの原子炉の設置変更(高速実験炉原子炉施設の変更)について(一部補正)
平成3年7月15日付け3安(原規)第377号をもって内閣総理大臣から通知を受けた標記の件について、科学技術庁から資料に基づき説明がなされ、引き続き審議することとした。
(解説) 本件は、平成3年3月20日付け2安(原規)第674号をもって諮問のあった標記申請について、添付書類の記述の適正化を図るため一部補正をするものである。
第30回(定例) 〔日時〕1991年7月30日(火)10:30~
〔議題〕
(1) 放射性棄廃物対策専門部会報告について
(2) ウラン濃縮懇談会について
(3) 動力炉・核燃料開発事業団大洗工学センターの原子炉の設置変更(高速実験炉原子炉施設の変更)について(答申)
(4) その他
〔審議事項〕
(1) 議事録の確認
事務局作成の資料「第29回原子力委員会臨時会議議事録」が了承された。
(2) 放射性棄廃物対策専門部会報告について
標記の件について鈴木専門委員から資料「TRU核種を含む放射性廃棄物の処理処分について(案)」に基づき報告がなされ、了承された。(資料2)
(3) ウラン濃縮懇談会について
標記の件について事務局から資料「今後のウラン濃縮技術開発に関する評価検討の進め方について(案)」に基づき説明がなされ、「ウラン濃縮懇談会の設置について」(昭和60年12月17日付け原子力委員会決定)を改定することを決定し、新技術の評価検討に当たっては、客観性の確保に配慮することとされた。(資料:委員会決定等)
(4) 動力炉・核燃料開発事業団大洗工学センターの原子炉の設置変更(高速実験炉原子炉施設の変更)について(答申)
平成3年3月20日付け2安(原規)第674号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認め、内閣総理大臣あて答申することを決定した。(資料3)
(解説) 本件は、照射試験能力の向上を図るため、炉内制御棒配置を変更した制御棒非対称配置炉心を追加し、新材料の照射データ取得のため、高速炉用フェライト系ステンレス鋼を被覆管材料等に用いたⅣ型特殊燃料要素を追加すること等を行うものである。
資料1
原子力委員会専門委員の変更について
1991年7月5日(金)
原子力委員会
1. 原子力委員会専門委員澤田一朗の辞任を認め、新たに成瀬喜代士氏を専門委員に任命し、林原子力委員の特命事項を調査審議させることとする。 2. 上記に伴い、所要の手続きを取ることとする。 以上
資料2
TRU核種を含む放射性廃棄物の処理処分について
平成3年7月30日
原子力委員会
放射性廃棄物対策専門部会
1. はじめに 使用済燃料の再処理とウラン、プルトニウム混合酸化物燃料(MOX燃料)の加工の過程で発生する放射性廃棄物は、ベータ・ガンマ核種のほかにアルファ核種である半減期の長いTRU核種も含んでおり、この放射性廃棄物から高レベル放射性廃棄物を除いたものを「TRU核種を含む放射性廃棄物」という。
TRU核種を含む放射性廃棄物については、昭和62年の原子力委員会の「原子力開発利用長期計画」において、適切な区分とその区分に応じた合理的な処分方策を確立することなどが示されている。
TRU核種を含む放射性廃棄物は、再処理事業やMOX燃料加工事業の進展に伴い、その発生量の増大が見込まれ、今後、処理処分を計画的かつ効率的に推進していくことが必要である。このため、TRU核種を含む放射性廃棄物の処理処分の推進のための具体的取組のあり方についてとりまとめたので報告する。
2. TRU核種を含む放射性廃棄物の種類とその処理の現状 (1) TRU核種を含む放射性廃棄物の種類
我が国において、現在、TRU核種を含む放射性廃棄物の大部分は、動力炉・核燃料開発事業団(以下「動燃事業団」という。)の東海再処理工場とMOX燃料製造施設において発生している。これに加え、動燃事業団や日本原子力研究所の核燃料サイクル関連の研究施設においても若干の量が発生している。これらのTRU核種を含む放射性廃棄物は、東海再処理工場及びMOX燃料製造施設の貯蔵施設等で安全に保管されている。また、今後は、海外再処理委託に伴う廃棄物の返還や国内の民間再生処理施設の稼働が始まれば、一層の量のTRU核種を含む放射性廃棄物の発生が見込まれることになる。
再処理施設から発生するTRU核種を含む放射性廃棄棄物は、プラントの構成、放射性廃棄物の管理形態等により、分類と名称が異なるが、動燃事業団の東海再処理工場の場合は、TRU核種を含む放射性廃棄物の主要なものとしては、①ハル・エンドピース、②プロセス濃縮廃液(濃度に応じて低レベルと極低レベルの2群に分けられている。)、③廃溶媒、④スラッジ、⑤再処理雑固体廃棄物(濃度に応じて低レベルと極低レベルの2群に分けられ、さらに焼却処理の観点から可燃性と不燃性に分けられている。)がある。また、動燃事業団のMOX燃料製造施設からは、⑥MOX雑固体廃棄物(焼却処理の観点から可燃性と不燃性に分けられている。)が発生している。
(2) 処理の現状
動燃事業団の東海再処理工場及びMOX燃料製造施設において発生するTRU核種を含む放射性廃棄物の現在の処理方法と発生量は、表1のとおりである。現在行われている処理は、東海再処理工場におけるプロセス廃液の蒸発濃縮による減容処理とその濃縮廃液のアスファルト固化、廃溶媒のプラスチック固化等及びMOX燃料製造施設における雑固体可燃物の焼却処理とその焼却灰のマイクロ波溶融固化、雑固体不燃物の溶融固化である。
(3) TRU核種を含む放射性廃棄物の特徴
TRU核種を含む放射性廃棄物の特徴は、その発生量が比較的多いこと及び含まれるアルファ核種の放射能濃度、ベータ・ガンマ核種の放射能濃度がそれぞれ低いものから高いものまで大きな幅があることである。
現在の動燃事業団にある放射性廃棄物の場合は、プロセス濃縮廃液のうちの極低レベル濃縮廃液のようにアルファ核種の放射能濃度が数百ベクレル/グラム未満で、ベータ・ガンマ核種の放射能濃度もかなり低いもの、プロセス濃縮廃液のうちの低レベル濃縮廃液のようにアルファ核種の放射能濃度が数百ベクレル/グラムから数キロベクレル/グラムで、ベータ・ガンマ核種の放射能濃度は低いもの、さらに、ハル・エンドピースのようにアルファ核種の放射能濃度が数百キロベクレル/グラムと高く、かつべータ・ガンマ核種の放射能濃度も高いものなどがある。また、雑固体廃棄物についても、再処理雑固体廃棄物のように、アルファ核種の放射能濃度が数百ベクレル/グラム未満で、ベータ・ガンマ核種の放射能濃度もかなり低いものや、MOX雑固体廃棄物のようにアルファ核種の放射能濃度が数キロベクレル/グラムから数百キロベクレル/グラムで、ベータ・ガンマ核種の放射能濃度が低いものがある。
表1 動燃事業団の東海再処理工場とMOX燃料製造施設における また、TRU核種を含む放射性廃棄物の大部分は、非発熱性であるが、ハル・エンドピース等のように放射化生成物による若干の発熱性を有するものもある。
施設の各々の工程から発生するこれらの放射性廃棄物は、その工程に特有の物理・化学的な性状を有しており、その性状に適した処理がなされつつある。固化処理についても、アスファルト、プラスチック、セメント、金属塊、人工鉱物等の様々な形態がある。
3. 現在の発生量と今後の見通し TRU核種を含む放射性廃棄物の現在までの累積量は、処理済の固化体と、まだ減容・固化処理を行わずに保管している放射性廃棄物を現在及び現在検討中の処理方法で処理し、固化したと想定したものを合わせて、200リットルドラム缶の固化体換算で約4万本である。
今後の発生量の見通しについては、現在までの動燃事業団の東海再処理工場及びMOX燃料製造施設の操業実績、国内の民間再処理施設の設計等を基に、各施設の工程毎の発生量と放射能濃度を算出して、これに昭和62年の「原子力開発利用長期計画」に、基づく国内、海外の再処理及びMOX燃料加工の操業計画を勘案すると、その発生量は、1990年代後半からその増加が顕著となり、200リットルドラム缶換算で、2010年時点で、約30万本になると予測される。これに加え、将来的には、関連する核燃料施設の解体に伴うTRU核種を含む放射性廃棄物の発生も予想される。
4. 処理処分の研究開発の状況 TRU核種を含む放射性廃棄物の処理については、基本的には現在までに開発された技術により処理可能であり、一部は既に動燃事業団において実証規模の処理がなされるまでに至っている。また、より安定的でかつ経済性に優れた固化処理の技術や高減容化による発生量低減化等の技術に関する高度化研究が動燃事業団及び日本原子力研究所において実施されている。特に、東海再処理工場のプロセス濃縮廃液等に対する高減容化やMOX雑固体に対する除染による大幅な発生量低減化については、具体的な研究成果が得られつつあり、今後の実用化の可能性が期待されている。さらに、放射性廃棄物中の核種や放射能濃度の測定に関しても、サンプリング等により直接測定が行われつつあるとともに、パッシブ中性子法、アクティブ中性子法等の非破壊測定技術の開発も行われている。
処分の研究開発については、動燃事業団及び日本原子力研究所において、廃棄物固化体の長期健全性に関する研究、コンクリート等の人工バリア材料の長期特性に関する研究、人工バリア中の核種の移行挙動に関する研究、核種と土壌又は岩石との地下水を介した相互作用の研究等の基礎的研究が、浅地中処分、地層処分等の処分方法を勘案して実施されている。また、種々の性能評価モデルを用いて、安全確保上重要な核種やパラメータの検討等が実施されている。なお、高レベル放射性廃棄物や原子炉施設からの低レベル放射性廃棄物の処分の研究により得られた成果は、TRU核種を含む放射性廃棄物の処分研究に反映されるとともに、それらの研究の一部は共通的に進められている。
5. 海外の処理処分方策の動向 (1) 処理の動向
現在、フランス、イギリスなどの再処理施設を有する国々においては、TRU核種を含む放射性棄廃物の処理は、我が国と同様に、セメント固化等の既存の技術を用いて実施されている。これらの国々の新たな処理技術の研究開発は、放射性廃棄物中の放射性核種を更に除去するなどによる発生量の低減化、高減容化等の高度化技術に重点が置かれている。
(2) 処分の動向
TRU核種を含む放射性廃棄物の処分については、米国やフランスのように、アルファ核種の放射能濃度に区分値を設けて浅地中処分と地層処分とに分ける考え方と、スイスやドイツのように、放射性廃棄物の分類を行うものの浅地中処分は行わずに、地層処分を中心に処分する考え方などがあり、それぞれの考え方に基づき各国において具体的な処分の計画が推進されている。
各国の放射性廃棄物の処分計画をみると、再処理施設等から発生するTRU核種を含む放射性廃棄物の処分は、原子炉施設から発生する低レベル放射性廃棄物の処分の実績を踏まえつつ、また、高レベル放射性廃棄物の処分の実施に先んじて、2000年前後の処分開始を目標としている国が多い。
6. 処理処分の基本的な考え方 (1) 処理の基本的な考え方
既に述べたように、TRU核種を含む放射性廃棄物は、発生量が多く、また、その発生源も多様であることから、除染、減容等によって放射性廃棄物の発生量を低減させ、処分の負担軽減を図るとともに、それぞれの廃棄物の物理・化学的性状に合わせた適切な処理を行うことが重要である。現在までの研究開発の成果により、処理技術は実用化の段階に達してきているものと考えられるが、今後も更に改良技術及び高度化技術の研究開発に取り組み、より優れた処理技術の確立を目指すことが重要である。
特に、プロセス濃縮廃液、金属の不燃性雑固体廃棄物等のTRU核種を含む放射性廃棄物については、現在研究が進められている廃液中の放射性核種の除去技術、除染技術等の処理技術の研究開発を更に積極的に進めていくことが発生量低減化の観点から重要である。
(2) 処分の基本的な考え方
TRU核種を含む放射性廃棄物のうちでも、含まれるアルファ核種の放射能濃度が低く、かつ含まれるベータ・ガンマ核種の放射能濃度の比較的低いものは、原子炉施設から発生する低レベル放射性廃棄物と同様に、浅地中処分が考えられる。一方、それ以外の含まれるアルファ核種の放射能濃度が比較的高い放射性廃棄物の処分に当たっては、人工バリア等が高度化された処分や地層処分等の浅地中処分以外の処分方法(以下「浅地中以外の地下埋設処分」という。)が適切と考えられる(以下このような処分の対象となる放射性廃棄物を「TRU廃棄物」という。)。
① 浅地中処分の可能性がある低レベル放射性廃棄物
我が国において、今後、TRU核種を含む放射性廃棄物の処分の具体的方策を検討し、推進していくに当たって、現段階で浅地中処分の可能性があるものについて、その放射能濃度の上限に関する一応の目安値を設定しておくことが望ましい。
原子炉施設から発生する低レベル放射性廃棄物の浅地中処分については、昭和61年から関連法令が整備され、浅地中処分が可能な放射性廃棄物についての濃度上限値が定められた。この濃度上限値のうち全アルファ核種の濃度上限値は、1.11ギガベクレル/トン(0.03キューリー/トン)である。この際の濃度上限値は、その算出において、核種毎の被ばく線量評価を基礎にしており、廃棄物の発生源となる原子力施設の種類には基本的には関係していない。
再処理施設等から発生するTRU核種を含む放射性廃棄物の処分方策を考えていくに当たっても、原子炉施設から発生する放射性廃棄物の場合と同様に、核種毎の被ぼく線量評価を基礎として考えると、この全アルファ核種の濃度上限値を一応の目安値とすることが適当であり、約1ギガベクレル/トンの値を全アルファ核種の「区分目安値」として設定する。今後、TRU核種を含む放射性廃棄物のうち、放射能濃度の低いものを対象として浅地中処分を実施する場合には、具体的な濃度上限値が定められる必要があり、原子力安全委員会において、この「区分目安値」、含まれる核種の組成、安全評価シナリオ等を勘案して、審議が行われることが期待される。
具体的には、再処理施設から発生する極低レベルのプロセス濃縮廃液や極低レベルの雑固体廃棄物などの固体化等は、含まれるアルファ核種の放射能濃度が「区分目安値」よりも低く、かつベータ・ガンマ核種の放射能濃度もかなり低いと考えられるので浅地中処分の可能性のある低レベル放射性廃棄物であると考えられる。
② TRU廃棄物
MOX雑固体廃棄物やハル・エンドピース等ように、TRU廃棄物として「浅地中以外の地下埋設処分」が適切と考えられるものについては、今後具体的な処分方策を検討していく必要がある。その場合、長寿命のTRU核種が長期間にわたり人間の生活圏に影響を与えないようにするため、TRU廃棄物の処分方策の具体的検討に当たっては、放射能濃度、発熱性の有無、固化体の物理・化学的性状等のTRU廃棄物の特徴を勘案して、必要な処分深度、人工バリアの性能等を考慮した安全確保方策を検討することが肝要である。
7. 今後の処分方策の具体化の進め方 浅地中処分の可能性がある低レベル放射性廃棄物の処分については、原子炉施設からの低レベル放射性廃棄物の処分を踏まえ、その具体化を推進していくことが重要である。その際、放射能濃度の特に低い廃棄物については、トレンチ処分等の合理的な処分の可能性についても検討していくことが望ましい。
浅地中処分の可能性がある低レベル放射性廃棄物の量については、将来の処理技術の動向によっても変わり得るものであるが、動燃事業団東海再処理工場及びMOX燃料製造施設においてこれまで発生しているTRU核種を含む放射性廃棄物について、現在の処理技術を基礎として見れば、その約4割程度と見込まれる。
TRU廃棄物の浅地中以外の地下埋設処分については、減容化処理などによる発生量の一層の低減化を進めていくとともに、今後、処分方法を明確にしていくことが必要であり、再処理事業等の本格化する時期を考慮し、1990年代後半までにその見通しが得られるように検討を進めていくことが適当である。また、あわせて、処分の実施スケジュール、実施体制、費用確保等についても検討を進めていく必要がある。
TRU廃棄物は、含まれる放射能濃度の範囲が広く、固化体の形態も多種多様であることから、まず、それぞれの放射性廃棄物毎に、その放射能濃度や物理・化学的性状等の諸特性を踏まえた処分方法の検討を行う必要がある。しかし、それぞれの放射性廃棄物の処分方法を別個に定めていくことは、TRU廃棄物処分の全体的合理性の観点からは、必ずしも実際的でないことも考えられる。このため、安全確保を図りつつ、個別の処分方法を統合化し、最適化していくことが適当である。
8. 処理処分研究開発の課題 (1) 研究開発を進める上での留意点
処理技術の研究開発において、現在進められている不燃性の雑固体廃棄物の除染技術開発、低レベルのプロセス濃縮廃液を対象とした放射性核種の除去技術開発等の高度化処理技術開発は、TRU廃棄物の発生量の大幅な低減と経済性の向上に寄与することが期待できる。なお、放射性核種の除去技術開発については、昭和63年10月の原子力委員会放射性廃棄物対策専門部会の「群分離・消滅処理技術研究開発長期計画」に基づき進められている研究開発も勘案して進めることが適当である。また、再処理雑固体廃棄物の溶融固化等のより安定化を目指した研究開発の成果は、貯蔵及び処分における安全性と経済性の向上に寄与することが期待できる。
また、TRU核種の測定・品質保証技術は、固化体中の放射能濃度の測定のために重要であるが、また、固化処理前における廃棄物の濃度別の分別管理を行うためにも必要となる。
TRU核種を含む放射性廃棄物の処分システムを明確にするための基本的な研究課題としては、①放射性廃棄物の諸物性の評価に関する課題、②具体的処分方法に関する課題及び③性能評価手法の開発に関する課題が考えられる。また、これらの研究開発は、高レベル放射性廃棄物や原子炉施設等から発生する低レベル放射性廃棄物に係る研究開発と共通性を有する面も多いと考えられ、これらの放射性廃棄物に係る研究開発状況も踏まえて進めていくことが効果的かつ効率的である。
なお、これらの処分技術の研究開発は、原子力開発利用長期計画にあるとおり、動燃事業団が日本原子力研究所の協力を得て進めるものとする。
(2) 具体的な研究開発課題
① 処理に係る研究開発課題(表2参照)
(ⅰ) 発生量低減化・高減容化技術及び安定化技術
廃棄物の発生量を低減するため、不燃性雑固体廃棄物の表面汚染の除去技術、プロセス濃縮廃液からの放射性核種の除去技術、廃溶媒等の分解処理技術等の開発を行う。
また、ハル・エンドピース等を対象とした、高圧縮、熱間静水圧加圧等による高減容化処理技術開発、不燃性雑固体廃棄物、プロセス濃縮廃液除染残渣等の安定固化処理技術等の開発を行い、貯蔵及び処分における安全性や経済性の向上を目指す。
(ⅱ)測定・品質保証技術
固化体中の放射能濃度等の測定や廃棄物の濃度別分別管理を行うに当たり、その測定時間の短縮、精度向上等を目指した測定技術開発を行う。また、固化体の物理・化学的性状を管理するために重要な固化体の品質保証技術を開発する。
表2 主な高度化処理技術開発 ② 処分に係る研究開発課題
(ⅰ) 個別のTRU廃棄物の発生量、放射能濃度、物理・化学的性状等の把握
再処理施設等の操業計画、返還廃棄物の動向、処理技術の開発状況・将来見通し等を踏まえて、今後の個別のTRU廃棄物の発生量、放射能濃度、固化体及び放射性核種の物理・化学的性状等をより正確に把握するとともに、それらのデータを管理し、活用するためのシステムを確立する。
(ⅱ) 個別のTRU廃棄物毎の特性を考慮した処分方法の検討
上記(ⅰ)の各TRU廃棄物毎の各種データを考慮して、安全確保の観点から個別のTRU廃棄物の処分方法を検討する。また、評価手法の開発等を行いつつその処分システムに要求される性能について検討する。
なお、濃度上限値を上回る原子炉施設からの低レベル放射性廃棄物、解体廃棄物、放射性同位元素廃棄物等の処分方法の検討状況等との関連にも配慮することが必要である。
(ⅲ) 個別の処分方法の統合による最適化
高レベル放射性廃棄物や浅地中処分が可能と考えられる低レベル放射性廃棄物の処分との関連を含めて、安全確保を前提に、全体的な整合性等の観点から、上記(ⅱ)のTRU廃棄物毎の個別の処分方法を、できるだけ少数の合理的な処分方法に統合化することの可能性を検討し、処分の全体的な最適化を図る。また、最適化した処分システムについて、システム全体としての安全性の評価を行う。
(参考1)
関連用語の説明
○TRU核種
原子番号92のウランよりも大きな原子番号をもつネプツニウム、プルトニウム、アメリシウム等の元素の核種の総称で、いずれも人工の放射性核種である。
○ハル・エンドピース
使用済燃料の再処理工程から発生する放射性廃棄物で、燃料集合体の剪断によって切り落とした燃料の端末部分をエンドピースといい、溶解槽で燃料を溶かした後に残る被覆管のことをハルという。
○プロセス濃縮廃液
プロセス濃縮廃液は、再処理施設の各工程から発生する酸回収凝縮水、分析廃液、廃ガス洗浄液、各機器の除染廃液等の廃液をまとめて蒸発濃縮したものである。
○廃溶媒
再処理施設においてプルトニウムとウランを分難するために用いる溶媒が劣化して廃棄物となったもの
○スラッジ
再処理施設の極低レベル廃液を凝集沈澱することによって発生する沈澱物のこと。
○ウラン・プルトニウム混合酸化物燃料(MOX燃料)加工施設
使用済燃料の再処理で回収されたプルトニウムとウランの混合酸化物粉末をセラミックに焼き固め、燃料集合体に加工するための施設である。
○パッシブ中性子法
廃棄物中に含まれるTRU核種から放出される中性子線、又はTRU核種から放出されるアルファ線による反応で放出される中性子線を中性子検出器で測定することにより、廃棄物中のTRU核種を定量化する方法である。
○アクティブ中性子法
廃棄物中に含まれる核分裂性核種に外部より中性子を照射して反応を起こさせ、その反応から、放出される中性子線を中性子検出器で測定することにより、廃棄物中の核分裂性核種を定量化する方法である。
(参考2)
TRU核種を含む放射性廃棄物の区分目安値と分類 (参考3)
構成員及び開催日
1.原子力委員会 放射性廃棄物対策専門部会 (1) 構成員
(2)開催日
2.原子力委員会 放射性廃棄物対策専門部会TRU廃棄物分科会
(2) 開催日
資料3
動力炉・核燃料開発事業団大洗工学センターの原子炉の設置変更
(高速実験炉原子炉施設の変更)について(答申) 3原委第25号
平成3年7月30日
内閣総理大臣殿
原子力委員会委員長
平成3年3月20日付け2安(原規)第674号をもって諮問のあった標記の件に関する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条第4項において準用する同法第24条第1項第1号、第2号及び第3号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については妥当なものと認める。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目次 | 次頁 |