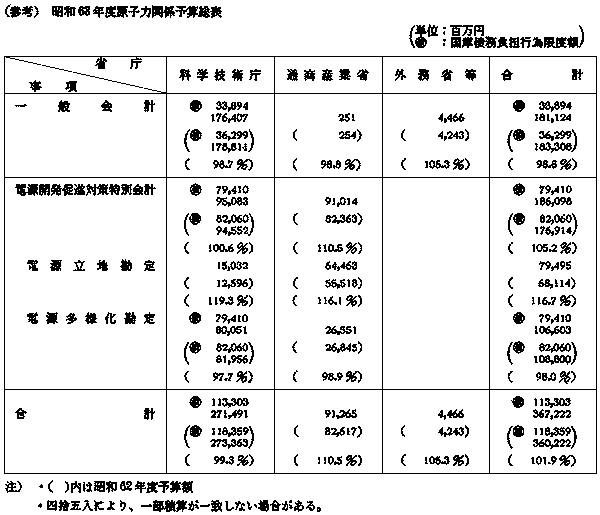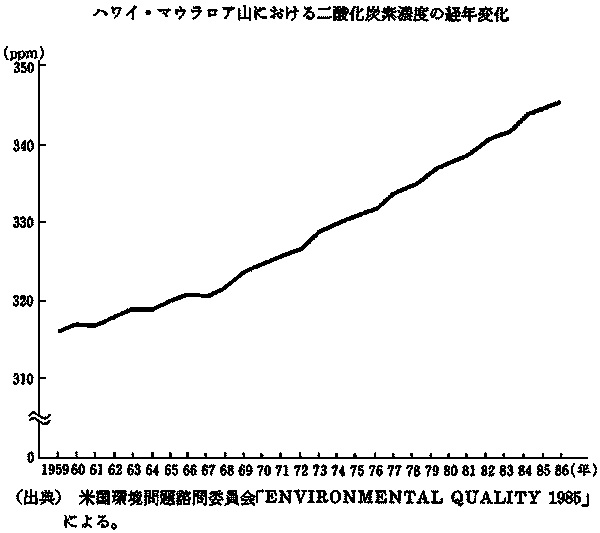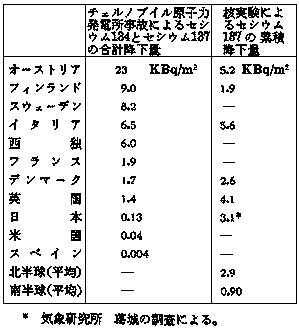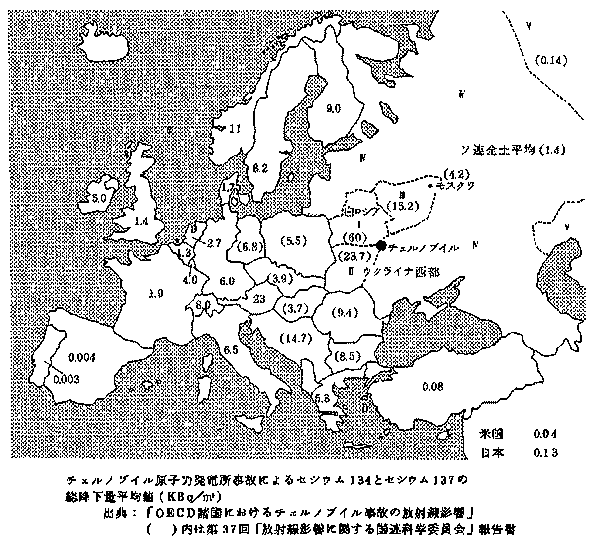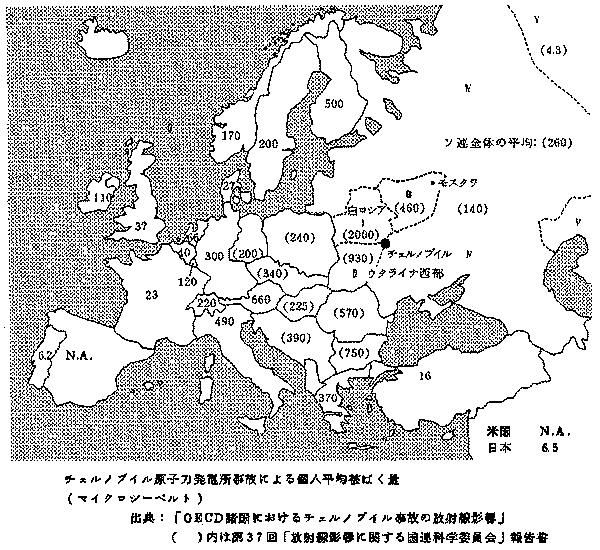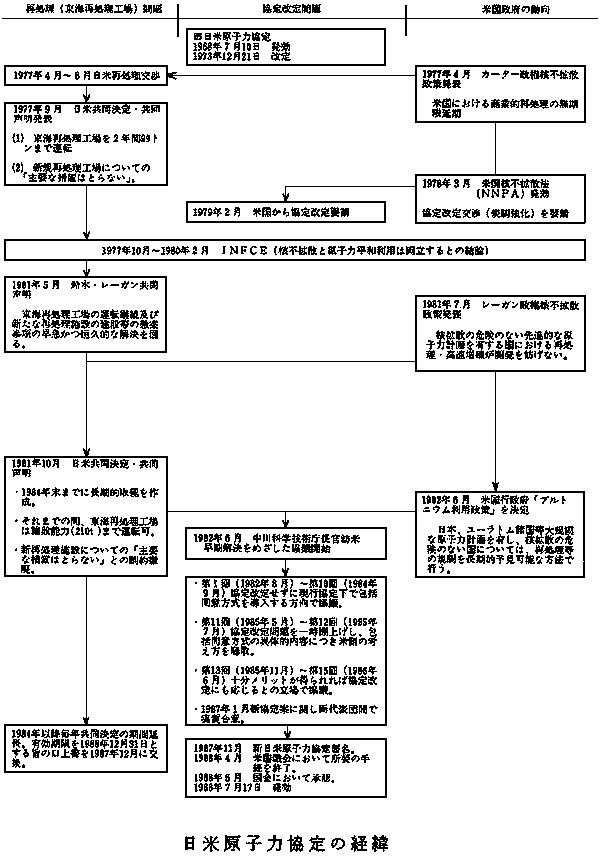委員会の決定等
昭和63年原子力年報
昭和63年12月
原子力委員会
(解 説)
「昭和63年原子力年報」は、昭和68年11月29日の原子力委員会において決定され、昭和63年12月2日の閣議に報告された。
本年報は昭和63年10月までの概ね1年間における原子力開発利用の動向について取りまとめたものである。
原子力年報は第1部「総論」、第2部「各論」、第3部「資料」の3部構成となっている。以下に要約を掲載する。
はじめに
1.今日、我が国の原子力発電は、既に36基、約2,788万キロワットの規模に達し、昭和62年度には総発電電力量の29.1%を占め、昭和60年度に石油火力発電の実績を上回って以来、主力電源としての地位を着実に築いてきている。また、このような原子力発電の推進に当たっては、安全対策に万全を期してきており、これまでの26年間にわたる我が国の原子力発電の実績の中において、公衆に影響を与えるような事故は皆無であり、運転時の故障・トラブル等に基づく計画外停止回数も、昭和61年には0.4回/基・年と世界で最も優れた実績を挙げている。これは、設計、建設、運転すべての段階における長年にわたる着実かつ地道な安全確保のための努力によるものである。
また、核燃料サイクルについては、青森県上北部六ケ所村における三施設建設計画が具体化してきており、我が国における総合的な原子力発電体系の確立へ向けて着実な進展が見られる。
原子力の研究開発分野においては、その科学技術全般に及ぼす波及効果にもかんがみ、基礎研究、基盤技術開発、先導的プロジェクト等が従来にもまして積極的に進められている。
2.このように、我が国の原子力開発利用は、安全性を確保しつつ、着実に進められてきているが、昨今、チェルノブイル原子力発電所事故により放出された放射性物質で汚染された食品のヨーロッパからの輸入問題や、伊方発電所における出力調整運転試験の実施をきっかけとして、国民の間に原子力発電の安全性・必要性等に対する関心が高まってきている。
そこで原子力委員会は、本年の年報の場を借りて、何故我が国において原子力なかんずく原子力発電を推進する必要があるかを改めて述べることとした。
3.原子力開発利用を円滑に進めていくためには、目標達成に向けた関係者の不断の努力と共に、国民の理解と協力を得ることが必要であり、今後とも関係者によるこのための努力がなお一層求められる。また同時に、原子力委員会は、原子力開発利用長期計画に基づき、今後の技術の進展や諸情勢の変化に適切に対応しつつ、国民の信頼に応える原子力開発利用の展開に努めていくことが重要であると考えている。
第1章 原子力に期待される役割とその展開
1.世界のエネルギー事情と原子力発電
(1)最近のエネルギー事情と原子力発電の現状
世界のエネルギー需要の伸びは、第2次石油危機以降、基調としては鈍化する傾向にある。また、一次エネルギー源の多くを占める石油資源については、消費量が抑制されていること、新規油田の探査・開発の進展により供給能力に余裕があること等から、近年、その価格は低位にある。この石油価格に連動して、天然ガス、石炭の価格も低水準で推移しており、全体としてエネルギー需給は緩和基調にある。
このようなエネルギー需給の緩和基調の背景には、石油危機を契機とした各国における省エネルギー努力及び近年の緩やかな経済成長の他に、石油代替エネルギーの開発によるエネルギー供給源の多様化が大きく貢献している。特に、先進諸国には、石油代替エネルギーの1つの柱として、積極的に原子力発電に取り組んでいる国が多い。経済協力開発機構(OECD)加盟諸国においては、1983年から1987年までの間に、国内総生産(GDP)が約15%伸びたにもかかわらず、石油消費量は約5%伸びたに過ぎない。一方、原子力発電によるエネルギー供給は同期間に約1.6倍にも増大し、一次エネルギー供給全体に占める割合も5.8%から8.4%へとその比重を増している。このようなことから、原子力発電は、石炭、天然ガス等の他の石油代替エネルギーとともに、石油消費量抑制に大きく貢献してきていると考えられる。
世界における原子力発電所は、1988年6月現在で410基(約3億1,562万キロワット)が運転中である。
原子力発電所の新規運転開始基数は、この5年間、毎年20~25基程度と安定しており、世界的に原子力発電計画が着実に進められていることを示している。また、1987年の原子力発電電力量は、1兆6,600億キロワット時に達し、これは世界の総発電電力量の約16%を占めるに至っている。原子力発電による発電電力量の割合は、毎年着実に増加しており、電力供給の主要な担い手としての地位を占めてきている。
(2)将来のエネルギー需給見通しと原子力発電
将来の世界のエネルギー需要は、先進国においては省エネルギーの進展、産業構造の変化等によって今後それ程大きな伸びは見込まれないが、開発途上国においては工業化の進展や人口の増加、生活水準の向上等から着実な増加が予測される。現在、国連統計によると、開発途上国には世界人口の約3/4の人々が住んでいるが、そのエネルギー消費量は、全世界の約1/4に留まり、1人当たりのエネルギー消費量は先進国の約1/10にしか過ぎない。これらの国々の人口規模と今後の経済発展に伴うエネルギー消費単位の増大を勘案すると、開発途上国におけるエネルギー需要の伸びは、潜在的に極めて大きなものと考えられる。
したがって、世界全体のエネルギー需要も緩やかながら着実に伸びていき、自由世界のエネルギー需要は、日本エネルギー経済研究所の見通しによると、2000年には1983年の約1.4倍に増大するものと見込まれている。
中長期的に見た石油供給については、再びOPEC依存度が上昇し、不安定化すると懸念され、石油需給は再びひっ迫し、原油価格は上昇するものと考えられている。
このような見通しの下で、先進各国は、引き続き、石油依存度低減を目標とした政策の下に、石油代替エネルギーの開発を推進することとしている。
また、石油代替エネルギーの開発は、石油依存度を低減させるためだけでなく、発電用燃料として使用されている石油を代替することにより、その分代替のきかない化学工業の原料等への石油供給を増やすためにも必要である。また、今後、経済活動の拡大が期待される開発途上国に、その経済発展に必要な石油資源を残しておくことも、我が国をはじめとする先進国の責務である。
このような考え方に基づき、先進諸国を中心に、石油代替エネルギーとして、石炭、天然ガス等の化石エネルギー、水力、地熱、太陽等の再生可能エネルギー、原子力発電等の開発が行われている。どの石油代替エネルギーをどの程度、どのようなバランスで開発していくかについては、各国のエネルギー事情により自ずと異なるが、多くの先進諸国においては、原子力発電をエネルギー供給源の主力の一つとして、積極的に開発していくこととしている。
(3)海外諸国の原子力発電に関する政策
1986年4月に発生したソ連チェルノブイル原子力発電所事故後の各国における原子力発電に関する政策については、同事故を契機として政策を変更した国、従来の政策を堅持している国等、各国のエネルギー事情により、様々であった。
① 主要先進国の原子力発電に関する政策
主要先進国は、経済成長率が鈍化し、エネルギー需要は従来に比べると緩やかな成長を続けている。先進国の中でも、その国のエネルギー消費量、国内資源の賦存状況等国情により、原子力発電に関する政策に相違が生じてきている。
米国は、既に稼働中の原子力発電所を106基有し、世界最大の原子力発電国である。しかし、電力需要の停滞や建設費の高騰により建設計画を断念したものもあり、1978年以降新規発注がない状態が続いている。発注済みの原子力発電所については、長期間は要したものの、この数年間は毎年7基程度が着実に運転を開始している。
フランスは、ウラン資源を除きエネルギー資源に恵まれていないため、第一次石油危機後、省エネルギー、国産エネルギーの拡大を柱とするエネルギー政策を推進してきた。この結果、現在、原子力発電は総発電電力量の約70%を占めている。1987年5月のエネルギー計画見直しでは、原子力発電を主体とした自給率向上というエネルギー政策の方針に変更はなかったが、近年の電力需要の伸びの鈍化を考慮して、フランス電力公社は、1987年末に、1988~1991年の原子炉の発注をこれまでの年間1基から2年に1基を変更した。
ソ連は、現行5か年計画(1986~1990年)により、1990年において原子力発電設備容量7,000万キロワット達成を目標としている。チェルノブイル原子力発電所事故後、チェルノブイルと同型炉の新規建設中止等によりこの目標達成は危ぶまれているが、引き続き原子力発電の開発を積極的に進めることとしている。
西独は、石炭資源に恵まれているが、石油の輸入依存度が高い。このため、エネルギー節約と石油消費の低減をエネルギー政策の柱としている。1986年9月に発表したエネルギー政策報告書によると、原子力発電については、短・中期的に見てこれに代わる代替エネルギー源が見あたらないことから、安全性を優先して開発を継続していくこととしている。
カナダは、ウラン資源に恵まれており、独自のカナダ型重水炉(CANDU炉)の開発を進めてきた。また、原子力発電は、化石エネルギーに比べ環境面で利点を有していることから、今後ともCANDU炉の開発を一層進めていくこととしており、1990年には、総発電電力量に占める原子力発電の割合は19.5%になると想定されている。
英国は、欧州共同体(EC)加盟国の中でも最大の資源保有国であり、この国内エネルギー資源(石炭、石油、天然ガス、原子力)を経済的に開発利用し、エネルギー自給を維持することをエネルギー政策の目標として掲げており、その中において原力子発電の開発を積極的に進めている。
一方、原子力発電に消極的な国の動向がチェルノブイル原子力発電所事故後注目を集めている。
例えば、オーストリアは、1979年の国民投票により、同国が初めて建設した原子力発電所の運転開始を凍結していたが、チェルノブイル事故後、その原子力発電の廃止を正式に決定し、原子力発電からの撤退を決めた。オーストリアは、1986年において総発電電力量の約7割を水力発電で賄っており、豊富な水力資源に恵まれているという背景がある。
イタリアは、1987年11月、国民投票により、原子力発電所の立地促進等のための条項の廃止を決定し、政府は新規原子力発電所の建設中断、運転中・建設中の原子力発電所の計画見直しを行う等、原子力発電の開発を大きく後退させた。1988年9月、政府は2000年までの新たなエネルギー需給計画案を提示し、今後、石炭及び天然ガスを主要エネルギー源として開発し、2000年には原子力発電への依存度をゼロにすることとした。イタリアは、もともと総発電電力量に占める原子力発電の割合が、1986年で約4%、1987年で0.1%に過ぎず、また1割以上の電力をフランス及びスイスからの輸入に依存している。
スウェーデンは、1980年の国民投票の結果を踏まえ、原子力発電所を12基に限定し、2010年までに原子力電発から漸次撤退するという方針を既に示している。これを受けて、1988年6月、議会は、原子力発電所12基のうち1基を1995年に、もう1基を1996年に閉鎖すをことを盛り込んだ1990年代の政府のエネルギー政策案を承認した。この方針通りに閉鎖するかどどうかは1990年に最終的に決定される。スウェーデンの総発電電力量に占める原子力発電の割合は1987年で約45%と高く、代替電源をどうするかが課題となっている。
原子力発電から撤退した国については、新エネルギーの開発が遅れた場合、原子力発電をやめた分、主として化石燃料に頼らざるを得ないと考えられる。
② その他の国・地域の原子力発電に関する政策
その他の国・地域のうち、開発途上国においては、工業化の進展や人口の増加、生活水準の向上等から今後のエネルギー需要は相当な伸びを示すものと見込まれている。その中でも、韓国、シンガポール、香港、台湾の新興工業経済地域は高い経済成長率を達成しており、これに伴いエネルギー需要も急激に伸びてきている。
これを支えるエネルギー源として、韓国、台湾においては原子力発電の開発に力を入れている。
中国も、石炭火力発電とともに原子力発電の開発も着実に進めることとしており、軽水炉のみならず、地域暖房用ガス炉等の新型炉開発を行う等、原子力に関する研究開発にも高い意欲を示している。
この他、アジアでは、インド、パキスタンで既に原子力発電所が運転されており、インドネシア、マレイシア等も将来の有望な電源として原子力発電に関心を寄せている。
東欧諸国では、チェコスロバキア、ブルガリア、東独、ハンガリー、ユーゴスラビアで合計24基の原子力発電所が運転しており、経済相互援助会議(コメコン)は、加盟国の科学技術分野における高レベルの進歩の達成等のため、原子力発電を優先分野の1つとして、加速的に開発することとしている。
2. エネルギー利用と地球規模の環境影響
(1)エネルギー利用と環境への影響
我々の享受している文明社会は、種々のエネルギー消費の上に成り立っている。しかしながら、このようなエネルギー利用は、多かれ少なかれ環境に対して何らかの影響を与えている。近年、酸性雨、二酸化炭素等による温室効果等、国境を越えた地球規模の環境汚染に対する関心が高まってきており、エネルギー利用による環境影響も世界的に注目を集めている。我々の経済活動や日常生活に大きな支障が生じるよううな形でのエネルギー利用の制限は現実的ではないものの、できる限りエネルギー利用による汚染を低減していく努力が求められていることは異論のないところであろう。
石油、石炭等の化石エネルギーは、その燃焼に伴い、硫黄酸化物、窒素酸化物等の大気汚染物質が発生する。これらの放出量を削減するためには、排出源を確定し、これを規制することが必要となる。これらの物質の排出源のうち、火力発電所については、我が国を先進として、各国において従来から公害防止機器の設置等の環境対策を積極的に行うとともに、必要な技術開発に熱心に取り組んでいる。しかしながら、排出源の増大に伴い、酸性雨等環境に対する集積的な効果が欧米を中心として地球規模にまで及んでいるのが現状である。
一方、化石エネルギーの燃焼に伴い二酸化炭素が発生するが、これについては、現状の技術開発状況の下ではその放出を抑制することが困難であり、排出量の増大に伴い、大気中における濃度の上昇による影響が心配されている。このような二酸化炭素の濃度上昇は、地表から宇宙空間への放熱を妨げ、地上の気温を上昇させる「温室効果」をもたらすものとされている。
昭和63年6月にカナダのトロントで開催された「大気変動に関する国際会議」において、オゾン層破壊、酸性雨と併せこの問題が議論された。その中で、現在のような二酸化炭素を中心とする温室効果ガス*濃度の増加が続けば、21世紀半ばまでに気温が1.5~4.6℃、海面が30cm~1.5m程度上昇し、大規模な気候変動や沿岸地方の都市の浸水等の影響が生ずるおそれがあるとしている。
注)* 太陽光のうち、可視光線及び紫外線を透過させ、地表に到達させるが、地表からの赤外放射を吸収し、温度効果を生じさせるガス。二酸化炭素、メタン、亜酸化窒素、クロロフルオロカーボン(フロンガス)等がある。
そして、温室効果ガスの排出抑制等の実施の提言の中で、原子力発電については、安全性、核不拡散、廃棄物処理の課題が克服されることを前提として代替エネルギーとなり得るとしている。
太陽エネルギー、風力エネルギー等の再生可能エネルギーは、環境に対する影響が小さいという特長を有しているため、従来より研究開発が行われてきているが、まだ研究開発途上のものが多く、経済性、供給安定性等の点において技術開発の余地が大きい。また、特に、我が国においては、国土、自然条件等の制約により大規模な開発は容易でないと考えられ、再生可能エネルギーは、原子力発電や化石エネルギーを代替することは困難であり、補完的な役割を果たすものと考えられる。
また、再生可能エネルギー利用よる環境への影響は小さいものの、皆無というわけではない。例えば、水力発電、地熱発電等の開発には何らかの環境影響が生ずるおそれがある。
ハワイ・マウラロア山における二酸化炭素濃度の経年変化
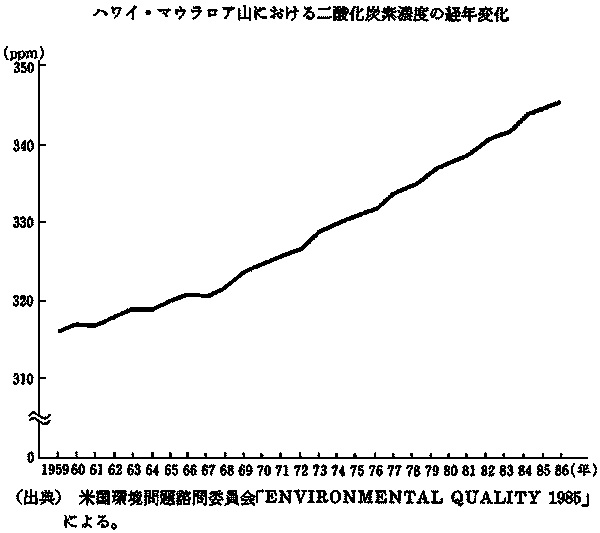
(2)原子力発電と環境への影響
原子力発電は、化石エネルギーの燃焼とは異なり酸化物や二酸化炭素の発生がないため、石油等の火力発電の有する環境上の問題を免れており、また、再生可能エネルギーと比較して量的、質的に安定した電力供給を行うことが可能であるため、代替エネルギーとして主要な役割を果たすことが期待されている。
しかしながら、原子力は、そもそも放射性物質を取り扱うことから、環境や人体に対する潜在的な危険を内包していることは否定できない。このため、原子力の開発利用においては、そのいかなる局面においても、放射性物質の生活環境への放出、拡散を十分に抑制、管理し、健康への影響のないよう、万全の安全対策を講じることが大前提となる。
実際、原子力発電の開発は、当初から放射性物質の管理を中心とした安全性の確立を第一として進められてきており、ソ連のチェルノブイル原子力発電所事故が起こるまでは、商業用原子力発電所からの放射性物質に起因して、従業員を含め死者が出たことはなかった。我が国においても、1963年に原子力発電が開始されて以来、現在に至るまで25年間、放射性物質に起因して死者を出すような事故はもちろんのこと、一般の人々に影響を与えるような事故も全くなかった。
このように、原子力発電は優れた実績を積み重ねてきたが、ソ連のチェルノブイル原子力発電所事故をきっかけとして、世界各国において原子力発電の安全性及び環境への影響が改めて議論されることとなった。
したがって、原子力発電所の環境への影響を考える場合、このチェルノブイル原子力発電所事故の影響を正しく評価する必要がある。ここではチェルノブイル原子力発電所事故による放射能汚染の状況とその影響について以下に述べる。
① チェルノブイル原子力発電所事故と放射性物質の放出
1986年4月26日に起こった、ソ連のチェルノブイル原子力発電所事故の環境への影響については、1988年1月に公表された経済協力開発機構原子力機関(OECD/NEA)の「OECD諸国におけるチェルノブイル事故の放射線影響」報告書によると、放出された放射性核種の中で、生体内にとりこまれ易いために問題となるセシウム134とセシウム137の各国への降下量は以下のとおりであり、オーストリア及び北欧諸国で核実験の場合の3~4倍、その他の国では核実験以下であったといえる。
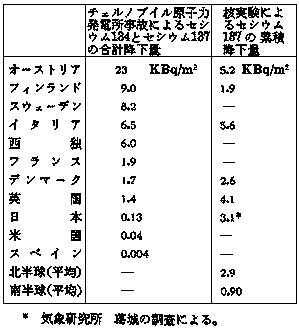
このように、過去多くの議論を呼び、世界的に中止が合意されるに至った大気圏核実験に匹敵するような放射能汚染が、原子力平和利用でも起きたという事実を厳粛に受け止めるとともに、二度とこのような事故を起こさないようにしなければならない。
② チェルノブイル原子力発電所事故の放射能による影響
事故による影響で最も心配されたのは、広範囲に降下した放射性物質により食物が汚染され、それを摂取することによる公衆の健康への影響である。各国政府は、環境放射能の監視体制を強化するとともに、食物等の摂取による公衆の被ばくを最小限に留めるため、雨水の飲用制限に関する勧告、食品の輸入規制、乳牛の屋外放牧禁止、食物の流通制限等、各国の状況に応じた各種の放射線防護措置を実施した。
事故発生地点からかなり離れていた我が国においても、事故発生から数日後に、事故に起因すると思われる放射性物質がわずかながら測定されたものの、直接的な影響はなかったと考えられる。むしろ問題となったのは、放射性物質で汚染されたヨーロッパの食品の我が国への輸入である。
我が国は、現在、ヨーロッパ等から輸入される食品の検査を行っており、ヨーロッパにおける乳幼児食品や米国における一般食品に対する基準と同じ1キログラム当たり370ベクレル(セシウム134及び137を対象核種として)という値を用いて、これを超える食品については輸出元へ送り返す措置を取っている。ヨーロッパからの輸入食品の日本の全食品中に占める割合は約2%であり、例えその輸入食品がすべて基準値ぎりぎりの放射性物質を含んでいたとして、この割合で食べた場合でも、年間の被ばく量は約40マイクロシーベルトと推定され、日本において自然界から年間に受ける平均の被ばく量1,000マイクロシーベルトに比べると問題にならない程微量である。
先に述べたOECD/NEAの「OECD諸国におけるチェルノブイル事故の放射線影響」報告書では、地上に降下した放射性物質や汚染された食品の摂取など、主な被ばくの経路について検討し、チェルノブイル原子力発電所事故の結果、事故後1年間に各国の公衆が受けた平均的な被ばく量を求めている。これによると、OECD諸国における公衆一人一人に対する生涯平均の放射線リスクはこの事故によって大きくは変化しないものとしており、また、集団に対するリスクについても、自然発生する健康障害に対し検出可能であるほど有意な追加をもたらさないレベルとしている。
一方、昭和63年6月に開催された「放射線影響に関する国連科学委員会(UNSCEAR)」では、ソ連を含めた東欧諸国の公衆の平均被ばく線量を評価しており、これによると、ソ連の一部の地域で自然放射線による被ばく線量(2,400マイクロシーベルト)と同程度で、それ以外は、自然放射線以下であったとしている。
上述の通り、チェルノブイル原子力発電所事故によりもたらされた放射性物質の環境への放出は前例のないものであり、二度とこのような事故を発生させてはならないと考える。しかし、その影響に関していえば、ソ連、とりわけチェルノブイル原子力発電所近傍の人々への影響については、今後の詳細な調査や科学的評価を待つ必要があるものの、OECD諸国及び東欧諸国において、チェルノブイル原子力発電所事故による人体等への影響が有意な形で現われるとは専門家は見ていない。
したがって、二酸化炭素の発生等による環境問題を免れているという特長を勘案した上で、原子力発電所が常に放射性物質による危険を内包しているという事実を十分認識し、安全確保に万全を期しつつ、これをエネルギー利用の中において正しく位置付けていくことが重要であると考えられる。
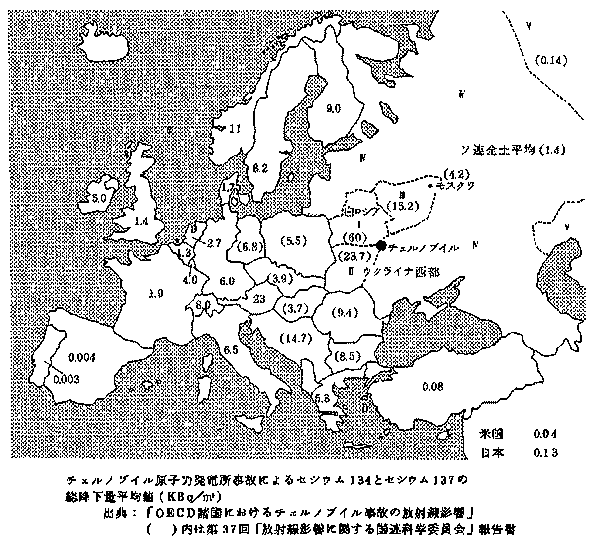
チェルノブイル原子力発電所事故による
セシウム134とセシウム137の総降下量平均値(KBq/m2)
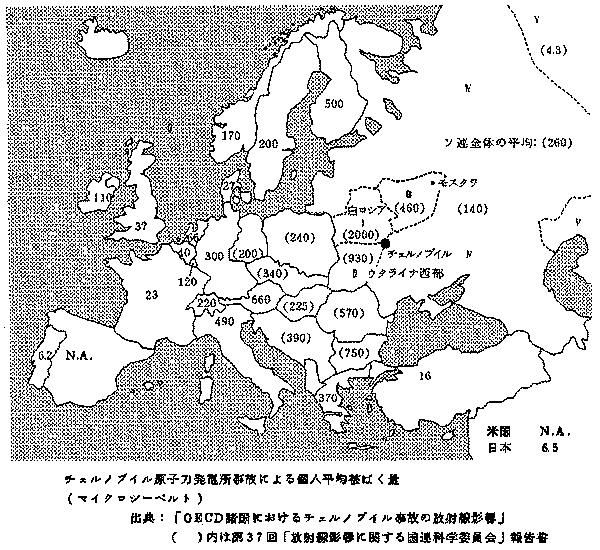
チェルノブイル原子力発電所事故による個人平均額ばく量(マイクロシーベルト)
(3)環境面から見たエネルギー利用
以上に見たように、どのようなエネルギーであっても、その利用に大なり小なり環境への影響を伴うものであり、ある特定のエネルギー源がすべての環境問題を解決するということはあり得ない。エネルギー利用が我々の豊かな文明生活を支え、人類の活動の一部分であることを考えれば、他の人類の活動が環境に対し様々な影響を与えてきたと同様に、それが環境に対し何らかの影響を及ぼすことは避けられないものである。
したがって、我々が現在の文明社会を受け入れるならば、エネルギー利用による環境影響についても、単にその否を論ずるだけではなく、どのようにして制御するかということについて真剣に考える必要があろう。
各国のエネルギー政策において、どのようなエネルギー源をどの程度導入していくかは、その国のエネルギー資源の賦存状況、経済規模等の条件の下で、各エネルギー源の経済性、供給安定性等を踏まえ決められていくだけでなく、当然、各エネルギー源の環境に対する影響も考慮すべきことと考えられる。
エネルギー利用に伴う環境影響は、化石エネルギー、再生可能エネルギー、原子力の各エネルギー源によって性格が異なり、ある特定のエネルギー源に依存することは、その影響効果を集積的に拡大し、もともと自然環境が有する自己回復機能の及ぶ範囲を越えて、とり返しのつかない深刻な結果をもたらすことになりかねない。このような危険を考慮すれば、多種のエネルギー源についてバランスのとれた開発を行っていくことが必要であり、その中において、環境影響の観点から優れた特長を有する原子力発電も、安全確保を大前提として、一つの重要な役割を果たしていくことは疑いない。
3. 我が国における原子力政策
(1)最近の原子力をとりまく状況
我が国において原子力開発が始まって以来30年以上が経過し、これまで原子力発電や放射線利用等の分野において優れた実績を積み重ねてきている。
しかしながら、昭和61年4月に発生したソ連チェルノブイル原子力発電所事故は、我が国国民の原子力、とりわけ原子力発電に対する考え方に少なからず影響を与えた。
事故発生当初は、遠く離れた外国での事故でもあり、我が国への放射性物質の降下も少なかったため、そのことが直ちに原子力発電反対につながるものではなかった。
しかしながら、昭和62年後半頃から、チェルノブイル原子力発電所事故により広くヨーロッパ各地に拡散した放射性物質で汚染された食品が、ヨーロッパ外にも輸出されて、その一部が我が国に輸入され、我々の食卓にも上がっているのではないかという不安が出始めたため、改めて原子力発電の安全性、必要性の問題が広く国民の関心を集め始めた。
この動きを決定的なものとしたのが、昭和63年2月の四国電力(株)伊方発電所2号炉における出力調整運転試験の実施に伴い活発化した原子力発電に対する反対運動であった。これに反対する人々は、専門的立場から見ると科学的根拠の乏しい主張を行い、その結果として原子力発電に関する国民の理解を混乱させることとなった。
伊方発電所2号炉の出力調整運転試験に対する反対運動以降、ヨーロッパからの輸入食品の放射能汚染問題への関心の高まりと相まって、婦人、若年層を含め、原子力施設立地地域だけでなく全国的に原子力発電に対する反対運動が急速に高まってきた。そして、その論点も、原子力発電の安全性や放射能汚染に関することだけでなく、原子力発電の必要性や我が国のエネルギー政策に関すること等にまで拡大してきている。
原子力開発利用を進めるに当たっては、国民の理解と協力を得ることが大前提であることは言うまでもない。
原子力委員会としては、広く国民に原子力の安全性に対する不安感が増大し、更にその一部が反対運動という形で表出してきていることを厳粛に受け止めている。このため、政府及び原子力関係者は、原子力に関する正確な知識及び情報の提供に努めつつ、国民の立場に立って解り易い言葉で丁寧に、原子力の必要性、安全対策等について、従来にもまして積極的に説明し理解を求めていくべきである。
我が国における原子力開発利用の基本的な進め方については、昭和62年6月に決定した原子力開発利用長期計画(以下、長期計画と略する。また、昭和62年6月に決定した長期計画を新長期計画と呼ぶ。)に詳述してあるところであるが、上記の反対運動の動向を踏まえ、原子力発電を含め、なぜ原子力開発利用を推進する必要があるかを改めて述べてみたい。
(2)エネルギー資源の確保と原子力発電
我が国の安定的経済発展及び豊かな国民生活を保障するためには、安定したエネルギー供給基盤の確立が必須であり、このためには、石油代替エネルギーの開発を推進する必要がある。
石油代替エネルギーのうち、原子力発電は、少量の燃料から莫大なエネルギーを取り出すことが可能であること、経済性に優れていること、燃料の供給が安定していること及び燃料の備蓄性が高いこと等を大きな特長としている。また、核燃料サイクルの確立により、発電過程で生成されるプルトニウムの利用が図られれば、海外からの輸入エネルギー依存度をより大幅に低減させることが可能であり、準国産エネルギーとして、我が国のエネルギー自給率の向上に大きく寄与することが期待されている。さらに、原子力は高度な技術を集約して生み出されるエネルギーであり、エネルギーの安定確保という課題を、「資源を持つこと」に加えて「技術を持つこと」により解決する途を拓くものである。
(参 考)
原子力発電の位置付けに対する疑問に答えて
最近、我が国のエネルギー供給構造における原子力発電の位置付けについて様々な疑問が呈されている。原子力委員会としては、これらの疑問に率直に答え、国民の理解と協力を得る必要があると考えるものであり、ここにいくつかの点に絞って記述する。
① 電力需給と原子力発電
現在、我が国が保有する発電設備は過剰であり、原子力発電所の運転を止めても、電力需要に十分対応できるのではないか、との議論があるが、これに対しては次のように考えている。
発電設備は、夏季の需要ピーク時に対応できるだけの供給力を保有する必要があるが、予測不可能な電力需要の伸びに対応して、停電を防ぐためにある程度の予備設備を有する必要がある一方、水力発電所の出力減、定期検査中のため稼働できない設備等があり、発電設備にはその分の余裕を見込む必要がある。したがって、原子力発電所の運転を止めれば、夏季の需要ピーク時には、大規模な停電が発生するおそれがある。
② 他の電源と比べての原子力発電の経済性
昨今、化石燃料の価格が低下しているため、原子力発電の経済性が失われたのではないかという指摘がなされている。これに対しては、次のように考えている。
(i)通商産業省の試算によると、昭和62年度運転開始ベースのモデルプラントについての耐用年発電原価は、原子力が9円/キロワット時程度、石炭火力が10~11円/キロワット時程度、石油火力が11~12円/キロワット時程度、LNG火力が11~12円/キロワット時程度と、燃料価格の低下等により、以前に比べ接近してきているものの、依然として最も経済性に優れている。
(ii)また、原子力の発電原価に、原子炉廃止措置及び放射性廃棄物の最終処分に係る経費は含まれていないが、現時点の知見で推定すると、これらを合計しても耐用年発電原価の概ね1割程度と見込まれるため原子力発電の経済的優位性に変化はない。
(iii)電源開発は長期的視点に立って進めなければならないものであり、現時点で電源開発計画を議論するためには21世紀初頭のエネルギー価格を見通す必要がある。
中長期的には、1990年代に入って、石油供給の不安定化と石油需給のひっ迫化が進展するとされており、石油価格は再び上昇、石炭や天然ガスの価格もその影響を受けて上昇すると考えられる。これに対し、原子力発電は、研究開発により建設費を低減できる見通しが得られること、かつ、ウラン価格がある程度上がったとしても燃料費の割合が小さいためそれ程影響を受けないこと等から、引き続き経済的優位性を保っていくものと考えられる。
③ 石油代替としての原子力発電
原子力発電は、石油の中でも石油火力燃料用のC重油の代替になっているだけであり、石油の消費削減に役立っていないという議論がある。これに対しては次のように考えている。
(i)原子力発電の開発利用は、石油火力発電所の燃料の大半を占めるC重油の代替が主であるという指摘は正しい。しかし、原油の精製プロセスを変更すれば、各製品の収量を変えることが可能であり、C重油の収量を減らし、ガソリン、軽油等の収量を増やすことにより、結果としてみれば、石油以外で代替できない用途への石油資源の供給を増大させることができる。
また、我が国において、石油火力発電所で使用されている燃料の約3~4割は原油であり、原子力発電の開発利用により、C重油のみならず、原油の代替も図られている。
(ii)前述のOECD諸国におけるエネルギー供給実績の推移を見ても、原子力開発は、石炭、天燃ガス等の他の石油代替エネルギーとともに石油消費量抑制に大きく貢献していると考えられる。
④ 高レベル放射性廃棄物の処分
原子力発電所からの使用済燃料を再処理することにより発生する高レベル放射性廃棄物は、長半減期の放射性核種を含んでおり、現在処分の見通しがはっきりしていない、それにもかかわらず、原子力発電を積極的に推進するのは問題であるという議論がある。これに対しては次のように考えている。
(i)原子力発電所からの使用済燃料の再処理に伴い発生する高い放射能をもった廃液は、まず、ガラスに溶け込ませ、丈夫なステンレス製の容器の中でガラス固化体とする。このガラス固化のための技術は、フランス等で確立しており、我が国でも研究開発が行われ実用化の直前である。
(ii)ガラス固化したもの*は、数十年間冷却した後、最終的に地下数百メートルより深い安定した地層の中に処分する予定である。現在、処分技術の確立に向けこの研究開発が進められているところであり、この地層処分には十分な見通しがあるものと考えている。
注)
* 一般家庭用、産業用等を含め、日本国民一人当たりが一生の間に使用する全電力量を仮に全て原子力発電で賄ったとしても、これより発生する高レベル放射性廃棄物のガラス固化体の量は、せいぜい野球ポール1個分程度に過ぎない。
(3)科学技術の新たな展開と原子力開発利用
原子力利用は人類が今世紀に生んだ科学技術であり、極めて広大な技術的可能性を有している。
核融合、核熱利用、放射線利用等原子力の研究開発は新しい技術や知識を創出してきたが、さらに、近時、原子力の研究開発はその幅を広げ、よ り革新的な分野へと展開しつつある。また、原子力技術は広範な科学領域に立脚し、各種の先端技術、極限技術等を総合化する巨大なシステム技術としての特質を有し、幅広くかつ高度な技術や知識を集大成するものであり、広範な科学技術の牽引力となるものであることから、21世紀における社会の基盤となる知的資産の形成に貢献することとなる。
したがって、原子力の研究開発の特質を踏まえて、新たな展開を図るため、創造型研究開発を指向し、ニーズの多様化・高度化に対応していくとともに、他の科学技術分野との連携・交流に努めることにより、次代の創造的な科学技術の育成を図っていく必要がある。
(4)国際社会への貢献
我が国は、「進んで国際協力に資する」との原子力基本法の基本方針に基づき、原子力平和利用推進国としての国際的責務を果たしつつ、欧米の主要先進国とともに原子力開発利用推進の牽引車として国際社会に貢献していかねばならない。
このため、以下に掲げる3点を国際対応の基本目標として、可能な限り主体的・能動的に推進する。
① 長期的視点に立って創造型研究開発を推進し、新しい技術や知識を生み出して、それを世界の原子力平和利用のために提供していくこと等により、世界共通の利益を追及する。
② 世界の核不拡散体制の健全な維持・強化、安全確保の体制、技術の一層の改善等、世界共通の課題について、積極的な協力を進める。
③ 各国が共通して推進している大型の研究開発
プロジェクトにおいて国際協力の可能性を追及し、研究開発資源の国際的な効率的活用を進める。
第2章 我が国の原子力開発利用の動向
ここでは、新長期計画に示された各項目毎にこの1年の進捗状況を振り返る。
1. 原子力発電の動向一基軸エネルギーとしての確立
(1)軽水炉による原子力発電の動向
① 原子力発電の現状
我が国の原子力発電は、昭和63年11月末現在、運転中のものは合計35基、発電設備容量2,788万1千キロワットとなっている。これに建設中及び建設準備中のものを加えた合計は53基、4,590万8千キロワットとなっている。
原子力発電は、昭和62年度末現在、総発電設備容量の17.1%、昭和62年度実績で、総発電電力量の29.1%と、主力電源として着実に定着してきている。また、設備利用率は昭和62年度には77.1%と過去最高の実績となった。運転時の故障・トラブル等に基づく計画外停止回数も、昭和61年には0.4回/基・年と低く、引き続き諸外国に比べ優れた実績を示している。
② 原子力発電の経済性
昭和62年度運転開始ベースのモデルプラントについて、耐用年を通じた発電原価を通商産業省が試算した結果によれば、原子力が9円/キロワット時程度、石炭火力が10~11円/キロワット時程度、石油火力が11~12円/キロワット時程度、LNG火力が11~12円/キロワット時程度となっている。現時点において、原子力発電は依然として最も経済性の高い電源である。
③ 立地の促進等
現在、政府及び事業者は、立地を促進するため、各種メディア、原子力モニター制度等を活用して、地元住民をはじめとする国民の理解と協力を得るための努力を続けている。
また、立地地域の振興対策の拡充を図るため、電源三法の活用等が逐次図られている。
④ 軽水炉技術の研究開発
我が国では、政府、電気事業者、原子力機器メーカー等が一体となり、自主技術による軽水炉の信頼性、稼働率の向上、従業員の被ばく低減等を目的とした軽水炉改良標準化計画を昭和50年から進めてきた。このうち、第1次及び第2次計画の成果は、既に運転を開始しているプラントに適宜反映されている。また、第3次改良標準化計画は、第1次、第2次計画の成果を基に自主技術を基本として、日本型軽水炉の確立を目指して昭和56年から開始された。本計画においては、いわゆる改良型軽水炉(A-LWR)の開発が進められた。
また、軽水炉は長期にわたって原子力発電の中核を担うこととなると考えられるが、現在の軽水炉の技術水準に満足することなく、更なる高度化を図っていくため、炉心の高機能化、燃料の高性能化、新素材の活用等の検討が進められている。
⑤ 原子炉の廃止措置
廃止措置関連の技術開発については、商業用原子炉の廃止措置が必要となる昭和70年代前半に向けて、昭和56年度から、日本原子力研究所において動力試験炉(JPDR)をモデルとして行われてきている。
また、(財)原子力工学試験センターにおいては、廃止措置に係る技術のうち、安全性、信頼性の観点から特に重要な技術について確証試験を進めている。
なお、廃止措置に伴って発生する放射能レベルが極めて低い多量の放射性固体廃棄物については、その合理的な処分を行うための放射能レベルに関する基準値について、原子力安全委員会放射性廃棄物安全基準専門部会において検討を行っている。
(2)核燃料サイクルの確立
① 核燃料サイクル事業化の進展
燃料加工については、既に民間における事業化が行われており、多くの実績を収めている。
ウラン濃縮については、日本原燃産業(株)が、昭和63年8月に、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」に基づく加工事業の許可を受けた。低レベル放射性廃棄物処分についても、同社が昭和63年4月に廃棄物埋設事業の許可申請を行った。また、軽水炉使用済燃料再処理については、日本原燃サービス(株)が、1990年代半ば頃の運転開始を目指して所要の準備を進めている。
② ウラン濃縮
我が国におけるウラン濃縮技術の研究開発については、当面遠心分離法によりこれを推進することとしており、これまで動力炉・核燃料開発事業団が中心となって進めてきた。同事業団は、昭和54年度から岡山県人形峠においてパイロット・プラントの運転を行ってきており、昭和68年4月には、原型プラントの第1期分(年間100トンSWU)の操業も開始した。
さらに、同事業団では、新素材高性能遠心機の研究開発を民間と共同で行っている。
一方、遠心分離法に続くウラン濃縮に関する新技術として研究開発が進められているレーザー法と化学法のうち、レーザー法については、日本原子力研究所とレーザー濃縮技術研究組合が、原子レーザー法の基礎プロセス試験及び機器開発・システム試験を進めており、動力炉・核燃料開発事業団及び理化学研究所は、分子レーザー法の工学実証試験、プロセスの最適化及びレーザーの高度化を進めている。
また、旭化成工業(株)では、国の助成を受けて化学法の開発を進めている。
③ 使用済燃料の再処理
軽水炉使用済燃料の再処理技術の開発は、これまで動力炉・核燃料開発事業団を中心に行われてきた。
我が国で発生する使用済燃料の再処理については、同事業団の東海再処理工場に加え、英国及びフランスに委託して行っている。
将来的には、東海再処理工場と日本原燃サービス(株)が青森県上北郡六ケ所村において建設計画を進めている再処理工場(処理能力は年間800トン)により、需要に対応することとしている。また、国内における再処理能力を上回る使用済燃料については、再処理するまでの間、適切に貯蔵・管理することとしている。
④ 放射性廃棄物処理処分
(i)低レベル放射性廃棄物
原子力発電所等において発生している低レベル放棄性廃棄物のうち、気体状廃棄物及び一部の液体状廃棄物については、十分に低い所定の放射能レベル以下であることを確認し、大気中または海水中に放出している。その他の低レベル放射性液体状廃棄物及び固体状廃棄物については、発生量を極力低減しつつ、適切に減容し、固化する等の処理を行って、各発電所等の敷地内に安全な状態で貯蔵されている。
低レベル放射性廃棄物の最終的な処分方法としては、陸地処分及び海洋処分を行うことを基本的な方針としている。
このうち陸地処分については、日本原燃産業(株)が昭和66年頃の操業開始を目途に、昭和68年4月に廃棄物埋設の事業の許可申請を行った。また、海洋処分については、関係国の懸念を無視して処分は行わないとの考え方の下にその実施については慎重に対処することとしている。
(ii)高レベル放射性廃棄物
再処理施設において使用済燃料から分離される高レベル放射性廃棄物については、これまで、動力炉・核燃料開発事業団東海再理工場において発生したものが、厳重な管理の下で工場内のタンクに貯蔵されている。
これらについては、今後、日本原燃サービス(株)が建設を計画している再処理工場の運転に伴い発生する廃棄物と同様、安定な状態にガラス固化する。その後、海外再処理に伴い返還される予定の高レベル放射性廃棄物と同様に、30~50年間程度冷却のための貯蔵を行った後、地下数百メートルより深い地層中に処分することを基本的な方針としており、現在、処分技術の確立に向けて破究開発が進められている。
我が国においては、これまで、動力炉・核燃料開発事業団を中心にガラス固化技術の研究開発が進められてきており、昭和68年6月には、東海再処理工場に付設してガラス固化プラントの建設に着工した。また、同事業団は、ガラス固化された高レベル放射性廃棄物等の貯蔵を行うこと及びその処分技術を確立するために必要な試験研究等を行うことを目的とした「貯蔵工学センター」を北海道天塩郡群幌延町に設置することを計画している。
高レベル放射性廃棄物の地層処分については、研究開発と並行し、全国的な調査を行い、処分予定地の選定を行う。その後、処分予定地における処分技術の実証を経て、処分場の建設・操業・門鎖を行う計画である。
(3)プルトニウム利用への展開
使用済燃料を再処理することによって得られるプルトニウムは、準国産エネルギー資源と考えられ、これを利用することによりウラン資源の有効利用が図れるため、エネルギーの安定供給上、その意義は極めて大きい。このため、当面は、軽水炉及び新型転換炉において一定規模のプルトニウム利用を進め、これと並行して高速増殖炉の研究開発を着実に進める方針である。そして、2020年代から2023年頃を目途に、高速増殖炉によるプルトニウム利用体系の確立を目指すこととしている。
① 軽水炉によるプルトニウム利用及び新型転換炉
軽水炉によるプルトニウム利用(プルサーマル)については、日本原子力発電(株)が敦賀1号機(BWR)及び関西電力(株)が美浜1号機(PWR)において、ウラン・プルトニウム混合酸化物(MOX)燃料の少数体実証計画を進めている。
新型転換炉(ATR)の開発は、動力炉・核燃料開発事業団が行ってきており、現在、原型炉「ふげん」(電気出力16万5千キロワット)が順調に運転されている。
また、実証炉(電気出力60万6千キロワット)については、電源開発(株)が、昭和73年の運転開始を目指して青森県下北部大間町に建設準備を進めている。
② 高速増殖炉
高速増殖炉(FBR)については、これまで動力炉・核燃料開発事業団が実験炉「常陽」(熱出力10万キロワット)において多くの技術データを蓄積してきている。また、この成果を踏まえ、原型炉「もんじゅ」(電気出力28万キロワット)の建設工事が福井県敦賀市において昭和67年度臨界を目指して進められている。
これに続く実証炉の開発については、官民の協力の下に進め、同炉の設計・建設・運転に主体的役割を果たす電気事業者が、動力炉・核燃料開発事業団と密接に連携してこれを進めることとなっている。
③ 高速増殖炉使用済燃料の再処理
高速増殖炉使用済燃料の再処理は、高速増殖炉の増殖の特性を発揮させ、燃料の有効利用を図るために不可欠であり、その技術については、動力炉・核燃料開発事業団において、実規模モックアップ試験、高レベル放射性物質研究施設における基礎的データの蓄積等が進められている。
④ MOX燃料加工
MOX燃料加工については、これまで動力炉・核燃料開発事業団が行ってきており、現在、新型転換炉原型炉「ふげん」用及び高速増殖炉用の燃料製造施設がある。また、新型転換炉実証炉用燃料製造施設の建設が進められている。
⑤ プルトニウムの輸送
海外再処理により回収されるプルトニウムの日本への国際輸送については、関係機関の緊密な連携の下に輸送体制の整備を図る必要がある。
回収プルトニウムの国際輸送の方法としては、航空輸送及び海上輸送が考えられる。航空輸送については、現在、動力炉・核燃料開発事業団において、万一の航空機事故の際にも健全性を確保しうる輸送容器に関する研究開発等が進められている。また、海上輸送についても、昭和63年10月、新日米原子力協力協定の下で米国の包括同意が得られたため、今後、その検討を進めることとしている。
2. 原子力研究開発の動向-創造的科学技術の育成
原子力技術の向上を目指した研究開発の推進は、原子力技術を構成する広範な科学技術の水準向上のための牽引力となる。このため、大きな技術革新を引き起こし、ひいては科学技術全般への波及効果が期待される基礎研究、基盤技術開発及び先導的プロジェクト等の推進を図ることが重要である。
(1)先導的プロジェクト等の推進
① 核融合の研究
我が国における核融合の研究は、今日、米国、ECと並んで世界の最先端の研究水準にある。
日本原子力研究所においては、昭和62年9月臨界プラズマ試験装置(JT-60)が原子力委員会の定めた臨界プラズマ条件の目標領域に到達した。その後、プラズマ性能の大幅な向上を図るための機器改良等を行い、トカマク型装置の高性能化に努めている。
一方、昭和63年4月からは、米国、ソ連、EC及び我が国の4者で国際熱核融合実験炉(ITER)共同設計活動が開始された。
② 放射線利用の推進
放射線利用は、原子力発等のエネルギー利用と並び原子力平和利用の重要な柱であり、農業、工業、医療等の幅広い分野に及んでおり、国民生活に直接かかわりのあるものも多い。
農業においては、ガンマ線を照射した不妊虫放飼法による害虫防除、農作物の品種改良等の放射線利用が行われている。また、食品照射については、今後の一層の実用化を図るため、関係行政機関の協力の下に消費者の理解の増進等に取り組むとともに、諸制度の整備等を行うこととしている。
工業においては、工業製品の寸法測定等に放射性同位元素が利用されているほか、放射線源を用いた非破壊検査法、電子線照射による高分子材料の改質等が実用化されている。
また、医療面においても、診断及び治療の両面で放射線が広く利用されており、エックス線コンピュータ断層撮影、電子線、エックス線及びガンマ線によるがん治療等は既に実用化されている。
今後の放射線利用の研究開発については、より高度な技術の創造を目指した研究開発に重点をおいて推進することとしており、高輝度のシンクロトロン放射光(SOR)や重粒子線などのビーム発生・利用技術の高度化、新しいトレーサを用いたポジトロン断層撮影装置等の研究開発が進められている。
③ 高温工学試験研究
我が国の高温工学試験研究は次世代の原子力利用を開拓する先導的・基礎的研究の一つとして、これまでに蓄積された技術及び人材を有効に利用しながら総合的・効率的に進めることとしている。現在、日本原子力研究所において高温工学試験研究炉建設のための設計が進められている。
④ 新しい型の原子炉の検討
高転換軽水炉、中小型安全炉、モジュール型液体金属炉等の新しい型の炉については、基礎的・基盤的研究を段階的に、かつ、幅広く推進し、将来の原子炉技術のブレークスルーの可能性の検討が行われている。また、新しい型の原子炉の研究開発の効率的推進を図るため、原子炉設計のノウハウ、データベースの有効利用等を目指した高度情報処理技術の検討も開始されている。
⑤ 原子力船の研究開発
原子力船「むつ」の研究開発については、昭和63年1月関根浜新定係港に回航後、機能試験を実施し、昭和63年8月より原子炉容器蓋開放点検が行われている。今後は昭和64年度に出力上昇試験、昭和65年度末までに概ね1年の実験航海を実施した後、解役する予定であるが、原子力船「むつ」の実験航海により得られる実験データ、知見は、内外の新たな知見と合わせて蓄積整備し、その成果を今後の舶用炉の改良研究に十分活用していくこととしている。
(2)基礎研究及び基盤技術の開発
① 基礎研究
原子力の分野においても、多様化するニーズに対応し、更に新しいシーズの探索を促進するため、基礎研究を段階的に、かつ、幅広く行い、その充実を図っていくことが重要である。
我が国では、炉物理・核物理に関する研究、燃料・材料の照射試験、放射性物質の環境中での拡散・移行に関する研究等、種々の分野について、日本原子力研究所をはじめとした国立試験研究機関、大学等が着実な研究を行っている。
② 基盤技術の開発
我が国の今後の原子力開発利用の推進に当たっては、新しい技術を創出し、ひいては既存の原子力技術体系にブレークスルーをもたらす可能性のある基盤技術の開発を積極的に進めていくことが不可欠である。
昭和62年9月に原子力委員会の下に設置された基盤技術推進専門部会は、本年7月に報告書をまとめ、これまで培ってきた原子力における技術ポテンシャルを活用しながら、従来の原子力技術体系にインパクトを与えるようないわば創造型の技術開発の推進を図ることとしている。
3. 主体的・能動的な国際対応の推進-国際社会への貢献
(1)核不拡散対応
我が国は、原子力の研究、開発及び利用を平和目的に限って推進している立場から、国際的核不拡散の枠組みの維持・強化については、これまでも積極的に国際協力を進めてきた。
① 二国間協議
(i)新日米原子力協力協定
昭和62年11月、個別事例毎ではなく、長期的及び予見可能な方法で同意を与える包括同意方式を導入した新日米原子力協力協定が署名された。その後、両国それぞれ所要の国内手続きを終え、同協定は昭和63年7月に発効した。
今回、協定を改定し、包括同意方式とすることにより、我が国の核燃料サイクル計画は長期的な見通しの下での安定的運用が可能となった。
さらに、新協定においては、回収プルトニウムの日本への国際輸送について、一定のガイドラインに従う航空輸送に対し包括同意が得られている。
また、海上輸送による回収プルトニウムの国際輸送についも、日米間で交渉を進めた結果、昭和63年10月、一定のガイドラインに従う海上輸送についても、米国の包括同意が得られることとなった。
(ii)その他の原子力協定
我が国は、英国、フランス、カナダ、オーストラリア及び中国とも原子力協定を締結しており、この協定に基づき、協定対象核物質の管理、原子力協力の実施等を行っている。
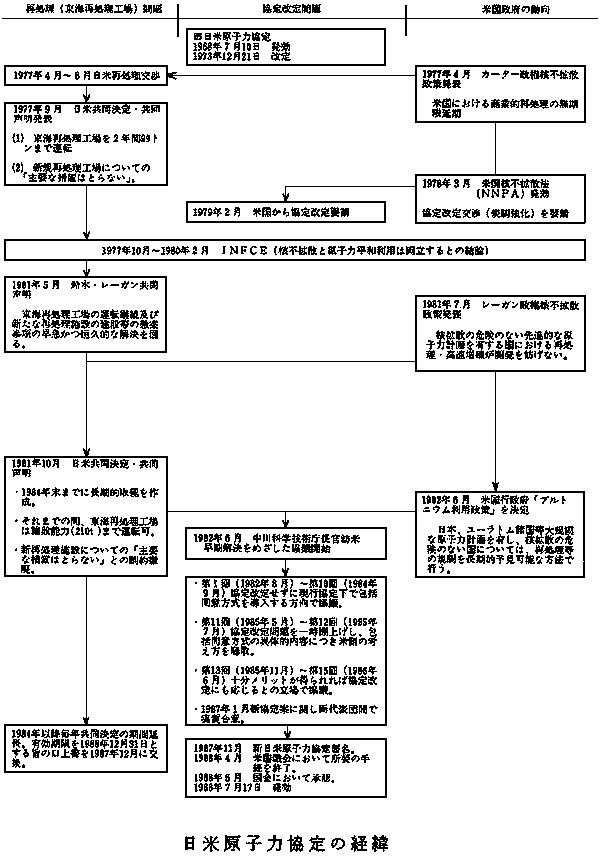
日米原子力協定の経緯
② 核物質防護
核物質の不法な移転によりもたらされる危険を防止するため、IAEAの場でまとめられた核物質防護に関する条約が昭和62年2月に発効した。
我が国においては、昭和63年5月、同条約への加入が国会で承認され、これと同時に、同条約に加入するために必要となる同条約が定める核物質を用いた犯罪の処罰規定等を盛り込んだ、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部改正が行われた。その後、同年10月に政府は加入のための手続きを終え、11月に同条約は我が国について効力を生じた。
③ 保障措置
我が国は、IAEAとの保障措置協定に基づいて、国内保障措置体制の維持を前提として、全原子力活動に対して、IAEAの保障措置を受入れている。また、IAEAの保障措置に関連する技術開発を支援するため、「対IAEA保障措置技術開発支援計画」(JASPAS)を積極的に推進する等、保障措置の効果的・効率的適用のための各種研究開発を行っている。
(2)研究開発協力
① 二国間協力
(i)先進国対応
我が国は、日本原子力研究所、動力炉・核燃料開発事業団及び大学を中心として、米国、西独、フランス、英国、カナダ等と、原子力の安全研究、核融合、高温ガス炉等の研究開発分野について、情報交換、人材交流、共同研究等の協力を活発に行っている。
(ii)開発途上国対応
我が国は、従来から開発途上国の要人・専門家の招聘、原子力関係研究者の交流、専門家の派遣・受入れ、技術研修生の受入れ、各種セミナー等の開催を実施している。
② 多国間協力
(i)近隣地域対応
我が国と地理的・経済的に密接な関係にある近隣アジア地域における資金、人材等研究開発資源を最も効果的・効率的に活用するために、我が国を含めた地域ぐるみの協力が有効であり、その可能性の検討が進められている。
(ii)国際機関対応等
我が国は、保障措置、放射性物質輸送基準等IAEAの主催する原子力に関する各種シンポジウム、専門家会合等に多数の専門家を派遣し、情報の収集と交換を行っている。
核融合の研究開発については、日本、米国、EC(ユーラトム)及びソ連が協力して、昭和63年4月から、国際熱核融合実験炉(ITER)の共同設計活動を開始した。
また、放射線・RI利用の分野でアジア地域と協力を行っている。
なお、昭和63年10月、我が国として初めて、IAEAのOSART*を関西電力(株)高浜発電所(3、4号機)に受け入れ、その専門家チームから高い評価を得た。
放射性廃棄物の処分、原子炉施設の安全性等原子力開発を推進する上で各国共通の問題を解決するためのOECD/NEAのプロジェクトに対しても、我が国は従来から参加している。
注)*Operational SAfety Review Team
世界の原子力発電の安全性、信頼性向上を目指し、IAEAが加盟国の要請に基づいて原子力発電所の運転管理状況を調査し、国際的に経験交流を行う専門家チームのこと。
(参考)昭和63年度原子力関係予算総表
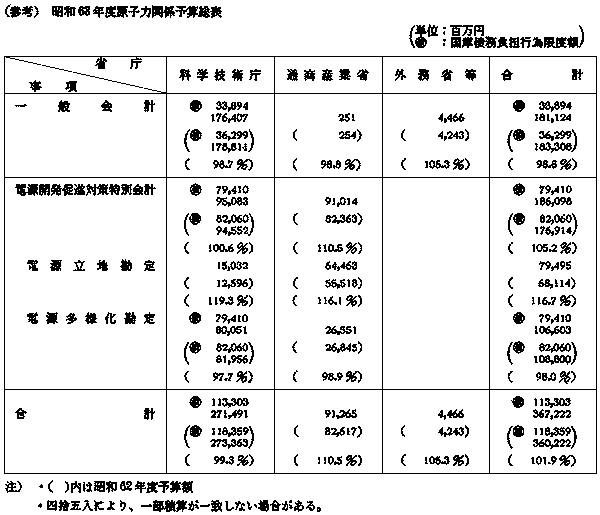
|