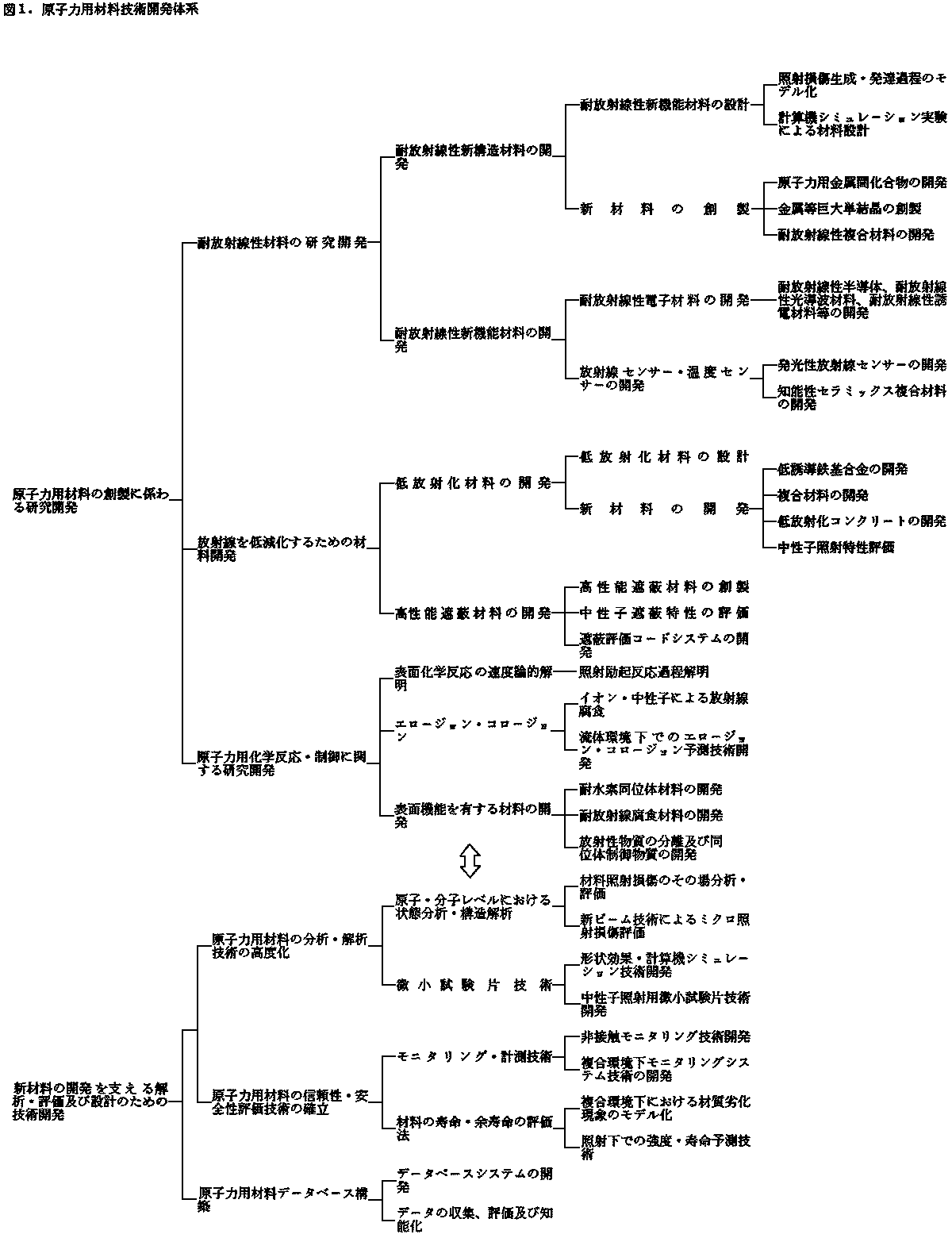
| 前頁 |目次 |次頁 |
|
資料 基盤技術推進専門部会報告書 昭和63年7月 先般策定された「原子力開発利用長期計画」(昭和62年6月原子力委員会)において、今後は原子力の持つ新たな可能性の開拓を目指していく段階にあるとの認識に立ち、これからの研究開発は、技術の芽の探索、体系的な研究開発の積重ね等により大きな技術革新を引き起こし、ひいては科学技術全般への波及効果が期待される原子力のフロンティア領域といわれる創造的・革新的領域を重視し、基礎研究とプロジェクト開発とを結びつける基盤技術開発を推進するとの方針が示されている。 このことから、これら基盤技術開発を計画的・効率的に進めることによって、原子力開発利用におけるリーディングカントリーとして国際的な責務を果たすとともに、安全性・信頼性・経済性の向上という原子力技術に課せられた今日的課題のブレークスルーを図り、21世紀初頭の原子力技術体系を構築する必要がある。こうした原子力利用のさらなる進展を図ることにより、活力があり豊かな未来社会を創り出していくことができるものと期待される。 このため、昭和62年9月に基盤技術推進専門部会が設置され、当部会の下に設けられた分科会における基盤技術の各分野毎の技術的な検討とともに、基盤技術の開発を着実に推進する方策等について審議検討を行い、今般以下のとおり取りまとめた。 なお、原子力基盤技術開発については、本報告書にて取り上げられている技術分野以外の新たな分野の技術開発の可能性も含めて、技術開発の方向、技術開発体系、推進体制等について、技術開発の進展、諸般の情勢変化に伴う見直しを適宜行いつつ、中長期的観点に立って、着実かつ積極的に推進することが重要である。 Ⅰ.原子力基盤技術開発の意義 1.これまでの原子力開発の方向性 我が国の原子力開発利用は、原子力発電等を早期に実用化することを目指しながら、初期段階では欧米の進んだ技術を導入することによりこれに追いつき、さらに高速炉などの新型炉や核燃料サイクル技術における欧米の技術に目標を置いた自主開発を進めてきた。 この結果が今日の原子力発電の定着、核燃料サイクルの事業化等に展開してきたものであり、この30年の技術開発はいわば“キャッチアップ型”の技術開発とでも言い表すことが出来よう。 こうして確立した原子力技術は、広範な学問領域に立脚する技術であるとともに、巨大なシステム技術、先端技術、極限技術及び高信頼性技術としての特質を持っており、幅広くかつ高度な知識及び技術が集大成されたものと考えられる。しかしながら、これまでの技術開発は、これらの幅広い技術的な基盤を強化することよりも既存の技術を組みあげていくプロジェクト型が中心であり、原子力分野における新たな技術革新や創造的な技術を積極的に生み出していくという視点を持って行っていくものではなかった。このため、原子力技術体系は既存技術の飛躍的ブレークスルーや創造的技術の創出のために必要な基盤を十分確立してきたとは言い難い。 2.原子力を取り巻く状況の変化 今日我が国が置かれている諸状況を鑑みるに、エネルギー情勢を始め、原子力を巡る環境はオイルショック時より大きく変化してきている。すなわち、原油価格が低位に推移し、エネルギー需要が緩やかな伸びを示している中、原子力発電についていえば昭和40年代、50年代の発電規模の増大といういわば量的拡大の時代から、発電の安全性・信頼性・経済性等の質的な向上を目指す時代へと移行しつつある。さらに、核燃料サイクルの実用化、放射線利用の高度化等原子力分野におけるニーズは一層多様化・高度化しており、これに弾力的に対応する技術開発が必要となっている。 こうした中で、1986年4月に発生したソ連チェルノブイル原子力発電所の事故が、国際社会に大きな衝撃を与え、これを契機とし安全確保の重要性に対する認識が今まで以上に高まっているが、今後とも原子力技術に対する信頼性及び安全確保の一層の向上のための不断の努力を続けていかねばならない。 さらに、国際的にも、既に原子力先進国となった我が国に対して、これらの期待が特に強まっていることを付け加えねばならない。 また、最近の科学技術の進歩に目を向ければ、現在の原子力技術体系の基本構成要素が構築された時にはまだ十分には技術開発が進められていなかったセラミックス等の新素材に係る材料技術、コンピュータのハードウェア・ソフトウェア等の情報処理・通信技術、レーザー等の光技術、遺伝子操作等のライフサイエンス技術に係る研究開発が近年急速に進められてきており、21世紀を担う技術として様々な技術分野で注目され、技術開発の新たな潮流を生み出しつつある。 3.今後の原子力技術開発の方向と基盤技術 以上のような諸般の情勢を踏まえ、20世紀を残すところ10年と少しとするに至った現在、来たるべき21世紀に必要とされる原子力技術体系を意識的に構築していく必要がある。これにより、現在進行している種々のプロジェクトにおける既存技術にブレークスルーをもたらす新たな技術的知見を与えたり、あるいは今までの原子力技術体系にはなかった未知の技術領域を創出することも十分に期待できる。 このため これまで培ってきた原子力における技術ポテンシャルを活用しながら、原子力用材料技術、原子力用人工知能技術、原子力用レーザー技術、放射線リスク評価・低減化技術を当面の原子力基盤技術として位置付け、従来の原子力技術体系にインパクトを与えるようないわば創造型の技術開発へと重点を移し、積極的にこれを推進する必要がある。これによって、原子力開発利用のリーディングカントリーとしての責務を果たすとともに、多様化・高度化する原子力分野におけるニーズに対応し、ひいては科学技術全体の進展において先導的な役割を担うなど、原子力開発利用の新たな展開を図っていくことが可能となるものである。 Ⅱ.原子力用基盤技術開発の概念 原子力基盤技術として開発する原子力用材料技術、原子力用人工知能技術、原子力用レーザー技術、放射線リスク評価・低減化技術の各概念を以下に示す。 なお、ここで示されている技術分野以外にも、技術開発の進展、諸般の情勢変化に伴って新たな分野の技術開発の必要性が考えられる場合には、これを加えて推進することとする。 1.原子力用材料技術開発の概念 材料技術の開発の特徴は、あらゆる科学技術において鍵となるものであると同時に、開発された技術が他の分野の技術革新を誘発するという波及効果を有しており、このような意味でいえば、いかなる分野の材料技術も将来的に「基盤技術」であるといえる。 原子力分野における材料技術のこれまでの研究は、軽水炉、高速増殖炉、核融合炉といった炉型別の開発戦略の中で、目標の早期達成のための限定的要素技術開発といったいわゆる「縦割型」中心で進められてきている。例えば、耐放射線性構造材料の研究開発としては、鉄基材料を中心とした材料の開発が行われている。しかしながら、ここでいう基盤技術としての原子力用材料技術開発においては、より中長期的観点に立って、21世紀の原子力技術体系にインパクトを与え、ひいては原子力分野に限らず他の分野の材料技術開発への波及効果も期待できるようなものを積極的に取り入れる。 原子力用材料技術開発の概念について大別すると、第一に特に高性能化、高機能化を狙った全く新しいタイプの原子力用材料の創製を行うとともに、創製した材料の優れた諸特性の機構解明に係る研究開発を行う。ここでは、耐放射線性に優れた構造材料、機能材料の開発、放射線を低減化する低放射化材料、高性能遮蔽材料等の開発及び放射線場における材料の化学反応といった複合極限環境下で実際におこる化学反応の基本的単位である反応素過程の解明を取り扱う。第二に、ますます高度化した機能を有する材料挙動の正確な把握や使用限界の決定を行ったり、新材料の開発のための貴重な知見、指針を与えるものとして、ミクロレベルにおける分析的・系統的な材料解析・評価を行う。中でも特に、放射線環境下で起こる諸現象の原子・分子レベルでの解析技術の高度化及び材料の信頼性・安全性技術の高度化に関する研究開発を行う。また、上記の研究開発により得られた結果を中心にして、データ及び知識の体系化を図り、原子力用材料設計のための独自のデータ・ペース構築に係わる研究を行う。なお、これら2つについてはお互いに独立なものではなく、相補的関係にあるものである。 2.原子力用人工知能技術開発の概念 人工知能技術は、1950年代に技術開発が開始されて以来、集積回路等のハードウェア技術やコンピュータ・ソフト等のソフトウェア技術の急速な技術革新に支えられて伸びてきており、1980年代に入ると専門家の知識を活用するエキスパート・システム技術を高度化するための知識の獲得・学習などの高度な機能を実現するための開発へ重点が移りつつある。また、単調なルーチンワークから人的資源の解放をもたらすことが可能なロボット技術開発も積極的に進められている。これらの技術は巨大技術システムにおける人間と機械との間のヒューマン・インタフェースを改善する技術としてあらゆる科学技術分野で適用されることが期待されている。 中でも、原子力技術のような特殊で巨大な技術体系では機器・設備面による安全性の向上に加えて、機器・設備を扱う人間や機器・設備と人間とのヒューマン・インタフェース面などを含めた原子力施設全体としての安全性の向上が重要である。このため、原子力施設設計・点検補修・異常データなどから得られた原子力施設に係る各種の知識を格納した知識ペースを用いる原子力用人工知能技術開発を進めることによって、原子力施設の運転管理・異常診断・ロボットによる点検補修などをより確実に行うことが可能となると期待されている。 一方、原子力施設は一般産業の施設と比較して大規模かつ複雑であり、作業の内容が極めて多様であること並びに放射線物質を取り扱う施設であること等の特殊性を有することから、原子力用人口知能技術は一般産業における人工知能技術に比べ高度な信頼性を持つ必要があること等厳しい要求が課せられていることを十分に認識して技術開発を進める必要がある。 これらを考慮しながら技術開発を進めることにより、狭あいな放射線場で複雑な判断・動作能力を有する点検・補修用ロボット、マン・マシン・インタフェースの良いプラント運転監視システムの研究開発を行い、人間の運転・保守等を支援するシステムを伴ったプラントを中間的な目標とし、究極的には自己判断・制御を行う自律型プラントを目指すこととする原子力開発利用長期計画に示す原子力用人工知能開発計画を具現化することができると考える。この場合、原子力施設に新たに導入されていく人工知能を有する制御装置、監視装置、ロボットなどの技術開発に際しては、原子力技術開発において従来からの安全確保の概念を堅持し、システムとして体系的に検討を行いながら、段階的に進める必要がある。さらに、人工知能を具備した原子力施設とそれに携わる運転員・保守員等とのヒューマン・インタフェースのあり方についても十分に検討する必要がある。 このような技術開発を進めることによって、「知的活動を行っている人間と高度化しつつある機械が混在しながら、ある目標に向かって動作する」という原子力施設特有の複雑な作業・操作・制御を示す「人間-機械系の世界」を記述することができる「原子力施設学」ともいうべき新たな学問領域も創出されてくると考えられる。 これら原子力施設の自律化を進めるためには、 ① 原子力施設の運転・保守において人間に代わり得る人工知能を備えたハードウェアおよびソフトウエア技術の開発を進めていく必要がある。 このような自律型システム技術には、自己診断機能、自己保存機能、学習機能等の自己改良機能、未知事項処理機能という基本機能が具備されている必要がある。 3.原子力用レーザー技術開発の概念 レーザーは、時間的・空間的制御性のきわめて良い光の利用を可能とし、高度のエレクトロニクス技術との結合によって、情報分野では既に技術革新を生み出しつつある。これらレーザー技術については、既にウラン濃縮、核融合等への利用のための研究開発が行われているが、レーザーの持つ特質をさらに広く原子力分野へと活かしていくことが期待されている。 すなわち、原子力利用におけるレーザーの注目すべき性質としては、①原子・分子を特定のエネルギー準位に励起することが可能なこと、②レーザーの指向性を利用した遠隔操作性、③大きなエネルギーを一ケ所に集中できること等が挙げられる。これらの性質を原子力分野に利用するに当たっては、高密度なエネルギーとしての特性はもとより、例えば分離技術においては大量処理、経済性が必要となるなど基本的に高出力が要求されるものである。それゆえこれに伴って効率、寿命、信頼性の向上が求められる他、高い繰返しにより高出力のレーザーを発生させる技術が必要となる。さらには同位体・元素とのかかわり合いが利用の中心となるため、様々な励起エネルギーに対応するための波長可変技術が必要となってくる。 これら原子力分野で用いられるレーザーに関する技術、すなわち原子力用レーザー技術には三つの技術領域がある。すなわち、原子力分野の技術革新に対応するためのレーザー応用技術、これらの応用技術を支えるために必要なレーザー本体及び周辺機器技術、及び原子力に新たな利用の可能性を与えるレーザー技術である。 4.放射線リスク評価・低減化技術開発の概念 近年におけるライフサイエンスの進展は著しく、遺伝子操作、発生工学、細胞融合、染色体工学等いわゆるバイオテクノロジーの開発がなされ、生物学のあらゆる分野に大きなインパクトを与えている。 原子力開発利用において常に留意している放射線の人体への影響を評価する放射線リスク評価については、従来は疫学的な研究により得られた知見を中心に進められてきたが、これに最新のライフサイエンス分野の研究成果を積極的に取り入れることにより、より一層充実した知見を得ることや放射線リスク評価技術に係る新しい技術を創出することが期待されている。 例えば、遺伝子操作を駆使した新生物種の創出によるバイオセンサーの開発、遺伝子操作・細胞融合法によって作出したモノクローナル抗体による発がん高リスク個体の検出法の確立、発生工学的技術を用いて各種クローン化遺伝子を導入した放射線リスク評価のためのモデル実験動物(トランスジェニックマウス等)の開発等が挙げられる。 さて、人間をはじめとして地球上のあらゆる生物は、生命の誕生以来、宇宙線、大地からの放射線、体内や食物、大気などに含まれている自然の放射性物質からの放射線などの自然放射線と永きにわたって共存してきた。これら自然放射線量には、地域差があるが、地球全体の平均値で年間約2ミリシーベルトである。これを原子力の開発利用に伴う放射線量と比較すると、例えば我が国の発電用軽水炉施設の線量管理目標値(全身)は年間0.05ミリシーベルトであり、これは関東地方と関西地方の自然放射線量の地域差に入るような小さいものである。しかしながら、原子力開発利用においてはこれら小さな線量についても高い線量の影響評価を外挿して安全側に評価している。 すなわち放射線医学的に低線量とされている0.2~0.25シーベルト程度以下の線量(以下、低線量という)では、疫学上放射線による影響は見られていないが、放射線リスク評価について安全を期するため、発がん、遺伝的影響について高線量域での線量効果関係を直線外挿して低線量域でのリスクの評価を行っている。これら低線量域でのリスクの評価について、ライフサイエンス分野の最新の研究成果を導入することにより遺伝子、分子レベルで評価することが可能となれば、発がん、発生障害、遺伝的影響等に関する知見をより一層充実させ、低線量域における評価をさらに適切に行うことにより、国民の安全確保に関する知見のより一層の充実を図ることができる。 放射線リスク評価・低減化技術開発においては、以上を踏まえながら、放射能等の測定技術開発、放射線被ばく線量評価技術開発、外部被ばく・内部被ばくの人体への影響評価技術開発等を進めることにより、放射線リスク評価技術開発を行うとともに、これらの知見をもとにして、放射線リスクを低減化するために必要な技術開発を行う。 Ⅲ.原子力基盤技術開発計画 推進すべき4つの技術分野について、各々行うべき技術課題及びその将来像について以下に示す。 1.技術開発課題 (1)原子力用材料の技術開発課題 原子力用材料技術開発においては、 ① 放射線の照射損傷による材料特性の劣化を改善するための耐放射線性材料の創製。を基本的な技術要素として、図1に示す原子力用材料技術体系を確立させ、これらの技術を効率的に開発していく必要がある。 ① 耐放射線性材料の開発(2)原子力用人工知能の技術開発課題 原子力用人工知能技術開発においては、その中核となる自律型システム技術に必要なハードウェアとソフトウェアを技術開発する必要がある。自律型システム技術に必要なハードウェア技術においては、特に機能分散と配置分散を行うことが可能な分散型高速並列処理コンピュータ・システム技術を確立することが必要である。これにより、原子力施設における運転・保守情朝を一括処理するのではなく並列処理することができるとともにネットワーク・システム等の故障時にも信頼性の確保を図ることが可能となる。この他、ロボット、センシング素子・機器等のハードウェア技術を確立させることが必要である。ソフトウェア技術においては、プラント用知識ベース、ロボット用知識ペースとともに、原子力施設に係る多種多様な情報を自動的に分類し、これを体系化するために必要な基本ツールである知識ペース形成システム技術を確立することが必要である。 さらに現在ではまだアイデア段階であったり、技術開発の初期段階ではあるけれども、人工知能に係る技術開発が順調に進めば21世紀初頭に目途が立つと期待されるニューロ・コンピュータ・システムやバイオ・コンピュータ・システム等の技術を原子力用人工知能技術に導入すれば、加速度的に技術開発が進捗することが期待される。 なお、人工知能技術開発が様々な分野・機関等で進められていることを考慮しながら、原子力用人工知能の技術開発を進める必要がある。 以上を踏まえて、これらの要素技術開発として、 ① 知識ベース・システムを基本的な要素技術として、図2に示す原子力用人工知能技術体系を確立させ、これらの技術を効率的に開発していく必要がある。 ① 知識ベース・システムに係る要素技術(3)原子力用レーザーの技術開発課題 原子力用レーザーは、基盤技術として、図3に示す①原子力用レーザー応用技術、②原子力に必要とされるレーザー技術、③原子力に新たな利用の可能性を与えるレーザー技術からなる。すなわち、 ① 原子力用レーザー応用技術(4)放射線リスク評価・低減化の技術開発課題 放射線リスク評価・低減化は、基盤技術として、図4に示す①被ばく線量評価技術、②放射線リスク評価技術、③放射線リスク低減化技術からなる。すなわち、 ① 被ばく線量評価技術2.技術開発の将来像 原子力開発利用体系の今後については、昨年6月に策定された「原子力開発利用長期計画」の中で将来の目標が示されている。これによれば、今日のエネルギー需給の安定は、世界的な石油危機後のエネルギー需給構造の調整によるところが大きく、将来のエネルギー需要は緩やかな伸びを示していくものと予測されているとし、原子力を我が国のエネルギー供給構造の脆弱性の克服に貢献する基軸エネルギーとして位置付け、その安全性・信頼性・経済性等の質の向上を重視して開発を進めていくこととしている。 すなわち、原子力発電の基本路線として、軽水炉によるウラン利用に勝るプルトニウム利用体系の確立を目指し「再処理-リサイクル路線」を、またプルトニウムの利用形態に関しては「軽水炉から高速増殖炉へ」を基本に炉型戦略を進めることとしている。このため、軽水炉及び新型転換炉における一定規模のプルトニウム利用を進めながら長期的な核燃料サイクルの総合的な経済性の向上を図ることによって、2020年代~2030年頃における高速増殖炉によるプルトニウム利用に係る技術体系の確立を目指していくこととしている。さらに、超長期的な未来を見れば、人類の恒久的エネルギー源の確保を可能とする核融合の実現や科学技術の高度化に寄与する放射線等原子力の利用など、未知の開拓領域があるとしている。 また、21世紀を担う科学技術の実現時刻の予測が昨年9月に科学技術庁から出されているが、これは最新の科学技術の進展状況やその動向を考慮に入れつつ、材料、ライフサイエンス、労働環境、情報・通信等の専門分野の研究者、技術者による実現予測を行ったものである。中でも原子力基盤技術分野に関連する材料技術では、金属材料の単結晶化技術、材料開発用のシミュレーション技術、残存寿命推定技術等の高度化された評価技術、金属・セラミックスの接合技術、新機能を持つ物質の合成手法技術等の機能材料技術等が21世紀には実現されると予測されている。 人工知能技術では、ニューロ・コンピュータ等の非ノイマン型並列処理コンピュータ等の高速処理コンピュータ技術、臨場感のあるテレビ映像システム、三次元画像処理技術、複雑なパターンを人間並に識別する技術等の情報収集・処理技術、人に代わって巡回しトラブルを除去することができる知能ロボット等が実現されると予測されている。また、レーザー技術では、X線領域のレーザー技術、工業用大出カエキシマーレーザー発生装置、波長可変レーザーを用いた材料合成技術等が21世紀の技術として確立あるいは普及することが予測されている。さらに、ライフサイエンス技術では、高等生物における遺伝情報発現機構の解明と人為的操作技術の開発、神経の形成機構やその高次活動としての記憶、思考等の脳活動を研究する神経科学、脳科学の進展、さらにがんや遺伝子病の発症機構や老化機構の研究が21世紀初頭までに大幅に進展すると予測されている。 また、環境科学分野では、環境及び生体中における元素の存在形態ならびに形態別生物影響のメカニズムが解明され、放射性核種等有害物質の存在形態を人為的に変換操作することにより、その無害化ならびに生物濃縮を阻止する技術の開発が可能となると予測されている。 これらに鑑みれば、基盤技術開発の意義のところでも述べたとおり、科学技術の面から見た原子力の総合性及び先端性に着目して、原子力研究の幅を広げ、高度な知識及び技術が集大成された原子力技術体系の技術基盤を充実強化し、他の分野との相互交流、連携を深めることにより創造的・革新的な技術や知識を生み出していくことにより科学技術全体への波及についても展望されるものである。 以下に基盤技術の各分野の将来像について述べる。 (1)原子力用材料の将来像 ここで取り上げた原子力用材料技術開発の明確な実現目標を正確に設定することは容易なことではないが、1990~2030年の長期的な開発イメージを与えるものを示す。 1990年代に0.1nmレベルでの材料照射損傷その場分析評価技術開発を確立する。これにより、照射損傷を起こしつつ、それを顕微鏡的手法により原子レベルで動的に観察することが可能となり、照射損傷の素過程の解析、材質劣化機構の解明、新材料の実現を期待する。 ポリエチレン等のポリマー系材料は、中性子線に対する軽量遮蔽材料の1つであるが、2000年代初頭には、500℃以上の高温に耐えるポリマー系遮蔽材料の実現を期待する。これにより、放射線が効率的に遮蔽でき、原子力施設の安全性の向上に資する。また、元素には複数の同位体が存在するが、その中の低放射化同位体だけから成る金属材料を実現し、原子力システムの安全性及び原子力の利用分野の拡大に資する。 2010年代には、耐放射線性新機能材料として、X線・γ線等の放射線場でも使用可能な光導波材料を開発し、光の伝送・制御に利用する。また、データベースの人工知能化及びそれを使った材料設計システム開発を行い、利用者の求めに応じた材料設計を行うためのデータ・ベースを提供する。さらに、照射損傷や化学反応等の素過程を追跡するために、それらの現象が起こる実際の時間を分解し、かつ試料の厚さ方向の分析を行う実時間3次元マイクロ構造解析技術の確立を期待する。 316ステンレス鋼は、照射量20dpa、ヘリウム生成量1800ppm程度の照射により、著しい脆化を示すが、2020~2023年には、照射量100dpa、ヘリウム生成量5000ppmで、しかも2000~3000℃の高温にも耐える耐放射線性構造材料の実現を期待する。さらに、照射により、特性劣化につながるような結晶欠陥等が見かけ上増加しない、いわゆる自己修復型耐放射線性半導体等の創製を期待する。 また、核反応利用による放射性同位体を消滅させる低放射化複合材料といった放射線低減化材料の実現を期待する。さらに、人工知能と照射損傷理論による汎用照射下寿命予測法を確立し、材料の信頼性・安全性評価の高度化に資する。原子力用材料化学においては、原子力用材料における放射線等の物理的攻撃と化学反応を併せた原子力極限複合環境下の表面反応速度制御利用による表面構造制御・改質材料の実現を期待する。 (2)原子力用人工知能の将来像 2000年過ぎまでに知識ベースの形成用ツール、知識ベースの形成、分散型高速並列コンピュータ・システムの実現を期待し、これらの技術を用いて改良したマン・マシン・インタフェース技術を活用した運転監視システムの実現を期待する。 また、2005年頃に知識ベース・システムの中核的技術である自律型基本形成システムを確立、自律型ロボットと自律型プラントの実現を期待する。 さらに、超知能化コンピュータ・システムとバイオ・コンピュータ・システム並びにそれらを統合したコンピュータ・システムが実現すれば、2015年頃に超自律型ロボットと超自律型プラントの実現が期待できる。 特に、原子力用人口知能技術開発は新型炉や核燃料サイクルに関して現在行われている技術開発に比べて、極めて早いテンポで進められることが予測されるので、原子力施設の機器開発等と整合性のある技術開発を進めていく必要がある。 (3)原子力用レーザーの将来像 技術開発課題に示したように、原子力用レーザー応用技術は、技術開発が進行中のレーザーまたは応用のために新たに必要となるレーザーを想定しつつ、その応用方法の技術開発を行い、原子力に必要とされるレーザー技術においてはこれら応用面からみた要求事項を満足するレーザーの技術開発を行うものである。 従ってこの二つは表裏一休となって技術開発が進められていく必要がある。また、原子力に新たな利用の可能性を与えるレーザー技術は、将来における原子力用レーザーの新しい可能性を発掘するための知見の獲得、その獲得方法の技術開発である。従って、原子力用レーザー応用技術開発と原子力に必要とされるレーザー技術開発は中期的ビジョンを持ち、また原子力に新たな利用の可能性を与えるレーザー技術開発は長期戦略的観点から推進していく必要がある。 技術開発の将来像としては、同位体・元素等の分離技術では、1990年代後半において、その目安としてgオーダーの分離が可能となるシステム技術の実現を期待する。 レーザー計測・分析技術では、1990年代後半における原子力施設へのインライン化の実現を期待する。 原子力材料、施設等のレーザー加工技術では、実際の施設等を解体する場合に必要となってくる要素技術の開発をおこなうものであり、1990年代後半において実用化試験段階へ移行することを期待する。 レーザープラズマ利用の可能性を拓くための技術では、既にプロジェクトの規模で進めている核融合への応用も含めて、プラズマ加熱及びプラズマレーザー発振等中心となる技術の実証を1995年頃までに達成し、2000年にプラズマ制御等のシステム化技術の実現を期待する。 (4)放射線リスク評価・低減化の将来像 被ばく線量評価技術のうち環境中での挙動の解析技術については、基本的な要素技術である拡散、沈着挙動等の解析及び環境中放射能(線)の測定技術の高度化を進め、この成果を広範囲、長半減期核種の時間的挙動の把握へと展開していく。また、生体内代謝挙動の解析技術については、モデルの高精度化を図るとともに、測定技術については1990年代後半における高度の物理・化学・生物的方法を用いたin ViVO法の実現を期待する。 放射線リスク評価技術は、将来における遺伝子レベルでの放射線影響の理解に基づき、関連する物理・化学及び情報科学の先端的技術の導入により、個人及び集団における健康リスクの総合的な評価を目指すものである。 放射線発がんについては、ライフサイエンスの先端技術を導入した高リスク集団の解析を行い、1990年代後半には分子レベルでの基礎的な検出技術の実現を期待する。また、放射線による発生障害については、まず障害の定量化、実験動物の開発等を行い、1990年代後半には発生工学技術等の導入による障害の検出及び評価技術の実現を期待する。さらに、放射線の遺伝的リスクについては、1990年代前半には体細胞突然変異及び染色体異常の分子レベルでの検出技術、後半にはその自動化技術の実現を期待する。以上を踏まえて、放射線リスクの総合評価技術については、1990年代後半に本基盤技術の進捗に合わせた革新的評価コードの実現を期待する。 放射線リスク低減化技術については、上記の成果を生かし1990年代後半から2000年にかけて新しい低減化の概念が生み出されることが期待される。 ただし、現時点で考えられる低減化技術についても高度化を図っておくことは当然のことであり、これはまた新概念の技術開発発想のための基礎としても非常に重要である。 Ⅳ.原子力基盤技術開発の効率的推進 原子力基盤技術開発は、プロジェクト中心に進められてきた我が国の原子力開発利用の足腰を強化することを狙って、原子力フロンティアと言われる先導的・ 創造的・革新的な技術開発を進めることとしており、前に示した技術開発計画に従って、効率的・効果的かつ体系的に進めることが求められている。このため、原子力基盤技術開発の特徴に鑑みた効率的推進方策を行う必要がある。 以下に研究交流、人材育成、国際交流、研究評価等について述べる。 1.技術開発の効率的推進に関する基本的考え方 ① 能動的な研究交流の推進 原子力基盤技術開発を進めることによって、21世紀初頭の原子力技術体系を構成する技術を組みあげることとしているが、このような技術体系を構築するためには研究者、研究機関の独自性を尊重しつつもある定められた技術開発の方向性のもとで進めるという従来の研究開発、技術開発とは異なる原子力基盤技術開発に適した開発体制を整え推進することが求められている。すなわち、原子力基盤技術開発は、相当長期間を要する技術開発になることから、国が主導して進めることが妥当であるが、この場合、基礎研究、プロジェクト開発等に様々な実績を持つ国研、国の研究開発法人、大学、民間等の研究機関がそれぞれの特色を発揮させながら産・学・官の研究ポテンシャルを結集する必要がある。 このうち民間では長期的な技術開発についてニーズが比較的明らかになっていても放射線等の原子力の特殊性が付随するものについてはその手段の整備が簡単でないため活発に行われているとは言えないが、これに対してコンピュータ技術等原子力基盤技術開発に係る一部の技術領域のように原子力のみならず科学技術一般におけるニーズが明らかになっているものについては長期的観点に立つ技術開発もかなり進んでいることを踏まえ、民間の研究ポテンシャルを最大限に生かすようにすることが必要である。 さらに、原子力基盤技術開発では、材料技術、情報処理・通信技術、光技術、ライフサイエンス技術等の最先端の科学技術を用いて技術開発を行うこととしており、特に最近のバイオ・テクノロジーを利用したコンピュータに関する技術開発のようにライフサイエンス技術と情報技術が結び付いた技術開発が行われている例にも見られるように、今後は原子力基盤技術開発においても従来行われてきた分野あるいは専門の領域を越えた幅広い技術開発を積極的に進めることが創造的な技術の創出にとってますます重要となってくるものと考えられる。 以上、原子力基盤技術開発を効率的に推進するに当たっては、原子力分野のみならず非原子力分野を含めた幅広い分野の研究者、研究機関間の研究交流が不可欠である。 このため、国研・国の研究開発法人では、既に共同研究、受託研究、委託研究、協力研究等の相互補完型の研究交流を行うとともに客員研究官制度、流動研究員制度、外来研究員制度等の研究者交流や施設の共同利用等の研究交流の諸制度が整備されているが、これらを十分に活用し、方向性を失うことなく能動的かつ弾力的な研究交流を積極的に行うため、産・学・官の研究ポテンシャルの結集に不可欠な協調的かつ競合的で活力のある研究開発環境を作っていく必要がある。 ② 創造的な人材の意識的な育成等 原子力基盤技術開発においては、単なる他分野の先端技術の導入ではなく、創造的科学技術が創出されることが重要である。このため中長期的視点に立ち、創造的な資質を有する若手研究者等人材の積極的な育成が必要となる。 すなわち、原子力基盤技術開発においては従来の原子力技術開発では部分的には行っていても体系的には行っていなかった分野の技術開発を行うこととしているので、民間を含めて国研、国の研究開発法人においても基盤技術開発分野に係る研究開発人材は必ずしも多いとは言えないのが現状である。 このため、研究者交流を積極的に行うことにより研究開発機関間における研究者の相互触発を図ることはもちろんのこと創造性のある研究者を意識的に育成していくことが不可欠である。この場合、育成される研究者がアクティブな技術開発現場とのつながりを持てるようにすることが重要である。特に大学と国研・国の研究開発法人の間の若手研究者を含めた研究者交流は、欧米を参考にしながら検討していく必要がある。 また、積極的な人材の活用を図るため基盤技術開発に必要な研究ポテンシャルを持つ研究者の発掘に努め、これを育成し、その潜在的な能力を最大限に活かすことも重要である。 さらに、創造的な技術開発を展開していくためには、それを担う研究開発機関自体が組織として活性化することはもちろんのこととしても、研究者一人一人が創造性のある研究開発能力を発揮できるように研究開発環境を整備していくことが肝要である。特に、最先端の研究開発を進めていくためには最先端かつ最新の研究開発情報に接することができるようにすることが必要である。このため必要となる情報収集は現状では個人の努力に依存するところが大きいが、システム的な情報サービスを行ってこれを効率化させていくことも必要である。 ③ 積極的な国際交流の展開 わが国の技術開発は、総じて欧米の研究テーマ・研究手法を目標に置いたり、基本特許を導入したりして進めてきたが、最近わが国の研究開発のポテンシャルは飛躍的に向上してきており、世界のわが国の科学技術に対する期待も高まっている。このことから、わが国は従来にも増して基礎・基盤研究に研究の重点を移し、原子力分野を含めた科学技術のリーディング・カントリーとしての責務を果たし、国際的に責献していくことが強く求められている。 また、最近の技術開発は、規模が大きくなってきていることや技術開発成果の影響が国内だけに留まらず国際的になってきていることから、国際共同の技術開発が行われつつあり、わが国はこれに対して積極的にリーダーシップを執っていく必要がある。 中でも、原子力基盤技術開発において取り上げている新素材、情報・エレクトロニクス・ロボティクス、レーザー、ライフサイエンスの各分野の科学技術は明日を拓く可能性のある技術として認識され、欧米では豊富な研究ポテンシャルを有する原子力研究開発機関がこれらの分野の研究開発を行うようになる等幅広く研究開発が進められており、わが国の研究開発と相互触発をすることによって加速度的に研究開発が進捗することが期待される。このため、諸外国の関係研究機関のポテンシャル及び共同研究等のニーズの把握に努めるとともに、わが国の共同研究等のニーズを諸外国に広く知らせる枠組を整備すること等によって国際共同研究、研究者国際交流等の国際交流をリーダーシップを執りながら積極的に進めていく必要がある。また、国際交流を展開するに必要な環境整備も進める必要がある。 ④ 新しい研究評価の導入 研究開発を効果的・効率的に推進していくためには、的確な研究評価を行うことが不可欠となる。 研究評価については、科学技術会議政策委員会が策定した「研究評価のための指針」(昭和61年9月)の中で研究評価を考える上で研究を基礎的研究と開発的研究に峻別し、前者については主として新しい研究の芽を育てる観点(独創性の高い研究開発課題の選択と推進、成果の発掘等)から評価を行い、後者については主として円滑な研究開発を推進する観点(必要性・有用性の高い研究開発課題の選択と推進、効率的・効果的な研究開発資源の配分等)から評価を行うのが適切であるとしている。 原子力基盤技術開発は、研究開発の方向性を持ちつつ創造的な研究開発を行うというここでいう二つの研究の中間に位置するものであり、両方の研究評価の持つ利点を融合させる等原子力分野における新たな研究評価を確立していくことが必要である。 すなわち、原子力基盤技術開発においては、研究開発の目標及び実現可能性がある程度明確になっている場合が多くチェック・アンド・レビューなど研究評価も比較的行い易かった従来のキャッチアップ型の研究開発とは違って、研究開発目標、スケジュール、研究開発のアプローチ方法等が模索的となることに留意しつつ研究評価を行う必要がある。 以上を踏まえつつ、原子力基盤技術開発における研究評価は研究開発テーマが持つ先端性・独創性・革新性・学術性等に重点を置き行うこととする。また、原子力基盤技術開発を進めることによって既存の原子力技術体系のブレークスルーを図るとともに他の分野の技術開発の牽引車となることも期待されているので、研究評価においては原子力基盤技術の成果の他の分野へのスピンオフの状況把握をも行うべきである。 さらに原子力基盤技術開発においては各研究機関に蓄積されている研究ポテンシャルを活用することとしているので、研究開発体制が適切であるかを評価するとともに共同研究等の研究交流状況や共同利用施設の利用状況についても評価を行うものとする。 一方、原子力基盤技術開発は開発対象としている技術の将来像をイメージとして置き、長期的な観点に立った開発が必要とされるので、研究評価も長期的観点に立ちながら技術開発目標達成度、スケジュール達成度について行うこととする、なお、原子力基盤技術開発の対象となっている材料、人工知能、レーザー、ライフサイエンス等の技術開発のスピードは極めて速いことから、研究評価を行うに当たっては国内外の当該技術分野の研究開発状況、研究開発体制等についても十分に調査し、評価把握することとする。 また、原子力基盤技術のような先端分野における研究開発においては、その研究開発規模が拡大するのに伴い、組織的な研究開発を進めることによって目標を達成することとなる。また、厳しい研究開発競争が行われている今日では、研究機関が持つ総合的な研究開発能力が重要となり、研究評価を活かした総合的な研究開発能力の向上が望まれる。 このことから、研究評価を行うに当たっては、研究開発課題自身のもつ先端性・独創性あるいはその成果の原子力分野でのブレークスルー効果や他の科学技術分野への波及の効果等の評価のみならず、人材・資金・施設等の研究資源の効率的・効果的な配分及び適切な研究開発体制の構築等の総合的な観点からの研究評価を行い、これを研究マネージメントに反映させていくことが必要である。 研究評価を行う時期としては、事前、中間、事後の三段階があるが、原子力基盤技術開発では、創造的な研究開発の新しい芽を育てる視点に立った事前評価、長期的ビジョンの中での研究の方向性を確認する中間評価、次のステップの芽を見い出し、技術開発の発展を図るための事後評価を的確に行うことが望まれるが、その中でも創造性を見つけるための最初のベクトルを与える事前評価が重要となる。 2.技術開発の効率的推進の方策 ① 研究交流促進の体制整備 基本的考え方にも示したように、原子力基盤技術開発は各研究機関の研究ポテンシャルを活用することとしているが、一方で原子力の研究開発においては原研、動燃、国研等の様々な性格・機能を有している研究機関が既にあることを踏まえ、新たな中核的な研究機関を設置することなく、既にあるそれぞれの研究機関の責任の下に進めるようにすべきである。 この場合、各研究機関の研究ポテンシャルを結集するために用いられる共同研究、施設共同利用、情報交流等を効率的・効果的でかつ円滑に推進することが、原子力基盤技術開発において特に重要であり、この役割を担うセンター的な研究交流促進機能を整備することが必要である。この機能を活用して、国内研究機関相互間の研究協力のみならず、広く諸外国との共同研究等の促進を図る必要がある。 また、創造的な原子力基盤技術開発を進めるために必要な原子力分野及び非原子力に関する基礎的な知識を有する人材については必ずしも多いとは言えない状況にある。従って、各研究機関におけるOJT(On the Job Training)による人材育成のみに頼るのではなく、最先端の研究開発を行っている研究者の指導を受けることができるようにする等人材の意識的な育成促進を図る必要がある。研究機関と大学との間の研究者交流を今まで以上に積極的に進める他、創造的な人材を育成促進する機能を上記センター的な研究交流促進機能に含めるべきである。 さらに、研究開発によって得られた成果は、可能なものについては各研究機関でデータベース化を図ることとするが、これらの成果を各研究者が効率的・効果的に利用することができるようにするためには、各研究機関に蓄積されたデータベースをリンク化する必要がある。このため、これらデータベースに関するネットワーク機能及びサービス機能を上記のセンター的な研究交流促進機能に含めるべきである。 ② 研究交流における施設整備と利用の促進 原子力基盤技術開発を進めていくために必要となる大型の研究施設については、共同利用を推進し、施設の効率的・効果的利用を図ようにすべきである。このため、国研・国の研究開発法人の各研究機関に既に設置されている大型施設のうち、共同利用可能な施設については利用機会の積極的な提供を進め、また未整備な施設については利用者のニーズを踏まえながら整備を進めることとする。 特に、原子力用材料開発においては中性子照射、照射後試験、大型放射光施設、材料評価等が不可欠であることから、かかる施設を整備することが必要である。また、レーザーにおける総合的な研究開発に必要となる自由電子レーザーや放射線による遺伝子等への影響を評価するために必要となる放射線リスク評価用の大型コンピュータ、実験動物施設の整備を進めることとする。さらに、原子力用人工知能技術開発等によって得られた成果を用いて実機実証を行う際には、動燃、原研等の原子力施設も活用し、それに必要な措置を行うこととする。 一方、国研の大型施設は、施設を有する国研と共同研究する場合及び国研の研究を受託する場合に無償で使用することが可能であるものの、施設の運転・維持のための専用の人員が確保されていないことから、現在のままで開放利用のような形で利用を進めることは事実上困難となっており、施設の効率的利用の障害となっている。以上を踏まえ、原子力基盤技術開発の推進に必要な施設が有効に利用できるよう、運営の弾力化とともに、施設の運転・維持を外部委託等することによって、内外の研究機関による共同利用化を促進することができるよう必要な措置を講じる必要がある。 国の研究開発法人が有する大型施設は、共同研究、照射の受託等により利用されている。これらの施設利用においては、原子力基盤技術開発に対して施設共同利用のインセンティプを与えるための必要な措置を講じながら利用効率の向上を図ることとする。また、利用者・有識者等の第3者等の参加の下に施設利用の調整を行う委員会を設け、円滑な利用を図っていくことが必要である。 さらに、原子力基盤技術開発においては、大型の共同利用施設を用いながら国際共同研究を積極的に進めていく必要がある。また、これを行うために必要となる国際会議場や外国人用の宿舎の整備を行う必要がある。現在、科学技術庁における原子力研究交流制度等の国際的な研究交流の用に供することができる宿舎が、新たに原研等にて整備されつつあるが、既存の宿舎については高い利用実績とともに、国際交流にとって極めて有効に機能していることを考えれば、原子力基盤技術開発においても、今後これらを整備充実していく必要がある。 また、原子力基盤技術開発によって得られたデータベースを包括的にサービス・管理するために必要となるコンピュータ・システム、このコンピュータ・システムをホストとして活用し、研究者間の情報交換に使用することができるパソコン通信システム、基盤技術開発に携わる人材の育成を行うために必要な施設等については、総合的な研究交流促進施設として整備を進めることとする。 ③ 研究者交流等の環境整備 基本的考え方にも示したように、研究者が創造的な研究開発を進めるためには、同じ分野や異なる分野の研究者の間で第一線の研究情報を交換することが不可欠であるので、原子力基盤技術開発の適切なテーマ毎に専門の研究者で構成する研究会を設置する等の措置を講じる必要がある。この研究会は、参加者、参加機関の自主的な運営のもとで開催することを原則とするが、国研、大学の若手の研究者が参加することができるようにするための必要な措置を構じることとする。また、最近の情報通信システムの発達によって研究者が一堂に会さなくとも情報の交流を任意の場所・時間にて行うことができるようなパソコン通信システムが開発されてきている。これを研究者交流の補完的方法として積極的に導入・整備することにより研究会のより一層の効率的・効果的な運営を図っていくこととする。 また、共同研究は国研等で積極的に進められているが、今まで以上に民間あるいは外国等との共同研究を促進するために、研究交流促進法(昭和61年5月)が制定されるとともに、産・学・官及び外国との研究交流の促進に関連する諸制度の運用に関する基本方針について(昭和62年3月)が閣議決定された。これにより、国研の研究者の共同研究における処遇改善、民間の研究者が国研で研究できるようにするための規程整備等の優先的実施許諾のための規程整備等が進められ、国研と民間との間においても共同研究のインセンティブが働くような措置がとられている。原子力基盤技術開発においては、この措置を十分に生かしながら共同研究を積極的に進めることとする。 国の研究開発法人における共同研究は、従来から共同研究で得られた成果を共同研究実施者間で共有することとなっており、受・委託研究も含めた共同研究を積極的に進めることとする。さらに、原研、動燃では研究者交流の諸制度が整備されていることから、原子力基盤技術開発ではこれらを積極的に活用していくこととする。 ④ 研究成果の普及促進 原子力基盤技術開発によって得られた成果を、積極的に原子力の各技術分野に移転されていく必要がある。また、原子力基盤技術で開発される材料、人工知能、レーザー・ライフサイエンスに係る技術は、非原子力分野でも有用な技術であることから、原子力分野から非原子力分野へも積極的に波及させていく必要がある。 このため、研究開発によって得られた成果が、原子力・非原子力を問わず多くの分野の研究者や研究機関に周知せしめることを目的として、成果報告会・シンポジウムを開催し、成果の普及促進を図ることとする。また、国際・共同研究を行う場合にも、国際シンポジウム等により成果の普及促進を図ることとする。更に、蓄積された研究成果を各研究機関においてデータベース化するとともに、これらをネットワーク化することにより広く利用できるようにする。 ⑤ 原子力基盤技術における研究評価 原子力基盤技術開発の研究評価に当たっては、研究開発課題そのものの評価から研究開発体制や研究機関の研究ポテンシャル活用状況評価までにわたる幅広い研究評価が行われる必要があることから、各研究機関が研究開発の実施責任者であるとの認識に立ち、自身による研究評価を確実に行うことが必要である。この場合、評価者に有識者等の第三者を入れながら、研究開発の成果、研究資源、研究マネージメント等に重点を置いて行われるべきである。 これを踏まえて国としての研究評価は、評価対象技術分野の国内外の研究開発状況調査を基に、研究開発目標達成度、スケジュール達成度並びにわが国全体としての研究ポテンシャル活用度を含んだ研究開発体制について行うものとする。研究評価は、基盤技術推進専門部会並びに同専門部会に設置されている分科会で行うこととする。 専門部会においては、技術開発の方向性、目標及びスケジュールの達成度、研究開発体制等の総合的な評価を、分科会においては、技術的見地から技術開発課題レベルの評価を行うことが適当である。また、両者とも各研究機関で行われた研究評価の結果についても報告を受けることとする。 なお、研究評価時期としては、基本的考え方に示したように、原子力基盤技術が長期的視点に立つ研究開発をされることに鑑み、研究開発テーマが持つ先端性・独創性等を中心に事前評価を的確に行うことを第一とする。 また、原子力基盤技術開発においては、可能性のある研究開発テーマを積極的に取り上げていく半面、研究開発の中途段階でも研究評価の結果によっては、研究開発をさらに促進したりあるいは中止することができるような研究開発の柔軟性を持つことが必要であるので、中間段階でマイルストーン的な研究評価を行うこととする。 この場合、評価時期として、初期の研究開発が終了して研究開発を拡大する必要のある時期に第1回目の中間評価を行うこととし、研究開発開始後例えば3年を経てから行うことを目途とする。さらに、第2回目の中間報告は、研究開発を本格化する必要のある時期に行うこととし、研究開発開始後例えば5年を経てから行うことを目途とする。 図1.原子力用材料技術開発体系 |
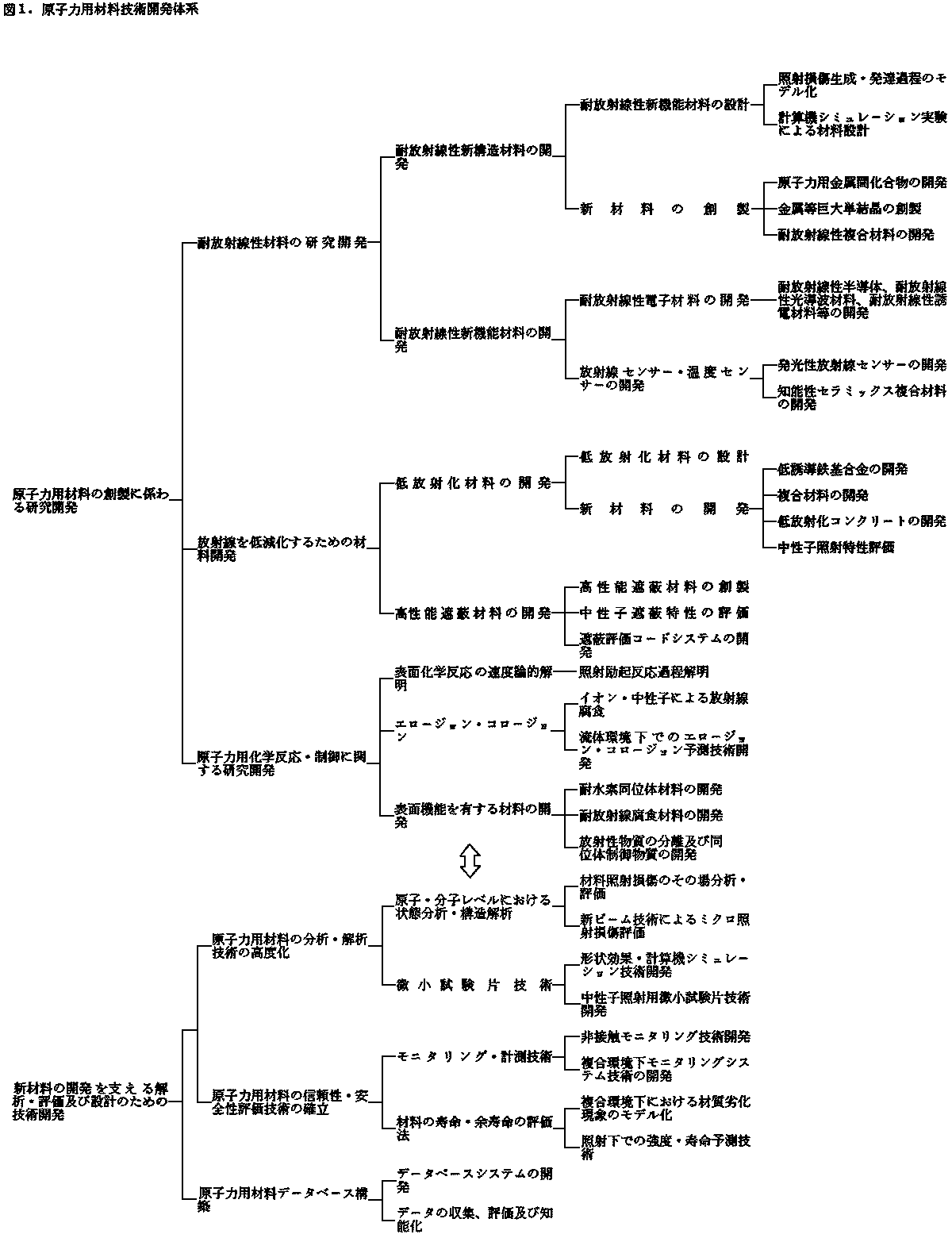
図2.原子力用人工知能技術体系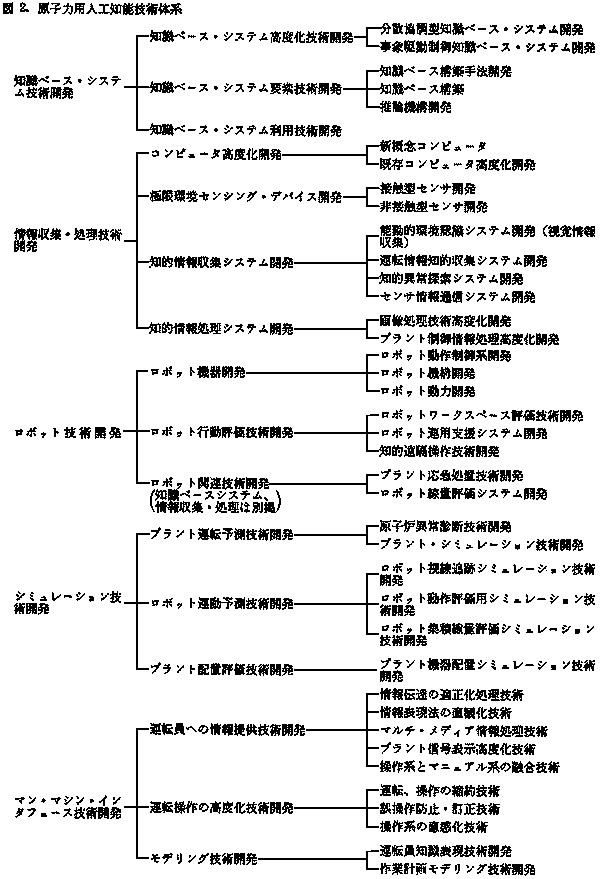 図3.原子力用レーザー技術開発体系 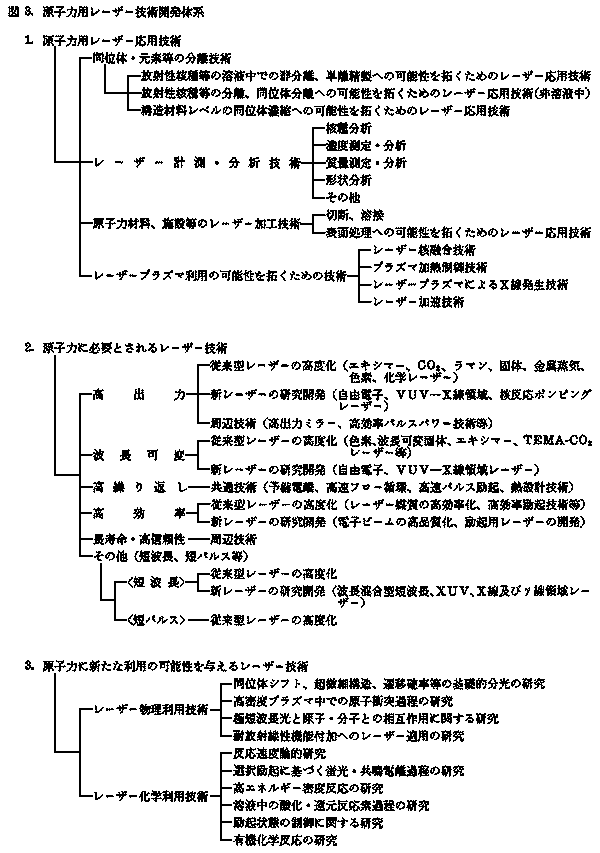 図4.放射線リスク評価・低減化技術開発体系 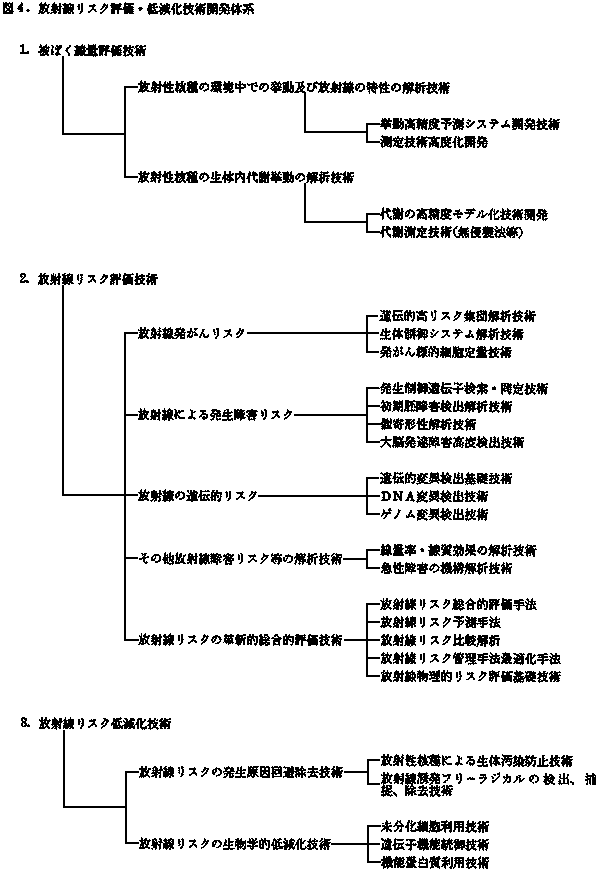 V.参考 基盤技術推進専門部会の設置について 昭和62年9月11日 我が国の今後の原子力開発利用の推進に当たっては、原子力開発利用長期計画(昭和62年6月22日原子力委員会決定)に沿って、新しい技術を創出し、ひいては原子力技術体系のブレークスルーを引き起こす可能性のある基盤技術の開発を積極的に進めていくことが不可欠である。 このため、基盤技術の開発を着実に推進するための方策等について、審議検討を行うことを目的として基盤技術推進専門部会を設置する。 2.検討事項 (1)推進すべき技術領域の選定 (2)研究開発の進め方 (3)研究開発成果の評価 (4)その他 3.構成員 別紙のとおりとする。 4.その他 専門部会に、必要に応じて分科会を置く。 (別紙)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前頁 |目次 |次頁 |