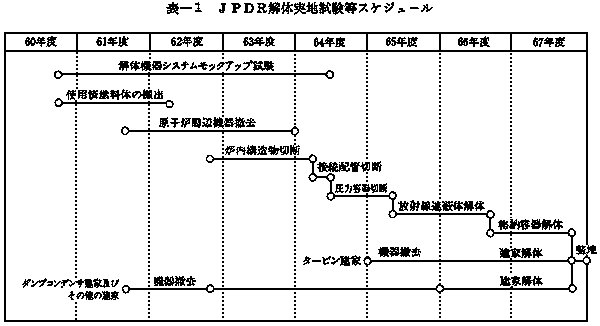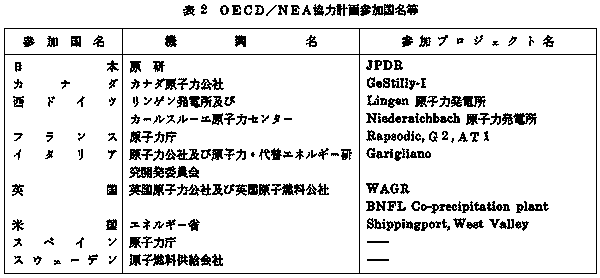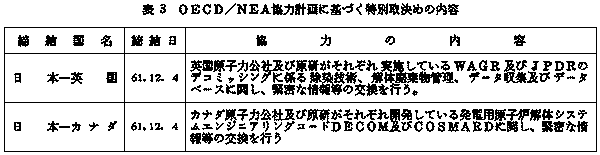| 前頁 |目次 |次頁 |
|
時の話題 原子炉解体技術開発の現状について 日本原子力研究所 日本原子力研究所では、科学技術庁の委託により、昭和56年度から原子炉解体に必要な要素技術の開発を行い(第1段階)、昭和61年12月4日からは、開発した要素技術を原子炉解体技術として総合的に検証するとともに、実際の解体作業を通じて原力発電所の解体に係る知見、経験を得ることを目的子として動力試験炉(JPDR)の本格解体に着手した(第2段階)。JPDR解体の2年目に当り、解体実地試験の進捗状況、国際協力を中心として解体技術開発の現状について報告する。 2 解体工法・解体機器の開発 JPDRの解体実地試験では、これまでに開発した解体工法・機器を使用し、従事者等の被曝線量の低減及び放射性廃棄物の量の低減をはかるとともに、その有効性を実証することとしている。放射化構造物のために開発した機器工法とその適用対象物を次表にまとめる。 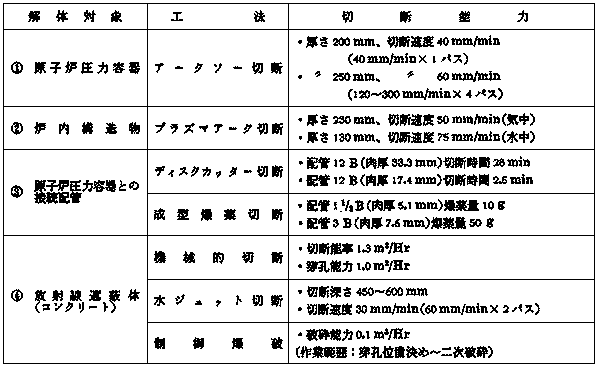 3 解体実地試験の進捗状況 1)概要及び工事内容 JPDR解体計画は表に示すとおりである。昭和61年12月から始めた工事は、計画どおり進捗しているが、撤去した主な対象工事の内容を以下に示す。 ① 原子炉圧力容器上蓋の撤去2)放射性固体廃棄物の処理処分について ① 処理処分の基本的な考え方4 国際協力について 1) OECD/NEA「原子力施設デコミッショニング・プロジェクトに関する科学技術情報交換協力計画」 標記協力計画は昭和60年9月に発足し、科学技術庁の指名により原研がわが国の参加機関として計画に登録されている。 同協力計画への参加国、機関及び参加プロジェクト名は表2に示すとおりである。 同協力計画では、特別取決めを締結することにより、二国間又は多国間において、より緊密な情報の交換を行い得る道が講じられている。これに基づき、日本一英国、日本-カナダの間に特別取決めを結んでいる。これらの特別取決めの内容は表3に示すとおりある。 2)昭和62年度の国際会議 ① WAGRワークショップ5 1987年国際デコミッショニングシンポジウムについて 1)概 要 標記会議は、DOE主催、IAEA及びOECD/NEA共催のもとに、本年10月4日(月)より7日(木)まで、米国ピッツバーグ市において開催された。会場のコンベンション・センターでは、会議と並行して、廃止措置技術についての工業見本市が開催され賑わった。会議出席者は、19ケ国より納600名を数えたが、その大半は産業界からの出席であった。日本からは、原研の他、日本原子力産業会議及びエネルギー総合工学研究所が派遣した調査団並びに産業界から合わせて約60名が参加した。会議では10のセッションテーマのもとに、64編の論文発表と39編のポスター発表が行われた。この内、原研からは7編の論文発表と2編のポスター発表を行った。また、日本の産業界及び学会より各1編のポスター発表があった。講演においては、各国の動力炉のデコッミッショニング技術の開発状況等が報告され、活発な質疑応答が行われた。 2)会議の内容 本会議の特徴は、1982年秋、シアトルにおいて開催された第1回会議を引き継ぐ形で開催され、この5年間の進歩や変遷を具体的な形で検討したことである。その主な点について述べると、 (1)研究用原子炉について、いくつかの施設での廃止措置が完了したこと。等である。 また、今会議で新しく発表され注目された事柄として、 (1)放射性廃棄物の再利用の問題3)シッピングポート原子力発電所の解体状況 シンポジウムの一環として、現在解体撤去工事が行われているシッピングポート原子力発電所(72MWe、PWR)の見学会が行われた。 シッピングポート原子力発電所は、ピッツバーグの北西約40kmのオハイオ川岸にあり、原子炉圧力容器を解体せずに一体物として撤去する計画を有している。解体撤去工事は現在最盛期であり、現状は以下のとおりである。 ・原子炉圧力容器 原子炉圧力容器接続配管は切断、止栓され、コンクリートが一部注入されている。・原子炉圧力容器チャンバ 約4/5が解体撤去されている。・ボイリングチャンバ 内部の熱交換器及び蒸気ドラムは撤去済みであり、チャンバのみが残っている。・補助チャンバ 内部の加圧器、フラッシュタンクなどの撤去を終了している。計画は予定どおり進んでおり、作業完了率は解体物量で51%、作業員の被曝線量は予想値(550人・レム)の約1/5(120人・レム)である。なお、1989年には原子炉圧力容器を搬出し、1990年に全ての作業を完了する予定である。 表-1 JPDR解体実地試験等スケジュール |
前頁 |目次 |次頁 |