| 前頁 | 目次 | 次頁 |
|
昭和60年原子力年報 原子力委員会
(解説)
「昭和60年原子力年報」は、昭和60年11月29日の原子力委員会において決定され、昭和60年12月3日の閣議に報告された。 本年報は昭和60年10月までの概ね1年間における原子力開発利用の動向についてとりまとめたものであるが、今年が原子力委員会発足以来満30年にあたり、ひとつの区切りの時期を迎えることから、これまでの歩みを振り返り、また、昭和60年代を展望するとの観点も含めて編集した。 原子力年報は、従来、「総調」、「各論」、及び「資料」の3部構成としていたが、今回の年報においては、第1部「総論」の次に特に第2部として「原子力開発利用の歩み」を設け、第3部「各論」、第4部「資料」を含め、全体として4部構成とした。以下に要約を掲載する。 はじめに
1. 昭和31年1月1日に原子力委員会が発足して、30年が経過した。 今日、原子力発電は31基、発電設備容量2,363万キロワットに達し、安全を確認しつつ順調に運転を行い、昭和59年度には総発電電力量の22.9%を担うまでに発展し、安定したエネルギー供給源として電力供給の中核的地位を占めるに至っている。また、核燃料サイクルの確立をめざして、研究開発及び事業化の計画が具体的に進展している。さらに、工業、農林水産業、医療等の分野で放射線利用が着実に拡大している。新型動力炉、核融合等将来の進んだ原子力技術体系の実現に向けて研究開発計画も強力に推進されている。また、原子力産業の成長も著しく、産業規模の拡大、経営の安定化、技術力の向上等の面で、産業としての自立期を迎えている。 2. 我が国の原子力開発利用は、その歩みにおいて紆余曲折を経ており必ずしも平担なものではなく多くの努力を払って進められてきた。 昭和40年代後半より二度にわたる石油危機によって、エネルギーの海外依存体質の脆弱性が大きな問題として浮き彫りにされたが、エネルギー源多様化の要請に対応して、今日では、原子力は石油代替エネルギーの中核として大きな役割を果たしている。このことを考えると、昭和30年代初頭から将来のエネルギー源を確保すべく原子力開発利用を開始したことの持つ意義は大きい。また、安全を確保しつつ開発利用を推進するにあたり、種々の課題を克服するための、関係研究開発機関、地元公共団体、電気事業者、メーカー等各方面の関係者の努力も忘れてはならない。さらには、これまでの成果は、国民及び地元住民の理解と協力に支えられたものであることを認識する必要がある。 3. 今日、国際的なエネルギー需給は安定し、また、省エネルギー、脱石油を中心とする産業構造の調整が進められた結果、我が国のエネルギー事情は大きく変化している。しかしながら、現下のエネルギー情勢に安心し、着実な原子力開発利用を進める努力を怠ってはならない。 原子力は、長期にわたる計画的な研究開発及び技術改良を行い、これによって技術基盤を確立してはじめて社会への定着が可能となることを十分認識する必要がある。 4. 今後原子力開発利用を推進するに当たっては、時代環境の変化及び我が国の国際的役割の増大等を十分に認識し、技術開発の進展に伴う新たな課題に柔軟かつ効率的に対応する体制を整備することが必要である。 エネルギー需要がゆるやかな伸びを示し、今後相当長期間にわたって軽水炉主流時代が続くとの見通しのもとで、原子力発電は、昭和40年代、昭和50年代の、いわば量的拡大を目指した時代から、質的な向上の時代へと移行しつつあり、技術の改良、高度化により安全性・信頼性を高めるとともに、これらを損なうことなく経済性の一層の向上に努めることが重要となっている。また、原子力は、一次エネルギー供給の8%(昭和59年度実績)を占めているが、長期的には、核熱利用も含めて、原子力全体として一次エネルギーに占める割合を高めていくことが必要である。さらに、放射性廃棄物の処理処分、原子炉の廃止措置への対応等原子力発電体系の一層の整備が求められている。 さらには、核燃料サイクルの事業化の進展及び高速増殖炉等の新型動力炉の技術開発の進展に伴い、研究開発における民間の役割が拡大しつつあり、こうした動向を踏まえた新たな官民協力及び研究開発のあり方が重要な検討課題となってきている。 一方、国際協力の一層の推進及び核不拡散をめぐる国際関係への対応が必要とされているほか、我が国原子力産業の国際的展開が開始されようとしていることから、多角的な視点から国際化を進めることが重要となっている。 5. 本年度の年報は、新しい時代を迎えつつある我が国原子力開発利用の現状と課題について、広く国民の理解の一助となることを目的として、原子力開発利用の30年の歩みを振り返り、現状についてとりまとめ、今後の展望と課題を示した。 第1章 新しい時代を迎える原子力開発利用
1. 原子力開発利用の歩み
昭和29年の初の原子力予算の成立、昭和30年の原子力基本法、原子力委員会設置法の成立等を経て本格的に開始された原子力開発利用の30年の歩みの中から、今後の課題を考えるに当たって基本的に重要と考えられる①平和利用の確保と核不拡散体制への協力②原子力発電の展開③核燃料サイクルの整備④新型動力炉の開発の4点に絞って取り上げる。 (1) 平和利用の確保と核不拡散体制への協力
我が国は、原子力開発利用を開始した当初から平和利用に徹してこれを進め、さらに進んで国際協力に資することを基本方針としてきた。我が国は、国際原子力機関(IAEA)の設立等に貢献するとともに、昭和49年のインドの核実験を契機とする国際的な核不拡散強化について、原子力の平和利用と核不拡散は両立しうるとの基本認識に基づき国際核燃料サイクル評価(INFCE)等に対処するとともに、その結論を踏まえて国際環境の整備に努めてきた。 (2) 原子力発電の展開
昭和32年に発電用原子炉早期導入方針を決定し、動力試験炉(昭和38年、発電成功)及び実用炉として英国コールダーホール型炉(日本原子力発電(株)東海1号炉、昭和41年運開)の導入が進められたが、その後、米国において軽水炉の開発が進展し、昭和38年の日本原子力発電(株)敦賀1号(昭和45年運開)計画決定以後、軽水炉路線が定着した。昭和40年代半ば以後、原子力発電利用が本格化したが、昭和40年代後半から昭和50年代初頭にかけて事故・故障等が多発し、稼働率も低迷した。その後も、TMI事故、敦賀発電所での放射性物質の漏洩が発生する等、原子力発電にとって試練の時代であった。 一方、昭和年48の石油危機以後、原子力発電への期待が増大し、原子力発電を推進するため、官民挙げて制度面、技術面での対応が進められた。国においては、電源三法の制定、原子力安全委員会の設置等の規制体制の整備、軽水炉の改良標準化、安全研究年次計画の策定等が行われた。 これらの経緯を経て、今日、稼働率も向上し、国産化率もほぼ100%に達する等原子力発電は石油代替エネルギーの中核として社会に定着した。 (3) 核燃料サイクルの整備
原子力委員会は当初より、長期的観点から核燃料の安定確保とその有効利用を図ることを基本とし、世界の核燃料需給の見通し及び動力炉開発の進展等をふまえて、次の考え方に添って、核燃料サイクル関連施策を推進してきた。 イ) 海外採鉱と開発輸入を推進すること。 ロ) ウラン濃縮については、全面的な海外依存は望ましい状況でないことに鑑み、一部国産化すること。 ハ) 使用済燃料の再処理については、これを我が国で実施し、回収ウラン及びプルトニウムを、新型転換炉、高速増殖炉等において有効に活用すること。 ニ) 原子力発電の進展に伴って増加する放射性廃棄物の安全な処理処分方策を確立すること。 ① ウラン濃縮については、動力炉・核燃料開発事業団により遠心分離法の技術開発が進められパイロットプラントの建設・運転が行われている。これに引き続き、昭和57年の原子力開発利用長期計画に基づき、同事業団により原型プラントを早急に建設することとされ、現在、着工準備が進められている。さらに民間において事業化計画が進められている。 |
|
我が国の原子力発電所発電設備容量の推移(昭和60年9月末現在)〔但し電気事業用のみ〕 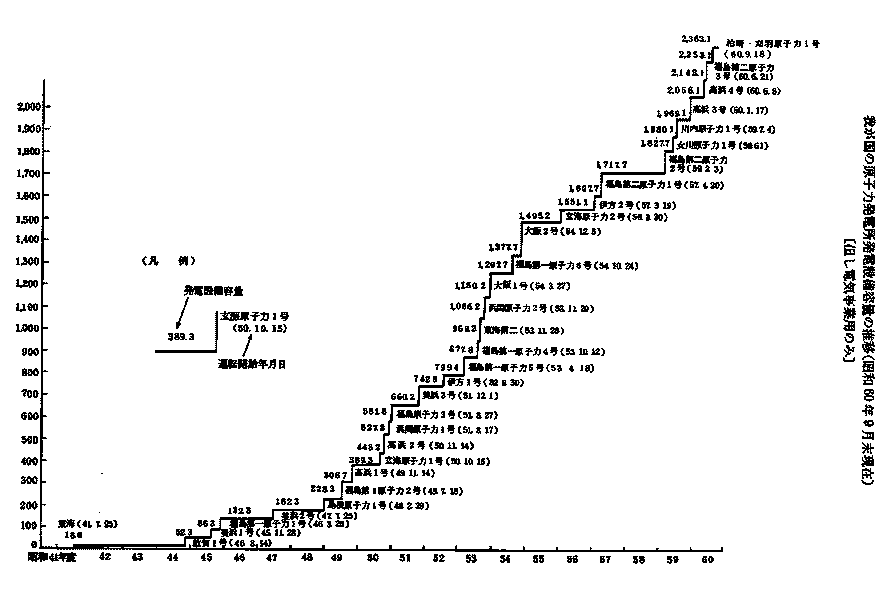 |
|
② 使用済燃料の再処理については、昭和39年の国内再処理の方針及び再処理工場建設の方針決定に基づき、原子燃料公社(後、動力炉・核燃料開発事業団に改組)によってフランスからの技術導入により計画が進められ、東海再処理工場が昭和52年に試験操業、昭和56年に本格操業を開始した。その後、ピンホールの発生等により長期間の停止を余儀なくされていたが、国内技術による改良等を経て操業を再開した。一方、増大する再処理需要に対処するため、早くから第二再処理工場の必要性が指摘されていたが、昭和53年民間においてこれを進める方針を決定し、その後、法律整備を経て民間事業主体が設立された。 ③ 放射性廃棄物処理処分については、原子力委員会は、昭和47年、陸地処分と海洋処分を併せ実施する方針を明らかにした。その後、滅容固化技術開発を促進する一方、日本原子力研究所及び原子力環境整備センターを中心に固化体の健全性確認試験、海洋環境調査等の処分に関する研究開発が進められた。海洋処分については、所要の法令等の整備も進み、安全に試験的投棄を実施しうる段階に至ったが、関係国の懸念を無視して強行はしないとの方針の下に、国際的協議を進めてきている。一方、民間において、最終貯蔵施設の建設計画が進められている。再処理に伴う高レベル廃棄物については、昭和51年、安定な形態に固化し、一時貯蔵した後地層処分を行う方針を示し、これに沿って、動力炉・核燃料開発事業団及び日本原子力研究所を中心に、ガラス固化等の技術開発が進められてきている。 (4) 新型動力炉の開発
① 新型転換炉及び高速増殖炉については、原子力委員会は、昭和41年、自主的開発を行う方針を決めた。開発については、昭和42年、原子燃料公社を発展的に改組して、動力炉・核燃料開発事業団が設立され、ナショナルプロジェクトとしてその開発が推進された。 ② 高速増殖炉については、昭和52年に実験炉「常陽」が完成し、現在まで実験が行われている。一方、「常陽」に引き続き建設する予定であった原型炉「もんじゅ」については、立地問題等により、計画が遅れていたが、今年10月建設に着工した。 ③ 新型転換炉については、原型炉「ふげん」が昭和52年に完成し、その後良好な運転実績を示している。原子力委員会は「ふげん」の経験、他の炉型との比較等をふまえて評価検討を行い、昭和57年実証炉建設の方針を決定した。現在、電源開発(株)による実証炉計画の具体化が進められている。 (5) 今後の開発利用推進に当たっての基本認識
① NPT体制の下でIAEAを中心とした平和利用推進の国際的環境整備を図ることが必要である。 ② 軽水炉を導入して進められた原子力発電の定義にいたるまでの経過に鑑み、技術導入を図る場合であってもこれを我が国の国情にふさわしい技術として定着させるためには並行して自主開発を行うことが必要である。 ③ 原子力発電が開始してから定着するまで20年の年月と多大な努力を要してきた。また、核燃料サイクルの確立と新型動力炉の開発について、当初構想した時点の見通しの実現が、立地、技術、資金の面で難しい問題であることが明らかになる一方、自主的な原子力利用を確保する観点からその重要性が高まってきている。原子力開発利用に当たっては、長期的視点に立ち着実かつ継続的な努力が必要である。 ④ 安全の確保を徹底しつつ、国民に理解される体制のもとで原子力開発利用を進めることが極めて重要である。 2. 昭和60年代の展望と課題
① 現在、エネルギー情勢は、緩和基調にある。しかしながら、1990年代には、開発途上国の経済発展、地OPEC地域における供給余力の限界等により再び石油需給が逼迫し、石油価格も上昇する可能性が大きいと見込まれている。省エネルギーの進展及び石油代替エネルギーの導入努力は昭和60年代においても重要であり、長期的視点に立って、安定したエネルギー需給構造を築く必要がある。このため、原子力発電を着実に進めること及び将来の高速増殖炉を中心とするプルトニウム利用体系の実現に向けて研究開発を進めることの意義は大きい。 ② 以上の認識の下に、原子力開発利用の進展状況を踏まえて、昭和60年代を展望する場合、イ)原子力発電の主力電源としての確立 ロ)核燃料サイクル自立化の進展 ハ)プルトニウム利用体系の基礎固め、が基本課題として挙げられる。 我が国の一次エネルギー供給の推移及び見通し(数値は構成比 単位%) 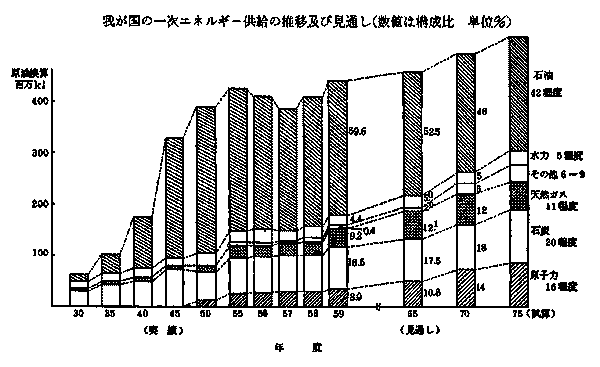 OECD諸国のエネルギー需要と自由世界の石油需給 (IEA「World Energy Outlool」1988年5月改訂) 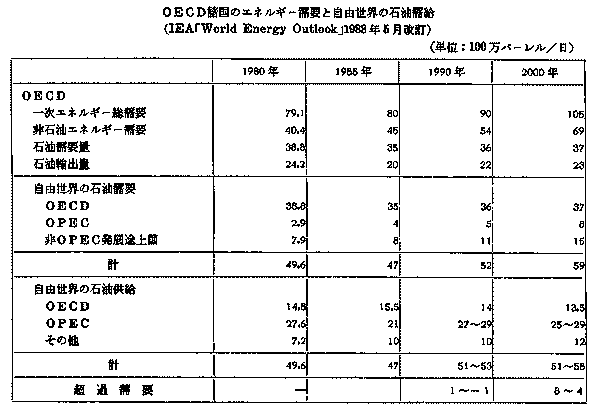 (1) 原子力発電の主力電源としての確立
① 原子力発電は、昭和70年度までに一次エネルギーで8%(昭和59年度実績)から14%、発電設備容量で2,363万kW(昭和60年9月末)から4,800万kW、発電電力量で22.9%(昭和59年度実績)から35%に拡大すると見込まれており、その結果、単一の電源としては最大となる見通しである。 ② 今後、原子力発電を推進する場合、これまで石炭火力発電に対して初年度発電原価の差が縮小してきており、現在経済性の一層の向上が重要である。現在検討が進められている軽水炉の高度化のための計画においても主要な課題となっている。 ③ また、原子力発電の比重の増大に伴い、電源構成における位置付けを踏まえつつ、負荷追従性を向上させることが必要と考えられるが、これについては、今後、経済性・信頼性を一層向上させつつ、燃料改善等を進めることによって、負荷追従型の運用が可能である。 ④ さらに、立地地点確保も重要であり、原子炉廃止措置に係る所要の準備等を進めることが肝要である。 電源構成現状と将来見通し 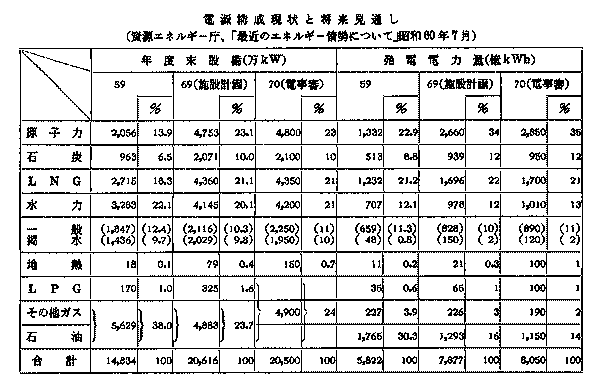 (2) 核燃料サイクルの自立化の進展
① ウラン濃縮及び再処理については、動力炉・核燃料開発事業団を中心に研究開発が進められており、昭和60年代にはその成果に基づき、民間においてその事業化が進展し、さらに低レベル放射性廃棄物についてはこれまでの研究開発を踏まえて民間による最終貯蔵施設の建設が具体化する見通しである。 ② ウラン濃縮については、国際的に需給が緩和し、米国におけるレーザー法選択に見られる厳しい国際競争が予想されるところであり、国際競争力を有する事業の確立が重要である。 ③ また、民間再処理工場については、国内外の技術の中から最良の技術を選定することとされており、海外の技術を導入する場合には、その国内定着が重要課題となる。また、民間再処理工場の設計、建設及び運転に当たっては、動力炉・核燃料開発事業団が保有する技術、経験等を適切に活用することが極めて重要である。 核燃料サイクル三施設の計画の概要 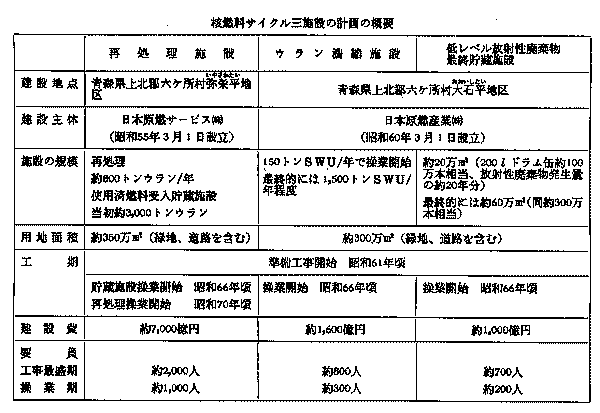 ④ 放射性廃棄物処理処分については、低レベル放射性廃棄物の陸地処分について、放射能レベルに応じた合理的な管理等を行えるよう、所要の調査研究を進める一方、民間における最終貯蔵計画に関して、安全基準、指針等の整備を図る必要がある。海洋処分については、今後予定されている国際的検討に関して、関係国と協議しつつ、海洋処分に対する国際的な理解が増進されるように対処する必要がある。高レベル放射性廃棄物については、今後、固化について技術実証を進め、さらに地層処分の技術実証を推進する必要がある。 (3) プルトニウム利用体系の基礎固め
① プルトニウムを利用する次世代の発電体系の要となる高速増殖炉及び新型転換炉の開発は動力炉・核燃料開発事業団を中心に進められている。昭和60年代には、高速増殖炉原型炉「もんじゅ」が建設・運転され、次の段階である実証炉については民間による建設計画が具体化する見通しである。新型転換炉については、動力炉・核燃料開発事業団の開発成果を踏まえて、電源開発(株)による実証炉計画が進められる予定である。また、電気事業者によって軽水炉によるプルトニウム利用の実証計画が進展する見通しである。 ② 今後、上記技術開発を推進するとともに、次の諸点を念頭におきつつプルトニウム利用体系定着のための諸準備を進める必要がある。イ)研究開発に必要なプルトニウムの確保 ロ)経済性を念頭においた研究開発 ハ)MOX燃料供給及び高速増殖炉燃料再処理等も含めた調和のある体系の整備 ニ)国際的な核物質防護に対する要請への対応などが必要であることに配慮する必要がある。 (4) 原子力開発利用推進上の共通的課題
① 今後の原子力開発利用は、核燃料サイクル、新型動力炉等の分野で、これまで国を中心に進められてきた技術開発が進展するに伴い、順次民間に成果を移転し民間が中心となって国の支援の下に実証・実用化の段階に移行する。その際、開発成果の円滑な移転が重要であり、当事者間の協力はもとより、関係者の協力体制の確立が必要である。また、官民の役割分担、研究開発のあり方を検討し、大型化する研究開発を効率的に推進する必要がある。 ② 今後、平和利用の促進を必要以上に制約するような措置を排し、核燃料サイクルの自主性確保に努めるとともに、平和利用と核不拡散を巡る国際的コンセンサス形成に努め、NPT、IAEA保障措置体制の強化に積極的に貢献することが重要である。また、我が国の責務として開発途上国協力を進めるとともに、研究開発効率化の観点から先進国間協力を進めることが重要である。さらに、我が国原子力産業は国際的展開を図る時期にきており、核不拡散上の配慮を図るとともに、プラント輸出の円滑な推進に必要な対策等の検討を進めることが重要となる。 ③ 基礎研究は、原子力利用の技術的基盤強化のため、また新しい技術を生み出すために不可欠である。原子力分野の基礎研究は大型設備を必要とし、計画的整備が重要である。また、民間の役割が増大するなかで、国の研究成果を大学・民間において活用できるよう産業間の協力を強化することが重要である。 さらに原子力研究開発には優秀な人材を数多く養成することが必要とされ、研究者の自主性を尊重し、資質の向上に努めるとともに、人材交流、共同研究を積極的に進めることが肝要である。 ④ 原子力をめぐって国民の間に様々な意見があるが、今後、巨額の資金と長いリードタイムを必要とする原子力開発利用を推進するに当たって国民各層の理解と支援が必要不可欠である。このため、原子力施設の安全運転の実績の積み重ね、全体として整合性のある体系の確立、地域社会の発展への寄与等の重要性を認識し、国民の信頼に応える原子力政策を展開する必要がある。 第2章 我が国の原子力開発利用の現状
1. 原子力発電の動向
(1) 原子力発電の現状は、昭和60年9月末現在、運転中31基、総発電設備容量2,363万1千KW。昭和59年度末で総発電設備容量の13.9%、昭和59年度実績で総発電電力量の22・9%を占める。 年間発電電力量の推移(電気事業用) 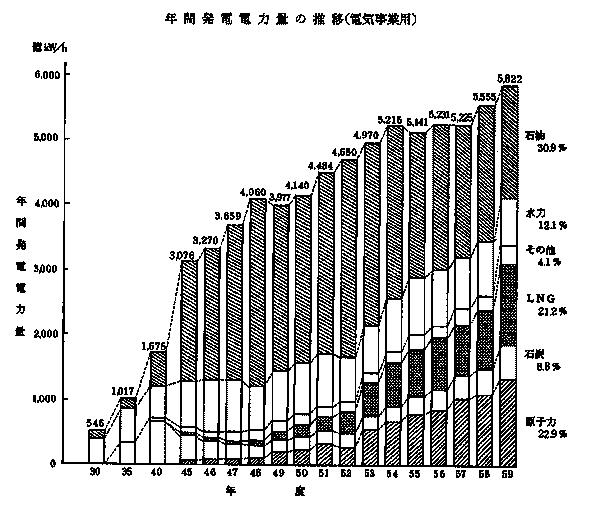 (2) 従業員に放射線障害を与えたり、周辺公衆に放射線の影響を及ぼしたりするような事故・故障は現在に至るまで皆無である。なお、原子力発電所の事故・故障件数は昭和59年度に18件、一基当たりの年平均事故件数は0.6件と昭和41年以来最低であった。 (3) 原子力発電の設備利用率は、昭和59年度には73.9%と過去最高を示した。また、運転中のトラブルによる運転停止頻度は0.1/炉・年と米国等と比較しても1桁低い値となっている。経済性については、通商産業省の試算によれば、原子力13円/KWh程度、石炭火力14円/KWh程度、石油火力17円/KWh程度、LNG火力17円/KWh程度(昭和60年度運開ベースのモデルプラント初年度発電原価)である。また、原子力委員会の調査においても同様の結果が得られている。 我が国の原子力発電所の立地点 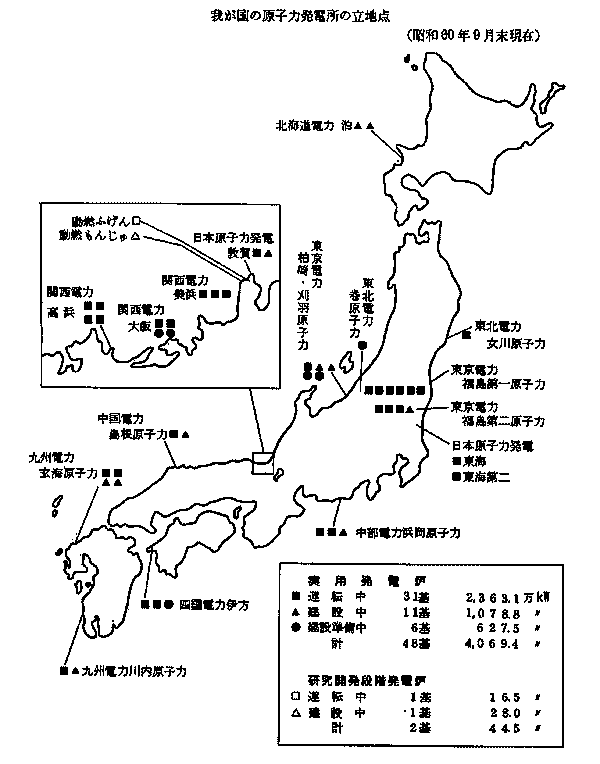 この原子力発電原価には廃炉費用及び放射性廃棄物の最終処分費が含まれていないが、これらは初年度発電原価の概ね1割程度と見られており、これを考慮すれば原子力と石炭火力の発電原価はほぼ同水準にあるものと見られている。 (4) 立地の推進に資するため、現在、立地促進の手段として広報活動等を、また立地地域の振興対策の充実を図るため電源三法の活用等が図られている。 (5) 軽水炉技術の向上を図るため、現在、第3次改良標準化計画が昭和60年度までの予定で進められている。 (6) 原子炉の廃止措置については、昭和60年7月、総合エネルギー調査会原子力部会において解体の標準工程及び費用(110万KW級の原子力発電施設で約300億円)等を示した報告書がまとめられた。また、関連の技術開発については、現在、要素技術の開発についてはほぼ終了し、解体実地試験の遂行に技術的見通しが得られたとの評価を受けている。 2. 核燃料サイクルの動向
(1) 核燃料サイクル施設建設計画及び事業化が進展している。昭和59年4月に電気事業連合会は、ウラン濃縮施設、再処理施設及び低レベル放射性廃棄物最終貯蔵施設の立地協力要請を青森県に対して行い、昭和60年4月「原子燃料サイクル施設の立地への協力に関する基本協定書」が関係者間において締結された。また、これら核燃料サイクル施設の立地に伴う「むつ小川原開発第2次基本計画」の一部修正について閣議口頭了解が得られた。 また、日本原燃サービス(株)は、昭和60年2月動力炉・核燃料開発事業団との間で技術協力実施協定を締結した。 さらに、昭和60年3月、日本原燃産業(株)が設立され、7月には動力炉・核燃料開発事業団との間でウラン濃縮施設の建設・運転等に関する技術協力基本協定を締結した。昭和59年12月には、遠心分離機の製造は当たるウラン濃縮機器(株)が設立された。 (2) 核燃料サイクル各分野の開発状況
① ウラン濃縮については、動力炉・核燃料開発事業団が人形峠に原型プラントを建設・運転することとなっており、昭和59年10月末から土地造成が始まっている。また、技術開発も順調に進展しており、新型遠心分離機RT-2が同事業団において完成し、試運転を開始している。一方、将来の濃縮法として期待されているレーザー法の技術開発も日本原子力研究所及び理化学研究所により進められている。 ② 再処理については、動力炉・核燃料開発事業団の東海再処理工場が改修を終え、昭和60年
遠心分離法によるウラン濃縮技術の開発スケジュール 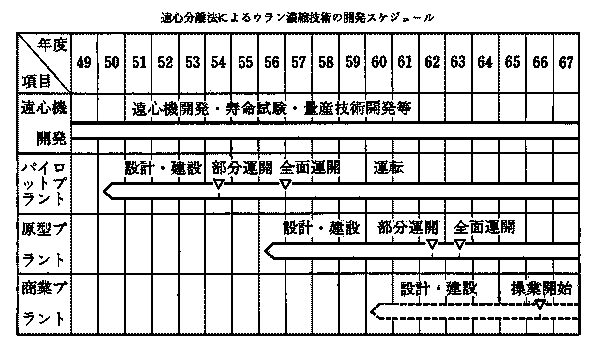 東海再処理工場における再処理実績 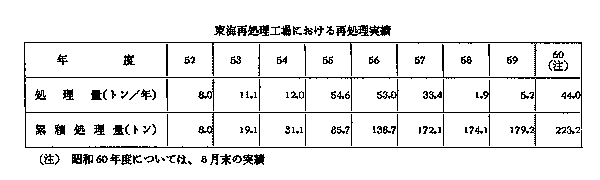 2月運転を再開し、以後順調に稼働している。昭和60年8月までの累積再処理量は約223トンに達している。 ③ 放射性廃棄物対策専門部会は、昭和59年8月、放射性廃棄物の処理処分方策の主に技術的問題に関する検討結果をとりまとめ、また昭和60年10月、処理処分の実施主体及びその責任のあり方等に関する事項について「放射性廃棄物の処理処分方策について」と題する報告書を取りまとめた。また、放射性廃棄物の海洋処分については、昭和60年9月の第9回ロンドン条約締約国会議において、科学的検討のみならず、政治的、社会的検討を含む広範な調査、研究を終了するまで海洋処分を一時停止するとの決議がなされたが、我が国としては、関係諸国とこの問題に関し協議しつつ対処していくこととしている。高レベル放射性廃棄物の固化体の貯蔵については、動力炉・核燃料開発事業団が、高レベル放射性廃棄物等を貯蔵するとともに、それらの処分の研究等を行うことを目的とした貯蔵工学センターの計画を進めている。 3. 新型動力炉の動向
(1) 高速増殖炉(FBR)
現在、原型炉「もんじゅ」について、昭和60年代中項の運転開始を目指して建設工事が進められている。また、実証炉の開発については、昭和59年10月高速増殖炉開発懇談会が官民協力のもとに研究開発を進めること等を内容とする中間取りまとめを行った。 高速増殖炉の開発経緯及び今後のスケジュール 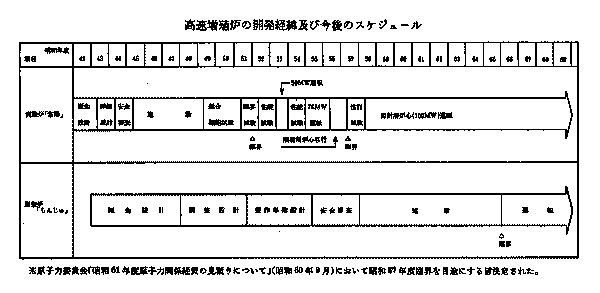 (2) 新型転換炉(ATR)とプルトニウム利用
新型転換炉については、実証炉について電源開発(株)が動力炉・核燃料開発事業団の支援のもとに基本設計を実施している。昭和60年5月ATR実証炉建設推進委員会において実証炉建設計画が見直され、昭和70年3月の運開を目途に建設が進められることとなった。なお、昭和60年6月には、電源開発(株)は、地元に対して建設計画への協力要請を行った。 軽水炉によるプルトニウム利用については、電気事業者を中心として、MOX燃料の少数集合体規模での照射計画の準備が進められている。 新型転換炉の開発経緯及び今後のスケジュール 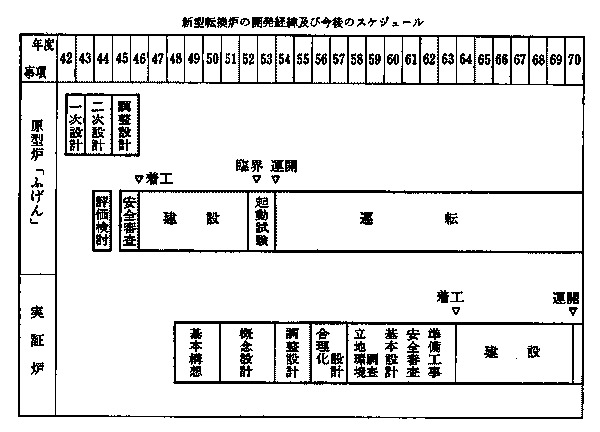 (3) MOX燃料加工及び高速炉燃料の再処理
MOX燃料加工については、「もんじゅ」用(5トンMOX/年)の燃料加工施設の建設が進められており、また、新型転換炉実証炉用(40トンMOX/年)の燃料加工施設の建設準備が進められている。 高速増殖炉の使用済燃料の再処理については東海再処理工場の経験を踏まえて研究開発が進められている。昭和59年9月には「常陽」から回収された初めてのプルトニウムが再び「常陽」に装荷され、実験室規模ではあるが、初めて高速増殖炉の核燃料サイクルが完結した。 プルトニウム燃料加工の開発スケジュール 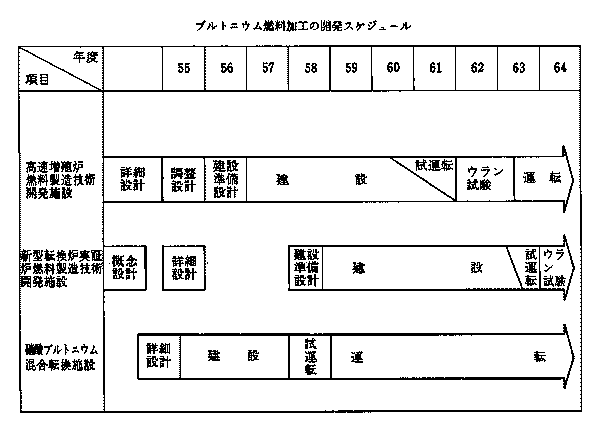 4. その他の研究開発
(1) 多目的高温ガス炉
昭和44年以来日本原子力研究所において研究開発が進められており、昭和60年5月には高温ガス炉臨界実験装置(VHTRC)の初臨界が達成された。 (2) 放射線利用
放射線利用は、医療、工業、農林水産業等の幅広い分野で利用されている。医療分野において、昭和59年からは、放射線医学総合研究所において、重粒子線がん治療装置の研究が開始された。 (3) 原子力船
「むつ」による原子力船の研究開発について、概ね1年を目途とする実験航海を行うこと等を内容とする「日本原子力研究所の原子力船の開発のために必要な研究に関する基本計画」が昭和60年3月31日に策定された。また、日本原子力船研究開発事業団は、同日、日本原子力研究所と統合された。 (4) 核融合
日本原子力研究所において建設が進められていた臨界プラズマ試験装置JT-60の本体が昭和60年4月に完成し、ファーストプラズマの発生に成功した。 5. 国際関係
(1) 国際協力等
先進国との国際協力については、昭和60年1月動力炉・核燃料開発事業団と米国DOEとの間で「高速増殖炉のデータベース整備のための共同研究に関する取決め」、同4月には日本原子力研究所とフランスCEAとの間で軽水炉の安全研究に関し「ROSA-Ⅳ/BETHSY-CATHAR計画に関する研究協力取決め」が締結された。また、同年7月日本、米国、ECにおいて「三大トカマク協力取決め」を締結することがIEA閣僚理事会で合意された。 開発途上国との国際協力については、原子力委員会は開発途上国との協力促進に資するため、昭和59年12月、特に、開発途上国のニーズに応じた技術協力の一層の促進、人材交流を中心とした研究交流が重要であること等を内容とした「原子力分野における開発途上国協力の推進について」を決定した。また、昭和60年8月、日本原子力研究所と韓国エネルギー研究所との間で「原子力安全性及びその関連分野における協力研究計画の実施に係る取決め」が締結された。 日中原子力協力協定については、昭和60年7月第4回日中閣僚会議において署名された。この協定においては、原子力の国際協力においても平和利用を確保するとの我が国の原則が貫かれ、IAEAの保障措置の自主的な受け入れ等具体的な措置が盛り込まれるなど、平和利用の担保が図られた。 (2) 核不拡散
日米原子力協議については、現在、昭和60年5月及び7月の協議において明らかにされた米国側見解をもとに今後の方向について検討が行われているところである。なお、東海再処理工場における米国産使用済燃料の再処理については、共同決定を昭和61年末まで延長すべく両国政府内で手続き中である。 多国間協議については、保障措置の改良や核不拡散に関する新しい国際制度等について、IAEAの場を中心として、検討・協議が引き続き行われている。また、核物質防護については、国際的に核物質防護条約の署名のため開放されており、我が国も署名のための検討を進めているところである。一方、NPT条約については、昭和60年8月から4週間にわたり第3回NPT再検討会議が開催された。第3回NPT再検討会議においては、NPTを引き続き支持する趣旨の「最終宣言」が採択された。 参考)昭和60年度原子力関係予算総表 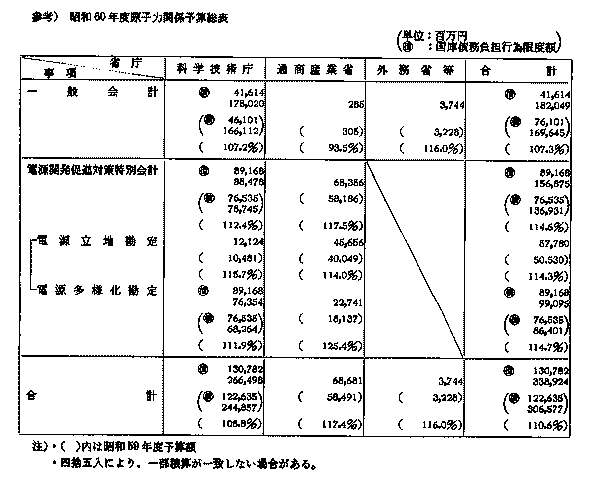 |
| 前頁 | 目次 | 次頁 |