| 前頁 | 目次 | 次頁 |
|
科学技術庁放射線医学総合研究所昭和60年度業務計画 第Ⅰ章 基本方針
本研究所は、昭和32年設立以来、放射線による人体の障害とその予防・診断・治療及び放射線の医学利用に関する調査研究並びにこれらに従事する技術者の養成訓練について多くの成果をあげてきたところであるが、近年、原子力平和利用の進展に伴い環境放射線の安全研究の重要性が一層増大するとともに、放射線の医学利用に対する社会の関心も一層高まっている。従って、本研究所としては、このような社会的、国家的要請に応えるとともに、長期的展望のもとに本来の使命を達成できるようこれまでの実績のうえにたって、調査研究活動の一層の推進を図る必要がある。 以上のような情勢を踏まえ、原子力委員会の定めた「原子力研究開発利用長期計画」(昭和57年6月)、原子力安全委員会の定めた「環境放射能安全研究年次計画」(昭和55年6月)、「放射線医学総合研究所長期業務計画」(昭和59年4月)(以下「長期業務計画」という。)を基として、昭和60年度の業務計画を策定した。 第1節 計画の概要と重点
1. 研究部門
(1) 特別研究については、所期の目標を明確にし、その目標を期間内に達成すべく適切な実行計画を立案するとともに研究体制の整備を図り、所内外の関係機関と協力しつつ一層の進展を図るよう努める。本年度は次の4課題を実施することとする。 なお、医用重粒子加速器施設の概念設計研究を強力に推進する。 ① 核融合炉開発に伴うトリチウムの生物学的影響に関する調査研究(昭和57年度開始)
② 放射線の確率的影響とリスク評価に関する総合的調査研究(昭和58年度開始)
③ 環境放射線の被曝評価に関する調査研究(昭和58年度開始)
④ 重粒子線等の医学利用に関する調査研究(昭和59年度開始)
(2) 指定研究については、長期業務計画における趣旨に基づき、所としてとくに強力に推進すべき適切な課題を選定し、その効果的実施を図るとともに、その内容の一層の充実に努める。本年度は3課題を実施する。 (3) 経常研究については、当面する諸情勢の変化及び研究の進展に即応しつつ、学問的水準の一層の高度化を図るようその充実に努める。本年度は61課題を実施する。 (4) 放射線の人体に対するリスクの解析・評価研究については、抜本的な強化・充実を図ることとし、関係各部との緊密な協力のもとに、情報収集・整理、リスク評価手法開発及びリスク評価の3部門からなる一貫したリスク評価体制を確立するよう努める。 2. 技術支援部門
技術支援部門については、研究業務の円滑な実施に支障なきを期するため、共同実験施設・設備の適切な運用、内部被曝実験棟におけるRI実験の開始に伴う同棟の合理的・効率的運用及び今後の研究需要に対応可能な電子計算機の更新に努める。 医用サイクロトロンの利用については、なお一層効果的な運用を図り、その成果を臨床研究、診療等に反映させるよう努める。 3. 養成訓練部門
養成訓練部門については、関連各部の緊密な協力のもとに放射線防護、RIの医学利用等に関する技術者の養成訓練のほかに、緊急被曝医療対策の一環として、緊急被曝救護等に係る要員の養成訓練等を実施する。 4. 病院部門
病院部門については、前年度までに得られた医療成果を基盤として、関連各部と密接な協力のもとに医療業務を推進するとともに、医用サイクロトロンの利用等による治療をはじめ診療業務の合理的運営を行い、その一層の充実を図る。また、特別診療研究を推進する。 更に、緊急被曝医療対策については、関連各部の緊密な協力のもとに前年度に引き続き体制の整備充実を図るとともに、所要の医療業務の実施に支障なきを期するよう努める。 5. 施設設備及び土地購入
(1) サイクロトロン棟の増築、RI棟空調設備の更新、東海施設給排気等設備の更新及び構内給水設備の改修等、研究施設等の整備、環境保全対策について、計画的にこれを実施する。 (2) 研究所拡張のため、計画的に用地の取得に努める。 6. 国内外関係機関との協力
当研究所の調査研究の促進等に資するため、内外の関係機関との交流の促進に努める。 第2節 機構・定員・予算(略)
第Ⅱ章 研究
第1節 特別研究
本年度は、特別研究に必要な経費として、302,852千円を計上する。 本年度における特別研究の目的及び計画の概要は、次のとおりである。 なお、特別研究については、各課題ごとに設ける班組織及び所長の諮問機関である研究総合会議の検討、審議を経て、調査研究の進捗状況の把握と計画的な推進に努める。 1-1 「核融合炉開発に伴うトリチウムの生物学的影響に関する調査研究」
本調査研究は、核融合炉の研究開発の進展に伴う放射線防護並びに作業者及び作業所周辺住民に対する生物学的影響研究の重要性に鑑み、従来からの研究成果を基盤として、昭和57年度から5カ年計画により推進しているもので、トリチウムの人体に対するリスクの評価に資するため、トリチウムの生体への取込みと挙動、実験動物を用いたトリチウムによる急性・慢性効果、発生異常及び発がん等の解明を目的とする。4年目にあたる本年度は、前年度の研究成果を踏まえて本調査研究を強力に推進するため、所要の実験機器を一層充実するとともに、以下の研究グループを編成して所要の調査研究を実施する。 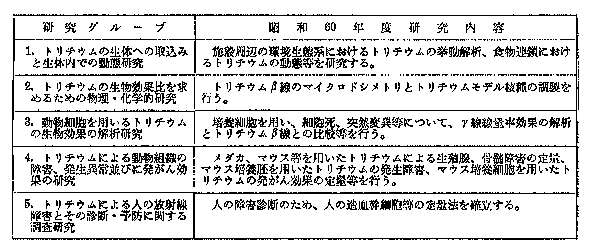 1-2 「放射線の確率的影響とリスク評価に関する総合的調査研究」
本調査研究は、昭和48年度から昭和57年度までの特別研究「低レベル放射線の人体に対する危険度の推定に関する調査研究」の研究成果を基盤として、昭和58年度から5カ年計画により推進しているものであり、環境放射線(能)による低線量及び低線量率被曝の人体に対する身体的、遺伝的な確率的影響とリスクを推定し、一般公衆の放射線防護のための総合的影響評価に資することを目的とする。 3年目にあたる本年度は、低線量及び低線量率被曝の人体に対する放射線障害の確率的影響とリスクの評価を推定するうえで重要な、晩発性の身体的影響、遺伝的影響及び被曝形式の特異性を考慮した内部被曝に伴う障害の総合的評価の三つの研究分野において、以下の研究グループを編成して目的達成に努める。 1. 放射線による発がんとその変更要因に関する調査研究グループ
本調査研究は、本研究所においてこれまでに蓄積された造血器病理、免疫生物学、細胞化学・分子生物学等の研究成果を基盤として、発がん(白血病を含む)とその変更要因との関係及び実験動物系とヒトとの相互関係の解明をめざしてこれを推進する。 このため、本年度は、従来の研究成果を基盤として以下の研究サブグループを編成して所要の調査研究を実施する。 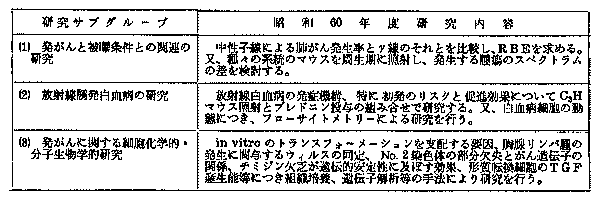 2. ヒトの遺伝的リスクの評価に関する調査研究グループ
本調査研究は、低レベル放射線のヒトに対する遺伝障害を明らかにするため、ヒトの遺伝障害のリスクの評価を目標とし、体細胞と生殖細胞に誘発される染色体異常等の線量効果関係を霊長類等の実験系を用いて解明する。 このため、本年度は、従来の研究成果を基盤として以下の研究サブグループを編成して所要の調査研究を実施する。 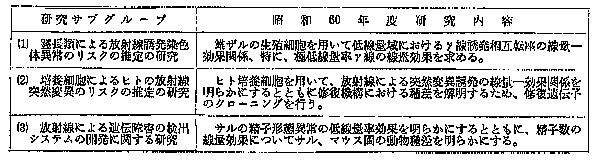 3. 内部被曝の影響評価に関する調査研究グループ
本調査研究は、超ウラン元素によるヒトの内部被曝に伴う障害評価を目的とするものである。その主要な問題点である実験動物系からヒトヘの内部被曝の影響評価の外挿を可能にするために、多種類の動物を用いて放射性核種の代謝に関する比較実験動物学的研究を遂行し、ヒトヘの外挿の理論を確立することを目標としてこれを推進する。 本年度は、従来の研究成果を基盤として、RI実験を10月から開始することとしており、以下の研究サブグループによる調査研究の本格的推進を図る。 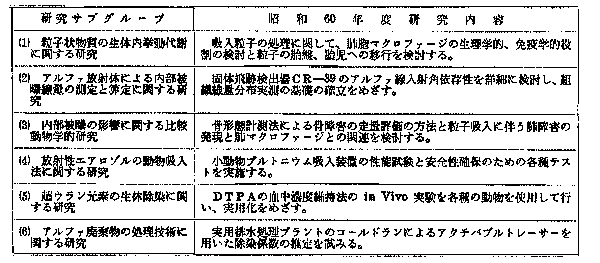 1-3 「環境放射線の被曝評価に関する調査研究」
本調査研究は、昭和48年度から昭和52年度までの特別研究「環境放射線による被曝線量の推定に関する調査研究」、昭和53年度から昭和57年度までの特別研究「原子力施設等に起因する環境放射線被曝に関する調査研究」の研究成果を基盤として、昭和58
年度から5カ年計画により推進しているものであり、環境中に放出された放射性物質の被曝線量評価の体系化を行うとともに原子力施設等の周辺住民に関して集団線量を求め、さらに、環境放射線による国民線量を算定しリスクの評価に資することを目的とする。 3年目にあたる本年度は、環境から人に至る経路の放射線被曝に係る計算モデルの開発と計算に用いるパラメータを実験的に求めて設定することに焦点を合わせて、大気・陸圏、海洋圏、人体成分と代謝に関する諸因子を定量的に究明するため以下の研究グループを編成して所要の調査研究を実施する。 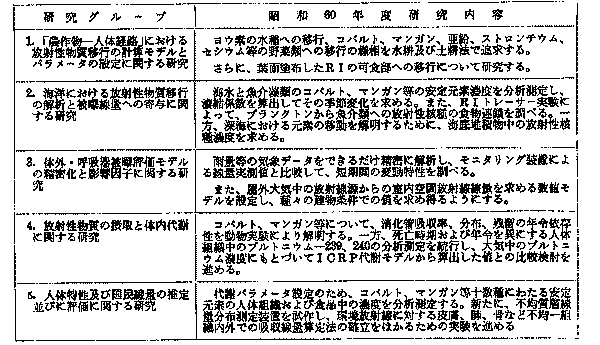 1-4 「重粒子線等の医学利用に関する調査研究」
本調査研究は、昭和54年度から昭和58年度までの特別研究「粒子加速器の医学利用に関する調査研究」の研究成果を基盤として、社会的要請であるがんの診断・治療を一層効果的なものとするため、X線CT、ポジトロンCT等の放射線診断技術の向上並びに速中性子線及び陽子線を用いた治療技術の実用化を進めるとともに、速中性子線の優れた生物効果と陽子線の集中的な線量分布の特徴を併せ持つ重粒子線を用いた新しい放射線治療技術を開発することを目的として、昭和59年度から5カ年計画により着手したものである。 このため、2年目にあたる本年度は、以下の研究グループを編成して所要の調査研究を実施する。 なお、本調査研究の推進に必要な医用重粒子加速器の概念設計研究を実施する。 また、サイクロトロン棟増築工事については、2カ年計画により実施する。 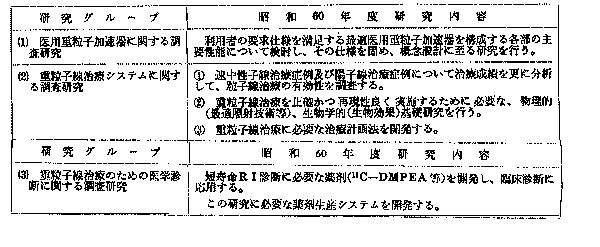 第2節 指定研究
本年度の指定研究については、長期業務計画における趣旨に基づき特に強力に推進すべき課題として、次の3課題を設定し、これを積極的に推進する。 (1) DNA修復遺伝子の構造と制禦に関する研究(化学研究部、遺伝研究部)
(2) T細胞の抗原認識におけるMHC拘束性の発生機序に関する研究(生理病理研究部)
(3) 好中球CSF(G-CSF)の高純度精製に関する研究(薬学研究部)
第3節 経常研究
本年度は、経常研究に必要な経費として、研究員当積算庁費247,420千円及び試験研究用備品24,118千円をそれぞれ計上する。 本年度の各研究部における経常研究の方針及び計画の大要は、次のとおりである。 3-1 物理研究部
本研究部は、放射線の医学利用ならびに放射線障害の防止に関する研究において理工学的方面を発展させることを目標とし、医用放射線イメージング、放射線の線量・線質の計測、放射線防護の基礎、および加速器等の医学利用等について調査研究を行う。 放射線イメージングに関しては、ポジトロンおよび単光子を用いるコンピュータ断層撮影(CT)について物理的基礎研究を行う。放射線の線量・線質の計測に関しては、気体電離箱線量計の精度向上、LET分布の測定、水熱量計の開発、診断用X線装置の精度管理および治療線量のトレサビリティ等を研究する。放射線防護に関しては、医療および職業被曝における線量評価とその低減、広島・長崎における原爆被曝の再評価、低線量被曝の生物効果の解析、および放射線の遮蔽等について研究を行う。加速器等の医学利用に関しては、陽子線および重イオンを用いる診断・治療のための物理的基礎研究、PIXE分光学の元素分析への応用、および固体線量計の開発等について研究を行う。 3-2 化学研究部
本研究部は、生体に対する放射線の影響の解明を化学的立場から推進するため、生物物理学的、生化学的、放射化学的及び錯塩化学的調査研究を行う。 生物物理学的研究に関しては、放射線のターゲットとして最も重要と考えられる染色体の構造を調べるために、ヌクレオソームの構造及びヌクレオソームと非ヒストン蛋白質の相互作用に関する研究を行う。 生化学的研究に関しては、放射線感受性に影響を及ぼす諸因子を、生体高分子相互作用の調節の面から、とくに遺伝子操作技術を駆使して細胞分裂の調節機構、放射線障害の修復と耐性機構等に関する研究を行う。 放射化学的及び錯塩化学的研究に関しては、主として水溶液中の放射性同位体の化学的存在状態を吸着法を中心として調べ、新しい放射化学分析法の開発を行う。また、時間的経過による放射性同位体の化学形の変化並びに平衡状態における化学形について、錯塩化学的及び熱力学的に調べるとともに、酵素の作用機構とも関連しながら、金属錯塩の触媒作用を研究する。 3-3 生物研究部
本研究部は、生体の細胞、組織及び個体の各レベルにおける放射線障害の機構について調査研究を行う。 細胞レベルの研究としては、培養細胞を用いて種々の条件下で照射したときのDNAの損傷及びその修復と細胞障害との関連を把握する。 組織レベルでは、哺乳類の組織細胞の発現形質、特に、細胞性膜および細胞間膜の照射後の変化を生物物理学的に解析し、発生異常や発癌など、増殖・分化の異常の発現過程の解明に資する。 また、魚類を用いた個体レベルの研究として、発癌過程における放射線と発癌剤との相互作用、処理時の発生段階と腫瘍の発生率との関連等を各系統のメダカ間で比較検討する。 3-4 遺伝研究部
本研究部は、放射線に対する人体の遺伝的リスクを評価する目的の下に、分子・細胞及び集団の各レベルにおける遺伝障害の本性を体系的に解明する調査研究を行う。 遺伝障害の分子レベルの研究に関しては、有核単細胞の酵母および哺乳類培養細胞を用いて放射線及び化学物質によるDNA損傷と突然変異、遺伝子変換、遺伝子組換の誘発とその修復の分子機構について解明する。このため哺乳類細胞における遺伝子操作法の開発を行う。 遺伝障害の染色体レベルの研究に関しては、哺乳類の培養細胞及び生殖細胞の、放射線及び化学物質による染色体異常の誘発と修復機構の関係を解明する。このため修復欠損株と体外受精法を用いて遺伝子発現に関する実験系の開発を計る。 遺伝障害の集団レベルの研究に関しては、日本人集団での遺伝的疾病とリスクの評価を行うため、関係諸機関の密接な協力によって各種疾患のデータを収集し、これについて統計遺伝学的解析を行い、その評価方法を確立する。特に不規則性遺伝病、先天異常の集団遺伝学的手法の開発を行う。 3-5 生理病理研究部
本研究部は、人体の放射線障害に関する病理学的概念を確立するため、動物実験、組織培養等による実験的調査研究を行う。 放射線の致死効果については、ヒト悪性黒色腫細胞等により、潜在性致死効果からの回復と細胞動態との関連について研究する。またヒト癌細胞等により、X線・中性子線の分割効果を検討すると共に、各種制癌剤との併用効果を解析する。 放射線の晩発障害の発現や転帰を支配する生体防御機構については、造血系及び免疫系に関する研究に重点を置く。造血系については、多分化能幹細胞の培養を目的として、造血刺激因子産生腫瘍の分離株化を試みる。また、トロトラスト患者の血液疾患等につき、疫学的研究を継続する。免疫系については、種々のコンジェニック・マウスの組み合せで骨髄キメラを作り、これによってGVH反応の統御機構、宿主Ir遺伝子が免疫応答に果す役割等について検討する。 放射線発癌については、放射線とウレタンの併用による肺腫瘍の発生につき、種々の系統のマウスによる比較を行って初発と促進効果を解析するほか、癌組織の糖蛋白・糖脂質の変化とそれに関連する酵素を調べる。又、腫瘍に対する放射線と加温の併用効果を検討する。 3-6 障害基礎研究部
本研究部は、各種被曝様式による放射線の急性、晩発性障害並びにその予防等に関する哺乳動物を用いた実験的研究を行うとともに、ヒトの身体的障害についての基礎的資料を得るための調査研究を行う。 急性障害に関しては、外部照射による栓球造血系、培養細胞および細胞膜の受動輸送能に対する効果とその修飾、特に放射線効果に対する温熱処理の影響を検討する。また、全体、又は部分照射による影響とその修飾に関する実験を行う。 晩発性障害に関しては、発育期被曝による中枢神経系における発達障害と晩発性障害について定量的に検索する。 内部被曝並びに外部連続照射による障害に関しては、造血系への影響を中心に定量的検討を行う。 ヒトの障害に関しては、染色体異常の急性被曝の障害評価への役割並びに晩発効果との関連性を引続き検討する。また、白血病の染色体研究を行い、放射線障害の解明に資する。 3-7 内部被ばく研究部
本研究部は、放射性物質による内部被曝の障害評価の精度向上に資することを目標とし、特に実験動物データからヒトの障害の予測に有用な実験的また理論的根拠を求めるための調査研究を行うほか、これらの研究を遂行するために必要な実験技術及び安全技術の開発を行う。 本年度は内部被曝実験棟でのRIホット実験の本格稼動をめざして実験施設、動物飼育実験設備の整備に努めると共に、61年度に予定されるプルトニウムホットランの開始に備えての諸準備を行い、本棟におけるプルトニウム研究実施体制をととのえる。 放射性物質の代謝に関しては、粒子状物質の体内挙動の動物種差をあきらかにするため、とくにマクロファージによる粒子貧食能について検討する。 線量評価に関してはプルトニウムの体外計測法とくに肺負荷計測の精度向上と体内線量分布の不均等性の検討を行う。 生物効果に関しては、吸入肺障害の発現メカニズムを肺マクロファージとの関連で、骨障害の発現機序を骨形態計測法を用いて検討する。 上記研究を支える実験手段として動物吸入実験法および各種の安全技術の開発を作業者安全確保のため実施する。 3-8 薬学研究部
本研究部は、生化学、有機化学を基礎として放射線障害の解析、障害の回復に関連する生理活性物質の合成、抽出、精製、構造解析、作用機構等について調査研究を行う。 放射線障害の発現過程に関して、生体高分子との錯体反応、及び生成された金属錯体とキレート剤、生理活性物質、あるいは活性酸素種との反応の生物有機化学的研究を、迅速測定技術を開発しながら推進する。 生殖腺の放射線障害に関する生理化学的研究として、精巣等に存在するステロイドホルモンの生合成に関与している酵素の基質結合部位等を生化学的に分析して、その酵素反応機構の解明を行う。また、卵巣については、ゴナドトロピンで誘起される卵胞の成熟、排卵等の過程における内分泌学的研究を推進する。 放射線障害の回復促進を目標として、血球前駆細胞等各種細胞の増殖分化因子を種々の原料から精製し生化学的研究を行う。さらに、細胞増殖分化促進作用機構に関する研究を推進する。 3-9 環境衛生研究部
本研究部は、個人及び集団の放射線被曝線量の推定と防護に資するため、自然と人工(核実験や原子力発電事業などによる)の環境放射線と環境放射性物質に関し、それらの一般環境中並びに食物連鎖網における特性と挙動を調査研究し、人体への被曝経路とその機構並びにそれに関与する変動要因の解明に関する調査研究を行う。 自然環境における放射性物質の様相の研究に関しては、大気中の自然放射性核種濃度の測定とその変動要因の解析、居住環境でのラドンとその娘核種の測定法の検討とその実用化をはかる。 食物連鎖における放射性核種の動向の研究としては、水産生物による環境水及び飼料生物からの放射性核種の取り込みと代謝、魚類への水中放射性核種の影響、水生生物に取り込まれた水中放射性核種が哺乳動物に摂取される場合の代謝の研究を行う。また、炭素-14とトリチウムについては高精度、高感度測定法の開発ならびに植物から動物への経路における挙動の研究を行う。 放射性核種の体内挙動に関する研究としては、環境と生体試料について微量元素の定量法と環境、生態系での循環の研究を行う。 3-10 臨床研究部
本研究部は、放射線の医学利用に関する調査研究を行う。この分野は診断への利用および治療への利用にて大別される。 診断の分野では、年間4億件近い利用のあるX線については診断効率の向上についての調査研究を行う。アイソトープ利用については特にサイクロトロン核医学の発展に必要な調査研究を行う。また新しい放射線診断技術としての核磁気共鳴の診断への寄与を追求する。さらにこれら各種の診断技術を体系的に総合化するための調査研究を行う。 放射線治療に関しては、治療効果を向上させるために必要な放射線生物学的、及び臨床的研究を行う。生物学的研究では、腫瘍治療のための分割照射効果、並びに腫瘍転移、再発に関する諸因子を追求し、臨床的研究では、治療の精度を向上させる技術開発と放射線治療病症登録システムを充実させる。特に粒子線治療効果を評価するために必要な対照症例を集積し、標準放射線治療方針の確立を重点課題として研究を行う。 3-11 障害臨床研究部
本研究部は、放射線被曝者の診断と治療に必要な医学的指標を確立するため、人体の放射線障害に関する基礎的、臨床的調査研究を行う。 このため、各種線源による被曝者、すなわち、ビキニ環礁降灰被曝者、イリジウム192事故被曝者ならびにトロトラスト被投与者等の遂年的医学調査を継続して行い、医学的データーを充実させる。調査研究の内容は、一般的診察、臨床検査に加えて、造血細胞の染色体解析、及び、特に培養法や単クローン抗体などを用いた血液学的、及び免疫学的な精密検査を行い、トロトラスト被投与者については、体内被曝線量の推定も併せて行う。特に被曝線量及び被曝様式と臨床症状、検査成績との関連に重点をおいて研究を推進する。さらに、障害検索のための新しい検査法の導入や開発研究も併せて行う。 このほか、リンパ球の放射線障害機構についても基礎研究を続行する。 緊急被曝に関しては、有事の被災に備えるため、派遣医療チームが行う処置、緊急医療棟及び無菌室での処置、治療手順を具体的にマニュアルにまとめ、臨床的実用化をはかる。 さらに、骨髄移植などの実用化に関しても調査研究を行う。 以上の調査研究は、病院部をはじめ、関連各研究部の密接な協力を得て実施する。 3-12 環境放射生態学研究部
本研究部は、環境放射性物質による人の放射線被曝線量の算定と予測に資するため、大気・土壌・陸水・動植物・人体における放射性物質の挙動の解明をめざして、環境科学的、並びに放射化学的な基礎的調査研究を行う。 環境科学的研究に関しては、土壌におけるヨウ素・ストロンチウム・セシウムなどの移動に及ぼす環境要因の影響を調べ、さらに、これら核種の土壌中における存在形態について究明する。また、淡水系生物の移行に関する生物学的影響に関する基礎的研究も行う。 環境研究手法の開発上関連する放射化学的研究に関しては、雨水・土壌などにおけるヨウ素の化学形態別分離法と、土壌中の可給態セシウム・ストロンチウム・ヨウ素などの分離法との検討を進める。 また、多くのアルファ放射体の環境-食品-人体系における移行の機構と被曝線量の解明を目的として、人体組織などにおけるアルファ核種の系統的分析法の検討を行う。 3-13 海洋放射生態学研究部
本研究部は、海洋経由の人工放射性核種による人体被曝線量の推定とその軽減方策に資する事を目的として、海洋中での放射性物質の挙動に関する調査研究を行う。 沿岸に関しては、海水・堆積物・懸濁物・生物間の放射性核種および安定元素の分布・移行・蓄積についてさらに研究を進める。これまでに得たヨウ素・コバルト等の元素についての知見や技法を基にして、元素の海水中での存在形態とその変化、生物への可給性、生物濃縮に対する海水と食物連鎖の寄与の比較、生物中での元素の存在状態等について研究を行う。また微量安定元素の定量法の検討をさらに進める。 また外洋では、深度別の海水と懸濁物中のセシウム、アルファ核種等の測定を行い、外洋での物質輸送の追求を行う。 第4節 放射線のリスク評価研究
原子力の開発利用に当たって、その安全の確保に万全を期することの重要性は、原子力開発の急速な進展を背景として、より一層増大してきている。 特に、原子力安全委員会環境放射能安全研究専門部会は、環境放射能による生物学的安全性に係る研究体制の整備の一環として、その要となる放射線の人体に対するリスクの評価研究について一層の推進及びその体制の整備の必要性を強く指摘している。 本研究所は、放射線の生物学的影響に関する中核的研究機関として、原子力安全委員会をはじめとする国の原子力安全行政の推進に寄与するため、計画的に放射線のリスク評価のための組織体制を整備してきたところである。 本年度は、総括安全解析研究官組織の抜本的な強化・充実を図ることとし、関係各部との緊密な協力のもとに、情報収集・整理、リスク評価手法開発及びリスク評価の3部門からなる一貫したリスク評価体制を確立することとする。 本年度は、この放射線のリスク評価研究に必要な経費として、11,358千円を計上する。 第5節 実態調査
本研究所の調査研究に関連する分野のうち、特に必要な事項について実態調査を行い、その結果を利用して調査研究の促進をはかる。 本年度は、実態調査に必要な経費として2,207千円を計上し、次の課題についてそれぞれ調査を実施する。 (1) ビキニ被災者の定期的追跡調査(障害臨床研究部、障害基礎研究部)
(2) 医療及び職業上の被曝による国民線量の実態調査(物理研究部)
(3) トロトラスト沈着症例に関する実態調査(生理病理研究部、障害臨床研究部、障害基礎研究部、養成訓練部、病院部)
第6節 外来研究員
本研究所においては、所外の関連専門研究者の協力を得て、相互知見の交流と研究成果の一層の向上を図るため、外来研究員制度を設けている。 本年度は、外来研究員に必要な経費として2,213千円を計上し、次の研究課題について、それぞれ、担当する研究部に外来研究員を配属し、研究を推進する。 (1) 日本における産業関連健康障害リスク統計データベースの作成(総括安全解析研究官付)
(2) 中性子散乱法によるクロマチンの構造研究(化学研究部)
(3) 化学発癌剤と放射線による色素細胞腫瘍誘発の系統差に関する研究(生物研究部)
(4) マウス受精卵のマイクロマニピュレーション法の開発改良(生物研究部)
(5) がん罹病の遺伝的感受性に関する疫学的研究(遺伝研究部)
(6) 放射線誘発突然変異に関与する修復遺伝子のクローニング(遺伝研究部)
(7) 細胞の癌化による細胞表面糖鎖構造の変化(腫瘍の組織発生と腫瘍細胞の特性の解析)(生理病理研究部)
(8) 細胞増殖統御因子に関する生物薬学的研究(薬学研究部)
(9) 環境のラドン等の測定に用いるNTD方式の実用化研究(環境衛生研究部)
(10) 受容体インビボ測定を目的とした核医学薬剤の開発に関する研究(臨床研究部)
(11) 農作物一人体経路における放射性物質移行の計算モデルとパラメータの設定に関する調査研究(環境放射生態学研究部)
第7節 受託研究
本研究所における受託研究は、本研究所の所掌業務の範囲において所外の機関から調査研究を委託された場合に、本研究所の調査研究に寄与するとともに研究業務に支障をきたさない範囲において受託することとし、本年度は、この受託研究に必要な経費として、994千円を計上する。 第8節 放射能調査研究
本研究所における放射能調査研究は、次のとおりである。 8-1 放射能調査・解析研究等
原子力平和利用の進展に伴い、原子力施設等から放出される放射性物質及び国外の核爆発実験等に伴う放射性降下物による環境放射能レベルの調査並びにこれらの解析を環境衛生研究部、環境放射生態学研究部、海洋放射生態学研究部及び物理研究部において行う。 また、本年度から、国民線量の推定に資するため、総括安全解析研究官及び環境衛生研究部において、ラドン・トロン及びこれらの娘核種濃度を測定する。 さらに、国内外の放射能に関する資料の収集、整理、保存等のデータセンター業務並びに放射能調査結果の評価に関する基礎調査の業務を管理部企画課において行う。 一方、我が国における環境放射線モニタリングの技術水準の向上を図るため、都道府県の関係職員を対象とする技術研修を養成訓練部において行う。このため、これらに必要な経費として119,941千円を計上する。 本年度における放射能調査研究に関する事項は、次のとおりである。 (1) 環境、食品、人体の放射能レベル及び線量調査
(2) 原子力施設周辺のレベル調査
(3) 放射能データセンター業務
(4) 放射能調査結果の評価に関する基礎調査
(5) 環境放射線モニタリング技術者の研修
8-2 緊急被曝測定・対策に関する調査研究等
原子力施設に起因する原子力災害事故時における緊急被曝測定・対策は原子力の安全性の確保という観点から重要な課題となっている。 本年度は、障害臨床研究部、病院部、養成訓練部及びその他関連各部の協力を得て、人体の放射線被ばく、環境の放射能汚染による影響等に関する対策を確立するための調査・測定及び研究を推進する。 また、救護要員等に対し、緊急被曝時の測定、防護、救護、被曝評価等について教育及び訓練を養成訓練部において行い、原子力災害時における緊急被曝の防災対策に資することとする。このため、これらに必要な経費として、12,958千円を計上する。 第Ⅲ章 技術支援
技術部においては、調査研究、診療等の遂行に必要な実験施設並びに共同実験用機器、電気及び機械等施設の運用、維持管理、職員及び放射線施設の放射線安全管理、実験動植物の生産供給、飼育・栽培、検疫等及びこれらに関する施設の運用、医用サイクロトロンの運用及び附属設備の管理等の諸業務を行う。 このため本年度は、これらの業務遂行に必要な経費として、経常運営費98,803千円、共同実験用備品費15,504千円、サイクロトロン設備整備費276,981千円、特定装置運営費17,555千円、安全管理・廃棄物処理対策費82,842千円、特殊実験棟運営費1,070,141千円、データ解析装置関係費95,124千円を計上し、計画的かつ効果的な支援を期する。 (1) 技術支援部門は、施設運用に関しては受変電、ボイラ、空調等基幹設備の効率的な運用とRI棟空調設備等老朽化設備の計画的改修に努める。また、内部被ばく実験棟におけるRI実験の開始に伴う同棟の合理的・効率的運用に努める。 共同実験施設(測定・分析機器、放射線発生装置及びRI照射装置)の運用に関しては、機器・装置の計画的更新並びに新規導入を行うとともに、これらの整備と適切な運用に努める。 データ処理業務では電子計算機の利用に関し、今後の研究需要に対応可能な電子計算機の更新に努めるとともに研究者への支援、指導を行い、医療情報処理システムの開発に関する研究を継続する。 (2) 放射線安全管理部門は、経常的業務の推進に努めるほか、放射性廃棄物処理においては、トリチウム廃液処理槽の新設に伴う効率的運用をはかるとともに、有機廃液の処理について技術的検討を行う。また、放射性廃棄物の保管及び管理体制を強化するため、保管庫の新設、除染棟の整備を実施する。 放射線安全管理においては、RI棟の各設備を更新して、使用施設等の安全性を向上させるとともに、健康管理においては、個人被ばく管理用機器を計画的に更新する。 那珂湊支所放射線安全管理においては、本所との連携を一層強化する。 また、東海施設については、給排気空調設備及び放射性廃液貯留設備の更新を行う。 (3) 動植物管理部門は、各種実験研究に必要な動植物について、安定した生産供給に努める。 更に一層の充実と向上を計るため系統維持について親種の凍結保存等についての検討並びに生産施設のクリーン化に努めるとともに、動物の衛生管理及び検疫業務を強化促進する。 実験用動物施設の管理運営については、安全衛生対策並びに設備の充足を計るとともに、老朽化対策の推進及び管理運営業務の確保に努める。 事務管理では、各種規程等の見直しと検討を計り、研究面では、近交系マウスの加齢性変化に関する病理学的研究・実験動物の骨疾患に関する病理学的研究及び放射線照射マウスにおける常在細菌叢の影響に関する研究を継続するとともに、小型霊長類を用いた実験動物学的及び放射線障害のための基礎的検討を新規に行う。 (4) サイクロトロン管理部門では、経常的業務を行うとともに、高周波系のチェックアップを実施し、サイクロトロンの運用に支障なきを期する。 技術運転関係業務では、2モードイオンソース系及びビーム取出し系の改善などを行い、サイクロトロン装置にとって安全性の高い運転条件の確立に努める。また、サイクロトロン棟施設の実効ある管理運営を図るとともに、老朽化対策を推進する。 短寿命RI生産関係業務では、従来と同様に特別研究班との協力のもとに、炭素-11、窒素-13、ふっ素-18及びよう素-123などの標識化合物の経常的な生産・供給に努める。 研究面では、各ビームトランスポートの効率的運用を可能とする共振器周波数自動制御装置の開発を行うとともに、サイクロトロン本体の安定した運転を確保するための改良・調整を実施する。また、RI生産用集中制御システムと品質管理システムとを結合するためのソフトウェアを開発し、効率的なRI生産に役立たせる。 第Ⅳ章 養成訓練
本年度は、養成訓練業務運営経費として、9,158千円を計上して、本研究所の長期業務計画の方針に従い、教科内容の充実を図り、関連研究部との緊密な協力のもとに、次の8課程を実施し、180名の科学技術者を養成する。また、効率的かつ合理的な運営により研修効果の向上に努める。 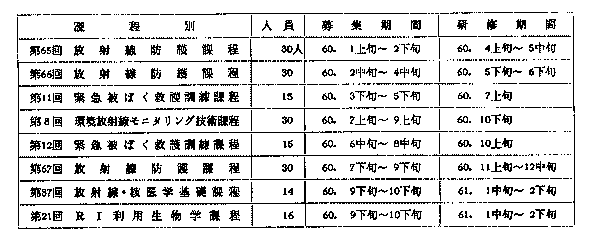 また、内外の養成訓練制度について、調査を進めるとともに、研究成果の向上を図るために必要な研究を行う。 なお、養成訓練部においては、昭和34年度から昭和59年度までに、下表のとおり研修課程を実施し、課程終了者の累計は、3,466名に達した。 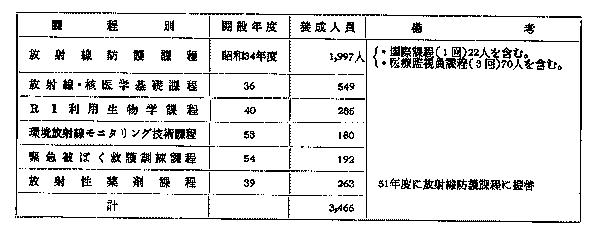 第Ⅴ章 診療
病院部は、予算定床78床、運営費290,157千円をもとに、診療技術水準の維持向上と運営の円滑化、効率化に努める。 このため、各部門毎に、以下の諸項に重点をおき、診療研究の遂行に遺憾のないよう期する。 (1) 放射線障害部門においては、急性、晩発性の両障害の診療と追跡調査を実施する。悪性腫瘍患者の診療にも関連する正常組織損傷の評価について臨床症例を重ね研究を進める。 (2) 放射線診断部門においては、陽電子RI及びNMR-CTの利用を含む画像診断全般について技術の向上をはかり、疾病診断能の評価を行う。 (3) 悪性腫瘍の放射線治療部門においては、粒子線治療の臨床評価を積極的に進めると共に、集学的治療技術の改善向上に努める。特に、社会復帰を目標にする質の高い治療の研究を進める。 (4) 特別診療研究に関しては、診療業務のシステム化を進め、本事業の一環として医療情報の処理及びその解析に関する研究を重点とする。 以上を実施するにあたっては、広く所内・外の専門家の支援・協力が得られるよう緊密な連携に努める。 第Ⅵ章 緊急被曝医療対策
本研究所は、原子力安全委員会「原子力発電所等周辺の防災対策について」(昭和55年6月)に示された緊急医療体制の整備等に関する施策の必要性に対応して、本年度も引き続き、原子力施設等に起因する原子力災害事故時における緊急医療対策の一環として、所内における体制の整備を行うとともに、緊急被曝医療のための設備、機器等の整備及び看護・救護要員に対する養成訓練を行う。 第Ⅶ章 研究施設等整備計画(略)
|
| 前頁 | 目次 | 次頁 |