| 前頁 | 目次 | 次頁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
「長期エネルギー需給見通し」の改定について 昭和58年11月16日
総合エネルギー調査会需給部会
企画専門委員会
-はじめに-
当専門委員会は、昭和58年9月以降、長期エネルギー需給見通しについて広範な角度から検討を重ねてきたが、以下のとおりとりまとめを行ったので報告する。 Ⅰ 需給見通し策定の背景と基本的考え方 1. 背景 (1) 世界と日本のエネルギー情勢の変化
石油危機以降10年を経過した今日、内外のエネルギー情勢は大きな変化を遂げている。 国際石油需給は世界的な石油需要の大幅な減少等を反映して緩和基調にあり、本年3月にはOPEC結成以来初めて基準原油価格の引下げが行われた。 また、我が国においても、昭和55年度以降、国民総生産(GNP)が毎年3%以上の成長を続けているにも拘わらず、エネルギー需要は毎年3%以上の減少を示す等、エネルギー需給構造は構造的な変化を遂げており、総合エネルギー調査会需給部会が昨年4月に策定した「長期エネルギー需給見通し」も現実との乖離が顕著になった。 加えて、石油危機以降のエネルギーコストの上昇は基礎素材産業をはじめ、我が国経済社会に広範かつ甚大な影響を及ぼし、エネルギーコスト低減の要請が強まっている。 (2) 長期エネルギー需給見通しとエネルギー政策の総点検
こうしたエネルギー情勢の下で、これからの時代に相応しいエネルギー対策のあり方を明らかにすべく、総合エネルギー調査会は、本年4月以降、審議を重ね、長期エネルギー需給見通しとエネルギー政策の総点検を実施し、去る8月22日に報告をとりまとめた。 本報告においては、エネルギー対策の目的は需要に応じてエネルギーの量的かつ価格的な安定供給の確保を図ることにあるとし、これを達成するため、具体的には、第一に、セキュリティの確保を図ること、第二に、エネルギーコストの低減に努めること、第三に、セキュリティとコスト等とのバランスのとれた最適エネルギー需給構造の実現を図ることが肝要としている。かかる観点から、本報告においては、新たな長期エネルギー需給見通しの目安として、セキュリティとコスト等とのバランスの確保に配慮した昭和65年度及び70年度のエネルギー需給構造についての暫定試算を示し、今後さらに専門的な吟味を経ることが適当であるとしている。 (3) 長期エネルギー需給見通しの改定
当専門委員会は、9月から長期エネルギー需給見通しの改定作業に着手し、エネルギー政策の総点検で示された基本方向に沿って専門的な審議を重ねた結果、概要以下に示すとおりの長期エネルギー需給見通しを策定した。 2. 需給見通し策定に当たっての基本的考え方 (1) 今後のエネルギー情勢
国際的な石油需給は現在緩和基調で推移しているが、今後の世界景気の回復に伴い、発展途上国を中心に石油需要も増大する一方、OPECを中心とする供給余力は限られていることから、1990年代には再び国際的な石油需給がタイト化し、また、石油価格も1980年代後半以降特に1990年代に上昇する可能性が高いとの見方が一般的である。もとより、国際石油情勢は流動的であり、今後の需給・価格動向を正確に見通すことは困難であるが、中東情勢の不安定性を勘案すれば、なお不安定な要素が大きいと考えられるため、こうした石油の需給・価格動向を前提に今後のエネルギー対策を進めていく必要がある。 一方、我が国のエネルギー需要の急激かつ構造的な変化は、最近に至り漸く一段落しつつあると考えられ、今後においては、産業構造の変化や省エネルギー等が進む中で、エネルギー総需要も経済成長に伴い緩かな増加を示すものと考えられる。 (2) 我が国のエネルギー政策
我が国は国内エネルギー資源に恵まれず一次エネルギー供給の8割以上を輸入に依存し、また、輸入石油の比率、とりわけ政情不安定な中東に依存する度合が国際的にみても極めて高いこと等から、エネルギー供給構造は極めて脆弱である。 かかる観点から今後とも石油代替エネルギーの計画的かつ着実な開発・導入を促進し、石油依存度の低減を図っていく必要がある。この場合、石油については、その汎用性や固有の需要分野の存在等を考慮すれば、今後中長期的にみても最大のエネルギー源であり、また、我が国エネルギー需給構造の弾力化に大きな役割を果たすものであることに留意し、石油依存度の低減は、現実的かつ弾力的に行っていくことが適当である。 他方、エネルギーコストの上昇が基礎素材産業をはじめ我が国経済社会に及ぼす影響の大きさに鑑み、より低廉な一次エネルギーの供給を拡大し、また、二次エネルギー部門においてもより一層の経済性の追求を行う等によりコスト低減に努めていく必要がある。 また、セキュリティの確保には、もとより費用を要するものであるが、エネルギーコストに過大な負担を課し、価格面においてエネルギーの安定供給を損うものであってはならない。今後においては、セキュリティの確保を図るとともに、時代の要請であるエネルギーコストの低減にも十分配慮し、併せて両者の間にバランスを確保していく必要がある。 Ⅱ 需給見通しの概要 1. 目標年度
長期エネルギー需給見通しの目標年度については、中長期に亘る官民の努力の基本方向やその効果を織り込み得る期間を考慮して設定することが適当である。かかる観点から、今回の長期エネルギー需給見通しにおいては、昨年4月に策定された長期エネルギー需給見通しの政策目標年度である昭和65年度については、今後7カ年が残されているに過ぎないことに留意し、可能な限り現実的・予測的な目標年度とし、新たになお10年以上の期間のある昭和70年度を政策的な目標年度として設定した。 なお、長期的なエネルギー需給の展望を行うため、昭和75年度(西暦2000年)についてもエネルギー需給の試算を行った。同試算は、エネルギー政策の長期的性格に鑑み、多くの不確定要因があるものの1つの試算として将来のエネルギー需給構造の方向を示したものである。 2. エネルギー需要
今回の長期エネルギー需給見通し策定に当たり、エネルギー需要については、最近におけるエネルギー需給の構造的変化を十分織り込み、現実的な総需要を見込むことを基本とし、「1980年代経済社会の展望と指針」(昭和58年8月12日閣議決定)等に示された今後の経済社会の方向を踏まえて見通しを行った。 この結果、産業、運輸、民生の各部門におけるエネルギー需要の動向は、以下のとおりと見込んだ。 (1) 産業部門
産業部門については、省エネルギー型生産設備が着実に普及する等により、エネルギー原単位は今後ともさらに改善されると見込まれる。 また、産業構造面でみると製造業においては、エネルギー多消費型の基礎素材産業からエネルギー寡消費型の加工組立産業へ比重のシフトが見込まれる。 したがって、経済規模の拡大とともに、エネルギー多消費型産業の生産量も今後緩やかな増加が見込まれるものの、産業部門全体としては、エネルギー需要の伸びは低く、エネルギー需要全体に占める産業部門のシェアは低下するものと考えられる。 (2) 運輸部門
運輸部門については、燃費の改善、輸送効率の向上等によるエネルギー原単位の改善が見込まれるものの、旅客、貨物ともに輸送量の安定的増大が予想され、特にエネルギー原単位の高い乗用車、トラック、航空機による輸送量の大きな伸びが見込まれることから、エネルギー需要は着実に増加するものと考えられる。 (3) 民生部門
民生部門については、家庭部門における世帯数の増加、生活水準の向上に伴うエネルギー消費機器の一層の普及、業務部門におけるサービス経済化の進展等に伴う業務用床面積の拡大等により、今後ともエネルギー需要の堅調な増加が見込まれ、エネルギー需要全体の伸びをかなり上回る伸びを示すものと考えられる。 以上の部門別エネルギー需要を合計した、昭和65年度及び70年度におけるエネルギー総需要は、需要端において、それぞれ原油換算で約4.4億kl及び5.0億klと推計される。 3. エネルギー供給
今後のエネルギー供給について、エネルギーの安定供給の確保を基本としつつ、時代の要請である供給コストの低減をも十分考慮し、更には各エネルギー源の有する諸特性や国際的な需給の状況等に配慮し、総合的視点から以下のように各エネルギー源の位置付けを行った。 ① 石炭
石油危機以後、石油に比しカロリー当たり価格での優位性が定着しているが、この傾向は今後当分の間続くものと見込まれる。 また、確認可採埋蔵量が豊富であり、地域的偏在性が比載的少ないため、潜在供給力は大きい。したがって、今後供給側の制約要因は少なく、むしろ需要動向に左右される部分が大きいものと考えられるが、電力用を中心に、一般産業部門においても一般炭需要の増加に対応して供給量の着実な増加が見込まれる。また、長期的には、技術開発により、用途範囲及び利用炭種の拡大が期待される。 ② 原子力
自主的核燃料サイクルの確立により供給安定性のある準国産エネルギーとして位置付けられるとともに、経済性、大量供給性等多くの優れた特性を有している。このため、安全の確保に万全を期しつつ、今後とも、電力供給の中核的役割を担うものとして、着実に供給シェアが拡大していくものと考えられる。 ③ 天然ガス
燃焼制御が容易であり、クリーンなエネルギーであることから、都市周辺の火力発電用燃料及び都市ガス原料として今後とも着実に導入されていくものと思われるが、石油と熱量等価で硬直的にスライドする価格決定方式や供給条件の硬直性(テイク・オア・ペイ条項)が緩和されない限り、電力における伸びが期待できないことから長期的には供給の伸びが鈍化する可能性が強い。 ④ 水力
今後は中小規模の開発が中心となるが、純国産の非枯渇性のクリーンなエネルギーとして、エネルギーの安定供給の観点から引き続き開発が行われていくものと見込まれる。 ⑤ 地熱
我が国に豊富かつ広範に賦存する純国産エネルギーであり、安定した供給が期待されることから、引き続き開発が進むものと考えられる。 ⑥ 新燃料油、新エネルギー、その他
中長期的な経済性についても十分評価しつつ、計画的かつ重点的、効率的に開発が進められ、太陽エネルギーをはじめとして、その供給は着実に増加していくものと期待される。 ⑦ 石油
省エネルギーの進展及び石油代替エネルギーの開発・導入が一層進むものの、近年見られたような極端な需要の減少傾向は、今後の世界的な景気回復等に伴いほぼ終了するものと見込まれる。 今後は、民生・運輸部門の需要増により、揮発油及び灯軽油等の中間留分の需要は引き続き堅調である一方、C重油の需要は石油代替電源の開発の進展等により引き続き減少するものと見込まれるため、今後とも中間留分への需要シフトは進展していくと考えられ、石油供給量全体としては、ほぼ横ばいないし若干の増加傾向で推移するものと考えられる。 4. 昭和75年度(西暦2000年)のエネルギー需給展望
(1) 不確定要因が数多く存在する中にあって、長期におけるエネルギー需給構造を正確に見通すことは困難であるが、エネルギー政策は、長期的視点に立って着実に推進していかなければならない性格のものであることに鑑み、エネルギー需給の将来の方向を示すものとして昭和75年度のエネルギー需給の展望を行った。 (2) 需給の推計に当たっての基本的な考え方は以下のとおりである。 ① エネルギー需要については、経済の成長に伴う生産額の伸び、国民生活水準の向上により需要が増加する一方、産業構造の変化、省エネルギーの一層の進展等により総じてエネルギー原単位が低下し、全体としては需要量の安定的な増加が見込まれる。 これを需要部門別に見ると次のように見込まれる。 イ 産業部門においては、生産額が伸びる一方、産業構造の知識集約化の一層の進展、省エネルギーの一層の進展に伴い、エネルギー需要はおだやかな増加を示す。 ロ 運輸部門においては、旅客、貨物ともに輸送量の安定的な伸びが見込まれることから、エネルギー需要は、着実に増加する。 ハ 民生部門においては、生活水準の向上に伴うエネルギー消費機器の普及、サービス経済化の進展に伴う業務用床面積の拡大等により、エネルギー需要は堅調に増加する。 ② 引き続き石油代替エネルギーの開発・導入、省エネルギーの推進等の政策努力が講じられることを前提にエネルギー供給は次のような方向で推移すると見込まれる。 イ 国際的な石油需給のタイト化、石油価格の上昇傾向のもとで、石油代替エネルギーの導入が着実に進展する。石油代替エネルギーの中では、石炭及び原子力については、その供給シェアが着実に増大して行くと見込まれる一方、LNGについては経済性が改善されない限り、電力における伸びが期待できないことから、供給の伸びは鈍化するものと考えられる。 ロ 技術開発の成果が逐次実用化されることに伴い、新エネルギーの利用が本格化し、かなりの幅はあるものの供給量の大幅な増大が予想される。 ハ 石油については、西暦2000年においても我が国の国民生活、産業経済を支える最大のエネルギー源として重要な位置を占め続けるが、量的な伸びは微増にとどまり、一次エネルギー供給全体の中での石油のシェアについては、オイルショック以降から現在までの様な急激なテンポではないものの、次第にそのウェイトは低下していくと考えられる。 長期エネルギー需給見通し 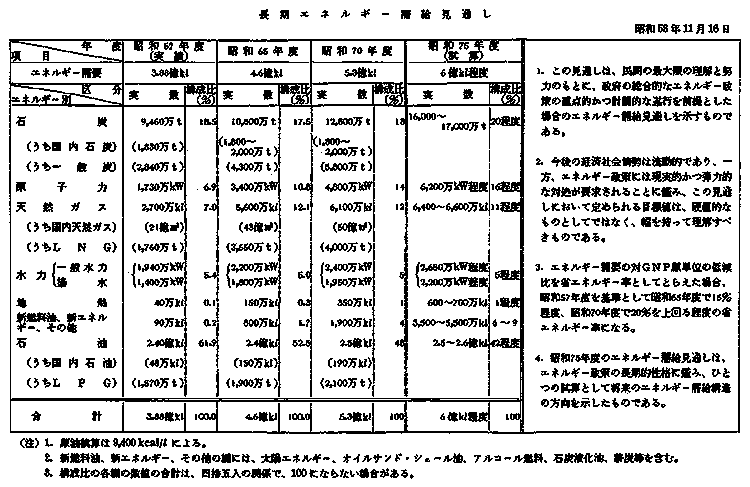 (参考資料1)
エネルギー需要見通し(需要端ベース) 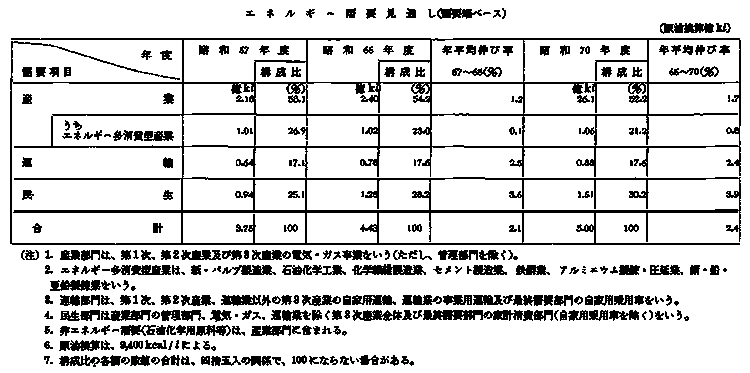 (参考資料2)
エネルギー供給見通し 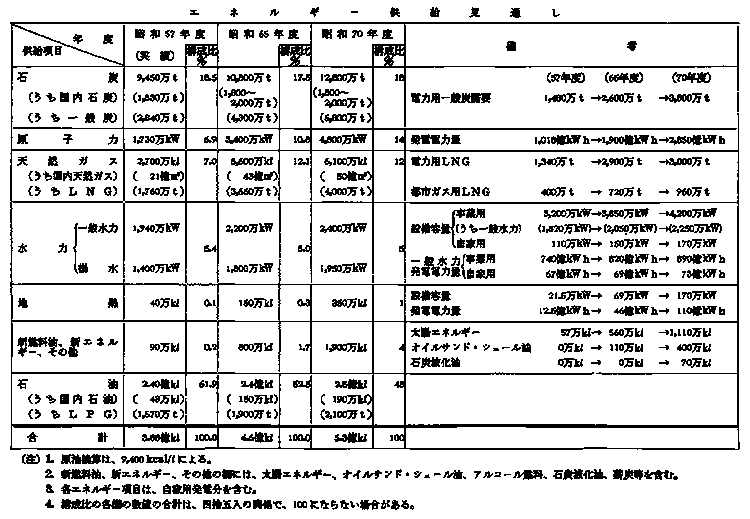 (参考資料3)
エネルギー需給バランス表
昭和57年度 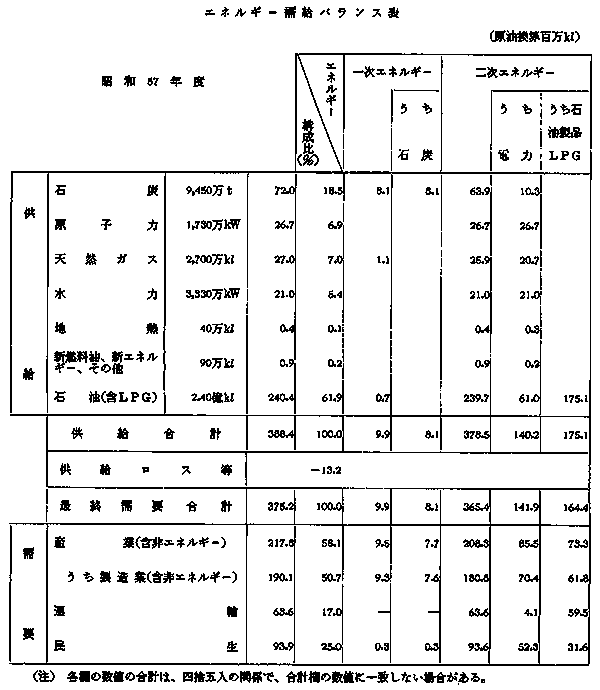 昭和65年度 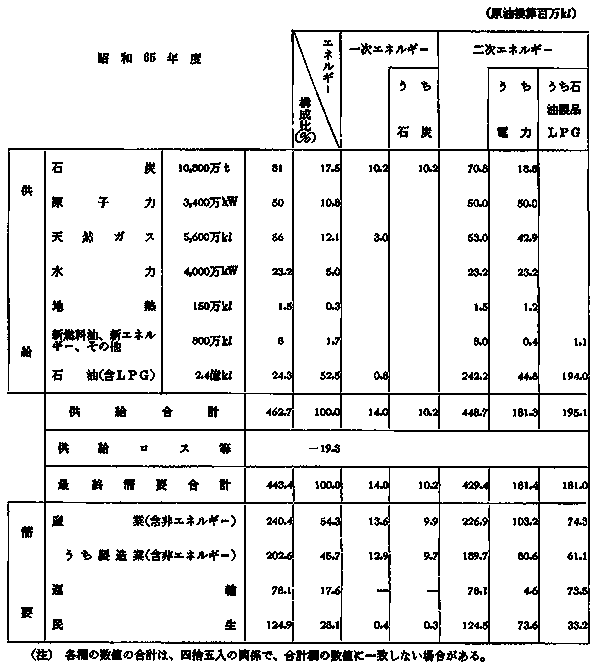 昭和70年度 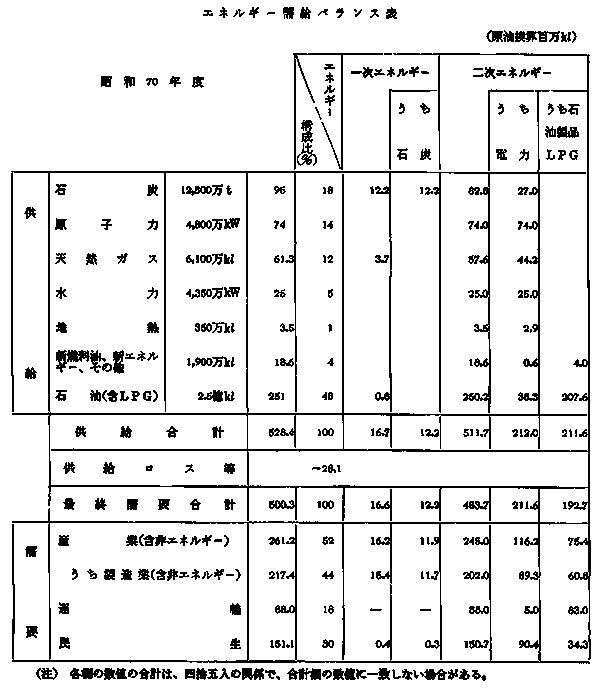 総合エネルギー調査会需給部会委員名簿
総合エネルギー調査会需給部会 企画専門委員会 委員名簿
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前頁 | 目次 | 次頁 |