| 目次 | 次頁 |
|
国際協力と日本の立場 原子力委員会委員
新関 欽哉
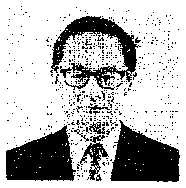 原子力基本法は、わが国における原子力の研究、開発および利用が、平和目的に限られ、その成果を公開し、進んで国際協力に役立てることをもって基本方針としている。 これまで日本は主として先進諸国との協力に重点をおいてきた。だが、これからは、自国の原子力開発のためのセキュリティーという観点に立った先進諸国との国際協力のみならず、開発途上国の原子力開発利用にも積極的に協力する必要がある。 わが国はこれまでも、IAEAの「原子力科学技術に関する研究、開発および訓練のための地域協力協定」(RCA)のワク内でアジア・太平洋地域の国々を対象として主にラジオ・アイソトープ、放射線利用の分野において技術、財政の両面にわたり各種の協力を行ってきた。RI、放射線利用は、開発進上国においても、農業(食品照射、品種改良など)、工業(非破壊検査、各種計測、滅菌など)、医学(診断および治療)等の分野で極めて有益であり、RCAプロジェクトに対する日本の協力は一般に高く評価されている。 しかしながら、最近に至り、これら諸国においても、原子力開発に対する関心が高まり、研究炉を利用しての基礎研究から原子力の安全性、原子力発電所の運転・保守・訓練、緊急時対策、廃棄物処理などに至るまで、わが国の技術協力が期待されるに至った。 わが国としては、こうした開発途上国の要請にこたえ、原子力先進国としての国際的責務を果す必要があるが、その場合は、特に次の二点について考慮を払うべきであろう。 まず第一に、開発途上国における原子力開発利用には種々の段階的な相違があることに注目しなければならない、国によっては、発電用原子炉の運転をすでに開始しているし、また原子力開発が基礎研究とか、RI、放射線利用に限られている国もある。しかし、なかには原子力の導入それ自体が時期尚早とみられる国もあり、この最後のグループが開発途上国の大部分を占めている。 従って、開発途上国に対する原子力協力は、それぞれの国の開発段階に応じて行われなければならない。そのためには、なによりもまず、相手国の要望を知るとともに、インフラストラクチャーの問題をふくめ原子力利用におけるニーズの妥当性を客観的に評価したのち、必要と思われる協力を行うことが適当であろう。 第二の重要な問題として、核拡散防止に対する配慮がある。原子力協力がRI、放射線利用に限られている場合は、技術移転も核不拡散上全く問題にならないが、国際協力が研究炉、発電用機材から、濃縮、再処理などの核燃料サイクルの分野に近づくにつれて核不拡散政策との関連で十分慎重な考慮を払う必要が生じる。 ただし、何が核拡散につながり、何がつながらないかの判断は、国際的に広く受客できる基準によるべきであって、一部の供給国のように国内法または政策によって一方的に国際基準を明らかに上廻る厳しい規制を課すことは、原子力平和利用と核不拡散の両立を計るというINFCEの結論にもとるものである。 開発途上国への協力の場合、その国がNPTに参加しているかどうか、或はIAEAのフルスコープ・セーフガーズを受けているかどうかは重要な判断の基準となるであろう。わが国としては、とくに密接な関係にあり、しかもNPTに加盟しているアジアの近隣諸国に重点をおいて原子力協力を進めてゆくのがよいのではなかろうか。 |
| 目次 | 次頁 |