| 前頁 | 目次 | 次頁 |
|
高レベル放射性物質研究施設(CPF)のホット運転開始 動力炉・核燃料開発事業団
1 はじめに
動力炉・核燃料開発事業団東海事業所における高レベル放射性物質研究施設(CPF:Chemical Processing Facility)は、ホット運転前の準備を終え、A系列(高速炉燃料再処理試験)、B系列(高レベル放射性廃液ガラス固化試験)共にホット運転を開始した。 CPFは、核燃料サイクルのかなめとなる高速炉燃料再処理技術及び高レベル放射性廃液の処理技術の開発に必要な、高レベル放射性物質を取扱うことのできるホットセルを中心とする基礎研究施設であり、53年7月から建設を開始し、内装・試験機器等の設置、総合通水作動試験、ウラン試験を経て、準備を進めてきたものである。 2 施設の概要
本施設は地下1階、地上3階の研究棟及び地上2階の管理棟からなっており、建家面積は床面積約2,800m2、延床面積約7,400m2である。構成は第2図に示す様に、研究棟にはA、B2系列の研究用セル、操作室、サービスエリア等を1階に配置し、さらに2階に実験室、分析室等を、地階には廃液貯槽室、蒸発缶室、使用済燃料ピン及び固化体貯蔵ピット等を配置している。また、管理棟は発電機室、機械室及び居室などから成っている。 研究用セルは、A系列のCA-1、2セルで使用済燃料ピンの受入、貯蔵及び剪断を行い、CA-3、4セルで溶解、抽出及び精製を、さらにCA-5セルで分析を実施する。一方B系列のCB-1セルでは、高レベル実廃液の脱硝・濃縮及びガラス固化を行い、CB-2、3セルでガラス固化体の密封、貯蔵を、さらにCB-4、5セルで試料調整、物性測定を実施する。 3 試験内容
3.1 高速増殖炉燃料再処理試験
57年4月、5月に、高速実験炉「常陽」MK-Ⅰの使用済燃料ピン14本の拠入が行われ、使用済燃料を再処理するに当り、7月に日米両国政府間で共同決定が行われた。そして9月30日に初めての燃料ピン(2本)の剪断を実施し、ホット試験が開始された。 本試験は将来、高速増殖炉において増殖された準国産資源であるプルトニウムを取り出し、そのプルトニウムを利用するという高速増殖炉燃料再処理技術を、自主技術により確立する第一歩である。 このために、今後、本施設において、溶解工程、抽出工程を中心とした下記の各種試験が計画されている。 (1) 燃料溶解性試験
軽水炉燃料に比べて溶解性の良くない使用済混合酸化物燃料(PuO2-UO2)について、燃料組成、製造履歴及び照射履歴の異なる燃料を用い、硝酸濃度や溶解運転モードを変えながら溶解速度、溶解率等の溶解データを取得する。 (2) 燃料溶解残渣性状確認試験
硝酸による燃料溶解の後に、不溶物として溶液中に浮遊し又は沈殿する溶解残渣について、量、性状及び組成を確認し、溶解残渣の除去方法(給液清澄)を検討する。 また、溶解残渣中のプルトニウムの回収のため、硝酸にさらにフッ酸などの他の試薬を加えた溶解残渣の再溶解試験を行い、適切な再溶解方法の検討を行う。 (3) 抽出条件確認試験
軽水炉再処理で実証されているPurex法(湿式再処理)に基づき、高速増殖炉燃料再処理に適合した溶媒抽出フローシートの確証試験を行い、FPの除染性能(DF)、U、Puの回収率、最適運転条件などを検討する。さらに放射線損傷による溶媒劣化の程度、洗浄方法の評価を行う。抽出器としては現在、ミキサーセトラー抽出器が設置されているが、現在計画中の「高速炉燃料再処理試験施設」で採用を予定しているパルスカラム抽出器についても、本施設において、模疑機を用いてホット試験を今後予定している。 (4) プルトニウム電解還元試験
抽出工程の中でUとPuを分離する分配工程で、プルトニウムの還元を化学試薬を用いず、電解法によって還元する技術を確立するために、小型電解還元パルスカラムを設置し、プルトニウム還元、抽出性能、電解条件、FPの影響、および副生ガスについて評価を行う。 (5) オフガス挙動試験
燃料剪断、溶解、給液調整、抽出工程、酸回収工程などの各工程に分散し、放出される揮発性FP(3H、I、Kr、Xe)について、その量的変化を測定し、これらの挙動を評価する。とくにヨウ素について効率的な捕集方法をプロセスの運転上から検討する。また、NOxガスについても発生量の推定及び洗浄効果について検討する。 (6) 材料信頼性試験
耐硝酸または耐フッ酸材料として開発中の新材料に対する実燃料溶解液による信頼性試験を行う。種々の条件の屈曲部や溶接部のテストピースを用いて腐食試験を行い、材料の信頼性を評価する。 3.2 高レベル廃液ガラス固化試験
57年12月上旬に、東海再処理工場から高レベル放射性廃液(約18l、1,400Ci)を搬入し、同月15日からガラス固化技術の基礎試験を開始した。ガラス固化技術は、使用済燃料の再処理に伴い発生する高レベル廃液を安全に処理処分するための技術であり、実廃液の性状評価、脱硝濃縮試験、ガラス溶融試験、オフガス処理試験、固化体評価試験、固化体貯蔵試験等が計画されている。 (1) 実廃液の性状評価
実際の高レベル廃液について放射能強度、組成分析を行い、計算による推定値との比較、評価を行う。 (2) 脱硝濃縮試験
廃液をギ酸により脱硝、濃縮する場合に安定な反応を維持するための操作特性を把握するとともに脱硝時、濃縮時のFP等のDFを把握する。 (3) ガラス溶融試験
脱硝・濃縮後の廃液にガラスフリットを混合し、均一なガラス溶融を行うための、ガラス組成の開発、スラリー供給試験、溶融試験、流出試験等を実施する。 (4) オフガス処理試験
脱硝・濃縮、ガラス溶融時に発生するオフガス中の成分のうち、Ru、NOx、微粉、ヨウ素等の発生量や挙動につき検討するとともに、各処理装置における除去性能を把握する。 (5) 固化体評価試験
ガラス固化体についての均質性、組成、密度等の基礎的な物性の測定及び化学的耐久性、熱的安定性等の固化体の特性測定を行い、ガラスの安定性につき評価する。 (6) 固化体貯蔵試験
固化体貯蔵時のガラスとキャニスタとの両立性、貯蔵時の発熱量、貯蔵時のガラスの健全性につき評価する。 4 成果の反映
4.1 高速増殖炉燃料リサイクル技術
58年2月以降に溶解試験を始め、抽出試験を実施し、PnとUを回収する予定である。引続き、種々の条件の高速増殖炉使用済燃料を用いて高速増殖炉燃料リサイクル工程におけるプロセスデータを収集するとともに、各種のホット試験を行う。これらの成果は、応用試験棟における工学試験、モックアップ試験の成果とともに、現在設計研究を進めている高速炉燃料再処理試験施設に反映してゆく。 「もんじゅ」及び高速実験炉「常陽」の使用済燃料を処理することのできる高速炉燃料再処理試験施設の設計は、昭和50年の設計研究に始まり、予備設計を経て現在概念設計を実施している。現在の計画では、概念設計の後に基本設計(59~60年度)、詳細設計(61~62年度)を経て昭和60年代中期建設・稼動にいたる予定である。 4.2 高レベル廃液ガラス固化技術
58年2月以降に第2回目のガラス固化試験を行い、その後、年間最大10回のガラス固化試験を実施する予定である。これらの試験により、ガラス固化プロセス及び固化体特性を解折・評価し、東海再処理工場の高レベル放射性廃液をガラス固化するガラス固化パイロットプラントの安全審査(58~59年度)、建設(59~61年度)及び実証運転(62年度)に反映させる計画である。 一方、本施設におけるホット試験と併行して、ガラス溶融炉等の工学試験及び全プロセスのモックアップ試験設備により、コールドにおける実証運転技術及び遠隔操作保守技術の確証試験を進め、遂時その成果を、ガラス固化パイロットプラントの設計、建設、運転に反映することとしている。 第1図 CPF外観 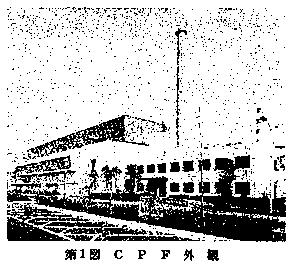 |
|
第2図 CPF1階平面図 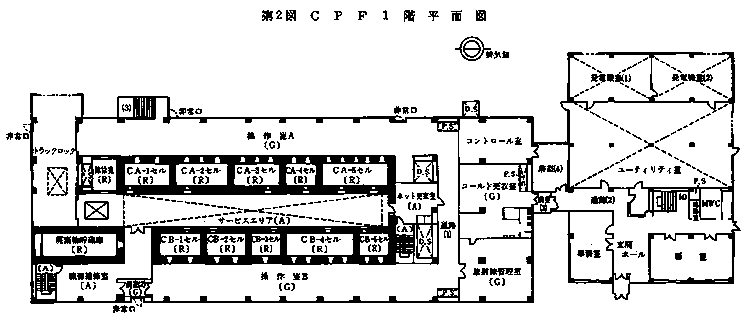 |
|
第3図 「常陽」使用済燃料ピンを剪断中の剪断機 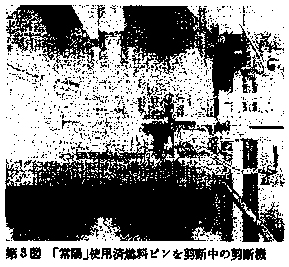 第4図 技術開発の進め方 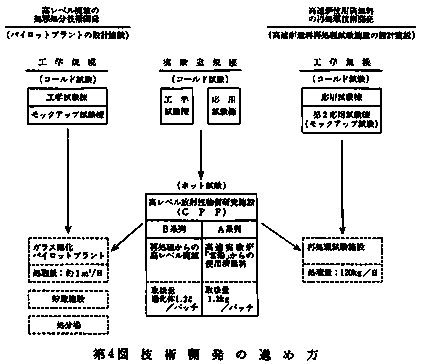 |
| 前頁 | 目次 | 次頁 |