| 前頁 | 目次 | 次頁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
放射性廃棄物対策専門部会報告書 低レベル放射性廃棄物対策について 昭和57年6月4日
原子力委員会放射性廃棄物対策専門部会
昭和57年6月4日
原子力委員会
委員長 中川 一郎殿
放射性廃棄物対策専門部会
部会長 天沼 倞
本専門部会は、昭和54年1月23日付原子力委員会決定に基づき、放射性廃棄物対策について調査審議を行ってきたところであり、このほど低レベル放射性廃棄物の処理処分対策についてとりまとめたので報告いたします。 はじめに
放射性廃棄物を適切に処理処分することは、原子力研究開発利用を推進していく上での重要な課題であり、原子力委員会は、昭和51年10月、「放射性廃棄物対策について」を決定し、放射性廃棄物対策の基本方針を示しているところである。 上記の基本方針に沿って、現在、低レベル放射性廃棄物の海洋処分については、技術的な検討、制度面の整備等の諸準備が行われ、内外関係者の理解を得るための努力がなされているところであり、陸地処分については、固化体からの核種の浸出性、核種の環境における移行等に関する所要の調査研究が行われてきている。 また、この間に、我が国における原子力発電設備容量は、昭和56年度末で23基約1,610万kWの規模に達しており、総発電電力量の約18%を占めるに至っている。これに伴って、原子力発電所等から発生する低レベル放射性廃棄物の量も増加しており、これに対応するための処理技術開発や新しい技術の導入が進められている。 本専門部会は、上記の原子力委員会決定に示されている基本方針及び最近の技術の進展や内外の情勢等を踏まえ、低レベル放射性廃棄物の処理処分対策に関して、調査審議し、ここにとりまとめたので報告する。 本専門部会では、昭和75年度に至る低レベル放射性廃棄物の発生量を予測し、処理、施設貯蔵及び処分の推進方策、極低レベル放射性廃棄物の合理的な処理処分、廃棄の事業制度等の課題について検討を行った。 なお、放射性廃棄物対策は、世界的にも共通の課題であり、国内における研究開発との関連に留意しつつ、今後とも、国際原子力機関(IAEA)における処分に関する指針策定作業、経済協力開発機構原子力機関(OECD/NEA)における情報交換等国際協力に積極的に参加していくものとする。 本報告書における低レベル放射性廃棄物対策については、エネルギー需給見通し、今後の技術の進展、内外の動向等に対応して適宜見直される必要があるが、ここに示された考え方に沿って、関係者間の協議を経て具体的施策が展開されていくことを期待する。 1. 低レベル放射性廃棄物対策の基本的考え方
低レベル放射性廃棄物は、原子力発電所をはじめとして、ウラン燃料加工施設、再処理施設、大型研究施設、RI使用施設等から発生するが、その種類、性状、放射能レベル等は極めて多種多様であり、それぞれに応じて適切な処理処分の方策を採ることが必要である。 低レベル放射性廃棄物対策においては、原子力開発利用の進展に伴って発生する放射性廃棄物の相当部分を占める固体状の放射性廃棄物が当面の課題である。 この固体廃棄物は、放射性核種に応じて、ベータ・ガンマ(β・γ)廃棄物とアルファ(α)廃棄物に分けることができ、その種類や処理の形態に応じて、海洋処分、陸地処分及び地層処分が考えられる。このうち、ベータ・ガンマ廃棄物は、主として原子力発電所から発生するものであり、その処分としては海洋処分及び陸地処分が考えられる。アルファ廃棄物は、主として再処理施設から発生する超ウラン元素を含むいわゆるTRU廃棄物(TRU:Trans-Uranium(超ウラン))及びウラン燃料加工施設等から発生するその他の固体廃棄物に分けることができる。アルファ廃棄物のうち、TRU廃棄物については、地層処分が考えられ、その他の固体廃棄物については、個々の固体廃棄物の特性に応じた取扱いが必要である。 低レベル放射性廃棄物の処理に当たっては、保管、輸送及び最終的な処分までを考慮して、安全の確保、環境の保全等の観点から、放射性廃棄物の発生量の低減、発生した放射性廃棄物の減容及び安定化を可能な限り行うことが重要である。また、低レベル放射性廃棄物の処分に当たっては、放射性廃棄物の特性に応じて人工バリア及び天然バリアにより総合的に安全性を確保することが重要である。 なお、低レベル放射性廃棄物の処理処分対策を円滑に進めるに当たっては、所要の体制、法令等の整備を図るとともに、関係者の理解を得るための施策を講ずる必要がある。 2. 低レベル放射性廃棄物の発生量予測
低レベル放射性廃棄物について今後の対策を検討するに当たっては、その現状を把握するとともに、将来の見通しを踏まえて行うことが重要である。このため、本専門部会では、原子力発電設備容量を昭和65年度4,600万kW、昭和75年度9,000万kWと想定し、また、今後10年程度の間に導入が可能であると考えられる焼却、圧縮、プラスチック固化等の処理技術等を考慮して、昭和75年度に至る低レベル放射性廃棄物の発生量予測を行った。 この結果、低レベル放射性廃棄物は、200lドラム缶にして昭和65年度には約7万本、昭和75年度には約9万本発生するものと予測され、累積では、昭和65年度に約110万本、昭和75年度には約180万本になると予測される。その大部分は、ベータ・ガンマ廃棄物であり、アルファ廃棄物の発生量の累積は、昭和75年度において全体の数パーセント程度と予測される。 また海洋処分の対象になるもの及び陸地処分・地層処分の対象になるものは、それぞれ半分程度と予測される。 図-1 低レベル放射性廃棄物の発生量予測 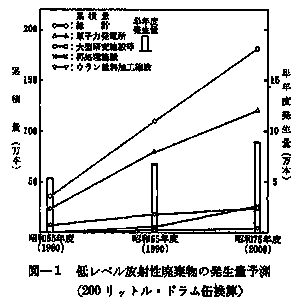 (200リットル・ドラム缶換算)
3. 低レベル放射性廃棄物の処理
3.1 基本的考え方
低レベル放射性廃棄物の処理に当たっては、保管、輸送及び最終的な処分までを考慮して、一般公衆の安全の確保、環境の保全等を図る観点から適切にこれを行うことが重要である。 また、低レベル放射性廃棄物は、各原子力施設から多種多様なものが比較的大量に発生することを考慮すれば、次のような処理を可能な限り行うことが重要である。 ① 放射性廃棄物の発生量の低減:放射性廃棄物の処理、保管、輸送、処分の所要量を低減するため、放射性廃棄物の発生量を低減すること
② 放射性廃棄物の減容:放射性廃棄物の保管、輸送、処分の所要量を低減するため、放射性廃棄物を減容すること
③ 放射性廃棄物の安定化:放射性廃棄物の取扱いを容易にし、保管、輸送、処分に係る安全性を確保するため、放射性廃棄物を固化するなど安定した形態にすること
3.2 処理の現状
原子力施設から発生する低レベル放射性廃棄物のうち、気体状のもの及び液体状のものの一部については、法令で定められた基準値を下回るようにして、環境に放出されている。その他の液体状のもの及び固体状のものについては、セメント固化、アスファルト固化、焼却、圧縮等の処理を行うなどして、施設内に安全に保管されている。 なお、RI使用施設等から発生する放射性廃棄物については、一部これらの施設内に保管されているほか、大部分は(社)日本アイソトープ協会によって集荷、保管され、逐次、日本原子力研究所において、焼却、圧縮等の処理がなされた後、同研究所の施設内に保管されている。 (1) 気体廃棄物
希ガス、ヨウ素等の気体状の放射性廃棄物は、フィルターや、希ガスホールドアップ装置等により法令で定められた基準値を下回るようにして、大気中に放出されている。 なお、これらの処理に使用されたフィルター等は、固体廃棄物となる。 (2) 液体廃棄物
プロセス廃液、イオン交換樹脂の再生廃液、洗濯廃液等の液体状の放射性廃棄物の大部分は、ろ過、蒸発濃縮、イオン交換、凝集沈澱等の処理を行い、その結果濃縮された廃液、凝集沈澱物等については、セメント固化等により固体廃棄物となる。一方、このようにして得られた水については再利用、又は、法令で定められた基準値を下回るようにして、海洋等に放出されている。なお、有機廃液等の一部の液体廃棄物については、施設内に保管されているものもある。 (3) 固体廃棄物
固体状の放射性廃棄物としては、紙、布等の可燃性のもの、ゴム、ガラス、コンクリート、金属等の難燃性、不燃性のもの、フィルター、フィルター・スラッジ、濃縮廃液を固化したもの、使用済のイオン交換樹脂等がある。 これらの固体廃棄物のうち、可燃性のものや難燃性、不燃性のものは、ドラム缶に封入して施設内の貯蔵庫に保管されているが、一部の原子力施設では、圧縮や焼却等の処理を行った後、ドラム缶等の容器に封入し、施設内の貯蔵庫に保管されている。 フィルターはドラム缶等の容器に封入し、また、濃縮廃液はセメント等でドラム缶内に固化し、施設内の貯蔵庫に保管されている。また、フィルター・スラッジ、使用済のイオン交換樹脂、凝集沈澱物の大部分は、施設内の貯蔵タンク等に保管されている。 3.3 今後の進め方
原子力施設から発生する低レベル放射性廃棄物は、今後の原子力利用の進展に伴い、相当な発生量増加が見込まれるので、これに適切に対応するため、発生量の低減、放射性廃棄物の減容、安定化を図るという観点から、処理技術開発の促進及び処理基準の整備を図っていく必要がある。 (1) 処理技術開発の促進
原子力施設における低レベル放射性廃棄物の処理技術としては、濃縮、焼却、圧縮、セメント固化、アスファルト固化等が既に採用されている。また、放射性廃棄物の発生量の低減、減容、安定化の観点から、①放射性物質で汚染されたものの除染、②新しい型式のフィルター、③イオン交換樹脂等の酸消化、焼却、④濃縮廃液、焼却灰等のプラスチック固化、などの技術開発が民間を中心に進められている。 これらの技術開発については、将来の処分方法との関連性を考慮しつつ、民間を中心に一層の促進が図られることを期待するとともに、国としては、これを積極的に支援していく必要があると考える。 (2) 処理基準の整備
現在、種々の形態で原子力施設内に保管されている低レベル放射性廃棄物は、必要に応じ、適切な処理を施した後、最終的には処分する必要がある。 低レベル放射性廃棄物の処分は、海洋処分と陸地処分をあわせて行うことが適当と考えられるが、処分を行うに当たっては、放射性廃棄物の処理の形態並びに海洋処分にあっては処分予定海域付近の状況及び陸地処分にあっては処分施設の健全性や周辺の環境条件等を考慮し、総合的に安全性を確保する必要がある。 処理の形態については、海洋処分に関して、セメント固化体の基準が定められており、今後、アスファルト固化体、プラスチック固化体等の新しい固化体についても、所要の試験研究を推進し、海洋処分、陸地処分に応じて早急に基準化を図る必要がある。 4. 低レベル放射性廃棄物の施設貯蔵
施設貯蔵は、原子力発電所等の敷地外において低レベル放射性廃棄物を集中的に貯蔵するものであり、陸地処分を進めるに当たって一つのオプションとして現実的な対応策である。 施設貯蔵は、既に原子力施設において安全に行われている保管の実績と経験を活かすことにより、技術的に十分実施が可能であると考えられるので、関係者の理解を得てできるだけ早期に開始することを目標とする。 施設貯蔵については、民間において進められる立地、環境調査、建設等今後の諸準備と並行して、国においては、法令、指針等の所要の検討を進めていく必要がある。 なお、施設貯蔵に当たっては、放射性廃棄物中の放射性核種、放射能レベル、放射線量率、形状等を考慮し、分類、管理することが望ましい。 5. 低レベル放射性廃棄物の処分
5.1 海洋処分
5.1.1 基本的考え方及び現状
海洋処分は、安定な固化体とした低レベル放射性廃棄物を深さ4,000メートル以上の海底に処分するものであり、その実施に当たっては、次のような原子力委員会の基本的方針のもとに進められている。 ① 事前に安全評価を行った上で、国の責任のもとに試験的海洋処分を行い、その結果を踏まえて本格的海洋処分を行う。 ② 国際的協調のもとに行う。 ③ 内外の関係者の理解を得て行う。 我が国においては、これまで環境安全評価、法令の整備等の諸準備が行われており、現在、内外関係者の理解を得るための努力が続けられている。 即ち、昭和51年、科学技術庁において環境安全評価がとりまりめられ、昭和54年、原子力安全委員会においてその評価内容ほ妥当であり、安全は十分に確保されることが確認されている。 また、海洋処分の国際的協調に関しては、我が国は、昭和55年「廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約」(ロンドン条約)を批准し、また、昭和56年には、OECD/NEAの「放射性廃棄物の海洋投棄に関する多数国間協議監視制度」に参加した。 更に、海洋処分の実施に関し、内外関係者の理解を得ることについては、昭和51年以来、国内水産関係者等への説明が行われており、また、太平洋関係諸国等に対しても専門家を派遣し、国際的な基準に基づき、安全性を確認の上で海洋処分を行うとの我が国の基本的な考え方、海洋処分の計画の内容等について説明が行われている。 5.1.2 海洋処分の進め方
このように海洋処分実施のための諸準備が進められてきているところであるが、できるだけ早い時期に試験的海洋処分が実施できるよう、今後とも、国内的には水産業界等の理解を得るため、なお一層説明の努力を重ねるとともに、対外的にも、あらゆる機会をとらえ、関係諸国等の理解を得るよう努めていく必要がある。 5.2 陸地処分
5.2.1 基本的考え方
陸地処分に当たっては、低レベル放射性廃棄物の特性に応じて固化体や処分施設等の人工バリア及び土壌や地層という天然バリアにより総合的に安全性を確保できるようその処分方式を決定することが必要である。 処分方式としては、トレンチ、ピット、構造物又は地下空洞内への処分が考えられる。 今後、これらの処分方式について検討を行い、その安全性を確保し、処分に移行するものとするが、処分を行った後も、必要に応じ環境モニタリング等が行えるよう措置し、一般公衆の安全の確保、環境の保全に配慮しつつ、順次、管理の軽減を図っていくことが考えられる。 5.2.2 陸地処分の進め方
(1) 安全評価手法の整備
陸地処分を進めるに当たっては、処分による低レベル放射性廃棄物の一般公衆に与える影響を評価し、安全性を確認するための安全評価手法の整備を行う必要がある。 この安全評価手法は種々の基礎データ及びそのデータを用いて放射性核種の環境移行から一般公衆の被曝までを評価できる安全評価モデルから成り立っている。 これらに関する試験研究は、これまで(財)原子力環境整備センター、日本原子力研究所を中心として行われてきており、基礎データについては、固化体からの核種の短期浸出性、土壌における核種の移行等主として核種の挙動に関するものが得られている。今後、これらのデータに加えて、核種の長期浸出性、土壌の環境条件の変化に対する核種の移行、処分施設の構造材等人工バリアの健全性等に関するデータの蓄積を図る必要がある。 一方、安全評価モデルについては、種々の環境における放射性核種移行モデル、人間の被曝線量の評価モデル等放射性核種の環境移行から一般公衆の被曝までを評価できる総合安全評価の実施に必要な個々のモデルが得られている。今後は、個々の安全評価モデルと今後得られるデータを用いた解析による結果と、解析条件を模擬したシミュレーション試験の結果を比較するなどして、安全評価モデルの改良を行う必要がある。 以上のように、安全評価手法については、基礎的なデータ及び個々の安全評価モデルにより基本的なものは得られているが、今後、上で述べたようにデータの蓄積と個々のモデルの改良を行い、精度良い総合安全評価を行う手法を開発していくものとする。 なお、このような試験研究の実施に当たっては、実験室におけるコールド及びホット試験並びに野外におけるコールド試験を組み合わせて行うことが効率的である。 (2) 処分施設に関する法令、指針の整備
陸地処分の円滑な実施を図るため、今後の処分の本格化に対応して処分の体制の整備を図るとともに、処分に関する法令及び処分施設の安全審査に際し、統一的な観点からの評価が可能となるよう陸地処分施設の設置に関する指針の整備が重要であり、国において、我が国の各種指針、諸外国の指針等を参考にしつつ、これを進める必要がある。 (3) 処分の実施
陸地処分の実施に当たっては、民間において立地、環境調査等を進めるとともに、処分施設の安全評価を行う必要がある。その後、当該施設において低レベル放射性廃棄物の搬入、収納、埋戻しに至る一連の処分技術を実証するため、試験的に処分を実施し、引き続き本格的な処分に移行するものとする。 6. TRU廃棄物対策
6.1 基本的考え方
再処理工場、混合酸化物燃料加工施設等から発生するTRU廃棄物については、現在、その発生量は限られているが、今後、民間における再処理工場の運転、プルトニウム燃料利用の本格化等により発生量の増加が見込まれることから、TRU廃棄物の処理処分対策の推進が必要である。 TRU廃棄物は、長半減期の放射性核種が含まれており、長期間の隔離を必要とするという点で高レベル放射性廃棄物と類似性があるが、遮蔽が容易で発熱量も少ないこと、放射性廃棄物の種類が多く、その性状が多様であること等の相異点も有している。このため、TRU廃棄物の処理に当たっては、第3章に述べたように、放射性廃棄物の発生量の低減、減容、安定化の諸点を配慮するとともに、処分に当たっては、高レベル放射性廃棄物と同様の長期間にわたる隔離を目標とした地層処分を行う必要があると考えられる。 6.2 技術開発の現状と今後の進め方
TRU廃棄物の処理については、現在、動力炉・核燃料開発事業団において、その減容、安定化の観点から可燃物を対象とする酸消化法、金属廃棄物の溶融法、焼却灰その他の不燃物等を対象とするマイクロ波溶融法等の技術開発が行われている。 今後は、これらの技術開発を一層推進するとともに、大型機材等の除染、解体技術、有用核種の回収技術、TRU廃棄物とベータ・ガンマ廃棄物との区分管理、処理の基準化等についても、調査研究を進める必要がある。 TRU廃棄物の処分については、高レベル放射性廃棄物に関する研究開発によって対応できる部分もあると考えられるが、TRU廃棄物の処理方法が高レベル放射性廃棄物の場合と異なることから、固化体の特性、処分環境下での放射性核種移行等TRU廃棄物に特有の課題について所要の研究開発を行う必要がある。 7. その他
7.1 陸地処分関連施設の立地促進
陸地処分関連施設の立地に関する関係者の合意の形成については、基本的に設置者が主体となって行うべきであるが、国としても立地手続の明確化を図るとともに、関係省庁、地方公共団体等との密接な連繋により当該施設の必要性、安全性等に関し、その理解を得るための努力を重ねることが重要である。また、当該施設の立地の促進が、原子力発電施設設置の円滑化に資することを考慮し、いわゆる電源三法(発電用施設周辺地域整備法、電源開発促進税法及び電源開発促進対策特別会計法)の活用を図り、広報対策、地域振興策等を講じていく必要がある。 なお、このような陸地処分関連施設については、我が国では事例がなく、今後、これらの立地を円滑に進めるため、海外において実際に行われている陸地処分等の例も参考にしつつ、我が国に適した施設の具体例を明らかにしていくことが必要と考えられる。 7.2 極低レベル放射性廃棄物の合理的な処理処分
原子力施設から発生する固体状の放射性廃棄物のなかには、そもそも放射能で汚染されていないもの及び放射能による汚染の程度が極めて低いいわゆる極低レベル放射性廃棄物も含まれている。 放射性廃棄物の処理処分は、その放射能レベルに応じて適切に行うことが重要であり、極低レベル放射性廃棄物は、放射能で汚染されていないものと同等に取り扱うなど合理的な処理処分を行う必要がある。 このため、これまでに実施された国内での調査研究の成果、海外での実施状況等を踏まえ、合理的に処分できる放射能レベルの設定、設定した放射能レベルの確認方法、具体的な処分方式、処分の実施体制等を十分検討し、所要の法令、体制の整備等を図る必要がある。特に、将来、原子力施設の解体に伴って大量の廃棄物が発生すると考えられることから、その合理的な処理処分は極めて重要な課題である。 7.3 廃棄の事業制度
低レベル放射性廃棄物を処理処分するに当たっては、それぞれの原子力事業のもつ特性を踏まえ、効率的に行うことが必要である。 RI使用施設等から発生する低レベル放射性廃棄物については、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律において、放射性廃棄物を業として廃棄しようとする者(廃棄業者)が規定されており、廃棄業者により放射性廃棄物の集荷、貯蔵及び処理が実施されている。今後、RI利用の拡大に伴い、放射性廃棄物の発生量の増加等に対応するため、これらを共同して処理する体制の拡充を図る必要がある。 原子力発電所、核燃料加工施設等から発生する低レベル放射性廃棄物については、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(原子炉等規制法)において、その処理処分は各原子力事業者が行うこととされている。しかし、核燃料加工事業等については、放射性廃棄物をそれぞれの施設内で処理することが適切でない場合もあることから、放射性廃棄物を共同して処理することが必要であると考えられる。 更に、今後、低レベル放射性廃棄物の試験的海洋処分の実施、陸地処分の研究開発を経て、処分が本格化することが見込まれる。 以上のような低レベル放射性廃棄物の共同処理の進展、処分の本格化に対応するため、これらの放射性廃棄物の集荷、貯蔵、処理及び処分に係る所要の体制を整備するとともに、原子炉等規制法における廃棄業者の位置付け等所要の法制整備を図る必要がある。 7.4 低レベル放射性廃棄物の輸送
我が国における新燃料、使用済燃料等の放射性物質の輸送は、IAEAの放射性物質安全輸送規則に基づいて整備された輸送に関する諸規則により安全に実施されてきており、既に十分な経験が積み重ねられている。 低レベル放射性廃棄物の輸送についても、基本的にこれらの輸送と同等に実施できるものであり、安全性については問題ないと考えられる。しかしながら、低レベル放射性廃棄物は一度に大量のものが輸送されると考えられるので、輸送の効率化を図るため、輸送システム等について検討する必要がある。 なお、上記IAEAの規則は、放射性物質の輸送をめぐる最近の動向を踏まえ、現在、改訂作業中であり、我が国も同作業に貢献しているが、本規則を参考にして我が国の輸送規制が行われていることから、この動向にも十分注目しておく必要がある。 放射性廃棄物対策専門部会構成員
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前頁 | 目次 | 次頁 |
