| 前頁 | 目次 | 次頁 | ||||||||||||||||||||
|
省エネルギーに関する世論調査 昭和57年1月
(総理府)
内閣総理大臣官房広報室
Ⅰ 調査の概要
Ⅱ 調査結果の概要 1. 省エネルギーについての認識
(1) 省エネルギーのための暖房温度(室温18度以下)
冬場に快適だと感ずる部屋の温度は何度ぐらいだと思うかを聞いたところ、「20度くらい」29%、「18度くらい」16%が1・2位を占めている。 これを55年11月調査結果と比べると、あまり違いはみられない。(表1)
表1 快適だと感ずる室内の暖房温度 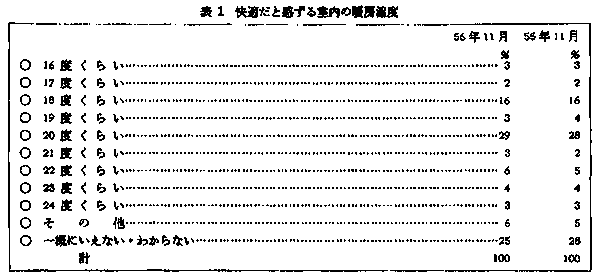 政府が提唱している省エネルギーのための室内の暖房温度のめやすは何度以下と思うかをきいたところ、「18度以下」と正確に答えた者は37%で、55年11月調査結果と比べてみても変化はなく、性別でみると女性より男性に多い。また、年齢別では、20歳台が45%と最も多く、高年齢層になるに従って減少している。(表2)
表2 省エネルギーのための室内の暖房温度の周知(何度と思うか) 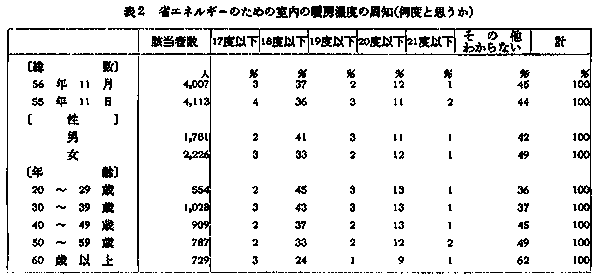 省エネルギー暖房温度(18度以下)の周知(何度と思うか)と快適だと感ずる温度との相関でみると、快適だと感ずる温度を「18度くらい」と答えた者に省エネルギー暖房温度を「18度以下」と答えた者が最も多い。(表3)
表3 省エネルギー暖房温度の周知と快適だと感ずる温度 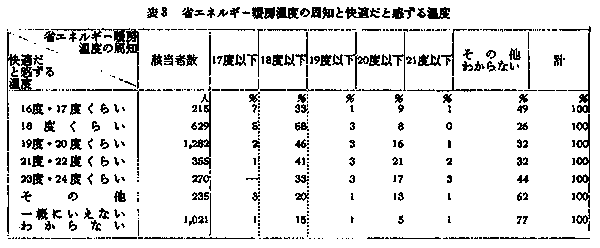 政府が提唱している省エネルギー暖房温度の「18度以下」に室温を保つよう心がけることは困難だと思うかどうかきいたところ、「困難ではない」とする者は61%で、「困難である」とする者の28%を大きく上回っている。これを快適だと感ずる温度との相関でみると、快適だと感ずる温度が低くなるほど、「困難ではない」とする者が多くなっている。(表4)
表4 省エネルギー暖房温度(18度以下)を保つよう心がけることは困難か 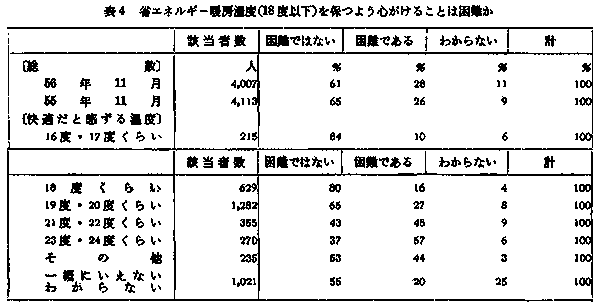 また、省エネルギー暖房温度を18度以下に保つよう心がけることは「困難ではない」とする者(2,448人)に、その対応策をきいたところ、「厚手の着衣又は一枚余分に着る」(27%)、「こたつやかいろなどで部分的に暖をとる」(21%)、「窓などにカーテンなどをして熱を逃さないようにする」(14%)が上位を占めている。 一方、「困難である」とする者(1,104人)にその理由をきいたところ、「暖かさになれてしまったから」(13%)、「老人や子供がいるから」(8%)、「温度調整が面倒だから」(5%)が主なものとなっている。(複数回答)(表5)
表5 省エネルギー暖房温度を保つための対応策など 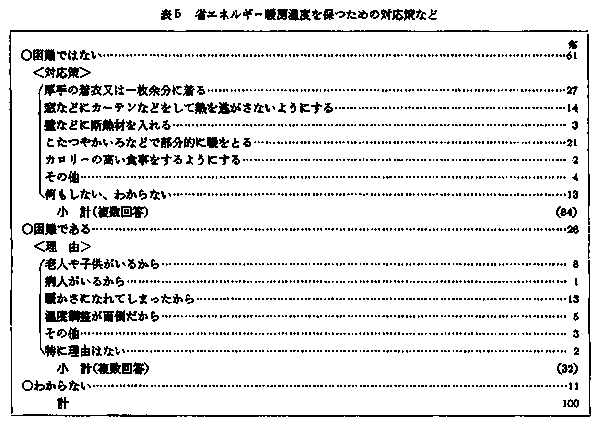 (2) エネルギーの節約意識
日常生活の中で、省エネルギーのために心がけていることとしては「不必要な電灯はこまめに消す」(79%)、「テレビ、ラジオのつけっぱなしをやめたり、見る時間をへらす」(62%)、「部屋の暖房は、暖房しすぎないように心がける」(42%)、「こたつの下に毛布などを敷く」(36%)、「入浴は家族全員が間をあけないようにすませる」(36%)が上位にあげられている。 これを55年11月調査結果と比べても、大きな変化はみられない。(複数回答)(表6)
表6 日常生活における省エネルギー 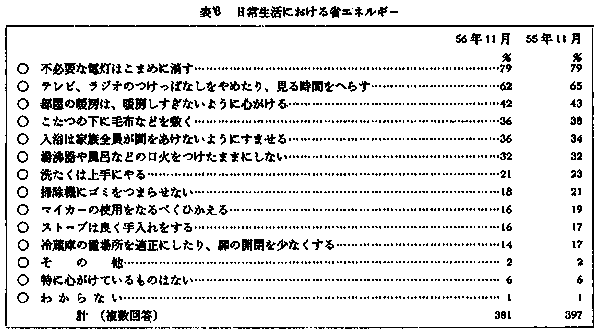 次に家庭以外で節約できると思うことは何かについてみると、「広告灯、ネオンサインなどの点灯時間を短縮する」(48%)、「マイカー通勤を自粛する」(35%)、「ビルの冷暖房を規制する」(33%)、「テレビの放送時間を短縮する」(32%)、「風俗営業や深夜飲食店営業の閉店時刻をくり上げる」(31%)などが上位にあげられている。 これを55年11月調査結果と比べると、ほぼ同様の傾向を示している。(複数回答)(表7)
表7 家庭以外でできる省エネルギー 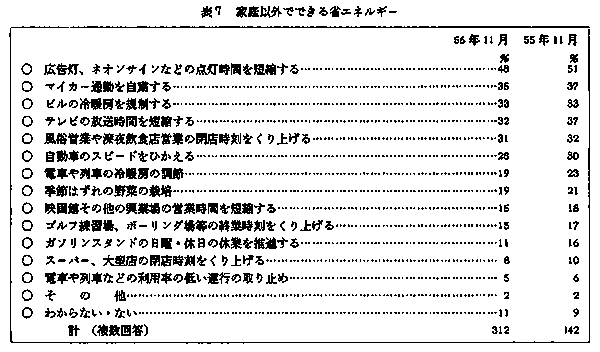 (3) マイカー使用の自粛と経済的なガソリンの使用
マイカーをどのような目的に使うことが多いかについては、「通勤」(20%)、「営業用(商売・セールスなど)」(14%)、「買物」(13%)、「レジャー」(8%)の順となっている。 都市規模別にみると、マイカーを「通勤」に使用する者は、都市部より町村に多く、「営業用」、「買物」に使用する者は、都市規模が小さくなるに従い多く、また「レジャー」に使用する者は、都市規模が大きくなるに従い多くなっている。(表8)
表8 マイカー使用の目的 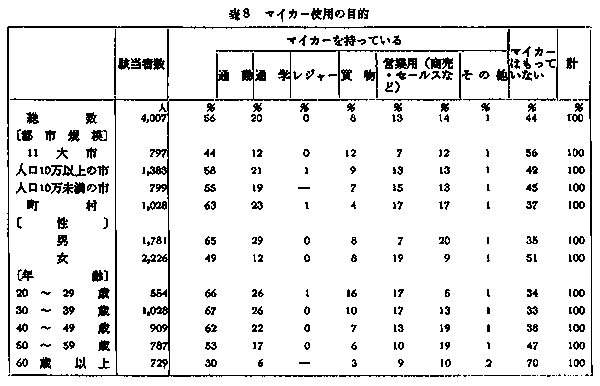 マイカーを持っている者(2,247人)にマイカー使用の理由をきいたところ、「仕事上必要だから」28%、「目的の場所まで直接行けるから」27%が1・2位を占め、以下、「バスや電車の運行本数が少ないので」(11%)、「手で運びきれない大きな荷物を運べるので」(10%)、「通勤・通学など時間が短縮されるので」(10%)などの順となっている。(表9)
表9 マイカー使用の理由 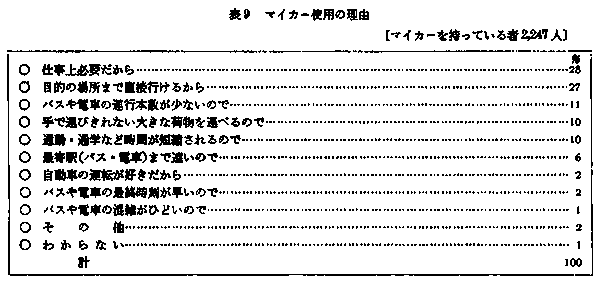 さらに、省エネルギーのために、マイカー使用を自粛しているかをきいた結果をみると、「自粛している」者が54%、「自粛していない」者が30%となっている。(表10)
表10 省エネルギーのためにマイカー使用を自粛しているか 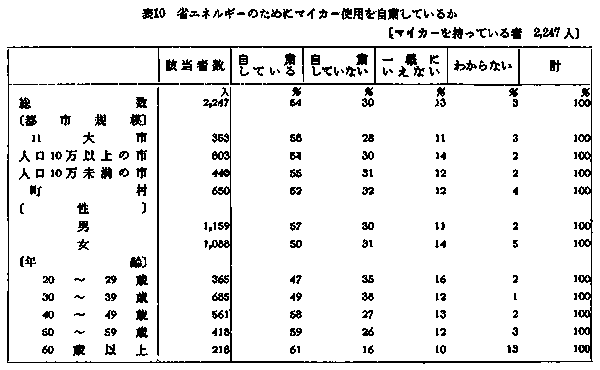 「自粛していない」、「一概にいえない」、「わからない」と答えた者(1,036人)に、これから先、自粛するつもりがあるかきいたところ、「自粛するつもりだ」27%、「自粛するつもりはない」30%、「一概にいえない」29%と意見がわかれている。(表11)
表11 これから先自粛するつもりがあるか 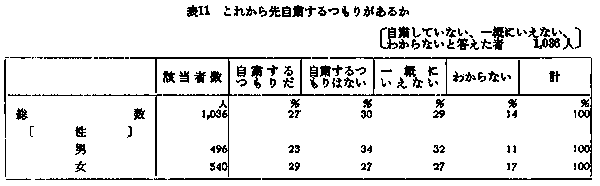 マイカーを持っている者(2,247人)に急発進や急加速をさけることなどによって、ガソリンを経済的に使うよう気をつけているかをきいたところ、「気をつけている」が61%を占めている。 性別では、「気をつけている」が男性70%で女性の51%を大きく上回っている。(表12)
表12 ガソリンを経済的に使うよう気をつけているか 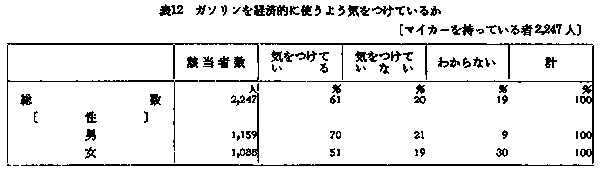 (4) エネルギー多量消費財購入時のエネルギー節約意識
次に、電気やガソリンなどを多量に消費するもの(テレビ、冷蔵庫、自動車など)を購入するときに、エネルギー節約の面について考えるかをきいたところ、「考える」とする者80%(「十分考える」38%+「少しは考える」42%)、「考えない」とする者18%(「あまり考えない」16%+「まったく考えない」2%)で、エネルギー節約についての意識は高い。(表13)
表13 電気やガソリンなどを多量に消費するものを購入するときにエネルギー節約の面についても考えるか 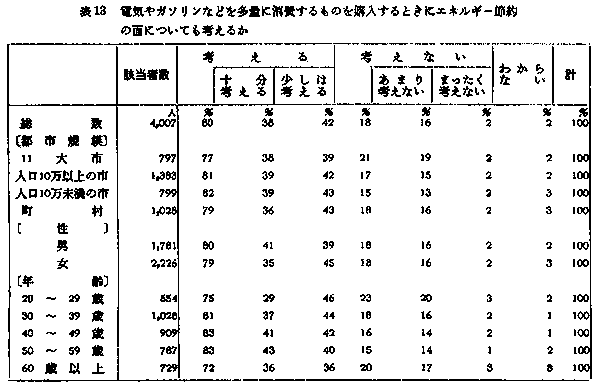 2. 将来のエネルギーについて
(1) エネルギー消費の在り方
今後のエネルギーの在り方については、「生活水準の向上にともなうエネルギー消費の増加はやむを得ないが、できるだけ増加はおさえるようにすべきである」40%、「節約に努めるとともに、足りないエネルギーは新たに開発すべきである」32%が上位を占め、次いで「生活水準をきりつめても、エネルギーの消費は増やすべきではない」(8%)、「必要なエネルギー源は新たに開発すべきである」(8%)の順となっている。(表14)
表14 今後のエネルギーの在り方 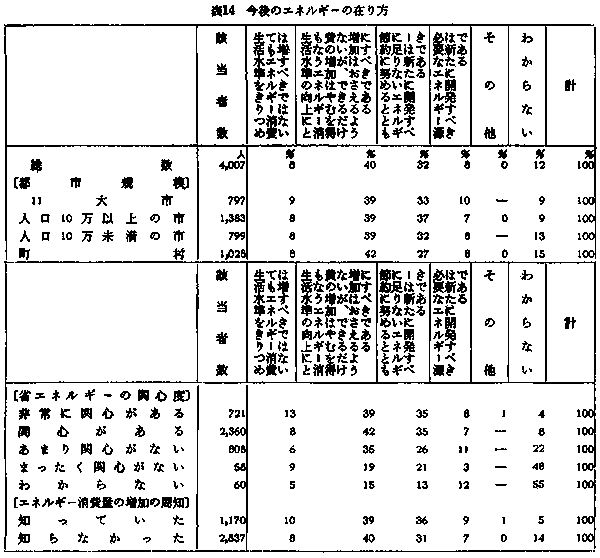 次に、生活水準を向上させるとともにエネルギー節約を図るためにはいまの生活の仕方を変える必要があると思うかどうかについてきいたところ、「思う」(43%)、「思わない」(41%)とほぼ同数となっている。 これを性別にみると、「思う」は男性46%、女性40%で、男性が女性をやや上回っている。(表15)
表15 生活水準を向上させるとともに、エネルギー節約を図るために生活の仕方を変える必要があるか 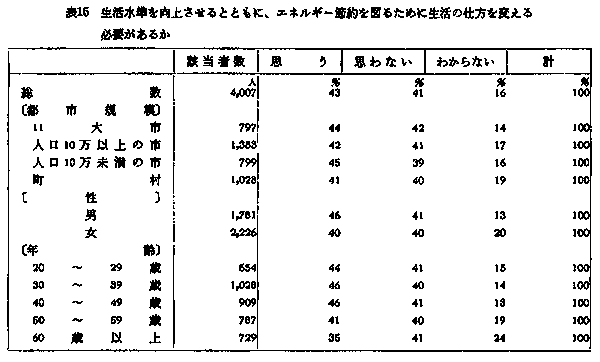 (2) エネルギー消費量の変化
わが国のエネルギー消費量が、この15年間で約2倍半になったことを知っているかどうかについては、「知らない」(71%)が「知っている」(29%)を大きく上回っている。 また、今後10年間に自分の家庭のエネルギーの消費量が、現在より増えると思うか減ると思うかについてきいたところ、「増える」と思う者が49%と約5割を占め、「変わらない」と思う者は35%、「減る」と思う者は5%となっている。(表16)
表16 エネルギー消費量の変化 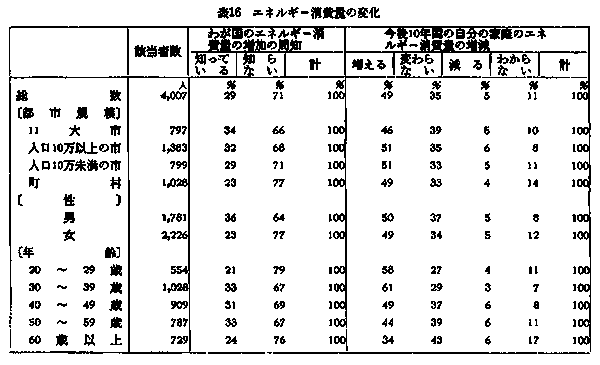 さらに、わが国の石油依存度を昭和65年度までに50%に下げられると思うかどうかきいたところ、「50%に下げるのは困難だが、下げなくてはならない」という者が40%と最も多く、次いで「50%に下げるのは困難であり、下げられない」が19%、「50%に下げるのは困難ではなく、下げられる」が13%、「50%に下げるのは困難であり、下げる必要はない」が2%の順となっている。(表17)
表17 石油依存度を昭和65年度までに50%に下げられると思うかどうか 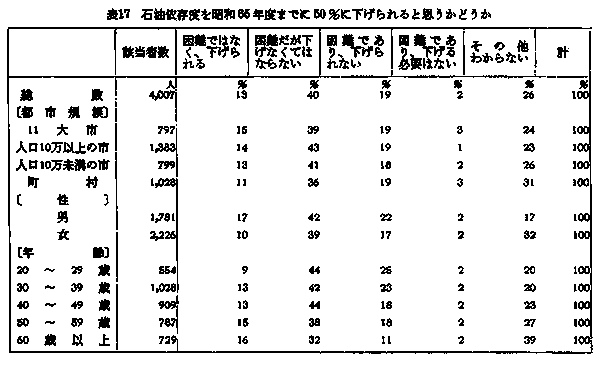 (3) 新しいエネルギーについて
見たり、聞いたりしたことがある新しいエネルギーは、「太陽熱発電」が84%と最も多く、次いで「風力発電」54%、「地熱発電」49%、「太陽光発電(太陽電池)」47%、「石炭液化」35%、「波力発電」32%、「石炭ガス化」31%などとなっている。 次に、10年後に代替エネルギーとして実用化されていると思うものをきいた結果、「太陽熱発電」が54%、「太陽光発電(太陽電池)」20%、「地熱発電」15%、「石炭液化」12%などとなっている。 なお、「わからない」と答えた者は29%を占めている。(複数回答)(表18)
表18 新しいエネルギーについて 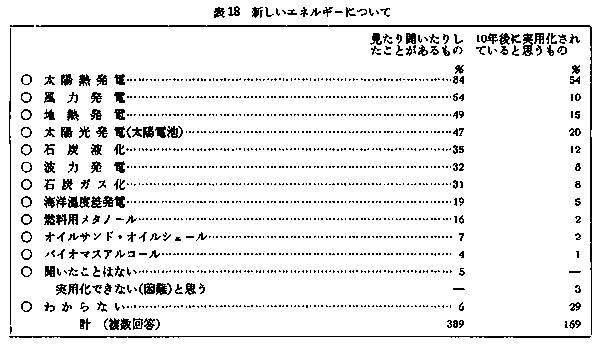 (4) 現在及び将来における主力発電
エネルギーとしての電力について、現在どの発電が電力の主力になっていると思うかきいたところ、「石油による火力発電」60%、「水力発電」19%、「原子力発電」7%などとなっている。 また、今後はどの発電が電力の主力になると思うかについては、「原子力発電」50%、「火力発電」14%、「太陽熱発電」11%などの順となっている。 これを55年2月、55年11月の調査結果と比べると、「原子力発電が電力の主力となると思う」者は漸増(33%→47%→50%)し、「太陽熱発電が電力の主力となると思う」者は漸減(28%→18%→11%)している。なお、「火力発電が電力の主力となると思う」、「水力発電が電力の主力となると思う」者については、大きな変化は見られない。(表19)
表19 現在及び将来における主力発電はどの発電と思うか 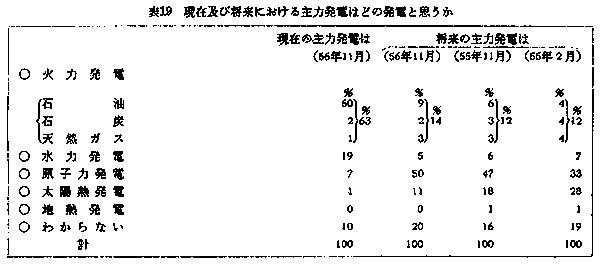 (5) 総電力量に占める原子力発電の今後の割合
現在、総電力量の約16%が原子力によって発電されているが、今後この割合をどのようにしたらよいと思うかきいた結果、「多くしたほうがよい」は40%、「現在程度でよい」25%、「減らしたほうがよい」10%となっている。なお、「わからない」が25%となっている。 これを55年11月調査結果と比べると、「多くしたほうがよい」が38%→40%「現在程度でよい」が28%→25%、「減らしたほうがよい」が5%→10%、「わからない」が29%→25%となっている。(表20)
表20 総電力量に占める原子力発電の今後の割合 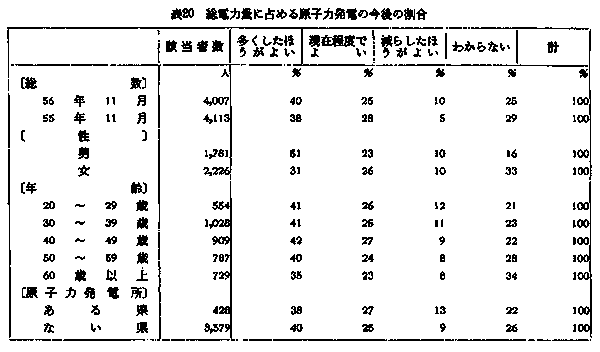 (6) 原子力発電所に対する不安感
原子力発電所に対する不安感については、「心配(不安)に思うことがある」とする者は59%であり、「心配(不安)に思うことはない」とする者(41%)を上回っている。これを55年11月調査結果と比べると、「心配(不安)に思うことがある」とする者は56%→59%、「心配(不安)に思うことはない」とする者は44%→41%となっている。さらに、原子力発電所のある県・ない県別でみると、不安感については原子力発電所の存否による差異はみられない。(表21)
表21 原子力発電所に対する不安感 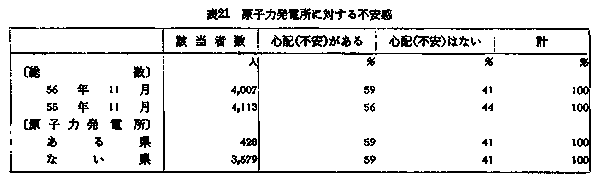 原子力発電所に対する不安感がある者(2,358人)に対して、それはどのようなことかきいたところ、「放射線(能)が出ることについて」が57%と最も多く、次いで「万一の故障や事故について」が37%、「原子炉やその他の施設の安全性について」が22%、「廃棄物の保管や処理・処分について」が17%、「地震などの自然災害に対する安全性について」が8%などとなっている。 55年11月調査結果と比べると、「放射線(能)が出ることについて」では54%が57%、「万一の故障や事故について」では29%が37%、「原子炉やその他の施設の安全性について」では13%が22%、「廃棄物の保管や処理・処分などについて」では13%が17%とそれぞれ増加している。 原子力発電所のある県・ない県別では、「放射線(能)が出ること」はある県(53%)よりない県(58%)が多く、「万一の故障や事故について」はない県(36%)よりある県(44%)が多くなっている。(複数回答)(表22)
表22 原子力発電所に対する不安感の内容 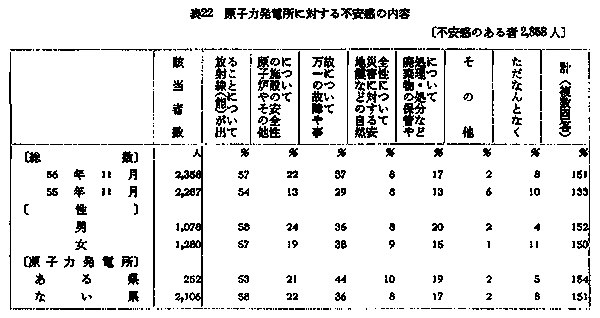 (7) 原子力発電所の安全対策など
原子力発電所の原子炉やその関連施設について安全対策が十分行われていると思うかどうかをみると、「十分行われていると思う」(27%)より「そうは思わない」(45%)が上回っている。しかし、「わからない」も28%と少なくない。55年11月調査結果と比べると「十分行われていると思う」が52%から27%へと大きく減少した。 原子力発電所のある県・ない県別では、「十分行われていると思う」がいずれも27%と同数であるのに比べ、「そうは思わない」では「ない県」45%に対し、「ある県」50%と多くなっている。(表23)
表23 原子力発電所の安全対策 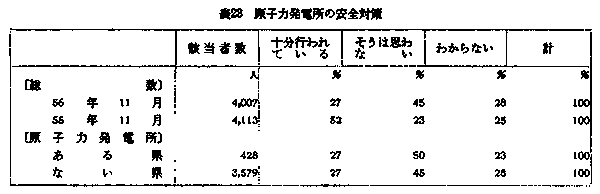 私たちが、自然界から1年間に約100ミリレムの放射線を受けていることを知っているかをきいたところ、「知っている」者が21%と少なく、「知らない」者が79%となっている。 性別でみると、「知っている」は、男性が28%に対し、女性は15%と少ない。(表24-1)
表24-1 人体が自然界から1年間に約100ミリレムの放射線を受けていることの 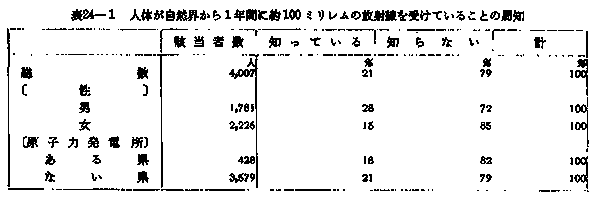 周知
次に、胸のX線(レントゲン)間接撮影の1回分は、約100ミリレムの放射線を受けることを知っているかをきいたところ、「知っている」者が31%で、「知らない」者が69%となっている。 性別にみると、「知っている」は男性が36%に対し、女性は27%となっている。(表24-2)
表24-2 胸のX線(レントゲン)間接撮影1回分約100ミリレムの放射線を受けることの周知 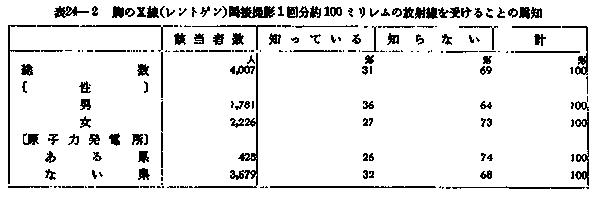 さらに原子力発電所によって受ける放射線の量はその周辺で1年間に5ミリレム以下になるように管理されていることを知っているかきいたところ、「知っている」者が11%と少なく、「知らない」者が89%となっている。 性別でみると、「知っている」は男性が16%に対し、女性は7%と少ない。(表24-3)
表24-3 原子力発電所によって受ける放射線量の管理の周知 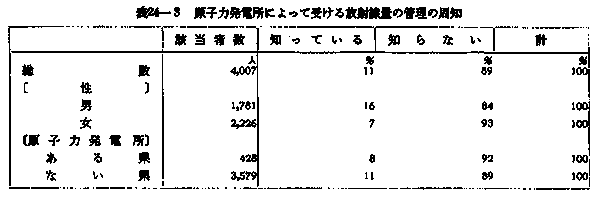 原子力発電について知りたいことは、「放射線(能)の人や環境への影響」が42%、「原子力発電所の安全対策」が40%、「放射性廃棄物の処理・処分対策」が32%と上位3位を占め、以下「原子力発電所の故障等の実状」18%、「原子力発電の必要性」13%、「原爆と原子力発電の違い」12%、「原子力発電所のしくみ」12%、「放射線の種類としくみ」9%となっている。(複数回答)(表25)
表25 原子力発電について知りたい事柄 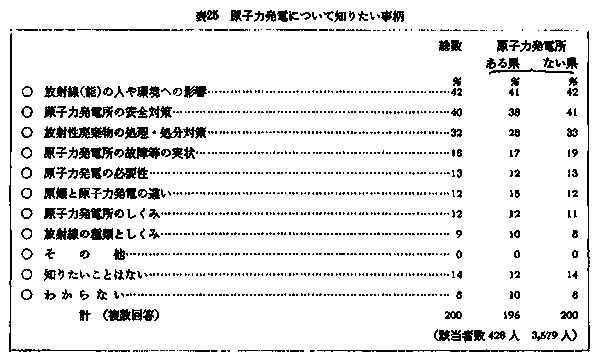 原子力発電を円滑に進めるにはどのようなことが重要だと思うかについては「原子力発電施設の安全対策を徹底させること」が49%と約5割を占め、以下「原子力発電の安全性や必要性を周知させること」19%、「公開ヒアリング(公聴会)などで地元住民の意見を十分きくこと」11%、「地元に開発利益が還元されるような措置を講じること」5%となっている。 原子力発電所のある県・ない県別にみると、「原子力発電施設の安全対策を徹底させること」では「ある県」の46%に対し、「ない県」が50%、「公開ヒアリング(公聴会)などで地元住民の意見を十分聞くこと」では「ない県」の10%に対し、「ある県」が15%となり、わずかな差が見られる。(表26)
表26 原子力発電を円滑に進めるために重要なこと 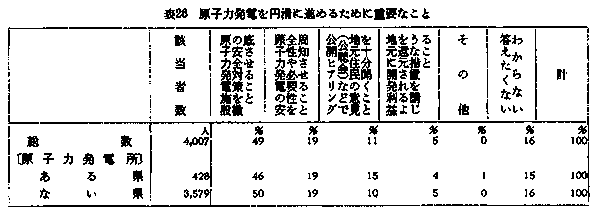 3. エネルギー対策
政府のエネルギー政策として特に力を入れてほしいと思うことは「太陽熱(光)、石炭液化などの新エネルギーの技術開発」50%、「石油供給の確保」28%が1・2位を占め、以下「原子力発電の推進」19%、「石炭、LNG(液化天然ガス)などの資源確保や利用の促進」17%、「国、地方公共団体、企業などでの省エネルギー運動の推進」14%、「家庭内での省エネルギー運動の推進」10%となっている。(複数回答)(表27)
表27 エネルギー政策として特に力を入れてほしいこと 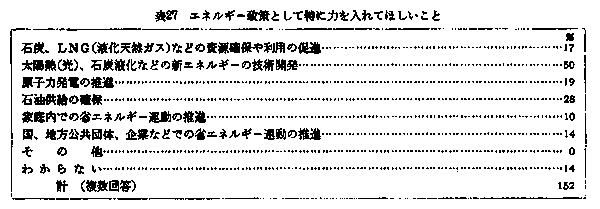 仮に、石油危機が再び起こった場合、政府にどのようなことをしてもらいたいと思うかを見ると、「便乗値上げ、買い占めの防止」、「石油危機による物価の上昇防止、インフレ防止などの対策」がともに28%と最も多く、以下「家庭などで使う灯油、ガソリンの量的な確保」(18%)、「公共料金の値上げなどの抑制」(12%)、「石油事情
の実態や供給見通しの情報提供」(7%)の順となっている。(表28)
表28 仮に石油危機が再び起こった場合に政府に望む対応策 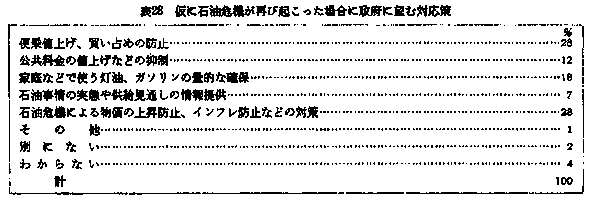 「省エネルギー月間」が設けられていることの周知については、「知っている」者が39%、「知らない」者が61%となっている。(表29)
表29 省エネルギー月間の周知 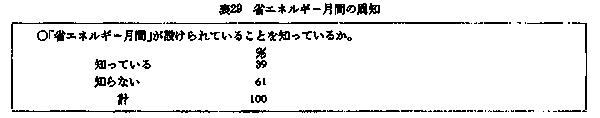 Ⅲ 調査票 省エネルギーに関する世論調査
昭和56年11月
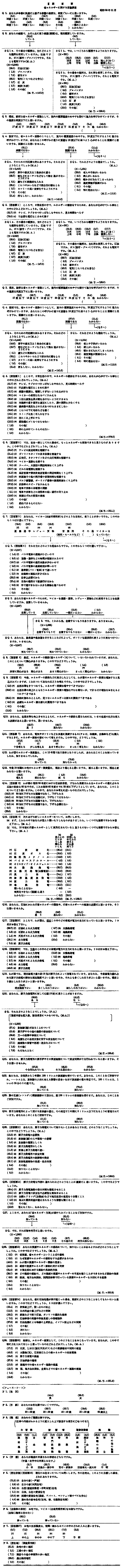 | ||||||||||||||||||||
| 前頁 | 目次 | 次頁 |