| 目次 | 次頁 |
|
原子力委員長代理所感 原子力委員会委員長代理
向坊 隆
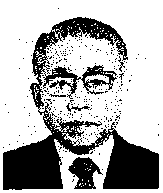 我が国の原子力発電は、昨年一年間で総発電電力量の約16%に達しており、これは日本の原子力開発が軌道にのってきたことを示すと同時に、エネルギー供給源として社会の中で無視できないものとなり、安全確保が一層重要になってきたと共に、供給上の責任が明確になってきたことを意味する。 原子力開発の25年間をふり返ってみると、初めのうちは原子力の良い点のみ強調され、大きな期待だけがあったように思われる。しかし、実用化が進むにつれ、さまざまな難問が生じてきた。世界的に見ても、社会情勢、石油事情等の複雑な変化により、原子力に対する力の入れ方には波があったが、エネルギー資源に乏しく、石油依存度の高い我が国としては将来の安定的エネルギー供給者としての原子力への期待は依然としてかわらず、困難な問題を解決しながらも、前進していかなければならないという運命にある。 エネルギーの安定な供給は、我が国経済社会の発展にとって大きな課題であるが、他方、エネルギー特に石油の多消費が、環境や社会に悪い影響や大きなひずみを与えることのないようにしなければならない。そのために、省エネルギーをはじめ、各種の代替エネルギーの開発が行なわれているが、そのなかでも石炭の無公害利用と並んで、原子力の健全な発達は最も大きな期待を担うものとなっている。この情勢は、当分続くものと思われる。 他の資源同様、ウラン資源にも不足する我が国では、ウランをできるだけ効率的に活用するとともにプルトニウムも積極的に利用するという基本方針を持っている。このためには高速増殖炉の実用化が理想であるが、それまでは、プルトニウムを軽水炉や新型転換炉など熱中性子炉で利用していくのを課題としており、それに向って努力が続けられている。 また多くの産業のなかでもエネルギー産業は根幹をなすものであり、できるだけ自立体制を確立することが望ましい。ウラン資源の輸入を行うとしても、開発輸入として、諸外国での探鉱の段階から協力するなどの努力が大切といえる。同時に国内での核燃料サイクルの完結が、これからの大きな課題で、この確立はかねてよりの基本方針である。 これらを進めるに当って、今後も日本が念頭におくべき三つの条件がある。そのひとつは、原子力を利用する宿命としての放射能による被害を人類に与えないこと。これは施設の安全性から放射性廃棄物の最終処分までにわたって第一に守るべきことである。 二つめとしては原子力利用を平和目的に厳しく限定することである。国際原子力機関(IAEA)が行っている保障措置あるいは世界の核拡散防止の努力に協力することと平和利用とを両立、共存させる道を諸外国とも協力して確立することである。 三つめは、大規模な基幹産業の一つである原子力産業は、社会に与える影響と責任を考える必要がある。それには立地も含めて地域の発展との調和をはかることが大切であり、巨大産業として社会に及ぼす影響についての責任を自覚することである。 原子力は国内の要求に対してだけでなく、人類すべての福祉に貢献するような発展が望ましい。そのためにも国際協力の推進が今後の課題となっている。 |
| 目次 | 次頁 |