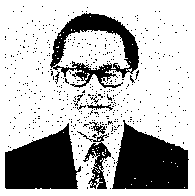| 目次 | 次頁 |
|
国際協力について 原子力委員会委員
新関 欽哉
わが国が原子力の研究開発利用をすすめてゆくうえにおいて今後ますます国際協力を積極的に行う必要があると思う。 原子力基本法第2条には「原子力の研究開発利用は平和目的に限り民主的な運営の下に自主的にこれを行うものとし、その成果を公開し、進んで国際協力に資するものとする」とあり、自主、民主、公開のいわゆる三原則と並んで国際協力が原子力推進上の一つの大きな柱であることを明示している。 従来わが国において国際協力というと、ともすれば、米英仏などからの先進技術の獲得とみられがちであった。だが、最近では、高速炉などの開発における国際協力も取沙汰されるようになった。これには原子力経費の増大にともなう資金分担の必要ということもからんでいるように思われるが、その場合はあくまで自主技術開路線のなかで明確に位置づけられた形での国際協力を行う覚悟が必要となろう。 いまや原子力先進国の一つとして自他ともにゆるすようになったわが国の国際協力としては、安全問題は別として、核拡散防止問題、開発途上国への技術援助などの問題がある。 まず、核不拡散の問題については、原子力基本法にうたわれているようにみずからの原子力開発利用を厳に平和目的に限って行うばかりでなく、世界における核不拡散レジームの確立にわが国とても積極的に貢献すべきであろう。そのためには、保障措置のより一層の効率化をめざしてIAEAとの協力を引きつづいて行うばかりでなく、機能的かつ実効的な国内保障措置制度の確立にむかって努力すべきであろう。核物質防護も拡散防止上の重要課題であり、さしあたっては核物質防護国際条約への参加を具体化する必要があると思う。 一方、いわゆるポスト・インフセの課題として核不拡散のための新国際秩序を作りあげようとする動きがあるが、わが国としては、なかんづく、これからのプルトニウム時代にそなえて、国際プルトニウム貯蔵(IPS)構想の実現のために積極的に寄与することが肝要である。反面、核不拡散のための規制を強めるだけでは核拡散防止条約(NPT)第4条で保証された原子力平和利用の権利が阻害される懸念があり、同時に原子力資材の供給が不当に妨げられることがないという国際的保証をえることが不可欠であり、そのため目下同じくIAEAが中心となって進められている供給保証委員会(CAS)が成果をえるようわが国としてもその検討に積極的に参加すべきであろう。 開発途上国に対する協力については、放射線やアイソトープの利用の分野で行っており、これを順次ほかの分野にも拡げてゆくのがよい。その意味でわが国がIAEAの地域協力協定(RCA)プロジェクトにおいて主導的役割を演じ、その努力が高く評価されていることはまことによろこばしい。今後は、さしあたり開発途上国の原子力関係人材の養成により多くの力をかす必要があると思っている。 |
| 目次 | 次頁 |