| 前頁 | 目次 | 次頁 |
|
高速増殖炉開発の現状 動力炉・核燃料開発事業団
1. はじめに
動燃事業団における高速増殖炉の開発は、動燃事業団の動力炉開発業務に関する基本方針に沿って、プルトニウムとウランの混合酸化物系燃料を用いるナトリウム冷却型高速増殖炉を開発することを目標としてすすめられている。 第1の目標である高速実験炉「常陽」は、昭和52年4月24日、熱出力50MWで初臨界を達成し、その後順調に各種性能試験を行い、現在、燃出力75MWで運転中である。 第2の目標の高速増殖原型炉「もんじゅ」は、設計を固めるとともに建設候補地である福井県敦賀市白木地区についての国および県による環境審査が終了し、福井県の了解を得て原子炉設置許可申請書を科学技術庁へ提出した。 これらの高速炉の開発に必要な研究開発は、大洗工学センターをはじめ、適切な機関に委託して実施し、その成果はそれぞれの設計、建設、運転に反映されている。 以下、それぞれについて現状を記す。 2. 高速実験炉「常陽」
「常陽」は、わが国初のナトリウム冷却型高速増殖炉で、原型炉の開発に必要な技術的経験を得るとともに、完成後は高速増殖炉用の燃料材料の照射施設として利用することを目的に大洗工学センターに建設された。 プラントの熱出力は、100MWを最終目標としているが、わが国初の高速増殖炉であることから第1期熱出力を50MWとして、昭和45年2月に設置許可を得て3月から建設を開始、昭和52年4月24日初臨界を達成した。 その後順調に各種性能試験を実施し、昭和53年9月から50MW定格運転を2サイクル行った。 昭和54年7月には出力上昇試験を行って初期炉心(MK-1)最大出力の75MWを達成、その後第1回定期検査に入り、昭和52年2月1日に75MW使用前検査および第1回定期検査に合格、引続き75MW定格運転第1サイクルを開始、8月末に第3サイクルまでの運転を無事終了して第2回定期検査を実施している。 75MW第3サイクルまでの運転実績は、炉心中心燃料の集合体平均燃焼度26,650MWD/T、延運転時間9,249時間、積算熱出力430,500MWHとなっている。 この間、照射後試験のため取出した燃料集合体を検査したところ、燃料被覆管表面に熱流力振動に起因すると思われる軽微な擦り痕が見つかったが、詳細に評価検討した結果少くなくとも第3サイクルまでの運転に支障がないとの結論に達し運転を継続した。現在、第3サイクル終了後23,000MWD/Tの燃焼度の燃料集合体を取出し、詳細な照射後試験を行っている。 今後の計画としては、昭和56年初めから75MW第4サイクル運転を行い、第6サイクルまで運転し、初期炉心の最終目標である炉心中心燃料の燃焼度42,000MWD/Tを達成して、第2の目標である照射炉心(MK-Ⅱ)への移行計画をすすめ、昭和57年度末にMK-Ⅱ最大熱出力100MWを達成、昭和58年度半ばからMK-Ⅱ定格運転を開始する予定である。 3. 高速増殖原型炉「もんじゅ」
「もんじゅ」は、わが国において高速増殖炉を昭和60年代に実用化するために、実験炉に引続いて電気出力30万KW程度の原型炉を自主開発するためのもので、その設計、建設、運転を通して高速増殖炉発電所としての所期の性能、信頼性、安全性を実証して、将来の実用炉が経済的に成り立つ見通しを得ることを目的として開発がすすめられている。 表1 高速実験炉および高速増殖炉原型炉の主要目 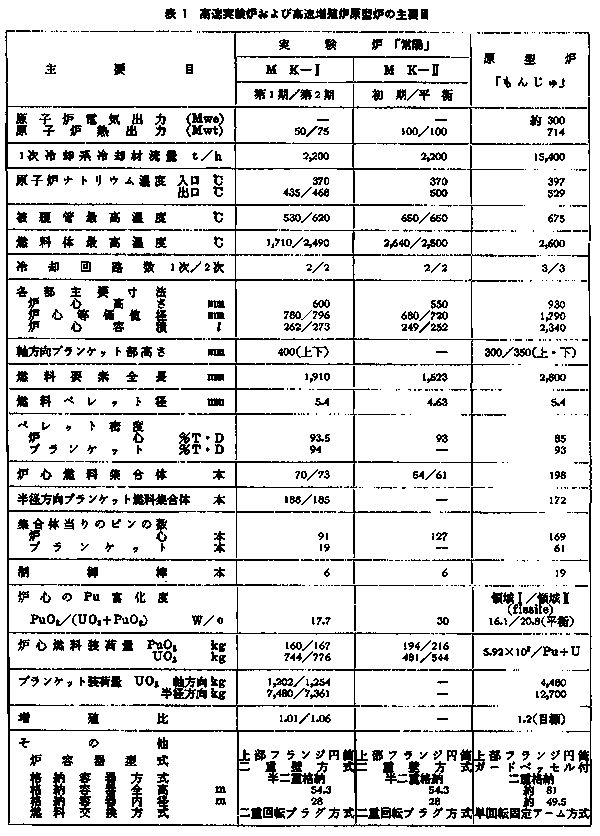 高速増殖炉原型炉「もんじゅ」完成予想図 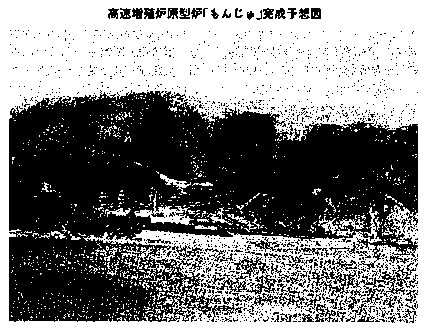 「もんじゅ」の設計は、昭和43年度に予備設計を開始して以来、昭和44~47年度に概念設計、昭和48~51年度に調整設計、昭和52~55年度に製作準備設計と継続して実施し、基準の変更など最近の状況変化をとり入れて、耐震設計、安全設計の評価および安全審査に必要な種々の解析を行い、設計の調整・詳細化をはかり安全審査、製作設計に備えている。 「もんじゅ」の建設候補地である福井県敦賀市白木地区の環境審査については、事前調査の結果原子炉の設置に支障のないことを確認して環境影響調査書をとりまとめ、昭和53年8月通商産業省、科学技術庁および福井県に提出し審査が開始された。その後、自然公園法にかかわる審査の過程で変更させられた事項を変更書として昭和54年12月および昭和55年4月に提出して審査が継続され、7月に資源エネルギー庁の環境審査顧問会の審査が終了し、直ちに国における各関係省庁との調整および福井県との調整がすすめられている。 自然公園法に関しては、昭和54年11月に福井県の自然環境保全審議会自然公園部会での審議が始まり、植生保全の観点から一部レイアウトの変更を行い、昭和55年3月に自然環境保全上の指摘事項を付して「もんじゅ」計画を承認する旨知事に答申された。 安全審査に関して科学技術庁は、新型炉であるため県知事の建設同意に先立って、国として安全性についての見解を示す必要性があると考えている。したがって、原子炉設置許可申請書の提出を受けて行政庁審査を開始し、終了後地元関係者に安全性に関する説明を行って充分な理解を得た後、知事の建設同意を得、電源開発調整審議会に相当する関係省庁の了解を得て原子力安全委員会によるダブルチェックを行い、設計許可を出す方針である旨昭和55年9月知事に申し入れた。この申し入れに対し、12月9日に県知事の安全審査に入ることについての同意が得られたので、10日に同申請書を科学技術庁に提出し受理された。 「もんじゅ」の建設に対する電力業界の協力体制は、昭和55年2月に9電力、日本原子力発電、電源開発が日本原子力発電を通して協力することになり、現在、設計および見積仕様書の技術審査について、軽水炉の経験から検討が行われている。 メーカーの体制については、昭和55年4月に「もんじゅ」およびそれに続く実証炉の開発のため、高速炉エンジニヤリング(株)が設立されている。 4. 高速増殖炉実証炉
高速増殖炉の実用化のためには、「もんじゅ」に引続き、実用規模の発電プラント技術を実証し、あわせてその経済性の見通しを得るために実証炉の建設が必要である。 実証炉は実用規模の発電プラントとほぼ同程度の出力(100万kwe~150万kwe)と機能を有するものである。実証炉はその建設、運転経験を確実に後続の実用炉の建設、運転に反映させるとともに、わが国のエネルギー資源需給における危機的状況を救済し、国際競争力を育成するためには、「もんじゅ」の臨界後1年程度で建設に着手する必要があると考えられている。 実証炉の研究開発は、「常陽」「もんじゅ」の自主開発によって得られた成果を有効に活用することは当然のことながら、主として機器の大型化、信頼性の向上、安全技術の追求、新しい設計概念の実証等のためのものがあり、リードタイムを考慮して、より長期的な観点に立って、早期から着実にすすめる必要がある。 動燃事業団では、昭和50年度から大型炉予備設計を開始、昭和52年度から実証炉予備設計を行って、実証炉として選択可能な種々のプラント概念および主要機器型式などの比較検討を実施した。昭和54年度からはわが国の実証炉プラントとして適切な概念および型式などを選定するための実証炉概念設計を開始、「もんじゅ」プラント概念および技術を外挿した設計研究をすすめている。 また、他よりも先行して行っている研究開発として炉物理研究があり、昭和52年度から大型炉特性解析、大型炉実験計画の検討、炉心安全解析などをすすめている。一方、国際協力として昭和53年度からANLにおいて日米共同の大型炉心モックアップ実験を実施した。 5. 研究開発
高速増殖炉は新型動力炉として最も秀れた特徴をもっているが、プルトニウム燃料を使用すること、冷却材にナトリウムを用い、500℃以上の高温で運転することなどこれまであまり経験のない工学的な問題があり、自主開発を行うには広い分野にわたる研究開発が必要である。 当初「常陽」のために必要な研究開発から着手し、性能、信頼性、安全性を確認してその成果を「常陽」の設計、建設、運転に反映したが、全く予期しなかったような特異な技術的問題点はほとんど経験されていない。 現在、「常陽」に関する研究開発は照射炉心のためのものを残してほとんど終了し、「もんじゅ」のために必要なものを実施している。 「もんじゅ」のための研究開発は、既存の技術および「常陽」の開発に関して得られた技術をできるだけ活用しながら、「もんじゅ」プラントの自主開発に必要な試験や解析を「もんじゅ」のスケジュールに沿ってすすめ、「もんじゅ」の設計に適宜反映してきたが、現在、安全審査および工事認可のために必要な事項を重点的にすすめている。その主要なものは以下のとおりである。 炉物理については、イギリスのZEBRA炉で行った「もんじゅ」炉心の完全模擬臨界実験に引続き、原研の高速炉臨界実験装置(FCA)で部分模擬臨界実験と解析を行うとともに、炉心解析法の開発、遮蔽実験とコード開発などを実施し、確証された炉心設計データを提供している。 構造機器に関しては、重要機器である制御棒駆動機構、燃料交換機、1次系主循環ポンプについては実機と同条件でナトリウム中モックアップ試験を実施し、その機能、信頼性を確認し、安全審査で説明し得るデータを得ているが、引続き耐久性、耐震性などに関する試験を行っている。炉内構造物、回転プラグ、中間熱交換器などについては「常陽」の成果を活用しながら、縮尺モデルまたは部分モデルにより各種試験を行い、性能、信頼性を確認している。また、バックアップ炉停止機構、供用期間中検査装置など「常陽」にない機器については、新たに試作して各種試験を実施し、作動性、信頼性を確めている。 図1 高速増殖炉開発計画 55.10.1 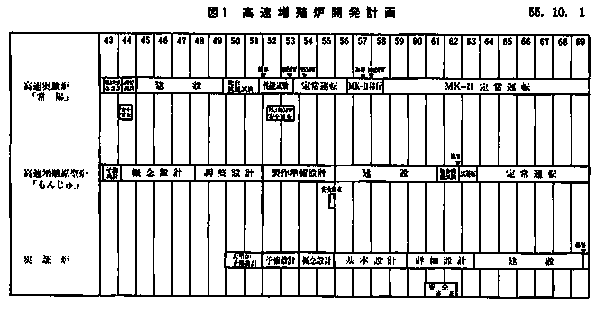 蒸気発生器は、「もんじゅ」で初めて製作使用する機器であるため、1MWの小型蒸気発生器に引続き、50MW蒸気発生器を製作して定常状態および過渡状態における各種性能試験を継続しているが、順調に試験がすすみ、2号機の運転実績は9,500時間に達している。 燃料については、燃料ピン、集合体部材、燃料集合体の数次にわたる試作を行い、それらを用いて流動試験、強度試験、照射試験を行って健全性を確認し燃料設計、安全審査に必要なデータを蓄積している。 構造材料については、「もんじゅ」ではナトリウム温度が500℃を越える高温で運転されるため、構造材料に対する熱応力とクリープ変形が重要となるので、これに対応する合理的な設計法として、高温構造設計法の確立をはかるとともに、高温における材料の許容応力データを集積するため、大気中、ナトリウム中および照射効果を考慮した構造材料試験を実施している。 安全性に関しては、「もんじゅ」の安全設計および安全審査に資するため、炉心の安全性、構造物の安全性、周辺環境に対する安全性などについて、各種試験、解析、評価を行っているが、特に炉心の安全性については、国際協力により反応度事故模擬炉内試験(CABRI)、大規模炉内安全性試験(TREAT/SLSF)を行っている。 その他、実用可能な検出器を含む計測系および回路系の開発、動持性解析、ナトリウム取扱上の工学的諸問題の究明なども「もんじゅ」のスケジュールに沿ってすすめている。 6. おわりに
動燃事業団発足以来13年余り経過し、高速増殖炉の開発は最盛期にある。「常陽」は、熱出力75MWで順調に運転中であり、いよいよ「もんじゅ」の安全審査を受けて着工し、全力をあげて「もんじゅ」の建設に当らなければならない時期である。 わが国のエネルギーの自立と安定供給を推進するためには、石油代替エネルギーの主役として、高速増殖炉の早期実用化が必要であり、そのためには「もんじゅ」に続く実証炉、初期実用炉の開発計画も遅滞なくすすめなければならない。 |
| 前頁 | 目次 | 次頁 |