| 前頁 | 目次 | 次頁 | ||||||||
|
低レベル放射性廃棄物試験投棄について 昭和55年8月
原子力安全局
1. 低レベル廃棄物の現状
(1) 発生量(昭和54年末現在、200lドラム缶本数)
全体約26万本
うち原発約17万本
(2) 増加率 年間5~6万本
2. 原子力委員会の基本方針(昭和51年10月)
低レベル放射性固体廃棄物対策については、処分方法として、海洋処分と陸地処分をあわせて行う。このため、事前に安全性を評価し、試験的処分を実施することとする。 3.陸地処分対策
(1) 陸地処分の研究
① 浅層処分(秋田県で模擬廃棄物による実験を実施)
② 坑内処分(国内の休廃止鉱山を調査)
(2) 廃棄物減容の対策
可燃物焼却炉の導入
圧縮処理の研究(54年原子力平和利用委託費)等
4. 海洋処分対策
(1) 試験投棄
① 昭和56年度投棄実施、その後2~3年間にわたり海洋調査を実施する。
② 投棄量500キュリー
(セメント固化体で1万本程度)
(2) 本格投棄 試験投棄後実施
いずれも水産界の了解を得たうえで実施する。 処分候補海域の位置 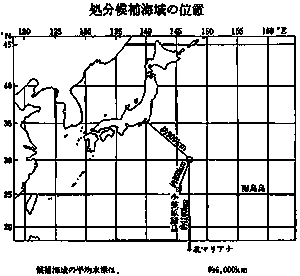 5. 投棄の手続
① 安全評価の実施(54年11月安全委員会ダブルチェック完了)
② 投棄海域の告示
③ OECD/NEA海洋投棄監視機構への参加及び事前通告(1年前、3か月前)
国際的安全評価、NEA代理人の監視
④ 原子炉等規制法に基づく国の確認
6. 法令の整備状況
昭和53年 原子炉等規制法の「廃棄」に関する規定を整備
昭和55年 海洋投棄規制条約(ロンドン条約)の批准に伴う原子炉等規制法等の改正法案は第91国会で成立
また、同国会でロンドン条約の批准も承認され、現在批准のための事務手続きが進められている。
7. 安全評価
(1) 科学技術庁
昭和50年から51年にかけて実施(51年8月安全評価報告書)
(2) 原子力安全委員会
昭和54年3月から放射性廃棄物安全技術専門部会でダブルチェックを実施し、54年11月科学技術庁の安全評価をオーソライズ
(なお、51年から53年にかけては、原子力委員会で検討を進めてきた。)
① 仮定
投棄物(セメント固化体)中の放射性物質は投棄物の海底着低後直ちに全量(試験投棄の場合500キュリー、本格投棄の場合毎年10万キュリー)が海水中に溶出すると仮定
② 結果
魚の摂取等による被ばくの増加量(全身、年間)
試験的海洋処分 0.00001ミリレム/年
本格的海洋処分 0.02ミリレム/年
(参考)
8. 水産界と折衝経緯
昭和51年11月 大日本水産会を窓口として関係団体に対し、海洋投棄の計画等を説明
昭和53年7月 同上
昭和54年4月 海洋投棄規制条約実施法案を説明、海洋投棄の実施については関係団体に対し個別に説明することに決定
昭和54年11月~55年2月 かつお、まぐろ漁業及び底びき網漁業等の業種別組合9業種23団体に対して試験的海洋処分の内容、安全評価の概要について説明
昭和55年7月 全漁連に対し、他の団体と同様の説明を実施、全漁連では本件の取扱いについて現在検討中
以上をもって主要関係団体に対する個別説明は一通り完了した。 9. 今後の折衝方針
水産業界の全体の理解を得るための方法については水産庁と協議し進めることとしている。 | ||||||||
| 前頁 | 目次 | 次頁 |