| 前頁 | 目次 | 次頁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
原子力モニターの声 昭和55年8月
科学技術庁
昭和54年度原子力モニターについて
原子力モニターは、原子力開発利用に関して、広く一般国民から率直な意見等を聴取し、原子力行政に反映させることを目的とした制度であり、昭和52年度に開始された。昭和54年度のモニターは、各都道府県知事より推薦を受けた候補者のうち、本人の同意を得た509名に委嘱を行っている。 先に、昭和54年9月から12月までの4ケ月間に原子力モニターから寄せられた随時報告の概要をまとめたが、今回は、昭和55年1月から3月までの3ケ月間における随時報告の概要及び昭和55年1月実施したアンケート調査結果の概要を取りまとめたものである。 Ⅰ 随時報告 1. 意見の内訳
全国509名の原子力モニターから昭和55年1月、2月、3月中に寄せられた随時報告の件数は73件であり、これを事項別にみると、原子力広報についての意見が17件で最も多く、次いで代替エネルギー・省エネルギーについての意見が16件、原子力開発利用についての意見が14件などとなっている。(表1参照) 職業別にみると、主婦等が38件と最も多く、次いで事務・販売・サービス・技能職が18件となっている。(表2参照) また、年代別にみると、20代が21件と最も多く、次いで50代が16件となっている。(表3参照) 男女別では、男性が30件、女性が43件となっている。(表4参照) 2. 意見の概要
寄せられた意見の中で、原子力広報についての意見では、 「原子力発電の安全性という面で、まだまだ不安がぬぐい切れない。原子力は安全なのだというPRに努力してほしい」「石油代替エネルギーとしての原子力発電は何故必要なのかのPRの必要を痛感する。」との意見や、「原子力の良い面ばかりを強調せず、デミリットの部分も出した方が良い。」とした意見が寄せられた。 原子力開発利用についての意見の中では、「原子力発電は必要に迫って止むを得ない措置である。それ故に現在あるものの安全性をより高めることに力を注ぎ、新規建設は見送るべきである。」とした意見や、「地元へのメリットとして電気料金(割引)を考慮してはどうか。」等の意見があった。 また、安全性・事故についての意見では、「原子力発電所の安全性を確認する方法として、常時の点検を会社だけでなく国の職員と合同すべきである。」とした意見や、「原子力発電所事故はいっこうに減少しない。事故の撲滅を期するためより厳重な事故対策を講ずるべきである。」等の意見が寄せられた。 原子力行政についての意見では、「事故に関する情報を正確に早く提供し、地域住民の信頼を得ることが必要である。」とした意見があり、原子力教育についての意見では、「原子力に対する正しい知識を義務教育の場に取り上げるようにしてはどうか。」等の意見が寄せられた。 代替エネルギー・省エネルギーについての意見では、「代替エネルギーの開発が、80年代における技術革新の命題とされているが、思い切った予算の計上とその体制づくりが必要である。」「省エネルギーは、地味な息の長い努力があって実を結ぶものだ。省エネの具体例を国民に知らしては…。」等の意見が多く寄せられた。 その他の意見としては、「原子力には、かなり難しい用語があり、分かりにくい。やさしく、わかりやすい用語辞典を発刊してほしい。」等の意見があった。 参考 報告(73件)の内訳
表1. 事項別の内訳 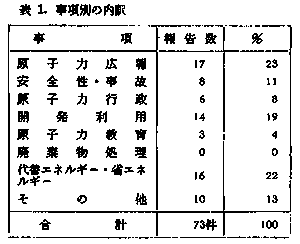 表2. 職業別の内訳 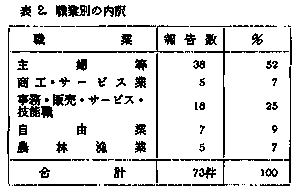 表3. 年代別の内訳 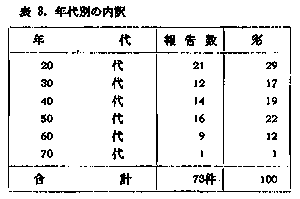 表4. 男女別の内訳 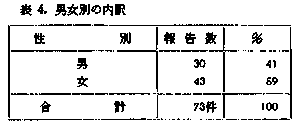 Ⅱ アンケート調査 1. 調査の概要
(1) 調査目的 10月26日の「原子力の日」を中心とした原子力広報に関連して、原子力の開発利用についての認識及び原子力安全行政に対する要望等についての意識を調査し、今後の施策の参考とする。 (2) アンケート項目 1) 「原子力の日」に関する記事等についての関心
2) エネルギー問題についての認識
3) 原子力開発の推進に対する認識と態度
4) 原子力安全行政についての意見
5) 米国TMI原子力発電所の事故に対する関心
6) 原子力広報に対する要望
(3) 報告時期 昭和55年1月10日~昭和55年1月31日 (4) 調査方法 郵送による選択回答方式 (5) 調査対象 昭和54年度原子力モニター(全国509名) (6) 回答者数 372名(回答率73.1%) (参考)
男女別、職業別、年代別モニター数及び回答者数 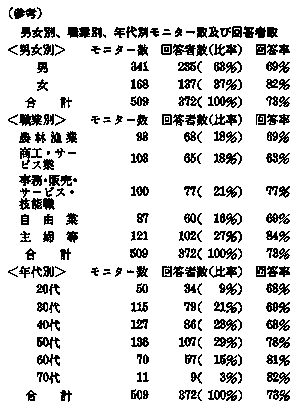 (注) この報告で使われる記号の説明
1. Nは比率算出の基数であり、100%が何人の回答に相当するかを示す。特に示していない場合はN=372人(回答数)である。 2. SQ.:前問で特定の回答をした一部の回答者に対して行った質問 3. M.A.:1回答者が2以上の回答をすることができる質問、このときの回答合計(M.T.)は回答者数(100%)を超える。 2. 調査結果の概要
(1) 「原子力の日」に関する記事等についての関心
原子力に関する広報については、87%の人が新聞、パンフレット、テレビ等を通じて何らかの広報に接しているが、「原子力の日」に関連した広報記事を見た人は71%となっている。 広報についての具体的意見としては、
◎原発の必要性はわかるが、原発の安全性についての説明がないので危険なものであるという先入観の解消にならない。 ◎原発の必要性よりも安全性を強調されたい。 ◎「原子力の日」に限らず何らかの広告(広報)を使って継続的な活動がほしい。 ◎広く国民にも分かるように地方自治体に呼び掛け、町や村の広報で知らせたらどうか。 などがあった。また、小冊子についての意見では、
◎興味が持てたが表やグラフの説明がほしい。 ◎専門用語が多く難しい、日常生活と関連させてやさしく表現してほしい。 ◎もっと広い範囲の人々に読んでいただけるように県報あるいは市町村広報に掲載されたらどうか。 などであった。 (2) エネルギー問題についての認識
エネルギー問題については、98%の人が関心を持ち、98%に近い人がエネルギー不足に不安感を持っていて、石油代替エネルギー源として、原子力(60%)、太陽(42%)に強い期待を抱いている。 (3) 原子力開発推進についての認識と態度
原子力開発の推進については、84%の人が賛成で、反対はわずか5%の人に過ぎない。また、77%の人が安全性を十分確認しながら建設すべきであるという条件付きで賛成、12%の人が今後は必要最小限に止めるべきという考えをあげている。更に、5割近い人が自分の居住地近くへの原子力発電所の建設に賛成しているが、反対者も23%である。 ちなみに反対の理由としては、
◎絶対に事故が起きないという保証もないし、事故が起きたときの責任のとり方、対処の仕方に不安を感じる。 ◎絶対に安全であるという保証がない限り反対する。 など
一方、賛成理由としては、
◎石油代替エネルギーとして原子力以外にないと思うが、安全性が確保されなければならない。 ◎国民経済上必要である。ただし、安全対策、防災対策について納得することが前提。 などである。 安全確保の方策として、安全な原子力発電所の建設とともに、安全性及び安全対策、防災対策等について、地元への一層ていねいな説明を希望している。 また、自主技術開発の進め方として、国、産業界及び大学が協力して進めるべきである(55%)か、国が主体となって進めるべきである(22%)としている。 (4) 原子力安全行政についての意見
原子力安全行政については、①国民に正しい知識を与え、国民の理解を得ていくための施策(37%)、②厳正な安全規制の実施(22%)、③安全性、信頼性等に関する研究開発の推進(22%)、④各種規制段階で、国民の意見を聞き、規制の実施にあたってこれを十分活用するための施策(17%)がほとんどである。 通産省と原子力委員会のダブルチェック体制については、7割以上の人が一応知っているが、よく知っている人となると11%に過ぎない。 原子力安全委員会に期待している機能としては、ダブルチェックの機能(30%)、公開ヒアリングを開催し、地元住民の意見を(29%)並びにシンポジウムを開催し、専門家の成果を(19%)安全行政に反映させることであると考えている。 原子力発電所等の防災対策に関する中央防災会議の決定については、4割近い人が知らないと答えている。 原子力安全行政についての具体的意見としては、
◎原発設置の場合の住民に対して安全を確認できる十分な説明を徹底させ信頼のうえに進めるべきである。 ◎住民を安心させるに足る十分な安全行政、たとえ事故が起こったとしても最小のものにとどめるに十分な安全行政が必要なのではないか。 ◎あらゆる機会をつくり、国民にその実態を広く、正確に知らしめ、その上にたって国民のコンセンサスを得て強力な行政を推進していくべきである。 などがある。 (5) 米国TMI事故に対す関心
米国TMI事故については、82%の人が新聞、テレビ、雑誌等を通じて何らかの情報を入手し、38%の人が以前から起こるかも知れないという不安を持っていた。26%の人は今後は起こらないとみているが、79%の人がわが国の原子力発電所の安全性に不安を感じている。また、今後は安全審査が厳しくなる(39%)とともに建設のテンポが遅れ(33%)、建設が難しくなる(18%)とみている。 米国TMI事故について、最も知りたい情報として、①わが国で起った場合の防災対策(21%)、②わが国の原子力発電所の運転管理についての総点検及び特別監査の調査結果(19%)、③事故を起こした原子炉とわが国の原子炉との関連性(16%)、④より詳細な事故の原因及び発生過程(14%)、⑤住民への影響(13%)に関心が寄せられている。 TMI事故に対する意見としては、
◎他山の石として、日本の原発に対する再認識が深まったと思う。それだけに、安全対策等について国民、地元民に対するPRを積極的に行って開発、設置に努力すべきである。 ◎もし、事故が起こった場合、住民をパニックに落し入れないような対策が必要と思う。 がある。 (6) 原子力広報に対する要望
原子力広報の重点ポイントとして、原子力発電所の安全対策については、①安全体制(47%)、②周辺住民の放射線防護(22%)。原子力の必要性については、①エネルギー供給の中での原子力の位置づけ(34%)、②原子力の長期的な展望(32%)、③わが国の自主技術の現状及びその見通し(27%)と答えており、放射性廃棄物の処理処分対策については、①処分地の場所の選定及び確保(43%)、②処分を実施するときの責任体制(25%)、③陸地処分及び海洋処分の見通し(24%)。放射能(線)の人や環境への影響については、①環境中心の放射性物質の挙動とその人間環境への影響(55%)、②放射線による遺伝的影響(20%)、③放射線による晩発障害の解明の現状(18%)に関心が集っている。 原子力広報の方法としては、テレビ、新聞、各種セミナーが三大方法である。広報を行う機関としては、政府としている人が大半(58%)であり、他は地方自治体(16%)などである。 新聞、テレビ等による広報の年間頻度としては、66%の人が10回以上をよしとしている。 原子力広報に対する要望としては、
◎石油代替エネルギーの中の原子力の位置付けと安全性をより良く国民の理解が得られるような広報にしてほしい。 ◎地方自治体と協力して、原発の建設している県(市町村)と建設中の県、将来建設予定の県とを区別して実状に合致した広報をすべきである。 ◎原子力の必要性は理解されているが、漠然とした不安感は常につきまとっている。したがって、一般の人達にも、もっと理解しやすく、安全対策に信頼性がもっと確立できるような体制と広報活動を活発にすべきである。 ◎多くの反対の方々から投げかけられてきた疑問に十分説得力のある解答が得られるような内容にしてほしい。 などがあった。 3. 集計結果
問1. 10月26日の「原子力の日」を中心とした原子力の広報について 1. 原子力に関する新聞広告(広報)や記事について
(1) 今年度、原子力の日の前後に政府あるいは関係機関等(電力会社や原子力関係団体など)による広告(広報)をご覧になりましたか。 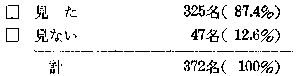 SQ. ご覧になられた方に〔対象者325名〕
(ⅰ) どこの広告(広報)をご覧になりましたか。(M.A.) 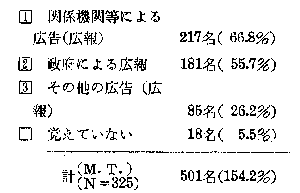 (ⅱ)また、その広告(広報)は何でご覧になりましたか。(M.A.)
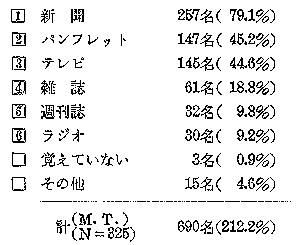 (2) 広告(広報)について、ご感想、ご意見等がありましたらお書き下さい。(回答数172件)
(3) 「原子力の日」に関連した記事はご覧になりましたか。 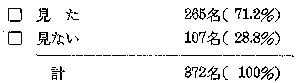 SQ. ご覧になられた方に〔対象者265名〕
ご覧になった記事の内容は何でしたでしょうか。(M.A.)
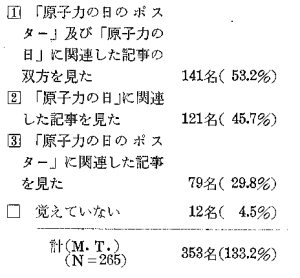 2. 「原子力の日のポスター」についてご感想、ご意見等がありましたらお書き下さい。(回答数131件)
3. 小冊子「くらしとエネルギー」、「わたしたちと原子力」及び「省エネルギーへの道」はお読みいただけましたでしょうか。 (1)「くらしとエネルギー」
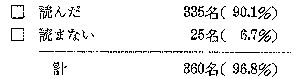 (2)「わたしと原子力」
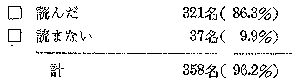 (3)「省エネルギーへの道」
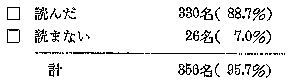 (4)この3種の小冊子について、ご感想、ご意見等がありましたらお書き下さい。
問2. エネルギー問題について
1. あなたは、エネルギー問題について関心をお持ちですか。 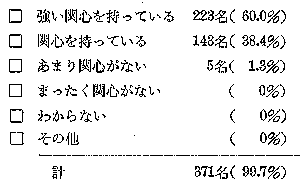 2. 電力、ガソリン、灯油などエネルギー不足についてどのように感じておられますか。 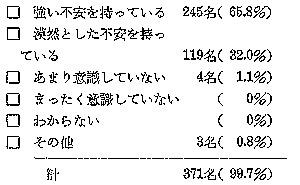 3. あなたは、石油に代わるエネルギー源として、今後どのようなエネルギーに期待されますか。 (M.A.)
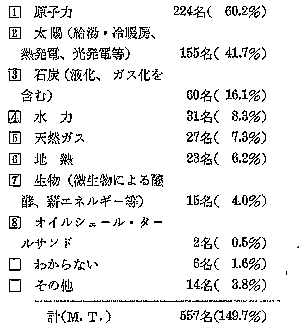 問3. 原子力の開発について
1. あなたは、わが国において原子力の開発が推進されることについて、どのようにお考えですか。 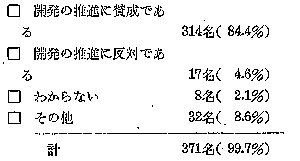 2. あなたは、原子力発電所の建設についてどのようにお考えですか。 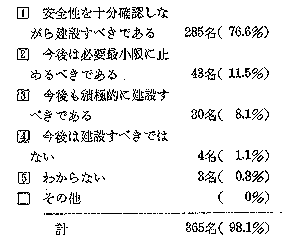 3. もし仮にあなたの居住地の近くに原子力発電所が建設されるとしたら、あなたは賛成しますか、それとも反対しますか。 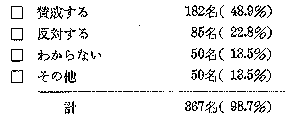 「賛成する」あるいは「反対する」とお答えになった方はその理由を簡単にお書き下さい。(回答数259件)
(1) 賛成の理由としては
(2) 反対の理由としては
4. 原子力発電所の建設を進める上で、安全確保に努めることは当然ですが、次のような方策の中では、どれが有効だと思われますか。 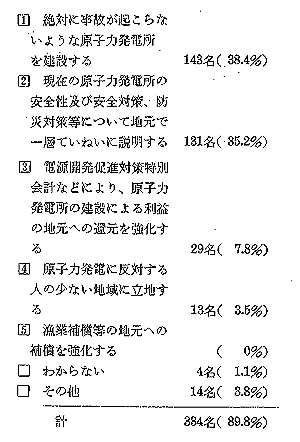 5. わが国は、原子力の分野において高速増殖炉をはじめ、新型転換炉、核融合、ウラン濃縮、使用済燃料の再処理、放射性廃棄物対策等について、様々な技術の自主的な研究開発を推進しています。あなたは、このような自主技術開発の進め方について、どのようにお考えですか。 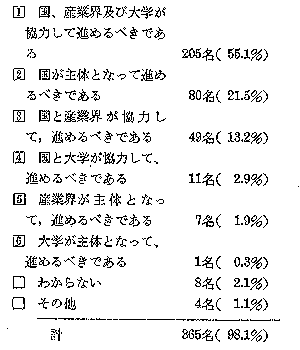 問4. 原子力安全行政について
1. 近年、原子力をめぐって、特に立地問題、安全問題等については、国民の理解を得ることが不可欠の課題となっており、政府としては、現在、次のようないろいろな施策を講じています。あなたは、このうち、どれが最も重要であるとお考えになりますか。 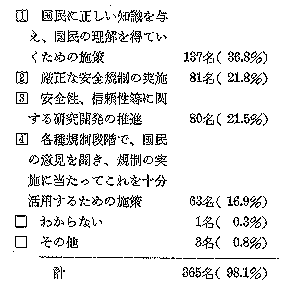 2. 原子力発電所の安全規制については、通商産業省が設置許可から運転管理に至るまで、一貫して規制を行うこととなっており、通商産業省が行う設置許可等に関する安全審査について、原子力安全委員会が最新の科安技術的知見に基づいて客観的立場から再審査(ダブルチェック)する体制になっています。
あなたはこのような体制をご存知でしたか。
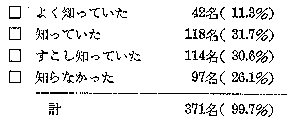 3. あなたが原子力安全委員会に最も期待している機能はどれでしょうか。 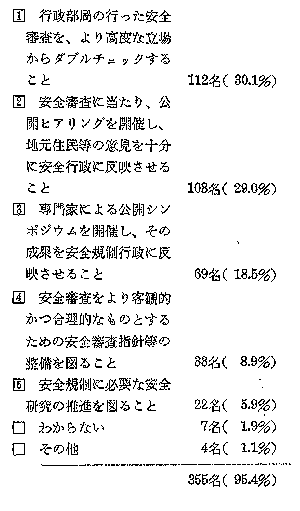 4. 原子力発電所等にかかわる防災対策については、先般のスリー・マイル・アイランド原子力発電所の事故の経験にかんがみ、当面とるべき措置について、昨年7月12日に中央防災会議決定がなされましたが、あなたはこのことをご存知ですか。 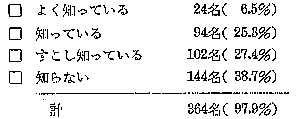 5. わが国の原子力安全行政について、何かご意見、ご提言等がありましたらお書き下さい。(回答数171件)
問5. 米国TMI(スリー・マイル・アイランド)原子力発電所の事故について
1. 昨年3月28日に発生した米国スリー・マイル・アイランドの原子力発電所の事故について、あなたは当方が送付した資料のほかに何らかの情報を入手されましたか。  SQ. 情報を入手された方に〔対象者306名〕
あなたが入手された情報は、次のどれからですか。(M.A.)
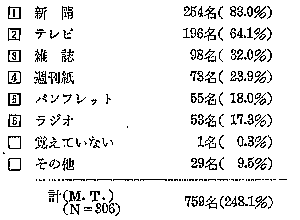 2. あなたは、このスリー・マイル・アイランド原子力発電所の事故をどのように受けとめておられますか。 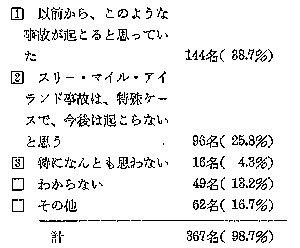 3. あなたは、スリー・マイル・アイランド原子力発電所の事故を知ることによって、わが国の原子力発電所について、どのようなお考えをお持ちになりましたか。 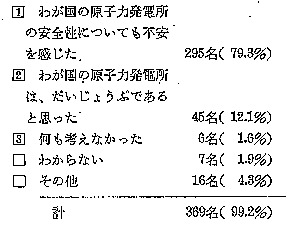 4. スリー・マイル・アイランドの原子力発電所の事故によって、これからのわが国の原子力発電所建設はどうなると思われますか。 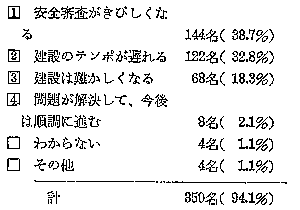 5. あなたが、スリー・マイル・アイランド原子力発電所の事故について、最もお知りになりたいことは何ですか。 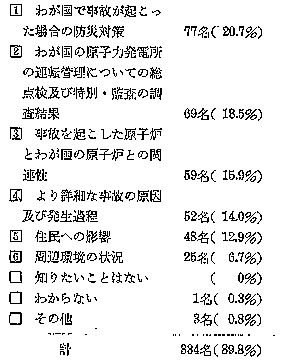 . スリー・マイル・アイランド原子力発電所の事故について、何か意見がありましたらお書き下さい。(回答数179件)
問6. 原子力広報について
1. あなたは、原子力について、特にどのようなことを詳しくお知りになりたいですか。 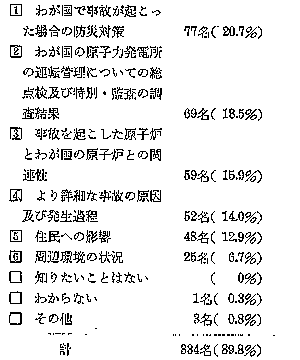 (2) 原子力の必要性について
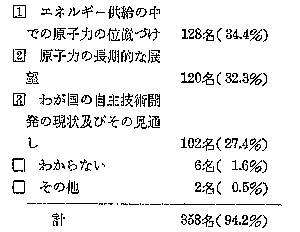 (3) 放射性廃棄物の処理処分対策について
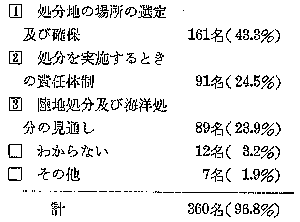 (4) 放射能(線)の人や環境への影響について
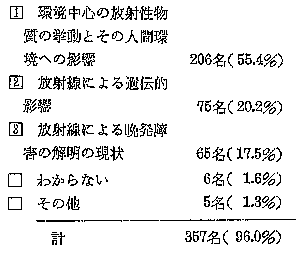 2. 原子力広報の方法について
(1) あなたは、原子力広報について、どのような手段媒体をお望みになりますか。(M.A.)
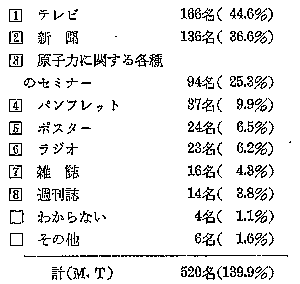 (2) これらの広報をどのような機関が行うことを期待されますか。 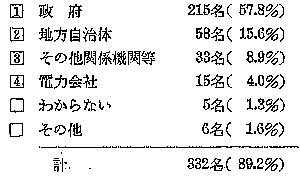 3. あなたは、新聞、テレビ、ラジオ等の媒体で、年間どのくらいの頻度で広報をした方がよいと思います。 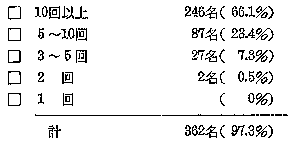 4. 原子力広報について政府に望まれることがありましたらお書き下さい。 (回答数215件)
Ⅲ 参考 昭和54年度原子力モニター構成 (略)
本誌(第25巻第3号19頁)参照
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前頁 | 目次 | 次頁 |