| 前頁 | 目次 | 次頁 |
|
再処理の現況 動力炉・核燃料開発事業団
1. はじめに
動燃事業団の再処理施設は、昭和45年1月茨城県那珂郡東海村への設置について内閣総理大臣から安全上支障がないものと認められ、ついで昭和46年6月「設計及び工事の方法」の認可を受けて建設工事に着手したものである。 昭和49年に工事を終え、引き続き化学試験、ついで昭和50年9月から試運転(ウラン試験、ホット試験)を実施し、昭和55年2月末終了した。 現在、原子炉等規制法に基づく使用前検査受検のための試験運転を実施している。建設着工後の工程を図1に示す。 2. 再処理施設の現状
(1) ホット試験
動燃事業団は昭和52年7月、内閣総理大臣よりホット試験の実施について安全上支障がないものと認められたのち、再処理施設への使用済燃料の受入れを開始した。 再処理施設 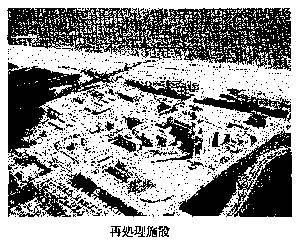 ついで、日米原子力協定に基づく共同決定を経て、昭和52年9月、使用済燃料のせん断、溶解を開始した。 図1 建設、試運転及び使用前検査の工程 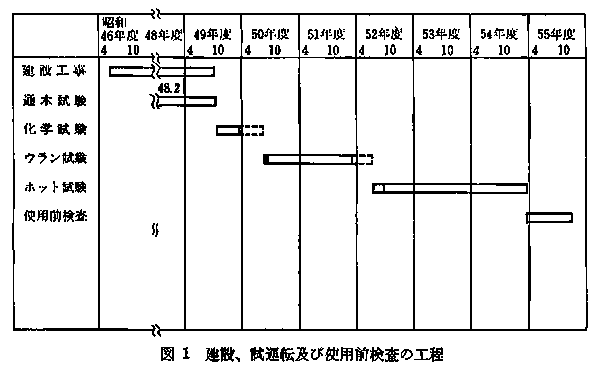 ホット試験は、使用済燃料を使用して再処理施設の操作性、安全性及び性能を確認し、かつ従業員の訓練を併せて実施し、今後の円滑な操業に資することを目的とするものである。 まず、比較的燃焼度の低い使用済燃料を使用して機器などの作動の確認と性能に関する試験を実施し、その後安全性を確認しながら、順次燃焼度の高い使用済燃料を使用して試験を実施した。 試験は次の4段階に分けて実施された。 (1) 日本原子力研究所動力試験炉(JPDR)燃料を用いた試験(JPDR試験) (2) 沸騰水型軽水炉(BWR)燃料を用いた試験(BWR試験) (3) 加圧水型軽水炉(PWR)燃料を用いた試験(PWR試験) (4) 再処理施設の総合的性能を確認するための総合試験期間中、酸回収蒸発缶修復のため約1年間、試験を中断した。 ホット試験の概略を述べる。 (ⅰ) 昭和52年7月15日から原研動力試験炉燃料の受入れを開始し、同8月末までに18回(合計71体、約4.1tU)の受入を完了した。 (ⅱ) JPDR試験は、昭和52年9月22日、最初の燃料集合体をせん断することによって開始し、ほぼ所期の目的を達成して同年12月末に終了した。 (ⅲ) 昭和53年1月31日東電福島第一原子力発電所1号炉の沸騰水型軽水炉燃料24体、ついで3月1日及び3月25日にそれぞれ24体(合計72体)を受入れた。 (ⅳ) BWR試験は、昭和53年2月14日から24体(約4.7tU)の処理をし、所期の目的を達成して、3月27日終了した。 (ⅴ) 昭和53年3月14日、関電美浜原子力発電所2号炉の加圧水型軽水炉燃料10体、ついで4月12日、5月20日及び6月12日にそれぞれ10体(合計40体)を受入れた。 (ⅵ) PWR試験は、昭和53年5月9日から12体(約6.4tU)の処理をし、所期の目的を達成して、6月16日終了した。 (ⅶ) 総合試験は、BWR燃料及びPWR燃料を用いて実施する計画で、先ず、昭和53年8月7日から24体(約4.7tU)を処理し、所期の目的を達成して、8月23日終了した。 (ⅷ) 引続きPWR燃料を用いた試験を開始しようとした矢先8月24日、酸回収蒸発缶の故障により1年余総合試験を中断した。 (ⅸ) 昭和54年10月末に酸回収蒸発缶の故障の修復作業を終え、11月に運転を再開した。運転の再開発にあたっては、施設の長期間停止に鑑み総合試験前に従業員の訓練を兼ねて、全施設の健全性の確認のため予備運転を実施した。 (ⅹ) PWR燃料を用いた総合試験は、昭和55年1月19日から17体(約6.8tU)の処理をし、所期の目的を達成して、2月24日終了した。 一連のホット試験により、再処理施設の性能について、以下の確認を行い、いずれも満足できる結果が得られた。 (1) 各機器の操作性、安全性の確認
(2) 処理能力
(3) 製品回収率及び製品の純度
(4) 物質不明量(MFU)
(5) 海中放出放射能及び大気中放出放射能の濃度、量
(6) 再処理施設各区域の空間線量率並びに空気中及び水中の放射性物質濃度
ホット試験期間中、大気及び海に放出した放射能の濃度及び量はいずれも放出基準値以下であり、陸上及び海洋の環境監視の結果についてもいずれの値にも異常は認められず周辺公衆の安全性を確認した。 なお、昭和52年7月から昭和55年2月末までに使用済燃料341体約71.8tUを受入れ、157体約31tUの使用済燃料を処理した。その間に回収したウランは約30tU、プルトニウムは約161kgPuであった。 (2) 使用前検査
昭和54年に「原子炉等規制法」が改正され再処理施設の検査について、従来の「工事」に関する施設検査と「性能」に関する検査を合わせた使用前検査の制度が新設された。 性能についての使用前検査は、検査の内容により運転時及び停止時に受検するものとがあり、使用前検査をホット試験終了後、2回の試験運転にまたがって受検することにした。1回目の試験運転は昭和55年4月に開始し、7月終了した。2回目の試験運転は9月から実施する。 使用前検査の検査項目は以下のとおりである。 (ⅰ) 警報装置、非常用装置、安全保護回路及び連動装置の性能
(ⅱ) 放射性廃棄物の廃棄施設の処理能力
(ⅲ) 主要な放射線管理施設の性能
(ⅳ) 再処理施設中人が常時立ち入る場所、再処理施設の使用中特に人が立ち入る場所その他放射線管理を特に必要とする場所の放射線量並びに空気中及び水中の放射性物質濃度
(ⅴ) 臨海に達することを防ぐ能力及び使用済燃料等を限定された区域に閉じ込める能力
(ⅵ) 製品中の原子核分裂生成物の含有率
(ⅶ) 製品の回収率
なお、昭和55年3月から8月末までに使用済燃料144体約35.3tUを受入れた。また4月から7月にかけて実施した1回目の試験運転では、使用済燃料(BWR型)157体約28.5tUを処理し、約158kgのプルトニウムを得た。 2回目の試験運転では、使用済燃料(PWR型)56体約20tUを処理し、使用前検査を受検することとしている。 表1使用済燃料の受入量 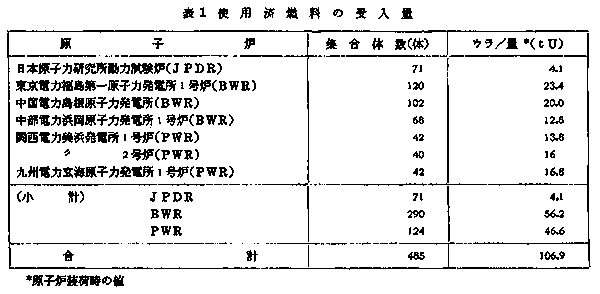 表2使用済燃料処理実績 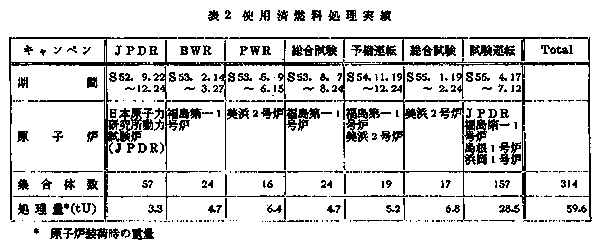 3. 回収製品の利用
ホット試験及び試験運転で今までに、三酸化ウラン製品約56tU及び硝酸プルトニウム溶液製品約315KgPuを得た。これらの製品のうち、ウランについては、約3.3tUの三酸化ウラン製品(UO3)粉体)をUO2粉体に転換し、新型転換炉原型炉「ふげん」の燃料として再加工する。プルトニウム製品は、昨年7月以降今年8月末までに累計約110KgPuをプルトニウム・ウラン混合酸化物(MOX)への転換技術開発に供しており、その結果が良好であり、ウランと同様、「ふげん」燃料に再加工することとしている。 4. 放出放射性廃棄物の低減化技術開発
動燃事業団は、再処理施設本体の建設、試運転と併行して昭和48年以来放出放射性廃棄物の低減化技術開発を進めている。 液体廃棄物については、蒸発処理法による技術開発として低放射性廃液蒸発処理開発施設(通称E施設)及び極低放射性廃液蒸発処理開発施設(通称Z施設)の建設、試運転を行ってきているが、ホット試験の成果をふまえて放出全ベータ放射能を約1/10に低減化する予定である。 気体廃棄物のクリプトン-85については、本年深冷分離法によるクリプトン回収技術開発施設の建設に着手しており、昭和57年完成後開発試験を始める予定である。 5. 再処理関連技術開発
(1) 混合抽出法の研究
日米共同声明・共同決定に基づいて、昭和52年から混合抽出法の研究を運転試験設備の小型試験装置を用いて行った。 混合抽出法の研究は、現再処理施設がプルトニウム単体で抽出されるのに対し、単体ではなくウランとの混合体として抽出することが出来るかを検討するものであり、本施設への適応性の検討をも行った。 (2) 保障措置の技術開発
日米共同声明、共同決定に基づいて、保障措置技術開発のために、米国、仏国、日本国及び国際原子力機関の3国1機関共同研究を行っている。使用済燃料受入区域の監視、計量槽内溶液量測定法第13項目について共同研究を行い、再処理施設への適用可能性について評価、検討を行っている。 |
| 前頁 | 目次 | 次頁 |