| 前頁 | 目次 | 次頁 |
|
頭部用ポジトロン・コンピュータ断層装置 放射線医学総合研究所物理研究部
富谷 武治
1.はじめに
従来のX線撮影は、人体のX線吸収の差異を描出する技術で、X線の透過方法に像が重るため、前後の位置関係がわからない。最近脚光を浴びているX線コンピュータ断層技術は、人体の横断面のX線吸収係数の分布を描出でき、深さ方向の情報を与えるため、画期的技術進歩といえる。しかし、X線を用いた人体イメージング技術は、X線吸収係数という単一の量しか描出できず、病変が臓器の形態変化、またはX線吸収係数に変化をもたらさないと描出されない欠点がある。 それに対して、ラジオアイソトープ(RI)を標識した薬剤を体内に投与し、その分布、経時変化を体外計測する核医学診断技術は、人体臓器の機能そのものを描出するので、“機能イメージング”といわれ、生理機能の直接的診断が行える。シンチレーション・カメラに代表されるように、従来の核医学診断装置は体内RI分布を平面的に描出するもので、X線撮影像と類似の画像であり、深さ方向の情報は得られない。一方、放射型CT(ECT,Emission Computed Tomography)はX線CTと類似の原理を用いており、人体横断面のRI分布を描出できる。ECTには、RIを標識する生化学物質を選択することにより、多数の生理機能情報が得られる利点がある。 2.ECTの原理と横断像再構成法
陽電子(ポジトロン)を放出するRIを用いると、陽電子が被検体内でエネルギーを失なって消滅する際、互に正反対方向に2つの消滅ガンマ線を放出するので、第1図(a)のように被検体をはさんで2つの検出器を向かい合わせ、その間で同時計数をとると、2つの検出器を結ぶ細長い円筒形領域内にあるRIが放射するガンマ線対のみが検出され、その領域内のRI量が測定できる。陽電子消滅に伴なって放射される対ガンマ線の上述の性質を利用したものがポジトロンCT装置である。検出器対を横方向にスキャンすると、RI分布の1つの方向へのプロファイルが得られる。次に検出器対の測定方向を少し変えて同様な測定を順次繰り返し、第1図(b)に示すように多数の方向へのRI分布の投影を測定する。第1図(c)のように円環状に多数の検出器を配置しておくと、その間の検出器対のうち適当なものを選ぶと、図の実験のように互に平行な対が得られ、この方向の投影を測定でき、また別の対を選ぶと、図の点線に示すように別の方向の投影が測定できる。 (a) 一対の検出器を用いたCT (b) 多方向投影データ収集 (c) 円環状に多検出器を用いたCT
第1図 ポジトロンCTの原理 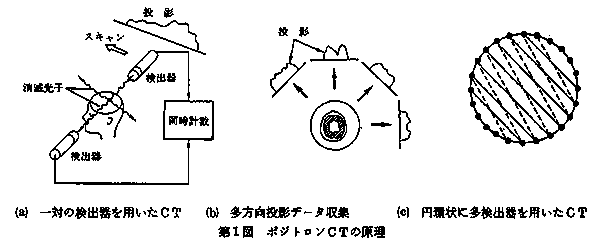 第2図 ポジトロンCT装置の外観 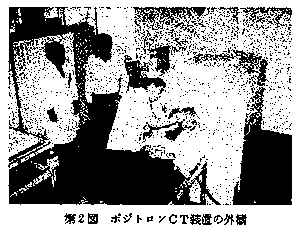 第1図(b)に示す多方向の投影のセットは、RI分布に一種の積分変換を施したもので、RI分布のすべての情報を含んでいる。この変換はラドン変換と呼ばれており、投影データにその逆変換を施すと元のRI分布が得られる。この関係は丁度、フーリェ変換とその逆変換の関係と類似である。逆変換を施すにはコンピュータが不可欠であり、コンピュータ断層と呼ばれる所以である。 3.装置既設
CT装置に要求される性能としては、位置分解能の良いこと、検出効率の高いことがあげられる。位置分解能は原理的には陽電子の飛程と、消滅ガンマ線対の正反対方向からのいずれから決る。検出効率に関しては、最近開発されたゲルマニウム酸ビスマス(B.G.O.,Bi4Ge3Q12)シンチレータがもっとも優れている。検出器を小さくすれば、位置分解能は良くなるが、実際には測定されるガンマ線対の数の統計的変動により決り、無暗に検出器を小さくしても意味がない。前述したRI分布の投影は検出器の大きさでデジタル化され、そのサンプル間隔は、検出器間隔で決る。このサンプル密度は、検出器の大きさで決る位置分解能を具現するには不充分である事に我々は着目し、検出器間隔を不均等にし、検出器系全体を回転することにより充分で一様なサンプル密度を得る方法を考案した。 放射線医学総合研究所では、昭和51年度より特別研究「サイクロトロンの医学利用に関する調査研究」(54年度から特別研究「粒子加速器の医学利用に関する調査研究」として継続中)の一環として上述の原理を用いた頭部用ポジトロンCT装置の開発研究を日立中央研究所の協力のもとに日立メディコ社と共同研究として進めてきたが、この程完成し、理論的に予想された高位置分解能を実証できた。 第2図に装置の外観写真を示す。開発に当っては、B.G.O.シンチレータの国産化、ナノ秒(10-9秒)程度の応答速度を有する超高速電子回路の開発、検出器系の回転に伴い、回転体から固定台への高速データ伝送を可能にする光結合データ伝送装置の開発、高速データ収集とその処理等の種々の問題を解決した。 4.陽電子放出核種とその標識化合物の臨床応用
従来、核医学で用いられているRIはほとんどβ−崩壊−γ線放射型の核種で、原子炉で生産される。この種の核種は原始番号がいずれも大きく、ヨウ素などを除いて本来生体とは親和性に乏しい。また、その半減期が比較的長いため、被検者の体内被曝線量の多いことも問題である。 それに対して、陽電子放出核種は加速器、特にサイクロトロンにより生産され、低電子番号の生体との親和性に富んだ11C、13N、15O、18F等であり、その半減期は10〜110分と短く、被検者の被曝線量の少ない利点がある。 頭部用ポジトロンCT装置を臨床応用するに当り、当研究所では、ガンマ・カメラと焦点検出器を組み合わせた対向型ポジトロン・カメラ、多結晶型検出器を2組用いた高速対向型ポジトロン・カメラなどで充分経験蓄積のある11CO、13NH3を用いて、成人病の代表格である脳血管障害の診断を目ざして、脳血流量を反映するといわれている13NH3および脳血液量を反映するといわれている11COの2つを用いて検査を行っている。第3図(a)に13NH3、同(b)に11COの正常人の像を示す。同(c)には比較のためX線CTの像を示す。開発されたポジトロンCT装置の位置分解能は半値幅で7〜9mmであり、X線CTのそれが2〜3mmであるのと比較すると、この点では劣るが、X線CTではかなり病変が進まないと検知できず、一時的な脳血管障害はまったく検知できない。ポジトロンCTによると、11CO、13NH3のような比較的単純な標識化合物でも脳の虚血性変化を早期に発見できる可能性があり、その実用化が期待されている。 (a)13NH3による脳内血液量の像 (b)11COの脳内血流量の像 (c)X線CT像
第3図 正常人の脳のCT像の例
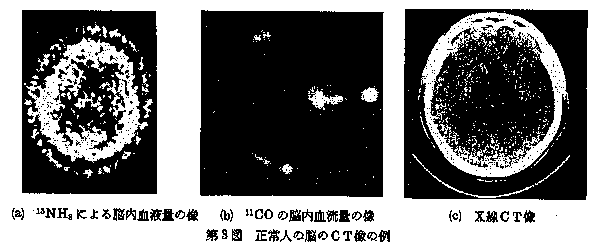 5.おわり
脳の活動の盛んな部位では、糖類の消費量の大きいことが知られている。当研究所では、糖類の一種であるデオキシ・グルコースの18F標識に成功している。これを用いると、脳の機能地図を作成でき、脳機能の基礎研究に大いに役立つものと思われる。 ポジトロンCTは、機能イメージングの特性を生かすと、RI分布の経時変化を測定する動態機能検査とか、各種のR.I.標識薬剤を並用し、相互の分布の差異、相関を求める複合イメージングなど多様性に富んでおり、今後の基礎医学、臨床診断の両面で役立つものと思われる。 |
| 前頁 | 目次 | 次頁 |