| 目次 | 次頁 |
|
ポスト・インフセについて 原子力委員会委員
新関 欽哉
(本稿は、本年2月原子力総合シンポジウムにおける講演の最終部分を抜粋したものである。)
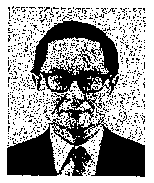 インフセ(INFCE)の内外で行われた論議を通じ、わが国は原子力先進国としての地位を国際的に認められ、再処理、濃縮等をふくむ核燃料サイクル活動を自主的に行うことができるようになったのであります。その場合、いかにしてわが国として、エネルギー安全保障政策上の必要からウラン資源を活用し、核燃料サイクルの自立を計るという基本方針を堅持しつつも、同時にこれを、核不拡散の目的と両立させるために、みずからも真剣に取り組み、その具体的方法について米国ばかりでなく、英、仏、独、さらにまた核燃料の重要な供給国である、カナダ、オーストラリアなどとも十分に協議してゆく必要があると思います。これがインフセ以後の時代、いわゆるポスト・インフセの大きな課題であると考えるのであります。 そのためには、まず、再処理、濃縮などの施設に対する保障措置の改善に今後とも努力を続ける必要があります。わが国は、日米両国間の取決めにもとづき、現在、米国、フランス、それにもちろんIAEAも加わって東海施設を利用しTASTEXとよばれる再処理に関する改良保障措置の研究開発を行っておりますが、濃縮についても従来の商業化に備えて同じく保障措置の改善方法を探究する必要があると思います。 さらに、保障措置ばかりでなく、PP、すなわち核物質の防護について、プルトニウムなどの危険な物質を取扱う以上、とくに慎重な施策をとる必要があります。最近、国際的にも核物質防護に関し、特に輸送面における国際的な連携システムを確立する目的で特別の国際条約が作られたのでありますが、わが国としてもこれに協力すべきであると思います。 なお、再処理と関連する極めて重要な問題としてプルトニウムの国際管理の問題があります。これは、ポスト・インフセの主要課題の一つとされているのでありまして、すでにIAEAが中心となって専門家会合が何回か開かれております。申すまでもなく、プルトニウムの使用は極めて微妙な問題でありますので、燃料として直ちには使われない余剰プルトニウムを厳重に管理する制度、すなわち運搬上の困難をも考慮して再処理施設のある地点においてプルトニウムの貯蔵を国際的に管理する仕組み(IPS)を設け、国際的に合意された一定の基準にもとづき必要に応じてこれを引き出して使用するという考え方を具体化して、ゆくゆくは国際的な協定を作ろうという動きがでております。 そのほか、今後大量に出てくる使用済燃料の貯蔵の問題があります。インフセの報告書のなかでも、使用済燃料は世界的にみて再処理される量をはるかに上回るものと予想されており、これを国際的に貯蔵し、管理するISFMという制度にも、同じくIAEA主催の専門家会合の形で準備が進められております。 もう一つのポスト・インフセの国際的課題としては、供給保護の問題があります。今後、核拡散防止とのからみ合いもあり、核燃料などの供給保障をいかにして担保するかということは大消費国である日本にとって重大な関心事項でありますが、IAEAのエクランド事務総長はIAEAがこの問題についても検討の場を提供する用意があると申しております。わが国としては、その場合には、核燃料供給国の規制権のあり方、およびその権利の行使の態様について十分討議が行われ、消費国の立場も十分考慮に入れたうえでコンセンサスがえられるべきであると考えておる次第であります。 以上は、いわゆるマルティ、すなわち、多数国間におけるポスト・インフセの主要課題でありますが、そのほかわが国の当面するポスト・インフセの問題としては、バイの関係、つまり東海再処理施設の運転に関する日米共同決定の問題や、日米、日豪などの原子力協定改訂交渉が控えていることは御承知のとおりであります。 最後にインフセとわが国の原子力開発政策との関連について一言申し上げたいと思います。 ポスト・インフセを中心として核不拡散をめぐる国際的動向と国内における原子力開発利用政策の進展とは、盾の両面と申しますか、車の両輪といった方がより適切であると思いますが、いわばもちつもたれつの関係にあるのでありまして、インフセのこれまでの作業を通じ、わが国にとって原子力白書の言葉をかりれば「曙光のみえる」状態になったとしても、今後における開発利用施策の進捗による国内的基盤の強化がこれに伴うのでなければ、描かれたモチに終わり、国際的にもわが国の立場を強く主張することができないのであります。 そういう意味におきまして、とくに重要なのは、自主的な研究開発の努力であります。過去におきまして、わが国が科学分野において新しい技術を必要とする場合、ともすればこれを海外からの先進技術の導入に依存する傾向が強かったのであります。その背景としては、自主技術の開発は、コストの点で高いものにつき時間的にも遅れるし、また成功しなかった場合のリスク負担が大きいということがあったと思われますが、いずれにせよ、自主的に研究開発を進めようとする積極的姿勢において幾分欠けるところがあったことは否みがたい事実であります。原子力の分野におきましても、従来は相当高度な技術でも比較的容易に海外から導入できたのでありますが、最近になって核不拡散問題がやかましくなって参りまして、機微な技術の移転は厳しい国際的な規制を受けるようになってきたのでありますので、一層その必要性が痛感されます。 幸いわが国においては、過去20年以上にわたる真剣な努力がようやく実を結びつつあり、いろいろな面で自主技術の蓄積ができております。 一例をあげるならば、動燃が中心となって開発してきた新型転換炉(ATR)については、原型炉「ふげん」が目下極めて順調な運転を続けており、次の段階である実証炉への進展に関するチェック・アンド・レビューを行うため、原子力委員会の専門部会が近く開かれることとなっております。この機会に一つご紹介させて頂きたいと思いますのは、最近米国のエネルギー省(DOE)が委託して行ったATRに関する調査報告書のなかで、大要次のように述べられていることであります。すなわち、
「ふげん」の開発は10年前に開始されたが、インフセの期間中にその運転開発に成功し、その結果、機微な技術に関する日本の立場が強化された。「ふげん」は、独特な方法によるプルトニウムのリサイクルによりFBRへの橋渡しとなるものである。「ふげん」は再処理をはじめとして日本が必要とする技術開発のすべてを包含しており、最終的には核燃料サイクルの独立に寄与するものである………
と述べており、わが国のこの面における自主開発努力を極めて高く評価しているのであります。 これからの自主技術の実用化の問題は、要するに商業化の問題であります。これまで、国の機関によって研究開発された技術をどのような手順で、どのような実施主体の手に移し、商業化に成功させることができるという問題であります。このことは、唯今申上げたATRばかりでなく、民間再処理工場の建設運転、高速増殖炉原型炉「もんじゅ」の開発および次の段階における民間への移行、ウラン濃縮パイロット・プラントから原型プラント、さらにその商業化の問題についてもいえることであります。このためには、これまでの国の研究開発の成果を受けつぐべき産業界において、それぞれの役割、分担に応じて適切な体制の整備を計ることが、とくに強く期待されるのであります。 繰り返して申上げますが、原子力平和利用と核不拡散は両立しうるものである、いいかえれば、資源に乏しいわが国のエネルギー確保のために必要な原子力の開発利用は、核不拡散のハドメをつけることを条件として認められるようになり、核燃料サイクルの自立に関する日本の基本的立場は過去2年半にわたったインフセの議論を通じて一般に国際的コンセンサスとして認められたといってよいのであります。 しかしながら、インフセそれ自体は外交交渉の場ではなかったのでありまして、各国政府はその結果に必ずしも拘束されるものではないとされておることは御承知の通りであります。従いまして、これから始まるポスト・インフセの段階におきましては、インフセの結論をふまえつつ、原子力開発利用に関する新しい国際的秩序を作りあげることを目的としまして、二国間の交渉、および多数国間の協議を行ってゆかなければならないのであります。そして、その成行次第では、今後におけるわが国の原子力分野における活動が制約をうけないとも限らないのでありまして、決して手放しの楽観はできないのであります。そういうことにならないためには、わが国としては今後ともインフセ期間中に劣らぬ努力を国際的に続けるとともに、官民一致して国内的基盤の整備を計る必要があると考えているのであります。 |
| 目次 | 次頁 |