| 前頁 | 目次 | 次頁 |
|
「長期エネルギー需給暫定見通し」中間報告 昭和54年8月31日
通商産業省
(総合エネルギー調査需給部会)
--はじめに--
当専門委員会は、昭和54年7月19日以降6回にわたり、長期のエネルギー需給の見通しについて、様々な角度から検討を進めてきたが、8月28日、下記の通り暫定的なとりまとめを行ったので報告する。 なお、本見通しについては、今後、内外の情勢を見極めつつ、年内を目途に成案を得ることとしている。 第1章 需給見通し策定の背景と基本的考え方
〈背景〉
1. 当専門委員会は、昭和52年6月、昭和60年度及び昭和65年度のエネルギー需給暫定見通しを策定した。これを踏まえ、総合エネルギー調査会の各部会等において具体的な政策の検討が行われ、これらをもとに昭和53年10月総合エネルギー調査会基本問題懇談会において、「21世紀へのエネルギー戦略」がとりまとめられた。 しかし、その後、我が国をめぐるエネルギー情勢が急変しており、我が国内外の新しい情況に対応した長期的なエネルギー需給の見通しを明らかにする必要が生じている。 2. まず、国際的なエネルギー情勢については、
① 従来、1980年代後半から1990年代にかけて到来すると考えられていた世界的な石油需給の不均衡は、最近における国際石油情勢の変化により、早期に発生する可能性が強まっている。すなわち、中東に内在する不安定要因は、この地域からの石油供給の安定性に懸念を抱かせているとともに、産油国においては、石油生産量をみずからの経済社会建設の必要に応じて決める等有限な石油資源を長期にわたって有効に活用する方向を一層強めていくものと考えられ、これが世界の石油市場におけるアベイラビリティを低める方向に働くものと思われる。 ② 本年6月末、世界的な石油需給逼迫化の中で開催された東京サミットにおいて、先進主要国は、軌道に乗りつつあった世界経済の安定的発展を将来的にも確保するために各国が協力して問題解決に当たらなければならないとの共通認識の下に、石油消費の抑制を図るため、1979年、1980年及び1985年の石油輸入目標の設定に合意し、併せて、石油代替エネルギー源の開発等についても協力、協調することで意見の一致をみたところである。とりわけ、石油輸入目標の設定に当たっては、アメリカ、欧州共同体が、1985年段階においても現状横ばいの輸入目標量を設定しているのに対して、我が国は、現在の17%~28%増にあたる630万バーレル/日~690万バーレル/日の石油輸入目標を採用することで合意をみた。しかしながら、自由世界第2位の石油消費・輸入国である我が国としては、最大限の努力を払うことにより世界の石油需給事情の改善に貢献すべきことは勿論であり、これは東京サミット宣言で言及された可能な限り石油輸入量を削減すべきであるとの国際的要請にも応ずるものである。このため、今後、石油輸入量をより低い数値に近づけるために、各種エネルギー政策を抜本的に強化し、官民あげて最善の努力を尽すことが要請される。 3. 他方、国内面においても、昭和60年度を最終年度とした新経済社会7カ年計画が策定され、新たな経済のフレームワークが設定されたことに加えて、最近における各エネルギー源の進展状況に応じ、改めてエネルギー需給の見通しを明らかにする必要がでてきている。 〈基本的考え方〉
1. 当専門委員会は、我が国経済の今後の健全かつ安定的な発展、国民生活及び福祉の向上、雇用の安定確保等を図るためには、エネルギーの安定供給を確保することが最も重要な政策課題であるとの基本的認識の下に、国際石油市場の動向、国際的責務の遂行、我が国のエネルギーセキュリティの確保等を踏まえ、我が国としては、今後、輸入石油に対する依存度を可能な限り低下せしめることが重要であり、このためには、新たな決意のもとに省エネルギーの推進、輸入石油代替エネルギーの開発・導入に意欲的に取り組む必要があるとの結論に達した。 2. 石油代替エネルギーの開発・導入を推進していく場合においては、まず、現実に利用されている代替エネルギー源の量的拡大についても、従来以上に立地問題、環境問題、海外開発問題等果敢に対応しなければならない問題が山積していることのほか、更に新しいエネルギー源については、実用化のための技術開発問題や普及促進問題等があること、また、省エネルギーについても、更に大胆かつきめの細かい対応が不可欠となっていくこと等が予想される。しかしながら、エネルギーの安定供給を確保することの重要性を考えれば、これらの困難に逡巡することは許されないものと考える。 3. 以上の点を踏まえて、当専門委員会は、官民あげての最大限の努力と協力を前提とし、東京サミットにおける合意等を踏まえた国際的責務の遂行と、我が国のエネルギーセキュリティの向上を指向しつつ国内のエネルギーの安定供給を確保することの両立を目指した長期的なエネルギー需給の見通しを策定することとした。 第2章 需給見通しの概要
1. 省エネルギー前の一次エネルギー需要量については、経済成長率が昭和52年度から昭和60年度までは年率6%弱、昭和60年度から昭和65年度までは年率5%程度、昭和65年度から昭和70年度までは年率4%程度で推移する場合には、昭和60年度においては6億6,000万kl程度(石油換算、以下同じ。)、昭和65年度においては8億2,000万kl程度、昭和70年度においては9億7,000万kl程度に達するものと見込まれる。 2. 省エネルギーについては、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」の積極的な運用を中核として、省エネルギー投資に対する助成、節約措置の徹底、技術開発の推進等により、昭和60年度には12%程度、昭和65年度には15%程度、昭和70年度には17%程度(いずれも48年度基準)にまで省エネルギー率を引上げることを目標とすることが可能であると考えられ、その目標が達成された場合における省エネルギー後の需要は、昭和60年度には5億8,000万kl程度、昭和65年度には7億kl程度、昭和70年度には8億1,000万kl程度になるものと見込まれる。 3. 輸入石油代替エネルギーの供給については、原子力、石炭、LNG、水力、地熱、国内石油・天然ガス、新燃料油、新エネルギー等の開発・導入により、昭和60年度において2億1,600万kl程度(一次エネルギー供給に占める割合、以下同じ。37.1%)、昭和65年度において3億5,000万kl程度(50.0%)、昭和70年度において4億5,900万kl程度(56.9%)に引上げることが必要であるが、これらは、それぞれについて、民間の最大限の努力と理解のもとに、政府の代替エネルギー開発施策等の重点的かつ計画的遂行なくしては達成不可能である。 4. 昭和60年度における輸入石油に係る需要は、以上の努力により3億6,600万kl程度とすることが可能であるが、それは、同時に、最小限確保すべき必要量でもある。昭和65年度及び昭和70年度においては、エネルギーの安定的供給確保の観点から、昭和60年度と同程度の供給を確保することが望まれる。なお、両年度については、以上のような官民の最大限の努力と協力により、それぞれ輸入石油に係る需要量を3億5,000万kl程度及び3億4,800万kl程度とすることを目標とするものであるが、その場合において生じる1,600万kl及び1,800万klは、将来の需給両面における不確実性を考慮し、供給の予備とすることが適当である。 なお、緊急時に備えた石油備蓄については、上記の石油供給量に加え、計画的備蓄の達成を図るものとする。 -結語-
1. 現時点において将来のエネルギー需給を見通すには、不確実な要因が多い。しかし、当専門委員会は、このような不透明な時期においてこそ我が国が官民一体となった努力を傾注すべき方向を示すべきであると考えた。また、今後の我が国のエネルギー供給において、代替エネルギーが重要な役割を果たし、かつ、その開発・導入に長期のリードタイムを要すること等にかんがみ、新たに昭和70年度のエネルギー需給見通しを提示した。 2. このエネルギー需給見通しの達成のためには、民間の最大限の努力と理解のもとに、省エネルギーの推進、代替エネルギーの開発・導入、石油の確保のそれぞれの分野において、政府の重点的かつ計画的な政策の遂行がなされなければならず、このためには企業活力の向上と国民意識の高揚に努めつつ、推進体制を整備するとともに受益者負担の観点も含め積極的な資金確保の対策を講じていくことが必要である。 各エネルギー源毎に講ぜられるべき官民の努力と協力の内容は様々であり、その実行の難易度も自ら異っている。このため、具体的な施策等については、今後必要に応じ、関係審議会における審議を経る等十分な検討を加え、早急にその実現を図って行く必要がある。 3. 当専門委員会は、審議の過程において、将来におけるエネルギー情勢は非常に厳しく、十分な努力がなされない場合には、エネルギーが経済社会の安定的な発展にとり大きな制約となる可能性があり、現在、いかなる途を選択するかの岐路に立たされていることを認識した。したがって、そのような不幸な結果を招来することのないよう民間の最大限の努力と理解のもとに、政府においても全力をあげて政策を推進することを強く希望する。 4. エネルギー情勢は流動的であり、時宜に適した柔軟な判断に基づく対応策が用意されねばならない。そのためにも、本エネルギー需給見通しについても、絶えず評価と検討を加えつつ、必要に応じて改訂されていかなければならないものと考えている。 長期エネルギー需給暫定見通し 昭和54年8月28日 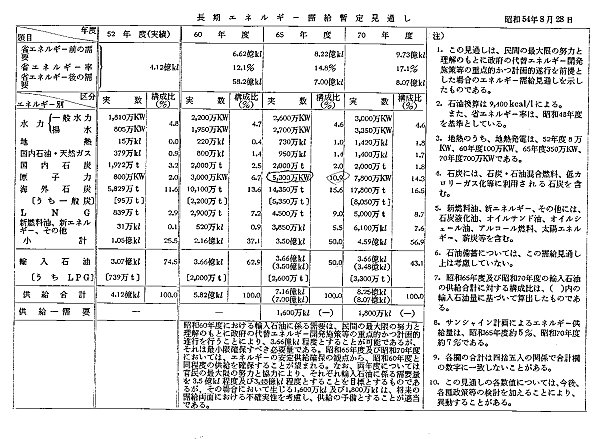 |
| 前頁 | 目次 | 次頁 |