| 前頁 | 目次 | 次頁 | ||||||||||||||
|
米国原子力発電所事故特別委員会第1次報告書(抜粋) 昭和54年5月
原子力委員会…特別委員会
1 まえがき
原子力安全委員会は本事故を重要な意味をもつものと受けとめ、本件に関し幅広く検討を行い、我が国の原子力安全確保に反映させるとの方針のもとに当特別委員会を設置し、本件事故に関する調査及び本件事故に関し、我が国の安全確保対策に反映させるべき事項の検討を指示した。 当特別委員会は、原子炉安全専門審査会TMI事故調査特別部会の審議を引き継ぐとともに、原子力安全委員会が米国に派遣した専門家による情報及び米国原子力規制委員会が公表した情報を中心に、本件事故に関する調査分析を鋭意進めてきた。指示された事項についての検討は未だ中途にあるが、本件事故に寄せられている国内の関心に応えるため、また、我が国の原子力の安全確保に反映させるためにも、早い時期に調査審議の内容をとりまとめ公表することは非常に有意義であると考える。 本報告は、現時点(5月中旬)までに得られた資料等に基づき、本件事故の事実関係を中心に若干の評価を加えたものとなっている。本報告が、関係各位の事故に対する認識を深めるのに有効なものとなることを希望する。 なお、現在も米国において当特別委員会の委員である専門家が、調査を継続しており、また、NRCにおける本事故に関する調査検討も引き続き進められているところから、本報告の内容も今後の調査審議により変わりうるものであることをお断りしたい。 2 スリー・マイル・アイランド原子力発電所の概要
2.1 発電所の位置、原子炉型式等
発電所は、米国ペンシルバニア州ミドルタウンの南方約2.5マイル(約4㎞)、サスケハナ川にあるスリー・マイル島にある。原子炉は2基設置されており、いずれもバブコック・アンド・ウイルコックス(B&W)社設計加圧水型軽水炉(PWR)である。その出力は1号炉が876MWe(2,568MWt)、2号炉が959MWe(2,772MWt)である。 発電所の所有者は、メトロポリタン・エジソン社、ジャージー・セントラル・アンド・ライト社及びペンシルバニア・エレクトリック社の3社となっており、この3社がジェネラル・パブリック・ユーティリティ(GPU)となっている。また、発電所の運転はメトロポリタン・エジソン社が行っている。 発電所の建設・運転の時期は、着工が1号炉(以下TMI-1号炉)1968年5月、2号炉(以下TMI-2号炉)1969年11月、臨界が1号炉1974年4月、2号炉1977年7月、運転開始が1号炉1974年8月、2号炉1978年12月である。 2.2 原子炉施設の概要
1号炉の原子炉施設の主要構造物は、原子炉建屋、タービン建屋、補助建屋、制御建屋、ディーゼル発電機建屋、2つの冷却塔、冷却水ポンプ建屋等からなる。防火システム、種々の廃棄物濃縮装置、燃料取扱クレーン、新燃料貯蔵庫等は2号炉と共用になっている。 原子炉は、2ループ(蒸気発生器が2台)のバブコックス・アンド・ウイルコックス社設計PWRであり、その主要データは以下のとおりである。 すなわち、燃料は、焼結UO2ペレットをジルカロイ4被覆管につめた燃料棒を15×15に配列した燃料集合体177体からなり、初期平均濃縮度は2.65%である。炉心の大きさは、等価直径129インチ、有効高さ144インチである。制御は制御棒とほう素濃度調整によって行われ、このほか減速材温度係数を負に保つためバーナブルポイズンが使用されている。制御棒及び出力分布調整用制御棒はAg-In-Cd(銀-インジウム-カドミウム)をステンレス被覆管に充填した棒をクラスタに組んだもので、それぞれ68体、8体である。 原子炉容器は、内径171インチ、全高39フィート(制御棒駆動機構のノズル等を含む)の鋼製圧力容器で、ステンレススチールの内張りがほどこされている。原子炉は、運転圧力2185Psig、1次冷却系流量137.8×106lb/hr、入口(公称)温度556.5°F、出口(公称)温度607.7°Fで、平均熱流束は185,090Btu/hr-ft2である。ループ数は先に述べたとおり2ループで、ループあたり1基の蒸気発生器と2基の冷却材ポンプを有する。なお、加圧器は全体で1基である。 格納容器は、炭素鋼のライニングを有するPSコンクリート製で主要寸法は胴部内径130フィート、高さ187フィート、壁厚3.5フィート(1号炉)、4フィート(2号炉)、屋根厚さ3フィートで、基礎マット厚さ9フィート、底部ライナープレート上のスラブ厚さ2フィートである。なお、基礎は岩盤上におかれている。設計漏洩率は0.2%/dayである。 図 スリー・マイル・アイランド原子力発電所の位置 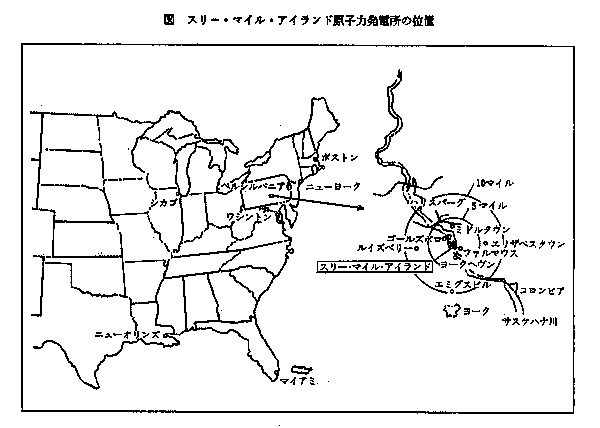 2.3 敷地及びその周辺の状況
発電所敷地があるスリー・マイル島はサスケハナ川の中にあるいくつかの島のうち最も大きなもので、東岸から900フィート離れたところにある。島は長さ約11,000フィート、幅は1,700フィートで、原子炉施設は島の北部約3分の1を占めている。また、島の下流にはヨークヘブンダムがある。(図参照)
敷地は、メトロポリタン社の所有地で814エーカーある。メトロポリタン社は、スリー・マイル島全部と近接するシェリー島の一部を除いた大部分を所有している。排除区域は、半径200フィートの範囲であり、スリー・マイル島の部分とその周囲の水面及びシェリー島の所有地の部分が含まれている。スリー・マイル島の南側の部分にはレクリェーション施設が計画されており、そこへ行くためには建設用に作られた橋を使うことになるであろうが、島はメトロポリタン・エジソン社が所有しているので非常時には容易に排除できる。また、非常時には、遊覧のための船が排除区域に接近するのをマリン・パトロールが防ぐことになっている。さらに、敷地の南北2ケ所に放射能放出の可能性を警告する表示器をもったブイがおかれている。 敷地周辺の人口は、1970年において1マイル内590人(1980年予想660人、以下( )は同年の人口予想)、2マイル内2,400人(2,700人)、5マイル内26,000人(29,000人)、10マイル内140,000人(166,000人)とされている。低人口地帯は発電所から半径2マイルとされている。最も近い人口中心地はハリスバーグ(約10マイル)で、1970年の人口は約68,000人である。 公共施設のうち学校は10マイル以内に69あり、病院としては、ペンシルバニア州立大学の病院が10マイル近くにあり、350のベッドと看護婦学校の250人の学生を収容している。その他、この地域には、北西約2.5マイルにオルムステッド空港及び西北西約8マイルにハリスバーグ・ヨーク空港があり、空港に近いので、飛行機に対する検討が行われている。 2.4 同型式の運転状況
スリー・マイル・アイランド1号炉、2号炉と同型の原子炉としては、アーカンサス-1号(1974年8月運転開始、以下( )内は同)、クリスタル・リバー3号(1977年3月)、ディビス・ベッスィ1号(1977年7月)、オコーニ1号(1973年6月)、同2号(1973年10月)、同3号(1974年12月)、ランチョ・セコ1号(1975年4月)がすでに運転されている。 2.5 TMI-2号炉施設の特徴
TMI-2号炉施設は、ワシントンD.C.の西北西約100マイル、ペンシルバニア州都ハリスバーグの東約10マイルの地点にあり、サスケハナ川の中の大きな中洲に設置されている。 TMI-2号炉は蒸気供給システム(NSSS:Nuclear Steam Supply System)がB&W、その他の系統はバーンズ・アンド・ロー(B&R)社の設計になる。営業運転は1978年12月30日開始された。 TMI-2号炉の特徴の1つに、このプラントから僅か2.5マイルに空港があり、航空機墜落の確率が10-6/年を上廻った唯一の(我々の知り限り)ものであるため、格納容器が厚いPSコンクリート製であることがあげられる。これが今回の事故の影響に緩和に一部役立っている。 B&W社のNSSSは、多くの点で他のPWRと異る特徴を有している。第1に、これが過熱蒸気供給システムであるということである。このため、蒸気発生器は直管型(once through type)であり、蒸気発生器側の上部は完全に蒸気で全体としても液相の量が少く、著しく高蒸気質の体系である。運転は、1次系は平均温度一定方式、2次系は蒸気圧力一定方式で負荷変動等に対して、給水量、蒸気発生器水位、熱出力等を総合的に制御するいわゆるIntegrated Control Systemを具えている。 第2に、TMI-2号炉の機器配置を見ると、蒸気発生器位置が圧力容器とほゞ同じ高さにあることが極立った特徴である。このことは、格納容器の高さを節約できる点では好適であるものの、1次冷却材ポンプ(RCP)トリップ時に自然循環冷却を確保するために、特別な工夫を要する。このため、補助給水系(AFW)は2次側頂部にスプレイするとか、RCPトリップ時には2次側水位を急上昇させるなどして、ヒートシンク位置を高める設計になっている。 自然循環についてさらに考察すると、この状態で、1次系で最も圧力が低いのは、ホットレッグが起ち上って蒸気発生器頂部に達する彎曲部であって、この部分に蒸気その他の気泡が生ずると、自然循環が生じなくなる。従って、1次系において、
P system(1次系の圧力)>P sat(飽和圧力)+(非凝縮ガスが存在する時はその分圧)であることが、自然循環冷却を行うための必要条件となる。 第3に指摘すべきことは、加圧器サージ管の構造である。サージ管はホットレグ垂直部から一旦下に向い、U字管を形成して加圧器に接続されている。これは、ある特殊な場合には、いわゆるループシールを形成する可能性がある構造で、加圧器水位のみによって、1次冷却材インベントリを代表させようとすれば、誤った判断を招くことになるので、1次冷却材インベントリの量を把握するためには、1次系の圧力、温度も含めて総合的な判断をすることが必要条件となる。 上記のサージ管の構造を別とすれば、TMI-2号炉は、全体として1次-2次系の結合が強く、負荷変動に対して即応性に富んだ特性になっていると思われる。事実、このプラントは、短時間の負荷喪失をスクラムなしで乗り切れる設計となっており、このため、2次側にはスクラム信号がない。B&W社は、安全回路等を簡略化し、それによって逆に信頼性を向上させることを狙っているようである。 これらは一応首肯し得る設計思想であるが、一面下記のような特性も有することになり、これが今回の事故では、事態を悪化させる方向に作用した。 (i)タービントリップ時などに、加圧器逃し弁が開く場合が多い。 (ii)給水ポンプトリップ時に、AFWの起動に許される時間余裕が少い。 (iii)RCPを停止する場合、自然循環のための条件が確立されていることを、特に慎重に確認する必要がある。 3 事故の概要
3.1 原子炉施設
3.1.1 事故の経過
昭和54年3月28日米国のスリー・マイル・アイランド原子力発電所2号機において2次給水系の故障に端を発し、一部設備の不良、機器の故障、運転員の誤操作なども重なって放射性物質が外部環境に異常に放出されるという事故となった。本件事故の原因、経過については、米国原子力規制委員会において詳細な調査が行われている。これまでに公表された情報及び米国原子力規制委員会関係者に対する面接調査によれば、事故の主要点は次の6項目である。(事故の時間的経過については表参照)。 (1)事故の起因である「復水ブースターポンプの停止、主給水ポンプの停止」が殆んど同時に発生したこと。ポンプが停止した原因については、まだ不明である。 (2)補助給水ポンプは3台(タービン駆動1台、モータ駆動2台)あるが、出口側に共通に2個の弁がある。この弁が事故発生前から閉の状態にあった。“閉”であることは、中央制御室に表示されていた。 この2個の弁は原則として“常時間”でなければならず、出口弁2個閉のまま運転することは技術仕様書違反であって、このような運転をすべきではなかった。このため、補助給水ポンプは主給水ポンプの停止で自動的に起動したが、弁が閉であったため給水されなかった。 (3)加圧器の逃し弁は加圧器圧力高で自動的に(設計通り)開放した。しかし、その後圧力が下っても逃し弁は閉じなかった。しかも、逃し弁が閉じていないことが、運転員に認識されなかったため、逃し弁の上流にある元弁を閉める操作がとられず約2時間20分にわたり蒸気と水の吹出しが続いた。 (4)非常用炉心冷却系ECCS(この場合高圧注入系2系統)が加圧器内の圧力低信号で設計通り起動し、水の注入が行われた。 しかし、NRCの発表によれば加圧器の水位計の表示が水位高を示したため、満水したものと判断して高圧注入系を4分30秒後に1台、10分30秒後に1台手動で停止させた。 (5)逃し弁から流出した水は格納容器内下部の加圧器逃しタンクに入り、さらに同タンクの逃し弁さらに破壊板を通し格納容器内サンプに溜った。しかし、格納容器は隔離の状態になかったため、サンプポンプの自動駆動によって、水が格納容器から補助建屋のタンクに送られた。この水がタンクから補助建屋の床にあふれ出た。この補助建屋の床上にあふれた一次冷却水から放射能が環境に放出された。(特にキセノン、クリプトンの希ガス及びヨウ素)
(6)一次系内の減圧により、局部的に蒸気気泡が発生し、ポンプの振動による損傷を恐れて一次冷却材ポンプ(2系統4台)が手動で停止された。 一次冷却材ポンプはAループ1台のみが16時間後に再駆動されたが、それまでの間重要な冷却機能が損なわれた。なお、蒸気発生器Bは細管の洩れがあると判断したため2時間20分後に隔離されている。 表 事故の時間的経過 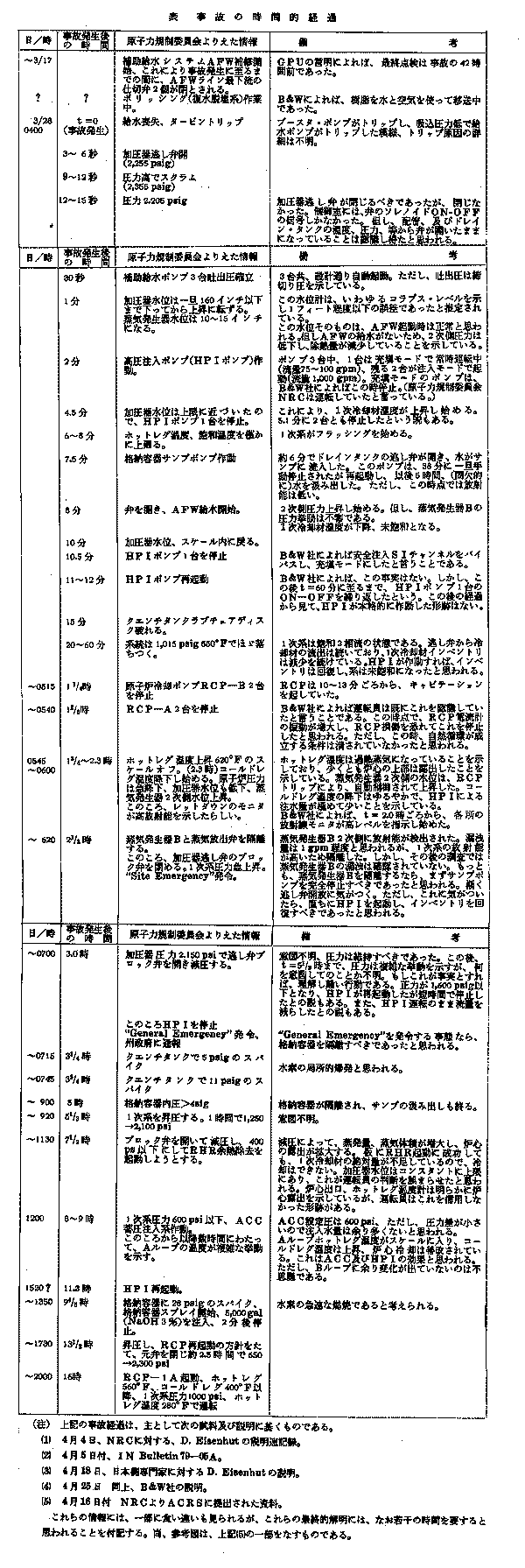 3.1.2 運転員が採った措置
スリー・マイル・アイランド原子力発電所の事故は悪化させた原因としてその主なものを拾ってみると
(1)技術仕様書に反して出口弁が閉じていたため、補助給水系が働かなかったこと(なお、事故後8分で手動により作動)
(2)加圧器逃し弁が開きっぱなしになり、かつその後2時間以上も元弁を閉じなかったこと
(3)加圧器水位計のみによって高圧注入系を早期に停止し、再起動後も断続的に起動、停止を繰りかえしていること
(4)格納容器隔離が早く行われなかったこと
(5)一次系ポンプを停止させたこと
等があげられる。この中には(4)のように設計方針に関連するものもあるが、運転員の処置が、軽水炉に本質的に要求される“冷却水の確保”の点から考えて不適当であったものが多い。 TMI-2号炉の運転員の資格、経験等或は事故当時の人数、配置等について現在必ずしも明確になっていない。また、事故時あるいはその後の運転員が如何なる論理的根拠にもとづいて判断し処置を行ったかについても充分明らかにされていないが、これまでの調査では事故後数時間にわたって状態が悪化して行くなかで、運転員が事故を防止し、あるいは軽減化するために必要な情報は殆んどすべて制御室に存在したと考えられる。しかし運転員はプラントで何が起っているかを正確に認識していなかったといわれている。 この原因としては事故後制御室内で部屋一杯にライトが点滅し警報ブザーがなり、更には運転員にとって相互に予知する情報もあり、いわゆる“hassle factor”の状態が存在して正確な判断の妨げとなったともいわれている。この中で運転員は日常の通常運転時の訓練の中心であった“加圧器水位の制御”の最大の関心を払ったといわれており、これが結果的に事故を拡大したと考えられる。 プラントで何が起っているかを知るうえで必要な情報は制御室に存在したにもかかわらず、運転員がそれを認識しなかった事情を次に示す。 はじめに“加圧器逃し弁を閉じよ”との信号が発せられ、運転員はバルブ位置指示用の温度計を見たが、バルブから連続して一次冷却材が流出していることを確認するだけの温度になっていなかったため、閉じていない。これはバルブが“部分開”の状態であったためかとも考えられるが、その他ドレンタンクの圧力指示、特に逃し弁開やラプチャーディスク破壊等によって確認出来た筈で2時間にも亘って開いたまま放置していたのは理解しにくい点である。 次に、加圧器圧力が異常に低下していることについても充分な関心を示さず、加圧器水位の調節を優先させたことが、高圧注入系を早期に止めることにつながっている。運転員は連続的な減圧によっても加圧器以外に蒸気泡が生成するとは考えなかった模様で、その後高圧注入系を何回も起動、停止を繰りかえしているが、水位調節のためバルブを絞った疑いが強い。 一方、格納容器内で水素の爆発あるいは燃焼が生じ、その記録が圧力計に28psiとなって表れているのに、だれかがこれを急いで巻込んでしまったため、2日間もこのことに気がつかなかった。これが炉内でジルコニウム水反応が大巾に生ずる程炉心損傷が進んでいるのを気付かず放置する結果となった。 さらに炉心モニター用の炉内熱電対52本のうち中心近傍のものがシステマティックな挙動を示していたのに何故か無視した。このことは炉心が飽和状態にあることの認識を遅らせた。 このように運転員が事態を充分認識出来ていなかったことが不完全な情報を生み、そのため、“水素爆発による格納容器破壊の危険性がある”という本来存在しえなかった情報を生み混乱をもたらした。 運転員の処置が不適当であったことは当然運転員の資質に関わる部分も多いことになろうが、従来の教育運転訓練の方法、必要経験、および制御室内の人員、機器の配置の仕方、信号の数、種類、優先順序等について検討の余地が多く残されていると云えよう。 3.1.3 事故再発防止対策
TMI-2事故を悪化させた原因としてその主なものをひろってみると
(1)補助給水系作動が遅れたこと
(2)加圧器逃し弁が閉じなかったこと
(3)高圧注入系を早く切りすぎたこと
(4)格納容器隔離が早い時期に行われなかったこと
(5)一次系ポンプを停止させたこと
(6)加圧器水位の維持に運転員訓練の中心があったこと
等があげられる。これらは種々な面から検討が加えられるべきだが、米国原子力規制委員会(NRC)は、この種の事故の再発を防ぐために、短期的対策と長期的対策を行うことにしている。 短期的対策は、IE BulletinやNRR Status Reportに示され、原子炉メーカーであるB&W社、CE社、WH社、GE社とそれ等の原子炉を所有する電力会社にその検討を命じた。 これに対しB&W社設計の炉の所有者である電力会社の対応は次の通りである。 (1)2次系の異常に対してスクラム回路を設けて即応性を良くする。 (2)小冷却材喪失事故に対して充分な解析を行う。 (3)小冷却材喪失事故解析に基づいて安全確保のための運転要領を作る。 (4)運転要領としては以下の事項を含める。 a 運転員が小破断を認識する方法および他の似たものと区別する方法
b 運転員が小破断を理解し適当な処置を行う上での手助けとなるような予想されるプラント応答
c 運転員が小破断事故を軽減し安全に処理するために必要な注意および処置(自然循環確保等)
(5)運転員の再訓練はB&W社のシミュレーターを用いて行い、TMI事故についての訓練を受け、ライセンスを持つ運転員を最低一名制御室に入れる。 NRCは4月27日の委員会において以上の改良が行われるまでB&W社製炉は運転を停止することになり、Oconee No.3.Rancho Secoは4月28日、Oconee No.1.No.2は5月12日および19日に停止する。 又、現在停止中のプラントも上記対策が終了する迄停止状態におくことを命じることにした。 なお、WH社、CE、GE社設計炉については検討が進められている。また、長期的対策についてもNRCスタッフ、原子炉安全諮問委員会(ACRS)等を中心に議論が行われている。 3.1.4 TMI-2プラントの長期管理
TMI-2プラント事故の終結は炉を冷態停止に導き、その状態で崩壊熱除去を長期間に亘って行うことによって達成される。 崩壊熱の減少と共に炉の冷却は一次系循環ポンプを停止した状態での自然循環冷却に移行する。 長期冷却のための作業として多重性の確保のためA、B蒸気発生器につながる二次側の改造が行われた他、崩壊熱除去系の改良も行われた。 冷態停止に向けての作業は4月13日に先ず炉内のガス抜きから始り、ガス抜きサイクルを行った後、温度を下げて来たが、4月27日になって加圧器の水位計がすべて使用不能になったため、予定を早めて1次系ポンプを停止し自然循環による冷却モードに入ったが、2次側は蒸気がタービンバイパスを通ってコンデンサに導かれ冷却が行われている。4月30日現在このモードによる冷却が続けられている。 3.1.5 原子炉炉心損傷の推定
炉心の損傷状況については、NRCでもまだ本格的な調査は行われておらず推定の域を出ていない。今後の本格的調査、さらには実物の確認(可能な時期は不明)によって正確な情報がうられることを期待するがとりあえずこれまでにNRCから予備的な情報としてえたものを取りまとめる以下のとおりである。 TMI-2炉では核分裂生成物の放出、水素の生成等、原子炉の炉心に損傷が起っていることを示す徴候が見られる。これまでにえられている温度記録放出された核分裂生成物の推定量、発生水素の推定量をもとにすれば炉心損傷の様子を大雑把に推定することができる。 事故記録から炉心の露出は事故中3回に亘って生じており各々数10分から数時間露出状態が継続したと考えられ、その間炉心は崩壊熱により加熱されていたと思われる。燃料棒は大幅に破損してガス放出を生じておりこれは膨張-破壊ballooning-and-ruptureによる損傷と考えられる。燃料棒の状態を核分裂生成物放出量と発生水素量から推測する。 (1)Xe-133放出量による推定(Xe-133は不活性ガスなので推定がしやすい)
Xe-133放出量
Bettis(BAPL)の測定では、炉心内保有量の約30%が放出(NRCのチェック計算も同様)しており、Xe-133はギャップだけでなくベレットからも放出されている。ベレットからの放出は温度依存性が強いので放出量と温度との対応が可能である。炉心温度を一様とすればこれは1750℃に相当する。 (2)発生水素量による推定
炉心での水素の発生はジルコニウム-水反応によるものが大部分で水の放射線分解によるものを考慮して水素量は次のように推測されている。 (a)格納容器内で爆発又は燃焼で消費された量 100㎏
(b)格納容器内にその後残存した量 35㎏
(c)圧力容器内バルブ中の水素 35㎏
この合計水素量は水の放射線分解によって生じた水素量を考慮に入れて、燃料領域のジルコニウムが約40%酸化したことに対応する。 この結果から、燃料棒上部1.5m程度は相当破壊されたfragmented領域と推測される。 下部には1.2~1.8mの完全な部分が存在すると考えられる。 尚、一次冷却材中の核分裂生成物を分析した結果、非揮発性のものが少く(Ba、Sr)、ウランも殆んど検出されていないところから燃料は一部数ミリからペレットそのまま位の大きさの破片debrisになって冷却材中に放出されていると考えられるが、燃料の溶融はなかったものと考えられる。このことは温度の評価からも推測される。燃料棒以外の制御棒バーナブルポイズン棒、出力分布調整棒、計測管などについては次のように推測されている。 燃料棒上部にある炉内熱電対は事故後大部分正常に作動していることから中央部の管形状は生残っている。 INELで案内管温度を計算した結果によると燃料棒温度に比べてわずか11℃しか低くない(B&Wの計算ではもっと低くなっている)。従って燃料が破損している領域では
(a)制御棒Ag-In-Cdとそのステンレス被覆はとけている。 (b)ジルカロイ管内管が酸化している。 (c)バーナブルポイズン棒のジルカロイ被覆が酸化している。 しかし、Ag-In-Cdは不溶性であること、又冷却材中に銀が検出されていないことを考えると制御棒セグメントは仮に溶融したとしても7~8㎝程度落下しただけで、吸収体はおそらく元の位置にあると推測されている。 バーナブルポイズン棒もおそらく元位置にあると考えられるが、ボロンはB4C-Al2O3から溶出している可能性がある。 3.2 環境への放射能の影響
3.2.1 環境への放射性物質放出量
放射性ガスおよびヨウ素等の現在まで(4月15日頃)の環境への放出量は次のとおりである。これらの値は環境におけるモニタリング結果にもとづいて推定されたもので、希ガスについては、熱螢光線量計TLDによる線量測定値と気象条件とから逆算されたものとされている。 (a)希ガス 数百万キュリー
(b)I-131 数キュリー(10キュリーに近い)
(c)Cs-137 無視できる程度
放出性ガスの大部分がXe-133(TL=5.29日、Eγeff=0.045MeV)とされているので、Eγ=0.5MeV換算
放出量は、
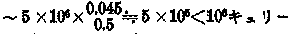 となる。 なお、補助建屋のベント・スタッフ(主な放出源)の排気中のI-131濃度の4月10日以降の測定値(活性炭カートリッジにサンプリング測定)が公表されている。その値を要約すると次のとおりである。 4/10:2.3×10-8μCi/㎝3
4/11~4/20:6.6×10-8~4.5×10-7μCi/㎝3
4/21~4/23:1.1×10-8~1.4×10-7μCi/㎝3
4/24~4/30:7.4×10-9~4.9×10-8μCi/㎝3
スタッフの排風量が不明であり、上記の値から放出量を算出することはできないが、上記の値から全期間のI-131放出量は10キュリーを超えることも考えられる。 なお、排気系のTrain A活性炭フィルターの交換作業が4月12日~19日の間行われたが、これがこの期間におけるI-131の放出量の増加の一因と推定されている。 3.2.2 環境モニタリング活動
(1)活動、人員、機器等
連邦政府各機関および州(ペンシルバニア州ほか周辺の州)が、環境モニタリングを実施した。 環境モニタリングに従事した人員(現地)は、州15人、DOE40人、EPA17人、HEW10人、NRC10人である。 また、TMIサイトに集められた装置の主なものは次のとおりである。
他にEPAは31地点にrエリアモニタ、ダストおよびヨウ素サンプラ、TLDから構成される測定器セットを設置した。 (2)DOEの分担と主要機器
DOEは、緊急時の環境モニタリング活動についても中心的役割を果し、Interagency Radiological Assistance Plan、(IRAP)に基づいて次の機関がそれぞれの分担作業を行った。 a)BNL:Radiological Assistance Planに基づいてRegion I、すなわち北部11州で発生する放射線事故に対し、実際の事故時モニタリングとその処理、または技術的援助の責任を有しており、現地に出動し環境モニタリングを実施した。 なお、BNLでは24時間の緊急時に対する当番責任者が定められているほか、可搬型キットおよびトレーラーが常時準備されている。 b)航空放射線システムAerial Measrement System(AMS):EG&G社による飛行サーベイシステムで、飛行機3機とヘリコプター4機(Hughes H-500、Boeing Bo-105各2機)を有し、放射線測定器を装備している。機上では出力が磁気テープに記録され、地上で計算機により解析される。 各原子力サイトにおいては、プラントの稼動前に航空写真をとるとともに、飛行(通常高度500ft)によるバックグランド放射線量率の測定が行われ、等線量線図が作図されており、事故時の測定との比較に用いられる。 c)大気放出助言能力Atmospheric Release Advisory Capability(ARAC):ローレンスリバモア・ラボラトリーが担当しており、①空軍による地球全体の気象データと②各サイトにおける局地的気象データとから計算機による気象予測と風下の濃度分布の予測を行う。 d)その他の機関:DOE Environmental Laboratoryによる環境試料の分布のほか、ORNL、SRLなど他の研究機関が応援活動を行う。 3.2.3 環境モニタリング結果
(1)外部被曝線量
外部放射線量については、熱螢光線量計(TLD)、地上走行サーベイ、31地点に設置されたガンマ線量率測定用モニタ等による測定のほか、放射性雲中線量率の測定値からの推定も行われているが、TLDによる測定値が他の測定値から算出され、公表されている。 a)TLDによる測定
NRCによる測定は次により行われた。 ① 3月29日 15:00時(事故後32時間)にサイト周辺15マイル以内17カ所に設置されていたTLDが回収された。(このTLDは1979年第1・四半期間線量測定用のもので事故後32時間照射されている)
② その後NRCによって1~12マイル内、37個所にTLDが設置され、第1回のTLD回収調査は4月1日に行われた。1個所に1日ごとの線量読取り用と長期間の線量読取用がセットで配置されている。 また、4月5日付近の学校、10個所にTLDが追加され、以後47個所で測定が行われた。 b)TLDによる測定結果
測定結果は次のとおりである。 ① 事故後32時間までの線量
居住区域の最大:26-15=11mR
North Bridge(プラントの北北東0.3マイルでは)
44-15=29mR
(注:15mRは3カ月のサイト周辺の通常のバックグランド値)
② 敷地外(サイト境界)における最大積算線量(4月7日まで)
3月28日から4月7日まで敷地外居住可能区域に最も近い場所0.5マイルに裸で連続的に立っている個人の最大推定被曝線量は約100ミリレム以下(測定値は83ミリレム、DOEレポート4月14日付で95ミリレム、4月23日付証言では85ミリレム)
放出放射性希ガスの大部分がXe-133であることから、その放出放射線エネルギーに対する感度に問題があり、校正が行われている。本測定値には、β線の寄与も含まれているが、その割合についてはNBSで検討中である。 ③ 居住区域における積算線量
居住区域の積算量線(3月29日~4月6日のNRCの測定)と事故後32時間までの積算線量(設置者の環境モニタリング用TLDによる)の和及びNRC職員の説明等から、居住区域における最大線量は30~50ミリ・レントゲンと推定される。 ④ 集団線量評価値
50マイル以内の住民(約200万人)の集団線量は、NRC、EPA、DOEによって評価されているが、その値は3,300(1,600~5,300)人・レム(4月23日付議会証言によれば3,550人・レム)である。 c)地上放射線量率の測定
NRCのモニタリング車などにより、地上における放射線量率の測定が行われている。(測定結果省略)
(2)飛行サーベイ
DOEのARMSが、ヘリコプター等を用いて放射性雲の追跡測定を実施している。 その測定内容は
a)放射性雲の大きさ(長さ、幅)
b)放射性雲の移動方向
c)放射性雲中線量率
d)放射性雲放射能濃度である。(測定結果省略)
(3)環境試料の測定
環境試料については、ペンシルベニア州他隣接州、FDA、EPA、DOE、NRC等によりサンプリング測定が行われている。 a)ミルク
主として牛乳であるが、羊のミルクも含まれる。 ミルク中のI-131濃度の最大値は41pci/l(やぎのミルク値)であった。これは小児甲状腺に対し0.2ミリ・レム/日に相当する(Regulatory Guideに示されるDose Factorに基づく)。 b)その他の環境試料
空気、野菜、牧草、表面水、土壤について測定が行われている。 空気については、EPAにより31地点に設置された空気サンプラや、NRCによりオブザベーション・センターおよび居住区域において空気サンプラによる補集試料の測定が行われている。 (測定結果省略)
3.2.4 全身カウンタによる住民の内部被曝検査
NRCの要請により1台の全身カウンターがペンシルベニア州によって4月10日ミドルタウンに設置された。4月10日16時よりサイト付近の住民の検査が行われ、4月18日までに3マイル以内に居住する住民721人の検査を完了し、バック・グランドレベルを越える値は検出されなかった。 3.2.5 TMI従業員およびNRC職員の被曝線量
4月26日までのTMI職員(Contractor従業員を含む)の全身被曝線量の内訳は次表に示すとおりである。 なお、3レム以上の被曝者のうち、2名(運転員と化学者)については、3月29日に1次冷却水サンプル採取時に補助建家内で被曝(それぞれ3.1レムと3.4レム)したものである。 個人被曝線量(原子炉設置者)(4月26日現在) 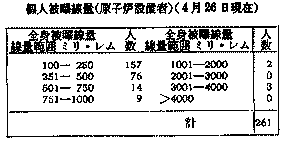 4.緊急時対策
4.1 緊急時計画の作成者
(1)電気事業者は原子炉サイトの緊急時計画を連邦規制10CFR50E′にもとづいて作成する(10CFR50E′の適用の仕方はRegulatory Guide 1.101に与えられている。)
NRCの担当者は「電気事業者の緊急計画と州の同計画のつなぎが重要であり、NRCとしては州と電気事業者間の合意書簡によってこれをチェックしている。」旨述べている。なお、これに関してペンシルベニア州の担当者によれば、州と電気事業者との間で四半期に1回程度会合を持っている由である。 (2)州と郡(カウンティー)は原子炉サイト外の緊急時計画を作成する。ただし、州と郡(カウンティー)は法律にもとづいて計画を策定するわけではなく、住民の健康と安全を守るための措置として作成している。(原子力災害以外の災害に対しても緊急時計画を持っている。)
NRCの担当者によれば、米国では28州に原子炉があり、6州は原子炉に隣接しており、合計34州が緊急時計画を持っている。連邦政府は州に対して指示する法的権限はなく州政府の協力的、自発的な態度によって連邦と州の関係が保たれている。大部分の州は連邦政府に対して協力的であるが、若干の州は連邦政府に対して懐疑的であるとのことである。NRCは11州(ペンシルベニア州を含まず)から緊急時計画について助言を求められた。 ペンシルベニア州では2機関が緊急時計画に関与している。 ① PEMA(Pensylvania Emergency Management Agency)ペンシルベニア緊急管理庁、ハリスバーグにあり、計画全般担当。 ② Environmental Resource Dept,Radiological Assessment Branch環境局放射線評価部、ハリスバーグにあり、放射線に関する評価を行いPEMAを支援する。 郡(カウンティー)にはEmergency Operation Center緊急時運営センターがある。郡(カウンティー)は退避に責任を有し、州は緊急時計画全体の調整に責任を有する。つまり具体的に緊急時対策を実施するのは郡(カウンティー)である。但し、交通手段、物資等について州は郡(カウンティー)を援助する。州でカバーしきれない分は連邦政府の援助に頼ることになる。 (3)連邦政府は州政府に対してガイダンス、訓練及び、現場支援を与える。連邦政府のうち緊急時計画に関与する機関は次の8機関でNRCは計画を作成するうえでの指導的な機関である。 ①NRC原子力規制委員会 ②EPA環境保護庁 ③HEW健康、教育、福祉庁(FDA:Food and Drug Administration,BRH:Bureau of Radiological Health) ④DCPA(Defence Civil Preparedness Agency) ⑤DOT(Department of Transport)運輸省 ⑥FDAA(Federal Disaster Assistance Administration)連邦災害援助局-大統領が国家災害national disasterを宣言した場合家屋のそう失等に対して資金を与える。⑦FPA(Federal Preparedness Agency)-緊急時について全般的にコントロールする。 ⑧DOEエネルギー省(RAP:Radiological Assistance Program BNL,IRAP:Interagency Radiological Assistance Program)-放射線支援チームを現地に派遣し、監視、評価を行う。 連邦政府の放射能に関するガイダンス
(1)ガス状プリュームからの全身および甲状腺被曝の回避のための防護活動
(勧告) 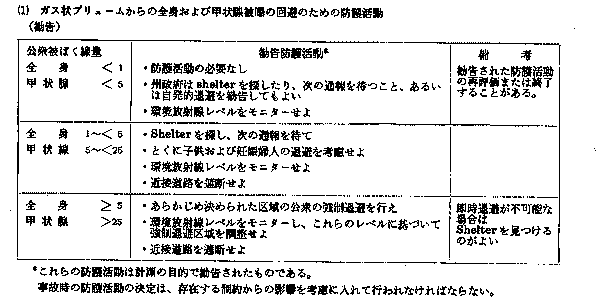 (2)牛乳の汚染による甲状腺被曝回避のための防護活動
12,000ピコキュリー/lを超えた場合には牛の餌を干し草等の貯蔵飼料とする。 120,000ピコキュリー/lを超えた場合には牛乳製品(チーズ等)とし、直接飲用しない。 連邦政府提供の訓練
緊急時対策に関し次のような訓練コースが開かれており、これまでに約1,000人の緊急時対策要員を無料で訓練した。 ① 計画コースPlanning Course
② 対応調整コースResponse Coordination Course
③ 放射線緊急対応運営コースRadiological Emergency Response Operation Course
4.2 緊急退避
(1)退避計画
ペンシルベニア州及び関係する3つの郡は事故発生前にサイトから5マイル以内の地域についての避難計画を持っていた。ところが、30日になって20マイルまで及び10マイルまでの退避計画を作ることとなり、急きょ作成された。関係する郡の数は3から6に増加した。5マイル以内には病院等はなかったが、20マイルともなれば、病院等退避上厄介な施設が多く、計画の作成を困難にした。 退避計画の策定段階でNRCは州に対して5マイルまでは全方向とし、それ以遠については必要に応じて10-15-20マイルの各々の範囲まで風下方向90°の扇形の地域を退避させることを提案したところ、州は、この季節は風向が一定していないとの理由で扇形地域ではなく全方向を対象とすべきであるとした。 州は退避に要する時間を5マイルまでの場合約3時間、10マイルで約7時間、20マイルで約10時間程度と見積った。今回の事故の際のミドルタウン等の住民の退避についてはとくに時間がはかられたわけではないが1~2時間程度でほぼ終了したと州はみている。 (2)退避
3月30日午前、州知事は10マイル以内の住民の屋内待機(Take Shelter,Stop Ventilation)を勧告した。また、午後、5マイル以内の妊婦と未就学児童の退避を勧告し、28の学校の閉鎖を行った。これは、放射性ガスの放出を制御できなくなる恐れがあったことが一因となっている。 この勧告は、NRCヘンドリー委員長の州知事に対する勧告及び州の健康省長官、州知事のプライベートな医者等のコンサルタントに相談した結果にもとづいている、いずれも、直ちに退避すべしとの意見ではなかったが、結局予防的な手段として、一部住民の退避を勧告することとなった。 NRCの担当者によれば「州知事が一部住民の退避、つまり未就学児童と妊婦のみの退避を勧告(命令ではない)したことについては州内部に一部批判がある。多くの人々が、幼稚園児は退避を要するのに小学1年生はしなくて良いのか等の疑問を持ち自発的に退避してしまった。風が北向きであったため、風下のミドルタウンの人は殆んど100%退避し、この町はゴーストタウンと化し、5マイル以内では約50%の人が退避した。約10マイルのハリスバーグの人もかなり退避した。20マイル以内の人口は約63万人であるが、10%程度の人が退避した模様である。」とのことである。 (3)退避の通報
州は緊急避難の住民への通報をハリスバーグにあるラジオ、テレビ放送局によって直ちに行う。深夜のラジオ、テレビの放送時間帯以外の時には、警官やボランティアーがドアをノックして歩くこと等により連絡される。 郡はラジオ、放送局との間に直接電話を設定しており、住民にラジオを通じて連絡する。 4.3 緊急連絡
電気事業者は事故を州と郡(カウンティー)に通報し、かつ、とるべき措置を勧告する事になっている。今回は4時に事故が発生してから7時迄通報せず、また勧告もしていない。 州は7時頃電気事業者から事故の通報を受け、直ちに関係の郡(カウンティー)に通報した。ペンシルベニア緊急管理庁は7時半に機能を開始した。 同庁は職員を関係郡(カウンティー)に派遣した。 電話回線が完全にふさがってしまったがNRCは何とか州との間にオープンラインを設定した。その後電話局の人がオープンラインを確実なものにした。 NRCの担当者によれば、オープンラインを主要な機関の間で設けることは是非必要であり、緊急時には電話の技術者が重要な役割をしめるとのことである。 4.4 モニタリング体制
時期によって増減はあるが、当初州:15人、DOE:40人、FDA:17人、HEW:10人、NRC:10人でモニタリングが実施された。 初期には誰が全体の調整をするか、不明で混乱し、サンプルを取った時期も場所も不明なものがあった。州は電話の対応等に時間をとられ、連邦政府機関の支援がなければどうにもならなかった。 連邦政府各機関間の調整もこれまでに経験がなく初期は混乱した。又州と連邦政府機関との調整も初期はうまくいかなかった。サンプリングは、3月30、31日頃からうまくいく様になった。 DOEは事故当日午後2時、現地に到着し、“AMS”航空放射線測定システム(Aerial Measurement System)によってサイト周辺の飛行測定を開始した。なお、AMSはプラントの運転開始前にバック・グランドを調査し、放射能マップを作成している。 BNLとNRCの放射線支援チームも現地に到着した。 州は事故発生後直ちに表面汚染計及び空間線量率計により、測定を行ったが、機器は連邦機関にくらべてそれほど整っていない。中国の核実験の際も州は測定を行っている。ライセンシーも環境測定を行っており、結局ライセンシー、州、NRC(連邦各機関を統括)の3つの機関がモニタリングを実施した。 4.5 甲状腺被曝低減対策
FDAは甲状腺被曝低減の為沃化カリKIを服用することが有効であるとしており、今回の事故の為に早急に準備された。多くの製薬会社にあたり、1社が緊急製造を引き受けた。 11,000本の小びんに入った液体沃化カリ(44,000人10日分)が用意され、州に送り込まれた。沃化カリについては配布による心理的な影響が考えられる他に副作用もあるのでその使用には慎重を要する。今回は実際には使用されていない。ライセンシーもプラントに従事者用のものを持っている。沃化カリの配布は使用されることになれば市民防衛のボランティアーに期待することとなるようである。 5.米国の事故への対応策
5.1 事故への対応
(1)3月28日:午前4時(現地時間)トラブル発生
○6時20分ライセンシー(原子炉施設運転者)“Site Emergency”発令(燃料破損が明らかとなったため)。7時“General Emergency”発令。州政府へ通報。 ○7時45分NRCのRagion I事務所に通報、30分以内にNRCの事故対応センターIncident Response Center活動開始
○9時15分ホワイトハウスが通告を受ける。 ○10時05分第1次NRCチーム(5人)がサイト到着
○10時15分NRC委員説明聴取
○10時30分NRC第1回の事故状況発表
○午後よりブルックヘブンのチームがサイト近辺のモニタリング開始、またAMSの飛行機サイト着
○夕方NRCのRegion I事務所より測定車サイト到着
(2)3月29日:下院内務委員会エネルギー・環境小委員会(ユドール小委員長)が公聴会開催
(本小委員会では、NRCのヘンドリー委員長等から説明を聴取した。事故の発生から3時間45分後にNRCのRegin I Officeに通報があったことについて遺感の意が議員側より表明され、今後通報システムを改善し、緊急な場合は住民に早急に連絡できるようにすべきことが要請された。また、運転開始早々事故を起こしたことはNRCの審査に不備があったのではないかとの疑問が出され、ヘンドリー委員長は今後究明の過程で審査過程についても見直しをする旨述べた。)
(3)3月30日:午前州知事が周辺住民に戸内に留まるよう勧告
午後州知事が5マイル以内の就学前の児童及び妊婦に退去を勧告。また、5マイル以内の学校の休校を命令。(補助建屋にオーバーフローした一次冷却水よりの放射性物質の放出が28日以来あり、これをおさえられなかったこと及び30日朝放出が増加し、以後の放出の制御ができなくなる恐れがあったことによってNRCの勧告にもとづいて州知事がこの勧告を行った。)
○NRC原子炉規制局長ハロルド・デントンのサイト着
(4)4月1日:午後、カーター大統領が夫人を伴って現地視察(数10分間制御室にて説明聴取)その後ミドルタウンにて記者会見。 ○NRCにはB&W社に対し、同社製の7つの発電所の総点検を至急行い、10日以内に報告するよう指示(IE Bulletin 79-05)
(5)4月4日:上院健康・科学研究小委員会(ケネディー小委員長)が公聴会開催
(教育・保健福祉省のカリファーノ長官は、これまでの放射能被曝線量は最大80ミリレム程度であり、また周辺住民に対する集団線量から統計的にみてガン発生率を増加させるものではない旨述べた。放射性ガスの放出、低レベル放射性廃液(産業廃液)の放出の責任はNRCか、ライセンシーかについて議論され、ケネディ委員長はライセンシーが放出の決定責任をもっていることにつき改善が必要である旨述べた。モニタリングステーションについて、γ線量率計がサイト内にしかなくサイト外には集積線量測定用のTLDしか配置されていなかったことに関し議員の批判があい次いだ。)
(6)4月5日:NRCは事故の要因として人間の操作ミス、設計の不備、機械の故障など6つの指摘事項を発表(IE Bulletin 79-05A)
(7) 4月7日:ウエスチングハウス社は、同社設計炉の設置者に対して、加圧器水位計の問題等について通告
(8)4月9日:州知事は5マイル以内の就学前児童及び妊婦の避難勧告を解除し、翌日から学校の再開を発表
(9)4月10日:NRCは加圧器水位計の問題についてライセンシーにBulletinを出すことを発表
○上院原子力規制小委員長(ハート委員長)公聴会開催
(ヘンドリーNRC委員長は検査、安全関係の運転要件、設計標準等について不適当なところがなかったかチェックするか、現状では事故はプラントの設計に起因するよりも、むしろ、運転ミスによるものと判断しており、他のB&W社製炉の運転停止は必要ないと述べた。これに対しブラッドフォード及びギリンスキ両NRC委員は設計者が悪いか運転者が悪いかをきめるのは時期尚早であると述べた。加圧器の水位が必らずしも原子炉の水の総量を示していないこと、つまり、今回の事故のように炉容器上部に気相が存在することがあることについて検討の必要があることが指摘された。ヘンドリーNRC委員長は、緊急時に対処するための運転員の訓練、規制側、運転者、サポートチームの関係の再検討が必要である旨述べた。ハート小委員長は各原子炉にこれを監督するNRCの職員を配置することを立法化する考えを示唆した。)
(10)4月11日:NRCはWH社及びCE社設計の原子炉設置者に対し、事故の原因に関し11項目についてレビューし14日以内に報告するよう指示(IE Bulletin 79-06)
○大統領直轄事故調査委員会(11人)発足
(11)4月14日:NRCはIE Bulletin 79-06を改訂し、WH社及びCE社設計の原子炉設置者に対して点検・検討項目についてレビューして10日以内に報告するよう指示(IE Bulletin 79-06A、IE Bulletin 79-06B、なお06Aについては4月18日に改訂が出されている)。 NRCは、BWR設置者に対して11項目についてレビューし、10日以内に報告するよう指示(IE Bulletin 79-08)
(12)4月18日:ACRSはNRCに対して自然循環の重要性等を指摘した勧告を行った。 (13)4月21日:NRCはB&W社設計の原子炉設置者に対してIE Bulletin 79-05Aに追加して指示(IE Bulletin 79-05B)
(14)4月25日:NRCの原子炉規制部よりステータス・レポートが出されるとともに、同部スタッフはNRCに対して、B&W社設計プラントのシヤットダウンを行うよう勧告した。 (15)4月26日から27日にかけてB&W社製の原子炉を運転しているDuke Power Company,Sacramento Municipal Utility District,Arkansas Power & Light Company,Florida Power Companyはデントン局長あて、B&W社設計原子炉の改善計画を提出、うちDuke Power Co.及びSacramento Municipal Utility Districtは稼動中の原子炉を停止する旨申し出た。 (16)4月27日:NRCはB&W社設計のすべての原子炉の改善及び停止命令を出すことを決定。 5.2 法令との関係
原子力規制委員会は、2次冷却系の補助給水系の弁が閉じられていたことは技術仕様書違反であることは明らかにしている。その他の法的な責任問題に関しては未だ明らかにしていないが、この問題は今後の原子力規制委員会の調査により明らかにされるものと思われる。 6.我が国の対応
(1)5月1日:通商産業省は、大飯発電所第1号機の加圧器水位計に関連するECCSの解析結果に基づく措置について原子力安全委員会に報告。これを受け、原子力安全委員会は直ちに原子炉安全専門審査会に審議を指示、同日原子炉安全専門審査会発電用炉部会を開催し審議を開始。 (2)5月11日:原子力安全委員会は御園生委員及び田島委員を福井県大飯町等に派遣。 (3)5月14日:原子力安全委員会原子炉安全専門審査会発電用炉部会は「大飯発電所1号機の加圧器水位計に係る問題に関する通商産業省の解析結果及びこれに基づく措置は妥当である。」旨の報告をとりまとめ原子炉安全専門審査会に報告。(翌日同審査会は同報告を原子力安全委員会に報告)また、通商産業省は原子力発電所の再点検について原子力安全委員会に報告。 (4)5月18日:発電用炉部会は、「大飯発電所の管理体制の再点検について通商産業省の電気事業者に対する指示は妥当である。」旨の報告をとりまとめ原子炉安全専門審査会に報告。(同日同審査会は同報告を原子力安全委員会に報告。 (5)5月19日:原子力安全委員会は、大飯発電所1号機の加圧器水位計に係る問題に関し通商産業省の解析結果及びこれに基づく措置は妥当である旨決定、また、大飯発電所の管理体制の点検結果について通商産業省が関西電力㈱に対し指示することとしている改善措置は妥当である旨決定。 原子力安全委員会委員長は上記2つの委員会決定に関連し声明発表。 | ||||||||||||||
| 前頁 | 目次 | 次頁 |