| 前頁 | 目次 | 次頁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
被ばく線量登録管理制度のシステム構成及び運用について(最終報告) 昭和52年11月
原子力事業従業員被ばく線量登録管理制度検討会
原子力安全局長
牧村信之殿
原子力事業従業員被ばく線量登録管理制度検討会
座長 中戸 弘之
放射線従事者の被ばく線量登録管理制度については、昭和51年11月以来検討を重ね、昭和52年4月科学技術庁原子力安全局長に中間報告(大綱)を行った。 以降、科学技術庁原子力事業従業員被ばく線量登録管理制度検討会は、ワーキンググループを設け、より詳細なシステム構成及びその運用の具体策について鋭意検討を重ねてきた。 本制度に参加を予定される原子力事業者ならびに各業界等関係者との意見調整、放射線管理手帳制度との関係、体制制度面での整備等、なお今後の検討事項もいくつかあるが、本制度の早期実施を図ることが極めて重要であるとの観点に立って審議を進めた結果、本制度のシステム構成及び運用について、成案を得たので、ここに報告する次第である。 Ⅰ 基本的事項 1 用語の定義
本報告書の用語は次のように定義する。 (1) 登録管理機関--核原料物質・核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下規制法という)等にもとづき国が指定する被ばく記録の引渡しを受け、ならびに被ばく前歴把握上必要な記録の整理等を行なう機関。 (2) 原子力事業者(所)--規制法の適用を受ける事業を行なう者(所)。 (3) 原子力事業等--原子力事業者及び放射線管理手帳発効機関。 (4) 使用者--放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下障防法という)のRI等の使用者、販売業者、廃棄業者。 (5) 事業者--労働基準法上の適用事業に該当し、労働安全衛生法上の届出がなされている雇用者。 (6) 放射線管理手帳発効機関--放射線管理手帳の発効等を行なう機関。 (7) 従事者--規制法、障防法等で従事者とされた者。 (8) 随時立入者--従事者、一時立入者以外の者であって、規制法、障防法等の管理区域に、業務上立ち入る者。 (9) 一時立入者--見学、取材、視察等直接放射線作業を行なわない者で、年間の被ばく線量が0.5レムをこえるおそれがないと事業者が判断した者。 (10) 従事者等--従事者及び随時立入者。 (11) 登録--登録管理機関において所定データを電算機に投入すること。 (12) 保管--登録管理機関において引渡された被ばく記録等を保管すること。 (13) 過去分--本制度切替日以前の期間に所属することを示す呼称。 (14) 経過分--本制度切替日以降本格実施までの期間に所属することを示す呼称。 (注)本報告書における原子力事業者(所)、使用者、事業者、従事者、随時立入者とは、これらの者のうち、本制度に直接参加する者(例えば原子力事業者)及び直接参加する者との契約関係等により参加することとなった者(例えば原子力事業者から工事等を受注した者)をいう。 2 被ばく線量登録管理制度の基本的考え方
放射線被ばく線量の登録管理制度の基本的考え方については、昭和52年4月の中間報告により、明らかにしたところであるが、最終報告検討の段階において、さらに明確化されたものをふまえ、制度の基本的考えは、次の通りとする。 (1) 登録管理機関を設置し、放射線業務従事者、随時立入者の被ばく前歴把握の強化、ならびに放射線業務を離れた者の被ばく記録の散逸防止を図る。 (2) 被ばく前歴の把握は、本制度と有機的に結びついた放射線管理手帳によることを原則とする。 (3) 本制度は、当面規制法対象の事業者を主体として発足し、ちく次対象者の拡大を図る。 (4) 登録管理機関に登録、保管される被ばく線量記録は、当面規制法対象事業者の所内被ばく線量の記録とする。 3 登録管理機関の名称
財団法人放射線影響協会、放射線従事者中央登録センター(以下登録管理センターという)とする。 4 登録管理センターの組織と設備等 (1) 組織
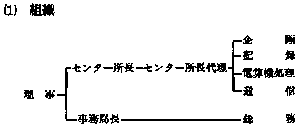 (2) 登録管理センターの設備等
a センター内において電算機の端末装置操作により、登録内容を検索する体制をとる。 b 原子力事業者等との情報伝送手段として、ファックスを設置する。 c 引き渡される記録を保管するための設備を置く。 5 登録管理センターの業務
(1) 規制法により原子力事業者から引き渡される記録の保管及びその一部の登録。 (2) 原子力事業者から報告された随時立入者の被ばく記録の保管及びその一部の登録。 (3) 障防法により使用者から引き渡される記録の保管及びその一部の登録。 (4) 原子力事業者等からの事前登録申請の受理、登録及びこれに基づく登録番号の付与と原子力事業者等への通知。 (5) 原子力事業者からの従事者等の指定登録及び指定解除登録。 (6) 原子力事業者からの従事者等の定期線量登録。 (7) 原子力事業者等からの個人の被ばく前歴の照会に対する回答。 (8) 放射線管理手帳の多重発行のチェックとその結果の原子力事業者等への通知。 (9) 放射線管理手帳発効機関の指定。 (10) 放射線管理手帳制度の普及推進。 (11) 前記各項に関連する必要業務。 ただし、(3)の障防法関係については、当分の間は「29.障防法対象事業者の取扱」に定めるところによるものとする。 6 原子力事業者の行なう業務
(1) 規制法に基づく記録の登録管理センターへの引渡し。 (2) 随時立入者指定解除時の記録の登録管理センターへの報告。 (3) 従事者等の個人識別事項の登録管理センターへの事前登録申請及びその結果にもとづく放射線管理手帳の発効。 (4) 原子力事業に関する建設、保守等の元請である放射線管理手帳発効機関の系列に属さない事業者の放射線管理手帳関係業務の助言、指導。 (5) 従事者等指定時及び指定解除時の記録の登録管理センターへの登録申請。 (6) 登録管理センターへの被ばく前歴の照会。 (7) 従事者等の被ばく線量の登録管理センターへの登録申請(定期)。 (8) 前記各項に関連する必要業務。 7 放射線管理手帳発効機関の業務
(1) 従事者等の登録管理センターへの事前登録申請、およびこれにもとづく放射線管理手帳(以下手帳という)の発効。 (2) 原子力事業に関する建設、保守等の元請である期間中の、系列事業者に対する放射線管理手帳業務の助言、指導。 (3) 前記各項に関連する必要業務。 (注)手帳発効機関とは、中間答申(52.4)にいうところのグループセンターである。 8 放射線管理手帳発効機関設置基準 (1) 設置基準
当面、放射線管理手帳委員会、将来は、設置の予想される放射線管理手帳制度協議会(仮称)で、手帳発効機関となることを希望する事業者を審査し、登録管理センターで指定する。 なお、選定の目安としては、
a 原子力関連大手総合メーカー等。
b 前項以外で、相当数の下請業者をもつ元請業者及びこれに準ずると考えられる機関。
c 原子力事業者ないしその委託業者。
が考えられる。
(2) 設置場所
手帳発効機関の具体的業務を実施する個所は、手帳発効機関として指定された事業者の本社およびその原子力工事地点、事務所、ならびに原子力事業者の本社および発電所等が考えられるが、具体的にどこに設置するかは原子力事業者等が個々に決定する。 Ⅱ 本格実施時における業務処理 9 事業所登録業務 (1) 事業所登録関係業務の概要
登録管理センターとのデータの送受信を行なう原子力事業者、手帳発効機関等はあらかじめ登録管理センターに対し、事業所関係項目の登録を申請。 登録管理センターは、これを受けて事業所番号を付番し、電算機投入を含む処理を行なう。 (2) 事務処理基準
a 登録管理センターとの間で、放射線被ばく線量の登録管理関係業務を行なおうとする事業所は、登録管理センターに対し、事業所関係項目(事業所の名称、所在地等)について事業所登録申請を行なう。 b 登録管理センターは、次の手順で業務を行なう。 ○ 事業所登録申請に際し、事業所番号を設定し申請者に通知した後、所定の受付手続を行なう。 ○ 申請内容を審査し、電算機に入力する。 事業所登録関係業務(フローチャート)
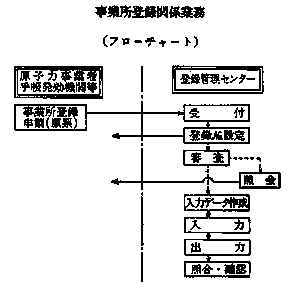 10 事前登録業務 (1) 事前登録関係業務の概要
放射線業務に従事することが予定される者について、事業者は、手帳発効機関に対し登録管理センターに対する個人識別事項の登録申請を依頼する。 登録管理センターは手帳発効機関からの申請に対し、電算機投入を含む処理を行ない登録番号を付番し、手帳発効機関に通知する。 手帳発効機関は登録番号を手帳に表記することにより手帳を発効させる。 (2) 事務処理基準
a 手帳発効機関は事業者の要請にもとづき、登録管理センターに対し個人識別事項(氏名、生年月日等)についての事前登録申請を行なう。 b 登録管理センターは、次の手順で業務を行なう。 ○ 事前登録申請に対し所定の受付手続を行った後、申請内容を審査し、可とした場合は電算機に入力する。 不可の場合は申請元に照会し必要に応じて申請の再提出を求める。(以下、登録関係業務において、不可の場合は、本取扱いに準ずる)
○ 電算機処理完了後、申請元に所定の手続により処理の結果(登録番号付番)を通知する。 c 手帳発効機関は、登録管理センターからの通知にもとづき、手帳に登録番号を表記し、手帳を発効する。 d 手帳発効機関は、事前登録の前、事前登録と同時又は事前登録不可の通知を受けた後、必要に応じて対象者の被ばく前歴の照会を行なうことが出来る。 事前登録関係業務(フローチャート)
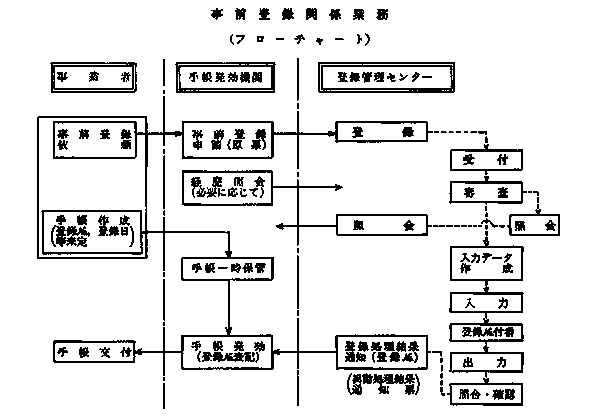 11 従事者等の指定登録業務 (1) 指定登録関係業務の概要
原子力事業者は、原子力施設等において、放射線被ばくをともなう業務に従事する従事者等の指定に関し、その記録を登録管理センターへ通告する。登録管理センターは、これを受けて電算機投入を含む処理を行なう。 (2) 事務処理基準 a 原子力事業者は、登録管理センターに対し、従事者等に指定した者について、指定登録申請(従事者指定年月日等)を行なう。 b 登録管理センターは、次の手順で業務を行なう。 ○ 指定登録申請に所定の受付手続を行なった後、申請内容を審査し、可とした場合は、電算機に入力する。 ○ 電算機処理完了後、申請元に所定の方法により処理の結果を通知する。 従事者等の指定登録関係業務(フローチャート)
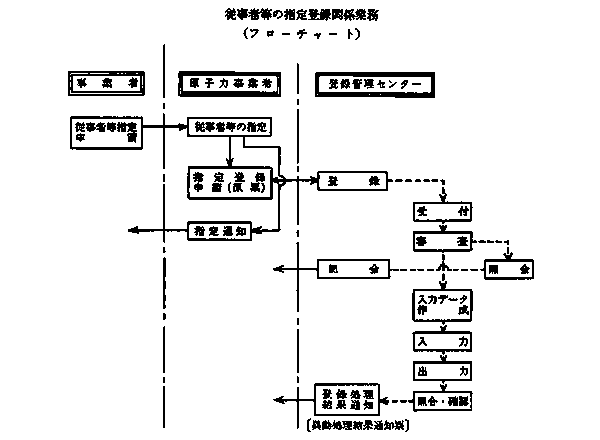 12 従事者等の事前兼指定登録業務 (1) 事前兼指定登録関係業務の概要
予め事前登録を行なう時間的余裕のない場合の例外的取扱いとして、原子力事業者等が登録管理センターに対し、従事者等の事前登録と指定登録の申請を同時に行い、登録管理センターはこれを受けて、電算機投入を含む処理を行ない、登録番号を付番し、申請者に通知する。 原子力事業者等は、登録番号を手帳に表記し、手帳を発効させる。 (2) 事務処理基準
a 原子力事業者等は事前登録をしていない者を従事者等に指定する場合は、例外的扱いとして、登録管理センターに対し、従事者等の事前登録、指定登録の手続に準じた事前兼指定登録申請を行なう。 b 登録管理センターは、次の手順で業務を行なう。 ○ 事前兼指定登録申請に所定の受付手続を行なった後、申請内容を審査し、可とした場合は電算機に入力する。 ○ 電算機処理完了後、原子力事業者等へ所定の方法により処理結果を通知する。 c 原子力事業者等は、登録管理センターからの通知にもとづき手帳発効を行なう。 従事者等の事前兼指定登録関係業務(フローチャート)
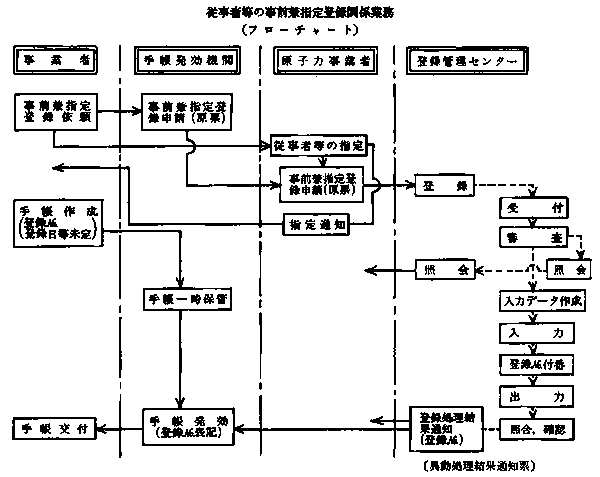 13 従事者等の指定解除登録業務 (1) 指定解除登録関係業務の概要
原子力事業者は、従事者等の指定解除を行なった場合は、指定解除の記録を登録管理センターへ通告し、登録管理センターはこれを受けて電算機投入を含む処理を行なう。 (2) 事務処理基準
a 原子力事業者は、従事者等の指定解除を行なった者について、後述の公文報告等を行なう際、登録管理センターに対して指定解除登録申請(従事者指定解除年月日等)を行なう。 b 登録管理センターは、次の手順で業務を行なう。 ○指定解除登録申請に所定の受付手続を行なった後、申請内容を審査し、可とした場合は、公文報告等と同一の整理番号を付し、電算機に入力する。 ○ 電算機処理完了後、申請元へ所定の方法により処理の結果とともに、公文報告等受理番号を通知する。 14 規制法にもとづく公文報告業務 (1) 公文報告関係業務の概要
原子力事業者は、従事者の指定を解除した者について、法令にもとづき、従事期間中の記録を登録管理センターへ引渡す。 (以下公文報告という) 登録管理センターは、引渡された記録について、以後整理・保管にあたる。 (2) 事務処理基準
a 原子力事業者は、従事者の指定を解除した場合、法令に従い記録をとりまとめ、報告すべき事業者(所)公印を押印した引渡書を付して登録管理センターに報告する。 この場合、公文報告の報告様式は正副2通とし、本制度で制定する報告書による以外、提出者の任意の様式によることも出来ることとする。 b 登録管理センターは、次の手順で業務を行なう。 ○ 公文報告(指定解除者線量記録報告書)を審査し、所定の受理手続により、受理番号の付番を行なう。 ○ 報告書(正副2通)は、正を保存用、副を被ばく経歴等の照会、回答用として、各々整理、保管する。 整理保管方法は、当面ファイリングシステムによる。 ○ 報告書が整理保管されたならば、報告受理の通知(異動処理結果通知……指定解除の結果通知による)を報告元に送付する。 c 公文報告の内容
○ 報告区分--法令の別ならびに従事者等の区分。 ○ 指定期間中の3か月線量(全身)--4月1日、7月1日、9月1日、1月1日を始期とする3か月線量。 ○ 指定期間中の年間線量(全身)--4月1日を始期とする年度内線量。 ○ 指定期間中の集積線量(全身)--従事者等指定時の前歴線量に指定期間中の総線量を加えたもの。 ○ 指定期間中の局部線量--皮ふ、手足等に区分 4月1日、7月1日、9月1日、1月1日を始期とする3か月線量。 (注)線量記載の際は、検出限度以下線量(X)の回数をも記入する。 ○ 内部被ばくの状況--吸入、嚥下の区分。 ○ 従事者等指定時の前歴線量--従事者等指定時に把握した集積線量(全身)
従事者等の指定解除登録と公文報告等関係業務(フローチャート)
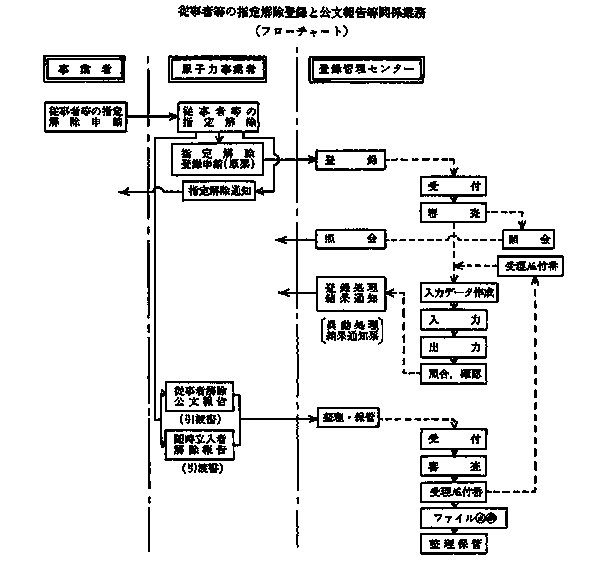 15 随時立入者指定解除報告業務 (1) 随時立入者指定解除報告業務の概要
原子力事業者は、随時立入者の指定を解除された者の指定期間中における被ばく線量記録等について、登録管理センターへ引渡す。(以下随時立入者報告という)。 登録管理センターは引き渡された記録について、以後の整理、保管を行なう。 (2) 事務処理基準
a 原子力事業者は、随時立入者の指定を解除した場合、その指定及び解除の年月日、指定期間中の被ばく線量等をとりまとめ、引渡書を付し、登録管理センターに報告する。報告様式、部数等については、公文報告の場合に準ずる。 この場合、随時立入者の被ばく線量記録の有無にかかわらず報告するものとする。 b 登録管理センターにおける受理、整理保管、報告元への通知等の業務手順は公文報告(従事者)の扱いに準ずる。 16 定期線量登録業務 (1) 定期線量登録関係業務の概要
原子力事業者は毎年4月1日を始期とし、翌年3月末日までの一年間について、その間に従事者等の指定を解除された者及び3月末日現在従事者等として指定登録されている者の当該年度内の線量記録について、毎年6月末日までに登録管理センターに提出し登録を申請する。登録管理センターはこれを受けて電算機投入を含む処理を行なう。 (2) 事務処理基準
a 原子力事業者は、従事者等で指定解除のある者については当該原子力事業所における指定期間中の指定解除のない者については当該原子力事業所における年間の総線量等所定事項について、定期線量登録申請を登録管理センターに行なう。 b 登録管理センターは次の手順で業務を行なう。 ○ 定期線量登録申請に所定の受付手続を行なった後、申請内容を審査し可とした場合は電算機に入力する。 ○ 定期線量登録の個人毎の処理結果についての提出者への通知は行なわない。 定期線量登録関係業務(フローチャート)
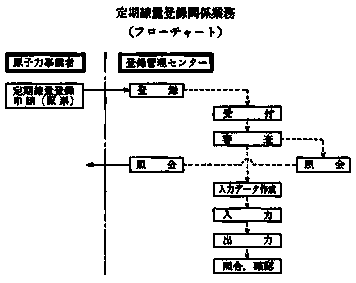 17 経歴照会、回答業務 (1) 経歴照会、回答業務の概要
原子力事業者、手帳発効機関、事業者、および本人は、登録管理センターに保管、登録されている事項の照会を行ない、これをうけて登録管理センターは回答を行なうことが出来る。 ただし、照会、回答の対象期間は、原則として、照会日以前2か年とするが、特に必要がある場合は、それ以前に遡ることも可能とする。 (2) 事務処理基準
a 原子力事業者は、自社の従事者等である者、従事者等であった者および従事者等として指定しようとする者について被ばく記録等の照会(公文報告等、非登録事項を照会する場合は、公文報告等写交付要請)を行ない、登録管理センターに対して、回答を求めることが出来る。 b 手帳発効機関は、当該機関で事前登録をした者および事前登録をしようとする者について被ばく記録等の照会を行ない登録管理センターに対し、回答を求めることが出来る。 c 事業者は自社の従事者等である者、従事者等であった者及び従事者等として指定しようとする者について、被ばく経歴等の照会を手帳発効機関に依頼し、これを受けて手帳発効機関は、登録管理センターに対し、照会を行ない回答を求めることが出来る。 d 従事者等である者、および従事者等であった者は、原子力事業者等に対し、本人であることを証明する書類等を提出し、被ばく経歴等の照会を依頼し、原子力事業者は、これを受けて、登録管理センターに照会を行ない、回答を求めることが出来る。 e 登録管理センターは被ばく経歴等の照会に所定の受付手続を行なった後、照会内容を審査し、可とした場合は、登録記録等を検索し所定の発信手続により、照会元へ回答する。 f 原子力事業者等からの被ばく経歴等の照会及び回答は、原則として文書によることとするが、特に事情ある場合は例外的扱いとして、電話による照会回答も可能とする。 この場合、登録管理センターは、照会してきた先方を確認(暗誦番号等による)するとともに、その事実を記録しておくこととする。 g 電話による照会回答を行なった場合、原子力事業者等は、回答受領後直ちに文書による照会と同様の手続を行なうこととする。 照会・回答業務(フローチャート)
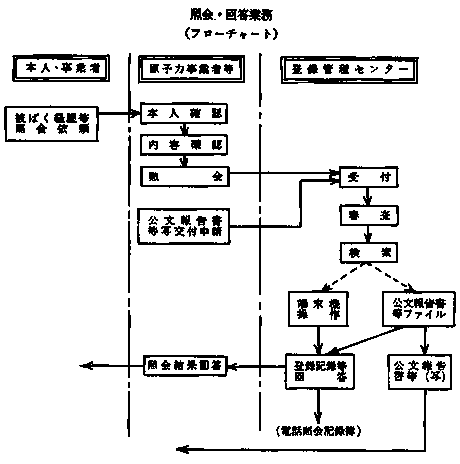 18 変更、訂正登録業務 (1) 変更、訂正登録関係業務の概要
従事者等の事前登録、指定登録、指定解除登録および定期線量登録として登録管理センターに登録した記録に変更、訂正(若しくは削除以下同じ)の必要が生じた場合、原子力事業者等は登録管理センターに対して登録記録の変更、訂正に関する申請を行ない登録管理センターはこれを受けて電算機投入を含む業務を行なう。 ただし、既登録事項を遡及して訂正・削除する場合は、原則として訂正削除申請日から2年程度の遡及を限度とする。 (2) 事務処理基準
a 事前登録した個人識別項目に変更又は訂正の必要が生じた場合、手帳所持者は事業者に対し、変更又は訂正の申し出を行なう。事業者は手帳発効機関に変更、訂正の要請を行ない、手帳発効機関はこれを受け、登録管理センターに変更、訂正申請を行なうとともに手帳記載事項の修正を行なう。 b 原子力事業者が従事者等の指定、指定解除、定期線量記録等既登録内容につき変更又は訂正の必要が生じた場合、原子力事業者は登録管理センターに対し、登録記録の訂正、変更申請を行なう。 c 事前兼指定登録に関する変更、訂正の場合も上記abの手続に準ずる。 d 登録管理センターは次の手順で業務を行なう。 ○ 登録管理センターは、変更、訂正登録申請に所定の受付手続を行なった後、申請内容を審査し可とした場合は、登録記録の変更又は訂正を電算機に入力する。 ○ 電算機処理を完了後、申請元に所定の方法により、処理の結果を通知する。 e 登録管理センターは一定期間中の個人識別事項にかかわる変更、訂正については、定期にその内容を編集し、全ての原子力事業者等に送付する。 変更訂正登録関係業務(フローチャート)
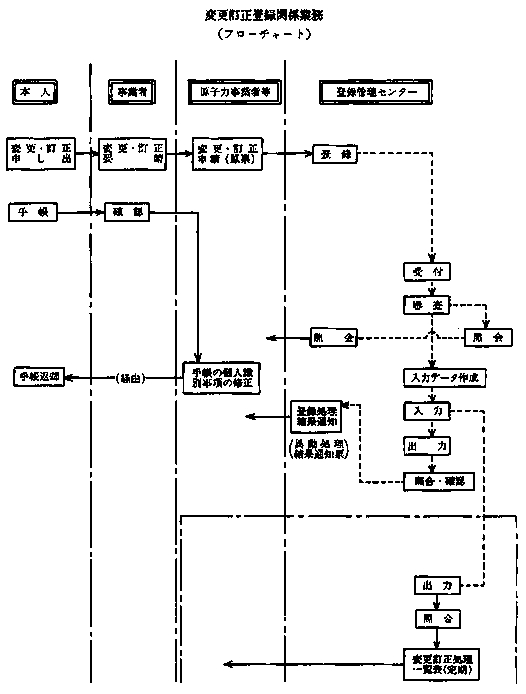 19 放射線管理手帳の再発行(効)業務 (1) 手帳再発行関係業務の概要
既に手帳を所持している者が、手帳の紛失等により、再発行を要請して来た場合、手帳発効機関は、手帳の再発行業務を行ない、再発効登録を登録管理センターへ申請する。 (2) 事務処理基準
a 手帳発効機関が手帳の再発行を行なう場合は、登録管理センターに手帳再発効登録申請を行なう。 b 登録管理センターは再発効登録申請に所定の受付手続を行ない、申請内容を審査し、電算機に入力し、電算機処理完了後、所定の方法により、申請元に処理結果を通知する。 c 登録管理センターは一定期間中の手帳再発効登録結果にもとづき、定期に手帳多重発行者のリストを作成し、全ての原子力事業者等に通知する。 20 放射線管理手帳多重発行の取消業務 (1) 手帳多重発行の取消関係業務の概要
手帳発効機関は、手帳を複雑冊所持している者に関して、登録管理センターからの定期に発行される複数所持者のリストによって、既発行手帳の整理を行なう。 (2) 事務処理基準
a 登録管理センターは、定期に手帳多重発行者一覧表(以下一覧表という)を作成し、全原子力事業者等に送付する。 b 手帳発効機関は、手帳の多重所持者を発見した場合は、所定の手順で手帳の整理を行なう。 c 手帳の整理を行なった手帳発効機関は、再発行手帳の取消処理の申請を登録管理センターへ行なう。 d 登録管理センターは、再発行手帳の取消申請にもとづき、電算機入力等の取消処理を行ない処理完了後、処理結果通知を申請元に通知する。 放射線管理手帳再発行(効)関係及び多重発行取消業務(フローチャート)
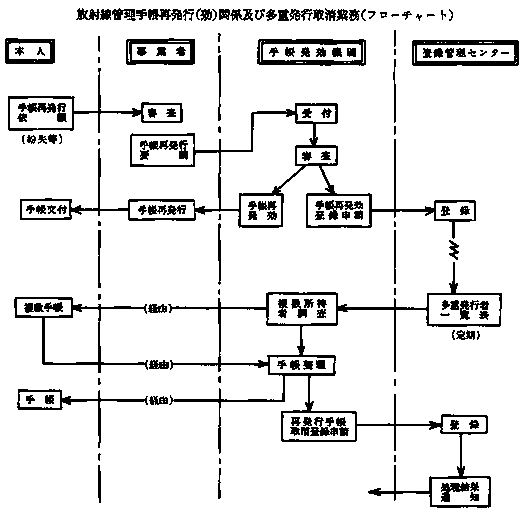 21 登録報告等の様式
(1) 事前登録、指定登録、その他各種登録申請等は、原則として電算機登録原票により行なう。 また、登録管理センターからの登録、報告、照会に対する処理結果通知等についても上記要素等を考慮した様式とする。 (2) 定期線量登録等、大量データの登録については、前項による他、登録管理センターの求める仕様で磁気テープによる提出が可能な原子力事業者に対しては、磁気テープによる提出を受け、又は求めることがある。 (3) 電算機登録原票等は、原則としてA4サイズ以下としてファックス電送等、処理の円滑化をはかる。 (4) 各種様式
本制度における各種様式(案)は、別添(略)のとおりとする。 22 登録原票、報告用紙等の送達方法
(1) 登録原票、照会票等は原則としてファクシミリで送達する。 (2) ファクシミリによらないものは、原則として郵便により送達する。 (郵便送達の際は、書留扱いとするなど、送達方法を考慮する)
(3) 登録管理センターから原子力事業者等への処理結果通知等の送達も原則として、前各項に準じ、ファクシミリ又は郵便による。 23 電算機処理の方式 (1) 電算機処理の体制
本制度による電算機処理は、委託によることとし、委託計算センターとの間で締結する業務処理委託契約にもとづき実施する。 (2) 登録管理事業に関する電算機仕様
a 登録管理センターに端末装置を設置し、委託計算センターとの間でTSS処理を行なう。 b 登録管理センター側に設置する端末装置は、ディスプレー装置(プリンター付)とする。 c 運用形態は、登録関係については、バッチ処理、照会、回答関係はTSS処理とする。 d 答録管理センター側の端末装置操作は、電算機処理の専門知識のない者にも可能なものとする。 e 機密保持に十分配慮し、必要な防護措置を講ずる。 24 データ伝送設備 (1) ファクシミリ設置台数
登録管理センター5台、原子力事業所、手帳発効機関には原則として各2台設置する。 ただし、原子力事業所、手帳発効機関が近接し、集中管理が可能な個所については、この限りでない。 (2) ファクシミリの選定基準 a 登録管理センター設置ファクシミリ
(a) 送受信速度は高速(1分間)~低速(6分間)とする。 (注)原子力事業者等の選択の幅を考慮した。 (b) 公社規格ファクシミリとの交信の可能なもの (c) 伝送用紙サイズはA4とする。 b 原子力事業者等の設置機種
原則として、登録管理センター採用のものと同一機種とするが事情ある場合は、登録管理センターの機種と交信可能なものに限り、他の機種とすることが出来る。 c 通信線は、電々公社電話回線とし、一般加入電話回線を使用することとする。 (3) ファクシミリ設置方式
登録管理センターはリースで設置する。 原子力事業所等は、リース、購入等は任意とするが、将来の変換の容易性も考慮しておくことが望ましい。 25 データ処理の所要時間
(1) 登録管理センターにおける1日のデータ受付には、締切りを設け(1日1~2回)締切後、処理結果の発送処理までの所要時間は、48時間以内とする。 (2) 経歴記録照会等については、可能な限り短時間に処理し、回答するものとする。 (3) その他各種申請、報告の処理日程、時間については、緊急度、処理量等を勘案の上、運用の過程で遂時定めるものとする。 26 記録等の保存期間
(1) 公文報告--永久保管を原則とする。 (2) 公文報告以外の報告、登録申請等--別途決定する。 27 機密保持・プライバシーの保護
登録管理センターに登録または保管されている個人被ばく線量の数値、その他個人にかかわる記録内容について、他に漏洩しないよう次の措置をとる。 (1) 登録管理センター職員の就業規則等に機密保持について規定するとともに、業務管理、施設管理面についての機密保持体制を明確にする。 (2) 委託電算機会社については、業務委託契約書等において、機密保持について規定するとともに、電算機運用管理、その他業務管理、施設管理面について、機密保持の体制を明確化する。 (3) 原子力事業者等についても、業務管理、施設管理面等について、機密保持面からの特段の配慮を行なう。 (4) 手帳発行、および従事者等指定時に提出させる本人申告書に「被ばく記録等について、照会することがある」旨明記する等、本人の承諾を得る。 28 登録管理センターに報告後の記録の取扱い
(1) 従事者についての規制法に基づく規則に定められた被ばく線量記録は原子力事業者から登録管理センターへ引渡されることにより、当該記録を原子力事業者が保管する必要が法的にはなくなる。 (2) 本制度にかかわる記録で上記法定記録以外の記録については、登録管理センターと原子力事業者の間の契約に属するものと考えられる。 29 障防法対象事業者の取扱い
当面、事業継続が困難となった障防法上の使用者の従事者等の被ばく線量記録について、その使用者から登録管理センターが引渡しを受け、整理保管することが出来るものとしまた、原子力事業者の原子力施設内で非破壊検査を行なう頻度の高い非破壊検査事業者の本制度への早期加入を図ることが当面の対応として、必要であると考えられる。 30 規制法、障防法対象事業が混在する事業所での線量記録の取扱い
(1) 原子力事業者(所)内にあって規制法上の従事者と障防法上の従事者等が同一人であり、測定記録の区分が困難な場合は、事業所単位で規制法上の被ばく線量に含めて、登録又は報告することが出来ることとする。 (2) 測定記録の区分が出来る場合は規制法上の被ばく線量は原子力事業者が、障防法上の被ばく線量は使用者が(原子力事業者を通じて)登録又は報告することが適当であると考えられる。 Ⅲ 制度切替時の業務処理 31 制度切替日(新制度が発足する日)
登録管理センターが原子力事業者等と協議のうえ定める。 32 本格実施
制度切替日より10か月程度経過後。 33 制度切替時業務の概要
制度切替日より、本格実施日までの間における業務は、概要次のとおりである。 (1) 過去分の処理
a 制度切替日までに従事者等であった者、及び制度切替日に従事者等である者についての個人識別事項の登録関係。 b 上記従事者等についての制度切替日の前日までの定期線量登録、直近の指定解除登録ならびに公文報告等。 (2) 経過分の処理
a 制度切替日以降本格実施までの間における事前登録。 b 上記期間中における従事者等の指定登録、指定解除登録、公文報告等。 (3) その他事業所登録等、新制度発足に要する業務。 34 過去分個人識別事項登録関係業務 (1) 過去分個人識別事項登録業務
制度切替日までに従事者等であった者、及び制度切替日に従事者等である者について、原子力事業者は登録管理センターに対して個人識別事項の登録を申請する。 登録管理センターは、これを受けて電算機投入を含む処理を行ない、登録番号を付番する。 原子力事業者等は上記登録番号を個人管理台帳等に記入するとともに手帳に表記し、既発行手帳の切替、又は新手帳の発効を行なう。 上記各業務は、それぞれ所定期間内に完了することを原則とする。 (2) 事務処理基準
a 原子力事業者は制度切替日までに従事者等であった者、及び制度切替日に従事者等である者の個人識別事項について、登録管理センターに対し制度発足日以降3か月程度の間に登録申請を行なう。 b 登録管理センターは、次の手順で業務を行なう。 ○ 個人識別事項登録申請に対し、所定の受付手続を行なう。 ○ 申請事項を申請締切後1カ月の間に電算機処理などにより整理し、登録番号を付番し、個人識別登録番号簿を作成する。 ○ 個人識別登録番号簿は、原子力事業者別に作成し、所定の方法により、処理結果通知とともに原子力事業者に3部送付し、登録番号を通知する。 c 原子力事業者は、個人識別登録番号簿(又はその写以下同じ)により個人管理台帳等に登録番号を記載する一方、個人識別登録番号簿を手帳発効機関に送付する。 d 原子力事業者等は個人識別登録番号簿受領後、自社及び系列事業者の対象者について、原則として6か月以内程度で既発行手帳の切替又は、新手帳の発効を行ない、切替(発効)完了分については、登録管理センターに対し、切替(発効)完了通知を行なう。 切替すなわち既発行手帳の失効、新手帳の発効は、既発行手帳の個人識別記録欄の張替・登録番号の記載等により行なう。 登録番号が付番されている者が本格実施日以降判明した場合についても本取扱いに準じた処理を行なうこととする。 (3) 上記特定期間中に過去分個人識別事項の整理、登録申請が困難な原子力事業者は、登録管理センターと協議し、個人識別登録番号簿の配布終了後上記の登録関係業務処理手順に準じて、別途個人識別登録を含む各種登録手続等を行なう。 35 過去分各種登録等の業務
(1) 原子力事業者は、制度切替の前日までの従事者等の指定登録、定期線量登録申請およびすでに指定解除されている者については、直近の指定解除登録申請ならびに公文報告等を登録管理センターに対して行ない、登録管理センターはこれを受理し、登録処理を行ない、公文報告等については、これを整理・保管する。 (2) 事務処理基準 a 原子力事業者は、個人識別登録番号簿に記載された従事者等について事業所毎に次の過去分としての登録申請ならびに報告を登録管理センターに対して行なう。 b 過去分指定解除登録 制度切替日の前日までに指定解除された従事者等について、直近の指定解除記録を登録申請する。 c 過去分定期線量登録 制度切替日の前日までに指定解除された従事者等について、各年度中の線量記録を年度毎にまとめ登録申請する。 d 過去分公文報告等 制度切替日の前日までの公文報告、随時立入者指定解除報告を行なう。 なお、報告の際には上記の過去分、指定解除登録申請を同時に行なう。 e 登録管理センターの業務手順等は、本格実施時の手順に準ずる。 36 経過分事前登録業務 (1) 経過分事前登録関係業務
制度切替日以降、本格実施日までの間に、従事者等の事前登録申請をしようとする事業者は、手帳発効機関に対し、登録管理センターに対する個人識別事項の登録申請を依頼し、手帳発効機関は、所定期日以降、登録管理センターに登録を申請する。 登録管理センターはこれを受けて、電算機投入を含む処理を行ない、登録番号を付番する。 手帳発効機関は登録番号を手帳に表記し、手帳を発効させる。 (2) 事務処理基準
a 手帳発効機関は、制度切替日以降個人識別登録番号簿受領までの間は事前登録申請を保留しておき、個人識別登録番号簿受領後、記載されていない者については、登録管理センターに対して本格実施時と同様な手続により、事前登録申請を行ない、登録管理センターからの処理完了通知により手帳の発効を行なう。 b 前項による事前登録保留期間中は、必要に応じて仮発行手帳(登録番号なし)により管理を行なうことが出来る。 37 経過分各種登録等の業務 (1) 経過分各種登録等関係業務の概要
原子力事業者は制度切替日以降、本格実施までの間の従事者等の指定登録、指定解除登録の申請及び公文報告等を所定期日以降登録管理センターに対して行ない、登録管理センターは、これを受けて、電算機投入を含む処理を行なう。 (2) 事務処理基準
a 原子力事業所は、制度発足日以降従事者等に指定された者及び指定を解除された者についての記録の登録申請、ならびに公文報告等を登録管理センターに対して行なう。 b この登録申請および公文報告等は、過去分又は経過分として登録番号の付番が完了している者についてのみ行なわれる。 従って登録番号の付番が完了していない者については付番の完了を待って、上記申請および報告を行なう。 c 登録管理センターは、本格実施時に準じて、登録申請の処理ならびに公文報告の受理、保管を行なう。 38 登録処理要件を満たさない情報の取扱い
過去分記録等において、従事者等につき、生年月日、本籍等の情報が明確でない等の理由により、電算機による登録処理要件を満たさない記録については、登録管理センターは、通常の記録とは別に保管、整理する。 39 事業所登録
制度切替日以降過去分、経過分のデータの送受を登録管理センターと行なおうとする原子力事業者等は、当該データの送受の前に事業所登録を完了しておくこととする。 40 その他
登録報告等の方式、原票等の送達方法、機密保持等については、本格時に準じて取扱うこととする。 付録 主要事項補足説明
1 事前登録関係
(1) 事前登録の申請は、原子力事業者の従業員については原子力事業者が、事業者の従業員については事業者の要請に基づき手帳発効機関が行なう。 (2) 事前登録をいつ行なうかは各事業者の判断によるが、一応の目安として原子力(放射線)関係の技術者を採用した場合、工事等を受注することが予測される場合及び原子力(放射線)関係の事業者を設置する場合等が考えられる。 (3) 原子力事業者の従業員も事前登録の対象となる。しかし事前登録と手張発効は必ずしも一致しない、例えば、手帳を発行しない原子力事業者の従業員は登録番号は付番されるが、手帳は「無い」ということになる。 2 指定登録関係
(1) 指定登録は、原子力事業者の行なった従事者等の指定記録の登録である。従って、原子力事業者は、登録管理センターへの登録申請に先立って従事者等の指定を行なうことが出来る。 (2) 指定登録は原則として登録番号確認のうえ行なう。登録番号確認の方法は、原則として手帳による。 (3) 本制度において、従事者、随時立入者の区分は行なわない(他の登録の場合も同じ)。 従事者の指定は、法令の定義に従って各原子力事業者が行なうものであるため、1人の作業者が2以上の事業所で従事者であることもありうる。 なお、従事者、随時立入者の区分については、明確な区分法はないが規制法上の従事者指定は、事業者が指定した電離則上の従事者ないしは随時立入者について、原子力事業者は当該工事等に伴う予想被ばく線量を通告し、そのうえで事業者の下した指定区分を尊重して行い、指定解除についても事業者の申請により行うのが一つの考え方として可能である。 3 事前兼指定登録関係
(1) 事前兼指定登録の場合も登録管理センターからの処理完了通知の到着とは別に、原子力事業者は従事者等の指定を行なうことが出来る。この場合、登録管理センターからの処理完了通知(含登録番号)を受領次第、直ちに個人管理台帳等への登録番号の記載、手帳の発効手続等を行なうこととする。 (2) 事前兼指定登録が必要か否かの最終的判断は原子力事業者が行なう。 (3) 事前兼指定登録申請(用紙)への所定事項の記入については、原子力事業者でなければ記入不可能な事項を除き、事業者又は手帳発効機関が、これを行なう。 4 指定解除登録関係
指定解除登録は、公文報告及び随時立入者指定解除報告と同時に本制度で制定した様式により行なう。 なお、様式は、公文等連結方式と公文等添付方式がある。(資料参照)(略)
5 公文報告、随時立入者指定解除報告関係
(1) 公文報告等に記入する被ばく線量は、指定期間中における当該原子力施設での3ケ月、年、集積線量を記入すれば良く、その前の指定期間中の線量との合算記入は不要とする。 また前歴については各指定登録時に把握した前歴線量(集積線量)を記載する。 (2) 公文報告等に記載される被ばく線量記録は、事業者等が測定した記録を記入するものとし、線量測定方法の統一化について本制度の問題とは切離して扱うことが必要である。 (3) 随時立入指定解除報告に記入する被ばく線量は、指定期間中における当該原子力施設での被ばく線量について、公文報告に準じて記載する。 なお、被ばく線量記録が無い場合はその期間について記録なして記入する。 (4) 従事者指定を解除されたが引続き随時立入者として指定、若しくは随時立入者の指定は解除されたが、引続き従事者として指定された者については、最終の従事者又は随時立入者指定を解除された後、公文報告として記録を引渡すものとする。この場合、報告書に従事者等の区分変更のあった旨の記述(又は特殊*マーク等)を行なう。 (5) 公文報告等での公印は、引渡書(いわゆる送り状)のみに押印すれば足りるものとする。 6 定期線量登録関係
(1) 定期線量登録に記載される被ばく線量は当該原子力施設での被ばく線量を記載することとし、前歴等当該原子力施設外での被ばく線量の記載は、不要とする。 (2) 定期線量登録における線量測定についての考え方は、公文報告等の場合と同様である。 7 照会、回答関係
(1) 登録管理センターからの回答の異動経歴には、照会日以前少なくとも1年間の指定解除事業所名、指定解除年月日が記載されることになっている。 (2) 手帳発効機関等は、従事者等本人(かつて従事者等であった者を含む)が登録記録を知りたいと申し出た場合は、本人であることを証明するためのものとして、自動車運転免許証等、公的機関で発行したものを提示させることとする。 8 過去分、経過分関係
(1) 過去分とは、原子力事業所において規制法上の管理区域の設定日を起点として制度切替日までの期間を言う。 (2) 本制度発足時から参加している原子力事業者等の過去分個人識別事項の登録は、昭和54年度末を目途に完了する。 (3) 既発行手帳とは、昭和47年原子力関連大手総合メーカー等が協力して制定した放射線管理手帳であって、制度切替日以前に発行されたもの。 9 その他
(1) 本格実施後、まれに発生するかもしれぬ不詳分記録の扱いについては、過去分不詳記録の取扱に準じて整理する。 (2) 事前登録及び放射線管理手帳制度のみについて参加を希望する事業者については、将来での本制度への全面参加を希望する旨を伝えた後これを認めることが出来る。 むすび
以上、放射線業務従事者等の被ばく線量登録管理制度について述べてきたが、未だ検討を要するいくつかの事項がある。 これらのうち、本報告で定めのない事務処理基準、様式記載要領、業務運営要領等、いわゆる業務運営の細目に関する事項および本報告で別途定めるとある事項については、登録管理センターで作案し原子力事業者等と協議のうえ実施にうつすこと、ならびに本制度推進の円滑化を期するため、次の事項については国及び登録管理センターが協力してこれを解決することが必要と考えられる。 1 本制度に参加の予定される原子力事業者等への本制度についての説明。 2 本制度への参加をみていない団体、諸機関等への本制度主旨の説明と参加の促進。 3 事前登録、指定登録等、法時裏付のない事項についての対策の立案推進。 4 放射線管理手帳制度と本制度との関係の明確化及びに同手帳制度の同時併行的推進
5 従事者の区分、被ばく線量測定方法等の明確化。 6 原子力事業者等から関係省庁へ提出する被ばく線量報告の一本化。 (付記1)
(付記2)
原子力事業従業員被ばく線量登録管理制度検討会における審議の経過
第1回 51年11月5日
原子力事業従業員被ばく線量登録管理制度のシステム構成及び運用に関する具体策について
第2回 51年11月30日
原子力事業従業員被ばく線量登録管理制度のシステム構成及び運用に関する具体策について(ワーキンググループ設置)
第3回 52年3月22日
原子力事業従業員被ばく線量登録管理制度検討会ワーキンググループの報告について
第4回 52年4月5日
原子力事業従業員被ばく線量登録管理制度検討会中間報告について
第5回 52年11月14日
原子力事業従業員被ばく線量登録管理制度検討会最終報告について (付記3)
原子力事業従業員被ばく線量登録管理制度検討会ワーキンググループ委員及び審議の経過 (委員)
(審議経過)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前頁 | 目次 | 次頁 |