| 前頁 | 目次 | 次頁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
原子力船「むつ」の燃料体の取扱いの安全性に関する検討 昭和52年7月29日
「むつ」総点検・改修技術検討委員会
昭和52年7月29日
科学技術庁長官
宇野 宗佑 殿
運輸大臣
田村 元 殿
「むつ」総点検・改修技術検討委員会
委員長 安藤 良夫
標記について、当委員会において審議した結果を次のとおり報告書として取りまとめたので、報告する。 「むつ」総点検・改修技術検討委員会委員
(順不同)
1 検討の経緯
当委員会は、さきの原子力船「むつ」の安全性総点検及び遮蔽改修の計画についての検討に際し、燃料体を炉心から取り出す技術的必要性の有無についても検討した結果、燃料体を装荷したままでの安全性総点検及び遮蔽改修の実施が可能であり、安全性は十分に確保しうるとの結論を得ている。(注1)
一方、去る5月17日に開催された原子力船「むつ」関係閣僚会議(内閣官房長官、科学技術庁長官及び運輸大臣から構成)において、「むつ」の燃料体の取出し等その取扱いの安全性について当委員会で審議することが決定された。(注2)
このため、当委員会としては、安全性総点検及び遮蔽改修の後、燃料体を再装荷して使用することを前提として、
(1)燃料体の取出し
(2)燃料体の輸送
(3)燃料体の保管 (注3)
のそれぞれについて、その方法と安全性について基本的考え方を検討することとし、日本原子力船開発事業団からの説明を聴取しつつ審議を行い、以下の結論を得たものである。 (注1)「むつ」総点検・改修技術検討委員会第一次報告
(昭和50年11月25日)
「むつ」の遮蔽改修・総点検時における燃料体取出しの必要性に関する検討(昭和51年10月1日)
(注2)原子力船「むつ」問題についての了解事項
昭和52年5月17日
内閣官房長官
科学技術庁長官
運輸大臣
原子力船「むつ」の核燃料体の取扱いの安全性については、原子力委員会の決定に基づき科学技術庁及び運輸省が合同で設置している「むつ」総点検・改修技術検討委員会(委員長・安藤良夫 東京大学教授)において審議することとする。 (注3)
(1)「燃料体の取出し」とは、原子炉室ハッチカバー撤去から炉心上部構造物の撤去、燃料体の取出し及び一時保管、模擬燃料体の取付けを経て、原子炉室ハッチカバーを取り付けるまでをいう。 (2)「燃料体の輸送」とは、取り出した燃料体を(1)に述べた一時保管場所から(3)に述べる長期保管場所まで輸送することをいう。 (3)「燃料体の保管」とは、取り出した燃料体を原子炉に再装荷して使用するまでの間、長期にわたり保管することをいう。 2 検討の内容
(1)燃料体の概要について
「むつ」の炉心部は、燃料体、制御棒等からなり、上下端が半球状の円筒形鋼製原子炉圧力容器(圧力容器は船体のほぼ中央に位置する。)に収容されている。 炉心は、濃縮度の異なる二種類の燃料体を配置した二領域炉心(中央領域濃縮度:約3.2重量パーセント、外側領域濃縮度:約4.4重量パーセント)であり、燃料体32体(約3.2重量パーセントのもの12体、約4.4重量パーセントのもの20体)及び制御棒12体をほぼ円筒形に配置した構造となっている。 燃料体は、多段のスペーサにより、112本の燃料棒及び9本のバーナブルポイズン棒を11列×11列の正方格子状に配列したものであり、燃料体1本あたりの重量は約123キログラムである。 燃料棒は、ステンレス鋼製の被覆管に二酸化ウラン燃結ペレットを挿入し、両端を密封した構造となっている。 「むつ」の燃料体(二酸化ウラン量:32体分で約2.8トン)は、最高燃焼度約14,000メガワット・日/トン・金属ウラン(平均約5,500メガワット・日/トン・金属ウラン)に応じ得るよう設計されており、約13,500メガワット・日の燃焼(36メガワットの出力で約9,000時間の運転)の後、新燃料体と交換することとなっている。 (2)燃料体の現状について
(イ)燃料体中の核分裂生成物
昭和49年の出力上昇試験時における原子炉の運転積算出力は約0.07メガワット・日であり、この運転によって生じた燃料体(32体)中の核分裂生成物の放射能は、昭和52年3月末現在、約4キュリーに減衰しているものと算定される。したがって燃料体1体中の核分裂生成物の放射能は、平均約0.12キュリー(最大約0.2キュリー)と算定される。 (ロ)燃料体の表面線量率
燃料体の表面線量率は、核分裂生成物の放射能、誘導放射能等に基づき計算した結果、最大約90ミリレム/時であり、この値は、法令に定める核燃料物質を運搬する場合の制限値(輸送容器の表面線量率200ミリレム/時)を十分に下回っている。 (ハ)燃料体の健全性
燃料体は、製造段階において厳重な検査が行われ、納入時においても真直度等の確認が行われており、燃料装荷に際しても慎重な作業が行われている。その後出力上昇試験までの約2年間を通じて、制御棒駆動操作は円滑に行われていることから、燃料体に問題となるような変形は生じていないものと判断される。 また、燃料体は、出力上昇試験においてわずかしか燃焼しておらず、この間に燃料体が受けた中性子照射及び熱サイクルの影響は無視しうるものと判断される。 さらに、燃料体装荷後出力上昇試験を経て現在に至るまで、一次冷却水は厳重な水質管理がなされてきており、問題となるような腐食が生じているおそれはないと判断される。 また、一次冷却水中の放射性物質の分析結果からも、燃料体は健全であると判断される。 (3)燃料体の取出しに係る安全性について
(イ)燃料体の取出し方法
燃料体を炉心から取り出す作業は、次の3つの工程からなる。 (i)第1工程(原子炉室ハッチカバー撤去から炉心上部構造物の撤去及び一時保管まで)
(ii)第2工程(燃料体の取出しから一時保管まで)
(iii)第3工程(模擬燃料体取付けから原子炉室ハッチカバー取付けまで)
上記のうち、第2工程については、次の2つの方法が考えられる。 (i)燃料交換キャスクを用いる方法(A方式)
(ii)船上に仮設したクレーンを用いる方法(B方式)
A方式については、約13,500メガワット・日(36メガワット出力で約9,000時間運転)まで燃焼させた使用済燃料体と新燃料体を交換するのに用いられる方法であり、既存の燃料交換キャスク等の施設・設備はこれを前提として燃料交換を安全に実施できるよう設計されている。 一方、燃料交換キャスクを使用しないB方式については、現在の燃料体を炉心に装荷した際(昭和47年9月)に用いたのと同様の方法である。 現在の燃料体は放射線レベルが低いので、あえてA方式を採用するには及ばず以下に述べる条件、施設・設備、安全対策(後述の「(6)安全性確保に必要なその他の対策」を含む)が満足されるならばB方式を採用することは安全上問題ないと考えられる。 (ロ)考慮すべき条件
作業の安全性確保及び燃料体等の保護のため船体姿勢は、燃料体装荷作業を実施した時と同様、ほとんど傾斜のない状態に保つことが必要である。 このため次のような配慮が必要である。 (i)作業実施場所は外洋の影響が少ない静穏な場所にある岸壁又は乾ドックであること。 (ii)静穏な気象・海象の日を選んで作業を実施すること。 (ハ)具備すべき施設・設備
燃料体取出し(B方式)に必要な主な施設・設備は次のとおりである。 (i)大型クレーン
原子炉室ハッチカバー、遮蔽体等重量物(最大重量約60トン)の取りはずし取付け、移送容器の船外への搬出等に使用する。 (ii)船上仮設クレーン及び建屋
燃料体の炉心から取出し等に使用する。 (iii)移送容器
取り出し燃料体の船上から一時保管施設までの運搬に使用する。 (iv)圧力容器蓋等一時保管施設
取りはずした圧力容器蓋等重量物の一時保管等に使用する。一時保管施設には重量物の取扱いのためのクレーン、乾燥設備等が必要である。 (v)燃料体一時保管施設
取り出した燃料体を一時的に保管するために使用する。燃料体一時保管施設には、燃料体の取扱いのためのクレーン、乾燥設備等が必要である。 なお、燃料体の一時保管にあっては、(5)(イ)に述べる保管の方法と同様、乾燥保管が適当と考えられる。 (vi)放射線監視設備
燃料体一時保管施設及びその周辺の放射線監視に使用する。 (ニ)安全対策
(i)燃料体取出しの作業管理
燃料体取出し作業中には常に制御棒が全数挿入されていることを確認するとともに、核計装により中性子数の変動を監視し、炉が未臨界状態にあることを確認することが必要である。 クレーンの吊り上げ用金具には防脱装置を取りつけるとともに、ワイヤー、チェーンブロック等は使用に際し十分な点検を行うことが必要である。 特に、燃料体取出し作業は、燃料体を損傷することのないよう慎重に実施する必要がある。 (ii)燃料体の一時保管管理
燃料体の一時保管施設は耐火耐震構造とし、燃料体の保管時のいかなる場合にも臨界とならないような構造及び配置の保管ラック及び収納容器を設置することが必要である。 また、一時保管施設の周囲には、フェンス等を設け、施設内への出入管理を厳重に実施する必要がある。 (4)燃料体の輸送に係る安全性について
(イ)燃料体の輸送方法
燃料体を取り出した場所(燃料体一時保管施設:(3)(ハ)(v)で記載)から保管場所(燃料体保管施設:(5)(ハ)(i)で記載)まで輸送する方法としては、陸上輸送又は海外輸送の2つの方法が考えられる。 (ロ)考慮すべき条件
輸送にあたっては、輸送経路、輸送体制、輸送中の放射線管理等を含め、綿密な輸送計画を策定することが必要である。 (ハ)具備すべき施設・設備
燃料体の輸送に必要な主な施設・設備は次のとおりである。 (i)輸送容器
「放射性物質等の輸送に関する安全基準」(原子力委員会、昭和50年1月)に合致したA型輸送容器(注1)であって、核分裂性輸送物(注2)としての基準をも満たすものを使用する。 (注1)「A型輸送容器」とは、比較的放射線レベルが低く、外部及び内部被曝の影響の少ない量の放射性物質等を収納する輸送容器をいい、これらの基準は原子力委員会が定めている。 (注2)「核分裂性輸送物」とは、核分裂性物質を収納した輸送物をいう。 (ii)輸送車輛又は船舶
燃料体中の核分裂生成物の放射能及び輸送物の放射線レベルから判断して一般の車輛又は船舶を使用することができると考えられる。 (ニ)安全対策
燃料体の輸送にあたっては、輸送物の健全性の確認を行うとともに、使用車輛又は船舶の整備状況、荷役積付方法等に十分注意を払うことが必要である。 (5)燃料体の保管に係る安全性について
(イ)燃料体の保管方法
燃料体の保管方法は乾燥保管と水中保管が考えられる。 現在の燃料体は発熱量及び放射線レベルが低いこと、長期的保管を考えるならば、水中保管より乾燥保管の方が保管雰囲気の維持管理が容易であること等により、乾燥保管を採用することが適当と考えられる。 (ロ)考慮すべき条件
燃料体の保管(乾燥保管)にあたっては、再使用するまでの間長期にわたって適切な維持管理を行う必要がある。このため燃料体の保管施設は燃料体に腐食が発生することのないよう保管雰囲気の管理を厳重に実施する必要がある。 (ハ)具備すべき施設・設備
燃料体の保管(乾燥保管)に必要な主な施設・設備は次のとおりである。 (i)燃料体保管施設
燃料体を長期にわたり適切に保管するために使用する。燃料体保管施設には、保管雰囲気の管理設備、クレーン、保管ラック、収納容器等が必要である。 (ii)放射線監視設備
燃料体の保管施設及びその周辺の放射線監視に使用する。 (ニ)安全対策
(i)燃料体の保管管理
燃料体の保管施設は耐火耐震構造とし、燃料体保管時に臨界とならないよう構造及び配置の保管ラック及び収納容器を設置することが必要である。 また、保管施設の周囲にはフェンス等を設け、施設内への出入管理を厳重に行うことが必要である。 (ii)燃料体の品質管理
燃料体は長期間にわたり適切な維持管理が必要であるので、保管施設への搬入に際しては十分慎重に行うとともに保管中は定期的に燃料体の保管状況を点検することが必要である。 (6)安全性確保に必要なその他の対策について
(イ)燃料体取出し等に伴い発生する廃棄物の処理・処分
燃料体取出し等の作業に伴って洗浄水、ウエス、作業衣等の液体及び固体廃棄物が発生する。 これらの廃棄物の放射能レベルは極低レベルであり、放射線管理上、特に問題はないと考えられるが、処理・処分にあたっては、放射線量の測定を行う等、適切に措置されることが必要である。 (ロ)予備訓練の実施等
燃料体の取出し作業の実施にあたっては、モックアップ装置を使用する等の予備訓練を実施するとともに、予め作業手順書を策定し、これに従って安全かつ確実に行うことが必要である。 (ハ)放射線管理
燃料体の取扱いにあたっては、作業従事者に対し放射線管理に必要な行動規制、作業規制、各種手続き等放射線作業上厳守すべき事項を予め周知徹底させることが必要である。 また、燃料体の取出し等の具体的作業にあたっては作業環境に予め管理区域を設定し、併せて、放射線管理者を立合わせる等厳重に放射線管理を実施することが必要である。 さらに、予備訓練による作業時間の短縮、燃料体の取扱い治具の効果的活用等により作業従事者の被ばくの軽減措置をとることが必要である。 (7)燃料体取出し場所の検討について
燃料体取出し場所については、作業を安全かつ確実に行うとの観点から主に次の2つの条件を満足することが必要である。 (i)(3)(ロ)に述べた船体姿勢を確保できること
(ii)(3)(ハ)に述べた所要施設・設備を設営できること
これらの条件を考慮して岸壁、乾ドック及びその他の場所について検討した結果は以下のとおりである。 (イ)岸壁
「むつ」の係留が可能な岸壁であって、外洋の影響を受けにくい場所にあり、かつ隣接地に所要施設・設備を設営できる敷地面積を確保できるものであれば条件を満足できるものと考えられる。 (ロ)乾ドック
「むつ」を入渠できる乾ドックであり、その隣接地に所要施設・設備を設営できる敷地面積を確保できるものであれば、条件を満足できるものと考えられる。 (ハ)その他
(イ)及び(ロ)以外の場所として、洋上において浮ドック、浮起重機等を用いる方法が想定される。しかしながら(3)(ロ)に述べた船体姿勢を保つための静穏な気象・海象状態が長期間継続するとは考えられないこと、及び所要施設を洋上に確保することは困難なことに加え、洋上においてこの種の作業を実施した経験がないこと等により洋上において燃料体の取出し作業を行うことは、極めて困難であると考える。 3 結語
「むつ」の燃料体の取出し、輸送及び保管は、現在の燃料体の現状に鑑み、これまで述べてきた方法、条件等を配慮し、慎重に作業を行うならば、安全性は十分確保できると考える。 なお、当委員会としては、冒頭で述べたように燃料体を装荷したままでの安全性総点検及び遮蔽改修の実施が可能であり、安全性は十分に確保しうるとの結論をすでに得ていることを申し添える。 (参考資料)
1「むつ」燃料体の概要
図1-1 燃料体及び燃料棒 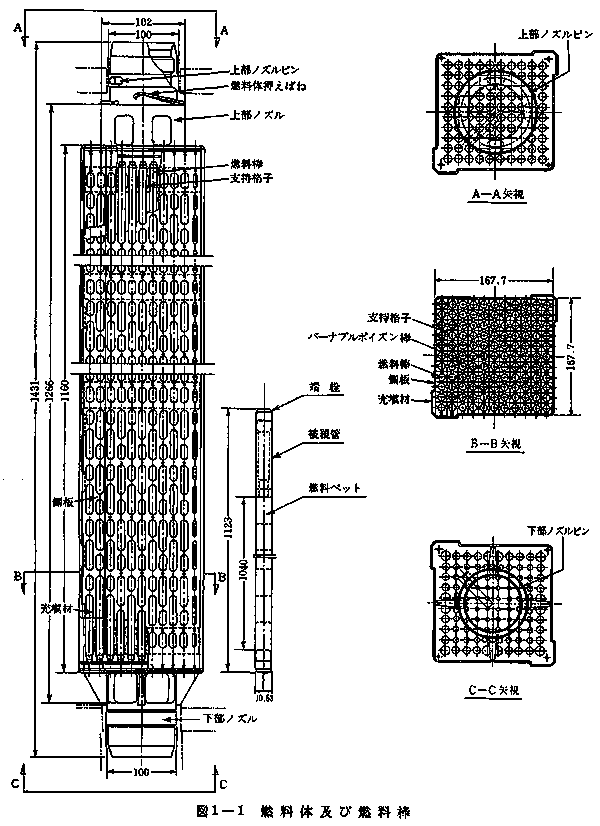 図1-2 炉心横断面 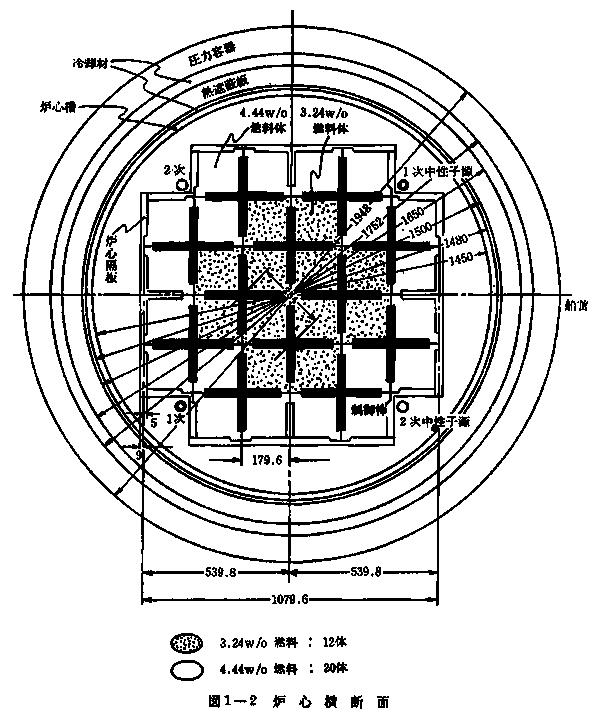 図1-3 圧力容器縦断面図 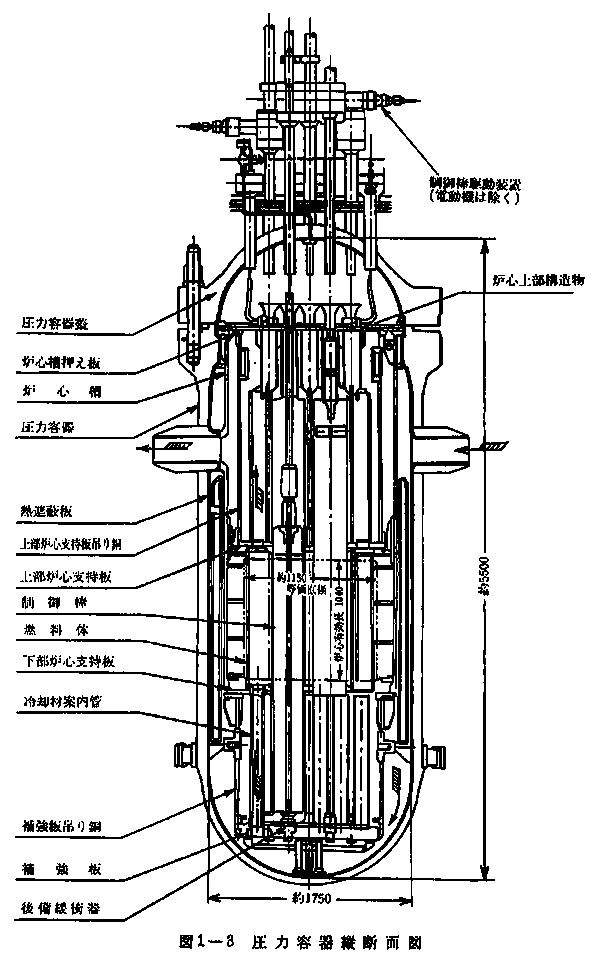 図1-4 原子炉の配置 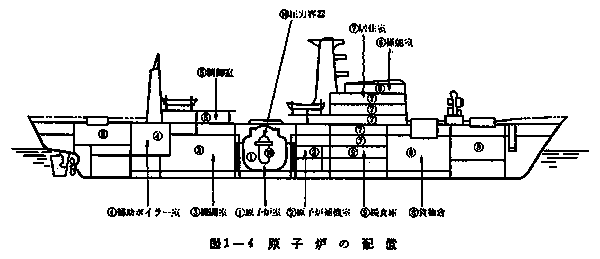 2 燃料体中の核分裂生成物の放射能
(1)燃料体(32体)の核分裂生成物の放射能:約4Ci(52.3末現在) 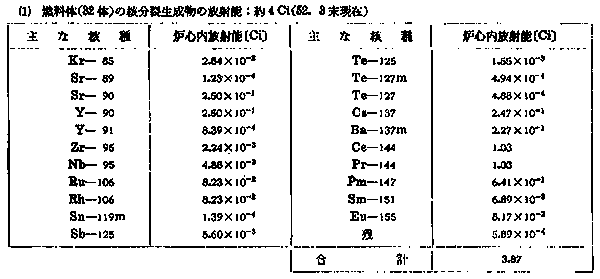 (2)燃料体1体当りの核分裂生成物の放射能:最大0.18Ci(約0.2Ci)
(ピーキングファクター 1.47)
(注)① 49年の出力上昇試験時の燃焼:約0.07MWD(1.4%出力で0.137日の運転に相当する。)
② 使用計算コード:PHOEBE及びRIBD
PHOEBE:Photons、Energy and Betas
U235核分裂生成物のβ及びα放射能及びスペクトル計算用コード。 (ORNL-3931、July、1966)
RIBD:Radio Isotope Build-up and Decay
燃料中に蓄積されるF.P.を計算するコード
(E0081-12-00、Sep.1970)
図2-1 燃料体(32体)中の核分裂生成物の放射能の変化 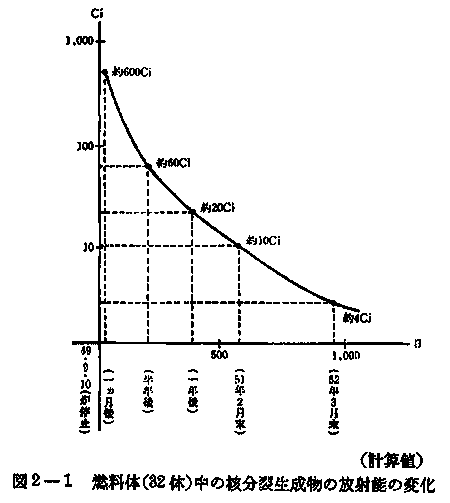 3 燃料体の表面線量率
(1)燃料体中の放射能(注)①
(イ)核分裂生成物の放射能:0.18Ci(最大)
(ロ)燃料体構成材の誘導放射能:0.0046Ci(最大)
(2)計算条件
(イ)使用計算コード:SDC(注)②
(ロ)計算形状
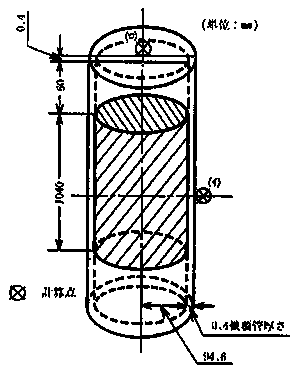 計算にあたっては、実際の燃料体を左図に示すとおりの等価な断面積を有する円柱形に置きかえた。 (3)計算結果
(イ)燃料体表面真横:約90mrem/hr
(ロ)燃料体真上:約38mrem/hr
(注)① 燃料体中の放射能としては(イ)、(ロ)以外に低濃縮ウラン(0.19Ci)等があるが、γ放射線源としては無視しうる。 ② SDC:Shielding-Design Calculation
燃料取扱い施設の遮蔽設計用に開発されたガンマ線線量率計算コード(ORNL-3041 March,1966)
4 一次冷却水の水質及び全ベータ放射能濃度 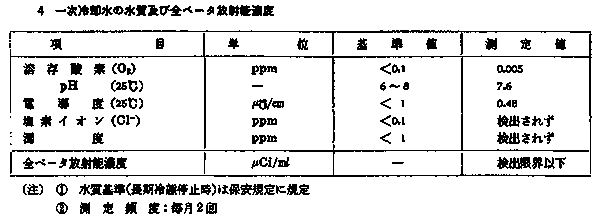 5 一次冷却水等の核種分析結果 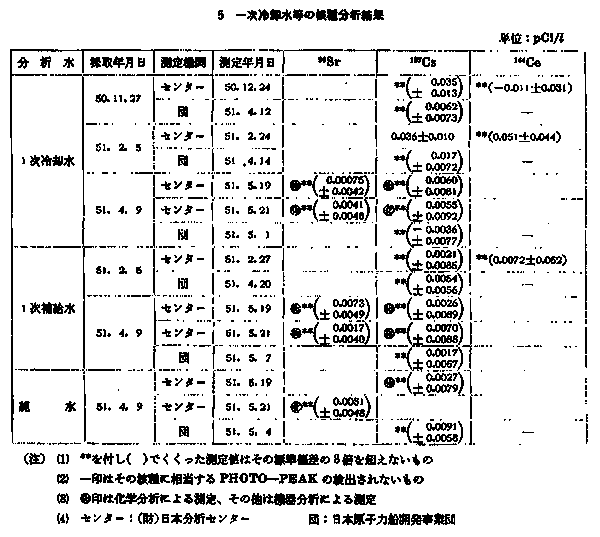 6 燃料体取出し作業手順(B方式) 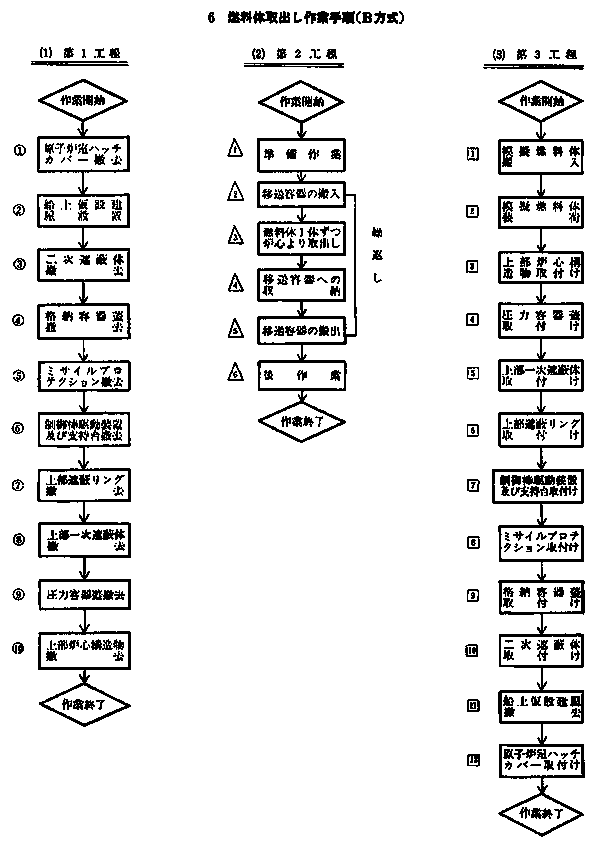 図6-1 第1工程及び第3工程の作業手順説明図 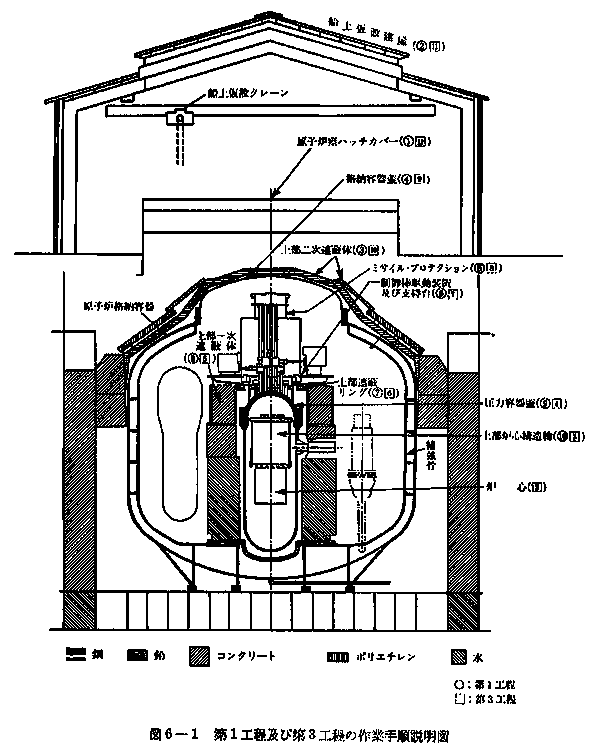 図6-2 第2工程の作業手順説明図 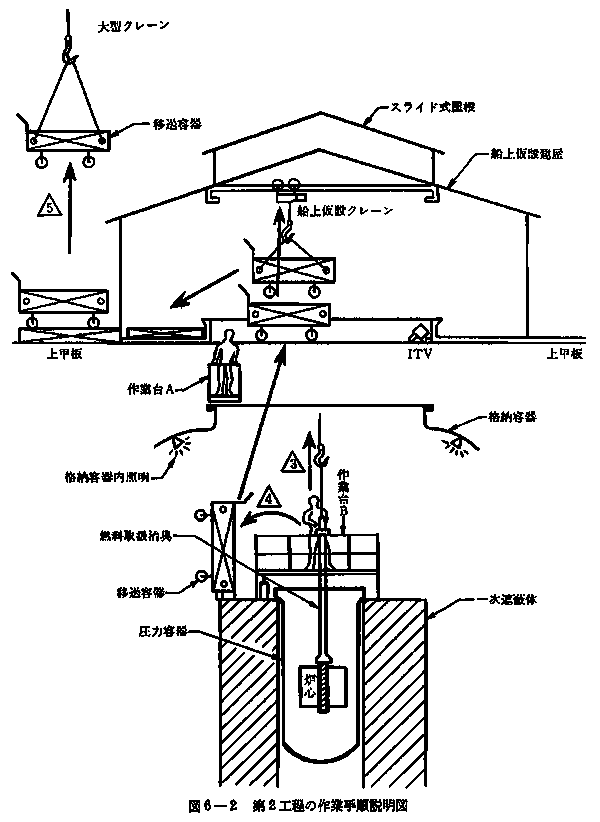 図6-3 燃料体取出し作業概略図 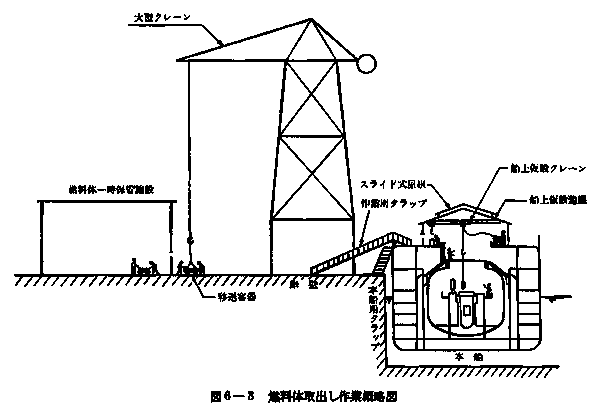 7 燃料体取出しに必要な施設・設備(B方式)
(1)燃料体取出し設備
(2)圧力容器蓋等一時保管施設
(3)燃料体一時保管施設(乾燥保管)
(4)関連附帯設備
8 輸送容器
(1)輸送容器
(2)輸送容器に収納する燃料体
(3)輸送数量
34体(予備燃料体2体を含む)
(4)安全性
容器は燃料体を収納した状態で「放射性物質等の輸送に関する安全基準」(原子力委員会、昭和50年1月21日)におけるA型輸送物及び核分裂性第2種輸送物の基準に合致するものであることを確認する。 (注)燃料体2体当たり
9 燃料体の保管に必要な施設・設備(長期乾燥保管)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前頁 | 目次 | 次頁 |