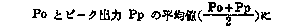| 前頁 | 目次 | 次頁 | |||||||||||||||||||||
|
反応度事故検討会報告書 (発電用軽水型原子炉の反応度事故に対する評価方法について)
昭和52年5月
原子炉安全専門審査会
反応度事故検討会
1 まえがき
本検討会は発電用軽水型原子炉の事故評価を行うにあたって、急激な反応度投入があった場合の反応度事故事象について必要とされる解析条件と解析結果に対する判断基準等を決定することを目的とした。 下記委員より成る本検討会は昭和51年6月の第149回原子炉安全専門審査会で上記目的のために設置された。以降合計14回の会合を持ち、鋭意検討を行い、本報告書をまとめた。
発電用軽水型原子炉の反応度事故に対する評価方法の適用の範囲としては、急激な反応度投入がある事象という観点からPWR、BWRそれぞれについて検討を行った結果、事象名を具体的に掲げることによって適用の範囲を明確にすることとした。 燃料ペレット・エンタルピによる評価基準はNSRR及び海外での実験データ等の最新のデータに基づいて決定したが、今後もNSRR反応度事故実験データ等が継続的に得られると思われるので、適時見直される必要があるものと考える。 なお、NSRR実験データからエンタルピ評価基準を決定した根拠を添付1に、また反応事故としての「運転時の異常な過渡変化」および「事故」に対する評価基準を燃料破損モードとの関連で整理し添付2に示した。 解析にあたっての要求事項については、解析結果に大きな影響を持つ因子に着目し、安全側の評価ができるように設定した。 注 記
本評価方法は上記評価基準の適時見直しを必要とするという観点から当面のあいだ審査会内規として取扱われるのが妥当であると考える。 Ⅰ 目的 この評価方法は、発電用軽水型原子炉の急激な反応度投入を伴なう「運転時の異常な過渡変化」及び「事故」(以下「反応度事故」と総称する)時における暫定的な評価方法を定めたものである。急激な反応度投入、すなわち燃料内で急激な熱発生がある場合の燃料挙動はその他の比較的緩慢な出力上昇を伴なう運転時の異常な過渡変化や事故時の燃料挙動とは異なるものであることは一般に良く知られた事実である。反応度事故時の燃料挙動は遷移沸騰の有無とかあるいは被覆管温度の上昇等に着目するよりはむしろ、反応度事故時の燃料破損との関係が比較的明らかな燃料内発熱エンタルピで判断することの方が適切であり、また各種反応度事故実験でも、実験データは燃料内発熱エンタルピで整理されている。このような観点から反応度事故に対する判断基準としては主としてエンタルピ基準を設け、これに対応する解析前提条件を定めるものである。 Ⅱ 適用の範囲 本評価で言う「反応度事故」とは急激な反応度投入を伴なう事象であって、具体的には、下記の事象を本評価方法の対象とする。 1 運転時の異常な過渡変化のうち
PWRでは
未臨界状態からの制御棒クラスタ引抜き
BWRでは
起動時における制御棒引抜き
2 事故のうち
PWRでは
制御棒クラスタ飛出し事故
BWRでは
制御棒落下事故
注)ここで云う「急激な反応度投入」とは原則的には1ドル以上の反応度投入がある場合を云う。従って、PWRの出力状態からの制御棒飛出し事故は、ここに示す評価基準による必要はない。 Ⅲ 評価基準 反応度事故の解析、結果は以下の評価基準を満足しなければならない。 1 反応度事故のうちⅡの1にあっては
1)燃料エンタルピ(ペレット半径方向平均)の最大値は当該事象の初期条件として燃料棒内圧が冷却材圧力を下回るか、または上回ったとしても2.5Kg/㎝2以内の場合は、非断熱計算で170cal/gUO2また燃料棒内圧が冷却材圧力を2.5Kg/㎝2以上上回る場合は非断熱計算で110cal/gUO2を超えてはならない。 2)原子炉圧力は原子炉冷却材圧力バウンダリの設計圧力の1.1倍を超えてはならない。 2 反応度事故のうちⅡの2にあっては
3)事故時の燃料内出力パルスのうちピーク出力部エンタルピ(ペレット半径方向平均)の最大値は断熱計算で230cal/gUO2を超えてはならない。 4)燃料エンタルピ(ペレット半径方向平均)の最大値は非断熱計算で230cal/gUO2を超えてはならない。 5)原子炉圧力は原子炉冷却材圧力バウンダリの設計圧力の1.2倍を超えてはならない。 注)
① 評価基準1)および4)に云うエンタルピは燃料ペレットの初期保有エンタルピと当該事象の非断熱解析によって追加される燃料ペレットの印加エンタルピの総和であって、基準は0℃の状態とする。 ② 評価基準3)に云うエンタルピは燃料ペレットの初期保有エンタルピと当該事象のピーク出力部の断熱解析によって追加される燃料ペレットの印加エンタルピの総和である。 ③ 評価基準3)に云うピーク出力部についての定義を図1に示す。当該事象発生の初期出力Poとピーク出力Ppの平均値 図1 反応度事故時のピーク出力部の定義 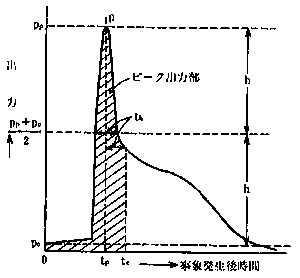 ④ 評価基準5)については原子炉安全技術専門部会で検討中の事故評価指針等ができた時点で見直される必要がある。 Ⅳ 解析に当っての要求事項 解析に当って必要とされる事項を以下に示すが、各要求及び指定事項からはずれたものを用いて解析を行う場合には、実験データ等によって、その妥当性を示す必要がある。 1 前提条件
1)炉心状態
解析初期条件としての炉心状態を示す冷却材温度、原子炉圧力及び出力分布等については、選定した条件が最も厳しい燃料エンタルピを与えるものであることを適切な方法で示さなければならない。また、被覆が破損する燃料棒本数が最大となるケースについても解析を行わなければならない。 2 動特性計算
1)原子炉スクラム
原子炉を停止する原子炉スクラム信号を明らかにし、この場合のスクラム遅れ時間を適切に考慮しなければならない。またこの際に最大反応度効果を有する制御棒(クラスタ)1本が完全引抜位置に固着して挿入されないものとする。 スクラム速度は実験的に確められた保守的な値を採用しなければならない。 2)反応度添加率
抜け出す制御棒価値は計算上の不確定要素を考慮して十分保守的に計算しなければならない。また反応度添加率は制御棒の微分価値と、抜け出す制御棒の位置対時間の関係より求め、もし微分価値が使えない時はそれに代わる保守的な手法を用いなければならない。 ① 「未臨界状態からの制御棒クラスタ引抜き」にあっては、最大反応度効果を有する2つの制御棒クラスタバンクが機構上許される最大速度で同時に引き抜かれるものとする。 ② 「起動時における制御棒引抜き」にあっては、制御棒価値ミニマイザが許容される最大価値を有する制御棒1本が機構上許される最大速度で連続的に引抜かれるものとする。 ③ 「制御棒クラスタ飛出し事故」にあっては、全制御棒バンクが炉心出力状態に応じて許容される最大挿入位置にあり、そのうち最大反上度効果を有する制御棒クラスタ1本が事故想定上考え得る最大速度で飛び出すものとする。 ④ 「制御棒落下事故」にあっては、落下し得る制御棒の最大制御棒価値が、制御棒価値ミニマイザで許容される最大のものであって、落下速度は制御棒落下速度リミッタで制限される最も速い値とする。 3)実効遅発中性子割合(βeff)及び即発中性子寿命(l*)
βeffとl*の計算は摂動論から導かれる定義に基づいて行うものとする。 4)ウエイティング・ファクタ
3次元核計算から低次元動特性計算へ次元を縮約するにあたってはウエイティング・ファクタを適切に選定しなければならない。ウエイティング・ファクタは時間依存で考えるのが妥当であるが、時間依存にしない場合は、保守的に選定しなければならない。 5)燃料の物性値等
ペレット及び被覆管の物性値ならびにギャップ熱伝達係数、被覆管表面熱伝達係数等については解析している対象に応じて適切に選定しなけらばならない。 注)ギャップ熱伝達係数及び被覆管表面熱伝達係数として、原子力委員会が定めた「軽水型動力炉の非常用炉心冷却系の安全評価指針」で使用を認めているもの、およびNSRR等の実験結果に基づいて決定されたものを使用することは妥当である。 6)UO2の比熱として以下に示すデータを推奨する。これ以外の比熱を使用する場合にはこれと同等か、ないし保守的であることを示さなければならない。 298K~融点では
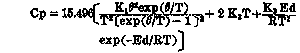 ここにCp=比熱(J/㎏-K)
K1=19.145(cal/mol-K)
K2=7.8473×10-4(cal/mol-K2)
K3=5.6437×106(cal/mol)
θ=535.285(K)
Ed=37694.6(cal/mol)
T=温度(K)
R=1.987(cal/mol-K)
融点以上では
Cp=502.95J/㎏-K
注)ANCR-1263
NRC-5
DATE PUBLISHED-FEBRUARY 1976
“A HANDBOOK OF MATERIALS PROPERTIES FOR USE IN THE ANALYSIS OF LIGHT WATER REACTOR FUEL ROD BEHAVIOR”
7)減速材反応度係数
非断熱計算を行う場合、冷却材のボイド、圧力、温度、密度等の変化に伴う反応度係数を考慮しても良いが、選定した値が十分安全余裕を持ったものであることを適切な方法で示さなければならない。 上記反応度フィード・バックのうち正になるものがある場合には、これを安全側に評価し計算しなければならない。 また、3次元解析をしない場合には適切なファクタを乗じ保守的に計算を行うこと。 8)ドップラ係数
ドップラ係数はダンコフ効果の修正を含む実効共鳴積分に基づいて計算するとともに、利用できる実験データ(Hellstrandのデータ等)と保守的に対比して決めなけらばならない。ドップラ効果の評価にあたっては、燃料、温度予測の不確定要素もあわせて考慮し保守的なものとしなければならない。 注)解析にあたっての要求事項7)、8)について
解析結果に影響を及ぼす各種反応度フィード・バックの計算は、想定する事象に適応した条件で求める必要がある。-般的に反応度事故の場合、燃料のみが急激に温度上昇し、引続いて減速材の温度が上昇する。また、この場合、炉心の制御棒パターンも通常パターンから異ったものとなる。従って、反応度フィード・バックの算出にあたっては、当該事象をできるだけ厳密に取扱い、燃料および減速材の温度条件、燃焼度、構成物の温度変化に伴う密度変化、制御棒パターン等を考慮した核計算を行う必要がある。 3 燃料挙動解析
1)ピーキングファクタ
燃料の熱点解析を行う場合中性子束分布に関するピーキングファクタは安全余裕を持って選定しなければならない。 2)炉心出力分布
被覆が破損する燃料棒の本数決定のための炉心出力分布は直接計算しない場合は安全余裕を持ったものであることを適切な方法で示さなければならない。 3)当該事象の初期条件として燃料棒内圧が冷却材圧力を下回るか、または上回ったとしても内外圧差が2.5Kg/㎝2g以内の場合、燃料エンタルピ(ペレット半径方向平均)が非断熱計算で180cal/gUO2また燃料棒内圧が冷却材圧力を2.5Kg/㎝2g以上上回る場合には120cal/gUO2をそれぞれ超える燃料被覆は破損したものとしなければならない。 注)ここに云うエンタルピは燃料ペレットの初期保有エンタルピと当該事象の非断熱解析によって追加される燃料ペレットの印加エンタルピの総和であって、基準は0℃の状態とする。 4)燃料の物性値等
2の5)に同じ
5)UO2の比熱
2の6)に同じ
4 圧力サージ計算
PWRにあっては圧力サージ計算は、燃料から冷却材への熱伝達、金属・水反応、冷却材中での熱発生に基づいて行う。 体積サージを用いて圧力トランジェントを計算する際には、原子炉冷却材系統内の流体の移動、蒸気発生器での伝熱および加圧器逃し弁、安全弁の作動を考慮に入れて良いが、制御棒飛出し事故にあっては、制御棒駆動機構圧力ハウジングの破損による減圧効果は見込んではならない。 Ⅴ 評価のための必要資料 反応度事故解析の評価をするにあたっては、前記の要求事項を満足していることを確認する必要がある。このほか解析に用いられている入力値の妥当性をも検討する必要がある。このため解析結果の提出に当っては技術的検討を行うに十分な解析手法および解析に用いられる入力値を記載した解析モデルの詳細説明書を提出しなければならない。 添付 1
NSRR実験データからエンタルピ評価基準を決定した根拠
1 燃料被覆の破損限度と運転時の異常な過渡変化に対する許容設計限界
NSRRの実験より大気圧、常温条件下における標準燃料の実験データを整理した結果253cal/gUO2以下では燃料の破損は発生していないことがわかった。 また大気圧、常温条件における加圧燃料(30㎏/㎝2g)に関しては164cal/gUO2以下では燃料破損は発生していなかった。 さらに、加圧燃料であっても燃料棒内外圧差が2.5㎏/㎝2以下の加圧燃料では加圧の影響は小さい。 (1)燃料被覆の破損限界
上記実験結果から、標準燃料および加圧燃料の燃料被覆の破損限界のしきい値はそれぞれ253cal/gUO2および164cal/gUO2と考えられるが、上記実験に含まれていないパラメータの影響と実験中の熱除去量の影響を考慮しなければならない。それぞれの因子の影響はNSRRおよびその他の実験データの技術的判断から以下のように評価できる。 1)実験中の熱除去の影響 -10%
2)燃料燃焼の影響 -10%
3)燃料バンドルと単一燃料棒実験の相違の影響 -10%
4)高温、高圧実験と常温常圧実験の相違の影響 0%
注)上記1)~3)の中に高温高圧条件のマージンがある程度含まれていると考えられるので0%としたが、高温、高圧実験の結果が利用可能となった時点で見直される必要がある。 以上のパラメータによる影響の補正をおこなうと、前記燃料被覆の破損限度のしきい値は標準燃料について180cal/gUO2、加圧燃料については120cal/gUO2となる。 その他、燃料濃縮度、燃料棒長さなどの因子についてはNSRR実験条件の方が厳しいので、これらに対する補正をしないことは安全側であると考えられる。 (2)運転時の異常な過渡変化に対する許容設計限界
運転時の異常な過渡変化においては燃料棒は損傷をおこしてはならない。従って燃料被覆の破損限界に対してある余裕を取ったエンタルピの値を許容設計限界とするのが妥当である。ここでは実験精度等から判断して余裕を10cal/gUO2との技術的判断をした。すなわち、標準燃料に対する許容設計限界は170cal/gUO2、加圧燃料(燃料棒内圧が2.5㎏/㎝2以上外圧を上回る場合)に対しては110cal/gUO2とした。 2 燃料棒破損による圧力波発生限界
NSRR実験によれば試験燃料棒が幾つかの破片に分断し破壊力が発生する限界のエンタルピしきい値は335cal/gUO2である。このデータについても前記燃料被覆の破損限界の場合と同じく、実験に含まれていないパラメータの影響を考慮し、さらに予備的安全余裕として10cal/gUO2を差し引くと230cal/gUO2を得る。 NSRRでの反応度事故実験の出力パルス波形と発電用軽水型原子炉で想定される反応度事故時の出力パルス波形は多少異なっており、後者の場合は前者と比較してランアウト出力の比重が大きく、パルス部の発熱量とランアウト部の発熱量の比はほぼ1:1になっている。このような観点から、ピーク出力部に対する制限とランアウト出力部に対する制限の2つを設けた方が良いとの考えに立ち、ピーク出力部ではほとんど除熱がないことからピーク出力部に対する制限は断熱エンタルピ、ランアウト部も含む総出力に対しては非断熱エンタルピとすることとした。 NSRR実験でのランアウト出力は全発熱量のほぼ10%にあたり、実験中の燃料棒からの除熱量にほぼ匹敵している。従って、前記制限値は以下のように書きあらわせる。 ① ピーク出力部のエンタルピは断熱計算で230cal/gUO2以下であること。 ② 全出力に対するエンタルピは非断熱計算で230cal/gUO2以下であること。 当検討会は反応度事故時のエンタルピがこれらのしきい値を超えなければ事故の結果、圧力衝撃波等が発生し原子炉の安全をおびやかすことはないと判断した。 加圧燃料に対するデータが未だ取得されていないことから、ここで検討の対象としたデータは標準燃料だけのものである。しかしながら燃料の分断という破損モードに対しては加圧の影響はあまりないとの技術的判断に立ち、このような評価基準を定めた。 3 浸水燃料について
浸水燃料については炉内に存在する本数が少ないと予想されること、圧力波が発生したとしても、その破壊エネルギーがそれほど大きくならないと考えられること、及び現状では十分な量の実験データが得られていないことなどから今回の検討範囲からは除外した。 4 まとめ
以上導かれた評価基準をまとめると以下の通りである。 (1)運転時の異常な過渡変化に対する許容設計限界
170cal/gUO2(外圧支配)
110〃(内圧支配)
(2)燃料被覆の破損限界 180cal/gUO2(外圧支配)
(事故解析要求事項) 120〃(内圧支配)
(3)圧力波発生限界
(事故評価基準)
ピーク部、断熱計算 230cal/gUO2
全出力、非断熱計算 〃
反応度事故における燃料状態と評価基準 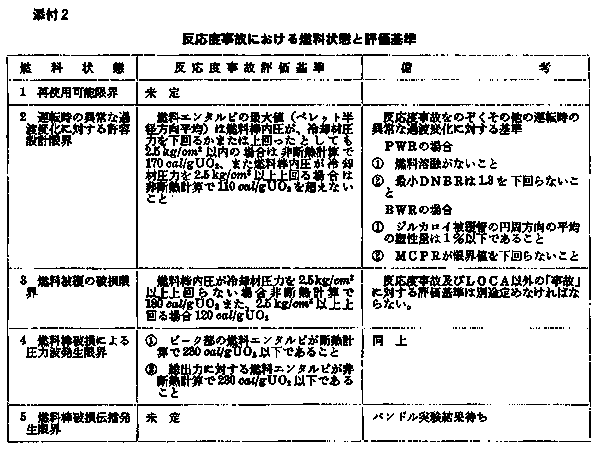 | |||||||||||||||||||||
| 前頁 | 目次 | 次頁 |