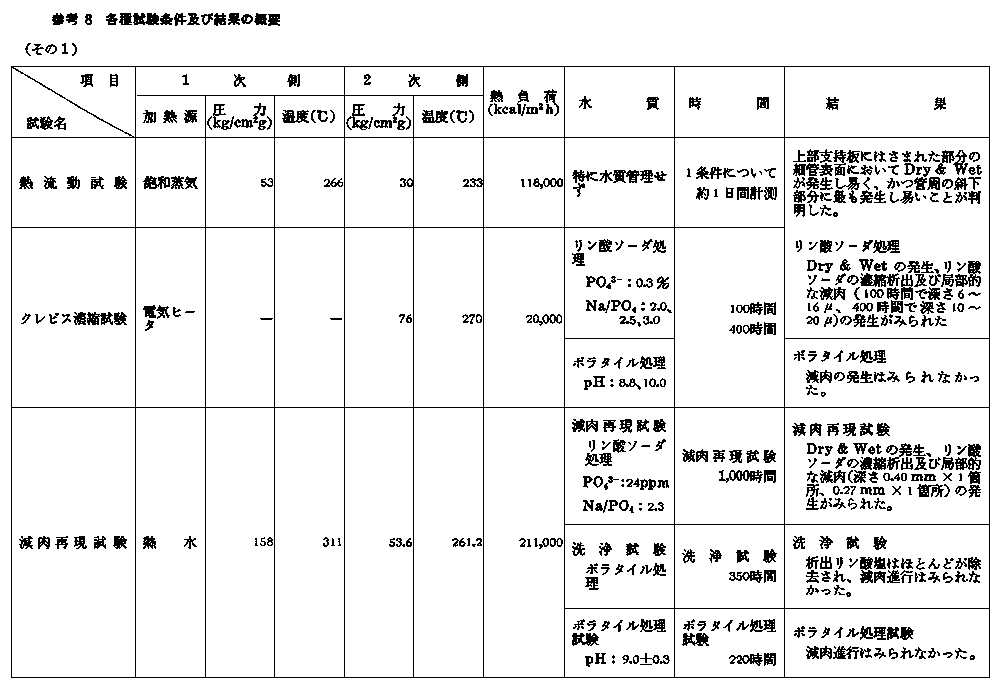|
昭和50年12月23日
原子力委員長談話
(1)美浜発電所1号炉は、昭和49年7月17日蒸気発生器の細管漏洩のため停止し、引き続き詳細な調査及び原因の究明が実施されている。
この間、細管減肉の原因については、通商産業省において原子力発電技術顧問会に専門家による特別委員会を設置してモデル蒸気発生器による減肉再現試験を始めとする各種試験及び検査の結果に基づき検討が進められてきた。当委員会は、この度、通商産業省の減肉原因についての調査結果について報告をうけたが、その内容は妥当なものと考える。(別添報告書参照)
(2)通商産業省の調査結果によれば、美浜1号炉蒸気 発生器の細管減肉は、①上部支持板にはさまれた部分の細管表面においては、沸騰により生じた気泡の離脱が妨げられ局部的にDry&Wetが発生することがあり、②この部分において水質管理のため、蒸気発生器内2次冷却水に注入されたリン酸ソーダの濃縮が生じ、③この濃厚なリン酸ソーダ溶液が細管表面に反覆接触するため、まず細管表面に形成されている保護皮膜を溶解し、④更に管材(インコネル600)と、直接反応してニッケル等(管材の成分)とのリン酸-金属塩となる化学的腐食現象により局部的に生じたものと推定され⑤粒界腐食あるいは応力腐食割れではないとしている。
(3)このようにして起る濃厚なリン酸ソーダ溶液によるインコネル600材の化学的腐食による細管減肉は、別添報告書に述べられているその発生の機構から明らかなように、発生箇所は細管表面のDry&Wetの発生する部分に限られ、かつ、その部分においても、一様に発生するものではなく、局部的な窪みをもった減肉として発生するものであり、又、短時間に急速に進行し細管の破断に至るような種類のものではないと考える。
(4)過去において美浜1、2号炉、玄海1号炉で発生した蒸気発生器細管の損傷は、予定された定期点検により、あるいは放射能漏洩に対する保安装置の第一段階である放射能監視装置により、漏洩に至らぬ段階ないしは微少な漏洩の段階で発見され、十分な余裕をもって措置が講じられ、周辺環境に漏洩放射能による影響を及ぼしたことはない。このように災害防止に対する多重防護のシステムは有効に作用しており、災害防止という観点からは、特段の支障があるものではない。
(5)当委員会は加圧水型軽水炉の蒸気発生器の2次冷却水の水質管理にリン酸ソーダを使用せず揮発性の添加剤を使用するボラタイル処理を採用することが、より適切な方法であると考える。美浜2号炉については、すでにリン酸洗浄についてのサイクリング運転の際に談話を発表したところであるが、現在この方向で通商産業省において取られている措置は、妥当なものであると考える。(別紙参照)また、美浜1号炉について今後、今度の調査結果を踏え、対策の検討を行ない、原子力発電に対する国民の信頼の同復に寄与するよう関係者が最大の努力をされんことを要望する次第である。
(別紙)
関西電力(株)美浜発電所1、2号機について
昭和50年12月23日
資源エネルギー庁
Ⅰ 2号機について
1 美浜2号機(加圧水型出力50万KW)は、昭和50年1月8日蒸気発生器の細管漏洩が発生したため、運転を停止し、その対策を定期検査と併行して実施中である。
2 この細管の減肉漏洩は、二次冷却水の流れが妨げられる部分においてりん酸塩の濃縮により生じたものと判断されるので、細管等に附着しているりん酸塩を除去しボラタイル処理とするため、減肉が認められた細管について栓工事を行った後、原子炉を停止した状態での温水洗浄及び原子炉のサイクリング運転による洗浄を行ってきた。
現在、二次冷却水中のりん酸濃度は十分(0.2ppm以下)下がり、又、渦電流探傷試験により細管の健全性は維持されていることが確認された。
3 関西電力は、今後蒸気発生器については二次冷却水の水質管理をボラタイル処理に切換えたうえ、復水器からの海水リークの早期発見監視、スラッジ発生防止のためのブローの実施等入念な配慮を払いつつ運転を再開したいとしている。
通産省としては、今後負荷試験等を行い、総合的な安全性が確認された場合には2号機の運転再開を認めることとしたい。
Ⅱ 1号機について
1 美浜1号機(加圧水型出力34万KW)は、昭和49年7月17日蒸気発生器細管漏洩が発生したため、運転を停止し、その対策を検討中である。
2 この細管の減肉漏洩は、別添の通商産業省原子力発電技術顧問会美浜発電所1号機蒸気発生器対策特別委員会報告書のとおり、二次冷却水の流れが妨げられる細管上部支持板部分におけるりん酸塩の濃縮により生じたものであるが、その対策については美浜1号機はりん酸塩の使用期間が長いこと、すでに栓工事を行っている細管が多いこと等の影響を含め、更に検討を進めることとする。
(別添報告書)
関西電力(株)美浜発電所1号機蒸気発生器細管減肉の
原因調査の結果について(中間報告)
昭和50年10月24日
通商産業省原子力発電技術顧問会
関西電力(株)美浜発電所1号機
蒸気発生器対策特別委員会
関西電力(株)美浜発電所1号機蒸気発生器
細管減肉の原因調査の結果について
昭和50年10月24日
通商産業省原子力発電技術顧問会
関西電力(株)美浜発電所1号
機蒸気発生器対策特別委員会
委員長 内田 秀雄
関西電力(株)美浜発電所1号機蒸気発生器細管減肉の原因についての調査結果は、次のとおりである。
第Ⅰ章 調査の概要
通商産業省原子力発電技術顧問会関西電力(株)美浜発電所1号機蒸気発生器対策特別委員会(以下「委員会」という。)は、関西電力(株)美浜発電所1号機(以下「美浜1号機」という。)の蒸気発生器細管の減肉現象の原因を究明するにあたっては、従来から上記の原子力発電技術顧問会における検討に供されて来た細管減肉原因解明のための各種試験あるいは検査の結果を整理し、これらに基づき細管減肉の原因を推定するとともに、更に実際の蒸気発生器細管を使用し実機と使用条件を合わせた減肉再現試験を行い、これを裏付けることとした。
原因の推定及び裏付けのためになされた各種試験あるは検査の結果、並びにこれらに基づく原因の推定の概要は、次のとおりである。
1 原因推定のための試験及び検査
(1)抜管検査
抜管検査は、47年6月の第1回漏洩時に1回、49年7月の第2回漏洩時に2回行われ、減肉細管を切取り、詳細な外観検査及び各種金属検査が三菱重工業(株)、(財)電力中央研究所及びウエスチングハウス社において実施された。
結果は、いずれも細管表面の局部的な減肉であって、粒界腐食あるいは応力腐食割れは見られず、又細管のその他の部分は健全であった。更に減肉部分及び細管の他の部分双方において、管材の組成、ミクロ組織、硬度等はインコネル600(ニッケルを主体としクロム及び鉄を加えた合金)として正常な状態にあり、材質変化は認められなかった。
(2)熱流動試験
美浜1号機蒸気発生器細管の減肉発生の要因を熱流動の面から究明するため、細管減肉が見られた上部支持板部に関する熱流動試験が48年4月から9月にわたり三菱重工業(株)高砂研究所において実施された。
本試験に用いられた装置は、コンバッション・エンジニアリング社型(以下「CE型」という。)蒸気発生器の実機運転中における細管上部支持板部(ホットレグ側)における気水混合状態を模擬したものである。
本試験の結果、上部支持板にはさまれた部分の細管表面においては、沸騰により生じた気泡の離脱が妨げられ、このため濡れた状態と乾いた状態との繰返しの周期が長いいわゆるDry&Wet現象(以下「Dry&Wet」という。)が発生し易く、かつ、その周方向の位置については管周の斜下部分において最も発生し易いことが判明した。
これは美浜1号機蒸気発生器細管の減肉発生箇所と一致しているものである。
(3)クレビス濃縮試験
上記熱流動試験の結果により細管上部支持板部における細管表面にDry&Wetが発生し易いことが明らかとなったので、このDry&Wet現象に伴う細管表面の局部的な減肉現象を解明するため、細管表面に冷却水の流れが妨げられる部分、いわゆるクレビス部を作り、オートクレーブ(高温高圧の条件下で目的とする化学反応を起させるための容器)を用いて細管表面にDry&Wetを発生させ、この部分におけるリン酸ソーダの濃縮及びこれによる減肉発生試験が、三菱重工業(株)高砂研究所において49年2月から9月にわたり実施された。
この結果、リン酸ソーダ処理では、濃度の異る何れの場合においても、クレビス部にDry&Wet及びリン酸ソーダの濃縮析出が起り、100~400時間で減肉が発生した。
なお、ヒドラジンを使用するボラタイル処理の場合について、同様の試験が実施されたが、減肉は発生しなかった。
(4)減肉再現試験
本委員会は、以上のような美浜1号機蒸気発生器における減肉現象に関する熱流動試験及びクレビス濃縮試験の結果から、減肉現象は実機においても同様の原因によるものと推定し、このことをモデル蒸気発生器を用いた細管減肉再現試験により裏付けることとした。このモデル蒸気発生器を用いた減肉再現試験は、50年4月から9月にわたり三菱重工業(株)高砂研究所において実施された。
本試験に用いられた装置は、新管1本と美浜1号機蒸気発生器から切取った旧管1本とをu字形に曲げて供試管として組込み、更にこの供試管にアンブレラ(2次冷却水の流れが妨げられる部分を模擬するための傘状の装置)及びサンドイッチ(上部支持板部における細管と支持板の構造を模擬するための板状の装置)を取付けることにより細管の内外における1次冷却水及び2次冷却水の流動と伝熱状態を模擬したモデル蒸気発生器である。
試験は、実機と同様の伝熱条件及び水質条件で約1,000時間行われた。
試験の結果、アンブレラ及びサンドイッチ部におけるDry&Wetの発生、リン酸ソーダの濃縮折出、及びアンブレラ8箇所のうち2箇所に局部的な減肉が見られた(新管ホットレグ側下部アンブレラ内深さ0.40mm×1箇所、及び旧管ホットレグ側下部アンブレラ内深さ0.27mm×1箇所)。
又、減肉の状況は、実機におけるものと類似しており、粒界腐食、応力腐食割れ、材質変化等は認められなかった。
引続き、析出リン酸塩を除去するための洗浄試験を行った結果、細管表面等に付着している析出リン酸塩はほとんどが除去され、又、この間の減肉進行は認められなかった。更に、洗浄試験の後リン酸ソーダを使用しないヒドラジンによるボラタイル処理試験が10日間実施されたが、減肉の進行は認められなかった。
2 原因の推定
以上の試験及び検査の結果から、細管減肉は、①上部支持板にはさまれた部分の細管表面においては沸騰により生じた気泡の離脱が妨げられ、Dry&Wet((2)熱流動試験の項参照。)が発生することがあり、②この部分において水質管理のため蒸気発生器内2次冷却水に注入されたリン酸ソーダの濃縮が生じ、この濃厚なリン酸ソーダ溶液が細管表面に反覆接触するため、まず細管表面に形成されている保護皮膜を局部的に溶解し、更に管材と直接反応してニッケル等管材の成分とのリン酸-金属塩となる腐食現象により生じたものと推定される。
第Ⅱ章 細管減肉原因解明のための各種試験及び検査とその結果
1 抜管検査
(1)抜管検査
実際の細管を蒸気発生器から切取って行う抜管検査は47年6月の第1回漏洩時に10本、49年7月の第2回漏洩時に当初1本、次いで本委員会の指示に基づき12本の細管を切取り、減肉部の外観検査、金属組織検査、管材化学分析、硬度測定、付着物の分析等の詳細調査が、三菱重工業(株)高砂研究所、(財)電力中央研究所及びウエスチングハウス社において実施された。
(2)検査結果
これらの抜管検査により、次のようなことが明らかとなった。(参考4参照)
ⅰ)現象は、いずれも上部支持板にはさまれた部分の細管表面における局部的な減肉であり、高濃度アルカリ及び応力集中の存在によって生ずるといわれている粒界腐食あるいは応力腐食割れや、細管表面全面にわたって均一に起る全面腐食ではなかった。
ⅱ)減肉している局部以外の細管の表面には異常は認められず、健全性が保たれていた。
ⅲ)金属組織、管材組成及び硬度の検査結果は、減肉部及び他の健全部とも差異はなく、それぞれインコネル600材としての正常な状態にあると認められた。
ⅳ)減肉は細管が上部支持板にはさまれている部分において発生しているが、その位置については、主として管周の斜め下側に発生していた。又、減肉部は付着物が非常に少なく最も減肉が進んでいる部分は金属色を呈していた。
ⅴ)付着物の分析結果については、健全部では給水系統から持込まれたと考えられる鉄、銅等が主成分であったが、減肉部近傍の付着物には、リン、ナトリウムが含まれており、局部的な濃縮があったものと推察された。
2 熱流動試験
(1)目的
美浜1号機蒸気発生器(CE型)細管減肉の要因を熱流動の面から究明するため、細管減肉がみられた上部支持板部に関する熱流動試験が48年4月から9月にわたり三菱重工業(株)高砂研究所において実施された。
(2)試験装置及び試験条件(参考5及び参考8参照)
本試験に用いられた装置は、CE型蒸気発生器の実機運転中の上部支持板部(ホットレグ側)における2次側の気水混合状態を、上部細管群及び支持板により模擬したものである。すなわち、試験条件としては1次側には温度266℃の飽和蒸気(1次側上部ヘッダにおいて)を2次側には圧力30kg/cm2g、温度233℃の気水混合流を供給し、この気水混合流が支持板により妨げられながら管群の間を上昇する間に細管表面から熱を受け、更に蒸気を発生させることにより、上部細管群内における2次側の気水混合状態を模擬するものである。
Dry&Wetの発生の確認は、支持板内外の細管表面の温度を熱電対により連続的に計測することによって行われた。
(3)試験結果
本試験により次のようなことが明らかとなった。
ⅰ)細管が上部支持板にはさまれている、いわゆる支持坂内の細管表面にDry&Wetが発生し易く、その周期は本試験装置の場合約2秒と測定された。又、支持板外においては、Dry&Wetは発生しにくい。
ⅱ)Dry&Wetの周方向の位置としては、管周の斜め下45°の面が最も発生し易い。このことは、実機における減肉発生位置と一致している。
このような結果は、細管の両側に挿入されている支持板(設計上の細管と支持板との隙間0.33mm)により2次冷却水の流動が妨げられるため、細管の下側において発生した蒸気泡の離脱が困難になり、蒸気泡が接触している細管表面の温度が上り、次に蒸気泡が離脱すると細管表面は再び冷却水により濡らされるという乾湿状態が繰り返されていることを示しているものと解された。
なおこのDry&Wetの周期については本試験装置の場合約2秒と計測されているが、実機においては位置、熱流動状態等の差異等によりそれぞれ異なった値をもつものと考えられる。
3 クレビス濃縮試験
(1)目的
細管表面においてDry&Wetが発生する場合に、リン酸ソーダによる蒸気発生器内2次冷却水の水質管理方式にあっては局部的なリン酸ソーダの濃縮とこれによる細管の減肉が発生するかどうかを確認するための静的条件下におけるクレビス濃縮試験が49年2月から9月にわたり三菱重工業(株)高砂研究所において実施された。
(2)試験装置及び試験条件(参考6及び参考8参照)
本試験に用いられた装置は、細管表面に冷却水の流れが妨げられる部分、いわゆるクレビス部(0.3mm)を設けた供試管をオートクレーブ中に入れ、供試管表面にDry&Wetを発生させ、この部分におけるリン酸ソーダの濃縮及びこれによる減肉発生試験を行えるようにしたものである。オートクレーブは電熱で加熱し、更に供試管内に入れた電熱ヒータによって所定の伝熱面熱負荷が得られるようにした。実験条件としては、実機の2次冷却水の温度圧力条件に相当するよう液温を270℃圧力76kg/cm2gとし、更に供試管表面の熱負荷を20,000kcal/m2h(実機は100%出力時において約200,000kcal/m2h)として、100時間及び400時間の試験を行った。
又、オートクレーブ内の水質は、PO43-濃度0.3%、Na/PO4モル比2.0、2.5、3.0でリン酸ソーダによる2次冷却水の水質管理に関する試験を行った。又、この他に比較のためボラタイル処理に関する試験として、ヒドラジンによりpHを8.8及び10.0に調節した場合について試験を行った。
(3)試験結果
ⅰ)クレビス部の管表面においては、予想どおりDry&Wetが発生していることが確認された。
ⅱ)リン酸ソーダ処理の場合では、クレビス部の供試管表面においてリン酸塩の析出がみられた。一方、クレビス部分以外においては、リン酸塩の析出はみられなかった。このように、リン酸塩がDry&Wetの部分において析出したことから、この部分においては明らかにリン酸塩の濃縮が生じているものと推定された。
ⅲ)リン酸塩処理の場合では、Na/PO4モル比に関係なく局部的な細管腐食が発生し、試験時間100時間で6~16μ、400時間で10~20μの減肉が認められた。この局部的腐食は、濃縮されたリン酸塩によるものと推定された。
ⅳ)ボラタイル処理の場合では、クレビス部の供試管表面においてDry&Wetが発生しているにもかかわらず、供試管表面には腐食の発生はみられなかった。
ⅴ)更に、ボラタイル処理であって、かつ復水器細管漏洩がある場合の条件(Cl-濃度2ppm)における試験でも、細管表面には腐食の発生はみられなかった。
4 減肉再現試験
(1)目的
美浜1号機蒸気発生器における減肉現象については、熱流動試験により細管上部支持板内における細管表面にDry&Wetが発生し易いこと、更にクレビス濃縮試験によりDry&Wet発生部におけるリン酸ソーダの濃縮、析出による減肉の発生が確認された。
本委員会は、以上のような試験結果から、減肉現象は実機においても同様の原因によるものと推定し、更に実際の蒸気発生器細管を使用するモデル蒸気発生器による細管減肉再現試験を行い、これを裏付けることとした。
このモデル蒸気発生器を用いた減肉再現試験はリン酸ソーダ処理による減肉再現試験、リン酸ソーダを使用しない場合のボラタイル処理試験並びにこれらの試験の間における洗浄試験からなり、50年4月から9月にわたり三菱重工業(株)高砂研究所において実施された。
(2)試験装置(参考7参照)
本試験に用いられた装置は新管1本と、美浜1号機蒸気発生器から切取った旧管1本とをU字形に曲げて供試管として組み込み、更にこの供試管にアンブレラ(2次冷却水の流れが妨げられる部分を模擬するための傘状の装置)を計8箇所、及びサンドイッチ(上部支持板部の構造を模擬するための板状の装置)を計2箇所取り付けることにより、細管の内外における1次冷却水及び2次冷却水の流動と伝熱状態とを模擬したモデル蒸気発生器である。
構成は試験部、1次ループ、2次ループ、及び付属機器からなっている。又、供試管には美浜1号機蒸気発生器から切取った旧管(19.05mmφ×1.42mmt)1本と、新管(22.22mmφ×1.35mmt)1本とが使用された。
(3)減肉再現試験(参考8参照)
1)試験条件
1次系及び2次系の入口温度及び圧力並びに熱負荷を実機の100%負荷に合わせ(1次系311℃、158kg/cm2g、2次側入口261.2℃、53.6kg/cm2g)、2次系の流動状況も極力実機に近いものとした。2次系の水質はPO43-濃度24ppm、Na/PO4モル比2.3とし、試験時間は1,000時間とした。なお、これらの値は49年6月4日~49年7月17日における水質条件及び運転時間に相当するものである。
2)試験結果
ⅰ)管表面温度
アンブレラ内及びサンドイッチ内の管表面温度を熱電対により連続計測した結果、275~295℃程度の範囲にわたり温度変化が繰り返されており、細管表面におけるDry&Wetの発生が明瞭に確認された(圧力53.6kg/cm2gにおける2次冷却水の飽和温度は261.2℃である。)又、その周期は約2秒であり、先に実施された熱流動試験の結果とよく一致した。
ⅱ)リン酸ソーダの析出
アンブレラ内及びサンドイッチ内の管表面に灰白色のデポジット(析出物)がみられたが、その他の部分に灰白色のデポジットはなく黒褐色を呈していた。
デポジットの組成は化学分析及びX線回折によってほとんどリン酸ソーダであることが確認され、又、管表面近くでは管材成分であるニッケル、クロムの含有率がやや高くなっていた。なお、本試験におけるリン酸ソーダの系内への残留量は収支バランスから約30g(PO43-として)と推定された。このように、クレビス濃縮試験と同様に、アンブレラ内及びサンドイッチ内におけるリン酸ソーダの析出が見られたことから、Dry&Wetが発生している細管表面においては2次冷却水の処理のため注入されているリン酸ソーダの濃縮が生じているのは明らかであると推定された。
ⅲ)減肉の状況
新管のホットレグ側下部アンブレラ内のデポジット付近に渦電流探傷検査において40%の減肉指示が1箇所みられた。この減肉部は、その近傍のデポジットを取り除いた後の表面アラサ測定により、深さ0.40mm(約30%)の減肉であることが確認された。又、旧管のホットレッグ側下部アンブレラ内1箇所にも、渦電流探傷検査では減肉指示がなかったが、目視によりデポジットの近傍に減肉が発生していることが認められた。これらの減肉は、いずれも実機の場合と同様、局部的に発生しており、形状もよく類似していた。
(4)洗浄試験
1)試験条件
減肉再現試験において減肉及び付着物を発生させた試験体(アンブレラ8箇所、サンドイッチ2箇所)について、1次冷却水の温度を調節することによって、2次冷却水の温度を200~272℃、100~200℃、100~176℃、176~272℃と繰り返し変化させて残留リン酸ソーダの溶解性を高め、連続ブローダウンによって排出した。
なお、洗浄時間は15日間約350時間であった。
2)試験結果
ⅰ)リン酸ソーダの排出
2次冷却水のPO43-濃度は、当初480ppm程度であったが、12日後には0.5ppm以下に落ちついた。開放点検の結果、細管表面等に析出していたリン酸ソーダはほとんど除去され、わずかに難溶解性と考えられるリン酸塩(例えばリン酸鉄、リン酸ニッケルのようなリン酸の金属塩)が残っているのみであった。
この洗浄試験により排出されたリン酸塩の量は、新管下部アンブレラ部に析出していたものであって、その後の成分分析に使用した分(約5g)を含め、約24g(PO43-として)であった。なお、残留している分は難溶性の上記塩類と考えられた。
ⅱ)減肉進行の有無
析出したリン酸ソーダを除去するための洗浄試験に際しての細管減肉進行の有無を確認するため、洗浄試験終了後、渦電流探傷検査及び表面アラサ測定が行われた。その結果、新管のホットレグ側下部アンブレラ内の減肉は、渦電流探傷検査の結果、洗浄前と変化はなく、表面アラサ測定でも0.40mm(約30%)の深さであった。又、旧管のホットレグ側下部アンブレラ内の減肉は、洗浄後の表面アラサ測定で0.27mm(約19%)の深さであることが確認された。
その他のアンブレラ及びサンドイッチ部については、渦電流探傷検査では減肉の指示はなく、表面に肌荒れが認められる程度であった。
(5)減肉部の調査結果
洗浄試験後、新管ホットレグ側下部アンブレラ内の減肉部を切取り、詳細調査が行われた。なお他の減肉部は、継続試験のため残置された。
1)減肉部の状況
減肉部は底辺約10mm、高さ約10mmの逆三角形状であり、又、深さ方向については、2つの深い窪みがあり、その深さはそれぞれ0.39、0.38mmであると測定された。又粒界腐食、応力腐食割れはみられず、実機と同様局部的減肉であった。
なお、本試験装置の場合、細管は鉛直であるが、アンブレラの形状は360°全周について対称であることから、Dry&Wetは細管表面全周において発生しうる条件にあったにもかかわらず、減肉の発生が局部的であり、全周にわたり一様には発生していなかったことは、実際の減肉発生の状況を示唆するものと解される。
2)材質調査の結果
金属組織はインコネル600として正常であり硬度も変化がなかった。
3)付着物の組成
減肉部近傍を含む細管表面に付着している黒褐色のものには、X線マイクロ分析の結果、ニッケル、鉄、クロム、リン及びカルシウムが認められた。又、X線回折により健全部において黒色を呈しているものには、これらの成分の他に、給水系統から持ち込まれたと考えられるマグネタイト(Fe3O4)、及び管材成分からと考えられる水酸化ニッケル(Ni(OH)2)、スピネル化合物(NiFe2O4・NiCr2O4)が確認された。
(6)ボラタイル処理試験
洗浄試験の後、詳細調査のため切取った新管ホットレグ側アンブレラ減肉部を新管で復旧してボラタイル処理試験が実施された。
1)試験条件
25~50%、75~100%の伝熱面熱負荷変化をそれぞれ2サイクル繰返した後、100%伝熱面熱負荷、2次冷却水のpHを9.0±0.3に調節して、計220時間の試験が行われた。
なお、試験中の2次冷却水のPO43-濃度は極めて低く、0.02ppm以下であった。
2)開放点検の結果
アンブレラ及びサンドイッチ部については細管表面にわずか残留していた難溶解性と考えられるものもほとんどなくなっており、又、他の部分は試験前と変化はなかった。減肉再現試験で認められた旧管のホットレグ側下部アンブレラ内の減肉は、表面アラサ測定で洗浄試験前と同じく0.27mm(約19%)の深さであり、減肉の進行はなかった。又、他の部分についても渦電流探傷検査及び目視によっても減肉は認められなかった。
第Ⅲ章 原因の推定
1 試験及び検査結果の要点
第2章で述べたとおり、これまでに実施された試験及び検査から次のようなことが明らかにされた。
ⅰ)上部支持板にはさまれた部分の細管表面ではDry&Wetが発生することがある。
ⅱ)細管表面にDry&Wetが発生する部分で、リン酸ソーダが濃縮し、このため局部的に腐食が起ることがある。
ⅲ)細管表面にDry&Wetが発生しない部分では、リン酸ソーダがあっても腐食は起っていない。
ⅳ)細管表面にDry&Wetが発生しても、ボラタイル処理では腐食は起っていない。
2 熱流動と構造上の要因(Dry&Wetの発生)
蒸気発生器の伝熱部分の上部においては、2次冷却水は蒸気の割合が大きい2相流となっており、特に細管が上部支持板にはさまれた部分においては、構造的に2次冷却水の流れが妨げられ、その部分の細管表面では支持板にはさまれていない部分よりも沸騰による気泡の離脱が困難となり、水の供給が不足することとなる。このため、細管の水平あるいは曲管部分の下側において間けつ的に過熱域(蒸気が過熱されている領域)が生じ易い。
3 リン酸ソーダの濃縮と析出
リン酸ソーダの濃縮と析出については、次のように考察される。
ⅰ)細管表面が2相流の2次冷却水により濡れている伝熱状態にあっては、蒸気発生器の細管は内側が熱を与える1次側、外側が熱を受けとる2次側となっているため、細管表面の温度は飽和状態で2相流となっている2次冷却水の温度よりも高くなっている。このため、細管表面に接する境界層の水の温度は飽和温度よりも高くなっている。このような状態で2次冷却水に塩類が存在すると、細管表面においては水の蒸発量に対し新しい水の供給が十分でない場合は塩類は濃縮され、溶解度を超えると析出に至る。従って、蒸気発生器内の2次冷却水の水質管理にリン酸ソーダが使われている場合、このリン酸ソーダが析出することとなる。
ⅱ)細管表面がDry&Wetを間けつ的に繰返している状態にあっては、或る小さな領域の細管表面がDry状態になるとその領域の細管表面温度は上昇し、このDry領域の温度上昇の影響をうけて、その近傍の領域(以下「影響領域」という。)においても細管表面温度は上昇する。
このため、2次冷却水に塩類が存在し、その溶液が濃縮されて飽和溶液になった場合の沸騰温度が影響領域の細管表面温度より高い場合にあっては、溶液が濃縮されるに止まり、塩類が析出するには至らない。しかし、その飽和溶液の沸騰温度が影響領域の細管表面温度より低い場合にあっては、溶液の濃縮が行われるだけでなく、表面において沸騰が起り、塩類の析出に至ることとなる(このような析出はハイドアウト現象といわれる。)
リン酸ソーダ溶液の場合は、このハイドアウト現象による析出が起り易く、クレビス濃縮試験、減肉再現試験においてもリン酸ソーダの顕著な析出が見られている。これによりこの析出の前提として濃縮が生じていることは明らかであると推定された。細管表面に一旦析出したリン酸ソーダは 細管表面がDry状態が終ってWet状態になると、細管表面温度が低下するため水へ再溶解することとなる。
従って、細管表面に間けつ的なDry&Wetが発生すると、リン酸ソーダは析出と再溶解の過程を繰り返すため、その部分はリン酸ソーダの濃厚な溶液が反覆接触することとなる。
4 濃縮による腐食
蒸気発生器内におけるインコネル600製細管の表面は、通常不動態化皮膜である酸化ニッケルの薄い膜で覆われており、しかも、この膜が破れても自己再生するので、インコネル600は十分な耐食性をもっている。又、運転中に給水から蒸気発生器内2次系に持ち込まれた鉄もマグネタイト(Fe3O4)となって細管表面にも付着し、保護皮膜となっている。しかし、これら防食の役割をしている皮膜でも、濃厚なリン酸ソーダ溶液が反覆接触すると、化学的に反応して破られるため、このような局部においては、管材そのものが直接リン酸ソーダ溶液に曝されることとなり、ニッケル等の管材成分がリン酸-金属塩となって細管表面から持ち去られる腐食現象によって減肉に至るものと推定される。
5 減肉原因の推定
以上のような試験及び検査の結果から、減肉は、①上部支持板にはさまれた部分の細管表面においては沸騰により生じた気泡の離脱が妨げられ局部的にDry&Wet(第1章、1(2)熱流動試験参照)が発生することがあり、②この部分において、水質管理のため蒸気発生器内2次冷却水に注入されたリン酸ソーダの濃縮が生じ、この濃厚なリン酸ソーダ溶液が細管表面に反覆接触するため、まず細管表面に形成されている保護皮膜を局部的に溶解し、更に管材と直接反応してニッケル等管材成分とのリン酸-金属塩となる腐食現象により生じたものと推定された。なお、これまでの減肉発生の場所とその度合の相異はDry&Wetの発生状況(温度、周期等)とそれに伴うリン酸ソーダの濃縮状況及び細管表面の不動態化あるいはマグネタイト付着の局部的な状況に依存するためと考えられる。
参考1 美浜発電所1号機蒸気発生器細管減内に関する経緯
(1)第1回細管漏洩発生まで
美浜1号機は、昭和45年7月29日に原子炉初臨界、同年8月5日に初併入し、同年11月28日に営業運転が開始された。
昭和46年11月の第1回定期検査時における管板直上部に関する渦電流探傷検査では、細管に異常は認められなかった。
(2)第1回細管漏洩発生
昭和47年6月13日に細管漏洩が発生し、同月15日運転を停止した。水圧試験により、♯A蒸気発生器に漏洩細管1本が確認された。
全数8,852本について行った渦電流探傷検査に基づき:及び試験のために切り取った10本を含め、♯A蒸気発生器78本、♯B蒸気発生器32本、合計110本についてプラグを施工し、同年12月9日に蒸気発生器1次冷却材入口温度を305.4℃に制限して運転が再開された。
なお、減肉は、ホットレグ側上部支持板内の細管外表面に発生しおり、抜管調査の結果、局部的な減肉であることが確認された。
(3)第2回渦電流探傷検査
美浜1号機は、昭和48年3月15日から第2回定期検査に入り、プラグを施工していない細管8,744本について、渦電流探傷検査が実施された結果、♯A蒸気発生器502本、♯B蒸気発生器543本、合計1,045本に局部的減肉の指示が認められた。減肉の発生箇所は、ホットレグ側上部支持坂内及び中央支持板内の細管外表面であった。
このため、健全細管を含め、領域的に♯A蒸気発生器922本、♯B蒸気発生器977本、合計1,899本についてプラグを施工し、同年8月19日に1次冷却材入口温度を302.5℃に制限して運転が再開された。
(4)第3回渦電流探傷検査
昭和49年2月12日からは第3回定期検査に入り、プラグを施工していない細管6,834本について、渦電流探傷検査が実施され、♯A蒸気発生器3本、♯B蒸気発生器1本、合計4本に減肉指示が認められた。この4本についてプラグを施工し、同年6月4日に前回と同じ使用条件で運転が再開された。
(5)第2回細管漏洩発生
昭和49年7月17日に、2回目の細管漏洩が発生し、同日運転を停止した。水圧試験によって♯A蒸気発生器から漏洩細管2本が確認された。
プラグを施工していない細管全数6,839本について、渦電流探傷検査が実施された結果、漏洩細管を含み、♯A蒸気発生器134本、♯B蒸気発生器24本合計158本に局部的な減肉の指示が認められた。発生位置は、すべて中央支持板内の細管外表面であった。
更に、減肉の詳細を究明するため、詳細な渦電流探傷検査、放射線検査、ファイバースコープ検査、スケール分析及び抜管検査が実施された結果、前回と同様、細管の斜下表面における局部的な減肉であることが確認され、粒界割れ、応力腐食割れ、材質変化等は認められなかった。
美浜1号機蒸気発生器細管プラグ施工経緯
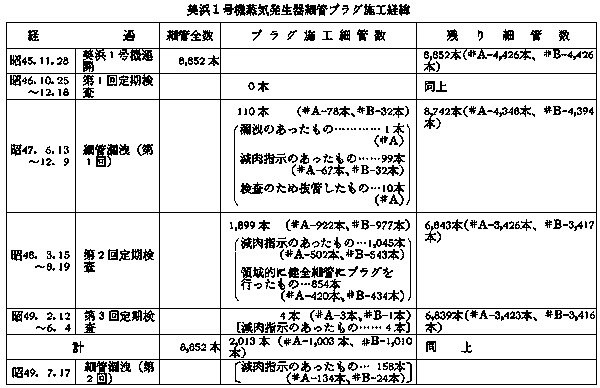
参考2 美浜発電所1号機蒸気発生器の主な設計仕様
| 種類 |
たて置U字管式熱交換器 |
| 最高使用圧力 |
|
| 1次側 |
約175kg/cm2G |
| 2次側 |
約76.3kg/cm2G |
| 最高使用温度 |
|
| 1次側 |
約343℃ |
| 2次側 |
約294℃ |
| 容量(蒸発量) |
約1,014×106kg/t/台 |
| 伝熱管 |
|
| 材料 |
ASTM B163(インコネル600) |
| 外径 |
19.05mm |
| 肉厚 |
1.42mm |
| 本数 |
4,426本/台 |
| 主要寸法 |
|
| 全高 |
14,567mm |
| 上部胴外径 |
3,854mm |
| 下部胴外径 |
3,023mm |
| 運転時圧力 |
|
| 1次側 |
157kg/cm2G |
| 2次側 |
55.6kg/cm2G |
| 運転時温度 |
|
| 1次側入口 |
310.8℃ |
| 出口 |
284.1℃ |
| 2次側 |
270.4℃ |
| 運転時流量 |
|
| 1次冷却水 |
17,695m3/h |
| 2次冷却水 |
約960t/h |
| 個数 |
2台 |
参考3 美浜発電所1号機蒸気発生器(CE型)断面図
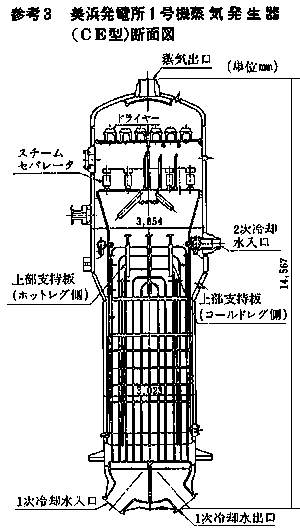
参考4 美浜発電所1号機蒸気発生器
上部支持板部概念図及び減肉状況図 |
参考5 熱流動試験装置概念図 |
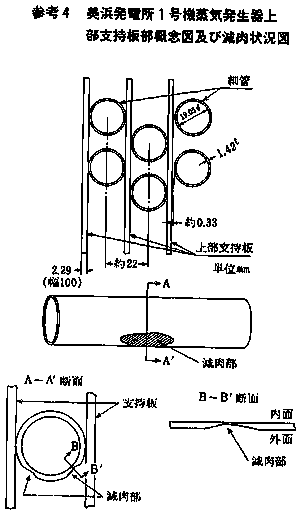
|
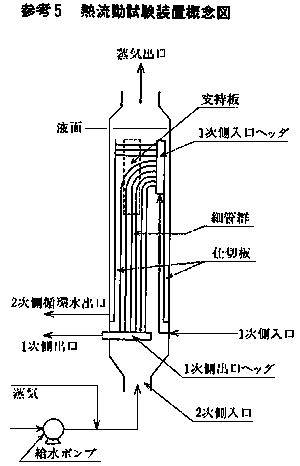
|
| 参考6 クレビス濃縮試験装置概念図 |
参考7 減肉再現試験装置概念図 |
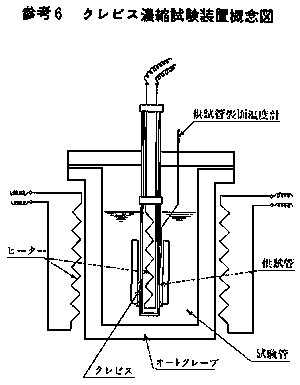
|
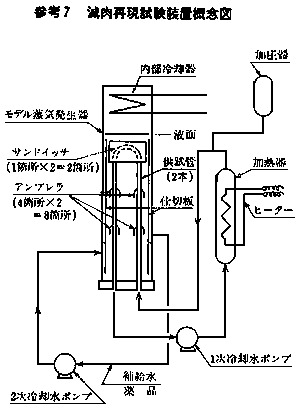
|
参考8 各種試験条件及び結果の概要
(その1)
|