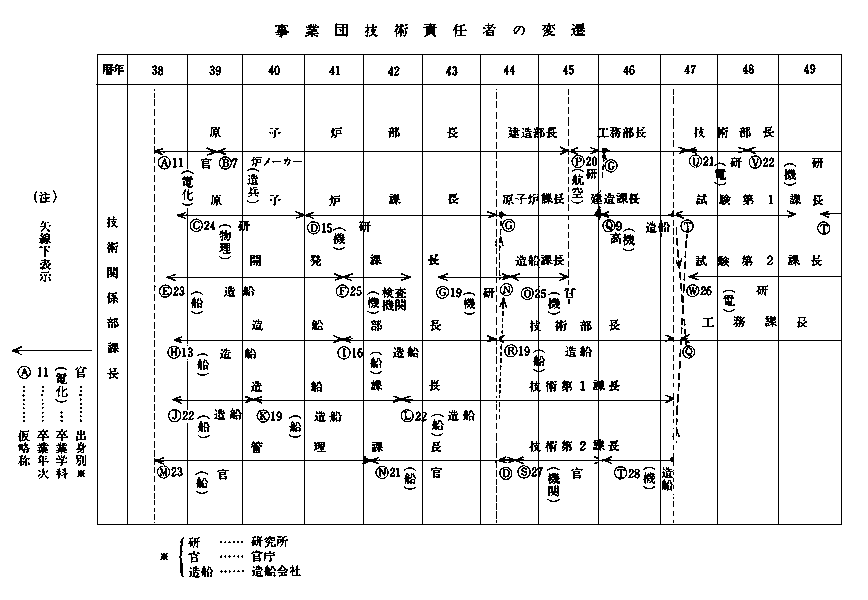昭和50年5月「むつ」
放射線濡れ問題調査委員会 |
「むつ」放射線漏れ問題調査委員会
|
|
委員長 |
|
大山 義年 |
|
委 員 |
|
安 成弘 |
|
|
〃 |
恒花 秀武 |
|
|
〃 |
柴田 俊一 |
|
|
〃 |
杉本 正雄 |
|
|
〃 |
堤 佳辰 |
|
|
〃 |
寺澤 一雄 |
|
|
〃 |
福山 雅美 |
|
|
〃 |
吉識 雅夫 |
|
|
〃 |
吉澤 康雄 |
|
専門委員 |
|
岸本 康 |
|
|
〃 |
藤田 譲 |
|
|
〃 |
古橋 晃 |
|
|
|
(50音順) |
|
本報告書においては、次のとおり略称する。 |
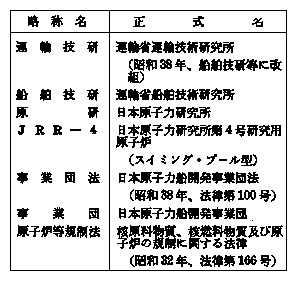 |
1. 調査の目的および経緯
さる昭和49年9月1日発生した原子力船「むつ」の放射線漏れの原因を調査するため、総理府において、臨時に、「むつ」放射線漏れ問題調査委員会を開催することが、昭和49年10月29日閣議決定され、10名の委員が委嘱された。
委員会の第1回会合は、同年11月22日開催されたが、この会合において、大山義年委員を委員長に選任するとともに、昭和50年1月13日には、専門的事項を調査するため、さらに3名の専門委員が委嘱された。
本委員会は、委員会13回を開催して、この問題を討検したほか、青森県むつ市における現地調査などを行って、この調査を進めた。
調査に当っては、原子力船「むつ」開発の計画段階から現在までの経緯について、広く関係者から事情を聴取するとともに提出された資料に対し専門的な検討を加えた。また、原子力船「むつ」の放射線漏れ発生後の船上調査およびその整理解析に当った専門家グループからも、その見解などについて説明聴取を行った。
上記のほか、本報告書の起草のため、昭和50年2月以降、起草小委員会5回を開催した。
この調査について、協力を受けた多くの方々に、この場を借りてお礼申し上げる。 |
2. 調査結果の概要
(1) 原子力船「むつ」放射線漏れの経緯
わが国における原子力船開発研究は、昭和32年、運輸技研において舶用炉について各種の基礎研究が行われたのが、実質的な始まりである。
これより先、民間においては、船舶関係各社による原子力船調査会が昭和30年から舶用炉や船型の検討を行ってきた。この調査会は、後に(社)日本原子力船研究協会に改組され、種々の調査研究活動を行ってきた。
このような流れと各方面からの強い要請にこたえ、昭和34年、原子力委員会は、まず、原子力船の遮蔽研究を主目的とする原子炉JRR-4を原研に設けることとした。JRR-4は、昭和40年完成以来、原子力船の遮蔽研究のため、かなり長時間にわたり活用された。
原子力委員会は、昭和36年4月、原子力第一船の建造についての基本方針を審議するため、下部機構として、原子力船専門部会を設けた。同専門部会は、諮問にこたえ、実験船を開発する主体としては特殊法人が適当であるなどの内容を含む計画案を答申した。これに基づいて昭和37年7月、原子力委員会は、原子力第一船の建造を決定した。昭和38年6月、「日本原子力船開発事業団法」が制定され、同年8月、「日本原子力船開発事業団」が設立された。
この事業団法は、当初昭和38年から昭和46年度末までの時限立法で制定されたが、その後事業の遅延に応じ、昭和50年度末まで延長された。
さて、政府は、原子力委員会の意見に従い、昭和38年10月、原子力船開発基本計画を決定した。それによると、第一船は、若干の積載能力と耐氷構造をもつ海洋観測船で、建造期間7年、実験航海2年、地上施設などを含む総経費60億円となっていた。
その後、実際の第一船の具体的計画が確定し、建造請負について入札が行われたが、船価予定額に対して、造船各社は余りに低過ぎるとして歩み寄りを見せず不調に終わった。そこでやむなく、建造着手時期を含めて大幅な計画変更が行われることとなったが、その際、船種も再検討され、特殊貸物の輸送船に変更された。
業界団体のあっせんもあって、ようやく、三菱原子力工業(株)と石川島播磨重工業(株)が建造を請負うこととなったが、船全体を一本化した建造契約は成立せず、原子炉と船体は、分割された別個の契約のもとに建造されることとなった。
このようにして船体は、昭和44年6月、東京湾で進水し、通常のぎ(艤)装を終えた後、直ちに、原子力船の定係港として昭和42年11月に決定していたむつ湾大湊港に回航され、原子炉関係のぎ(艤)装が行われることになった。
原子炉の据付けを含むぎ(艤)装工事は昭和47年7月完成し、いよいよ舶用炉試運転の段階を迎えたが、ここで予期しない事態がもち上がったのである。
おりから、定係港周辺の社会情勢は次第に変化していたが、事業団側がこれを十分察知できず、たえず地元と意思疎通を図るという努力に欠けるところもあったため、試運転計画の発表にあたって、予期しない地元住民の反対にあい、低出力で原子炉を運転して行うこととしていた係留試験および湾内試運転の実施は、不可能な状態となったのである。政府、事業団では、その後、地元関係者と折衝を重ねた結果、洋上で原子炉の試運転を行うことについて、ようやく了解に達したと判断されるに至った。そこで、出港を昭和49年8月25日と決定した。一部地元住民による反対があったものの、出港することができた。放射線漏れはこのような情勢下に起こったのである。それまで一応了承の立場をとっていた住民も、これを機にかなり反対にまわり、ついに運転停止のみならず定係港移転と設備の撤去までも約束せざるを得ない事態に至ったのである。
(2)「むつ」放射線漏れの原因
この放射線漏れの事情について正確な判断をするためには、本来ならば、本委員会は独自で改めて漏れ自体の観測、測定をし直すことが必要と考えられるが、上述のような事情から、原子力船「むつ」は現在運転しないという約束の下に係留されているので、到底そのことは不可能であった。しかし、すでに「むつ放射線しゃへい」技術検討委員会(「むつ」の放射線漏れについて、技術的調査を行うため科学技術庁と運輸省が合同で設置した委員会)において、運転できた範囲での測定をもとにかなり詳しい検討が行われていたので、本委員会はその説明を聞いて判断することとした。
その結果、今回の放射線漏れは、主として高速中性子が遮蔽体の間げき(隙)を伝わって漏れ出るいわゆるストリーミングと称する現象に起因するものであることが判明した。※(注)また、それは、局部的には予測した線量率をはるかに上回っていたが、全般的にみて、新しい形状、材料の遮蔽の場合には、時として起こり得る程度のものと考えられることがわかった。
原子力第一船の設計当時、わが国には、遮蔽設計の実例が少なく、経験の重要なこの分野における本来の遮蔽設計専門家がほとんど育っていなかった。
そのため、設計に当って、計算に乗り難い複雑な形状をした避蔽材の遮蔽能力についての判断力が足りなかったことが今回の問題の大きな原因になったと考えられる。近年、電子計算機の容量が著しく増大し、2、3年前には非常に進んだ遮蔽計算法が開発されたが、仮に、当初設計の時期において、この程度に計算法が進歩していたならば、このストリーミングを予測し、それを防ぎ得たかも知れない。
この場合も、これらの計算の不備などを補うため一般に行われているモックアップ(模擬試験体)による遮蔽実験が計画、実行された。この実験は、JRR-4を用いて行われたが、そのときすでに問題のストリーミングを予測し得る明らかな現象が観測されている。また、米国ウェスチングハウス社による設計のチェックアンドレビューの結果もストリーミングの可能性を指摘し、一つの対策を勧告している。
しかし、計画、設計、建造ならびに審査、検査の各段階の担当者らは、いずれもこれら一連の技術的問題が従来経験された以上に複雑で、未知の部分が多かったことに加え、相互の連絡も十分でなかったため、事態を正確には握し、適切な判断を施して、設計、建造に反映させるということができなかった。
また、追加研究を行ったり、外国の原子力船についての技術情報をとり入れるということも十分にはなされなかった。
かくて、最初の出力試験において、問題の放射線漏れが起こったのである。
ここで、もう一つの事実を指摘しなければならない。新型炉の場合あるいは新たな遮蔽が完成した場合、最初の出力運転では設計、施工のいずれに不備があっても局部的な漏れが起こり得ることを予想し、漏洩線量を監視するため各部に適当な人員配置をするのが普通である。「むつ」の場合もこのような配慮がなされていたならば、警報発生の数時間前に行われた試験運転ですでにかすかに起こりかけていた放射線漏洩を計器上または記録紙上で発見し得たはずであり、直ちに適切な措置がとられたと考えられる。
今回の問題は、たまたま表面に現れた一つの技術的問題とみることもできる。しかし、本委員会は、これをそのような単なる偶発的な事象とみるよりも、むしろ、そこに内在する本質的な諸問題を検討する一つの契機と考えた。すなわち、本調査委員会は、この問題について発生の原因を単に技術面に限らず、広範囲な見地から調査、追究した。それは、国の政策面、事業団の組織・運用面、研究開発面、契約面など可能な限り多面的に行われた。さらに、技術面では、当然遮蔽に主眼をおきつつも、それのみに限ることなく、なるべく全般的に注意を払うという姿勢をとった。
今回の調査により、この問題には多くの要因のあることがわかった。これらの要因はそれぞれ相互に絡み合い、いずれを主とし、いずれを従とするか容易に判断し難い。しかし、それぞれこの問題についての責任があるものと考えられる。
しかしながら、原子力船「むつ」自体は、そのような誤りはあったにせよ、全体としてかなりの水準に達しており、適当な改善改修によって、十分所期の技術開発の目的に適合しうるという判断に達した。
そこで本委員会は、過去の責任は単に指摘するにとどめ、むしろ今後の進め方についての提言を行うこととした。
(3)今後の進め方についての提言
今後、「むつ」の研究開発計画を進めるとした場合、次のような考慮や施策が適当と考える。
① 事業団の組織を、単なる事務処理機関的性格のものから、一層技術的な能力をもったものに改めること。
② 政府の計画は、安全性の確保を含めて十分な技術的裏付けのもとに慎重に行われるべきこと。
③ 今回のように新しい不確定な要素を多分に含む新型式炉に対しては、現在の設計、施工、監督、規制等の体制には問題がある。新しい研究成果を消化するとともに、経験に裏付けられた高い技術的能力をもつ強力な技術組織の確立が望まれる。
また、この技術組織は、その原子炉の運転開始後は運転に伴って生まれる技術的経験をさらに集積、解析し、以後の自主技術確立のために機能するよう国としても配慮することが望ましい。
④ 以上の体制整備に当っては、それぞれの役割の限界と責任の所在を明確にするよう配慮すること。
⑤ 念のため、「むつ」の原子炉部分について全面的に技術的再検討を行い、必要な改善・改修をすること。
⑥ 今後、地元の住民に、責任をもって積極的に接触、交渉し、正確な情報を伝え、理解を深めるよう努力をすること。
(4)付記
本委員会は、以上述べた諸提言が実質的に行われ、原子力第一船「むつ」の研究開発がひき続いて推進されることを期待する。
なぜなら、資源問題において次第に危機にひんしつつあるわが国の国民が、エネルギー政策に関して、その針路を判断するときの重要な一つの根拠として、この研究開発の結果が必要であり、また、この種の技術開発は、長い年月を必要とし、いったん中止した後は、簡単に再出発できるものでないからである。
※(注)
ここで問題となったストリーミングは、原子炉圧力容器と一次遮蔽体の間げき(隙)を伝わって、上方向に漏れたものが主であり、こうして漏れ出た中性子が二次遮蔽体等の構造物によって吸収され、二次的にガンマ線を発し、これが、上甲板上に設置されたエリアモニターに検出されて警報が鳴ったものである。 |
3. 問題点の整理
本委員会は、「むつ」放射線漏れ問題の調査検討を、単に技術的問題にとどまらず、幅広い立場から行ってきた。その結果、大別して(1)政策、(2)組織、(3)技術、(4)契約の4点について、それぞれに問題点があるとの結論に達したので、以下にそれを指摘する。
(1) 政策上の問題点
(ア) 経緯
わが国の原子力船開発は、昭和32年運輸技術で原子炉の船舶推進への適応性についての研究が行われたのが始まりである。政府は、運輸技研に原子力船の研究開発促進の予算を計上し、舶用炉の適応性、特性、負荷応答性などの研究を行わせた。運輸技研は、そのほか、舶用炉に有効な遮蔽構造を確立するための研究を行うとともに、大型振動・動揺試験機を建設して原子炉機器の振動・動揺実験を行い、さらに遮蔽材の強度試験や効率のよい船型を選定するための模型船による実験などを進めた。
これに先だって、昭和30年未、民間船舶関係各社による原子力船調査会が設立され、舶用炉や船型の検討を行っていたが、昭和33年10月同調査会は、(社)日本原子力船研究協会に改組され、同協会は、同年12月、原子力委員会に対し、原子船開発の方針の明示、助成策の確立、舶用炉関係技術の早期導入などを要望した。
原子力委員会の原子力船専門部分は、約1年間審議した結果、昭和34年9月、①原子力船開発の対象となる船舶の選定基準を明確にし、②舶用炉は加圧水型軽水炉および沸騰水型軽水炉を選び、③早急に船種と舶用炉を選定して、詳細な設計研究への着手と研究体制の確立、研究開発方針の明確化などについて原子力委員会に報告した。
当時、原子力委員会、船舶業界、運輸省の一部には、原子力船の将来の実用化を現実の造船開発計画に組み込むのは時期尚早という意見もあった。(社)日本原子力産業会議は、このような情勢を踏まえて昭和34年10月、政府および海運、造船各界の代表21人からなる原子力船調査団を50日間にわたり、米、英、仏、ノルウェー、IAEA(国際原子力機関)などへ派遣した。同調査報告は、緊急に検討すべき問題として、①開発推進機構の確立、②研究開発計画の策定、③研究施設の強化、④米国の原子力船サバンナ号の受入れと安全基準の制定をあげている。原子力委員会は、これらの情勢から、昭和34年10月、遮蔽構造の実験研究を行い、わが国独自の原子力船体構造を探求するため、原研に、JRR-4を設置することを決めた。
原子力委員会は、昭和36年2月に決定した原子力開発利用長期計画において「原子力船はおそくとも昭和50年ごろまでにその経済性が在来船に匹敵し得ることが期待されるので、前期10年間においては後期の開発に備え、原子力船技術の確立、運航技術の習熟、技術者・乗組員の養成訓練等に資するため適当な仕様の原子力船を1隻建造し、運航する」とし、同年4月、すでに、いったん解散していた原子力船専門部会を再編成した。同専門部会での第一船についての審議は、船種船型、建造主体、資金調達などに関する具体的方針、建造前に解決すべき放射性廃棄物の処理、安全管理体制などを対象として行なわれた。これらの審議を経て同専門部会は、第一船の建造の基本的な考え方として、①早急に開発に着手すべきである。②日本の海運・造船界の現状からみて国またはこれに準ずる機関を中心とし、国家資金を根幹とし、これに民間産業界が積極的に協力する形をとるのが妥当である。③第一船は、資金効果、建造運航上の諸問題からみて排水量1万トン以下、主機出力2万馬力以下で、なるべく高速力のものが適当であるとまとめた。その後、さらに具体的な検討が行われ、第一船は、総トン数6,350トンの海洋観測船とし、とう(塔)載する原子炉は熱出力33~35MWの軽水炉、主機出力1万馬力、建造期間7年などと計画されるに至った。一方、開発のための組織の形態とその業務、資金の分担および出資形態と時期、燃料交換施設をはじめ付帯設備の設置に関する事項なども検討された。
以上要するに原子力委員会は、昭和31年3月に策定した原子力開発基本計画では原子力船には触れておらず、舶用炉開発のみに言及していたに過ぎなかったが、(社)日本原子力産業会議の原子力船調査団報告を境に初めて原子力船開発に明確な姿勢を示したことになる。
以上の経緯を経て、科学技術庁は、事業団設立のため初年度予算1億円を計上し、第43回国会(昭和37年~38年)に「日本原子力船開発事業団法案」を運輸省と共管で提出した。当時の国会は特殊法人の新設には否定的であったが、この事業団をめぐる国会審議では与野党とも原子力船建造に積極的であった。同法案は、衆参両院において、①建造には極力国産技術を使い、②安全確保に万全を期し、③事業団の人的構成は設立の趣旨に沿うようにする、などの付帯決議をつけて可決され、昭和38年6月公布され、同年8月事業団が設立された。
これにより、原子力第一船開発は、本格的に推進されることとなった。
昭和38年10月、事業団法の規定に基づき政府が原子力委員会の意見に従い策定した原子力第一船開発基本計画によれば、①第一船のみを官民共同出資で作る、②一貫した責任体制下で資金・人材・研究開発面において広く官民協力して開発を推進する、③第二船以降を民営とし、第一船も完成後民間に引渡すか、民営の運航会社を設立するかなどの運営方針その他については改めて検討するという方針であった。また、同計画によれば、第一船は、若干の積載能力と耐水構造を持つ海洋観測船とし、建造を完了し実験航海を終了するまでの期間は昭和38年~46年の9年間、建造費約36億円、地上施設などを含む所要総経費約60億円とされた。
同年12月、事業団が発表した長期業務計画書によると、第一船の基本設計の完了と建造契約が翌昭和39年10月、進水は昭和42年初め、引渡しが昭和44年3月、事業団の解散は昭和46年度末となっていた。
事業団は、まず、(社)日本原子力船研究協会の試設計による観測船兼補給船の資料をベースに学識経験者に協力を求めて設計条件を検討し、造船7社、原子炉メーカー5社に対し、設計計算を含む基本設計を委託した。昭和39年3月、第一船建造予算(国庫債務負担行為限度額36億円)が決定したので、事業団は、上記の検討を経て仕様書作成に着手し、建造契約の準備に入った。
その後、各社と折衝を続けたが、昭和40年3月に至ってもなお、大手造船7社からの応札は得られなかった。この入札不調を収拾するため、(社)日本造船工業会のあっせんで、事業団は、石川島播磨重工業(株)と三菱原子力工業(株)を随意契約の相手として、第一船の建造契約について折衝することとなったが、その結果、見積総額が予定船価を大幅に上回って約60億円となった。原子力委員会は、諸般の事情を勘案して建造着手を延期し、同年8月原子力船懇談会を設け、基本計画の実施上の問題点を検討することを求めた。同懇談会は、舶用炉の輸入の可否や資金問題などを米国パブコック・アンド・ウイルコックス社製のCNSG-J型原子炉を輸入する場合をも含めて検討したが、国産炉であっても第一船建造経費にほとんど差がないと判断した。昭和41年4月の同懇談会では、当初の計画通り国産炉をとう(塔)載する原子力船を建造すべきだとの意見が圧倒的であった。
そこで原子力委員会は、昭和41年7月14日、同懇談会の検討状況と各界の意見、海外の原子力船開発状況などを勘案して、既定方針に沿って国内技術による原子炉をとう(塔)載する第一船の建造を推進する方針を再確認したのである。
当初、原子力船建造費約36億円所要総経費約60億円であったものが、原子力船建造費約64億円、所要総経費124億円(昭和49年度末には約160億円)となったのは、船価見積りの修正、定係港施設費の増加などによるものである。国の負担が当初の予想をはるかに超えた額になると判断されたので、船種の再検討も行われ、昭和42年3月海洋観測船から特殊貨物の輸送船へと変更されることとなった。このようにして、さらに契約の折衝が続けられたが、事業団の希望する船全体を一本化した建造契約はついに成立せず、船体を石川島播磨重工業(株)、原子炉を三菱原子力工業(株)に分割して発注することとなった。
さて、原子炉の建造に際しては、まず原子炉等規制法により内閣総理大臣の設置許可を求めなければならないが、事業団は、「むつ」の原子炉設置許可申請を昭和42年4月に行っている。内閣総理大臣は、この申請について原子力委員会に諮問し、その意見を聞いて同年11月設置を許可した。
このあと、原子力船の場合、船舶安全法(昭和8年法律第11号)による規制が行われる。石川島播磨重工業(株)と三菱原子力工業(株)は、船舶安全法の規定にもとずき、昭和43年4月「むつ」の建造にかかる製造検査を運輸大臣に申請した。引続き必要な手続を経て、「むつ」は、同年11月起工、船体は昭和44年6月進水した。つづいて、事業団は、第一回定期検査を運輸大臣に申請した。この定期検査は、建造の途中から行われ、原子炉についてもその製造工程を含めて検査されることになっている。船全体としては、最終的に海上公試運転を含む効力試験を完了して初めて建造段階におけるすべての船舶検査を終了したことになり、ここで、船舶検査証書が交付されるので、「むつ」はその意味ではまだ船舶として完成したとは認められていないのである。
(イ) 問題点
以上のように事業団は、当初9年間の時限立法により、昭和38年設立されたのであるが、10年間に満たない寿命の事業団に基本設計から詳細設計、建造、運転に至る過程を一貫して担当する人材を固定させることは困難であったと思われる。
しかし、第二船以降の民間計画の目途がたっていれば、時限立法による弱点は克服できたかも知れない。重要と思われるのは、人材が事業団に集まらなかったこともさることながら、むしろ時限立法では、国家事業として推進してきた開発が技術的な完結に達しないまま挫折してしまう恐れが大きい点であろう。
原子力第一船の原子炉は、事業団発足以前から国産とするという考え方が主流であった。すなわち、わが国の発電炉は、まず英国コールダーホール改良型炉を導入し、その国産化を進めるという路線が最初にあり、間もなく米国の軽水炉の導入が可能になったので、産業界はコールダーホール改良型の国産化路線から軽水炉導入に大きく傾斜した。しかし、国には軽水炉国産化に乗り出す姿勢は乏しく、軽水炉は業界の導入に任せており、国が軽水炉に対し基礎研究の必要性を認識したのは比較的近年になってからであるといえる。 こうして、わが国の軽水炉研究は、その炉物理実験を原研のTCA(軽水臨界実験装置)で、技術は同じく原研のJPDR(沸騰水型動力試験炉)で、舶用炉は原子力第一船による船上試験で、舶用炉の遮蔽研究は原研のJRR-4でという構想で始まった。最初から、舶用炉については国産とする方針が打ち出された理由には、原研のJRR-3(天然ウラン重水型研究炉)が国産に成功したことと、舶用炉は商用発電炉に比較して小型で、技術的に容易であるとする先入観があったこと、および原子力船懇談会が米国の舶用炉を検討して国産化可能と判断したことなどがあげられる。しかし、原理的には可能であっても工学上の問題は残る。そこで、陸上に同型炉をペアで建造すべしとする意見や、実験炉あるいは原型炉を経て、開発を段階的に進める計画も示されたが、いずれも、結果的には見送られた。
事業団法によれば、事業団の業務範囲は、原子力船の設計、建造および運航を行い、この目的を達成するため、研究を含め必要な業務を行うこととなっている。しかし、現実には基礎的な研究や実験についてはその業務に含め得なかったきらいがある。
一方、原子力委員会が原子力第一船の開発基本計画を決定したのは昭和38年7月であり、翌8月には、事業団は基本設計にかかり、造船および原子炉メーカーの協力を得て遮蔽などの基本図面を作成し、昭和39年末に入札仕様書をまとめた。
事業団法の内容とこの経緯から考えると、事業団の設立以前に運輸技研などで、すでに第一船の基礎研究は終了しており、事業団は第一船を建造し、その実用化試験を担当するだけの機関という一般認識があったと感じられる。
事業団が専従の研究者や技術要員を十分に置くことに積極的でなかったのは、このためであろう。
現実には、遮蔽実験など一層詳細な基礎研究が不可欠の実情であった。だが、事業団は、上記経緯により、JRR-4による遮蔽効果確認実験に際しても、主体性をもちつつ必要な実験を進めるに十分な体制を作ることができなかった。
遮蔽実験は、事業団、原研、船舶技研の三者の共同研究で行われ、実験結果を原子力第一船に反映させる責任は、本来事業団にあったにもかかわらず、十分機能することはできなかった。このような経緯から、第一船の舶用炉の開発については、原子炉建設の請負業者としての三菱原子力工業(株)に大幅に依存する結果となった。こうして随意契約の運びとなったのであるが、この場合、事業団が細部の計画について、かなり業界に依存したという点に問題が残るであろう。
船種変更の問題についても、船価見積りの増加を収拾することにこだわらず、まず、関係各界の十分な理解を得る努力をすべきであった。一般的に言えば、行政府は予算獲得技術に、企業は利潤追求にそれぞれ重点をおきがちとされている。仮に価格高騰のこの段階で、科学技術振興とは縁遠いこのような異なった価値体系によって、問題が優先的に審議されたとすれば、開発にとって核心となるべき技術開発を中心に据えた総合的な体系としての原子力船開発の審議は、不十分のまま終わったと思われる。確たる原子力船開発政策を樹立するよりも建造費の高騰に目を奪われたとあれば、そのこと自体に大きな問題がある。要するに、外国の情報の表面的な解釈と技術以外の要因によって船種船型の変更という重要な決定が行われたとみられ、このような指導の態度が回り回って技術開発の目標をばく然とさせる結果を招いたことは否定できないであろう。
次に、安全性確保のための規制問題について述べる。
公共に対する原子炉の安全確保のために、原子炉等規制法によって規制が行われている。このほか、発電用原子炉については電気事業法(昭和39年法律第170号)により、舶用炉については船舶安全法によって別個の安全確保の体系がつけ加えられる。原子炉等規制法および船舶安全法(または電気事業法)の双方による二重の規制を排するためとして、原子炉等規制法では、一部規定(第27条(設計及び工事方法の認可)、第28条(使用前検査)、第29条(定期検査))については、その適用が除外されている。
原子炉の設置許可は、原子力委員会の意見を尊重して、内閣総理大臣が行う。内閣総理大臣に対し、設置者から設置許可申請が出されると、その内容の是非について、内閣総理大臣は原子力委員会に対し諮問する。原子力委員会は、設置許可申請に対する原子力委員会の意見をきめるに際し、安全性に関する部分については、内部機構として設けられた原子炉安全専門審査会に調査審議を行わせる。同審査会は、原子炉などの基本設計について審査を行うが、詳しい設計・工事の方法の内容にまでは立ち入ることはない。
当面問題となっている原子力第一船の遮蔽について、原子炉安全専門審査会で審査を担当したのは、環境専門の委員を主体とするグループであった。同グループには放射線防護についての専門家は含まれたが、遮蔽設計の専門家と評価された人はいなかった点を指摘しなければならない。原子炉安全専門審査会の委員は非常勤と定められており、一般に大学、研究所の研究者がパートタイマーという形態で審査に当っているので、必ずしも常に最も適当な専門家を当て得るとは限らない。したがって、審査の実態についても、申請された原子炉の安全性について、申請者例の計算を再計算によって確認することなどは事実上困難であり、また、原則として書面審査のみであるため、設置許可を決めた原子炉がその後どのように運転されているか、また、技術的に問題はないかなどを絶えず注意し、これを次の審査に反映させるという一貫した技術のシステムに欠けるところがある。いうならば、高名で多忙な学者、研究者にこのような実務的な作業を委ねること自体に無理があると言わざるを得ない。この結果、審議内容は往々にして、結果に対する責任と役割の限界をあいまいにしたまま、無難な結論が採用される恐れがある。そこで、この審査と現実的な設計との間には、工学的・技術的空げき(隙)の存在する可能性が考えられる。
原子力委員会から内閣総理大臣に答申が出されると、この答申を受けて、行政機関は行政機関としての判断を行い、内閣総理大臣の名で設置が許可される。
さて、舶用原子炉の場合、原子炉等規制法により内閣総理大臣からの設置許可があった後は、船舶安全法によって規制され、運輸省によって各種の検査が行われる。内閣総理大臣は、その後、舶用炉を運転する際、運転者が遵守すべき保安規定について審査する。
船舶安全法による規制には、製造検査と定期検査があり、在来船の場合、数十年にわたる技術的経験に基づく詳細な検査方法が確立されている。
原子力船については、当面の問題である遮蔽を含め在来船のように詳細な技術が確立されているわけでなく、検査法自体も長年の経験で練られてきたものではない。事実、原子力船の特殊性を考慮して付加的に適用される「原子力船特殊規則」も、原子炉を含めた原子力船の安全確保のための基本的な性能を規定するにとどまっており、その詳細な技術基準は個々の検査の段階で定めているのが現状である。もちろんこれらは、実際の原子力船の検査経験も豊富となれば、将来は一般規則として次第に整備されるべきものと考えるが、現実に、このような新型式炉の場合、いわゆる「安全審査」と現実の原子炉建造との間には、技術的にかなりの間げき(隙)が生じ得ることを特に注意する必要がある。
もっとも法体系や制度がいかに完備されたとしても、技術はしょせん人に付随するものであり、この点については、今回の「むつ」問題の関係者の厳しい反省と今後の努力が望まれる。
次に、情報交流の欠陥について述べる。地域住民との間で直接問題となった「石川書簡」が一つの例である。一般に舶用エンジンは岸壁に船体を係留した状態で低出力の船上試験を受ける。「むつ」においても、その舶用炉試験の主要部分を、この岸壁係留状態で行うことが予定されていた。しかし、事業団と地元の漁連などとの間で、「むつ」の安全性をめぐる対立が高まってきた際、この書簡が問題となり、事業団不信の空気が広まり、結局、岸壁係留試験の計画を放棄せざるを得なくなった。この書簡は、昭和42年、当時の事業団理事長と青森県知事との間で交されたいくつかの往複文書の一つであるが、昭和42年10月2日付の知事からの「定係港についての質問」中にある「停泊中の原子炉についての稼動状態」という項目に対し、昭和42年10月9日付の理事長の回答は「原子力船は定係港に停泊する場合、原子炉は停止しております。」となっているが、これが問題となったものである。もっとも、この書簡をはさむ一連の往復文書を点検すると、前後の関係から、この書簡は「むつ」が実用化した後で使用される定係港の意味で相互に文書が往復したとも判断され、出力試験そのものについて述べたとは理解し難い。一方、地元住民は停泊中の原子炉運転停止はおろか、原子炉運転によるむつ湾航行まで行わないという約束があったと主張している。このように、この書簡やそれぞれ各方面で行った説明がトラブルの材料になり得た一つの原因には、この書簡自体の記載上の説明不足もあるが、むしろ、原子力船に関連して事業団内部はむろん、外部関係者との間にも余りに情報交流が少なく、もしくは片寄った情報が多く、統一的な対応を敏速にとることができず、次第に住民の信頼を失う結果を招いたものと思われる。
原子力船開発を含めて、原子力が持つ内容は、国民にとって、あるいは他分野の専門家にとっても、一般常識を超えた高度かつ専門化した知識になっている。原子力の本質についての認識が国全般に統一されておらず、これが原子力第一船開発に対し、現在ではさまざまな形の力となって推進を妨げていることを否定できない。政府や事業団は、国民に信頼される総合的な施策を積極的に実行するためには、なによりも国民の理解と協力を求める努力をすることが先決である。
しかし、ここに至っては、地元住民や国民一般が原子力船開発に対しいだいている不信感は、事業団のみの努力によって解消することは到底期待できないであろう。各界からの積極的な協力が要望されるのである。
(2)組織上の問題点
(ア) 事業団の組織および構成員の変遷
前述の原子力第一船開発基本計画の変更、その他の理由により、事業団の組織は昭和49年末までに3回にわたり大きな変更が行われている。以下に主として技術関係の部課についての変遷を示す。 |
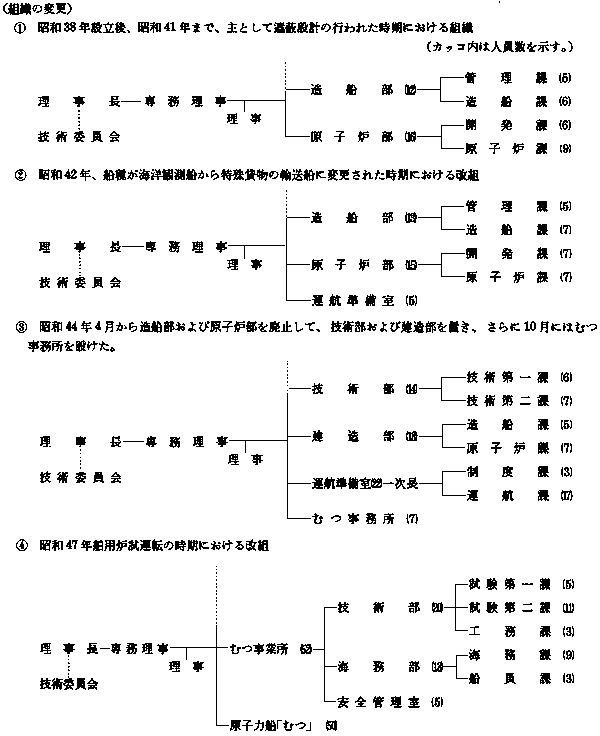 |
(構成員の変遷)
事業団の責任者および技術者についても、次のような交替が行われている。
① 昭和38年の事業団の設立から昭和49年末までに理事長および専務理事は、同時に一回交替が行われた。任期は昭和38年8月から昭和43年4月までと、昭和43年5月以降である。(昭和49年末現在)
② 技術担当理事の交替は以下の通りである。昭和38年8月から昭和39年11月までは原子力を専門とする理事が、昭和39年4月から昭和43年3月までは造船、昭和40年1月から昭和44年1月までは原子力、昭和43年5月から昭和47年5月まで造船、昭和47年5月から昭和49年末までは造船を専門とする理事が、それぞれ技術担当理事であった。
③ 昭和38年から昭和49年までの間、技術関係の責任者である原子炉部長、技術部長などは、官庁または民間からの出向者であり、次表に見られるとおり、2~3年で次々に交替が行われている。
(イ) 問題点
大規模な開発計画を遂行するためには、十分な組織と強力な指導者が必要であり、かつ、その組織の技術上の責任分担が明確であること、できれば技術上の主な責任者は開発の段階を通して変わらないことが、首尾一貫した開発の推進のためには望ましい。また、これに従い協力する技術者も、最終の段階まで責任をもち、問題が発生したときは、直ちに対応出来る体制であることが望まれる。
一般には、実験などを伴う開発や研究においては、前任者との細部にわたる完全な引き継ぎは難しい場合が多い。特に時間的制約のもとに開発が行われる場合には、不十分な検討により出されたものであっても、一度出された結論は必要以上に信用されやすく、あらためて再吟味することは、比較的行われ難いと思われる。このことからも前述のように責任者または担当技術者がしばしば交替したことは好ましいことではなかった。
また、事業団発足の時点において、それ以前に(社)日本原子力船研究協会などで行われた調査研究をそのまま引き継いで実施することが基調であったことは、昭和38年8月に発足して、昭和39年10月基本設計完了、建造契約、昭和42年初め進水、昭和44年3月引渡し、昭和46年解散という事業団の当初の性急な予定がそれを裏付けている。本来、事業団は責任をもって原子力船を開発するのであるから、基本から設計その他をあらためて独自に検討すべきであり、そのような方針であれば、開発の過程およびその後の経過の途中においても国内の原子力の専門家との情報交換も活発に行われ、また新しい計算コードによる遮蔽効果の再検討なども実施されたであろう。
事業団の原子力船開発に関する技術能力については、今回の資料および事情聴取からのみでは、必ずしも明らかではないが、設立の時からの事業団の体質として「原子力第一船遮蔽効果確認実験研究協力職員派遣に関する契約」からも、また、昭和40年に遮蔽実験計画の調査検討を、(社)日本造船研究協会に委託したことからも知られるように、自ら主体的に開発するのではなく、協力を得てまとめるという方向にあり、人事もそのような線で行われたことにも今回の問題の遠因を求めることができる。
一方、「組織は人なり」と言われているように、どのような組織でも人を得なければ有効には働かない。原子力船という大きな開発を、効果的に遂行するためには、前述のように使命感をもってことに当る指導者を持つことが必要であり、そのためには原子力第一船のみの開発でなく、それ以後の原子力船の取り扱い、実験・研究などを含めた長期プロジェクトが必要である。また実物実験などを実施できるだけの予算、設備を確保し、優秀な研究者の協力を得ることが可能な体制を作ることが必要である。
また、原子力船「むつ」の乗組員の編成については、各種のデータを収集するための試験航海を行うものであるから、原子炉主任技術者を含む特別に強化した原子炉要員の組織を編成し、保安上の責任体制を十分に確立するとともに、技術上の問題の処理や記録に万全を期することが必要である。
上述のような体制を作るためには、わが国の終身雇用制度が障害になっているにせよ、昭和49年末までの事業団は、原子力船開発プロジェクトの全体的な推進体制として、必ずしも十分であったということはできない。
事業団技術責任者の変遷
|
|