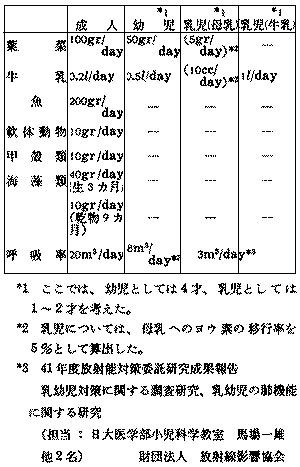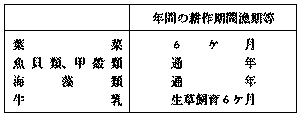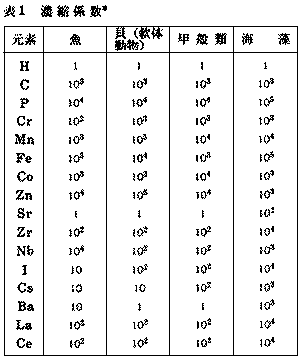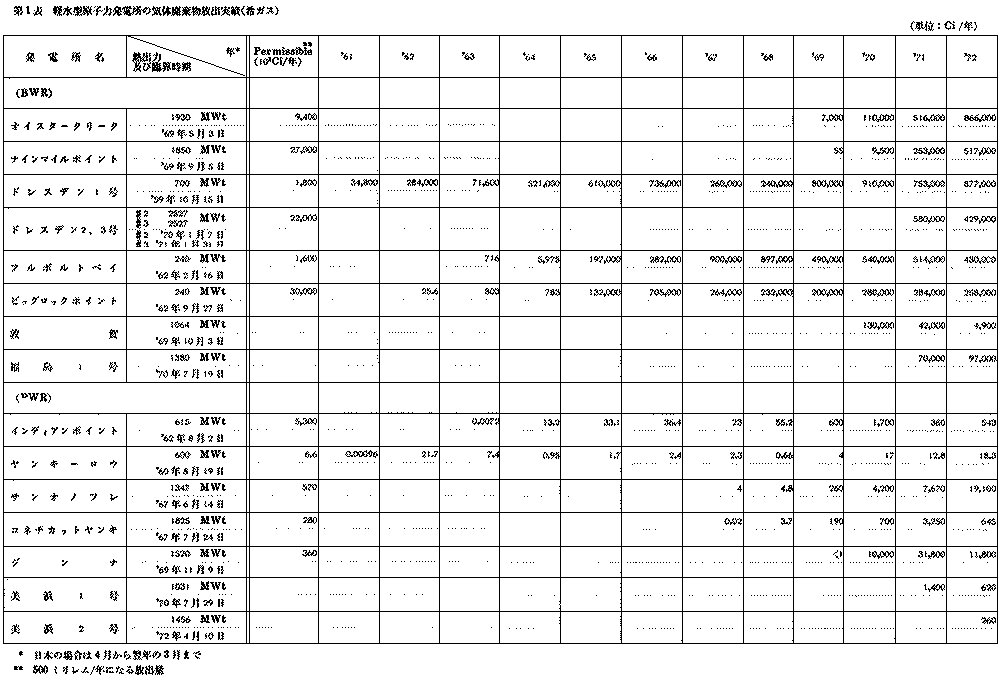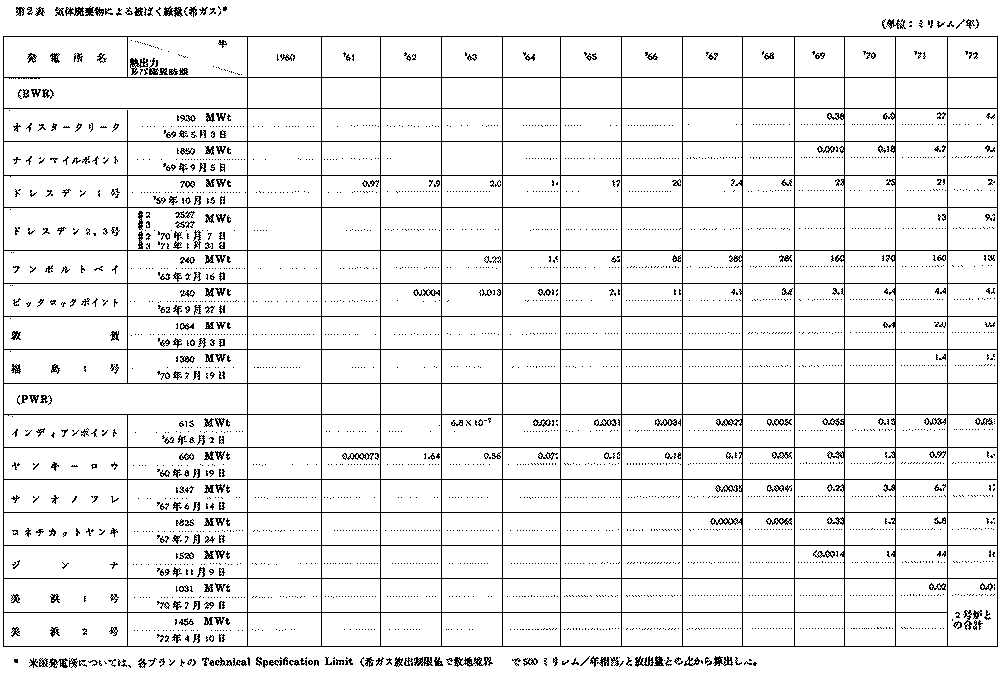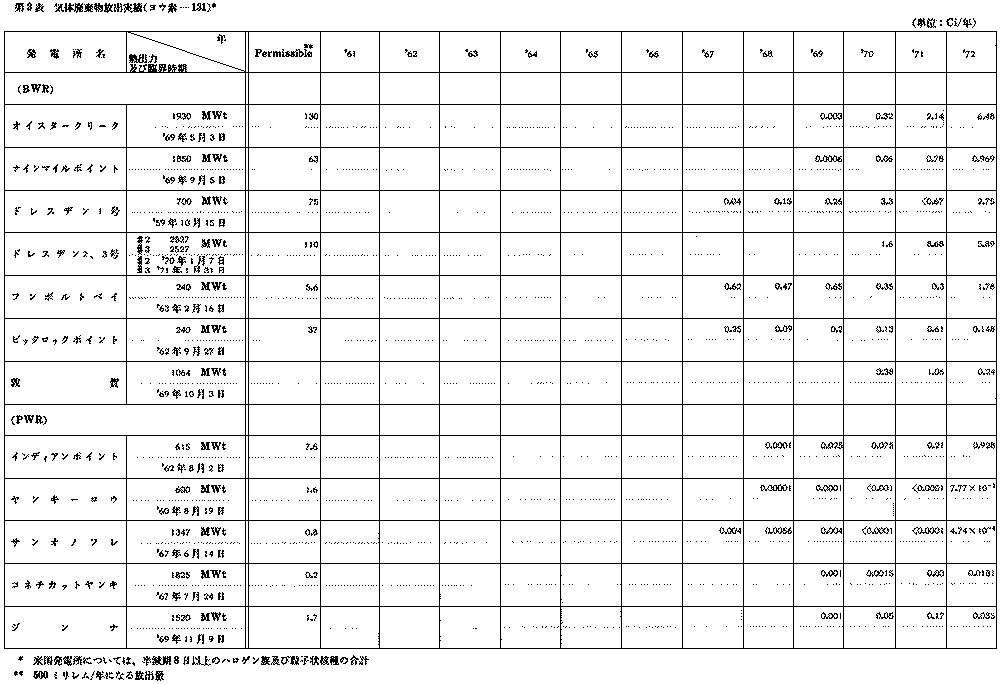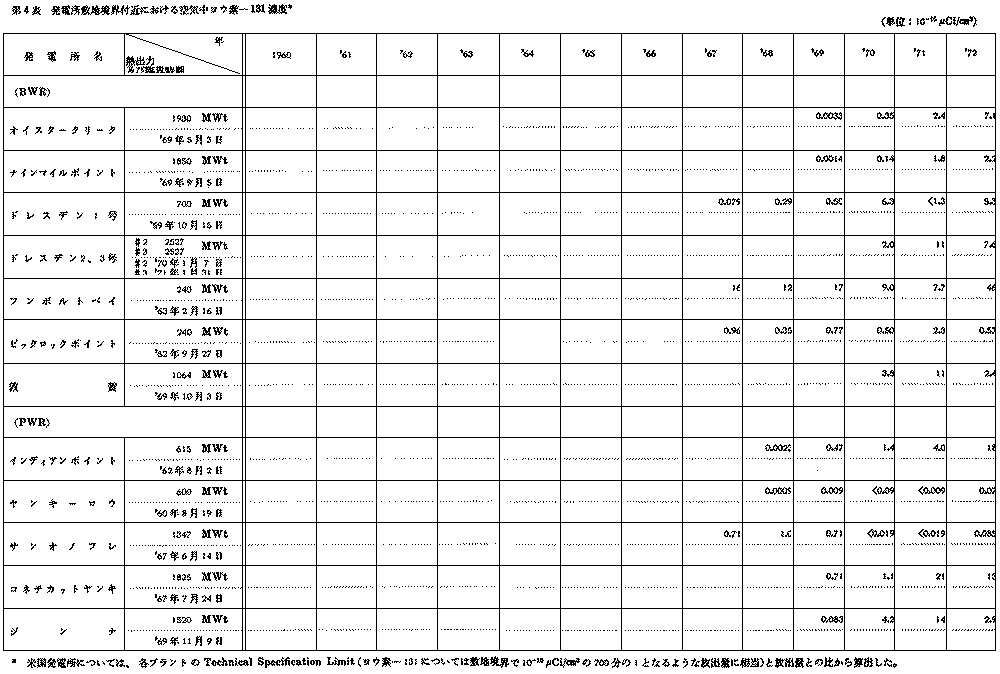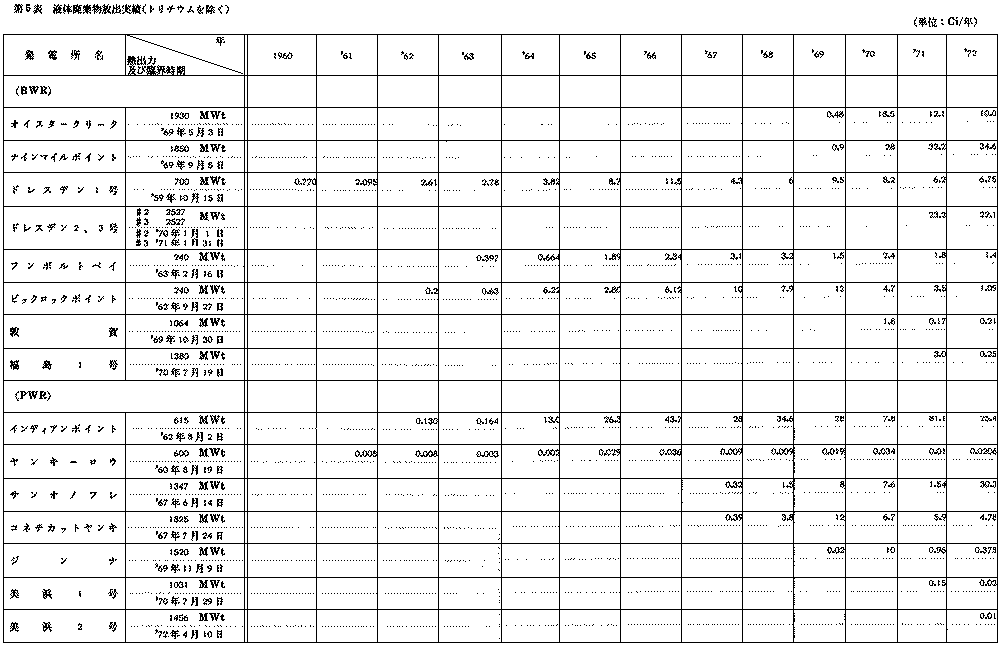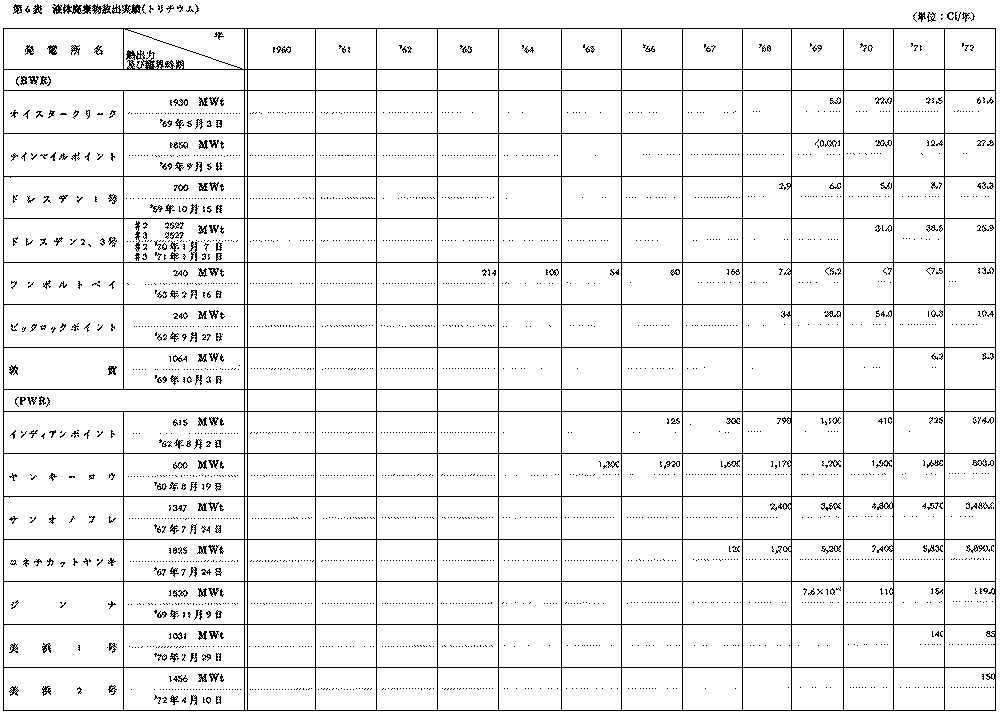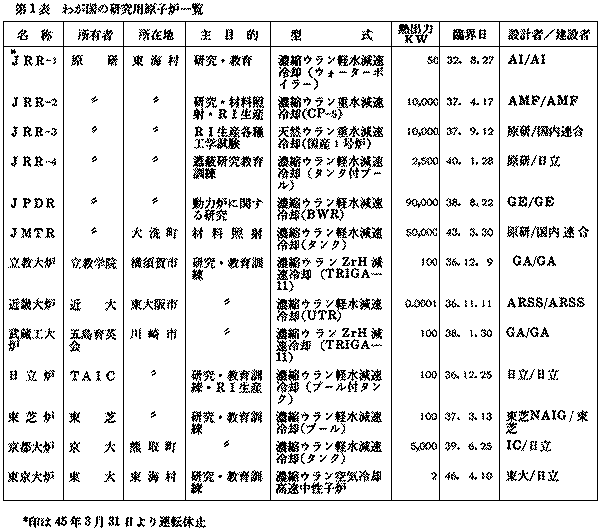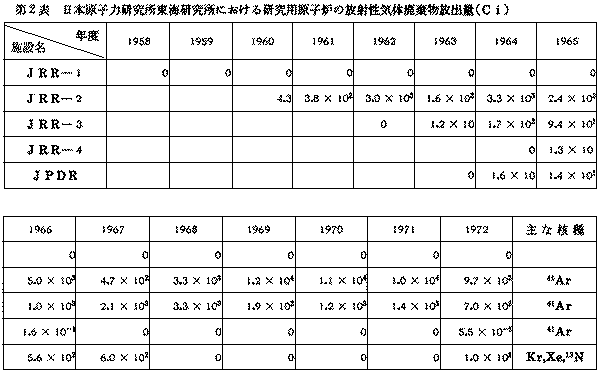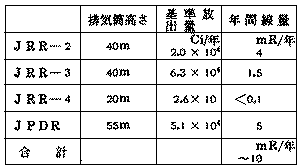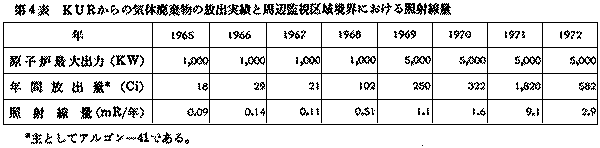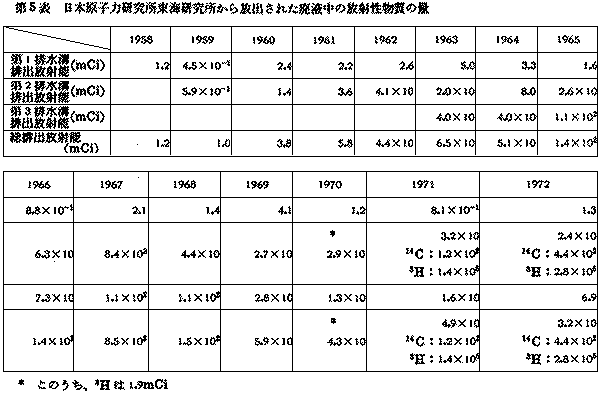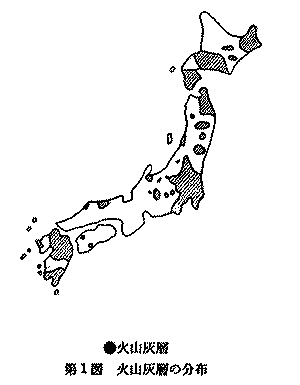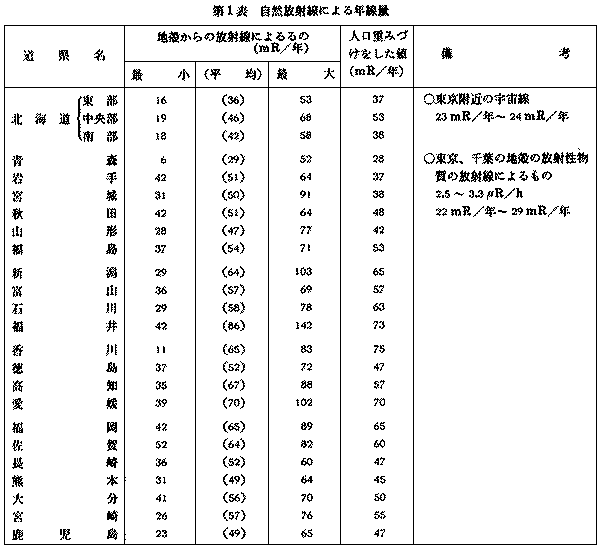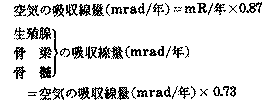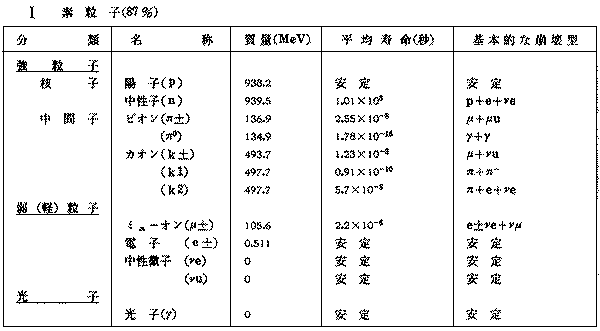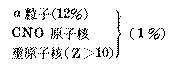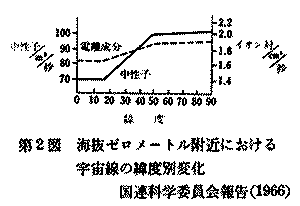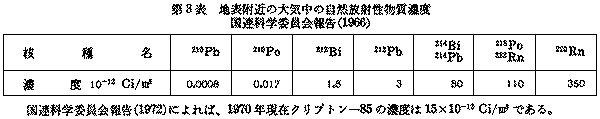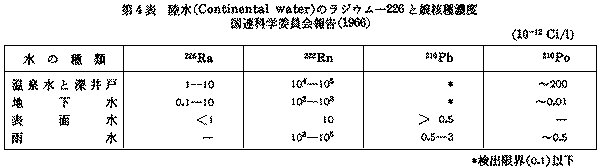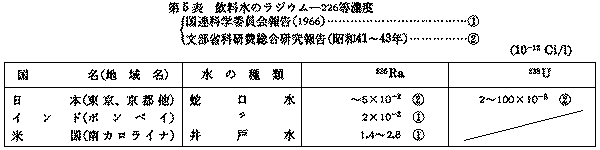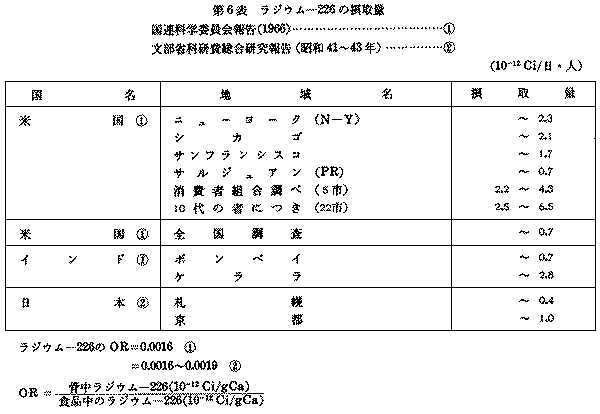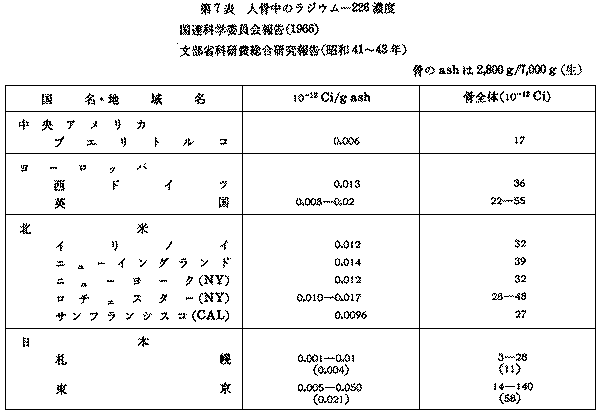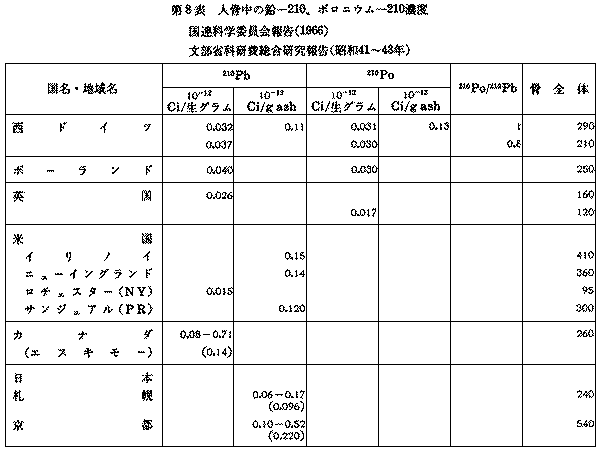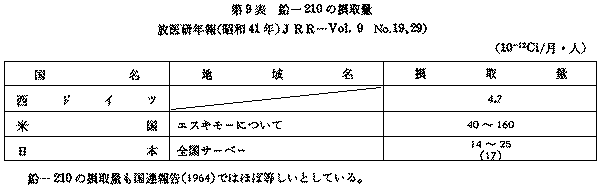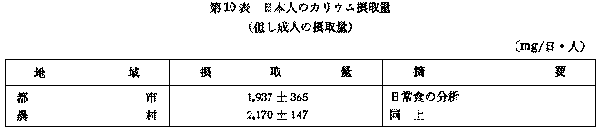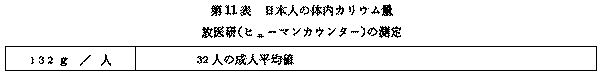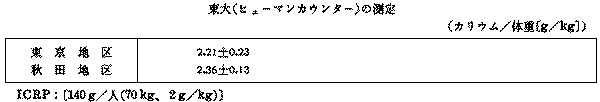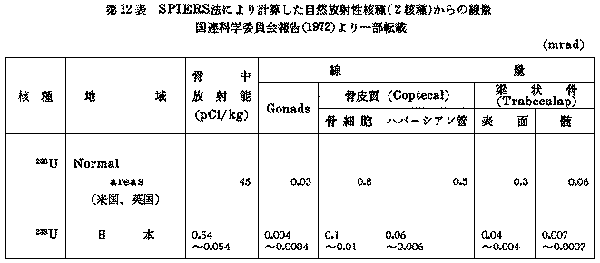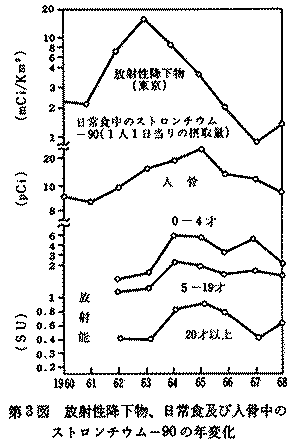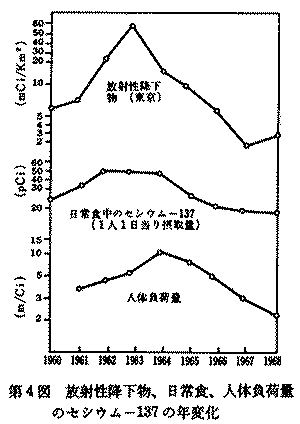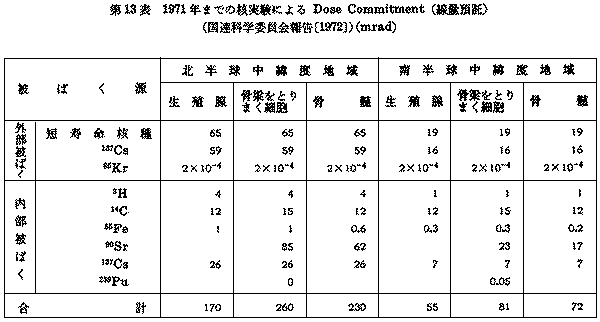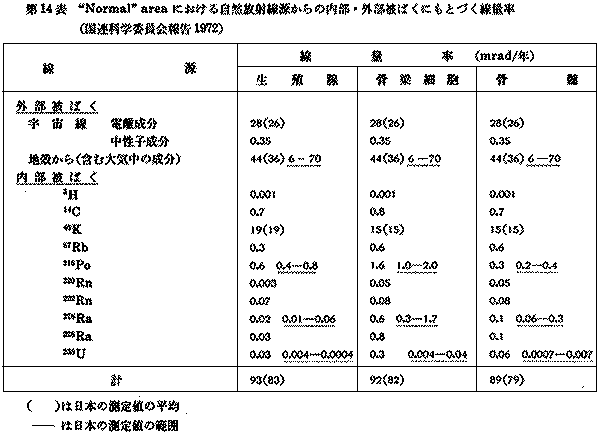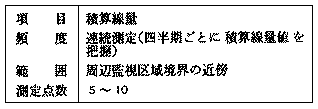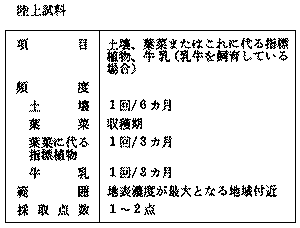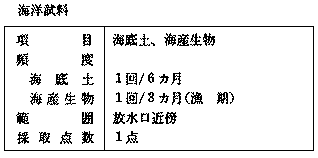| 前頁 |目次 |次頁 | |||||||||||||||||||||
| 資料 環境・安全専門部会報告書(環境放射能分科会) 昭和49年7月
環境・安全専門部会 |
|||||||||||||||||||||
|
1 昭和47年6月に発表された原子力開発利用長期計画によれば、原子力発電開発規模は昭和55年度において約3,200万キロワットと見込まれており、さらに昭和60年度には約6,000万キロワット、昭和65年度には約1億キロワットの規模の原子力発電が必要であるとされている。 2 当分科会は、原子力委員会の諮問により、昭和47年6月以降、原子力施設から放出される放射性物質に関し、 (1)「as low as practicable」の原則のとり入れ方 環境放射能分科会委員名簿(50音順)
ALAPワーキング・グループ構成員名簿(50音順)
環境モニタリングワーキング・グループ構成員名簿(50音順)
環境放射能分科会開催日
ALAPワーキング・グループ会合開催日
環境モニタリングワーキング・グループ会合開催日
第1章 原子力利用と環境放射能 第1節「実用可能な限り低く」(as low as practic-able)の考え方 1 原子力の開発利用の進展にともなう放射線防護に対する当分科会の基本的考え方は、原子力の積極的な開発利用を計る際の放射線被ばくに関し、国民の健康の保護と環境の保全を第一義とすることである。 2 放射線の個人及び集団に対する影響については1895年レントゲンがX線を発見して以来研究が重ねられており、国際放射線防護委員会(ICRP)は、それらをもとに広く世界の専門家の参加を求めて検討した結果、原子力施設からの放射線のみならずあらゆる線源からの放射線に対する防護の基本的な考え方と個人及び集団に対する具体的な線量限度とを勧告している。1)そしてその基本的な原則の一つに「被ばく線量は実用可能な限り低くすべきある」(doses be kept as low as practicable)という考え方が示されている。2) 3 原子力施設からの放射性物質の放出に伴う環境問題は比較的新しく起ってきた問題であり、その解決には、従来からの知見をもとに環境放射能の影響を推定し、それに基づいて放出制限などの対策をたてることが必要である。 4 当分科会は、本検討を進めるにあたって、ICRPの考え方に沿って諸施策が進められるべきものと考えた。そこでICRPの勧告から一部を引用しその考え方を再確認することとしたい。4)
5 わが国においては、ICRPの勧告の趣旨を尊重し放射線審議会の答申を経て所要の法令が制定されている。すなわち、一般公衆に対する放射線防護の10)
観点から原子力施設10)に対して周辺監視区域の設定を義務付けるとともに,周辺監視区域外の許容被ばく線量並びに空気中及び水中の放射性物質の許容濃度をICRPの勧告に基づいて定めている。 第2節「実用可能な限り低く」の原則の原子力施設への適用に際しての考え方 1 原子力施設の周辺公衆に対する許容被ばく線量(ICRPの勧告にいう線量限度に相当する。)についてはすでに現行法令に明確な値が定められているが、さらに被ばくをこの線量限度より「実用可能な限り低く」保つということについての規定ないしは指針等を定めることは、次に述べるようなことから望まれるところである。 2 すなわち、一般公衆の立場としては、原子力利用による放射線被ばくについて、それが単に線量限度を大幅に下まわるものであると定性的に説明されるよりも、どの程度まで低いのかが数値的に明らかにされることによって,より安心感を持つことができるであろう。 3 「実用可能な限り低く」の定量的目標を原子力施設から環境に放出される放射性物質の量について定めるか、周辺の住民が受ける線量について定めるかについては議論の分かれ得るところである。 4 ICRPの勧告に示されている線量限度はこれをわずかにあるいは相当こえたとしても、それに由来する影響は非常に低いレベルにあると考えられるものである(ICRP
Publication9、第74項参照)。 5 わが国をはじめ諸外国の原子力施設のうちで軽水型発電炉はその運転基数が多く、また、放出放射性物質低減技術の実用化についてはかなり具体的になっており、開発段階ではあるが一部その効果が実証されている。一方、その他の原子力施設については、同一種類の施設数も少なく、それに対する有効な低減技術の研究がかなりすすめられているものの、未だ実証されたものは少ない。 6 また、線量目標値が設定された場合には、それに加えて、この線量目標値を達成するために、原子力施設における環境への放射性物質の放出に係る管理のための基準(「管理の基準」)を設定することが必要である。 第3節 軽水型原子力発電所からの放出実績及び被ばく評価 1 軽水型原子力発電所で生じる放射性廃棄物の種類、発生量及び環境への放出量は、原子炉の型式をはじめ、廃棄物処理系等の原子炉関連設備の設計、運転管理方法等により異なる11)。また、放出量が同一であっても発電所周辺におよぼす影響は発電所の立地条件(気象条件、周辺監視区域境界までの距離等)によりかなりの相違が生じる。 2 放射性気体廃棄物の大半は放射性希ガス(クリプトン、キセノン)である。これによる被ばくは大気中に放出された希ガスを含む放射性雲(plume)からの外部被ばくである。 3 被ばく経路による被ばく線量の算定には、放出量と放出の形態、気象条件、海象条件、海産生物の種類、生物による濃縮係数、食品の摂取量等の諸パラメータが必要となる。上記の主なパラメータについては附録1の「被ばく評価モデル」12)に示してある。当分科会ではこの「被ばく評価モデル」を用いて被ばく線量の算定を行った。 4 まず気体廃棄物の放出実績に基づく被ばく評価であるが、わが国の沸とう水型(BWR)発電所周辺における希ガスによる被ばく線量は、1972年の米国の実績約10~130ミリレム/年に対して0.6~1.9ミリレム/年(昭和47年度実績)であり、また加圧水型(PWR)発電所については、1972年の米国の実績0.05~17ミリレム/年に対して、わが国では0.1ミリレム/年以下(昭和46、47年度実績)となっている(附録2第2表参照13))。なお、これらの実績はほとんど1敷地当り1基の場合のものである。一般にわが国の実績が米国のそれより低くなっている理由は、運転日数が浅く原子炉内部の状態が比較的清浄な時のものであること及び放出放射性物質低減化技術を積極的にとり入れたことである。とくに沸とう水型(BWR)の発電所についてその差が大きいのが活性炭式希ガスホールドアップ装置を採用することにより希ガスの放出量を積極的に低減させたためで一般に米国の実績より低くなっているのである。 5 液体廃棄物については、わが国の軽水型原子力発電所では、放射性廃液の回収処理による水の再使用の徹底化と積極的な固化により、液体廃棄物として環境中に放出される放射性物質は非常に少なくなってきており、放出実績(附録2第5表参照)を考慮すると今後も平均的レベルで見れば100万KW級の軽水炉においても1基当り年間1Ci程度(トリチウムを除く)におさえることは可能であると考えられる。 第4節 軽水型原子力発電所の線量目標値と管理の基準 1 軽水型原子力発電所については、前節で述べたとおり、線量目標値の具体的な数値を設定することが可能と考える。なお、「実用可能な限り低く」の原則をその他の原子力施設にどのように適用して行くべきかについては、次節にその考えを述べる。 2 前節で軽水型原子力発電所からの放出実績をみてきたが、「実用可能性」を基礎にして線量目標値を設定する場合、発電所の耐用年数中のほとんどの年度でこれを超えるべきでなく次のような配慮をする必要がある。 (1)わが国の軽水型原子力発電所からの放出実績に基づく被ばく線量の算定値は米国にくらべ低くおさえられているが、わが国での運転経験年数が少ないため燃料サイクルが平衡サイクルに到達しておらず、米国の実績によると同一の原子炉で同一の処理施設を有する場合でも経年的な増減が大きいこと。 (2)1敷地当り1基のみ設置している現状から複数基設置に進む場合、及び1基当りの出力も大型化すること。さらに、近接する軽水型原子力発電所間の被ばくの重畳についても考慮すること。 (3)線量の算定については、被ばく経路、被ばく評価に用いる種々のパラメータをどのように想定するかによって値が異なり、一義的に決るものでないこと。 (4)設計に当って原子炉の耐用年数中に起り得ると想定した運転状態の変動幅を含めて達成できるようなものとすること。 3 個々の軽水型原子力発電所の運転にあたっては、間接的な線量目標値よりも環境に放出する放射性物質に関する基準を定めた方が管理上好ましいと考えられる。このような管理の基準は発電所によって当然異なることになるので、当分科会は個々の施設の保安規定において管理の基準を決めることを提案する。 4 線量目標値から管理の基準を定めるにあたっては、軽水型原子力発電所から環境に放出される放射性物質に関して、発電所周辺のクリティカル・グループの代表的な個人について、放射性希ガス及び海産物摂取による全身被ばく並びに葉菜、海産物、母乳摂取(敷地周辺に牧場がある場合は牛乳摂取も含める)による甲状腺被ばくを考慮すれば良いと考える。また、この場合、現実的な計算方法及びパラメータを用いて評価するものとする。 5 線量目標値の達成の難易度は、個々の軽水型原子力発電所によって異なることになる。 第5節 その他の原子力施設についての線量目標値と管理の基準 1 軽水型原子力発電所以外の原子炉施設のうち、わが国においてかなりの運転実績が得られているのはガス冷却型原子力発電所及び研究用原子炉施設である。 2 現在運転中の研究用原子炉としては、附録3第1表に示すものがあるが、これらはほとんどが炉型式及び炉出力がそれぞれ大きく異なるものであり、一括して論ずることはできない。そこで、ここでは炉出力、設置基数、年間の利用率等を考慮し、その代表例として、日本原子力研究所東海研究所及び京都大学原子炉実験所の研究用原子炉を検討の対象にした。 3 以上の検討結果からガス冷却型原子力発電所(日本原子力発電㈱東海発電所)については、軽水型原子力発電所について定めた線量目標値に準じた値を適用することが可能であると考える。また、研究用原子炉施設においても近い将来において可能であると考える。 4 一方、軽水型原子力発電所、ガス冷却型原子力発電所及び研究用原子炉施設以外の原子力施設(例えば新型炉、再処理施設)に対する有効な低減技術についてはかなりの研究がすすめられているものの未だ実証されたものは少ないので、これによる効果をとり入れて周辺公衆の被ばくを試算することのできる段階にはない。これらの原子力施設については、将来の施設数の増加及び容量の増大の見通し並びに放出放射性物質低減技術の実用可能性の見通しを考慮し、適切な時期にそれぞれの線量目標値を定めること、及びこれらの原子力施設についても放出放射性物質低減化についての努力をすることを強く望むものである。 第6節 まとめ 1 当分科会は、ICRPの放射線防護に関する基本的考え方を考慮し、また原子力利用に伴なう放射線被ばくに対する国民一般、とくに原子力施設周辺公衆の認識と、急増するわが国のエネルギー需要に対処するための原子力の役割とを念頭におき、「実用可能な限り低く」の原則の取り入れ方を検討した結果、この原則を以下に述べるような形でわが国の原子力の開発利用の推進の際に取り入れることは極めて有用と考える。 2 原子力の開発利用による国民の被ばくについては、現在においても線量限度19)を十分下まわっているのであるが、当分科会は、さらに、ICRPの精神である「実用可能な限り低く」(as
low as practic-able)の考えを具体化するための検討を行なった。 3 当分科会は、原子力施設の設計、運転の上からも、また、国民の納得を得る上からも、さらに原子力施設の設置運転等について指導監督するという行政上の立場からも、放出放射性物質による一般公衆の被ばくを「実用可能な限り低く」するという原則を数量化した「線量目標値」を定めることが望ましいと考えるので、それが可能な場合にはこれを定めることを提案する。また、この線量目標値を設定した場合には、それを達成するために、原子力施設の運転に対応した「管理の基準」を定めることを提案する。 4 原子力施設のうち軽水型原子力発電所は、わが国において当面原子力発電の主流を占めるものであるが、その運転基数は多く、放出放射性物質低減技術の具体的見通しが得られている。したがって軽水型原子力発電所についての「線量目標値」の具体的数値を定めることは可能であると考える。 5 軽水型原子力発電所の「線量目標値」を達成するための放出放射性物質に関する「管理の基準」としては、放出方法を考慮して、例えば年間の総放出量、平均放出率、平均放出濃度等適切なものを定めることを提案する。 6 軽水型原子力発電所の「管理の基準」の各施設に対する具体的適用にあたっては、その基礎となっている「線量目標値」がICRPの勧告している線量限度の100分の1以下となっていることに鑑み、厳密な意味での上限値と考える必要はない。したがって、軽水型原子力発電所に対してこの値から導かれる「管理の基準」を適用するにあたっては、ある期間を限ってある程度の自由度は国の監督下において考慮されてしかるべきであると考える。 7 軽水型原子力発電所以外の原子力施設についても放出放射性物質低減技術の開発について努力し、軽水型原子力発電所と同様に適切な考え方で「線量目標値」が定められるよう望まれる。 8 なお、提案された「線量目標値」は、長期にわたって固定されるべき性質のものではなく、今後の技術の進歩、社会環境の変化等に応じて検討が加えられるべき値である。 9 当分科会としては、「線量目標値」及び「管理の基準」がすみやかにわが国の原子炉施設等に関する規制体系内に取り入れられるよう望むものである。 10 当分科会は、本報告書が国民の健康の保護と環境の保全とに役立つとともにわが国の円滑な原子力開発利用に寄与し、ひいては国民の生活水準と福祉の向上に資することを望むものである。 1)ICRPの放射線防護に関する基本的考え方及び線量限度に関する勧告は、初め1959年にICRP Pub li-cation(1958年採択)として刊行されたが、その後、1964年に、1962年までになされた改訂及び修正を加えたICRP Publication6が、1966年にはさらに広範囲にわたる再検討の結果を踏まえたICRP Publicati-on9(1965年採択)が、それぞれ刊行されている。 2)「実用可能な限り低く」(as low as practicable)という表現は、1962年のICRP勧告におけるものであり、1965年の同勧告では「容易に達成できる限り低く」(as low as is readily achievable)と述べられているが、両者には基本的な考え方の相違はない。 3)わが国の法令は基本的にはICRPの勧告を受け入れて制定されており、ICRPの勧告における線量限度に対応する数値が示されているが、「実用可能な限り低く」(as low as practicable)の原則のような一般的方針については明示されていない。 4)以下の勧告文は1965年に採択された勧告(ICRP Publication9)による。なお訳文は日本アイソトープ協会発行の「国際放射線防護委員会勧告」(1965年9月17日採択)による。 5)()の数字はICRP Publication9の各項を示す。以下同じ。 6)「不当に制限する」とは、原文では"undue restriction”となっている。 7)集団に対する遺伝線量とは、その集団の各人が、受胎から子供をもつ平均年令までにこれを受けたと仮定した場合に、それらの個人が受けた実際の線量によって生じるのと同じ遺伝的負担を全集団に生じるような線量である(84項)。集団に対する遺伝線量は遺伝有意年線量に子供をもつ平均年令をかけたものとして算定することができ、この平均年令はこの勧告の目的には30年とされる。集団に対する遺伝有意年線量とは個人の生殖腺線量に被ばく後受胎される子供の期待数を措けて平均した値である(85項) 8)「危険」とは原文では”risk”となっている。 9)「伴うことがある」は原文では“may involve”となっている。 10)ここで言う原子力施設とは、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」(昭和32年法律第166号、以下「原子炉等規制法」という。)によって規制を受ける原子炉施設並びに核燃料物質等の製錬、加工、再処理及び使用施設である。以下同じ。 11)軽水型原子力発電所における放射性廃棄物の発生、処理技術及び放射性物質の環境への放出実績については附録2に示す。 12)本モデルは、軽水型原子力発電所からの放出放射性物質の量から被ばく線量を算定するために設定されたものであって、その設定にあたり当分科会は現在までに報告されているもののうち、現実的と考えられる計算方法、評価パラメータを採用することを基本方針とした。これらの計算方法、評価パラメータは、新しい知見に基づき変更されるべきものであり、また評価にパラメータは実態調査等に基づく数値を導入してさらに現実的にしうる性質のものである。なお、以下の被ばく線量の算定にあたっては可能な限り本モデルによることとしたが、個々の発電所について具体的なデータの欠けているものについては過大な被ばく評価となるような仮定を設けて算定した。 13)これらの数値は各発電所の放出量から算定された周辺監視区域境界における値である。計算方法等については個々の施設で若干の相違はある。 14)ICRP Publication7を参照。 15)たとえば希ガスについては、評価地点の照射線量を算出し、滞在時間、住居によるしゃへい効果等を考慮して計算する。 16)全身線量及び年少者(16才未満)の甲状腺線量については100分の1また年少者以外の甲状腺線量については200分の1となっている(10頁参照)。 17)この値は、原子炉施設の周辺監視区域境界に常時人が居続けるとした場合、その人が受ける仮定的線量であって、個人が位置する場所、滞在時間、住居による遮蔽効果、人体の吸収線量への換算係数などを考慮すれば実際に周辺公衆の個人が受ける全身線量はこの算定値よりも下まわる。 19)ICRP勧告によれば公衆の構成員に対する線量限度は1年につき全身被ばく0.5レム、甲状腺被ばく3レム(ただし、16才未満の年少者については1.5レム)である。
被ばく評価モデル 当分科会は軽水型原子力発電所から放出される放射性物質による周辺公衆の被ばく評価にあたり以下のモデルを設定した。本評価モデル設定にあたり、当分科会は、現在までに報告されているもののうち、現実的と考えられる計算方法、評価パラメータを採用することを基本方針とした。これらの計算方法、評価パラメータは、新しい知見に基づき変更されるべきものであり、また評価パラメータは実態調査等に基づく数値を導入してさらに現実的にしうる性質のものである。 1 評価対象 (1)評価対象 評価の対象としては、原子力発電所周辺のクリティカル・グループ(1部落程度の大きさ)の代表的大人を対象とした。 (2)被ばくの経路 (3)評価地点 2 拡散モデル(気体) (1)放出有効高さ (2)風向、風速、安定度 (3)拡散計算
3 被ばく線量の算定 (1)γ線による全身線量への換算係数について (2)食物摂取による全身線量 (3)食物摂取及び呼吸による甲状腺線量 甲状腺へ達する割合:経口摂取については0.3、経気道摂取については0.23とした。 甲状腺の質量:大人、幼児、乳児に対してそれぞれ20(gr)、4(gr)、2(gr)とした。 放射性物質の摂取率:次節以降のパラメータを用いて算出した。 また、海産物摂取による甲状腺線量は、海水中にヨウ素の安定同位体が多量に存在することを考慮し、海水、海産生物及び甲状腺における放射性ヨウ素の比放射能が一定であると仮定して算出した。 (4)食物摂取量、呼吸率
*1ここでは、幼児としては4才、乳児としては1~2才を考えた。 (5)濃縮係数等
(6)希釈係数、減衰期間、除染係数
表1濃縮係数*
なお、放水口の平均濃度の算定にあたっては、各種冷却水ポンプの年平均利用率を80%とした。 1)本評価においては、乳牛飼育に当っての生草とその他の飼料との使用割合を半々と仮定し、この値の2分の1を用いた。 *本表の濃縮係数は、NAS新(1971)、Freke(1967)、UCRL-5064(1968)、NEA-IAEA(1973)に集録されたデータをもとにしたが、これら四データはかなりばらつきがあるので、ここでは濃縮係数が高いものの桁数を採った(四捨五入による)。 附録-2 軽水型原子力発電所からの放出放射性物質 1 気体廃棄物 (1)沸とう水型(BWR)原子力発電所 イ 放射性希ガス 通常運転時に発生する気体廃棄物の主なるものは、燃料から漏洩する放射性希ガス(クリプトン、キセノン)であり、これらの大部分は、タービン主復水器での脱気により空気抽出器を通じて連続的に放出される。この主たる排気であるタービン主復水器空気抽出器排ガスに対して、米国では減衰管により約30分間の放射能減衰を待って大気に放出する方式が標準的設計であったにもかかわらず、敦賀発電所をはじめ、わが国で建設されたBWR発電所では、約1日間貯留可能なガス減衰タンク方式を採用し、大気中への放出放射性物質の低減をはかってきた。すなわち、わが国のBWR発電所は、減衰タンク方式により減衰管方式を採用している米国BWR発電所にくらべ、希ガス放出量を約10分の1程度におさえることができた(第1表参照)。さらに現在では、活性炭式希ガスホールドアップ装置を開発し、これを米国に先がけて採用している。この装置は一般に排ガス中のクリプトンを約40時間、キセノンを約30日間保持し、24時間の減衰タンク方式にくらべて放射能をさらに50分の1程度にまで減衰させるよう設計されており、敦賀発電所では昭和46年12月より、福島発電所1号炉では昭和47年7月より使用を開始し、現在まで順調に稼動している。 ロ 放射性ヨウ素 (2)加圧水型(PWR)原子力発電所 イ 放射性希ガス ロ 放射性ヨウ素 2 液体廃棄物 軽水型原子力発電所の液体廃棄物には、原子炉冷却系統の腐蝕物の放射化により生じた腐蝕生成物と燃料から原子炉冷却水中に漏洩する核分裂生成物が含まれる。液体廃棄物は次のように大別できる。 イ 原子炉冷却系のポンプ弁等からの漏洩水(PWRではホウ素濃度調節の際の抽出水が含まれる)からなる機器ドレン ロ 原子炉関連建家からの床ドレン ハ イオン交換樹脂の再生で生ずる廃液(化学実験室の廃液、除染廃液を含む)。 二 汚染作業服等の洗濯で生ずる洗濯廃液
|
| 第1表 軽水型原子力発電所の気体廃棄物放出実績(希ガス) |
| 附録-3
研究用原子炉施設からの放出放射性物質 研究用原子炉の放射性廃棄物は、炉型によって異なるが、主として原子炉冷却材それ自体、冷却材中の構造材腐蝕物並びに照射孔及び実験孔内の空気又は不純物の放射化により生成されるものである。 第1表 わが国の研究用原子炉一覧
現在運転中の研究用原子炉としては第1表に示すものがあるが、炉出力、設置基数、年間の利用率等を考慮し、代表例として、日本原子力研究所東海研究所及び京都大学原子炉実験所の研究用原子炉を挙げ、これらの施設における放射性廃棄物の放出実績及びこれによる周辺公衆の被ばく線量の評価結果について以下述べることとする。 1 気体廃棄物とそれによる被曝評価 研究用原子炉においては、実験孔や照射孔の空間部に存在する空気中の元素が熱中性子照射を受けることによりアルゴ-41、窒素-13、窒素-16などが生成される。これらの放射化生成物は排気系を通じ排気筒から周辺環境に放出されるが、アルゴン-41以外は半減期が短くまた生成量も少ないので気体廃棄物として被ばくが問題になるのは一般にアルゴンー41のみである。 (1)日本原子力研究所東海研究所の場合
JPDRの場合気体廃棄物は、主として燃料被覆のピンホールから漏洩した核分裂性の希ガス(クリプトン及びキセノン)であり、この他に窒素-13がある。 第3表 日本原子力研究所東海研究所の研究用原子炉の放射性気体廃棄物に関する基準放出量に対する周辺監視区域境界における年間線量(最大値)
第3表は、東海研究所の研究用原子炉及びJPDRから放出される気体廃棄物による被ばくが最大になる周辺監視区域境界の照射線量を年間の各炉の基準放出量をもとにして算定したものである。ここでJRR-2とJRR-3の基準放出量は、両炉の機能、運転条件に基づく蓋然的な年間の最大放出量である。JPDRについては、最大被ばく地点における年間照射線量が5mRになるような放出量である。 (2)京都大学原子炉実験所の場合
(STDOSE)を用いて計算したものであり、風向分布を考慮していないので約3倍程度過大な評価になっていると考えられる。国連科学委員会の換算係数を用いれば人体組織の吸収線量は、過去の年間の照射線量の最大値9.1mRに対し 2 液体廃棄物による被ばく評価 研究用原子炉施設の液体廃棄物には、原子炉冷却系中の腐蝕物の放射化により生じた放射性物質のほか、被照射試料等の照射実験により生ずる放射性物質を含む廃液がある。一般にこれらの放射性廃液はいったん放射性廃液貯槽に貯えられた後放射能測定を行ない、その濃度が管理基準値以下であると確認されたものは一般排水と混合希釈して海へ放出される。管理基準値以上のものは廃棄物処理場で濃縮固化等の処理を受ける。 (1)日本原子力研究所東海研究所の場合
東海研究所の研究用原子炉施設以外のR・I施設等を含む全施設からの放射性廃液の放出実績を第5表に示す。放射性廃液中のトリチウム、炭素-14以外の主な核種は、コパルト-60、セシウム-137などである。 (2)京都大学原子炉実験所の場合 2)原安協海洋放出調査特別委員会
環境放射能による被ばく (原子力施設から放出されるものを除く) 1 地殻からの放射線による被ばく 現在、日本で大多数の国民が居住している地域には、放射性物質の濃度が著しく高い所はない。居住地域を大別すると地表面が火山灰層で被覆されている地域は放射線被ばくが比較的小さく、花崗岩系の地質が地表面に存在する地域では比較的大きい。火山灰層の地域での被ばくは主として放射性カリウム(カリウム-40)の寄与であり、花嵐岩地域では放射性カリウムに加えて、ウラン系列、トリウム系列からの寄与がある。(第1図参照)
これらの測定結果から体内組織臓器の吸収線量を求めるために下記の手法を用いた(国連科学委員会報告(1972)による)。
したがって10mR/年~110mR/年から組織臓器の吸収線量を求めれば 組織臓器の吸収線量=8.7~96mrad/年×0.73=6~70mrad/年 となり、前述の平均値57mR/年は36mrad/年となる。 2 宇宙線からの被ばく 地球上の人類の大多数が生活している地域では、ほぼ同じ位の線量の被ばくを宇宙線から受けている。成分は第2表に示した通りで、その源は銀河系からのものが大部分であり、太陽を源とするものがわずかに加わる。海抜零メートル附近の宇宙線は、地球の大気により一次線(宇宙空間をとおってきたもの)が吸収、散乱され大気中で生成された二次線が主成分となっている。これらは、地磁気により赤道附近では線束密度が低く、極に近づくにしたがって高くなる。海抜ゼロメートル附近の赤道では24mrad/年で緯度55度以上は28mrad/年となっている。(第2図参照)
Ⅱ その他(13%)
また、高度による宇宙線強度の変化は高度数千メートルまでは1.5km増すごとにほぼ2倍となる。
体内に経気道摂取され、また食物連鎖を通して経口摂取される自然放射性核種のうち主なものはトリチウム、炭素-14、カリウム-40、ルビジウム-87、ポロニウム-210、ラドン-220、ラドン-222、ラジウム-226、ラジウム-228、及びウラン-238である。これ等の核種について日本で人体内の量を測定した結果によれば、カリウム-40、ポロニウム-210、ラドン-220、ウラン-238、が主な核種である。(第3表~第12表参照)
内部被ばく線量に最も大きく寄与する核種はカリウム-40であり、他はこれより1桁から4桁低い値となっている。カリウム-40については国際放射線防護委員会の報告及び国連科学委員会報告(1958、1962、1966年)の値と日本での測定値は同じであり、したがって線量寄与も等しい。 4 核実験の放射性降下物による被ばく 大気圏内での核実験の大部分は1963年以前に行なわれており、それが地球上の人工放射能の主源になっている。人への影響評価の見地から注目されているストロンチウム-90、セシウム-137についてみると、1970年までにストロンチウム-90については15MCiが地球表面に達しており、この約1.5倍のセシウム-137も降下したことが推定される。また量的に多いものとしてトリチウムがあげられる。
中のセシウム-137の量は、放射性降下物の降下量に比例して1963年頃を頂点として1964年以降は減少しているが、食品中のストロンチウム-90の量は降下物の頂点より2年遅れて1965年に頂点に達し、1966年以降に減少が認められている。セシウム-137の人体負荷量と人骨中のストロンチウム-90含量は食品中のセシウム-137、ストロンチウム-90の含量の年変化とほぼ同様の傾向を示している。 5 まとめ 以上のように我々は環境中に存在する放射性物質の放射線による被ばくを常時受けている。第14表
に国連科学委員会報告(1972年)の”Normal”areaにおける自然放射線源からの内部及び外部被ばくにもとづく線量率を示す。 第2章 環境放射線モニタリングのあり方 第1節 まえがき 「原子力施設周辺環境の放射線モニタリング」(以下「環境放射線モニタリング」という。)の意義とその計画は、それぞれの原子力施設(原子炉施設及び使用済燃料再処理施設)がおかれた自然条件、社会環境並びに施設からの放射性物質の放出条件、施設の安全対策といった各種の前提条件を十分考慮するとともに環境放射線モニタリングの目的をふまえて決められるべきものである。しかしながら、環境放射線モニタリングについては、往々にしてこれらの前提条件や目的の相違を考慮することなしに論じられるきらいがある。 第2節 環境放射線モニタリングに対する基本的考え方 2.1 環境放射線モニタリングの前提条件 我が国では、国民を放射線障害から守るためICRP(国際放射線防護委員会)勧告を尊重することを基本としており、国内法令にもこれがとり入れられている。原子力施設の設置や放射性物質の使用は、法的に許可届出制がとられており、かつ、許可に際しては厳重な審査が行われる。また、施設設置後の放射性物質の環境放出に関しては、ICRPが勧告している公衆の構成員に対する線量限度を越えないよう十分な規制が行われている。 2.2 環境放射線モニタリングに対するICRPの基本的考え方 (1)環境放射線モニタリングの目標を「(a)人の環境中に存在する放射性物質または放射線への、人の現実の被ばくあるいは潜在的被ばくの算定、またはこのような被ばくとして考えうる上限値の推定(b)時には被ばくの算定に関連し、また時には他の目標に関連する科学的調査(c)対公衆関係の改善」(2項)1)と述べている。 (2)そして、環境放射線モニタリングプログラムの型をサーベイの種類「(a)放射性物質を取り扱う施設外のサーベイ、必要ある場合には操業に先立つサーベイを含む。(b)緊急時サーベイ(c)核爆発からの破片のフォールアウトに関するサーベイ」(5項)に分けて、(a)、(b)を主体とし、全体に共通する環境放射線モニタリングに関する考え方とサーベイの種類による具体的事項に関する考え方とを述べている。 (3)全体に共通する環境放射線モニタリングに関する考え方としては、環境への放射性物質の放出から人の被ばくへの道筋として、いくつかの考えられる経路のうち、決定的(crⅰtical)と考えられる核種、経路に着目すべきであると述べている。 (4)一方人の側からは、施設外の集団の中で集団中のほかの人々よりも大きい線量を受けることを考慮する必要のあるグループ(決定グループ)について着目することを述べている。 (5)そして、操業に先立つ調査により、施設に由来する人への放射線量がごくわずかであると決定的にいいうるのに十分な資料が得られる場合は環境放射線モニタリングプログラムは不要であると述べている。 (6)しかし、使用者個々には少量の放射性物質しか取り扱わないが使用者が集中して総計としては有意の環境汚染をひきおこす危険が生ずる場合は、環境放射線モニタリングプログラムの必要性が生ずると述べている。 (7)そして、環境放射線モニタリングの実施に関する管理者側と公共機関側の責任の区分について次のように述べている。 (8)具体的事項については、「施設外の日常サーベイ」(C項)「堅急時サーベイ」(D項)に分けて、それぞれのサーベイの考え方を具体的に述べている。 (9)フォールアウトに関するサーベイに関しては、「施設外の日常サーベイ」「緊急時サーベイ」に関連して一部触れることもあるが、国際連合原子放射線の影響に関する科学委員会の調査対象としているので、特に対象とはしないとしている。 2.3 当分科会の基本的考え方 2.4 環境放射線モニタリングの目的 (1)「原子力施設の操業に起因する周辺公衆の被ばく線量が法令に定める許容被ばく線量を越えていないことを確認すること。原子力施設からの放射性物質の予期しない放出による周辺環境への影響の判断に資すること。また『実用可能な限り低く』(as
low as practicable)の考え方から許容被ばく線量以下に設定される線量目標値が維持されていることを推定、評価すること。」 (2)「環境における放射性物質の蓄積傾向を把握すること」 1)()内の数字は、ICRPPublⅰcation7の各項を示す。以下同じ。
環境放射線モニタリングでは、環境放射能の測定、放射性物質の放出量と環境パラメータに関する情報の収集が行われる。 3.1 計画策定に際しての基本的考え方 放射性物質が環境に放出される場合、これが人の被ばくに結びつく過程には、環境に放出された放射性物質からの直接外部被ばくと空気、水及び農水産食品を介して人が摂取する放射性物質から受ける内部被ばくの2つがある。これらの過程による人の被ばくの大きさは ① 施設から環境へ放出される放射性物質の量、核種及び物理的・化学的形態 ② 環境のもつ拡散、希釈能力 ③ 生物等による濃縮 ④ 環境と人とのかかわり合いの程度 といった諸要因によってかなり異なる。したがって環境放射線モニタリング計画においては、これらの諸要因を含めた事前の被ばく評価を参考とし決定核種、決定経路及び決定グループに注目して具体的方法の検討を行うことが望ましい。具体的な環境放射線モニタリング実施に際しては、簡便で合理的な方法を用いることも適当である。例えば、サンプリング試料の全放射能測定のような簡単な測定方法によって迅速に放射能レベルを把握し、その結果必要ならば、核種の同定、試料数の追加測定等を行うといった方法が考えられる。 3.2 環境放射線モニタリングの具体的項目、頻度、範囲 (2)頻度 ICRP勧告や我が国の法令では、3か月とか1年といった期間の積算の被ばく線量で評価することになっている。従って、長寿命核種の影響調査を主体とした環境放射線モニタリングは、空間線量、空気、水等は3ケ月という期間の合計又は平均を考えることが妥当であり、農水産食品では収穫期、漁期とすることが妥当である。また、全体的な傾向把握のための項目、例えば土壌や海底土、指標生物等は半年ないしは1年といった期間ごとに1回の試料採取で足りる。 (3)範囲及び試料数 3.3 分析、測定方法 現在行われている方法としては、主として核実験を対象に放射線審議会の審議を経て科学技術庁が制定した方法等があるが、原子力利用に伴う環境放射線モニタリングにおいて必要とされる対象核種、測定目標値、精度等を考慮して再検討すべきである。 3.4 操業前環境放射線モニタリング 施設の操業に先立って行われる環境放射線モニタリングは、次の諸点に注目して2年位前から実施することが望まれる。 ① 天然及び人工の放射性物質は、どこにでもいくらかは存在するので、これと施設の操業により放出されるかも知れない核種との区分に役立たせるため ② 操業時の環境放射線モニタリング計画の立案に必要な情報の収集及び訓練のため ③ 決定核種、決定経路及び決定グループに関する情報を得るため 3.5 環境放射線モニタリング計画の見直し 第4節 環境放射線モニタリングの体制 4.1 施設者、地方公共団体及び国の役割 原子力施設からの放射性物質の放出については、施設者は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「原子炉等規制法」という。)に基づく保安規定によって放出管理等を定め周辺環境の保全に努めるとともに環境放射線モニタリングを実施している。また、国は環境放射線モニタリングに関する指導、助言等を行うとともに原子力事務所や原子力連絡調整官事務所をおきその一部では環境放射線モニタリングを実施している。 (1)施設者の役割 (2)地方公共団体の役割* (3)国の役割 ① 国民の被ばく管理に関連する諸法令の整備 4.2 評価機関 わが国の放射能調査は、核爆発実験に伴うフォールアウトに係るもの、原子力施設に係る環境放射線モニタリング及び放射性同位元素使用の一般事業所に係るものについて種々の機関で実施されているが、これらを包括的に評価する体制になっていない。 (1)評価機関の必要性 (2)評価機関の役割 ① 環境放射線モニタリング結果の総合的評価 *原子力施設の設置により環境放射線モニタリングを実施する区施は、いくつかの市、町、村に亘る場合が殆んどと考えられるので、環境放射線モニタリングの円滑な実施のため、地方公共団体の単位は、都、道、府、県とすることが適当と考えられる。 付言 中央評価機構のあり方 原子力発電所、再処理施設等の原子力施設設置県においては、それぞれの地元の実情に応じて、地方公共団体、地元住民、施設者等をまじえて、施設の安全操業を監視する機構が組織されており、環境放射線モニタリングの結果の評価検討が行われている。これらは、実際上、その地方における評価機関の役割を持つものであり、今後育成、強化をはかることが必要である。当分科会は、こうした実情に鑑み、モニタリングの方式、評価方法等環境放射線モニタリング全般に関する判断基準を確立し、各地域におけるモニタリングの斉一を図るとともに、その結果を総合的に評価するため中央に評価機関を設置すべきであるとの観点に立って検討を行い以下のとおり考え方をまとめた。 1 設置の目的 2 機能 中央評価機関は、次の機能を有することが適当であると考える。 (1)環境放射線モニタリング計画の立案及び結果の評価について、基準となる考え方を確立し、方法を斉一化すること (2)国又は地元の要請に応じて、各地域における実施計画について科学的、技術的な指導、助言をすること (3)放射性物質の環境への放出記録及び環境放射線モニタリング結果に基づき、放射性物質の環境中での蓄積傾向を広域的、長期的に把握すること (5)その他環境放射線モニタリングに関し、地元の評価機関の解決し得ない問題を処理すること 以上の機能を全うするためには、中央評価機構は常設的機関であることが望ましい。 3 設置、運営にあたって考慮すべき事項 付録 原子力発電所における環境放射線モニタリング計画作成の指針 本指針は、原子力発電所周辺における環境放射線モニタリング計画作成のための手引となるものである。 I 空間γ線量の測定 現在、原子力発電所から放出される気体廃棄物による被ばくは、自然放射線による被ばくの約5%程度であり自然放射線の変動範囲内のものである。
Ⅱ 環境試料の測定 発電所から排出される放射性物質はきわめて少ないものであり、それがただちに食品を汚染するものではないがごく微量であっても、長半減期核種が環境中に蓄積されることを考慮しこれらの動向を把握するため陸土や海底土を長い時間間隔で測定しておくことは必要である。
海洋試料
Ⅲ その他 前述の他、陸水、海水、空気中の放射性粒子濃度等については、従来、測定の対象となっている例が多いが発電所から放出される放射性物質の量はきわめて少なく、かつ、水や空気中で濃縮されることもないので、これら試料中の放射性物質濃度は低く測定が困難であり、むしろ放出源での測定が有効であろう。
|
||||||||||||||||||
| 前頁 |目次 |次頁 |