昭和46年度原子力開発利用動態調査報告書
| ま え が き |
原子力開発利用の各分野における従事者、研究開発費、設備投資、生産実績等の実態について科学技術庁で調査した結果を昭和46年度原子力開発利用動態調査としてとりまとめた。
調査結果はつぎのような背景のもとでわが国の原子力開発利用が順調に推移したことを示している。
昭和46年度におけるわが国の原子力開発利用は、原子力発電が実用化の時期にはいり、昭和46年度末で発電容量が1323千kwに達したほか、国のプロジェクトとして現在開発を進めている新型転換炉の原型炉の建設が始まり、新型動力炉の開発が本格化したのをはじめ、使用済燃料再処理施設の建設着手原子力船「むつ」の艤装工事完了など原子力開発の広範な分野にわたって順調な進展がみられた。
一方、昭和46年度のわが国の経済は、46年8月、ニクソン・ショックと通称されるアメリカ新経済政策の発表と、それにひき続く国際的な平価調整の渦の中で大きな試練に立たされ、新しい経済環境への適応を迫られたが、わが国の原子力関連産業は、原子力に対する強い要請に応えてこのような経済動向に余り影響されることなく好調に推移した。
本結果を報告するにあたり、調査の実施に関し、御協力をいただいた関係省庁、関係機関、民間企業等に深く謝意を表する。 |
Ⅰ 調査の概要 |
§1 調査の目的
わが国における原子力平和利用の全分野について、従事者、研究開発費、設備投資、生産等の実態を総合的定期的に調査し、原子力開発利用の推進をはかるうえに必要な基礎資料を作成し、行政施策の充実に資することを目的とする。 |
§2 調査の時点
調査は、昭和47年3月31日現在について行ない、研修、研究開発費、設備投資、生産等については、昭和46年4月1日から昭和47年3月31日までの期間におけるものをとりまとめた。 |
§3 調査の対象
調査の対象は、昭和47年3月31日現在「放射性同位原素等による放射線障害の防止に関する法律」(放射線障害防止法)および「核原料物質、核燃料物質および原子炉の規制に関する法律」(原子炉等規制法)にもとづく許可等を受け、または届出を行なっている者のほか、次の原子力関係諸機関である。
ⅰ)原子力関係予算を計上している国の試験研究機関および特殊法人
ⅱ)昭和46年度および47年度原子力平和利用試験研究委託費の交付を受けた者
ⅲ)科学技術庁関係の許可団体のうち原子力関係の団体およびその加盟者
ⅳ)その他、上記ⅰ)~ⅲ)に準ずる者 |
§4 調査事項
調査事項は次のとおりである。
(1)原子力関係従事者
ⅰ)従事者の構成
ⅱ)放射線関係従事者
ⅲ)研究者および技術者の専門分野
(2)研 修
(3)研究開発費
(4)設備投資
ⅰ)原子炉、核燃料施設
ⅱ)放射線利用関係施設
(5)生産等実績
ⅰ)核燃料関係
ⅱ)原子炉等関係
ⅲ)放射線利用機器関係 |
§5 調査の方法
本調査の調査対象は2,670機関で、この全機関に対して、昭和47年7月15日を提出期限とし、調査表を郵送した。
なお、大学関係の調査対象については、文部省大学学術局、民間企業の従事者研究開発費、および、設備投資関係の調査項目については、日本原子力産業会議をそれぞれ通じて行なった。
1 調 査 票
調査票は、「医療機関用」、「教育機関用」「研究機関用」および「一般用」の4種類を用意し、これを、医療機関については病院、診療所ごとに「医療機関用」の調査票を、教育機関については学校または学部ごとに「教育機関用」の調査票を、研究機関については研究所、試験所ごとに、「研究機関用」の調査票をそれぞれ郵送した。
民間企業およびその他機関については、法人または機関ごとに「一般用」の調査票を郵送したが、原子炉等規制法または放射線障害防止法の規制対象となっている付属の試験所または病院等がある場合には、これら付属の試験所または病院についての回答を得るため、「研究機関用」または「医療機関用」の調査を併せて郵送した。
2 調査の回答
1)調査票の回答
調査票を郵送した2,670機関のうち、2,253機関から回答を得た。回答率は84%である。
なお回答のあった機関のうち、710機関は「白紙」回答で、有効回答(記入回答)のあった機関は、1,543であった。
(「白紙」回答について本調査の対象となる活動を行なっていないものとして処理した。)第1表は、記入回答機関数を機関別にとりまとめ昨年と比較したものである。 |
第1表 |
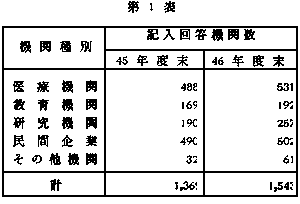 |
Ⅱ 用 語 |
(1)「医療機関」とは、国立、公立、私立の病院および診療所ならびに教育機関、研究機関等の付属の病院および診療所。
(2)「教育機関」とは国立、公立および私立の学校、ただし、教育機関付属の病院、研究所等を除く。
(3)「研究機関」とは、国立、公立、私立の研究所、試験所および教育機関の付属研究所、試験所ならびに研究開発を行なう特殊法人(日本原子力研究所、動力炉・核燃料開発事業団、日本原子力船開発事業団等)。
(4)「民間企業」とは、株式会社、有限会社等の法人(民間企業に付属する研究所および病院を含む。)
なお、民間企業の業種別分類は、日本標準産業分類によった。
(5)「その他機関」とは、財団法人、社団法人等の団体ならびに国の機関で医療機関、教育機関および研究機関に属しない機関(例、建設省、農林省、運輸省等の地方出先機関等)。
(6)「医療利用」とは、医学、医療に関する原子力開発利用を行なう分野。
(7)「農業利用」とは、農林水産事業に関する原子力開発利用を行なう分野。
(8)「工業利用」とは、鉱工業に関する原子力開発利用を行なう分野。
(9)「その他利用」とは、医学利用、農業利用および工業利用以外の分野。
(10)「医師、歯科医師」とは、医師法においていう医師および歯科医師法において行なう歯科医師である者。
(11)「薬剤師」とは、薬剤師法において薬剤師である者。
(12)「診療放射線技師」及び「診療エックス線技師」とは、診療放射線技師及び診療エックス線技師法で定義する診療放射線技師及び診療エックス線技師である者。
(13)「技師等」とは、臨床検査技師、衛生検査技師に関する法律で定義する衛生検査技師、理学療法士および作業療法士法で定義する理学療法士および作業療法士、歯科衛生士法で定義する歯科衛生士および歯科技工士法で定義する歯科技工士である者。
(14)「看護婦等」とは、保健婦、助産婦、看護婦法で定義する保健婦、助産婦、看護婦および准看護婦である者。
(15)「その他」(医療機関)とは、医師、歯科医師、薬剤師、診療エックス線技師、技師等および看護婦等以外の者。
(16)「管理者」とは、研究機関にあっては部長、または、これと同等以上の管理または監督の地位にあり、専らその業務を行なっている者、民間企業にあっては、本社(部)の課長、事業所の部長、またはこれと同等以上の管理または監督の地位にあり、専らその業務を行なっている者。
(17)「研究者」とは、医理工科系の大学(短期大学を除く。)の課程を修了した者、または、これと同等以上の専門的知識を有す者で、2年以上の研究業務の経験を有し、かつ、国有の研究テーマをもって研究を行なっている者。
(18)「技術者」とは、理工科系の大学(短期大学を含む。)の課程を修了した者、または、これと同等以上の者であって、高度の知識、技術を要する業務に従事する者。
(19)「事務職員」とは、事務的業務を行なっている者。
(20)「その他職員」とは、教育機関、研究機関における管理者、研究者、技術者、事務職員以外の者。
(21)「工員等」とは、民間企業、その他機関における工員、作業員等で管理者、研究者、技術者、事務員以外の者。
(22)「管理区域常時立入者」とは、放射線施設等の管理区域内で、放射線作業に従事している者であって放射線障害防止法の施行規則で定める「放射線作業従事者」および原子炉等規制法の関係布令で定める「従事者」。
(23)「管理区域随時立入者」とは、放射線施設等の管理区域内に業務上立ち入る者(一時的に立ち入る者を除く。)であって、管理区域常時立入者以外の者。具体的には、放射線障害防止法規則で定める「管理区域随時立入者」および原子炉等規制法施行規則で定める「従事者以外の者(一時的に立ち入る者を除く。)」等。
(24)「原子力専門科学技術分野」とは、原子炉物理、原子力工学等について高度の知識、技術を要する分野
(25)「原子力関連科学技術分野」とは、機械、電気、物理、化学、冶金等について、それぞれの知識、技術を要し、あわせて、原子炉の設計、製造、運転等の原子力関係の知識、技術を要する分野。
(26)「核燃料科学技術分野」とは、冶金、化学、機械等について、それぞれの知識、技術を要し、あわせて核燃料の製錬、加工、使用済燃料の再処理等についての専門知識、技術を要する分野。
(27)「放射線利用科学技術分野」とは、理学、工学、農学、医学等について専門の知識、技術を要し、あわせて放射線の利用に関する知識、技術を要する分野。
(28)「原子力安全管理科学技術分野」とは、原子力発電所、原子力船、核燃料関係施設、大規模な放射線取扱施設等において、放射線防護、安全設計、廃棄物の管理および処理、緊急時の安全対策、安全管理等についての知識、技術を要する分野。
(29)「基本研究」とは、知識の進歩を目的として行なう研究で、特定の実際的応用を直接のねらいとしないもの。
(30)「応用研究」とは、知識の進歩を目的として行なう研究で、特定の実際的応用を直接のねらいとするもの。
(31)「開発研究」とは、基礎研究および応用研究等による既存の知識の利用であり、新しい材料、装置、製品、システム、工程等の導入、あるいは、既存のこれらのものの改良をねらいとするもの。
(32)「人件費」とは、一年間に支払った給与(退職金等を含む)の総額(税込)。
(33)「設備等購入額」とは、施設、器具、図書等の当該年度における購入額。
(34)「その他経費」とは、消耗資材費、光熱費等。 |
Ⅲ 調査結果の概要 |
昭和46年度の原子力開発利用動態調査の結果について概括すれば、原子力発電の実用化の進展に伴う民間企業の原子力関係従事者の順調な伸び、原子力発電所設備投資の急速な伸び、および、新型動力炉開発の本格化に伴う研究機関の開発費の急増等が顕著なことであった。
民間企業による原子力発電所の建設については、東京電力(株)福島2号、3号、4号、5号、中部電力(株)浜岡1号、関西電力(株)美浜2号、3号、高浜1号、2号、中国電力(株)島根1号、九州電力(株)玄海1号の各原子力発電所建設工事が順調に進捗した。
また、新型動力炉の開発は、動力炉・核燃料開発事業団の大洗工学センターの高速増殖炉実験炉の建設および同事業団の敦賀市における新型転換炉原型炉の建設等が主なものとなっている。
以下、主要項目について前年度と比較しながらその概要を述べる。
(1)原子力関係従事者は前年度に比し18%の増加をしめしている。とくに民間企業の伸びが大きい。(25.3%増)。
(2)放射線関係従事者数は前年度に比し15.2%の増加をしめしており、なかでも研究機関(29.2%増)の伸びが大きい。
(3)研究者、技術者の数は、前年度に比し27%増加しているが、このうち、とくに民間企業における「原子力関連科学技術者(56.7%増)」および「核燃料科学技術者(72.4%増)」の増加が著しい。
(4)研修派遣の状況は、前年度に比し7%増加している。とくに、1ヵ年未満の国内研修が大きな分野を占めており、原子炉研修は海外の方が多いが、放射線利用については、国内での研修が中心になっていることを示している。
(5)研修開発費は、45年度の548億円に比し46年度は834億円と約50%増加している。とくに、開発(研究)の増加が著しく、動力炉・核燃料開発事業団が実施している新型動力炉開発の本格化していることを示している。
(6)設備投資額は45年度の998億円に比し46年度は1,560億円と約57%増加している。増加は主として民間企業の1,465億円(前年度937億円)によるものである。
設備投資の増加した主要なものは原子力発電所の1,378億円(前年度849億円)が最も大きく、再処理施設、核燃料加工施設がそれぞれ43億円(前年度0)、31億円(前年度23億円)とこれについで大きくなっている。
逆に設備投資の減少した分野は、「原子炉製造施設」で、これは、原子炉圧力容器のような大きな機器の製造施設の設備投資が一段落したことを示している。
また、民間企業の設備投資の増加を日本標準産業分類の業種別にみると、電気、ガス、水道業が1,387億円(前年度850億円)でその大部分を占め、このほかその他業種(核燃料製造業)が31億円(前年度23億円)となっている。
逆に設備投資の減少した業種としては化学工業、鉄鋼業、輸送用機械工業等がある。
(7)生産額は、45年度の228億円に比し46年度は323億円と41%増加している。この増加を生産分野別にみると主として原子炉機器関係によるものである。
これを、さらに品目別にみると原子炉冷却設備が大部分をしめている。
一方、業種別にみると、原子炉の冷却設備を生産している電気機械工業が131億円で前年度に比し77億円と大きく増加している。
しかしながら原子炉の本体の圧力容器を生産している輸送用機械工業部門は、73億円で前年度に比し50億円減少している。 |
§1原子力関係従事者
昭和46年度末における原子力関係従事者は、49,226人で前年度の41,906人に対し、17.5%増加している。
これを機関別にみると、民間企業(付属研究所および付属病院を含む)に従事するものが24,435人で全従事者の49.6%を占め、45、年度の全従業者数比率46.5%より増加している。
以下医療機関が10,427人で、全従事者の21.2%、研究機関が9,211人で18.7%、教育機関が4,763人で9.7%等となっている。 |
第2表 原子力関係従事者 |
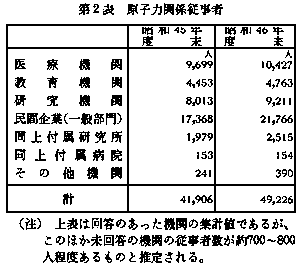 |
(注)上表は回答のあった機関の集計値であるが、このほか未回答の機関の従事者数が約700~800人程度あるものと推定される。
その内訳を機関別にみると、医療機関では、医師、歯科医師(大学付属病院では教官)が3,743人で医療機関全従事者の35.8%を占め、これにつづいて看護婦が3,365人で医療機関全従事者の32・3%となっている。
また教育機関では、研究者が3,771人で教育機関全従事者の79.2%を占め、研究機関では、研究者が3,862人で、研究機関全従事者の41.9%を占め、つづいてその他職員が1,992人で21.6%となっている。
民間企業では工員等が9,452人で民間企業全従事者の38.7%を占め、つづいて技術者が8,463人で34.6%、事務職員が2,690人で11%、研究者が1,848人で7.6%となっている。(第1図) |
第1図 機関別従事者の構成 |
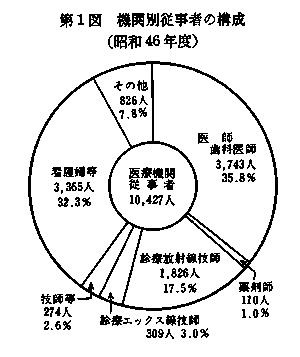 |
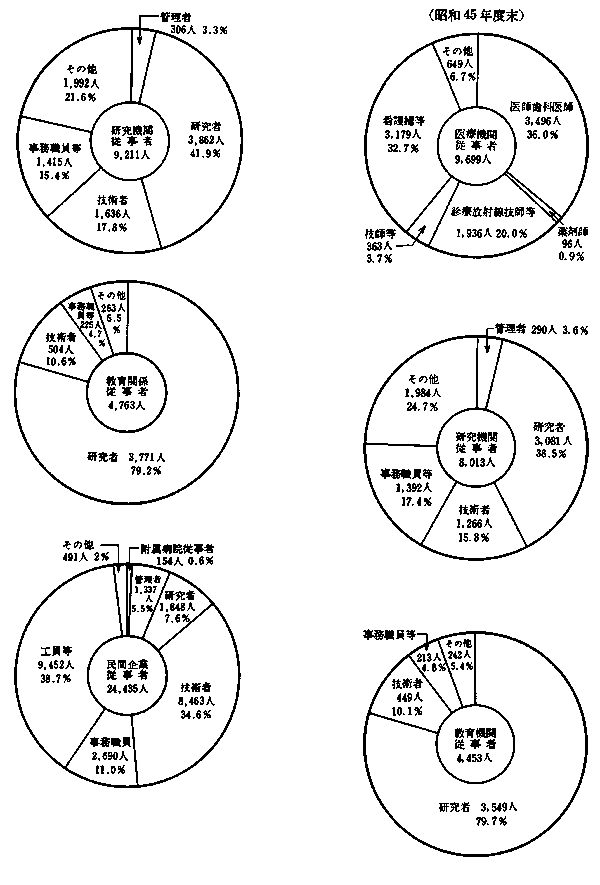 |
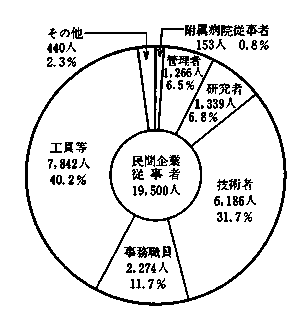 |
§2 放射線関係従事者
昭和46年度末における放射線関係従事者の数は38,233人で、前年の33,176人に対し15・2%と増加している。
つぎに同従事者の内訳をみると放射線施設管理区域常時立入者が19,596人、放射線施設管理区域随時立入者が18,637人となっている。
放射線関係従事者の機関別内訳は、民間企業が14,268人で全従事者の37.3%を占め、以下、医療機関が10,454人で27.3%、研究機関が7,296人で19.1%、教育機関が5,865人で15.2%等となっている。(第2図)
|
§3 研究者、技術者
原子力関係従事者49,226人のうち、研究者、技術者はそれぞれ9,502人、10,754人(合わせて20,256人)であった。
つぎに研究者の機関別内訳は、研究機関が3,862人で40.6%、教育機関が3,771人で全研究者の39・7%、民間企業が1,848人で19.5%等となっている。
このように、研究者の内訳をみると、研究者は教育機関と研究機関で全体の80.3%を占めており、この数字からも原子力関係の研究は、その主たる部分を国が負担していることが判る。
技術者の機関別内訳は、民間企業が8,463人で全技術者の78.7%(前年度77.7%)、ついで、研究機関が1,636人で15.2%となっている。(第3図)
第2表は、これら原子力関係の研究者、技術者、20,256人について、機関別に専門分野との関連をみたもので、原子力をエネルギー利用するための研究者、技術者は9,982人で全研究者および技術者数の49.3%、一方放射線を利用するための研究者、技術者は10,274人で50.7%を占めている。
放射線利用科学技術分野では、教育機関が3,572人で34.8%を占め以下、研究機関が3,358人で32.7%、民間企業が3,180人で31%の順になっている。
一方、原子力関連科学技術分野では、民間企業が5,031人で82.2%、以下研究機関が829人で13.5%、教育機関が258人で4.2%となっている。 |
第2図 機関別放射線関係従事者数(昭和45、46年度末)
第3図(a)機関別研究者数(昭和46年度末)
(b)機関別技術者数(昭和46年度末) |
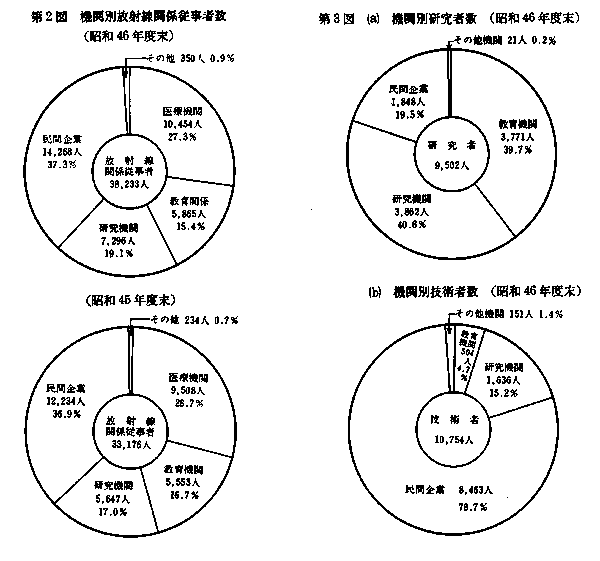 |
第2表 機関別、専門分野別研究者および技術者数 |
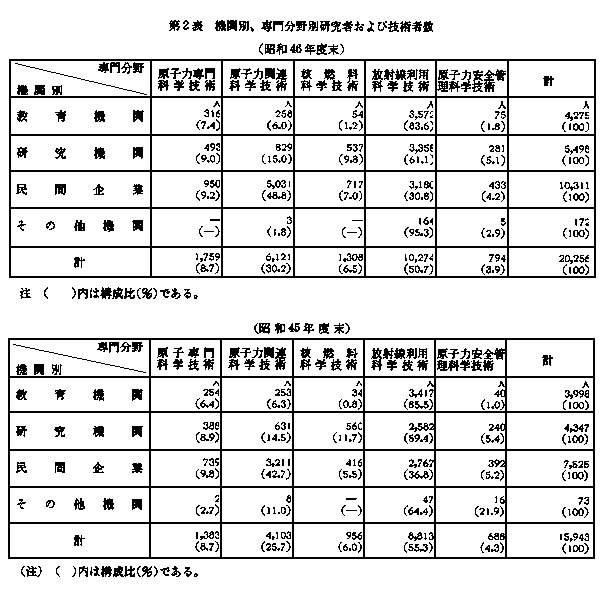 |
§4 研 修 派 遣
昭和46年度の研修派遣人員は2,700人で、前年度の2,505人に対し7.8%の増加であった。
これを研修期間別にみると、期間1ヵ年未満が2,553人で94.5%(前年度92.2%)、期間1ヵ年以上が147人で5.5%(前年度7.8%)となっている。 |
第4図 研修期間別、研修地別、研修派遣人員(昭和46年度) |
| 第4図 研修期間別、研修地別、研修派遣人員(昭和45年度) |
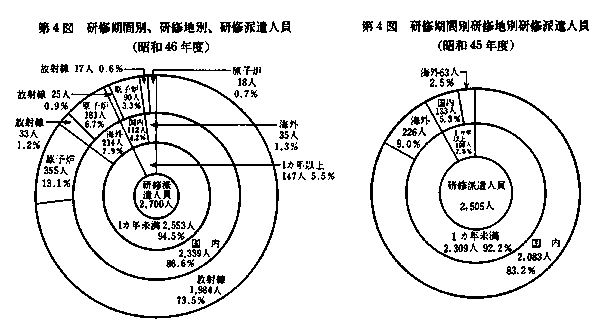 |
また、研修地別にみると、国内研修が2,451人で、90.8%、海外研修が294人で9.2%となっている。
また、研修内容別にみると、放射線研修は2,056人で76.1%、原子炉研修が644人で23.9%となっている。
このように研修に派遣する人員は、年々増加の一途を辿っているが、原子力開発利用の進展に伴ない、原子力関係従事者の需要が高まり外部への研修
派遣のみならず社内教育で不足を補なう傾向がある。また、研修内容についても従来の広く浅い教科内容から、より高度、より専門的なものに変りつつある。 |
§5 研究開発費
昭和46年度の研究開発費は総額で834億3,000万円で、前年度の547億4,900万円にくらべて52.4%の増加となっている。
これを機関別にみると、研究機関が625億円で全投資額の74.9%(前年度69.6%)を占めている。
この比率はわが国の研究開発費全体に占める研究機関の比率13%(昭和45年度)に比べると大きな差異があり原子力分野における研究開発活動の特徴が出ている。
このように研究機関の比率が高いのは、わが国が現在ナショナル・プロジェクトとして開発を進めている新型動力炉、原子力船「むつ」の開発を担当している動力炉・核燃料開発事業団、日本原子力船開発事業団、および原子力開発利用に必要な基礎、応用研究にたずさわる日本原子力研究所が含まれているためである。
以下、民間企業が161億2,500万円で19.3%、教育機関が32億3,100万円で3.8%、医療機関が14憶9,600万円で1.8%となっている。
また、研究開発費を研究性格別にみると、開発研究がもっとも増加が著しく、558億700万円で全研究開発費の66.9%(前年度60.0%)を占めている。
以下、応用研究が151億7,300万円で18.2%、基礎研究が124億5,000万円で、14.9%となっている。
なお、総理府統計局が毎年実施している科学技術研究調査によれば、わが国の研究調査費の基礎研究、応用研究および開発の比率(昭和45年度)はそれぞれ23.3%、27.6%し49.1%である。
一方、経営主体別の研究開発費をみると、国(国に準ずるものを含む。)の研究開発費が621億2,200万円で全研究開発費の74.5%、民間の研究開発費が186億9,600万円で22.4%、地方自治体が26億1,100万円で3.1%を占めている。 |
第3表 機関別、研究性格別研究開発費
|
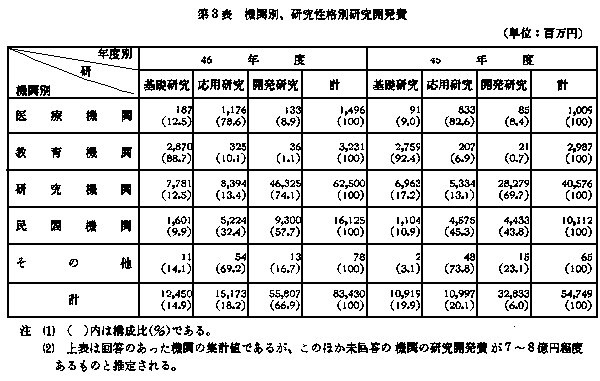 |
第5図 研究開発費の割合 |
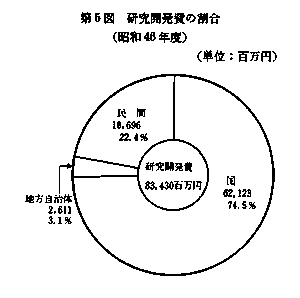 |
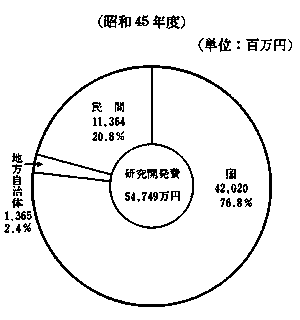 |
国と民間企業の研究開発費の負担比率も、わが国全体の研究開発費における比率が民間75%、対国25%(昭和45年度)とまったく反対の関係になっており先導的科学技術分野における国の役割が大きいことの例証の一つとなっている。
研究開発費を内容(科目)別にみると、人件費は193億5,200万円で全開発投資額の23.2%、設備等購入額は389億300万円で46.6%、その他経費は、251億7,400万円で30.2%となっている。
わが国全体の研究開発費についてその割合をみると、45年度では人件費43.6%、設備等購入額22.9%、その他33.5%となっている。(昭和45年度)
第4表は民間企業の研究開発費を業種別にみたもので、電気機械工業が62億7,100万円で民間企業の全研究開発投資額の38.9%を占め、つづいて化学工業が32億4,200万円で20.1%、その他製造業が29億1,900万円で18.1%となっている。 |
第4表 民間企業業種別研究開発費 |
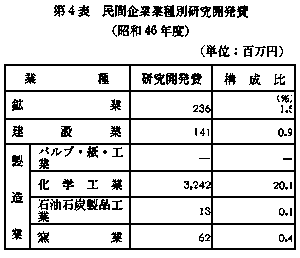 |
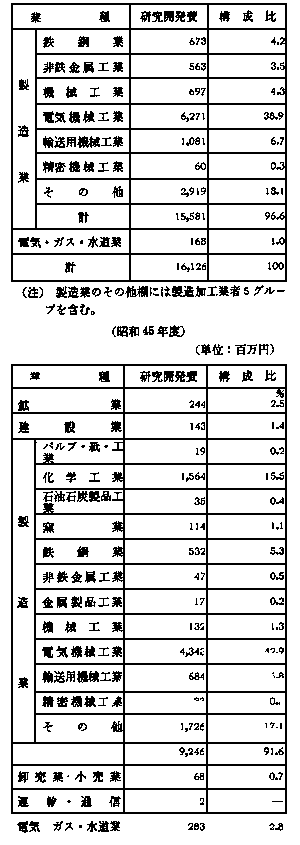 |
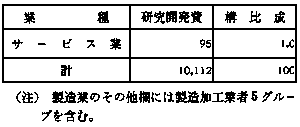 |
§6 設 備 投 資
昭和46年度の設備投資額は1,599億7,300万円(うち外資252億1,000万円)昭和45年度の設備投資額は997億5,200万円(うち外資190億180万円)であったが、前年度に比べて56.4%増加し急速に伸びている。
これを機関別にみると、民間企業が1,464億8,300万円(うち外資252億1,000万円)で全投資額の93.9%を占めているが、この増加は電力会社が建設中の原子力発電所によるものが殆んどである。 |
第6図 機関別設備投資額
|
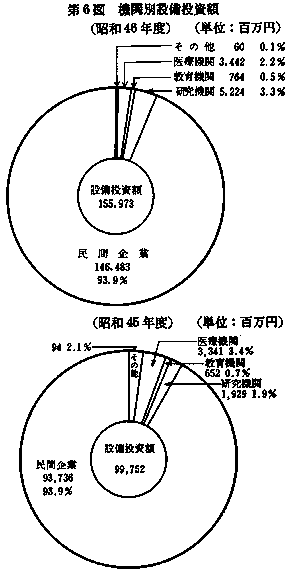 |
以下医療機関が34億4,200万円で2.2%、研究機関が52億2,400万円で3.3%、教育機関が7億6,400万円で0.5%となっている。
一方、投資額を投資対象別にみると、原子炉、核燃料関係が1,482億6,400万円で全役資額の95.1%を占めている。このうち、原子力発電所に1,378億3,000万円で、原子炉、核燃料関係投資額の93%、再処理施設42億6,100万円で2.9%、加工施設に31億3,500万円で2.1%、原子炉製造施設に19億7,400万円で1.3%、原子力船関係に9億6,200万円で0.6%となっている。
また、放射線利用関係の投資額は77億1,000万円で、全投資額の4.9%(前年度6.0%)を占め、このうち、放射線利用機械器具等は48億6,600万円で、放射線利用関係投資額の63.1%(前年度62.6%)建物構築物に22億4,900万円で29.2%(前年度28.2%)が投資されている。(第5表) |
第5表 原子炉核燃料関係および放射線利用関係施設別投資額 |
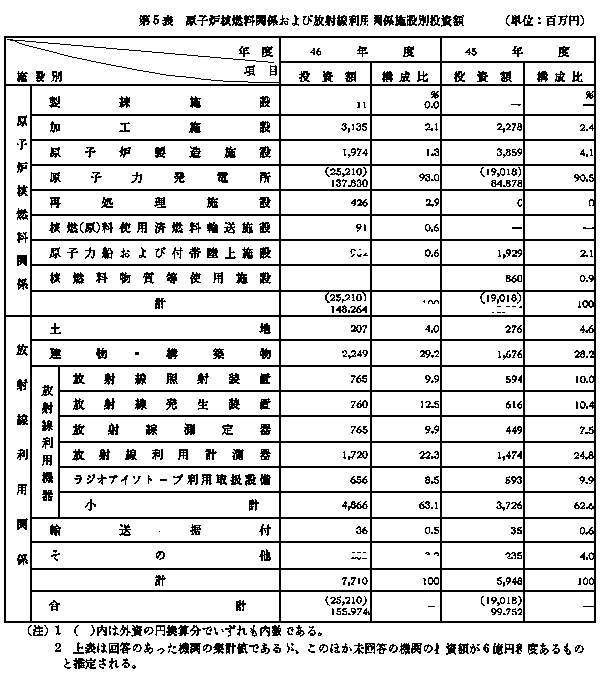 |
第6表 民間企業施設別業種別設備投資額 |
| (昭和46年度) |
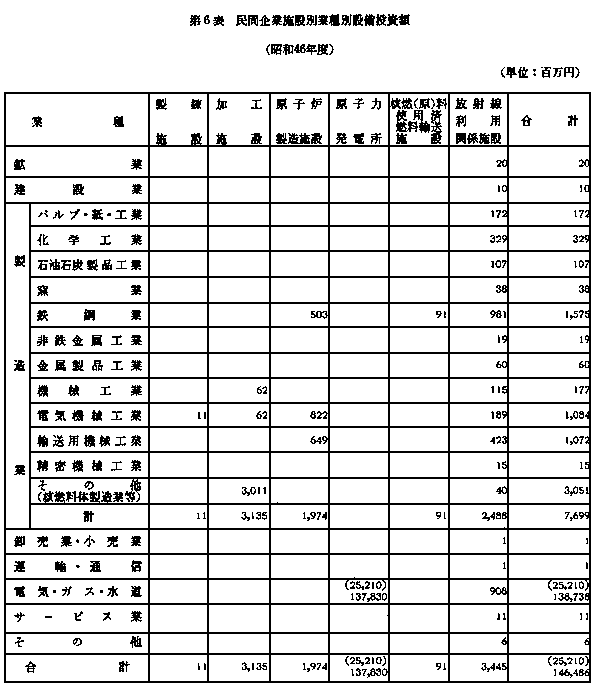 |
民間企業施設別業種別設備投資額
(昭和45年度) |
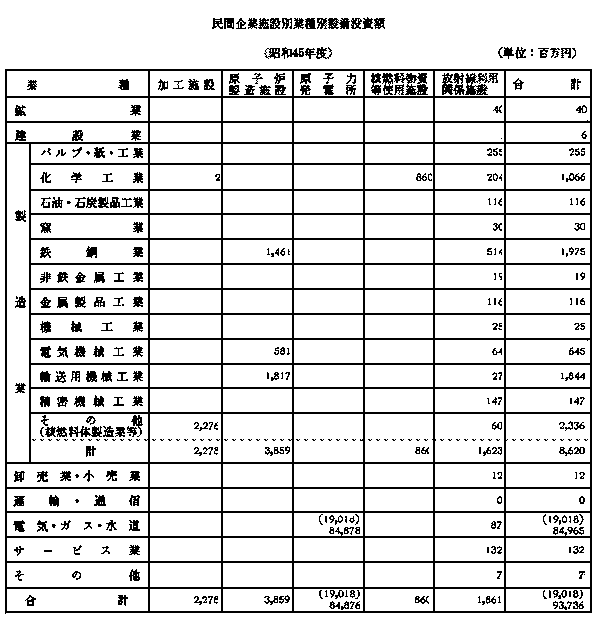 |
第6表は民間企業の業種別の投資額を見たもので原子力エネルギー利用関係の投資額1,430億4,100万円のうち、電気事業者による原子力発電所への投資額1,378億3,000万円(前年度848億7,800万円)、核燃料体製造等30億1,100万円、鉄鋼業5億9,400万円、輸送用機械工業が6億4,900万円となっている。
放射線利用関係の投資額は、34億4,500万円で、このうち、鉄鋼業が9億8,100万円、輸送用機械工業4億2,300万円、化学工業が3億2,900万円、パルプ・紙工業が1億7,200万円となっている。 |
§7 生産等実績
昭和46年度における原子力関係の生産額は、322億1,200万円で、前年度227億8,000万円に対して41.4%と増加している。これを品目別にみると、原子炉機器が233億4,900万円で全生産額の72.5%を占め、以下、放射線利用機器が62億2,700万円で19.3%、核燃料関係が26億3,600万円で8.2%となっている。 |
第7表 品目別生産実績
(昭和46年度) |
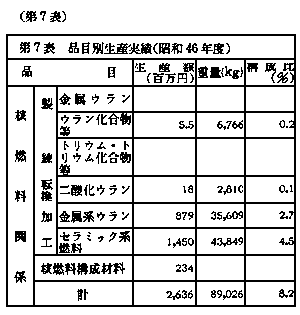 |
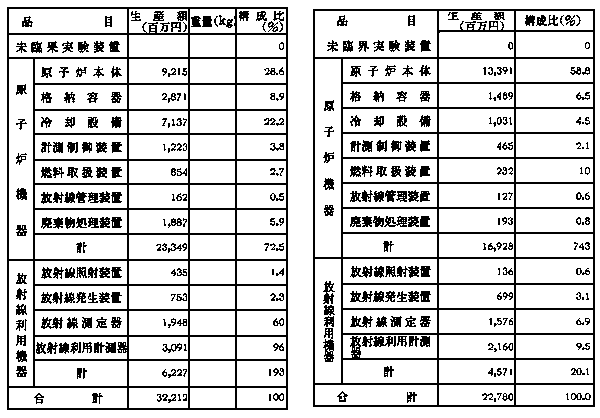 |
品目別生産実績
(昭和45年度) |
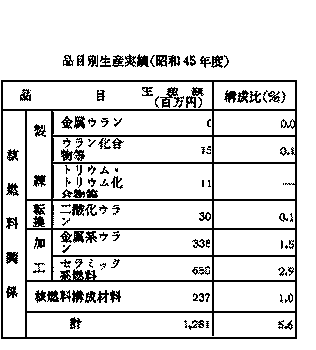 |
第8図は民間企業の生産額322億円を業種別にみたもので、電気機械工業が130億1,500万円で総生産額の40.4%を占め、以下輸送用機械工業が73億200万円で22.7%、機械工業が43億5,300万円で13・5%、鉄鋼業34億500万円で10.6%、精密機械工業16億9,500万円で5.3%となっている。 |
第7図 民間企業における業種別生産額 |
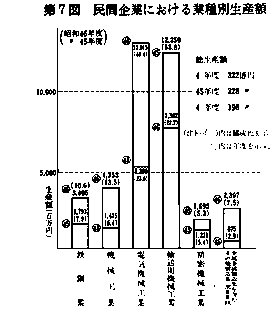 |
<参 考 資 料> |
| -過去 5 年 間 の 推 移- |
1 設備投資総額
1-(1)原子炉核燃料関係施設投資額
1-(2)放射線利用関係設備投資額
1-(3)民間企業設備投資額における国内資および外資の内訳 |
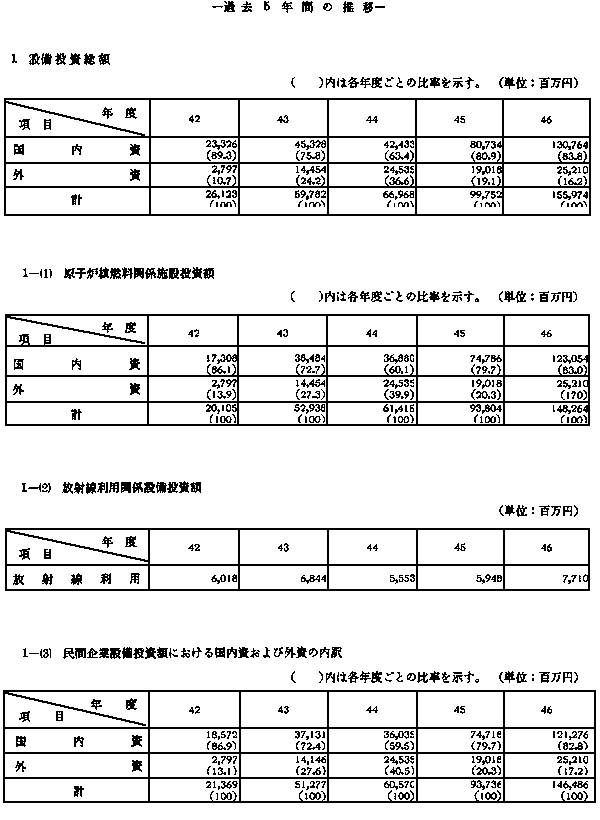 |
1- (4)民間企業施設別業種別設備投資額
1-(5)原子炉核燃料関係施設別投資額
1- (6)放射線利用関係設備投資額 |
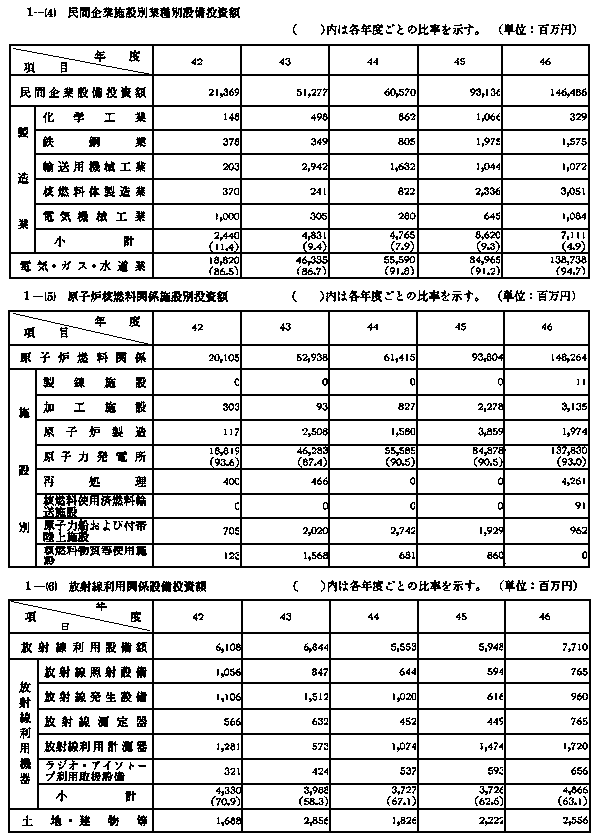 |
1-(7)電力会社における設備投資額
2 生 産 実 績 |
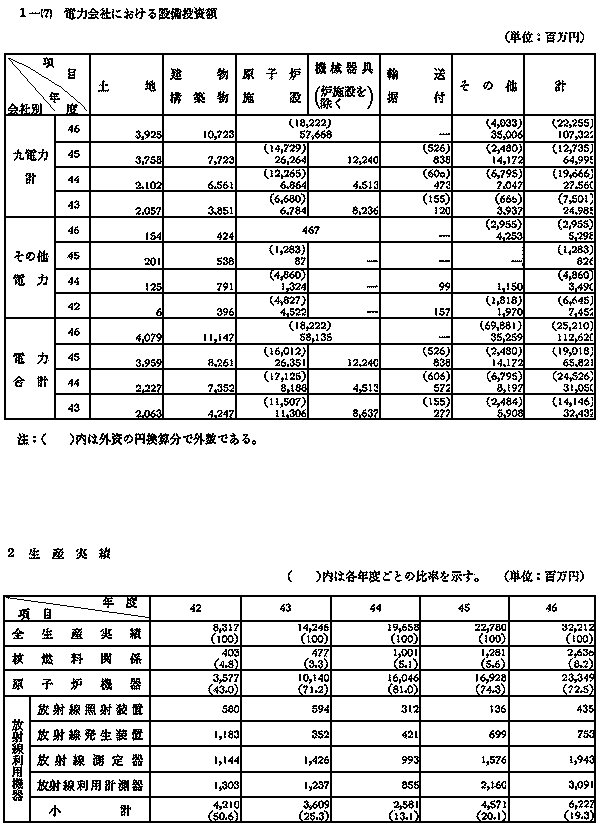 |
2-(1)民間企業における業種別生産額
3 研究開発費
4 原子力関係従事者 |
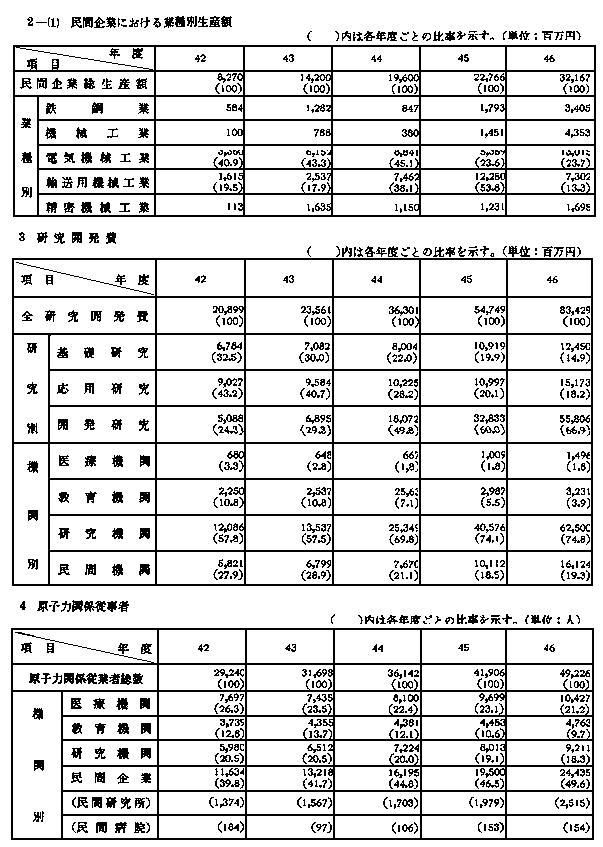 |
4 原子力関係従事者(続き)
4-(1)原子力関係における民間企業業種別従事者 |
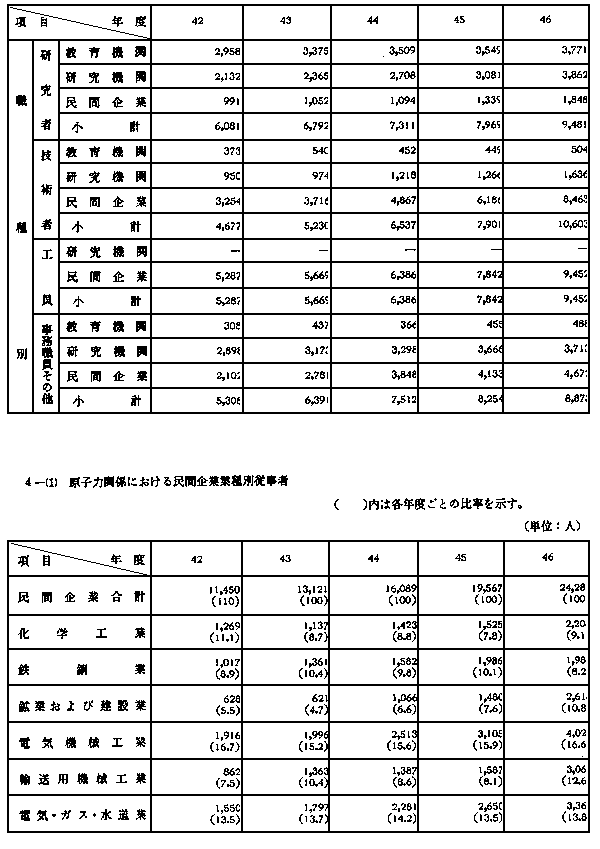 |
5 研究者・技術者の専門分野
5-(1)機 関 別
(イ) 研 究 者
(ロ)技 術 者
5-(2)専門分野別 |
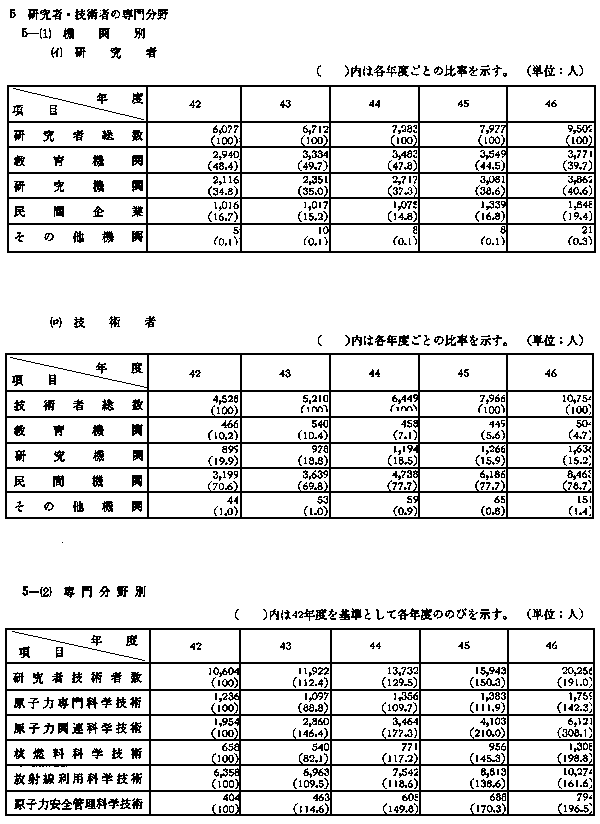 |
6 放射線関係従事者
7 研 修 派 遣 |
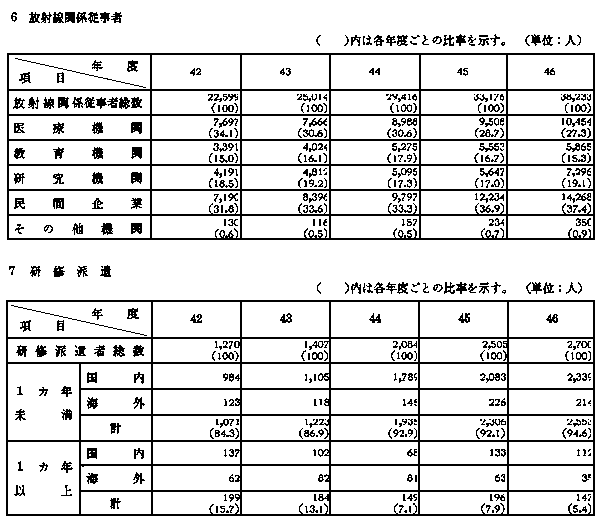 |
|