昭和47年7月19日
原子炉安全審査会 |
| 原子力委員会 |
| 委員長 中曾根康弘 殿 |
原子炉安全専門審査会 |
| 会長 内 田 秀 雄 |
動力炉・核燃料開発事業団大洗工学センターの原子炉の設置変更(重水臨界実験装置施設の変更)に係る安全性について
当審査会は昭和47年6月15日付け47原委第220号(昭和47年7月18日付け47原委第282号で一部訂正)をもって審査を求められた標記の件について結論を得たので報告します。 |
Ⅰ審 査 結 果 |
動力炉・核燃料開発事業団大洗工学センターの原子炉の設置変更(重水臨界実験装置施設の変更)に係る安全性に関し、同事業団が提出した「原子炉(臨界実験装置)設置変更許可申請書」(昭和47年6月6日付け申請および昭和47年7月18日付け一部訂正)に基づき審査した結果、本原子炉の設置変更に係る安全性は十分確保しうるものと認める。 |
Ⅱ変 更 内 容 |
1.プルトニウム富化燃料の追加使用 |
現在使用中の二酸化ウラン燃料体、ウラン・アルミニウム合金燃料体、0.54W/O富化プルトニウム・ウラン混合酸化物燃料体に加え、0.87W/O富化プルトニウム・ウラン混合酸化物燃料体(約92%Pu fissile、約75%Pu fissileの2種類以下0.87W/O
PuO2-UO2燃料という)を約50体製作し、臨界実験を行う。 |
2.昇温実験装置の使用 |
燃料の温度係数を測定するため炉心中央の1チャンネルをヘリウムにより約600℃まで昇温実験装置を設ける。また、昇温実験用燃料体を数体製作する。 |
Ⅲ審 査 内 容 |
1.安全設計および安全対策 |
本変更に係る原子炉施設は、次のような安全設計および安全対策が講じられることになっており、十分な安全性を有するものであると認める。 |
(1)炉 心 構 成 |
本変更により0.87W/O PuO2-UO2燃料が従来の燃料といっしょに使用され、また、炉心中央に昇温実験装置の炉内試験部が挿入される。しかし、格子間隔、制御装置等既設の施設の変更はない。 |
(2)燃 料 |
0.87W/O PuO2-UO2燃料は、約92%Pu fissileのもの27体約75%Pu fissileのもの27体使用される。これらの燃料は使用中である0.54W/O PuO2-UO2(約92%Pu fissile)と同構造で、被覆管端栓部を溶接密封構造とする等プルトニウムの漏減が生ずる可能性がないように設計製作、検査等配慮することになっている。
また、昇温実験用燃料は、劣化ウラン燃料を除き手持ちの燃料と同種である。ただし、被覆材およびタイプレート、スペーサ等の部材はSUS 304を用いている。
本燃料は臨界実験装置の出力が低いため発熱は無視できる程度であり、また、Heガスの運転温度が約600℃であるのでペレット、被覆管の破損はないと思われる。
しかし、熱サイクルをかけたときのペレットと被覆管のかじりを防止するためペレットの面取りを行なったり、運転後のHeのαモニタリングや運転前後の被覆管の外観表面検査等を実施して、健全性を確保することにしている。 |
(3)昇温実験装置 |
本装置は炉内試験部内最高温度約600℃、Heガス圧約5Kg/cm2・g最大ガス流量約120Kg/hrの使用条件を満たす開回路で、Heガス圧縮装置、加熱装置、炉内試験部等からなる主循環系とHeガス供給系、計測制御系等からなる。
これら機器、配管の設計、製作、検査にあたっては温度変化や耐震を考慮し、細心の注意を払うことになっている一方、これまでに使用実績を有する十分信頼性のあるものを採用することにしている。
また、運転時の安全を確保するため安全保護装置を設けている。
インターロック回路としてHeガス加熱装置、重水給水ポンプ等に起動インターロックが設けられており、特に本実験装置は原子炉出力が数W以上であるときのみ運転ができ、かつ、実験中は原子炉水位上昇ができないようなインターロックになっている。
さらにHeガス加熱装置出口温度が規定値以上になったとき、および、炉内試験部入口圧力が規定値以上となったときは臨界実験装置はスクラムするようになっている。
なお、本装置で使用されたHeは、サンプリング測定した後専用のフィルターを通した後炉室内排気系に導かれる。本排気系では連続のαモニタリングを行なうことになっている。 |
(4)核 特 性 |
0.87W/O PuO2-UO2燃料を使用することに伴ない、燃料装荷方法、格子ピッチ、冷却材ボイド率、減速材中のボロン濃度等のパラメータを変えた各種炉心を計算し実験可能な炉心パターンをきめている。それら炉心パターンにおける、ドップラ係数および冷却材温度係数は正にならない。 |
(5)燃 料 管 理 |
変更により多種類のPuO2-UO2燃料および昇温実験用燃料ができるか、燃料棒の刻印、燃料集合体の色分け、燃料懸架台の色分け等により誤装荷が生じないよう注意することになっている。 |
2 平常時の被ばく評価 |
本変更後も年間積算出力は最大50Kw/hrと変らないので、敷地外の一般公衆の受ける被ばく線量は変らない。
また、従事者の被ばくについては十分な放射線管理を行なうことになっており、変更することにより被ばく線量が特に多くなるには認められない。 |
3 事 故 評 価 |
本変更に係る原子炉について各種事故を検討した結果、それぞれ適切な対策が論じられており、本原子炉は変更後も十分安全性を確保しうるものと認められる。
さらに最大想定事故として起動時における重水水位の異常上昇事故を想定して解析した結果燃料の温度上昇は約415℃となり燃料の溶融、被覆管の破損には至らない、放出エネルギーについては483MW・Secであり、変更前の0.87W/O PuO2-UO2燃料を使用しない炉心の563MW・Secに比べ小さい。
従って、変更後の放射線被ばく線量は変更前の制御室、0.4rem、炉室外の最大地点0.87rem、敷地外の最大となる敷地境界(原子炉から約180m)0.036remを上まわらない。
また、昇温実験における最大想定事故として制御棒引抜き事故を想定して解析した結果、放出エネルギーは約175MW・Sec、燃料温度上昇は約170℃である。)この放出エネルギーは563MW・Secに比較して小さいので、放射線被ばく線量は問題にならなく、燃料温度上昇は、昇温実験用燃料が600℃であったとしても、燃料の溶融、被覆管の破損には至らない。
以上から原子炉立地審査指針で規定するためやす線遠と比較して十分小さく、敷地外の一般公衆に対して安全であると認められる。 |
Ⅳ 審 査 経 過 |
本審査会は、昭和47年6月16日第102回審査会において次の委員からなる第90部会を設置した。 |
審査委員 西脇一郎(部会長)宇都宮大学 |
| |
弘田実弥 |
日本原子力研究所 |
|
|
調査委員 |
森島淳好 |
日本原子力研究所 |
|
審査会および部会において審査を行ってきたが、昭和47年7月15日の部会報告書を決定し、同年7月19日の第103回審査会において本報告書を決定した。 |
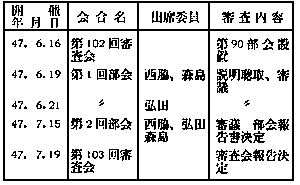 |