|
46原委第176号
昭和46年5月27日
内閣総理大臣 殿
原子力委員会委員長
日本原子力研究所東海研究所の原子炉の設置変更
(軽水臨界実験装置施設の変更)について(答申)
昭和46年3月11日付け46原第1698号(昭和46年5月24日付け46原第4131号で一部訂正)で諮問のあった標記の件について、下記のとおり答申する。
記
標記に係る許可の申請は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第24条第1項各号に掲げる許可の基準に、適合しているものと認める。
なお、本設置変更に係る安全性に関する原子炉安全専門審査会の報告は別添のとおりである。
日本原子力研究所東海研究所原子炉施設
(軽水臨界実験装置)の設置変更に係る安全性について
昭和46年5月25日
原子炉安全専門審査会
原子力委員会
委員長 西田 信一 殿
原子炉安全専門審査会
会長 内田 秀雄
日本原子力研究所東海研究所原子炉施設
(軽水臨界実験装置)の設置変更に係る安全性について
当審査会は、昭和46年3月11日付け46原委第72号(昭和46年5月24日付け46原委第173号をもって一部訂正)をもって審査の結果を求められた標記の件について結論を得たので報告します。
Ⅰ 審査結果
日本原子力研究所東海研究所原子炉施設(軽水臨界実験装置)の変更に係る安全性に関し、同研究所が提出した「東海研究所原子炉設置変更許可申請書」(昭和46年3月6日付け申請及び昭和46年5月22日付け一部訂正)に基づき審査した結果、本原子炉施設の変更に係る安全性は十分確保し得るものと認める。
Ⅱ 変更内容
1 本体装置用燃料として2.7w/o富化プルトニウム、天然ウラン混合酸化物燃料(ペレット直径約10.7mm、燃料有効部最大長さ約706mm、最大装荷本数600本)を追加し、本体系による炉心構成の場合の減速材対燃料体積比の範囲を1.5から5.5までとする。(従来1.5から3.0まで)
2 実験用燃料要素として次のものを追加する。挿入本数は次のいずれかの1本とする。
(1)二酸化ウランペレット、燃料要素(ウラン濃縮度約10w/o、ペレット直径約10.7mm、燃料有効部最大長さ約1,470mm)
(2)高速炉用ウラン・プルトニウム混合酸化物燃料要素(ペレット直経約5.5mm、燃料有効部最大長さ約780mm、核分裂性核種最大含有率7.3g/cm3、核分裂性核種最大装荷量140g/要素)
(3)新型転換炉用ウラン・プルトニウム混合酸化物燃料要素(ペレット直経約15mm、燃料有効部最大長さ約1000mm、核分裂性核種最大含有率0.11g/cm3核分裂性核種最大装荷量20g/要素)
Ⅲ 審査内容
1.安全設計および安全対策
本変更に係る原子炉施設は、次のような安全設計および安全対策が講じられることになっており、十分な安全性を有するものであると認める。
(1)炉心構成
炉心は、燃料要素、燃料支持板、格子板、格子板支持枠、制御安全要素等により構成され、本変更によって積荷する燃料および格子間隔の異なる格子板が用いられる以外は、全て既設の施設を変更することなく使用される。
(2)燃料
本変更に係る燃料要素は、いずれも動力炉級仕様のジルカローイ2およびSUS32ステンレス鋼の被覆管に燃料ペレットを入れ、困端を溶接によって、密封し、内圧、外圧に対して気密にすることとしている。特にプルトニウム富化燃料要素の製作に当っては、プルトニウムの漏洩の生じる可能性がないように、設計・製作・検査等を行なうこととしている。
(3)燃料の管理および取扱い
本変更に係る燃料要素には、他の燃料要素とともに刻印、色別等が施され、種類の異なる燃料を混用しても判別、管理が十分行なわれることになってる。プルトニウム富化燃料要素の取扱いについて、使用の前後にαサーベイを行ない、α放射能の漏洩がないことを確認することとしている。また、燃料要素は、取り扱い中に取り落すことはないと考えられるが、万一取り落した場合にも安全上十分な対策がなされることになっている。
(4)核特性
本変更によって生ずる新たな炉心は、2.7w/o富化プルトニウム・ウラン燃料のみの炉心、2.7w/o富化プルトニウム・ウラン燃料と従来の本体装置用燃料との二領域炉心および2.7w/o富化プルトニウム・ウラン燃料と実験用燃料との二領域炉心があるが、炉心構成の場合に従来の核・熱的制限値を変えることなく構成することになっている。いずれの炉心の場合にも燃料温度係数、減速材温度係数および減速材ボイド係数は、負の反応度係数となり、反応度事故に対して自己制御性が高い。
なお、本変更に係る実験用燃料は、一回炉の心構成に1本挿入して実験を行なうことになっているので、漏洩用燃料が炉心全体の核特性に影響を与えることは殆んどない。
2.平常時の被ばく評価
前項で述べたとおり本変更に係る燃料要素は、厳格な品質管理のもとに製作されるので、漏洩に伴なう内部被ばくの生ずるおそれはないと考えられる。また、原子炉の運転中および燃料取扱いに伴う外部被ばく線量は、従来と同程度である。したがって、一般公衆および従事者の受ける被ばく線量は、許容値を十分下まわるものと認められる。
3.事故評価
本変更に関しては燃料要素および格子間隔以外はとくに施設に変更はなく、また炉の操作方法にも変更はない。本変更に係る原子炉について各種事故の検討をした結果、運転特性、安全保護系などに関連する事故に対して安全性は確保し得ると認める。
最大想定事故としては、反応度係数が最も不安全側となる減速材対燃料体積比5.5の場合の2.7w/o富化プルトニウム・ウラン燃料600本表荷の炉心について、従来と同様、炉心タンク水位上昇に伴う反応度事故を想定した。その結果、放出エネルギー約161MW・Sec、燃料温度上昇は最高約850℃となるが、燃料被覆の破損には至らない。
また、この事故時において被ばく線量が最大となるのは、従来と同様炉室建屋付近であって、その値は約1.8remである。
なお、本変更に係る実験燃料を、通常装荷する炉心に挿入した場合の最大想定事故についても検討を行なったが、燃料被覆の破損には至らない。
したがって、変更に係る本原子炉施設は、敷地外の一般公衆に対して安全であると認められる。
Ⅳ 審査経過
本審査会は、昭和46年3月17日第89回審査会において次の委員よりなる第77部会を設置した。
| 審査委員 |
三島 良績(部会長) |
東京大学 |
|
吹田 徳雄 |
大阪大学 |
|
都甲 泰正 |
東京大学 |
|
渡辺 博信 |
放射線医学総合研究所 |
| 調査委員 |
海老塚佳衛 |
東京工業大学 |
以後部会および審査会において、審査を行なってきたが、昭和46年5月17日の部会において部会報告書を決定し、同年5月25日の第91回原子炉安全専門審査会において本報告書を決定した。
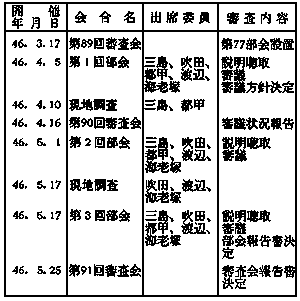
|