|
44.8.21
わが国の原子力開発利用が原子力委員会を中心とする体制のもとに推進されはじめてから、すでに10年余を経過した。
この間、原子力開発利用はかなりの進展をみ、最近では動力炉開発のごとき大型プロジェクトの遂行、特定総合研究の実施、原子力発電所の建設等開発利用は本格化しつつある。
これらの情勢に対処し、原子力の開発利用をなお一層強力に推進するため、原子力関係機関の体制に検討を加える必要があるものとしていたところ、国会においても昭和42年7月、同趣旨の付帯決議が行なわれたので、その意をも体し、昭和43年3月、原子力委員会は当懇談会の設置を決定し、原子力委員会のあり方、原子力研究開発機関のあり方およびこれらに関連する事項について、検討を行なってきた。
当懇談会は、別紙に示すような構成員によって、約1年5ケ月にわたり慎重な審議を重ね、概ね下記のような結論を得た。
記
1.基本的な考え方
わが国の原子力関係機関の体制を審議するに当っての基本的な考え方は次の通りである。
第一に、わが国における原子力の研究、開発および利用は、原子力の平和利用による産業基盤の強化と科学技術の振興を目的として、これを推進すべきである。
第二に、原子力の平和利用は現在のわが国の経済体制のもとに、原則として国と民間が協力して推進すべきものであり、それぞれの限られた資金と人材を、できる限り集中して効率的に活用する必要がある。
2.原子力委員会
原子力委員会の性格は現状通りとし、その課された任務を一層十分に遂行するため、次の通り機構上の改善を図るべきである。
(1) 原子力委員会に委員会の調査事務に専従する調査資料室を設けること。また、原子力委員会の事務のとりまとめ等に専任する者(例えば参事官)をおくこと。
調査資料室においては、原子力委員会の企画機能を強化するため、内外の諸事情の調査・分析および原子力委員会に対する適切な情報の提供等を行なう。
なお、調査資料室および専任者は、機構上は科学技術庁原子力局におくこととし、調査資料室員は、民間をはじめ関係省庁、特殊法人からも有能な人材の起用を図るものとする。
(2) 原子力に関する主要な分野に、常設の部会を設置して、主として、原子力委員のブレーン的役割を果たさせること。
なお、この部会のメンバーは、参与および専門委員の中から選任する。
(3) 原子炉安全専門審査会に調査委員をおくこと。
調査委員は、原子炉の安全に関する申請を効率的に処理できるよう審査委員を補佐するものとする。
なお、原子力委員会を国家行政組織法上の3条機関(行政委員会)とする案については、現状の方が平和原則の確保と平和利用に関する重要政策の樹立に、より適していると考え、これを採用しないこととした。
3.原子力研究開発機関
日本原子力研究所、動力炉・核燃料開発事業団および日本原子力船開発事業団の3法人による現在の研究開発体制は前述の基本的な考え方に立却して、今後も維持してゆくべきである。しかし、3法人の業務実施上の相互関係および科学技術庁との関係については、さらに、検討のうえ、運用の適切化を図るとともに、3法人と原子力委員会との接触を密にすること等により、各機関の使命を達成できるよう措置すべきである。
なお、3法人を合併し、恒久的な研究開発公社を設立する案は、現時点におけるわが国の原子力開発の段階や、経営管理の難かしさ、民間企業との協力の必要性あるいは英国の原子力開発体制の再編成が必要とされた事情等にかんがみ、これを採用しないこととした。
4. 次の各事項については、さらに検討をすすめる必要がある。
(1) 原子力に関する基礎研究に関し、大学および日本原子力研究所の協力関係
(2) 放射線安全管理のための機構の整備およびこれに伴う関係行政機関の協力関係
(3) 新しいプロジェクトの遂行等に伴う総合研究開発機構のあり方
(4) 動力炉開発等の大型プロジェクトの遂行に要する資金の数年度にわたる予算措置
原子力関係機関体制問題懇談会構成員
| (座長) |
有沢 広己 |
(原子力委員会委員長代理) |
| (委員) |
赤堀 四郎 |
(理化学研究所理事長) |
|
芦原 義重 |
(関西電力(株)社長) |
|
安西 正夫 |
(昭和電工(株)社長) |
|
岩武 照彦 |
((株)神戸製鋼所常務) |
|
大来 佐武郎 |
(日本経済研究センター理事長) |
|
金沢 良雄 |
(東京大学教授) |
|
兼重 寛九郎 |
(科学技術会議議員) |
|
菊池 正士 |
(東京理科大学学長) |
|
河野 文彦 |
(三菱重工業(株)会長) |
|
駒井 健一郎 |
((株)日立製作所社長) |
|
荘村 義雄 |
(電気事業連合会副会長) |
|
田中 慎次郎 |
(評論家) |
|
西村 熊雄1) |
(前原子力委員会委員) |
|
丹羽 周夫2) |
(前日本原子力研究所理事長) |
|
平田 敬一郎 |
(前日本開発銀行総裁) |
|
藤波 収 |
(電源開発(株)総裁) |
|
伏見 康治 |
(名古屋大学教授プラズマ研究所長) |
|
松根 宗一 |
(日本原子力産業会議副会長) |
|
向坊 隆 |
(東京大学教授) |
| (特別委員) |
岡 良一 |
(前衆議院議員) |
|
前田 正男 |
(前衆議院議員) |
| (オブザーバー) |
井上 五郎 |
(動力炉・核燃料開発事業団理事長) |
|
佐々木 周一3) |
(日本原子力船開発事業団理事長) |
|
宗像 英二4) |
(日本原子力研究所理事長) |
|
御園生 圭輔 |
(放射線医学総合研究所所長) |
注
1)第3回より参加
2)第4回より参加
3)第3回までは石川一郎(前日本原子力船開発事業団理事長)
4)第3回までは丹羽周夫(前日本原子力研究所理事長)
審議経過
1.概要
当懇談会は、昭和43年3月原子力委員会においてその設置を決定し、ただちに第1回の会合を開いた。
第1回は懇談会の趣旨説明と今後の進め方について打合せを行ない、第2回から審議を開始した。まず、海外の原子力関係機関の組織について、概要調査を行ない、そのうち、英国および米国の組織とその実情については詳細な検討を行なった。それから、わが国の現体制の分析に移り、国会の論議、諸委員会の勧告、各種論文等により、客観的な問題点の摘出に努めた。これらの検討に4回(第2回〜第5回)をあてた。
次いで、第6回から、そこで把握された問題点に立脚して個別機関の検討に入り、まず原子力委員会の業務と機構をとりあげ、第7回には、日本原子力研究所等原子力関係の4研究開発機関(日本原子力研究所、動力炉・核燃料開発事業団、日本原子力船開発事業団、放射線医学総合研究所)の現状について各機関の首脳者から説明をきき、意見交換を行なった。
そのあとで、海外の原子力開発体制のシミュレーションチャートを中心に審議した。これらの審議に4回(第6回〜第9回)をあてた。第10回からは具体的な体制試案の作成に入り、三つの試案がまとめられ、それらを中心に相互比較や修正が行なわれた。
そして5回(第10回〜第14回)の審議を経て、報告書(案)の討議に移り、本報告書がとりまとめられたものである。
2.開催日付および議題
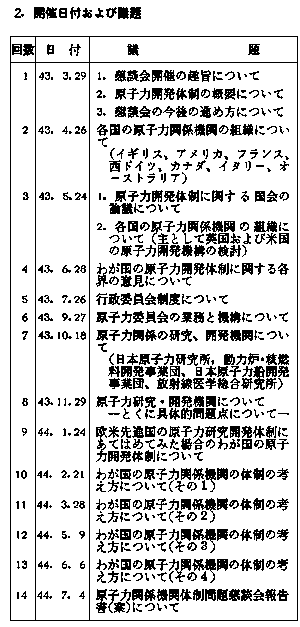
|