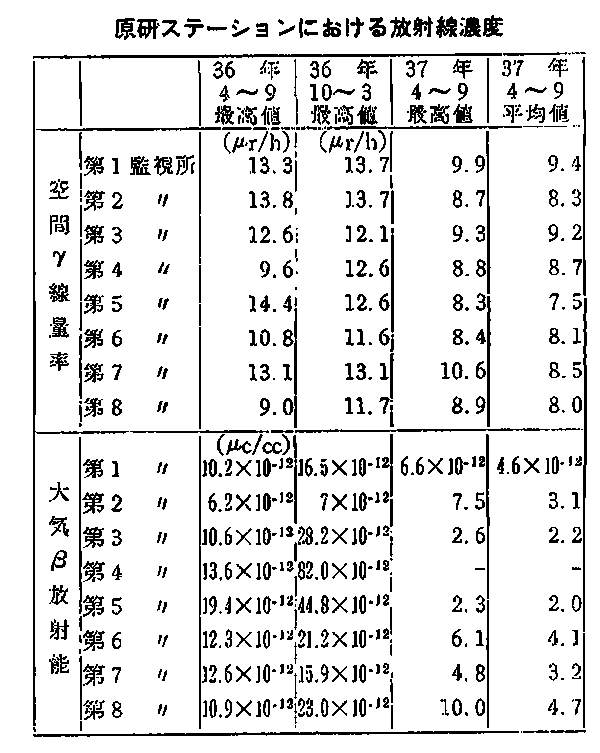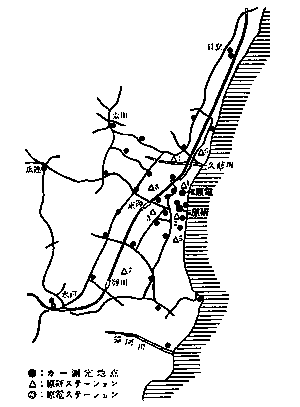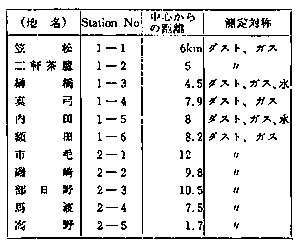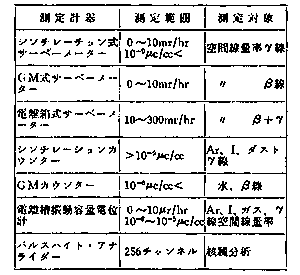|
モニタリングカー(放射線監視車)の概要および連行計画 1. はじめに 昭和37年歳出予算に計上されたモニタリングカーは11月中旬に車体および計器類の積込みを終了し、12月3日から水戸市の原子力館に常駐し、東海地区の放射線観測業務に従事することになった。 車体はピンク色に緑色のツートンで、屋根には赤いスカイベーン風向風速計が取付けられている。車自体が動く実験室としての機能を有し、内部で試料の調整から測定まで全部できるようになっている。すなわち自家発電機を備え、これを電源とし、また、清水、汚水タンクを取り付け都市水道と同様に水が使えるようになっている。 2. 目的 現在東海地区に設置されている原子炉はすでに運転中のものとしては日本原子力研究所のJRR-1、JRR-2JRR-3と半均質型、水均質型、BW型の各臨界装置があり、近く運転に入るものでは日本原子力研究所の動力試験炉、JRR-4および日本原子力発電(株)のコルダーホール発電炉ならびに三菱電機の研究炉等がある。 このように東海地区に集中している原子炉から放出されるガス、ダスト、排水および空間線量率をモニターするためにはすでに原研の8無人ステーションがあるが、これとは別に第三者としての国が直接監視するものである。 これは、常時放射能の分布、線量を調査し、その地区内に放射能の汚染による危険がないことを常に住民に知らせ安心感を与えると共に、事故時に必要な対策に関する資料を得ることを目的としているのである。 3.東海地区におけるモニターの現状 現在東海地区には、日本原子力研究所の8無人ステーションがあり、また、計画中のものとしては日本原子力発電(株)の3ステーションがある。 原研モニターステーションにおける昭和36年4月から37年9月までのβ、γ線量率、放射能の最高値と平均値を参考までに示す。これは自然計数率からあまり出るものではないことを示している。 また昭和35年度に東海地区の放射能調査に関する各機関の協力態勢を密にするためと放射線の管理を統一的にするために東海村放射線監理連絡会の中に小委員会をもうけた。この小委員会が36年度に実施した結果 原研ステーションにおける放射線濃度 は資料「東海村およびその近郊の放射能調査」『日本原子力研究所』(1962年6月26日発行)に詳しく述べられている。 この調査によると、各機関の試料採取、測定法はほぼ統一されており、放射能濃度に関しても核実験の影響が現われただけで、原子力施設からの影響と思われるものはなかったと述べている。 東海村放射線管理連絡会参加メンバー 茨城県原子力事務局 茨城県衛生研究所 茨城県環境衛生課 水戸地方気象台 電気通信研究所茨城支所 原子燃料公社 日本原子力発電株式会社 日本原子力研究所 科学技術庁原子力局原子炉規制課 4.測定地点の選定 移動可能という利点を利用して固定ステーションでは不可能な地点、測定項目について測定できるという利点を利用し、次の点を考慮して選定を行なった。 (1)日本原子力発電(株)の発電炉を中心に半径10kmの線を引き、この円を60°ごとに等分し、一つの区分の中に少なくとも2観測地点が含まれること (2)サンプリングに便利なこと (3)低 地 (4)台 地 (5)山 沿 い (6)原研ステーションと重複しないこと (7)県民に大きな影響をもつ久慈川、那珂川および原子力施設の排水口 (8)10km以遠でも人口の多い日立、常磐太田、爪連、水戸の4ヵ市の市街地、合計31ヵ点を選定することとした。
① 1-1~5-3まではすべて空間線量を測定する。 ② 6-1、6-2については原研の排水、6-3、6-4については原燃の排水を主対象とする。 5.運行計画 37年度においては前記測定地点の測定に関し、次のごとく定めた。 (1)1日に2地点を測定すること。 (2)2地点は異なった区分(60°等分による)のものであること。もし、都合により同一区分の地点を選ぶ場合にはできるだけ距離がはなれていること。 (3)1ヵ月について原則として1地点以上を測定すること。 (4)測定は月の第1週から第4週の前半の日曜から金曜日までとする。 (5)土曜日は、データ整理にあてる。 (6)第4週の後半と第5週は車体、計器の整備、保守、パルハイの測定、報告書の作成にあてる。 (7)1日の行程は平均約50kmとする。 (8)道路の状況、気象条件等により若干の変更もある。 6.計測器の性能および測定対象 平常時における放射能濃度分布をできるだけ詳しく 正確に調査し、安全確保につとめるために次のような性能を持った計器を備えた。 またその測定対称は次表のとおりである。
7.モニタリングカーの構造および積載機器 7-1モニタリングカー (1) 〈車体〉 豊田製作 FC80ボンネット (2) 〈エンジン〉130HPの6気筒、3,878ccガソリン (3) 〈寸法〉室外長×幅×高(6600×2400×3400) 室内〃×〃×〃(4600×2200×1760) (4) 〈積載能力〉 3t (5)(発電機〉ドーデンSR型3kV 配電盤付 モーター自動車エンジン使用 (6) 〈その他〉流し台(蛇口付)、測定台(ステンレス張り)、ケース(測定器Set用)、風向風速計(屋根に取付) (7) 〈定 員〉 5名 (8)配置図にて概要を示す。(D参照) 7-2 塔載機器 A 測定器頸 (1)パルスハイト・アナライザー 256チャンネル(RCL製)、チャンネルあたりのcount容量:10-6、Dead time 14 ±0.5Nμsec/channel、ブラン管指示、記録器付 (2)シンチレーションカウンター(神戸工業製作) スケラー(トランジスタ式1000進法)プローブ、測定台(鉛シールド製)付 (3)GMカウンター スケラーシンチレーションカウンターと共用プローブ、測定台付 (4)振動容器型電位計 タケダ理研製作 メインアンプ、プリアンプ 最高検出感度;20μV、10-17A、5×10-16 クーロン 精度;電位、電荷 ±1%> 電流 ±5%> 4π空間線量用チェンバー 1l容量 4πガスチェンバー 500ml容量 (5)サーベーメーター GM式サーベーメーター(TEN) シンチレーション式サーベーメータ(東芝) 電離箱式サーベーメーター(TEN) (6)ポケット線量計 4個 理化学研究所製作 直続式顕微鏡付 充電器付 B 気象関係器具 (1)スカイベーン風向風速計(玉屋) ①1個の発信器で風向風速を同時に測定 ②指示器のダイヤルは1個のキャビネットに納められ瞬時値が遠隔指示 (2)気圧計(玉屋) アネロイド(鏡付) 690mmHg~790mmHg 920mp~1055mp刻度 (3)直読式温度湿度計(玉屋) (4)ポケットコンパス 半 径 42mm 目 盛 1° 水平器 2個付 C その他の機器 (1)収塵機(スタープレックス) ダストサンプリング 吸引力:平均15~30ft3/min 1/100/μフイルター使用 (2)無線電話 富士通信機製 27MC(市民バンド) 1~2km送話可能 (3)熱風式乾燥器(容器乾燥用) (4)赤外式 〃 (水蒸乾濃縮用) (5)電 気 炉(ろ紙焼成用) (6)純水装置(オルガノ製) アンバーライトIR使用 5l/hr、500l採水可能 (7)ロータリーポンプ ガスチェンバー用 (8)天 秤 上皿自動天秤 5g~1kg 上皿天秤 10mg~100g D 車内配置図 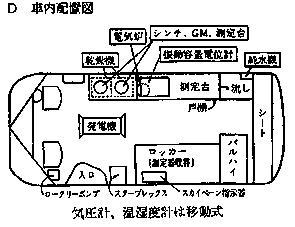 8.測定要領 1.測定地点における測定時の平均風速、風向、温度、湿度、気圧等の気象条件を観測する。 2.GMサーペー シンチレーションサーベー、電離箱型サーベーで空間線量率を約5~10分間おのおの測定する。 必要のある時は4方チェンバーを備えて振動容量電位計にかける。 3.収塵機で適当な位置を選んでろ紙をセットし、環境の空気を約10分間吸引しダストを集める。(15~25ft3/min) ろ紙を静かにまるめて電気炉で焼く。約20分で炭化から完全燃焼へと進みダストのみ残る。(ルツボ使用) このダストを試料に移してシンチレーションカウンターで計測する。 測定時間 バックグラウンド前後各10分間 試料 10分間 4.河川、排水口の水を約500mlとりそのうちの100mlについて蒸発乾固を行ない、GMカウンターで測定する。他の要領はダストに準ずる。赤外ランプ使用。 5.4方ガスサンプラー(500ml)にロータリーポンプをセットし、振動容量電位計につなぐ。ダスト、湿気分のない乾燥空気を一定量吸引して放射能濃度を測定する。 測定時間 計器安定:約1時間 計 測:〃30分間 6.パルスハイト・アナライザーは温湿度条件、電気的、機械的な高度の安定性を必要とするため自動車には常時積込まないことにし、月2回以上および自然計数以外の放射能が検出された時に用いることにする。 水、ダスト、河床泥等を試料皿にとり核種分析の直接測定を行ない記録にとる。 7.以上の測定結果、機器の状態、個人の被曝線量等について月間報告書を作成する。 |