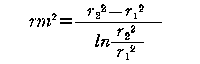|
第3回原子炉主任技術者筆記試験問題 1.原子炉理論 第1−1.次の事項について簡単に説明せよ。 第1−2.次の文章の中の空白の部分に適当な文字を書き入れ、文章を完全にせよ。 裸の球形原子炉の場合には、波動方程式は次のように書ける。
この場合の境界条件としては、中性子束が(i)到るところで そうすると上式の解として、
いま、外挿距離を含めた球形炉の半径をRとすれば、境界条件から が求められるが、臨界状態ではn=1に対する最低固有値だけが意味を持つ。 したがって、求める中性子束分布をγを用いて表わせば、 と書くことができる。 第1−3.原子炉の制御は、即発臨界(Prompt critical)以上になると一般に非常に困難になるに対して、即発臨界未満では制御が容易になる。これらの理由について説明せよ。 第1−4.熱中性子サイクルについて、共鳴エネルギー範囲における核分裂の効果を考慮に入れると、実効増倍率keffは次の式により与えられることを説明せよ。
ただし、(f,η)、(fr,ηr)は、それぞれ熱中性子、共鳴中性子に対応するものとする。 2.原子炉の設計 第2−1.非均質型原子炉における燃料の燃焼度 (burn up)向上の方法について述べよ。 第2−2.下記の事項について簡単に説明せよ。
ただし、冷却材への熱流束はすべて一様であるとし、その熱伝達係数(h)は、次の諸式によって与えられる。 又、この冷却材の物性値は、400℃で次のようである。 第2−4.制御棒駆動機構の設計方針について、下記原子炉のうちいずれか一つを選び説明せよ。
ただし、(a)燃料内の熱発生率は一様 として、計算せよ。 3.原子炉の運転制御 第3−1.次の事項を説明せよ。 第3−2.次の各文章において、それぞれ最も適切と思われるもの一つを選び、その番号を記せ。 (1)原子炉の臨界実験を行なう場合、燃料挿入前の中性子源のみによる測定器の計数値は、次の値が最も適切である。
(2)研究用原子炉の出力上昇時の周期は、次の値が最も適切である。
(3)研究用原子炉を急停止(scram)した後の周期は、ほぼ
(4)すでに定常運転を行なっている水冷却原子炉の起動に際し、次の操作を行なう必要がある場合、最初に行なうべきものは、
第3−3.既発臨界より十分大きい反応度がステップ状に原子炉に加えられた場合、その後t秒の間に開放される全エネルギーは、近似的にP(t)・Tであることを示せ。 ただし、P(t)は時刻tにおける原子炉の出力、Tは原子炉周期である。 第3−4.原子炉を臨界にした後、制御棒の校正を行なうため、制御棒を100%引き抜いた位置から80%まで挿入し、中性子検出器の計数値を測定したところ、38,728cpmであった。 この制御棒挿入による等価反応度は、-0.38%であった。 次に、制御棒を60%、40%、20%、0%まで挿入したときの計数値は、それぞれ7,889cpm、3,602cpm、2,240cpm、1,848cpmであった。制御棒の各位置での等価反応度を求めよ。 第3−5.次の事項を簡単に論ぜよ。 4.原子炉燃料および原子炉材料 第4−1.ウラン合金燃料とセラミック燃料とを比較して、その得失を述べよ。 第4−2.プルトニウムを核燃料として使用するには、どのような方法があるかを述べよ。 第4−3.次の(a)、(b)2問のうち、いずれかに答えよ。 ただし、合金組織の違いによる差などまで論議する必要はない。 第4−4.原子炉圧力容器用鋼材の選定にあたっては、中性子照射の影響をどのように考慮する必要があるか。 第4−5.原子炉材料としての黒鉛の用途を記し、それぞれの用途において黒鉛に要求されるおもな性質をあげよ。 第4−6.次の(a)、(b)2問のうち、いずれかに答えよ。 5.放射線測定および放射線障害の防止 第5−1.次の事項について簡単に説明せよ。 第5−2.最大許容線量は、外部被曝と内部被曝との和について規制しているものであるが、放射線管理上、内部被曝は特に厳重に制限することが期待される。内部被曝の原因になる汚染(表面、空気、一般排水)ならびにその伝播を防止するための基本的な考え方について簡単に述べよ。 第5−3.原子炉の事故に伴って原子炉室から問題となるほどの量の気体状放射性物質が放出された場合に、構外一般居住域において考えられる放射線被曝の種類をあげ、その形態についてそれぞれ簡単に説明せよ。また、この種の事故に際しての被暴防止のおもな対策を四つあげて、それぞれ説明せよ。 第5−4.次の諸臓器および組織のうちから、放射線障害の見地から特に問題とされるもの四つを選び、放射線の被曝によってどういう障害が起こるおそれがあるかを説明せよ。 皮膚 肝臓 眼 結合組織 血管 腸 骨髄 筋組織 生殖腺 脂肪組織 6.原子炉に関する法令 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「原子炉等規制法」という。)およびその関係法令につき、解答せよ。 第6−1.原子炉等規制法の目的を述べ、その目的が原子炉の設置許可基準によって、いかに確保されているかについて説明せよ。 第6−2.原子炉の運転開始後における原子炉施設の使用に係る安全性を確保するためおよび原子炉災害が発生するおそれがある場合にこれを防止するため、原子炉等規制法上、どのような規定が設けられているかを簡単に述べよ。(原子炉の設置、運転等に関する規則にまで言及する必要はない。) 第6−3.管理区域、保全区域および周辺監視区域とはそれぞれいかなるものか。また、原子炉設置者は、これらの区域についてどのような措置を講じなければならないか。 第6ー4.従事者の集積線量の管理に関する原子炉設置者の義務について述べよ。 第6−5.次の文章中、正しいものには○印を、誤っているものには×印をつけ、誤っている場合には、その箇所を指摘し、誤っている理由を簡単に説明せよ。 (1)原子炉の運転に係る放射線障害の防止に関しては、原子炉等規制法の規制を受けることとなっているので、労働基準法に基づく「電離放射線防止規則」の適用は除外される。 (2)日本原子力研究所は、日本原子力研究所法により原子炉の設置をその本来の業務として認められており、また、同法により特別の監督が行なれることとなっているので、原子炉を設置しようとする場合には、原子炉等規制法による設置の許可ならびに設計および工事方法の認可を受けなくてもよいこととされている。 (3)保安規定は、原子炉設置者の遵守すべき内部規程として定められるものであるから、原子炉設置者が保安規定に違反しても、原子炉等規制法上罰則を科せられるものではない。 (4)何人も、300グラム以下の天然ウラン等政令で定める種類および数量の核燃料物質の使用については、原子炉等規制法による使用の許可を受ける必要はなく、また、当該核燃料物質の譲渡および譲受についてもなんら制限を受けることはない。 (5)従事者の被曝放射線量の算定にあたっては、診療を受けるための被曝は計算から除外されるが、自然バックグラウンドの放射線による被曝は加算される。 (6)従事者が緊急作業に従事することにより12レムをこえない範囲内において被曝した結果、その者の集積線量が科学技術庁長官の定める許容集積線量をこえた場合には、その超過した線量は、その者の以後の集積線量の算定にあたっては、加算されない。 |
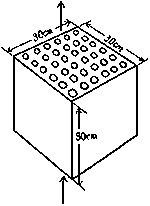 第2−3.辺の長さが30cmの立方体形をした固体核燃料からなる原子炉を考えよう。この原子炉から熱を取り出すために図のように直径3.2cmの円形冷却路を36本通し、これに冷却材として液体金属を流すものとする。いま、この原子炉の熱出力が0.5MWであり、冷却材の入口温度が390℃、出口温度が410℃のとき
第2−3.辺の長さが30cmの立方体形をした固体核燃料からなる原子炉を考えよう。この原子炉から熱を取り出すために図のように直径3.2cmの円形冷却路を36本通し、これに冷却材として液体金属を流すものとする。いま、この原子炉の熱出力が0.5MWであり、冷却材の入口温度が390℃、出口温度が410℃のとき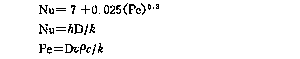
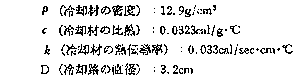
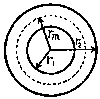 第2−5.内面、外面が共に冷却される中空円筒燃料において、燃料内面(r=r1)、外面(r=r2)が同じ温度の場合、燃料内の最高温度の位置rmは、次の式で表わされることを示せ。
第2−5.内面、外面が共に冷却される中空円筒燃料において、燃料内面(r=r1)、外面(r=r2)が同じ温度の場合、燃料内の最高温度の位置rmは、次の式で表わされることを示せ。