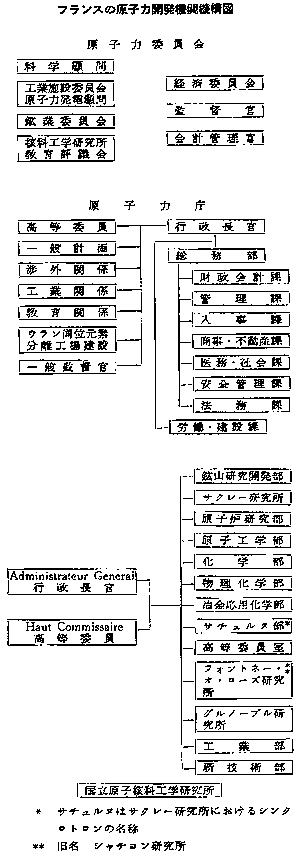|
フランスサクレー研究所における留学報告
サクレー研究所の活動状況 C E Aに所属する最大の研究所で1949年に建設に着手し、研究事務を開始したのは1952年である。パリから西南約25kmにあり、約170ヘクタールの敷地にC EA各部の研究室、原子炉、加速器、その他の建屋が立ち並んでいる。 主要装置 加速器; a. Van de Graaff-最大エネルギー5.5MeV、粒子束最大強度100μA 原子炉; a. EL2(旧称P 2)-1952年10月27日完成、重水減速、炭酸ガス冷却、中性子束1013n/cm2/sec、熱出力3,000kW(常時2,400kW) 1. サクレー研究所 庶務、経理、厚生のような管理部門および文書、図書の管理、発行のほか、次のような研究部門をもっている。 フランスの原子力開発機関機構図
a 電気工事課-職員約250名(1957年12月,以下同様)、各種の目的、たとえばウラン探鉱、放射線防御、核物理研究、原子炉の制御、運転などのための電子管装置の研究を主とす。ここで開発された結果が外部で工業化される。 b 核物理課-約180名,加速器の科学的開発、高エネルギーの微粒子物理、中および低エネルギーの核反応など核現象の一部を担当する。 c 応用物理課-約140名、サクレーの加速器の建設を使命としているが、サチュルヌ完成後は気体中の放電、磁場、プラズマ、微粒子光学、イオン源など応用核物理の分野を担当する。 2.同位元素分離装置・プロトン加速器部(サチュルヌ部) 上記応用物理課によるサチュルヌ完成後,その保守運転を任とする。 3.化学部 サクレーには人工放射性元素課およびプルトニウム課の一部がおかれている。 a 人工放射性元素課-約85名、人工放射性元素の製造および利用計画を担当し、利用者との連絡を行う。フランスの全需要アイソトープ量の80%を供給している。なお利用者の内訳は病院(l0%)、大学(32%)、民間工業(58%)となっている。 b プルトニウム課-主体はシャチヨンにあるが、ここではウラン233の研究を行っている。 4.高等委員室付き 次の3課がサクレーに置かれ、約400名の職員を有し、放射能の管理を主要任務としている。 a 生物学課-アイソトープおよびイオン化放射線の領域における生物学(動物、植物、医学)の研究を行う。 b 原子力衛生・放射線病理課-イオン化放射線による障害およびその診断、発見、予防、治療の研究および放射線照射や汚染に関する許容量、放射線による危険をともなう労働条件などについて担当。 c 放射線管理・放射能工学課-放射線および放射能汚染の防御の方法についての研究およびCEA所属諸施設内外における放射線の管理、職員個人についての被爆線量の記録を行う。また放射能測定関係機器の開発をも研究する。 5.原子炉研究部 職員約750名(フォントネー・オ・ロ-ズに約100名)、現存ないし研究中の原子炉に関する科学的および技術的データの採集整理、原子工学に関する純および応用物理の領域における実験、原子炉の設計、核融合の研究および工学的な原子炉の建設の指導などを担当する。 a 数理物理課-原子炉における中性子経済および分布の数学的研究、理論計算および数値計算の方法の研究、理論核物理の研究を行う。 b 実験中性子学課-同上の研究を実験的に行い、また原子炉材料の中性子断面積の測定を行う。実験炉としてAQUILONおよびPROSERPINEを管理。 c 機械研究課-原子炉の構造、機械装置、流体の循環、熱交換などの研究。 d サクレー大原子炉課-EL2およびEL3の管理、開発。 e 磁性共鳴研究室-高周波の場における正磁性原子核の挙動の研究。 6.冶金応用化学部 原子炉の建設に必要な材料の研究すなわち核燃料物質、被覆材、減速材、冷却材、構造材料の開発および冶金的研究およびそれらの原子炉内における挙動および性質の変化、腐食などを研究する。職員約500名、うち20名がフォントネー・オ・ローズに勤務する。 a 工学課-原子炉材料、燃料要素の開発研究を担当する。金属材料に関するほとんどすべての研究がここで行われている。 b 固体化学課-焼結、特に耐火物(酸化ウラン、酸化ベリリウムなど)の研究、ガス分析、ガス腐食、金属ナトリウムの研究などを行う。 c 放射性冶金課-燃料に及ぼす放射線の効果およびプルトニウムの冶金から燃料要素までの開発などを担当。 d 分析・応用化学研究室-液体腐食、電気化学などを取り扱う。 7.物理化学部 主として減速材の開発、同位元素の分離の研究を行う。特にウラン235の分離の研究が重要である。職員約330名。 a 物理化学課-主として黒鉛に関する研究。 b 安定同位元素研究室-主として重水の研究。 c 放射性元素利用研究室-放射性アイソトープの利用に関する研究。 d ウラン同位元素分離研究室-ウラン235の濃縮に関する化学的、化学工学的研究。 国立原子核科工学研究所-略号INSTN わたくしのおもな留学先であり、当研究所の概況について述べる。 この研究所は1956年6月原子核科学および工学に関する高度に専門的な教育を行い、技術者を養成する目的で、総理大臣および文部大臣の管轄の下に創立された。 原子力庁(CEA)とは直接の行政関係はないが、サクレー研究所内に置かれ、同研究所長Debiesse氏が当研究所長を兼任しており、 CEA研究員およびパリ大学その他の教授によって講義、実習が行われる。 国立原子核科工学研究所にて行われる講習は次のとおりである。 1.原子工学の講習 目 的:原子炉の建設ならびに運転に関する専門技術者の養成 受講資格:国立大学および大学校卒業程度 期 間:11月〜7月(9ヵ月) 内 容:原子物理、核物理、原子炉工学、冶金、化学など原子炉の設計、建設、運転、管理に関する講義、放射能に関する測定実習、専門分野における実習、原子炉の設計など 2.冶金に関する特別講習(3ヵ年) 目 的:原子炉の建設に必要な金属、合金に関する冶金学の研修(パリ大学と連絡) 内 容:第1年 基礎講習、ゼミナール、実習 3.加速器の理論と技術(3ヵ年) 目 的:加速器に関する専門的研修(パリ大学と連絡) 内 容:第1年 講義、実習 4.放射線生物学の講習 目 的:放射線生物学に関する専門的研修 期 間: 2年 5.原子炉中の流体の熱学および力学の講習 目 的:原子炉の熱学および熱交換に関する専門家の養成 内 容:第1年 講義、ゼミナール、実習 6.理論物理 パリ大学理学部理論物理の3ヵ年教育と連携量子力学、核物理、固体物理の講義 7.放射性元素利用者のための教育 (a)化学、物理、工業利用 (b)生物学 (c)医学 原子工学コース 1.講義および実習日程 わたくしが参加した国立原子核科工学研究所原子工学コースはフランスの大学教育制度に準じて1学年間すなわち11月から翌年7月まで行われている。このコースには資格候補者(学生)と自由聴講生の2種があって、後者は前期4ヵ月の講義のみに参加できる。前者はさらに実習および研究、原子炉設計および資格試験が課せられる。 1957〜58年度においては全体で約120名うち聴講生50名であった。なお外国からの学生は17名で、内訳はイタリア3,スイス3、オーストリア2、イギリス、カナダ、ベルギー、トルコ、イスラエル、べトナム、日本、アルゼンチン、ベネズエラ各1であった。 コースは32年11月4日から次のようなプログラムで開始された。 講 義 11月〜2月 2.講 義 講義は一般および選択講義にわかれ、各人の専門に従って物理関係あるいは化学関係を受講する。講義は教科書を併用して行われたが、化学関係に属する講義のかなりの部分はテキストなしであった。配布された教科書は全8巻11冊約2,500頁に及んでおり、さらに別冊が追加された。これらの題目は次のようである。 Vol.I 総論-核物理 別冊 安全からみた制御棒速度の限界、 P 2炉CO2の放射線分解について、パルスコラム、原子炉建設における表面処理、ウラン合金、炉の構造について、ウラン合金-照射下の変形、核融合について、熱伝達とエネルギーの利用、原子炉の調整 3.実 習 A 放射能測定の基礎的実験 12月から午後を実習にあてられ、 2人1組で各種の測定実験を行うことになった。 No.1 GMカウンタ-の特性曲線 B 各種実験I 12月末から1月にかけて4人一組となり下記実験を行った。 No.1 イオン交換樹脂によるクロマトグラフィー C 各種実験II 以上の実習はサクレー研究所にある教育館と呼ばれる建物内で行われたが、 2月には8〜10人1組となってサクレー研究所内各所およびフォントネー ・オ・ローズ研究所などで下記の実験が行われた。 No.1 ベリリウムの定量 D 鉱石からのウランの抽出 3月以降は次に述べる専門研究に入ったが、その間に化学関係者のみがこの実験を行い, TBPによる抽出法を検討した。 以上の実習は原子核科工学研究所の職員によって指導され、その主任は物理関係にCambou、化学関係にTibiの両氏であった。実験はこれらの職員によって準備され、全くUbung的なものであったが、実験題目の選定にかなりの考慮が払われており、特に中性子を含む各種放射線の測定に関しては充実したものであった。 4.専門的研究 学生は各自の専門によってサクレー研究所あるいはフォントネー・オ・ローズ研究所などに研究室をおくCEA各部において3月から実習生として勤務した。 わたくしは冶金応用化学部、固体化学課のCaillat課長の下でガス分析グループ主任Darras氏および研究員Champeix氏の指導により金属ソーダの精製、取扱、酸素分析、腐食実験などについての研究を行った。この研究は当課が終了を急がれていた金属ソーダに関する研究の一部で、特に酸素分析法の確立が重要であった。 分析法としては金属ソーダが水銀とアマルガムを作り、酸化物は反応せずにアマルガムの上部に移行する。いわゆるアマルガム法をChampeix氏らが改良した方法を用いた。 精製は5μの孔をもつ焼結鋼フィルターを用いて行い十分許容酸素量(10ppm)以下の金属ソーダを得ることができた。 腐食については不銹鋼、ニオブ、モリブデンについてシーソー法を適用したが、これは長期にわたる試験のため、実験の準備のみに終った。 冶金応化部の実習を選んだのは、この部において核燃料および原子炉材料一般の開発研究が行われていて、それらについてのフランスにおける状況を知ることができると思ったからである。事実、それらについての知識が容易になり、また燃料製造組立工場、酸化ウランおよび酸化ベリリウム、焼結工場、ガス腐食試験設備その他の重要な施設を見学することができた。 5.原子炉の設計 4月から10人程度のグループにわかれて原子炉の設計を行うことになったが、サンゴバン化学会社からの学生とともにフランス電力公社から派遣されていた7名の学生の計画に参加した。この計画はフランス電力公社が設置の可能性を検討しようとしていた型式の炉であり、天然ウラン原子炉の進むべき次代の型式である。すなわち黒鉛減速・炭酸ガス冷却で天然ウラン酸化物を燃料とするが、プルトニウムで濃縮される。熱出力1,
500MW、電気出力450MWの発電所で、工学的な設計にまでわたり経済問題にも論及することにした。 6.試 験 6月中にこれまでの実習、専門的研究および原子炉設計の報告書を作成提出し、 6月末に原子炉設計についての口頭発表および試問が課せられた。その形式は日本の大学における卒業論文発表会とほとんど変らず、われわれの場合は数理物理課長Horowitz、機械研究課Martinその他7〜8名の職員による試問が行われた。 7月に入って講義について筆答試験が行われた。試験は2日にわたって行われ、第1日は講義全般にわたる常識的な問題が課され、第2日は専門別、すなわち原子炉理論、熱学、原子炉制御、原子炉遮蔽、冶金、化学などにわけて各自の選択する部門での試験であり、これは参考書の使用を許された。わたくしは冶金を選択した。 放射線管理放射能工学課における実習 8月からCEA高等委員室付き放射線管理放射能工学課の原子炉、加速器室における実習を行った。課長はDuhamel氏であり、室長はJoffreおよびFitoussi両氏である。実習内容は放射能管理および原子炉の安全性に関するもので、次のとおりであった。 原子炉室における放射能管理 1.放射能の管理 1.1原子炉室 原子炉室の空気放射能の測定は毎朝7時、すなわち始業時間の2時間前から行われ、そのために1名の測定者が専従する。 EL3研究炉における測定の実習を行ったが、要領はまず一定体積の空気(1m3)を吸引してろ紙上に空気中の塵挨を補集し、その放射能をシンチレーションカウンターによって計数し、それから許容量との割合を求めることである。測定は3ヵ所について行われるが、実習時のEL3炉上部における放射能は4.11×10-9c/m3、すなわち許容量(10-7c/m3)との比は0.0411であった。 放射能汚染をこうむった機器は原子炉に付属する化学室において除染されるが、その室における空気放射能も同様に測定される。これらの測定を所定の様式の報告書に記入し、上司に報告する。 原子炉室における各所のX線、 γ線、熱中性子、速中性子が常時測定されており、 2週間ごとに報告を提出する。 1.2 個人爆射 所員の爆射線量の管理はフィルムバッジおよび万年筆型線量計によって行われている。フィルムバッジは2週間ごとに集めてシャチョンに送りそこで処理される。線量計は朝夕2度係員が指針を検査して,
2週間ごとに報告する。 特別に監視を必要とする仕事に従事する場合には許可証が交付され被爆線量および汚染が記入される。 1.3 原子炉周辺大気放射能 サクレー研究所敷地内に1ヵ所、敷地周辺約1kmの地点4ヵ所に大気放射能測定ステーションが置かれてあり、敷地内は毎日、外部は隔日にデータを集録する。 敷地内のステーションでは気温、風向、風速、大気中のα、 β, γ放射能が自記記録されている。またデータ集録時に空気中の塵挨(および雨水)を採取して研究室に持ち帰り、測定を行う。外部においては大気中のα、 β、 γ放射能のみを対象として自記測定している。 2.原子炉安全問題 原子炉の安全問題については文献資料を収集し、その要約をとる作業を行った。サクレー研究所付属図書館は米国AECリポートをはじめ各国の原子力関係リポ-トがすべて収められ、またほとんどの学術雑誌がそろえられていて、かなり系統的な文献索引カードが備わっているので、関係文献の調査は比較的容易であった。 この調査のために利用することのできたのが約3ヵ月であり,多数の資料を消化するには不十分であったが、それでも多方面にわたってかなりの資料を閲読あるいは複写することができた。またこの関係についてはFitoussi氏から指導を受けた。 3. EL2の原子炉施設の放射線管理 3.1検出すべき放射線の種類と源 γ線-原子炉、実験孔、冷却回路、放射性元素の取り出し時など 3.2 検出装置 γ線および熱中性子
速中性子
塵挨β放射能
気体β放射能
塵挨および気体のβ放射能測定装置は組み合わせられている。 3.3 警 報 ある箇所の放射能が許容濃度をこえるとき次の段階で警報が与えられる。 第1段 燈灯点滅 これらの警報は放射線管理盤にも伝えられる。 3.4 放射線管理盤 γ、速中性子、塵埃放射能、気体放射能、測定装置のおのおのからの信号が記録される。 3.5 検出器の配置
あ と が き 1年にわたる滞仏留学中専門分野において学び得た知識はもちろんのこと、人的、物的な面での欧州の生活の経験もまことに貴重なものであった。 サクレー研究所の原子工学コースに最も期待していたことはそれまで無秩序に学んできた原子工学という学問を系統だてて整理し直したいということであった。また実際に原子力関係の施設を見学し、あるいはそれらを使用することはどこかに不安のあった日本での勉強に根を下ろさせることになって、これまでの研究が本当の物になってくるだろうと期待した。これらの期待は自分自身の努力によって満たされるべきものであったことはいうまでもない。 サクレーをはじめ原子力関係研究所の施設や装置あるいは研究体制というものも調査の対象になっていた。日本を出発するまではあまり豊かでないフランスのことゆえ研究設備も日本とそれほど開きがないであろうと思っていたが、原子力関係の政府予算は優遇されていてかなり裕福な施設を持っており、研究の成果もたいしたものであった。サクレーでの研究は重点的に行われているようで、重要な研究は期限づけられているような節があり、米ソなどの先進国に追いつこうと努力しており、かつてのわが国の戦時研究を思い起こさせた。研究員個人の専門はかなり分科されているが、各自の専門が尊重され、また研究員の間の横の連絡がみごとにとれているので専門外の知識を必要とするときはその専門研究者から容易に得ることができて自分の研究の進行に支障を与えない。このような研究体制がフランスの原子力の急速な進歩をもたらした一つの要素であろう。 1年の生活を送ったパリは世界各地からの留学生が集まり、国際的な様相を持つ都市となっている。その中で日本からの留学生は各自の仕事や研究を充実させて将来への地歩を固めるのが目的であって大学や研究所などで業績をあげて認められ、あるいは美術を志ざす者はサロンへの出品を、音楽家はコンセルヴァトワールなどでの賞をとろうと努力している。国際的な競争の雰囲気の中にあってはおのずと勉学に励むというものであろう。もちろん外国留学は単に勉学のみでなく、広く見聞を広めることも大きな目的の一つであるが、この点でも豊かな歴史的背景を持った欧州での留学はまことに恵まれたものであった。 終戦以来米軍の進駐によって日本人にとってアメリカはかなり身近かに考えられるようになってきたが、欧州は北極回りで30時間という今日でもいまだに遠くはるかに感じられており、そこに住む人達の社会あるいは生活について十分理解されていない。欧州人が日本と支那とを混同しやすいように、われわれも西欧諸国としての類似を先入観として諸民族の社会制度や生活方式の違いにあまり留意していないようである。このようなことは欧州に行って初めて理解できることであった。 欧州で送った1年を思い返して仕残してきた努力の足らなさが心残りであるが留学の成果をさらに結実させるために今後いっそうの研鑚を積みたいと念じている。 |