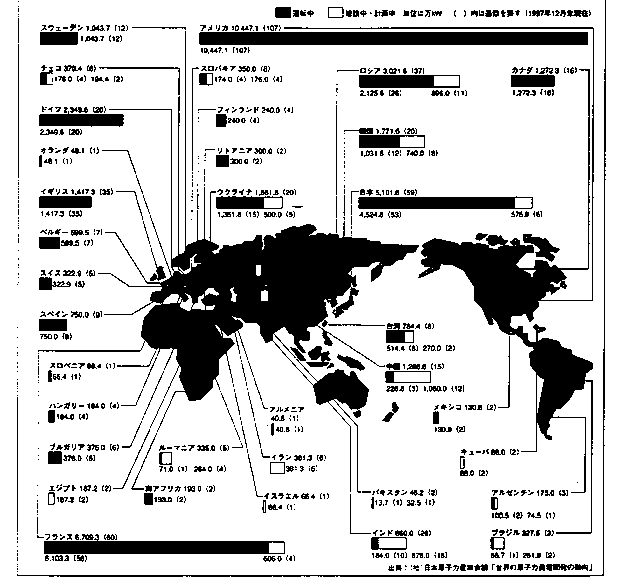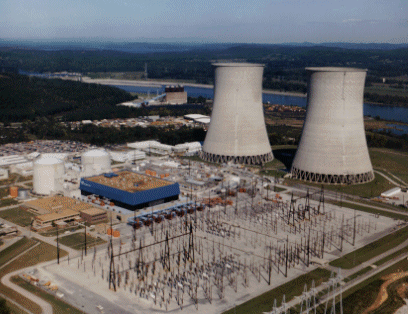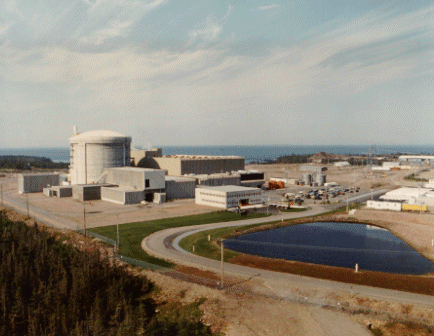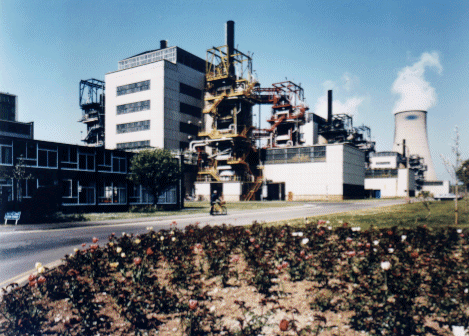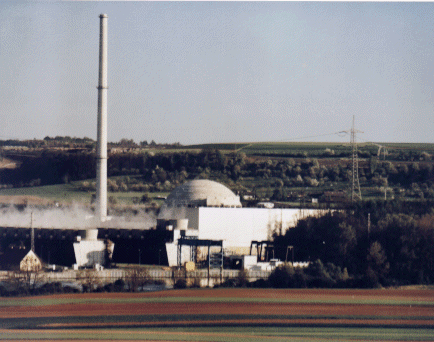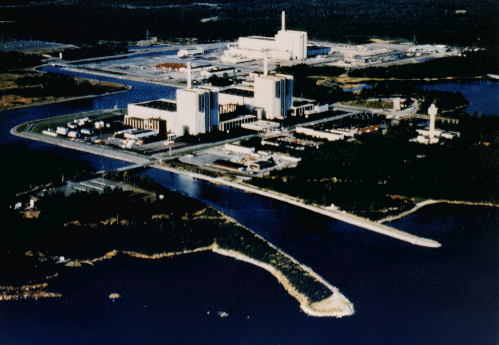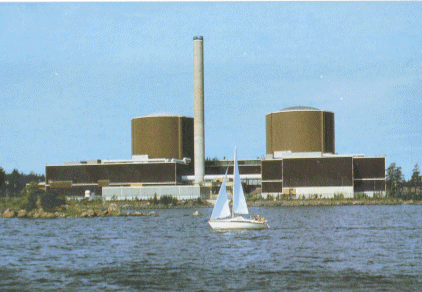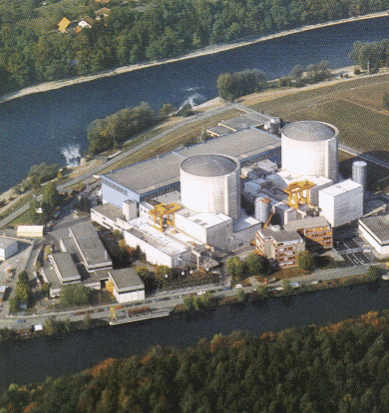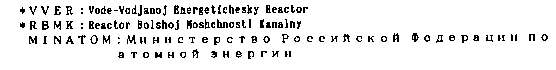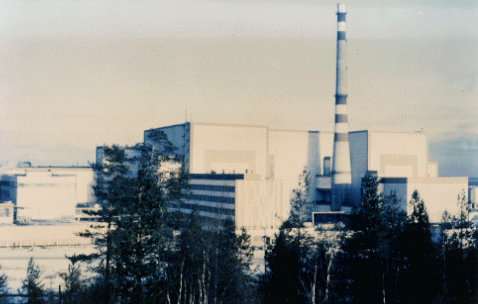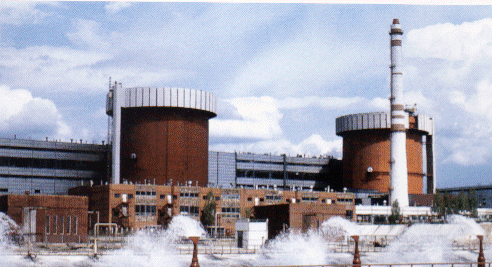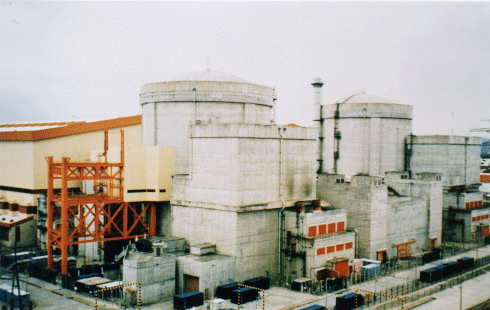6.原子力発電の展開
(3)世界の原子力発電の状況
世界の原子力発電設備容量は、1997年12月末現在、運転中のものは429基、3億6,470万キロワットに達しており、建設中、計画中のものを含めると総計523基、4億3,913万キロワットとなっている。
原子力による発電電力量については、1996年実績で2兆3,001億キロワット時に達し、世界の総発電電力量の約17%を占めている。これは、サウジアラビアの年間石油生産量(世界第1位:1996年実績約4億2,880万トン)を上回る約5億2,000万トンの石油を現在の火力発電所で消費した場合に発生する電力量に相当する。
表2-6-5 世界の原子力発電設備容量(1997年12月末現在)
基 数 総容量(グロス電気出力) 運転中 建設中 計画中 合 計 ((社)日本原子力産業会議調べ) 現在、欧米などの先進諸国を中心として原子力発電所の運転が行われているが、1996年に韓国、米国、日本、ルーマニアで1基ずつ、また、1997年に韓国で1基、日本で2基が新たに運転を開始した。一方、1997年にはオランダで1基、米国で2基が閉鎖された。なお、カナダで運転休止中の6基については、表2-6-5の集計から除外した。
図2-6-11 世界の原子力発電所 1997年12月末現在、原子力発電国(地域)は、32か国(地域)である。その他開発途上国などにおいても原子力発電所の建設あるいは計画が進められており、これらの国を合わせると39か国(地域)となる。
運転中のものについて見ると、米国が全世界の原子力発電設備容量の約29%を占めており、フランス、日本がそれに続いている。炉型別では全体の約87%が軽水炉で占められており、軽水炉のうち約74%がPWR、残り約26%がBWRとなっている。①米国
(1997年12月末現在)
運転中 107基 10,447万kW 合 計 107基 10,447万kW
総発電電力量に占める原子力の割合(1996年):21.9%
平均設備利用率(1996年):75.2%
- クリントン政権はエネルギー・環境政策の基本的方向として、エネルギー効率の改善、省エネルギーの促進、天然ガス及び再生可能エネルギー利用などに重点を置き、原子力に対しては高い優先度を与えていないが将来のオプションとしては維持されるべきとしている。
- 1993年10月の「環境改善行動計画」では、発電による炭酸ガス排出の抑制の面で原子力が引き続き主要な役割を果たすとの認識を示している。
- 1997年12月、エネルギー省発表の2020年までの長期的エネルギー需給を予測した「1998年エネルギー概観(AEO98)」によると、24基の原子炉が早期閉鎖されることを前提とした「参考ケース」では、2020年に稼働中の原子炉は45基で、総発電電力量に占める原子力の割合は8%になると予想されている。また、原子炉の運転期間を10年延長するとした「ハイケース」では、2020年時点での炭酸ガス排出量が「参考ケース」に比べて4,200万トン少なくなると予測されている。
- 1997年5月、改良型軽水炉の設計の標準化に関し、米国原子力規制委員会(NRC*)は、改良発展型プラントであるABWRとシステム80+に設計認定を行った。受動的プラントであるAP-600については、1999年に最終設計承認を取得する予定である。なお、エネルギー省の改良型軽水炉開発への支援は、1997会計年度で終了した。
- 1998年2月、1999会計年度の予算教書が発表された。この中で、クリントン大統領は、21世紀に向けて「アメリカ研究基金」の創設を提案しており、科学技術面でのリーダーシップ維持のために、科学技術投資の強化を目指している。
*NRC:Nuclear Regulatory Commission
図2-6-12 米国 ワッツバー発電所 ②カナダ
(1997年12月末現在)
運転中 16基 1,272万kW 合 計 16基 1,272万kW
総発電電力量に占める原子力の割合(1996年):16.0%
平均設備利用率(1996年):68.6%
- 自国の豊富なウラン資源と自主技術によるカナダ型重水炉(CANDU*)を柱とした独自の原子力政策を一貫して採っている。
- オンタリオ・ハイドロ社は、1997年8月、所有する原子力発電所の数年来の稼働率低下を解決するために、大幅な改善を行うことを発表した。これによると、今後3年間かけて、ブルースB発電所(CANDU、92万キロワット×4基)、ピッカリングB発電所(CANDU、54万キロワット×4基)およびダーリントン原子力発電所(CANDU、94万キロワット×4基)で広範囲にわたる品質向上作業を実施する。また、ブルースA発電所(CANDU、90万キロワット×2基)とピッカリングA発電所(CANDU、54万キロワット×4基)は、運転を休止しており、両発電所の運転再開については経済性と電力市場に基づき決定するとしている。
- カナダ原子力公社は、CANDU炉の輸出にも力を入れており、アルゼンチン、韓国、インド、パキスタン及びルーマニアで同炉が運転されている。また、中国とは、1996年11月、中国核工業総公司との間で、CANDU炉2基を建設する正式契約を結んだ。
図2-6-13 カナダ ポイントルプロー発電所 ③フランス
(1997年12月末現在)
運転中 56基 6,103万kW 建設中 4基 606万kW 合 計 60基 6,709万kW
総発電電力量に占める原子力の割合(1996年):77.4%
平均設備利用率(1996年):75.4%
- エネルギー資源に乏しく、エネルギー自給率を改善するため原子力発電を積極的に導入している。原子力発電の推進により、エネルギー自給率を1973年当時の23%から約20年間で53%に回復した。
- 原子力を中心とする積極的な電源開発の下に同国は、近隣欧州諸国への電力輸出にも力を入れており、1996年には総発電電力量の約14%を輸出した。
- 軽水炉開発に際して国内の原子力発電所の標準化を進めているが、さらに21世紀初頭の運転開始を目指して、ドイツと共同で欧州加圧水型炉(EPR*)の開発を進めており、1995年2月より基本設計を実施している。
- フランス電力公社(EDF*)、フランス原子力庁(CEA*)その他の機関の委託により、世論調査機関BVA社が行った1997年12月の世論調査によると、今後10年間に最も重要なエネルギー源として原子力を挙げた回答者は62%(前年比6%増)で、再生可能エネルギーについては18%(前年比2%減)と2番目であった。
- 1997年6月、総選挙で発足した新内閣のジョスパン首相は、国民議会における一般政策演説の中で、原子力の重要性を認めながらも、経済的理由により、高速増殖炉スーパーフェニックスを将来的に放棄することを言及していたが、1998年2月、フランス政府は高速増殖炉スーパーフェニックスの閉鎖を決定した。一方で、研究は継続するとして、原型炉フェニックスを2004年まで運転するとしている。
*EPR:European Pressurized Water Reactor
*EDF:Electrite de France
*CEA:Commissariat a I' Energie Atomique
図2-6-14 フランス クリュアス発電所 ④英国
(1997年12月末現在)
総発電電力量に占める原子力の割合(1996年):260%
運転中 35基 1,417万kW 合 計 35基 1,417万kW
平均設備利用率(1996年):70.5%
- ・英国政府は1995年5月の「英国における原子力発電の見通し」により、改良型ガス冷却炉(AGR*)と英国初の軽水炉であるサイズウェルB発電所(PWR、126万キロワット)は、民間会社であるブリティッシュ・エナジー社(BE)が所有し、ガス冷却炉(GCR*)については引き続き政府が所有することとなった。また、1995年の原子力公社法により、英国原子力公社(UKAEA*)の商業部門が、1996年9月にAEAテクノロジー社となり民営化された。
- ・1998年1月、英国政府が保有していたマグノックス・エレクトリック社(ME)株が英国核燃料会社(BNFL)に移転され、ME社はBNFLの所有子会社となった。
- ・1996年7月、世界初の商業規模の原子力発電所であるコールダーホール発電所(GCR、6万キロワット×4基)およびチャペルクロス発電所(GCR、6万キロワット×4基)に対し、今後10年間の運転延長が認められた。これにより、両発電所は最高50年間運転を継続することが可能となった。
*AGR:Advanced Gas-cooled Reactor
*GCR:Gas Cooled Reactor
*UKAEA:United Kingdom Atomic Energy Authority
図2-6-15 英国 コールダーホール発電所 ⑤ドイツ
(1997年12月末現在)
総発電電力量に占める原子力の割合(1996年):30.3%
運転中 20基 2,350万kW 合 計 20基 2,350万kW
平均設備利用率(1996年):78.6%
- 旧東独の旧ソ連型原子力発電所は、安全調査結果を受けすべて閉鎖された。
- 1994年5月、原子力法の一部改正を含むエネルギー一括法が成立した。この中にはシビアアクシデントを考慮した発電所の設計要件及び使用済燃料の直接処分も選択肢として認めるなどの内容が含まれている。1994年10月に一旦は頓挫したエネルギー・コンセンサス協議が、1995年3月に再開された。しかし、連邦政府と社会民主党との意見調整がつかず、結局同年6月に協議は放棄された。
- 1997年3月、ドイツ政府が発表した「エネルギー・コンセンサスを目指した研究開発政策」によると、原子力発電は見込まれる将来において最大、かつ既に今日において技術的、経済的に実現可能な二酸化炭素排出削減能力を有しているとし、政策の中心を次世代のより安全な原子炉開発を含む安全研究、放射性廃棄物の処理処分の研究開発、研究・技術の後任者確保の3点に中心をおくとしている。
図2-6-16 ドイツ ネッカー発電所 ⑥イタリア
- 現在、主要先進国(G7)の中で、唯一、原子力発電所の運転を行っていない。
- 1987年の国民投票の結果を受け、5年間の新規原子力発電所建設禁止(モラトリアム)が決定され、稼働中の原子炉は閉鎖された。1992年12月にモラトリアムは終了したが、現在、政府・議会レベルでの原子力発電計画の再開に向けての方針転換は見られない。
- イタリア政府内には、輸入電力への依存度が大きくなり過ぎることを懸念する声があり、イタリア電力公社(ENEL*)も原子力技術の研究開発は継続していく方針である。
*ENEL:Ente Nazionale per I'Energica Electrica
⑦スウェーデン
(1997年12月末現在)
総発電電力量に占める原子力の割合(1996年):52.4%
運転中 12基 1,044万kW 合 計 12基 1,044万kW
平均設備利用率(1996年):81.2%
- 1980年6月の国民投票の結果を受け、2010年までに原子力発電所12基を全廃するとの国会決議を行った。
- 1991年6月、議会は、2010年までの原子力発電所全廃の決定は変更ないとしながらも、1995年から1996年にかけて2基を廃止するという計画の放棄を含む新しい国家エネルギー政策を承認した。
- 1995年12月、原子力問題を含めエネルギー問題の検討を行っていたエネルギー委員会は、1990年代に1基の原子力発電所を閉鎖することは可能であるが、最終的な閉鎖時期の期限については設定されるべきでないとする報告書を発表した。
- この報告を受け、政党間の協議の結果、1997年2月、与野党3党はバーセベック原子力発電所の閉鎖等を盛り込んだエネルギー政策について合意に達した。さらに、議会は、この政策を基にしたエネルギー政策法案を同年6月に決議した。
- 1997年12月、原子力発電所の閉鎖及び資産の収用を可能とする法案が議会にて可決され、1998年1月より施行された。これにより政府は、安全性の問題の有無に係わらず、原子力発電所の閉鎖を命じることができる。
- 1998年2月、政府は、バーセベック発電所1号機について、1998年7月以降の認可を取り消すことを表明した。
図2-6-17 スウェーデン フォルスマルク発電所 ⑧フィンランド
(1997年12月末現在)
総発電電力量に占める原子力の割合(1996年):28.1%
運転中 4基 240万kW 合 計 4基 240万kW
平均設備利用率(1996年):92.4%
- 1986年のチェルノブイリ原子力発電所事故後、新規原子力発電所の建設計画を凍結している。
- 1993年2月、政府は5号機計画を原則決定し議会に承認を求めたが、結局、同年9月の議会における採決で同計画は否決されるに至った。
- 1997年5月、政府は2025年までの長期的なエネルギー戦略案を発表した。この中で、将来の二酸化炭素放出の抑制については、基本的には石炭火力を天然ガス火力に替えることにより対応するとしているが、石炭の代替として天然ガスが不十分とされた場合には、原子力を考慮すべきとしている。
図2-6-18 フィンランド ロビーサ発電所 ⑨スイス
(1997年12月末現在)
総発電電力量に占める原子力の割合(1996年):44.5%
運転中 5基 323万kW 合 計 5基 323万kW
平均設備利用率(1996年):88.2%
- ・1990年9月の国民投票で、以後10年間に原子力発電所の建設許可を発給しないというモラトリアムが決定されている。火力、原子力とともに、環境問題・モラトリアムなどの理由から新規発電所建設計画はなく、水力も環境問題から開発は困難な状況となっている。
- ・政府は、長期の電力・エネルギー供給計画についてのコンセンサス、2000年以降のエネルギー政策等について各界と協議を重ねている。
図2-6-19 スイス ベツナウ発電所 ⑩ロシア
(1997年12月末現在)
総発電電力量に占める原子力の割合(1996年):13.1%
運転中 26基 2,126万kW 建設中 4基 360万kW 計画中 7基 536万kW 合 計 37基 3,022万kW
平均設備利用率(1996年):58.3%
- 現在運転されている原子力発電所は、ソ連型加圧水型炉(VVER*)13基、黒鉛減速軽水冷却沸騰水型炉(RBMK*)11基、沸騰水型炉(BWR)1基及び高速増殖炉(FBR)1基である。
- ロシアでは、2000年までは既存の原子力発電所の改良を行いつつ、建設中の発電所を完成させ、2000~2010年には新世代の原子力発電所を建設する一方で、古い原子力発電所を閉鎖することとしている。
- ロシア原子力省(MINATOM*)は、チェルノブイリ原子力発電所事故の影響で建設が中断していたクルスク5号機(RBMK-1000改良型、100万キロワット)、カリーニン3号機(VVER-1000、100万キロワット)を完成させる予定である。また、ソスノブイボル原子力発電所、コラ原子力発電所等において原子炉の増設を計画している。
図2-6-20 ロシア コラ発電所 ⑪ウクライナ
(1997年12月末現在)
総発電電力量に占める原子力の割合(1996年):43.8%
運転中 15基 1,362万kW 建設中 5基 500万kW 合 計 20基 1,862万kW
平均設備利用率(1996年):65.6%
- ウクライナは、チェルノブイリ原子力発電所について、エネルギー及び電力不足から、事故があった4号機以外の炉(RBMK、各100万キロワット)の運転を当面の間継続する動きがあったが、同発電所の閉鎖及び代替電源に関して西側が援助することを条件に、1995年4月、同発電所を2000年までに閉鎖することを明らかにした。
- 1995年12月に、G7とウクライナの間で覚書を作成し、ウクライナが2000年までにチェルノブイリ原子力発電所を閉鎖することを支援するため、他の支援国や国際機関などの貢献も得つつ、ウクライナの電力部門改革、エネルギー投資計画、原子力安全などの分野に関して協力していくことを表明した。この覚書に基づき、1996年11月に欧州復興開発銀行との間で、原子力安全基金からのチェルノブイリ原子力発電所閉鎖のための資金援助に関する合意文書が調印された。
- 1996年11月、チェルノブイリ原子力発電所の1号機が、閉鎖に向け、停止された。現在、3号機だけが運転を続けている。
- 1997年6月、デンバー・サミットにおいて、チェルノブイリ原子力発電所閉鎖後、2000年以降のウクライナの電力需要を満たすためのエネルギー・プロジェクトの資金動員について、1995年覚書の範囲内でウクライナを支援することが再確認された。さらに、4号機石棺に関しては、環境上の安全性を確保することの重要性について、また、多数国間資金供与メカニズムの創設を指示し、G7がこのプロジェクトの存続期間にわたって3億ドルの貢献を行うことで意見が一致した。この合意を受けて、1997年12月、欧州復興開発銀行(EBRD)内にチェルノブイリ石棺基金(CSF)が設立された。
- 1998年5月、バーミンガム・サミットにおいて、G7は、上記基金への拠出を未だ表明していない国に対して拠出を検討するよう求めた。
図2-6-21 ウクライナ 南ウクライナ発電所 ⑫韓国
(1997年12月末現在)
総発電電力量に占める原子力の割合(1996年):35.8%
運転中 12基 1,032万kW 建設中 6基 540万kW 計画中 2基 200万kW 合 計 20基 1,772万kW
平均設備利用率(1996年):87.5%
- 1995年12月に発表された長期電力需給計画によると、2010年までに17基を建設するとされており、計画が順調に進めば、2010年には原子力発電設備容量が、2,633万キロワットとなり、総発電設備容量の33.1%を占めることになる。また、原子力発電の総発電電力量に占める割合は、45.5%に達すると見られている。なお、2007年には、130万キロワット級の次世代原子炉の営業運転開始を予定している。
- 韓国では、原子力技術の国産化と標準化を進め、韓国標準型原子力発電所(KSNP*)の開発を行ってきた。建設中のウルチン(蔚珍)3、4号機(PWR、各100万キロワット)を標準化の初号機とすることにしており、それらの国産化率は95%程度に達するとしている。
*KSNP:Korean Standard Nuclear Power Plant
図2-6-22 韓国 蔚珍発電所 ⑬中国
(1997年12月末現在)
総発電電力量に占める原子力の割合(1996年):1.3%
運転中 3基 227万kW 建設中 3基 220万kW 計画中 9基 840万kW 合 計 15基 1,287万kW
平均設備利用率(1996年):-*
- 中国核工業総公司(CNNC*)は、運転中の原子力発電設備容量を2010年までに2,000万キロワット、2020年までに4,000~6,000万キロワットに拡大する計画である。
- 1995年10月発表の「第9次五ヶ年計画」(1996年~2000年)に基づき、4サイト・8基の原子力発電所の建設計画が進められている。具体的には、秦山Ⅱ期、Ⅲ期、広東省嶺澳、江蘇省連雲港の4プロジェクトで、合計の発電設備容量は、660万キロワットに達する。
- 秦山Ⅱ期計画では、国産型PWR(60万キロワット×2基)を建設中であり、1号機の送電開始は2002年が予定されている。秦山Ⅲ期計画では、2基のCANDU-6炉が計画されており、2003年の営業運転開始を目指している。広東省嶺澳サイトでは、フラマトム社の100万キロワット級PWR2基が計画されており、営業運転開始は2003年を予定している。江蘇省連雲港サイトでは、ロシアの100万キロワット級改良型VVER-1000型炉2基が建設予定であり、1号機の完成は2004年が予定されている。
- 1996年10月、大亜湾発電所は、IAEAの運転管理調査団(OSART*)の安全性レビューを受け、国際安全基準に従って運転されていると結論されている。
*データなし
*CNNC:China National Nuclear Corporation
*OSART:Operational Safety Review Team
図2-6-23 中国 大亜湾発電所 ⑭台湾
(1997年12月末現在)
総発電電力量に占める原子力の割合(1996年):29.1%
運転中 6基 514万kW 計画中 2基 270万kW 合 計 8基 784万kW
平均設備利用率(1996年):83.6%
- エネルギー資源に恵まれない台湾では、原子力発電に大きな期待を寄せている。特に、台湾では、近年の電力需要の増大に伴い新たな電源確保が急務となっている。
- 第4原子力発電所(龍門)1、2号機の建設計画に関し、1994年7月に「立法院」本会議において建設予算が承認された。1996年5月には、国際入札により、供給メーカーが決定したが、同月、「立法院」は建設計画中止を決議した。これに対し、「行政院」は、「電力の安定供給に影響する」とし、一種の゛拒否権゛である決議撤回動議を「立法院」に提出し、同年10月に「立法院」にて可決された。このため、原子力発電所の建設計画中止決議案は撤回された。計画では、2基のゼネラル・エレクトリック(GE)社のABWRが建設される予定であり、原子炉部分の設置を1998年に開始し、1号機が2004年、2号機が2005年に運転を開始することになっている。
図2-6-24 台湾 第2原子力発電所(国聖) ⑮その他
その他として、以下の国において原子力発電所を運転中である。
地 域 国 運転基数 発電設備容量 欧州
(中・東欧を除く)スペイン
ベルギー
オランダ
7基
1基
600万キロワット
48万キロワット旧ソ連地域 リトアニア
アルメニア
カザフスタン
1基
1基
41万キロワット
15万キロワット中・東欧 ブルガリア
ハンガリー
チェコ
スロバキア
ルーマニア
スロベニア
4基
4基
4基
1基
1基
184万キロワット
176万キロワット
174万キロワット
71万キロワット
66万キロワットその他の地域 南アフリカ
インド
メキシコ
アルゼンチン
ブラジル
パキスタン
10基
2基
2基
1基
1基
184万キロワット
131万キロワット
101万キロワット
66万キロワット
14万キロワットイラン及びキューバにおいては、原子力発電所を建設中であり、北朝鮮では2基のPWR建設に向けて、1997年8月に起工式が行われた。また、エジプト及びイスラエルにおいては、原子力発電所の建設を計画中である。
さらに、トルコでは1996年12月、トルコ発送電会社によって、同国初の原子力発電所となるアックユ原子力発電所建設計画の国際入札が実施された。また、インドネシアでは1997年2月に原子力法改正案が議会で承認され、新たな原子力規制機関を設立するなど、原子力発電導入のための環境整備が進められている。(注記)
- 運転中、建設中、計画中の基数および容量は、(社)日本原子力産業会議「世界の原子力発電開発の動向」による。総発電電力量に占める原子力の割合は、IAEAの発表データによる。平均設備利用率は、NUCLEONICS WEEK等による。
- 四捨五入により、一部積算が一致しない場合がある。
目次へ 第2章 第7節(1)へ