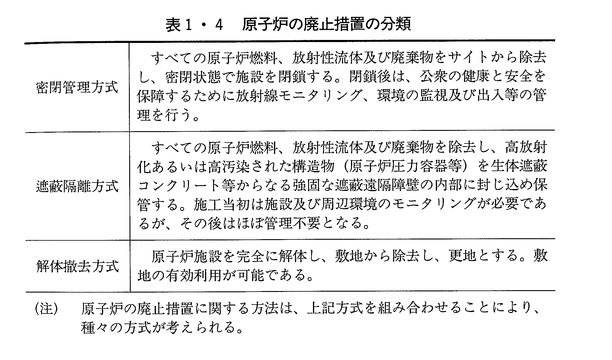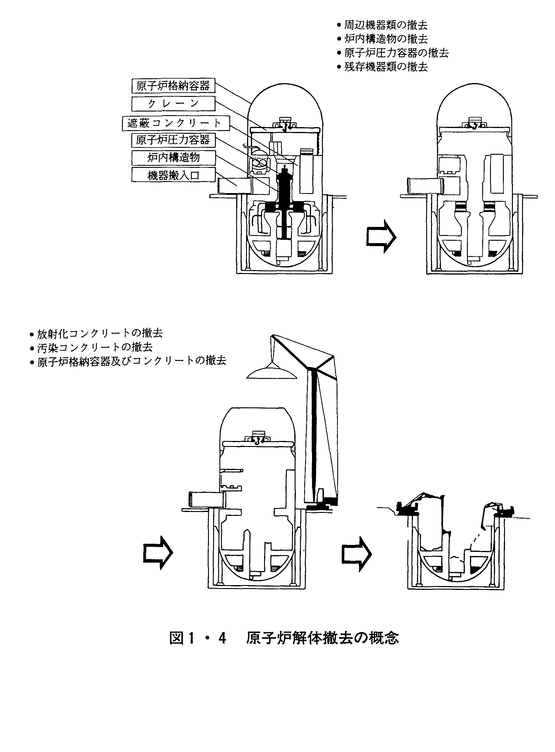第1章 原子力発電
5.原子炉の廃止措置
5.原子炉の廃止措置
我が国における実用発電用原子炉の廃止措置は,1990年代後半以降に現実のものになると予想される。
原子力開発利用長期計画においては,原子炉の廃止措置を進めるに当たっての基本的考え方として
① 安全の確保(作業環境の放射線防護及び周辺公衆の被ばく防止等)
② 原子炉の廃止措置後における敷地の有効利用
③ 地域社会との協調
を挙げ,原子炉の運転終了後できるだけ早い時期に解体撤去することを原則とし,個別には合理的な密閉管理の期間を経る等,諸状況を総合的に判断して定めるものとしている。
原子炉の廃止作業は,既存技術又はその改良により対応できると考えられるが,作業者の安全性の一層の向上を図る等の観点から技術の向上を図ることとしている。
このため,科学技術庁では日本原子力研究所に委託し,1981年度から解体撤去のための技術開発を進め,解体技術,除染技術,遠隔操作技術等の総合的な技術開発を行った。なお,計画前半の技術開発の成果については,日本原子力研究所が外部専門家等からなる検討委員会に評価を依頼し,動力試験炉(JPDR)の解体実地試験の遂行に技術的見通しが得られたとの評価を受けている。また,1986年度からは,それらの技術を用いて同研究所のJPDRをモデルとして解体実地試験を実施している。
さらに,1990年度からは,これまで得られた成果等をもとに,原子炉解体高度化技術開発を進めている。
国際協力の面においては,1985年に経済協力開発機構原子力機関(OECD/NEA)の原子力施設デコミッショニング・プロジェクトに関する科学技術情報交換協力計画(参加10か国)が,また,国際原子力機関(IAEA)においても1989年より「原子力施設の除染及び廃止措置に関する協力研究計画」の第2次計画(参加15か国)が開始された。我が国からも,これらの計画に日本原子力研究所が参加し,解体技術等に関する情報の交換を行い,一層円滑な原子炉の廃止措置に備えている。
なお,1986年12月から開始したJPDR解体実地試験は,圧力容器の解体を終了し,1991年12月から放射線遮蔽体の解体作業に着手している。
(財)原子力発電技術機構(前(財)原子力工学試験センター)においては,廃止措置に係る技術のうち,安全性,信頼性の観点から特に重要な技術の実用化を促進するため確証試験を進めている。また,商業用原子力発電施設の廃止措置の在り方について,1985年7月総合エネルギー調査会原子力部会において,最終的に運転を終了した原子力発電施設は,その規模,炉型等にかかわらず,5~10年の密閉管理後解体撤去することを基本方針とする旨の報告書が取りまとめられた。同報告書によれば,費用については,例として,110万キロワット級の原子力発電施設で約300億円程度(昭和59年度価格)と試算している。
廃炉費用の確保に関しては,1989年3月期決算から,原子炉廃止措置費用の引当金方式による積立が開始された。さらに,1990年度より租税特別措置法に原子力発電施設解体準備金制度が創設され,解体費用見積額のうち当該年度相当分の85%を限度として損金算入することが認められた。
また,1988年12月には,研究開発用の原子力施設の廃止措置に関する技術の確立を目的として,(財)原子力施設デコミッショニング研究協会が設立され,試験研究及び技術情報の提供等を行っている。
目次へ 第1章(参考)へ